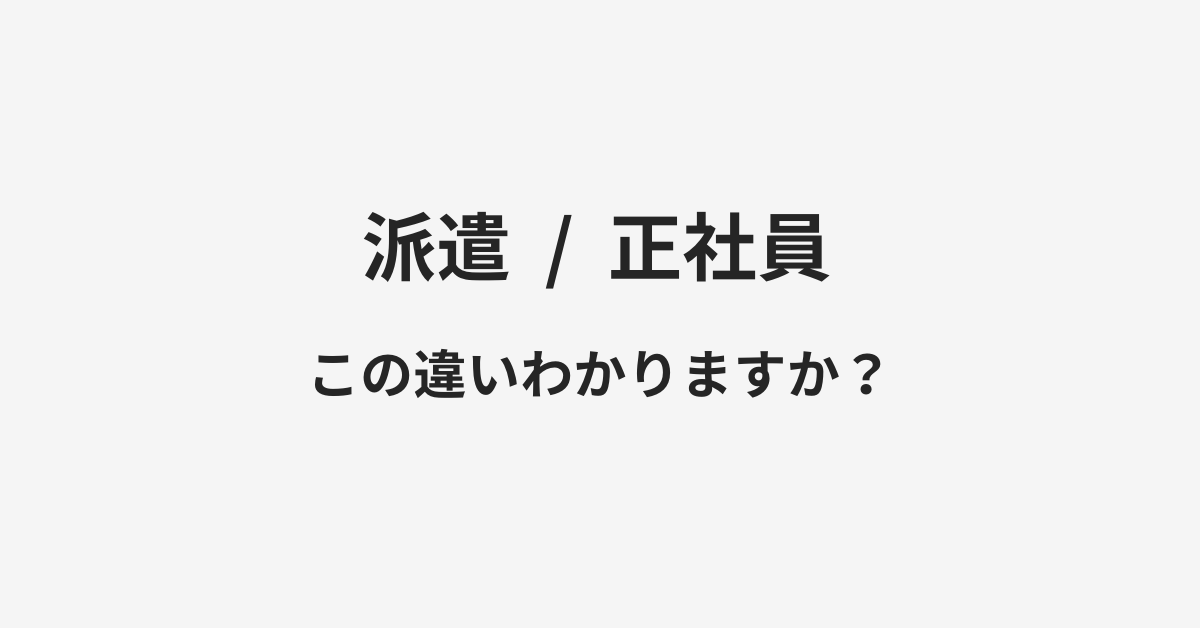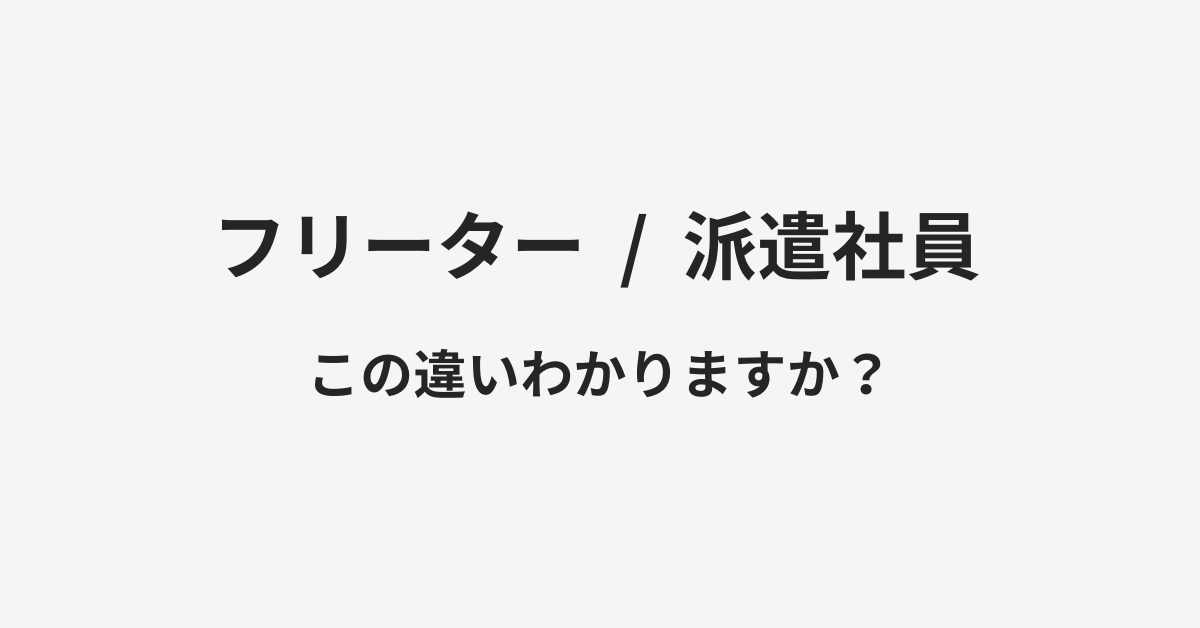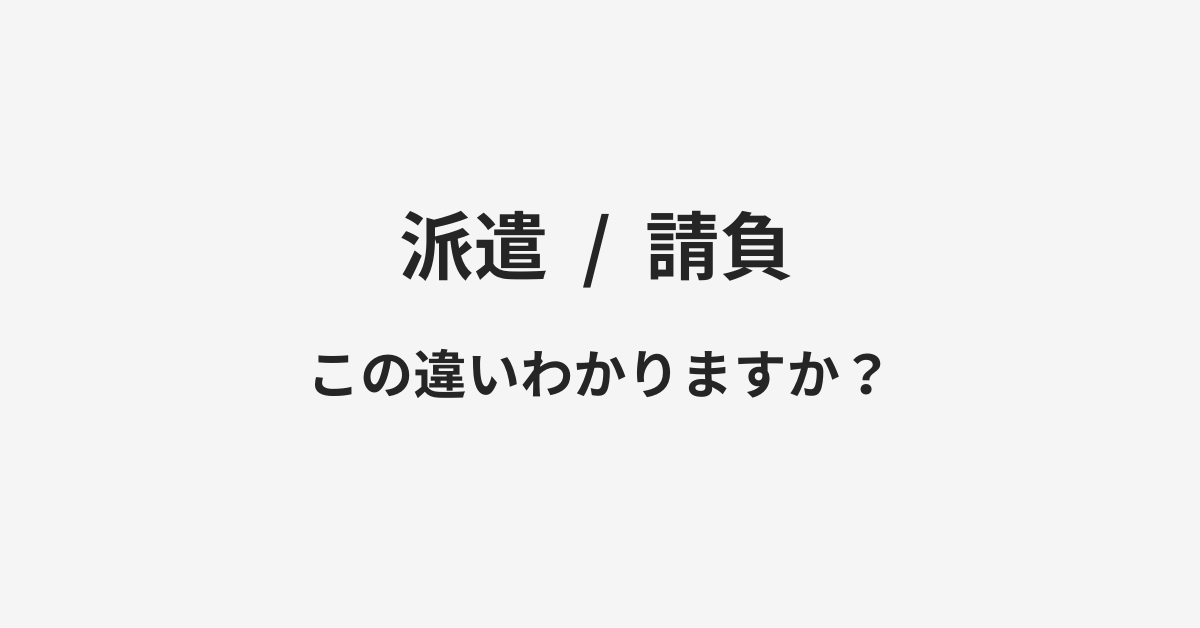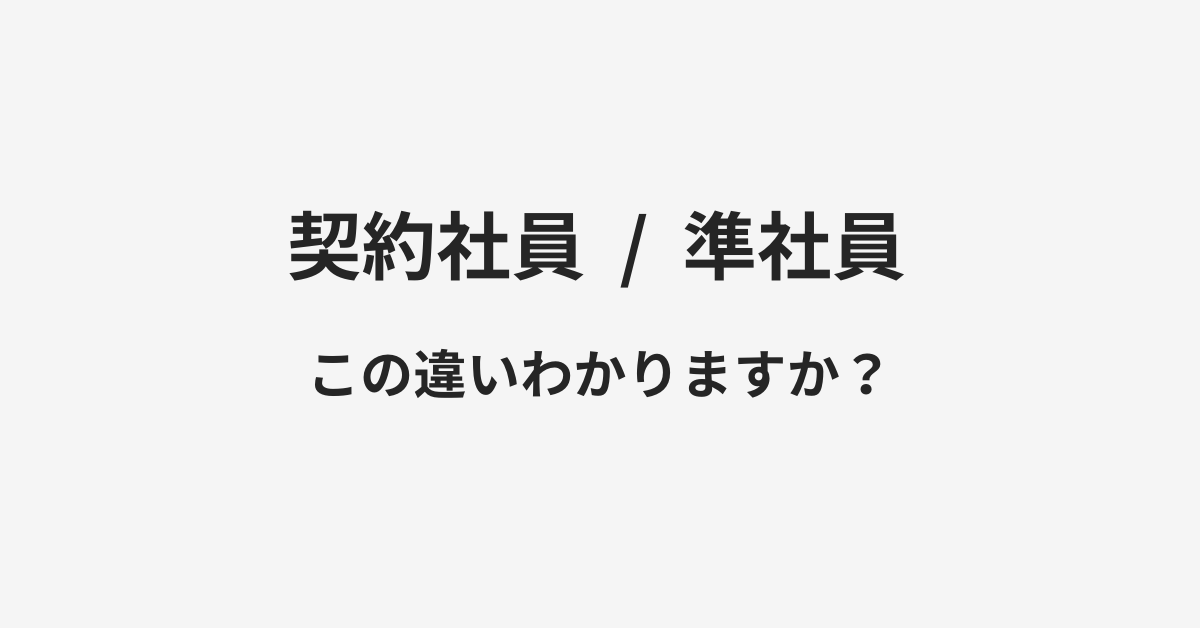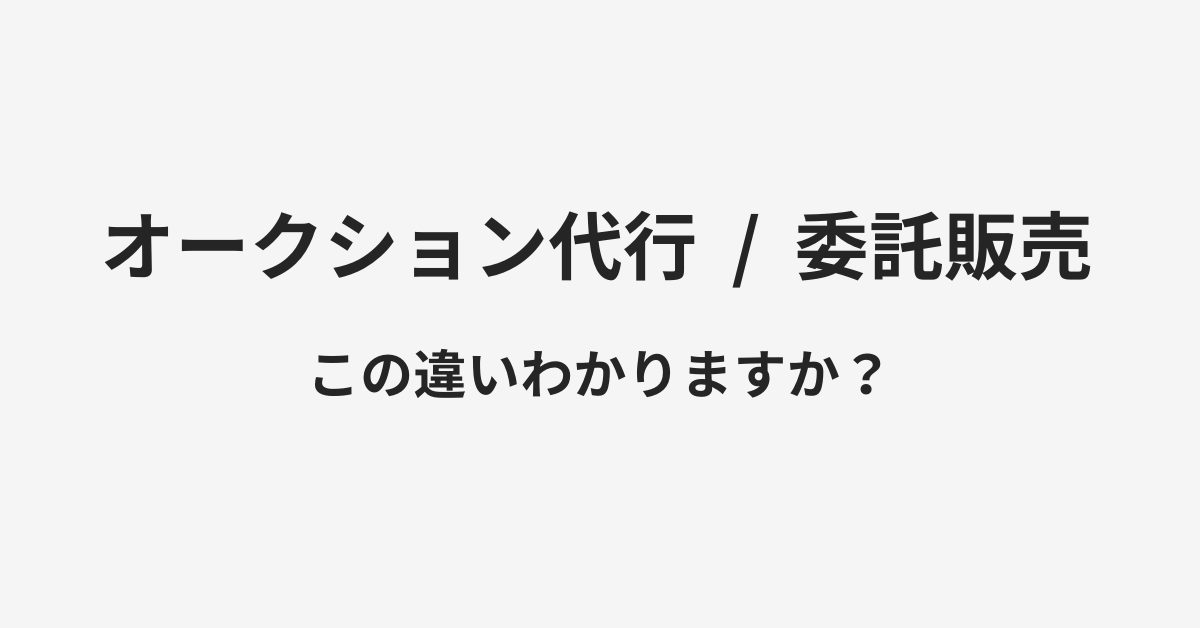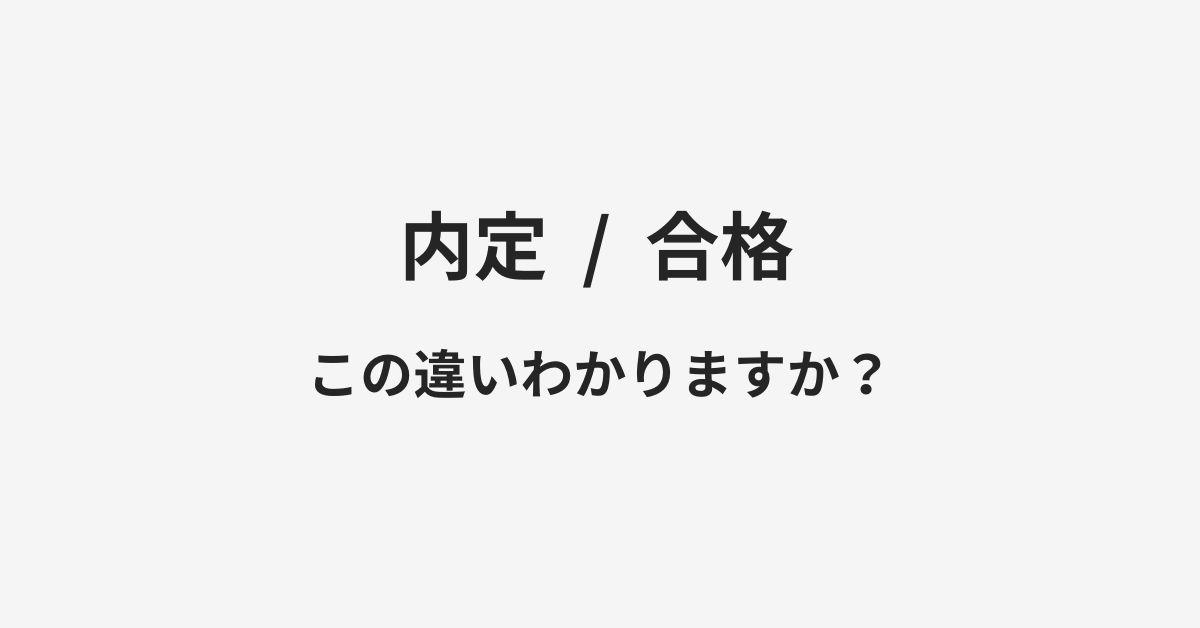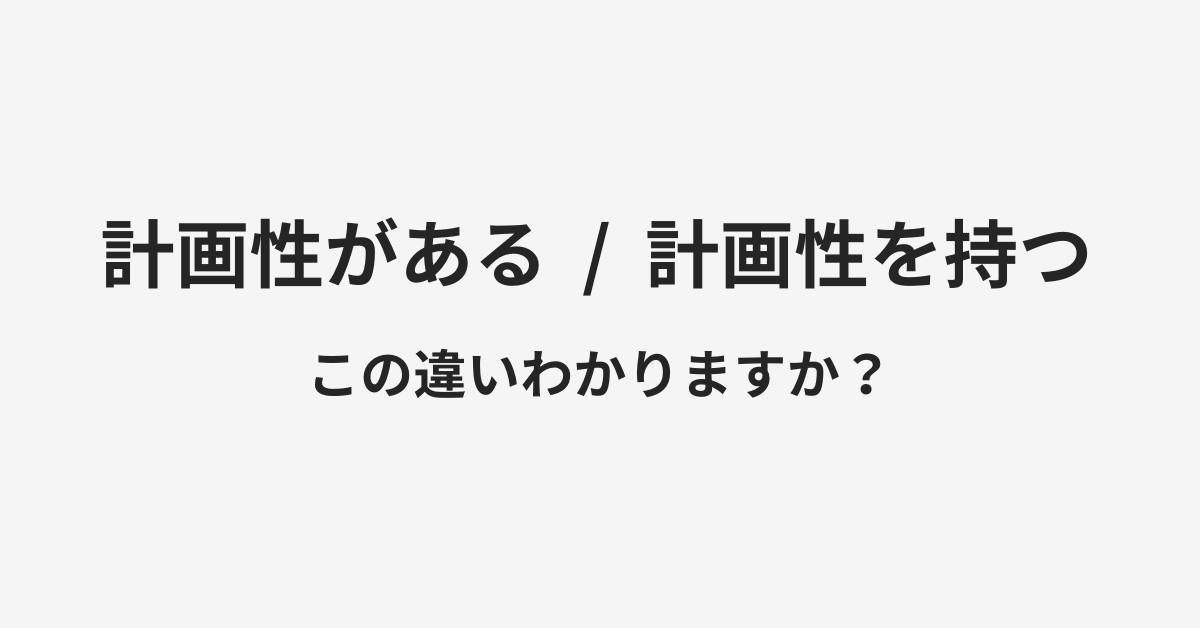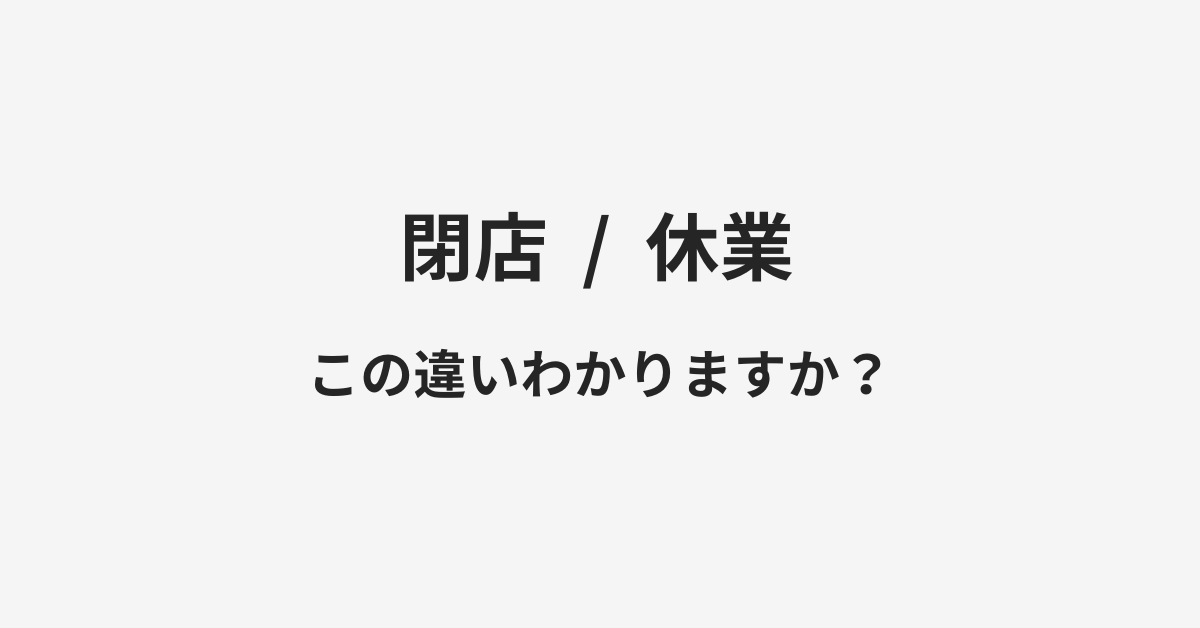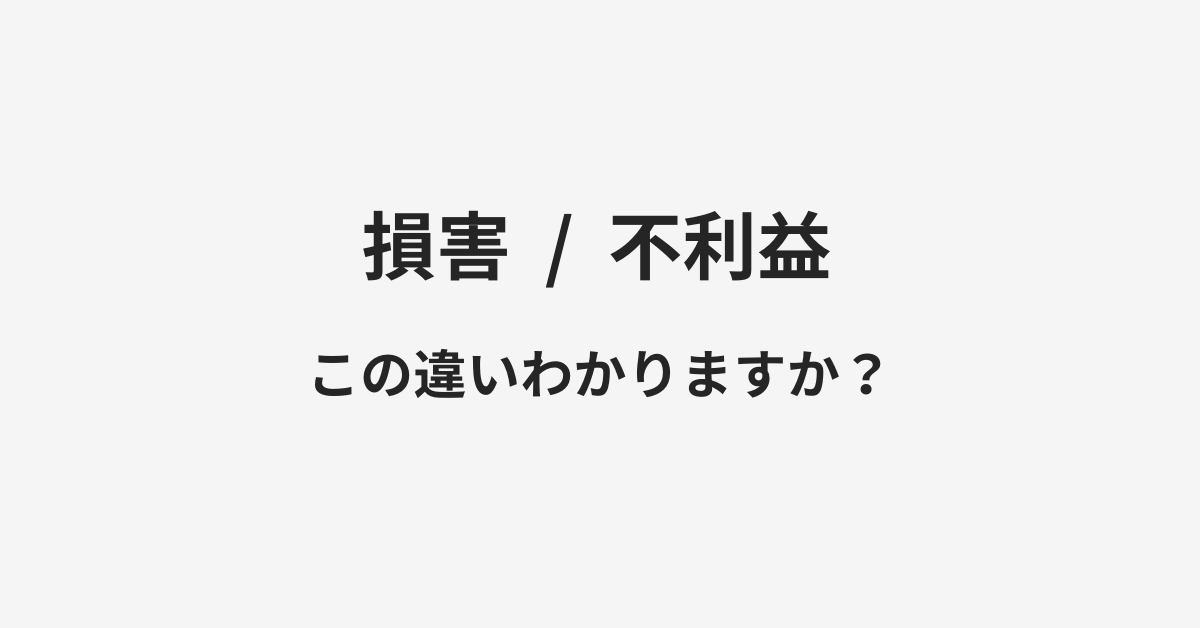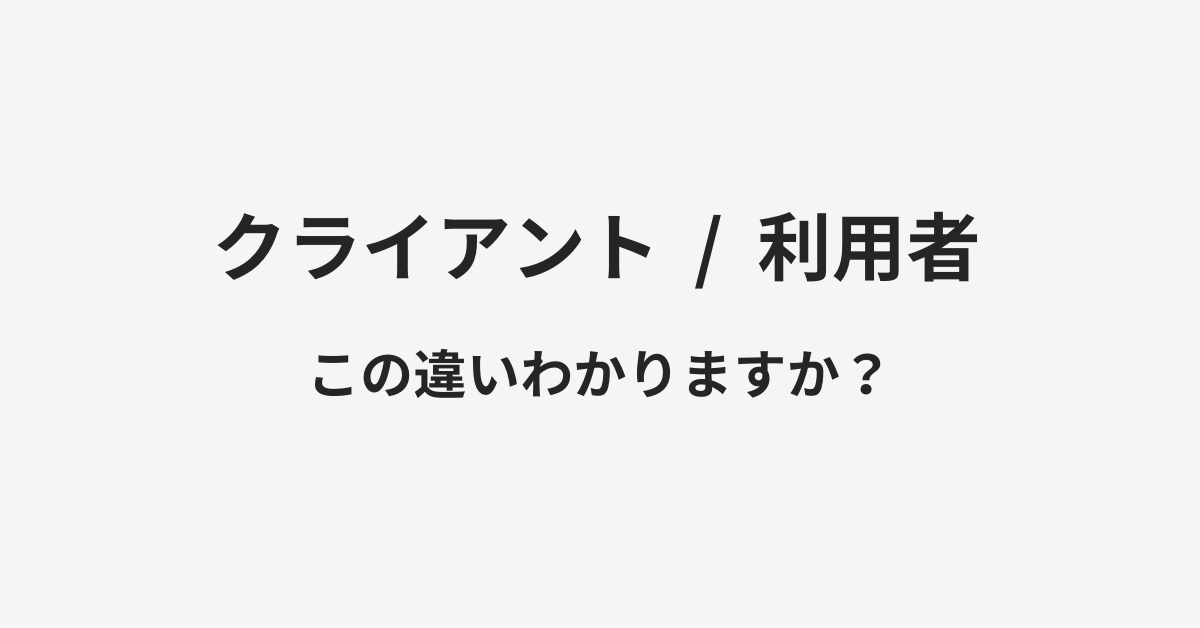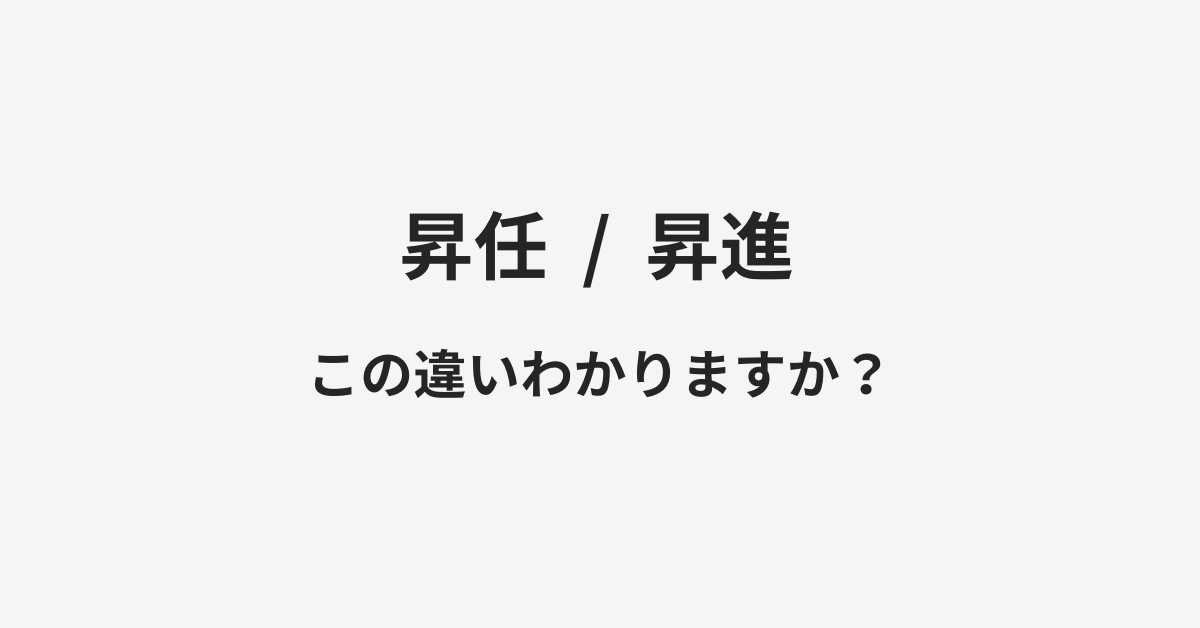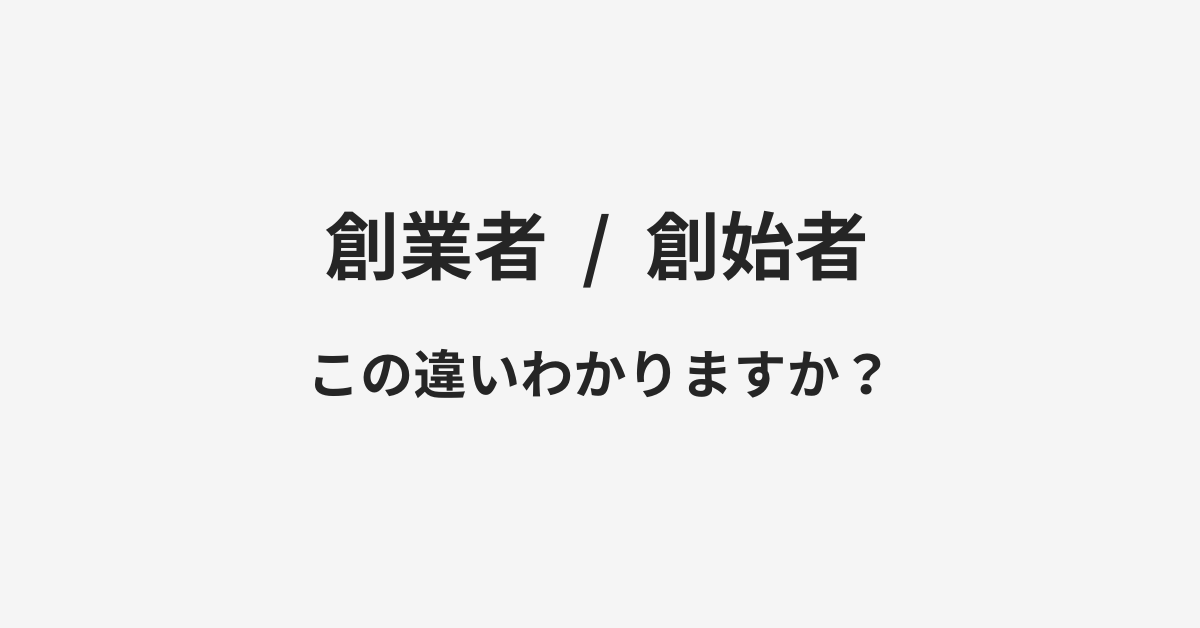【ビジネス】と【商い】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
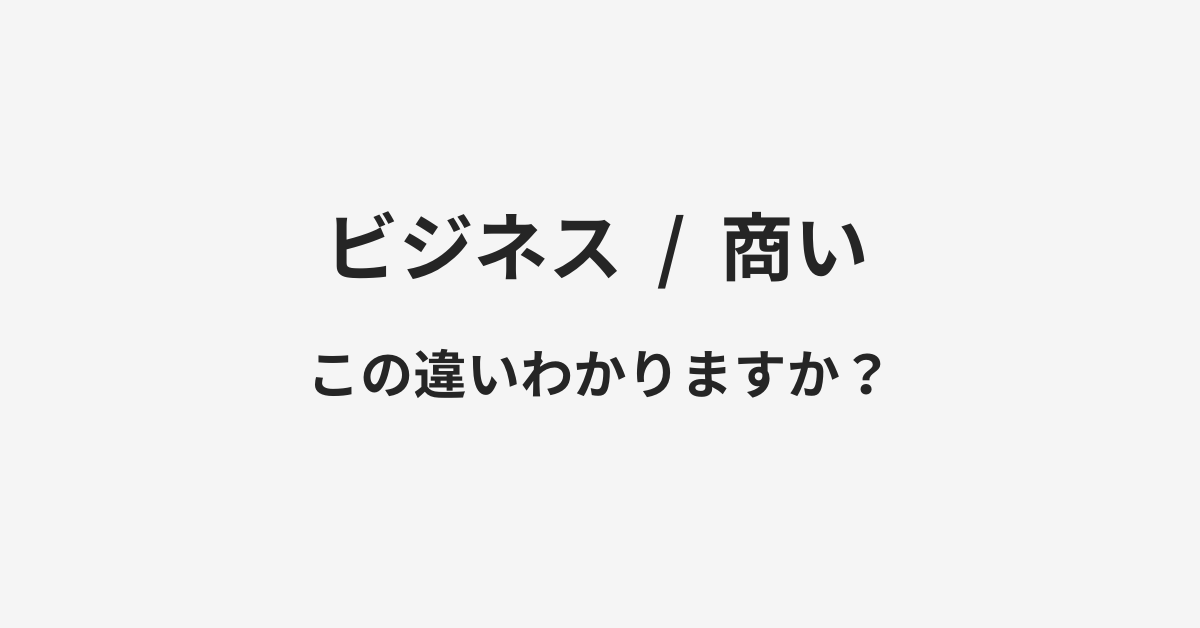
ビジネスと商いの分かりやすい違い
ビジネスと商いは、どちらも経済活動を表す言葉ですが、その範囲と使われ方に大きな違いがあります。
ビジネスは企業経営、マーケティング、金融など幅広い事業活動を含む現代的な用語で、商いは物品の売買を中心とした伝統的な商業活動を指します。前者は包括的、後者は限定的な意味を持ちます。
現代の経済活動において、この違いを理解することは、適切な言葉選びと効果的なコミュニケーションに重要です。
ビジネスとは?
ビジネスとは、利益を目的とした事業活動全般を指す包括的な用語です。製造、販売、サービス提供、金融、IT、コンサルティングなど、あらゆる産業分野の経済活動を含みます。英語のbusinessから来た外来語で、現代の企業活動を表現する際に最も一般的に使用される言葉です。
ビジネスの範囲は、戦略立案、マーケティング、人事管理、財務管理、イノベーション創出など多岐にわたります。グローバル化、デジタル化の進展により、ビジネスモデルも多様化し、プラットフォームビジネス、サブスクリプションモデル、シェアリングエコノミーなど新しい形態が生まれています。
現代のビジネスでは、単なる利益追求だけでなく、社会的責任(CSR)、持続可能性(サステナビリティ)、ステークホルダー価値の創造が重視されています。ビジネススクールでは、これらを統合的に学ぶMBA教育が行われています。
ビジネスの例文
- ( 1 ) 新規ビジネスの立ち上げに向けて、事業計画を策定しています。
- ( 2 ) デジタルビジネスへの転換により、売上が前年比150%成長しました。
- ( 3 ) ビジネスモデルの革新が、当社の競争優位性の源泉です。
- ( 4 ) グローバルビジネスの展開には、異文化理解が不可欠です。
- ( 5 ) ビジネススクールで学んだ知識を、実務に活かしています。
- ( 6 ) サステナブルなビジネスの構築が、企業の長期的成功の鍵となります。
ビジネスの会話例
商いとは?
商い(あきない)とは、物品の売買を中心とした商業活動を指す日本の伝統的な言葉です。秋の実りを交換することが語源とされ、江戸時代から使われてきた歴史ある表現です。小売業、卸売業、問屋業など、主に物品の流通に関わる商売を表す際に使用されます。
商いには、商いは牛の涎(よだれ)商いは道によって賢しなどの格言があり、日本の商業文化や商人道徳を反映しています。信用第一、正直な取引、顧客との長期的な関係構築など、日本的な商慣習の精神が込められています。老舗企業では今でも商いという言葉を大切にしています。
現代でも、伝統的な商店街、地域密着型の小売業、職人的な製造販売業などで商いという表現が使われます。単なる売買ではなく、人と人との繋がり、地域社会への貢献、代々受け継がれる信用を重視する姿勢を表現する際に適した言葉です。
商いの例文
- ( 1 ) 三代続く商いを守りながら、時代に合わせた改革を進めています。
- ( 2 ) 正直な商いこそが、長年の信用を築く基盤となります。
- ( 3 ) 地域に根ざした商いで、お客様との絆を大切にしています。
- ( 4 ) 商いの心得として、売り手よし、買い手よし、世間よしを実践しています。
- ( 5 ) 小さな商いでも、誠実に続ければ大きな信頼を得られます。
- ( 6 ) 伝統的な商いの知恵を、現代の経営に活かしています。
商いの会話例
ビジネスと商いの違いまとめ
ビジネスと商いの最大の違いは、対象範囲と現代性です。ビジネスは製造からサービス、金融まで幅広い事業活動を包含する現代的な概念、商いは売買中心の伝統的な商業活動という違いがあります。
使用場面も異なり、ビジネスは国際的な企業活動や最新の経営手法を語る際に使用され、商いは日本の伝統的な商業精神や地域密着型の商売を表現する際に使われます。
言葉の選択は、相手や状況によって使い分けることが大切です。グローバル企業ではビジネス、老舗企業や地域商店では商いという使い分けが、適切なコミュニケーションにつながります。
ビジネスと商いの読み方
- ビジネス(ひらがな):びじねす
- ビジネス(ローマ字):bijinesu
- 商い(ひらがな):あきない
- 商い(ローマ字):akinai