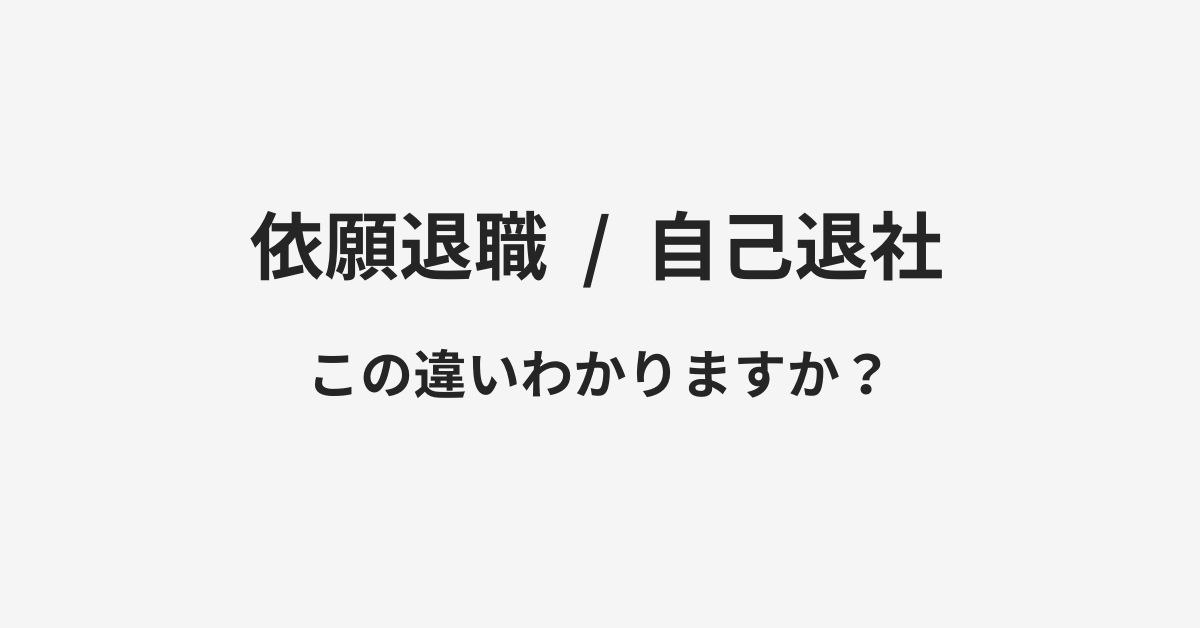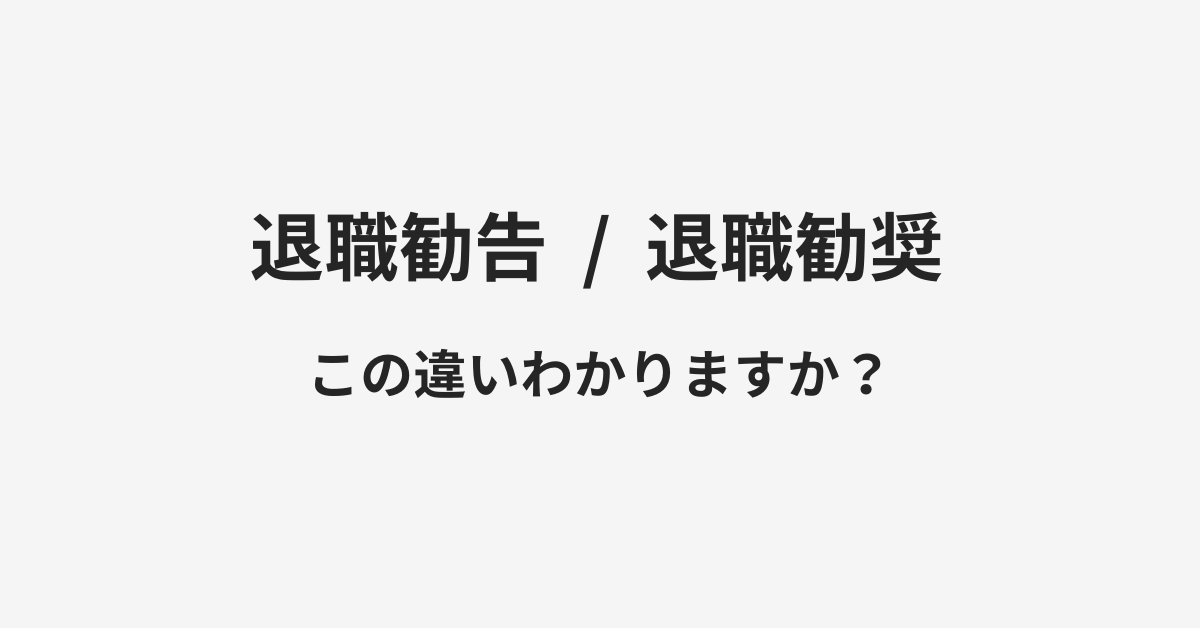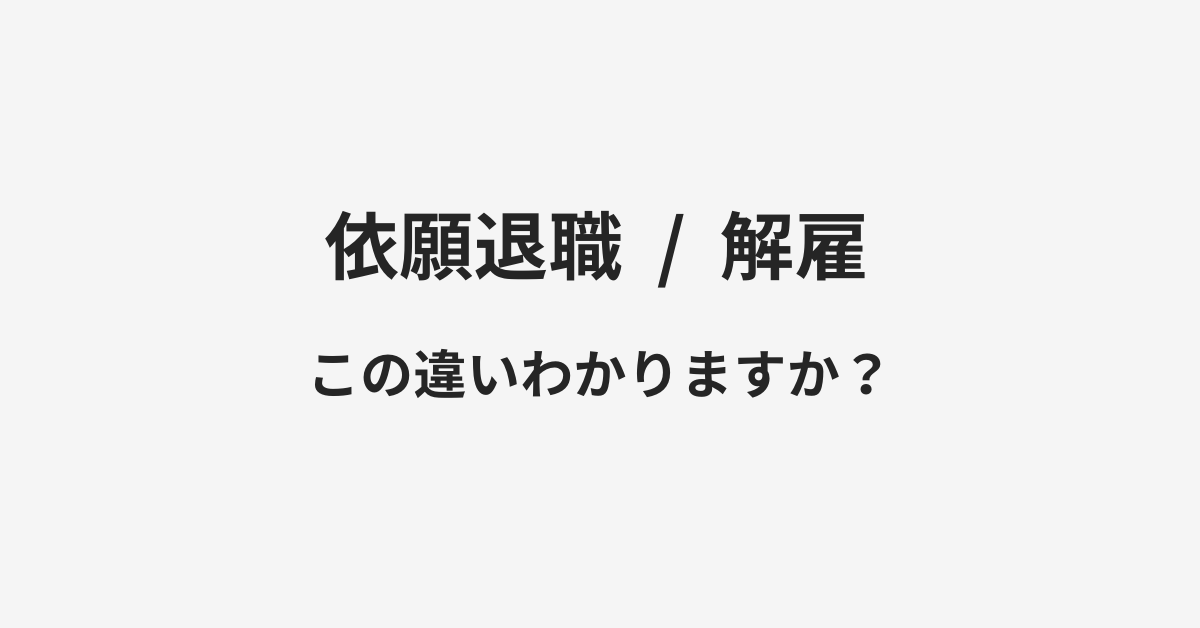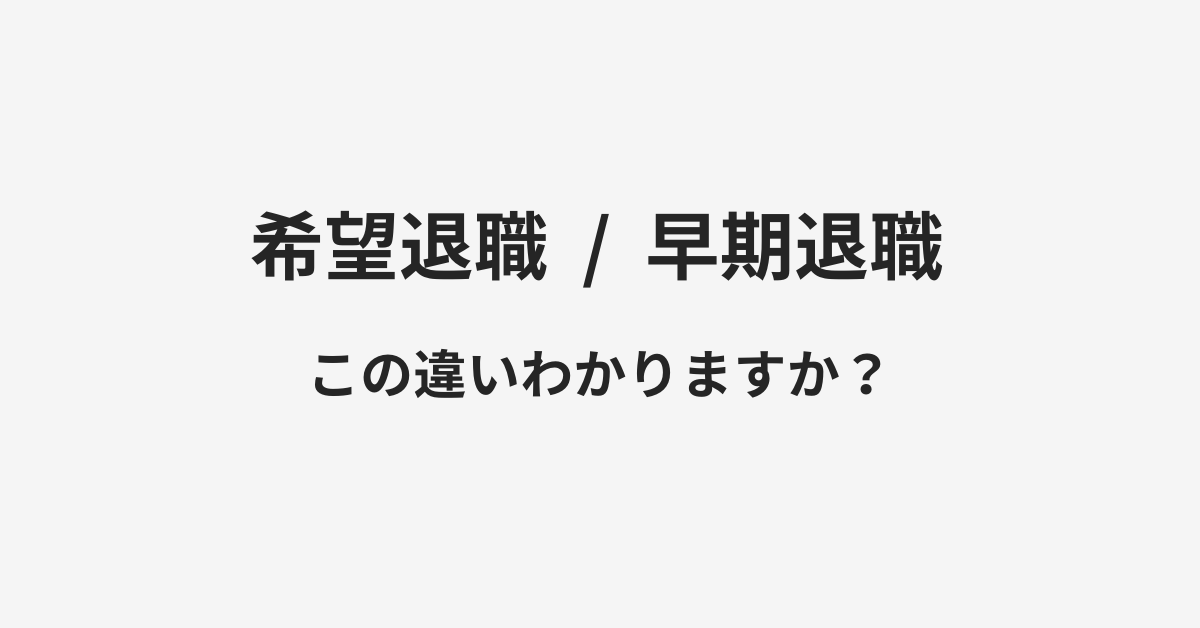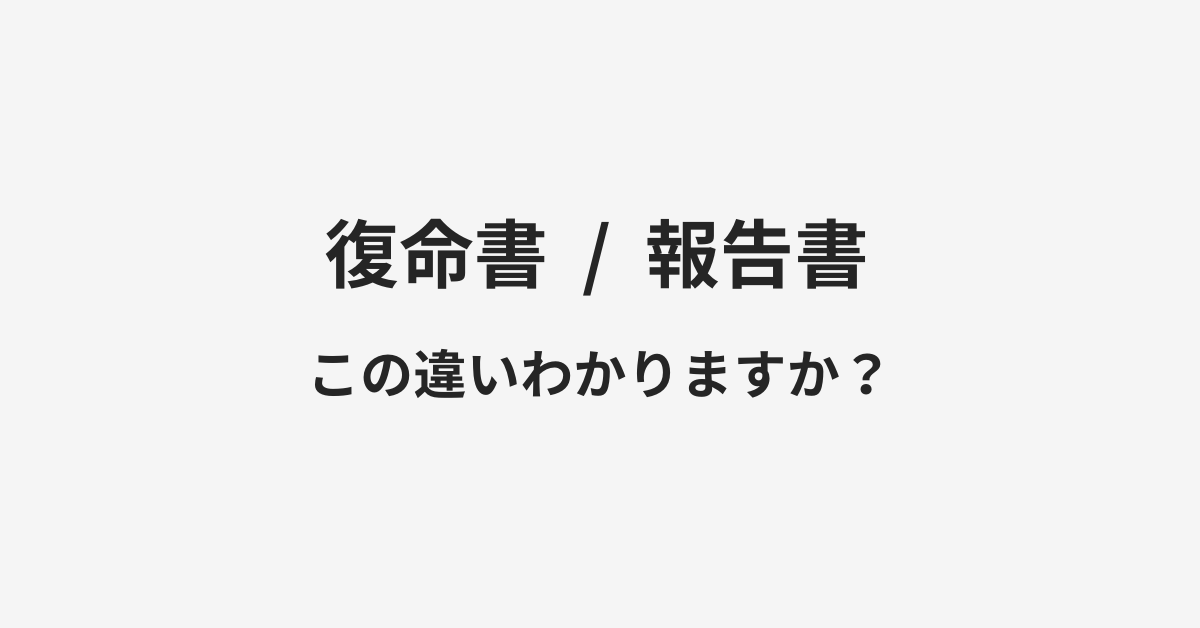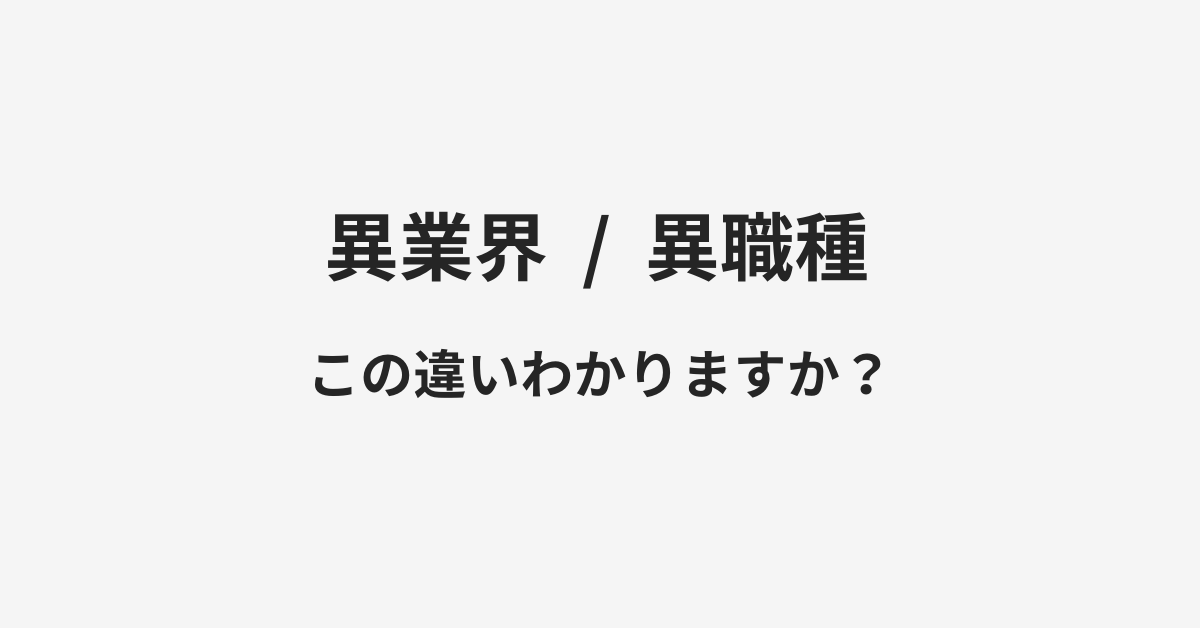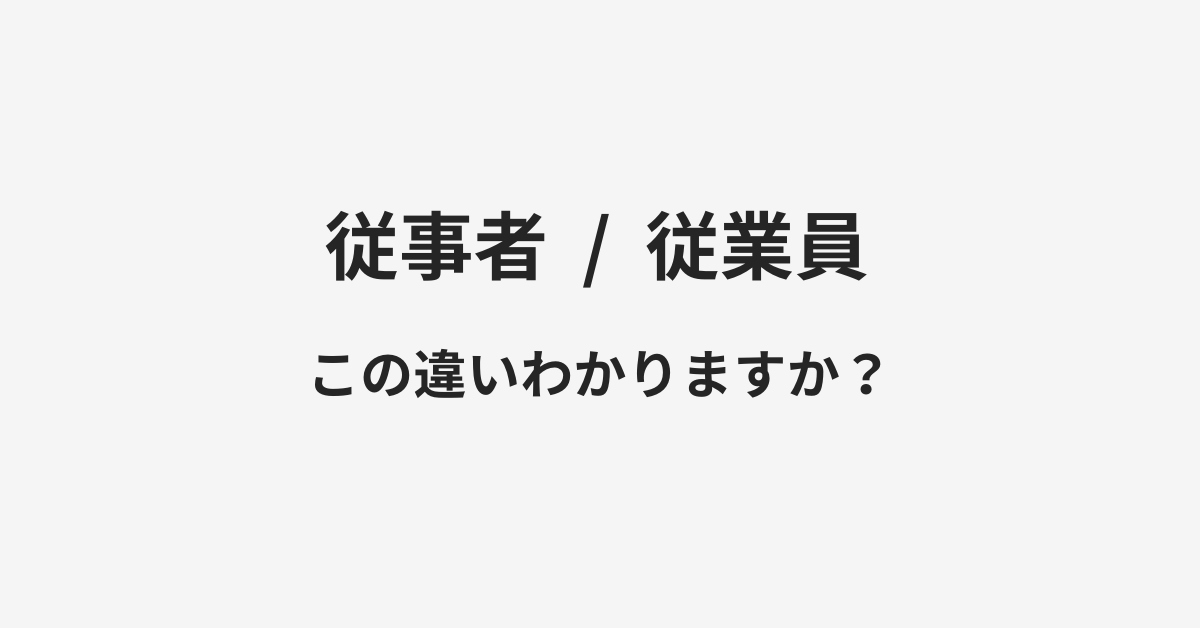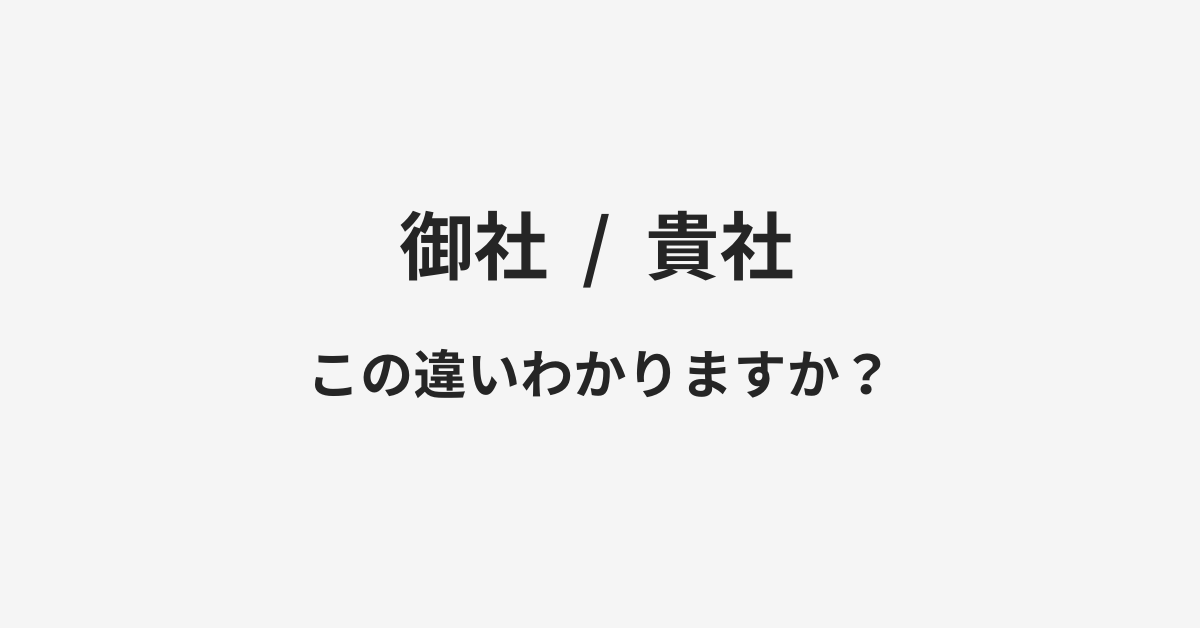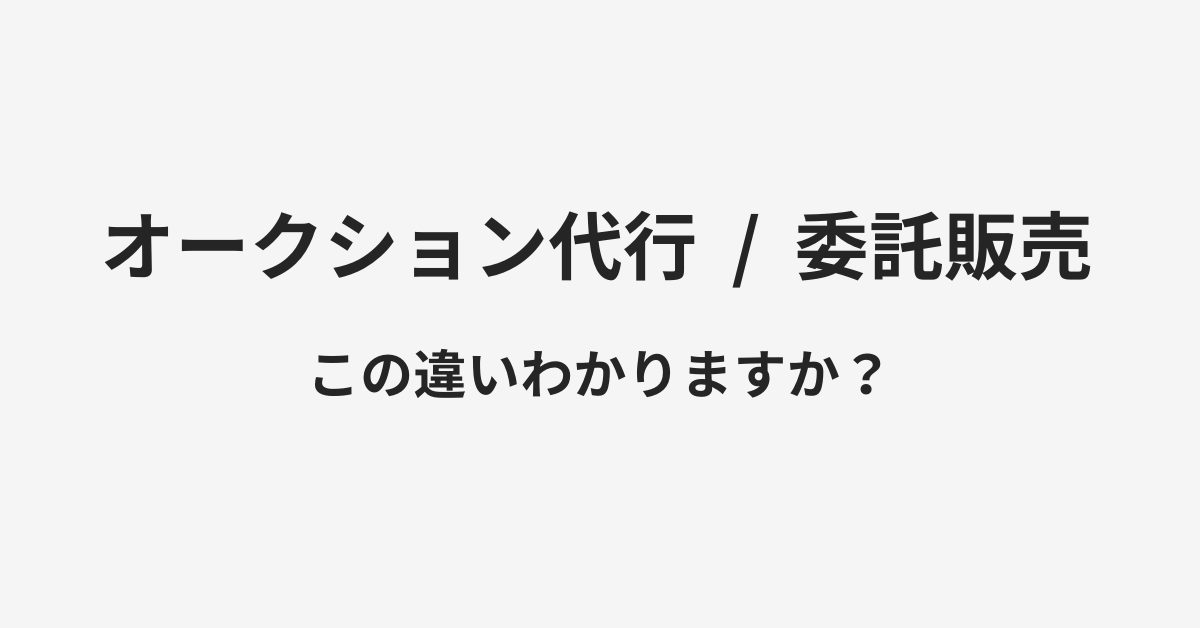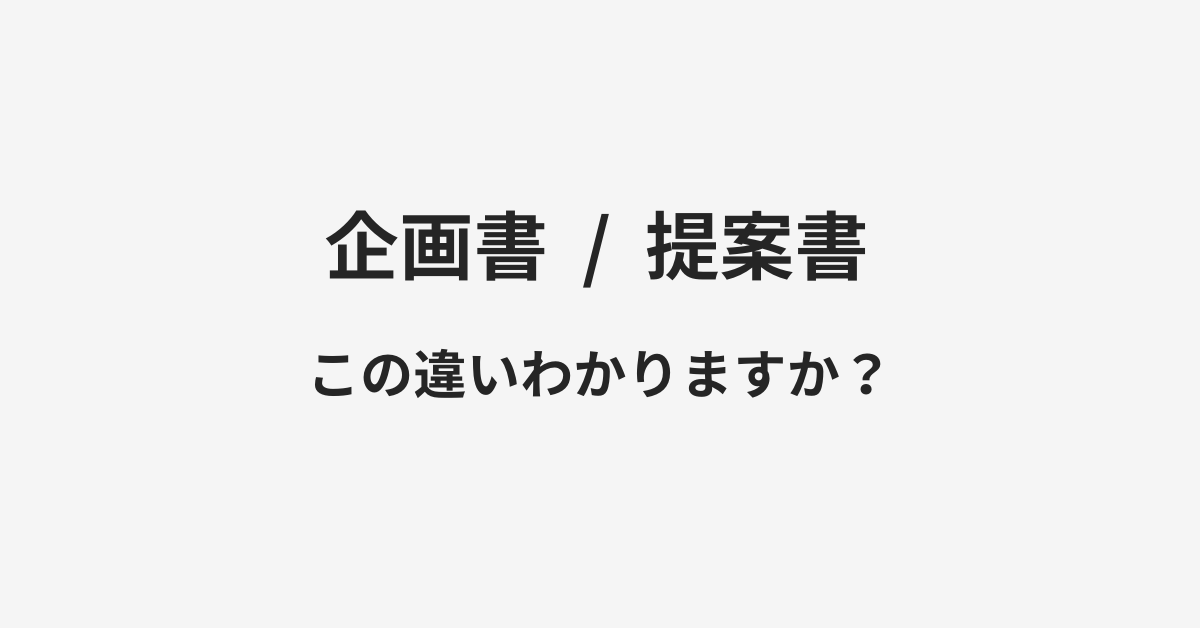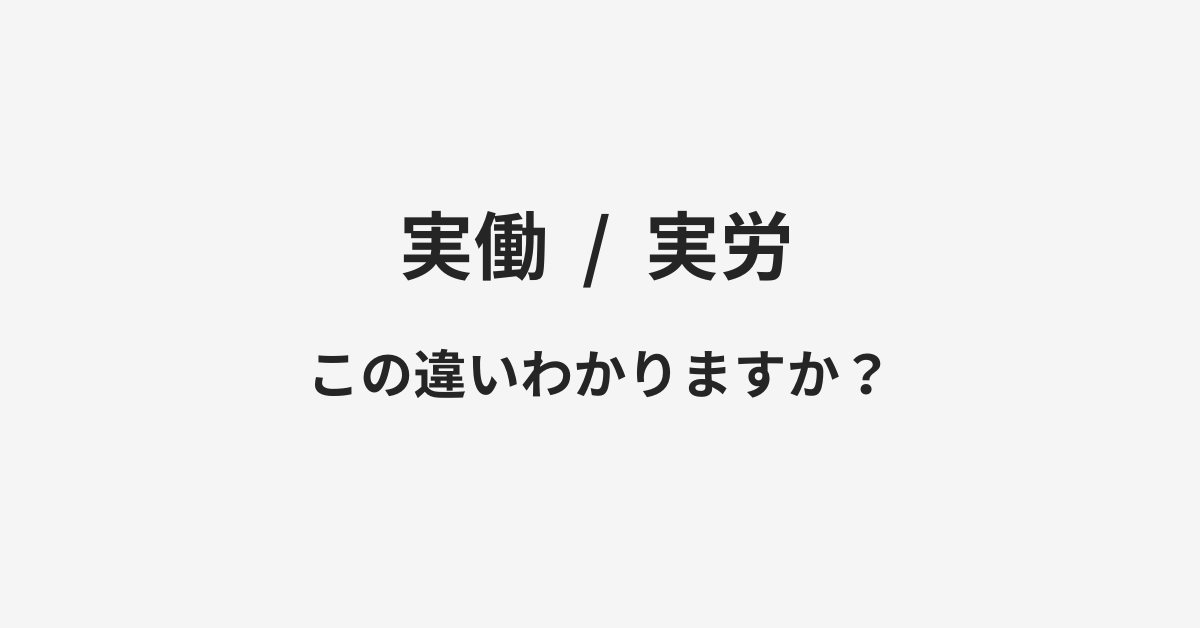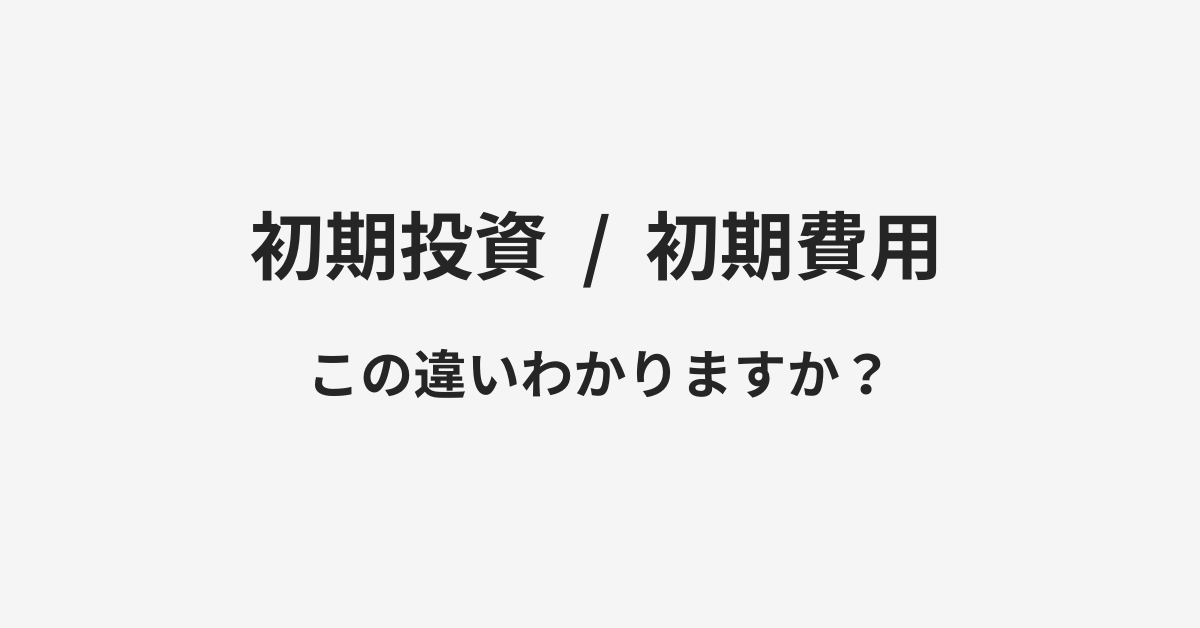【退職届】と【退職願】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
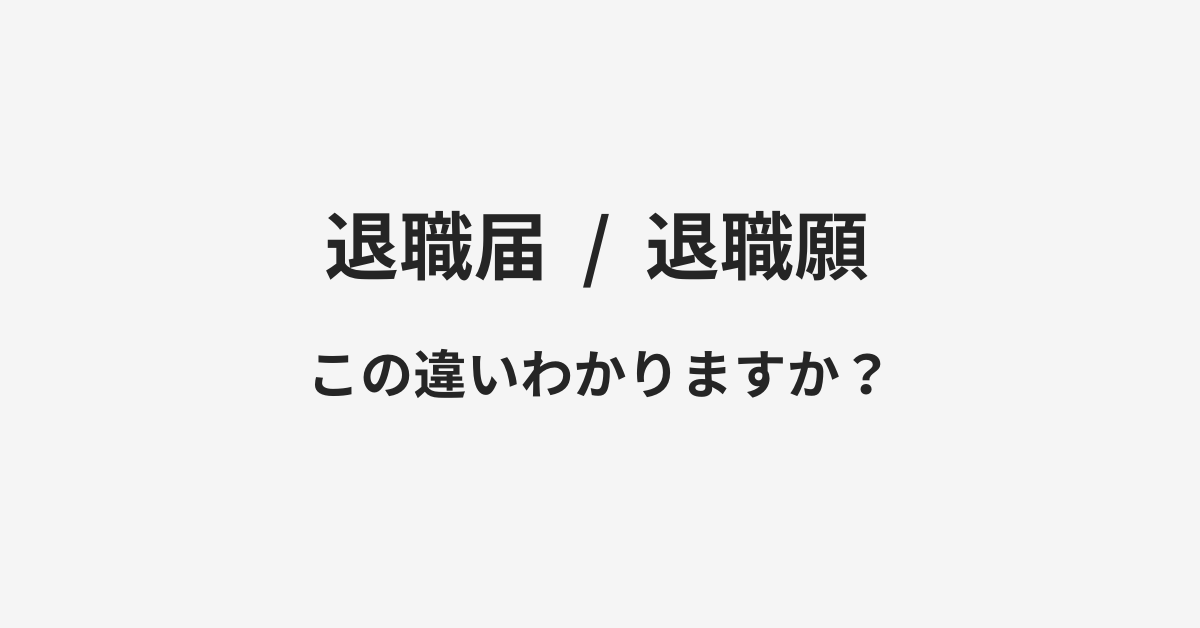
退職届と退職願の分かりやすい違い
退職届と退職願は、退職時に提出する書類ですが、その法的性質が全く異なります。
退職届は労働者の一方的な意思表示で撤回不可、退職願は会社への申し出で承諾前なら撤回可能です。
円満退社を目指すなら退職願から始めることが一般的です。
退職届とは?
退職届とは、労働者が会社に対して退職の意思を一方的に通告する書類で、民法上の「解約の申し入れ」に該当します。提出後は原則として撤回できず、会社の承諾も不要で、正社員なら提出から2週間後に自動的に退職となります。会社との話し合いが決裂した場合や、やむを得ない事情で確実に退職したい場合に使用されます。
退職届の提出は、労働契約の解約という重大な法律行為であり、慎重な判断が必要です。パワハラや違法な労働環境など、会社側に問題がある場合は、証拠を残すためにも内容証明郵便で送付することもあります。ただし、一方的な退職は円満退社とはならず、退職金や有給消化で不利になる可能性もあります。
書式は「退職届」というタイトルで、退職日を明記し、「退職いたします」という断定的な表現を使います。就業規則で定められた提出期限を守ることが重要です。
退職届の例文
- ( 1 ) 明日、退職届を人事部に提出します。
- ( 2 ) 退職届を内容証明で送付しました。
- ( 3 ) 退職届提出後、2週間で退職となります。
- ( 4 ) 会社が退職を認めないので、退職届を準備しています。
- ( 5 ) 退職届の撤回はできないと説明を受けました。
- ( 6 ) 弁護士に相談して退職届を作成しました。
退職届の会話例
退職願とは?
退職願とは、労働者が会社に対して退職の許可を求める書類で、双方の合意により退職が成立します。会社が承諾するまでは撤回可能で、円満退社を希望する場合の一般的な方法です。まず上司に口頭で相談し、了承を得てから提出することが通常の流れです。
退職願は会社への配慮を示す書類であり、「お願い」の形式を取ることで、引き継ぎ期間の調整や後任の手配など、双方にとって最適な退職時期を協議できます。多くの企業では、退職願の提出から1〜3か月後の退職が一般的で、この期間に業務の引き継ぎや後任者の採用を行います。
書式は「退職願」というタイトルで、「退職させていただきたく、お願い申し上げます」という謙虚な表現を使います。退職理由は「一身上の都合」とすることが多く、詳細な理由の記載は不要です。提出後も会社との協議により、退職日の調整が可能です。
退職願の例文
- ( 1 ) 上司と相談の上、退職願を提出することにしました。
- ( 2 ) 退職願を提出しましたが、慰留されています。
- ( 3 ) 退職願の承認をいただき、引き継ぎを開始します。
- ( 4 ) 体調不良のため、退職願を提出させていただきます。
- ( 5 ) 退職願を一旦撤回し、もう少し考えることにしました。
- ( 6 ) 円満退社のため、3か月前に退職願を提出しました。
退職願の会話例
退職届と退職願の違いまとめ
退職届と退職願は、退職プロセスにおける重要な選択肢です。
退職届は確実だが強硬的、退職願は柔軟だが会社の対応次第という特徴があります。
多くの場合、まず退職願で円満退社を目指し、必要に応じて退職届に切り替えるという段階的アプローチが賢明です。
退職届と退職願の読み方
- 退職届(ひらがな):たいしょくとどけ
- 退職届(ローマ字):taishokutodoke
- 退職願(ひらがな):たいしょくねがい
- 退職願(ローマ字):taishokunegai