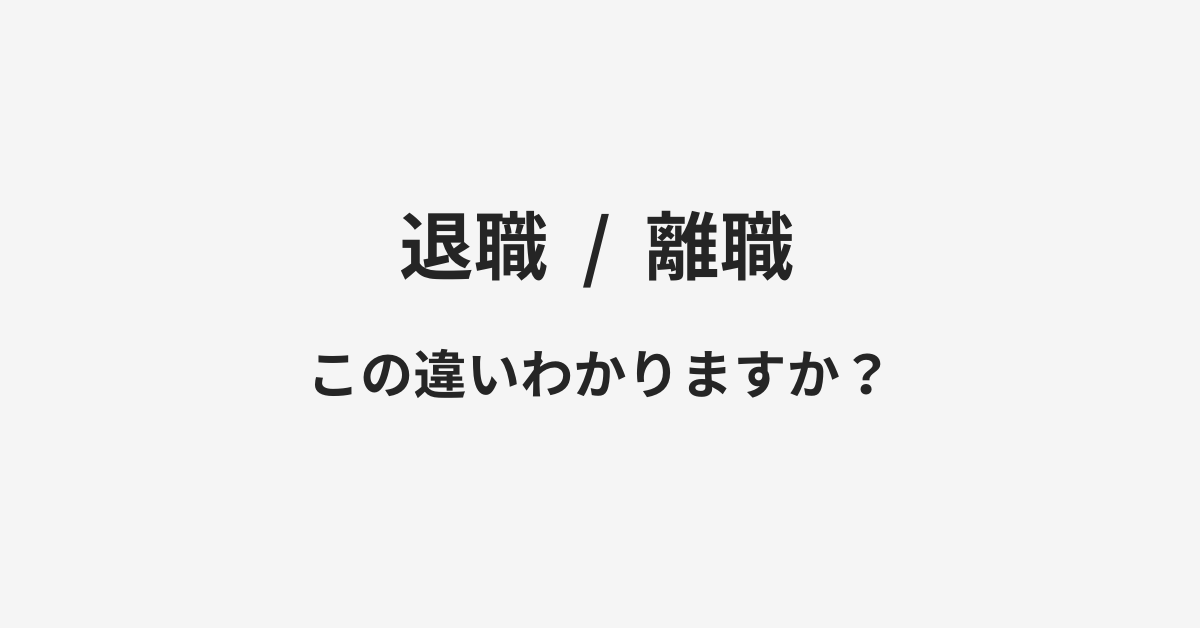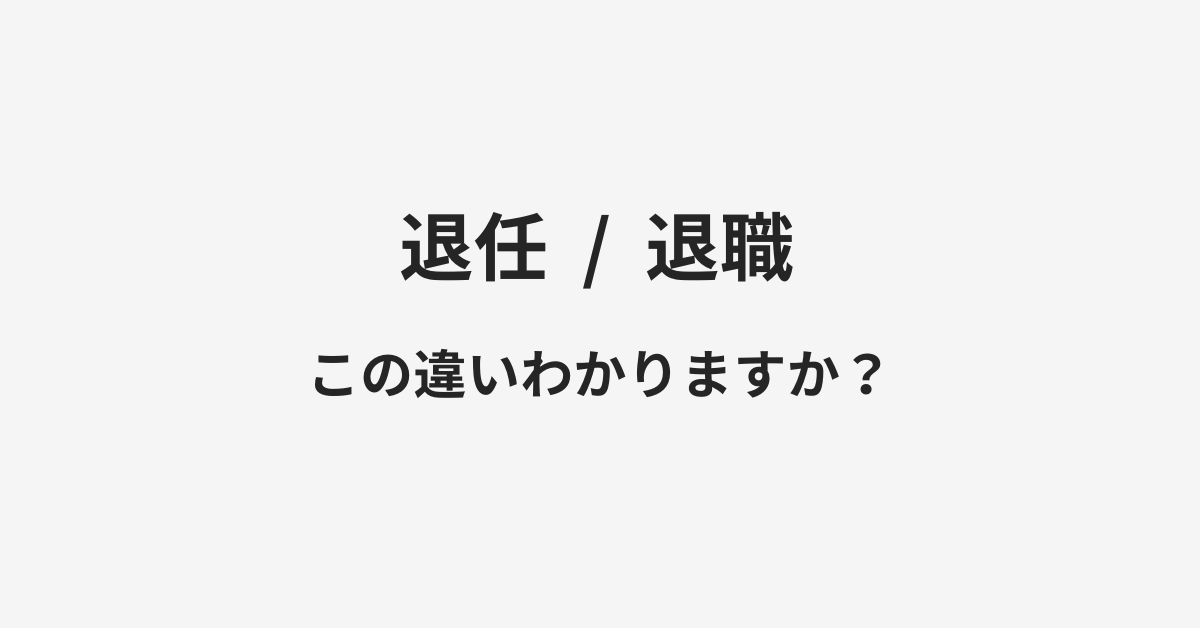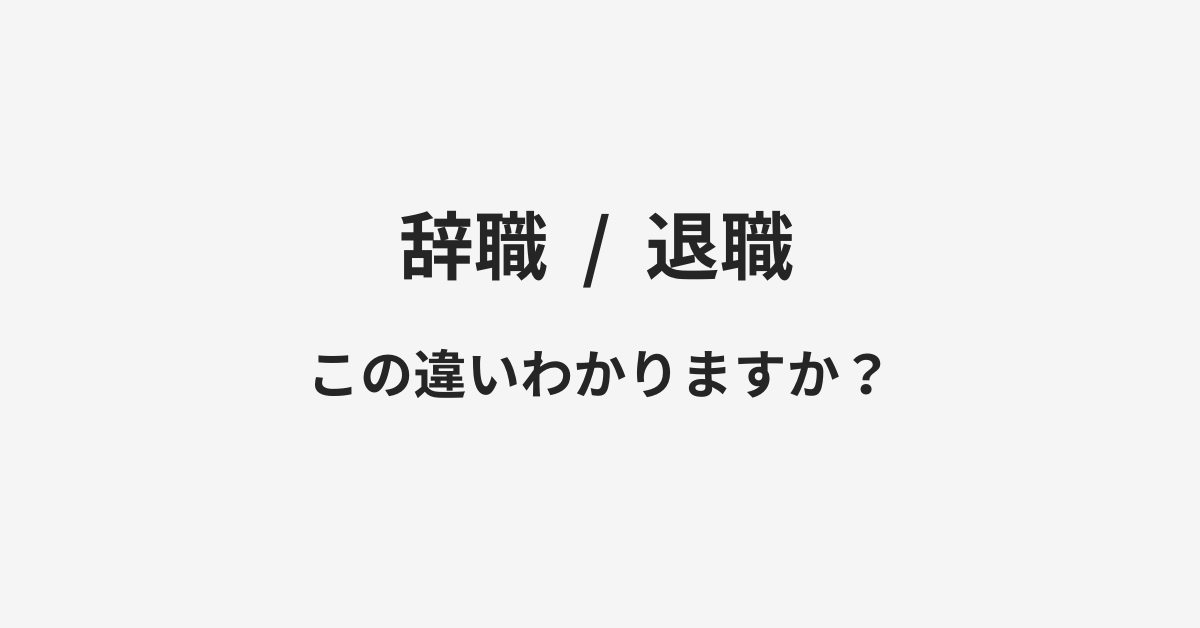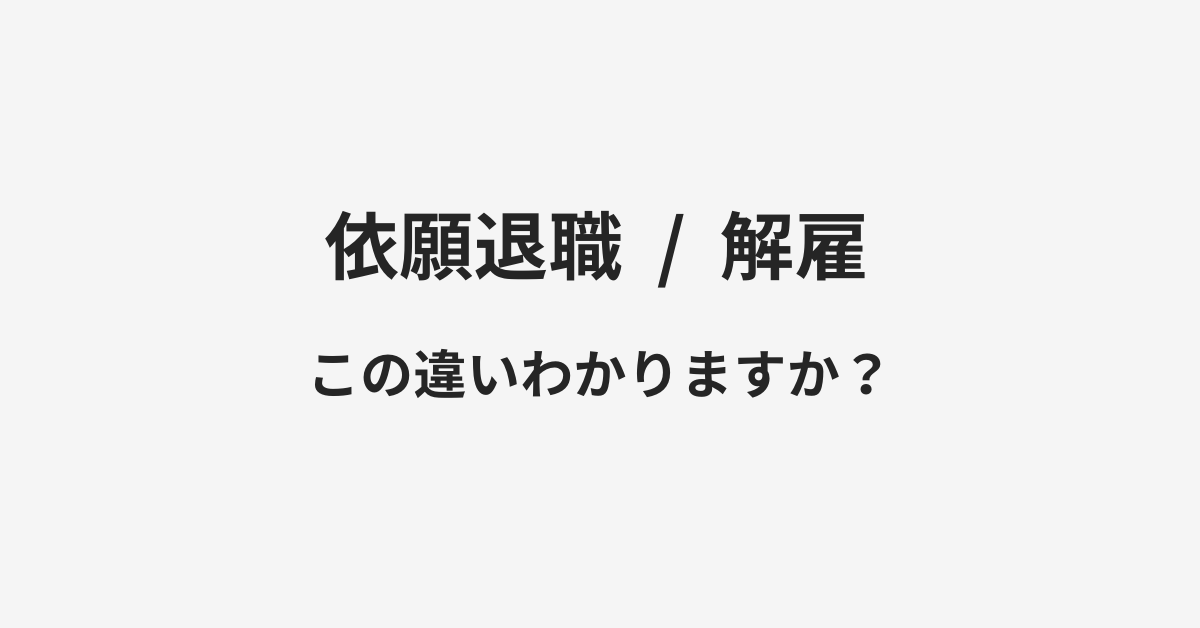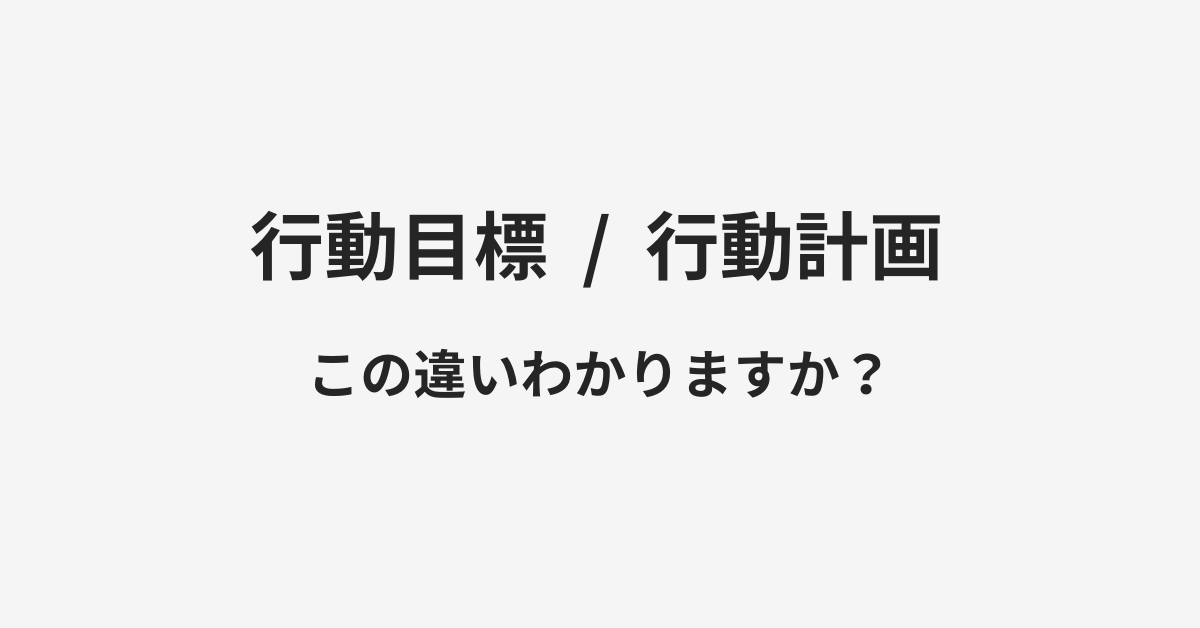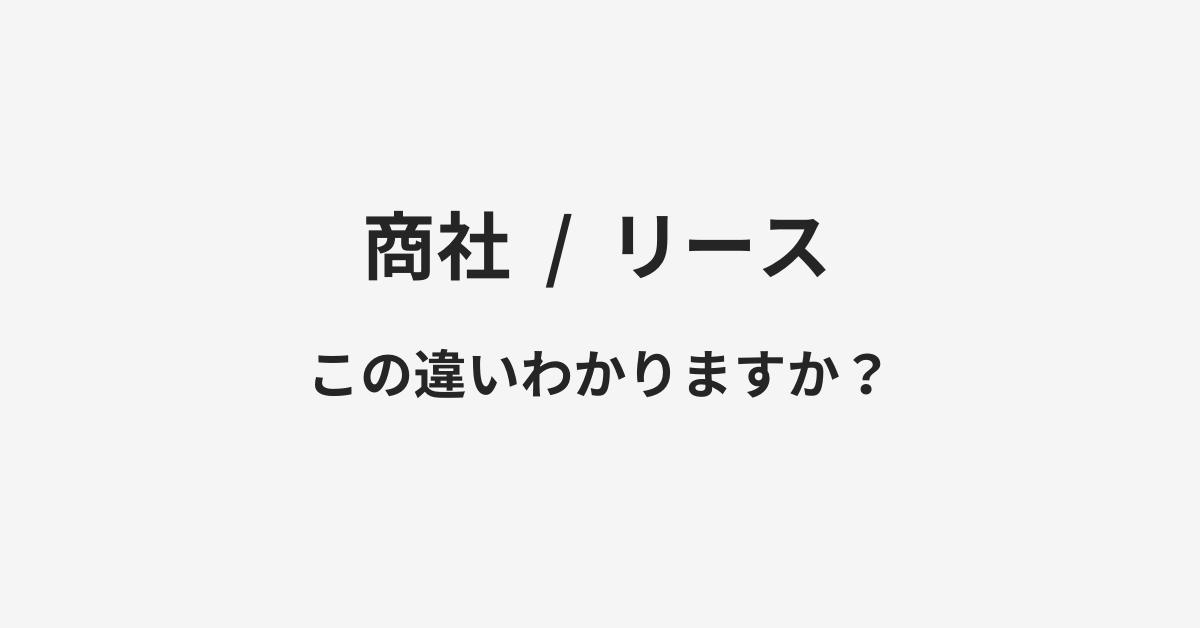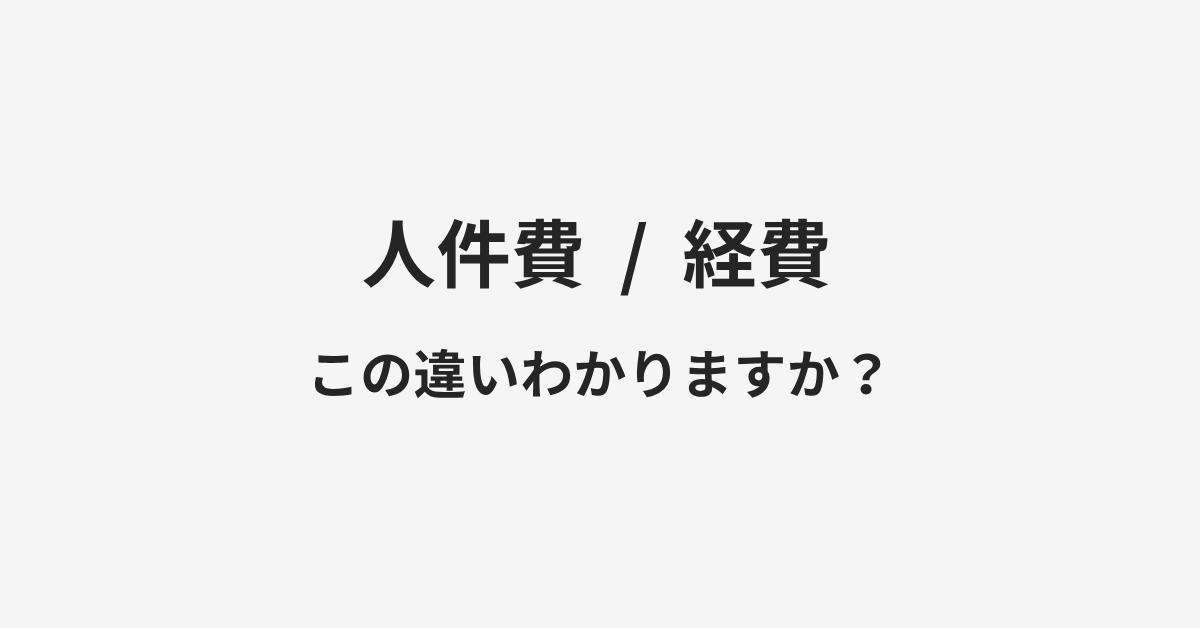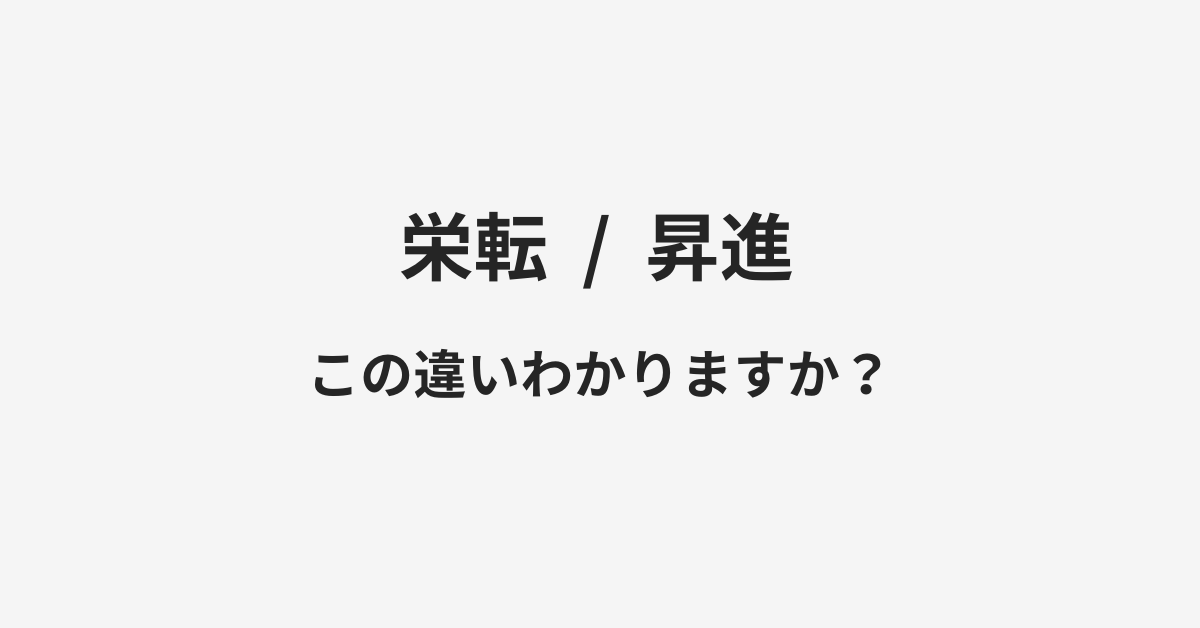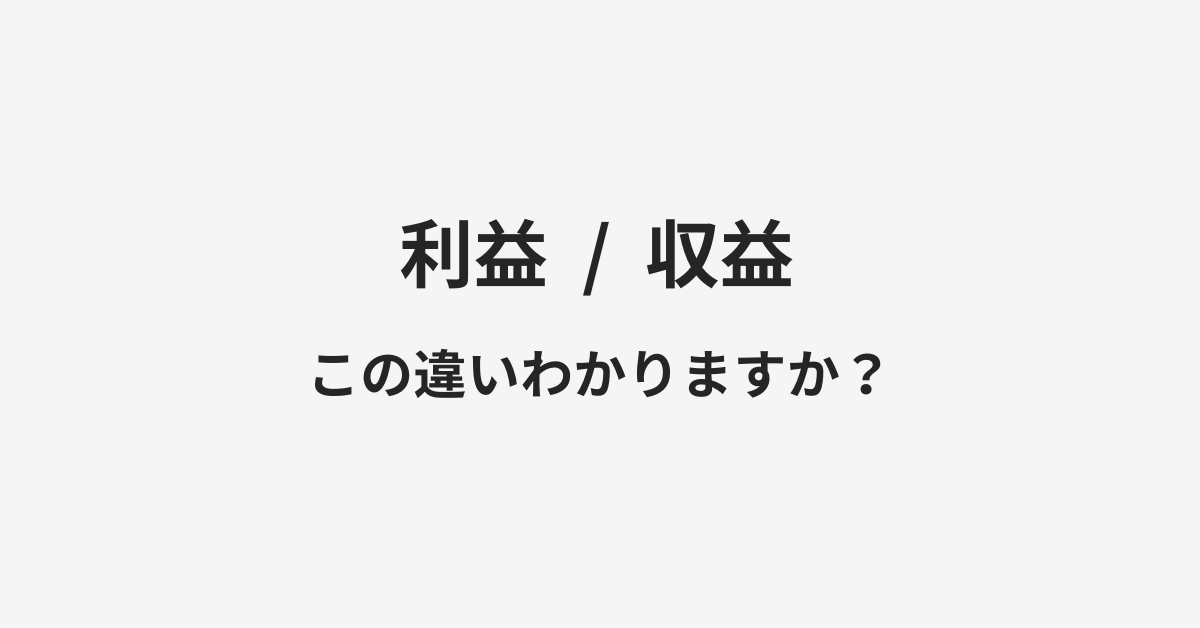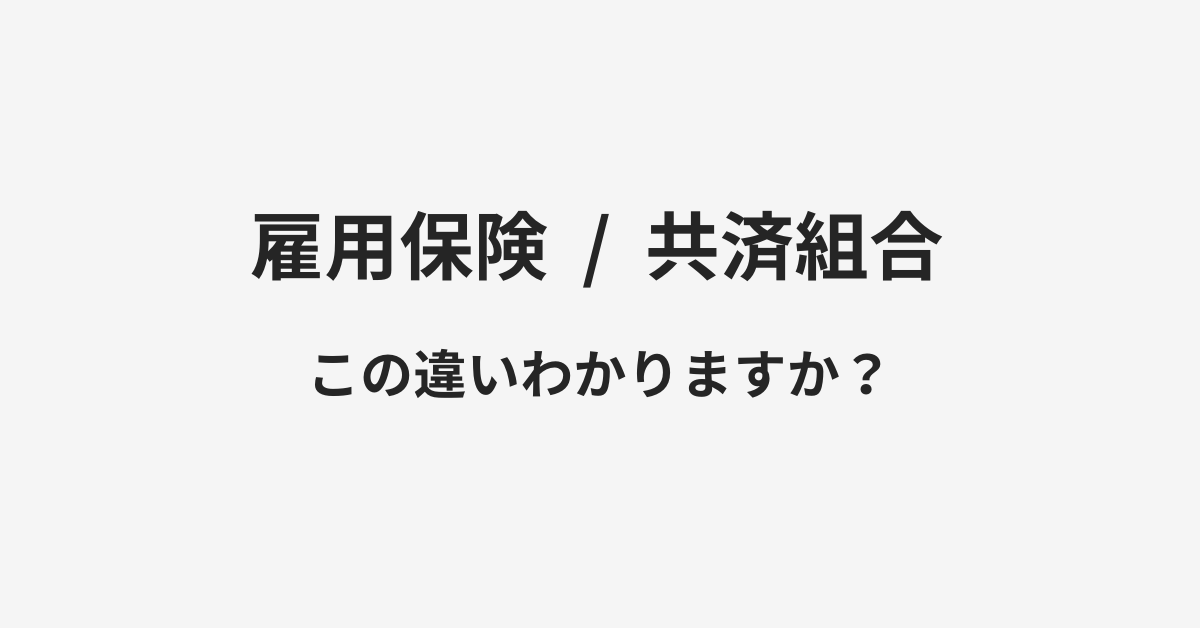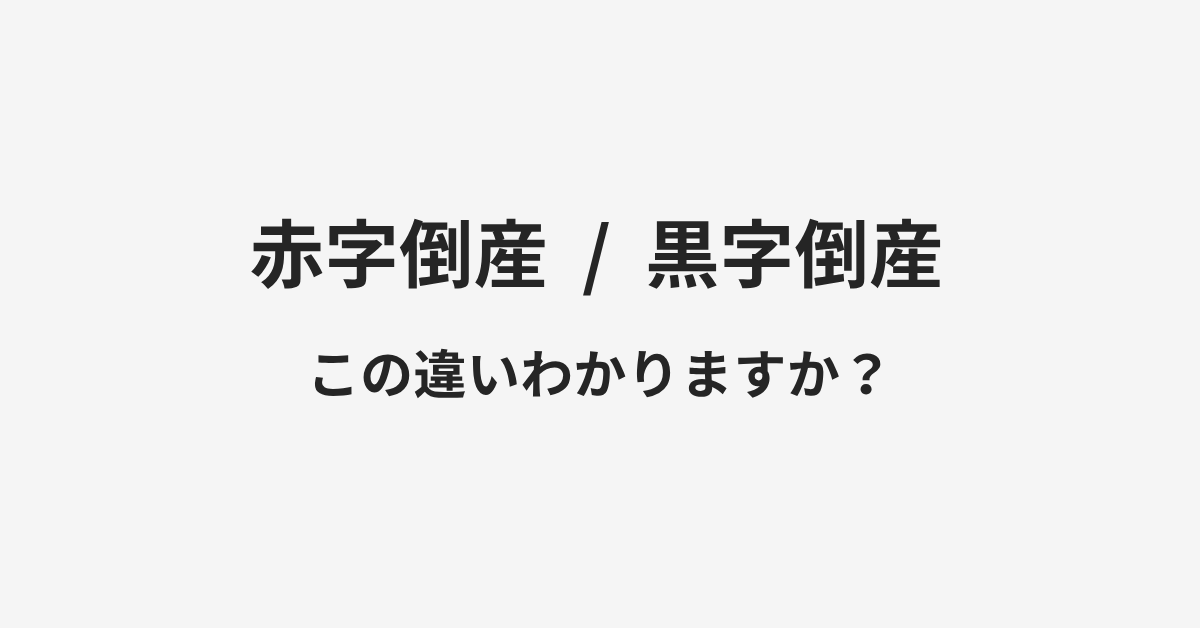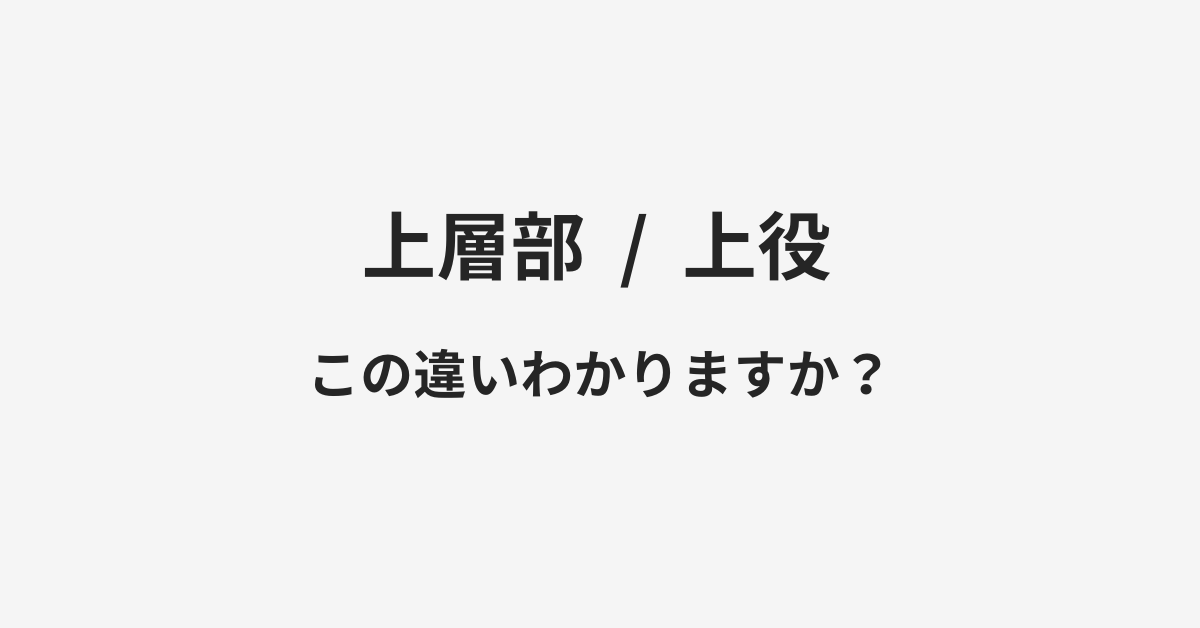【退職】と【退社】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
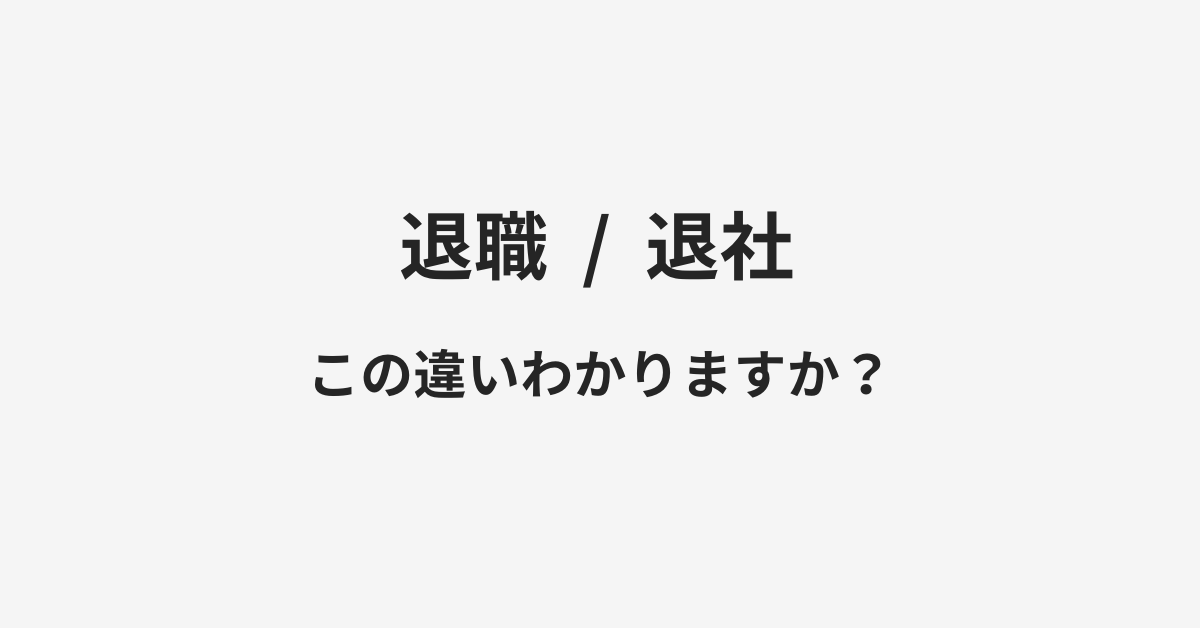
退職と退社の分かりやすい違い
退職と退社は、どちらも会社を離れることを表しますが、その意味と使用場面に大きな違いがあります。
退職は雇用関係の終了を意味し、退社は日々の業務終了後に会社を出ることを指します。退職は人生の転機、退社は日常的な行為という違いがあります。
ビジネスコミュニケーションにおいて、この違いを正確に理解し使い分けることは、誤解を避ける上で重要です。
退職とは?
退職とは、勤務している会社や組織との雇用関係を終了し、その職を離れることを指します。定年退職、自己都合退職、会社都合退職など様々な形態があり、退職金、有給休暇の消化、社会保険の切り替えなど、多くの手続きを伴います。
退職プロセスは、退職願・退職届の提出から始まり、業務引き継ぎ、退職手続き、退職日を迎えるという流れが一般的です。労働基準法では、退職の申し出から2週間で退職可能ですが、就業規則により1ヶ月前の申告を求める企業が多いです。
企業側にとって退職は、人材流出による損失であり、退職率の管理、退職面談の実施、引き継ぎ体制の整備が重要です。一方、円満退職は将来のビジネスネットワーク維持にもつながるため、双方にとって適切な対応が求められます。
退職の例文
- ( 1 ) 来月末での退職を決意し、上司に退職願を提出しました。
- ( 2 ) 定年退職後も、嘱託社員として働き続けることになりました。
- ( 3 ) 退職手続きの一環として、会社支給品の返却を完了しました。
- ( 4 ) 円満退職のため、後任への引き継ぎを丁寧に行っています。
- ( 5 ) 退職金制度の改定により、確定拠出年金へ移行しました。
- ( 6 ) 早期退職優遇制度を利用し、セカンドキャリアをスタートします。
退職の会話例
退社とは?
退社とは、その日の業務を終えて会社から出ること、または会社を辞めることの両方の意味を持つ言葉です。日常的には前者の意味で使われることが多く、定時退社早退などの表現で、物理的に会社を離れる行為を指します。
働き方改革の文脈では、定時退社の推進、ノー残業デーの設定など、適切な退社時間の管理が重視されています。退社時刻の記録は勤怠管理の基本であり、残業時間の把握、労働時間の適正化に不可欠です。
ビジネスマナーとしては、退社時の挨拶お先に失礼しますお疲れ様でしたが重要で、職場の人間関係を円滑にします。また、退社後の連絡可否、緊急連絡体制の確立も、現代のビジネスにおいて重要な要素となっています。
退社の例文
- ( 1 ) 今日は定時退社日なので、18時には退社します。
- ( 2 ) 働き方改革の一環で、19時以降の退社を原則禁止としました。
- ( 3 ) 退社時刻をICカードで記録し、正確な勤怠管理を実施しています。
- ( 4 ) 上司より先に退社する際は、必ず挨拶をしてから帰ります。
- ( 5 ) フレックスタイム制により、15時退社も可能になりました。
- ( 6 ) 退社後の緊急連絡は、部長の携帯電話にお願いします。
退社の会話例
退職と退社の違いまとめ
退職と退社の最も重要な違いは、雇用関係の継続性にあります。退職は雇用関係の終了を意味し、退社は単に会社を出る行為を指すことが多いです。
使用場面も異なり、退職金退職願とは言いますが退社金退社願とは言いません。逆に定時退社早退社とは言いますが定時退職とは言いません。
ビジネス文書では、この違いを明確にすることが重要です。誤用により彼は昨日退職しました(会社を辞めた)と彼は昨日退社しました(帰宅した)では、全く異なる意味になります。
退職と退社の読み方
- 退職(ひらがな):たいしょく
- 退職(ローマ字):taishoku
- 退社(ひらがな):たいしゃ
- 退社(ローマ字):taisha