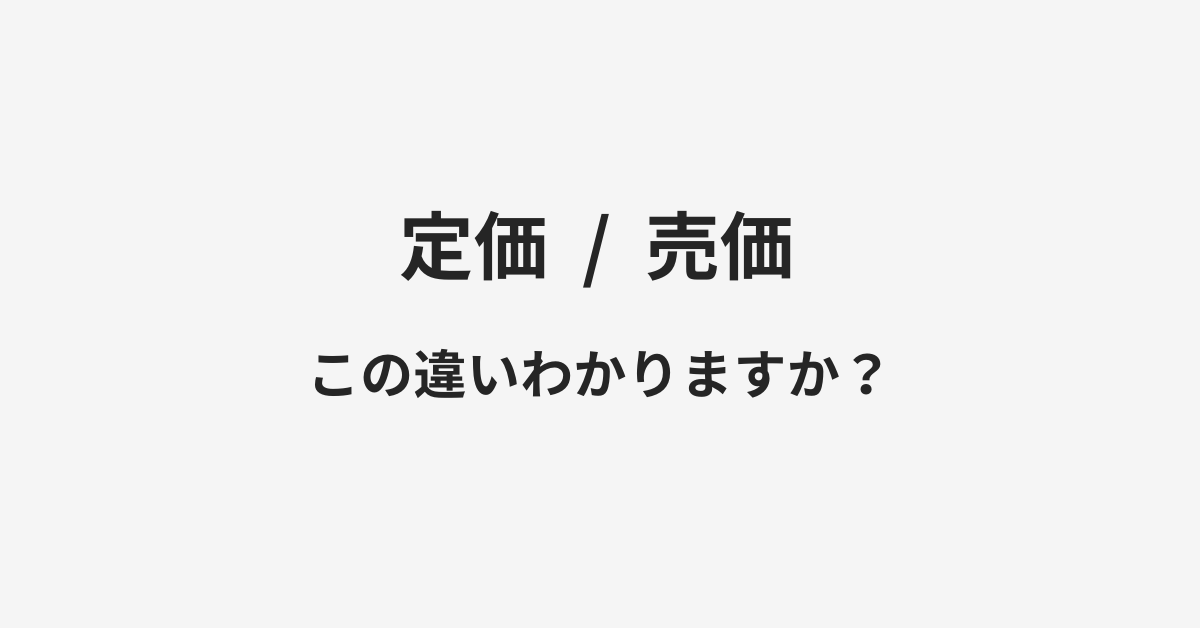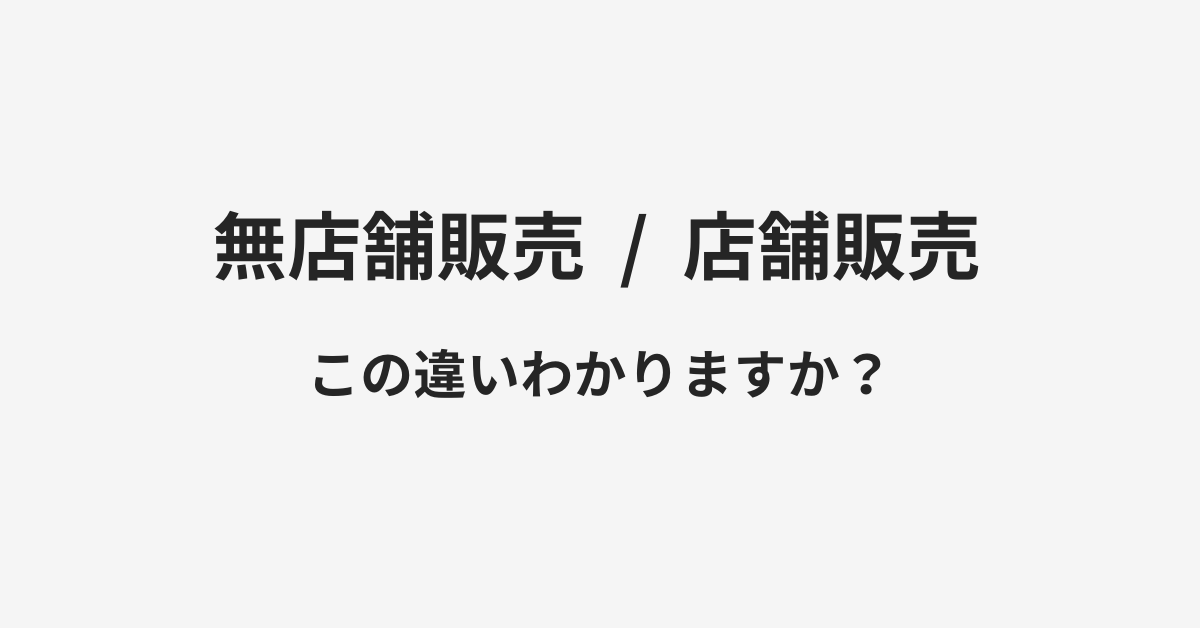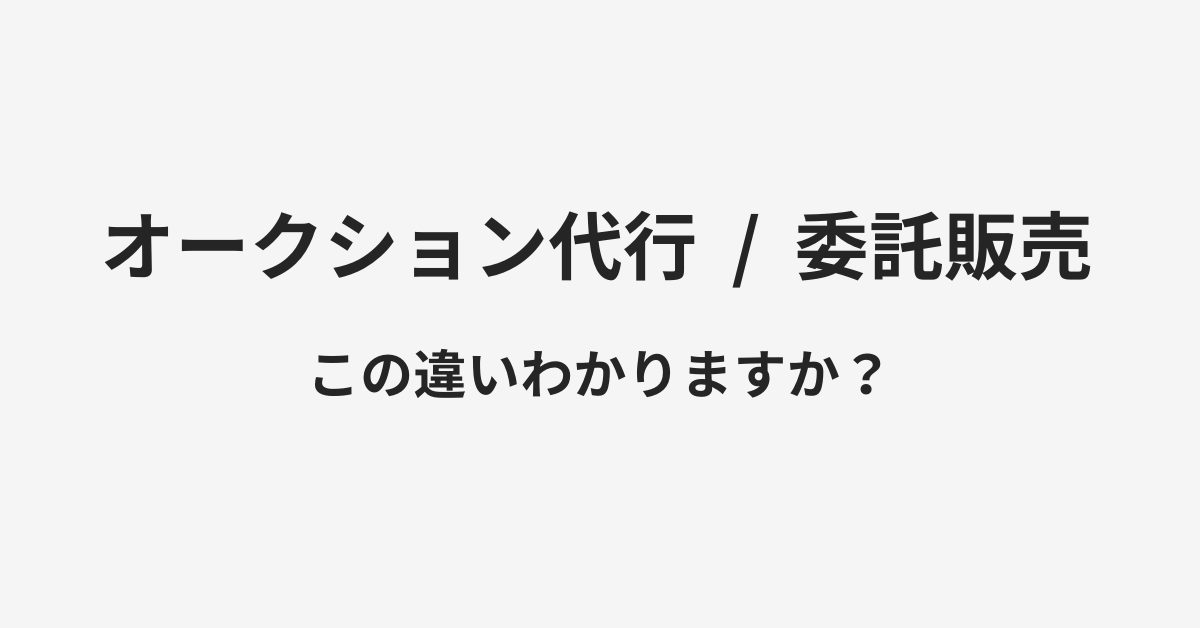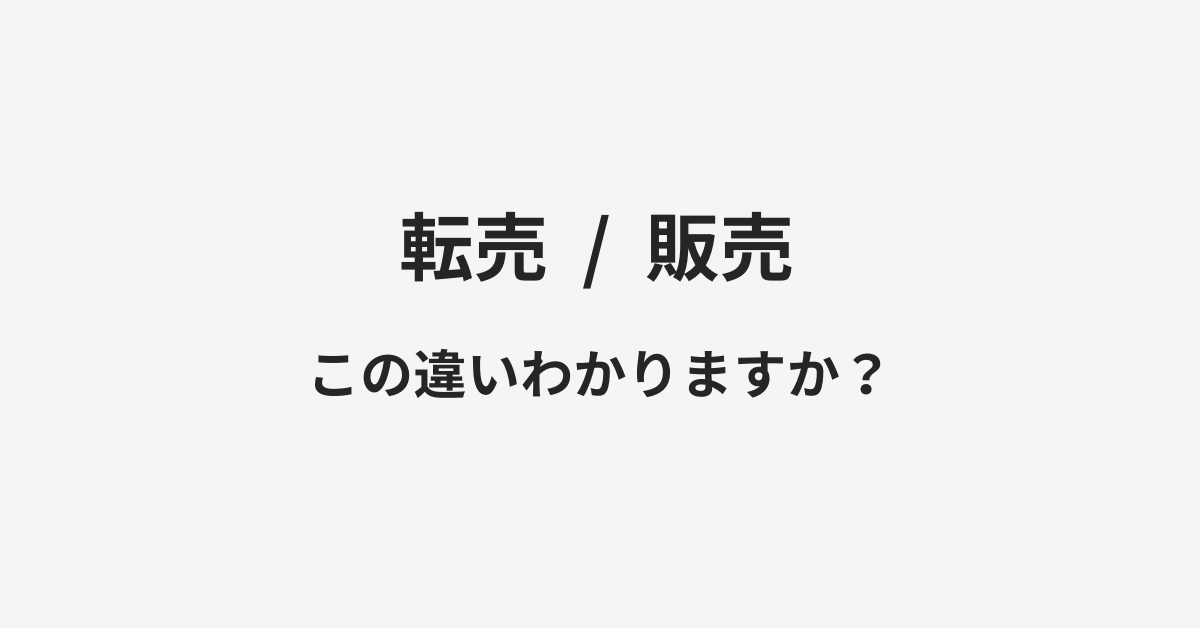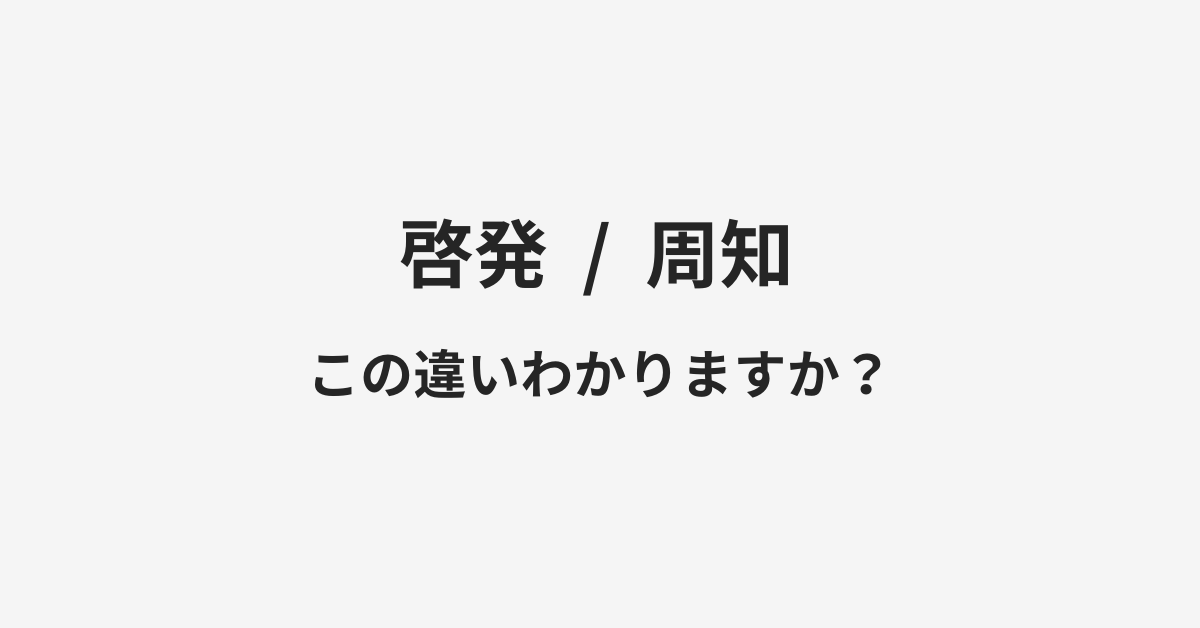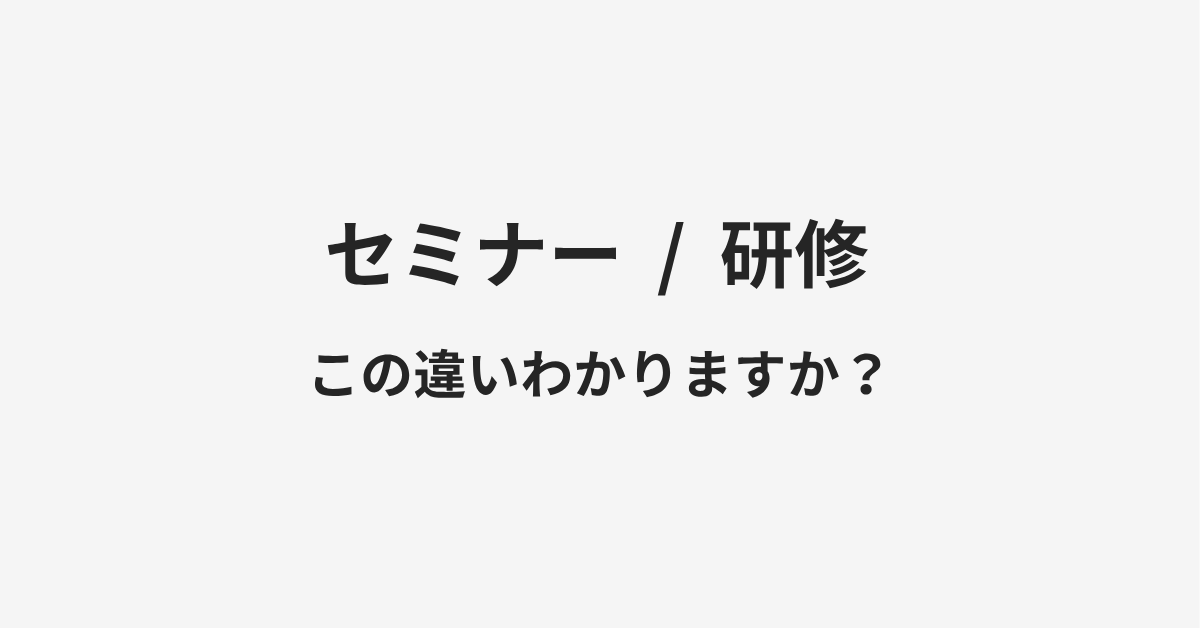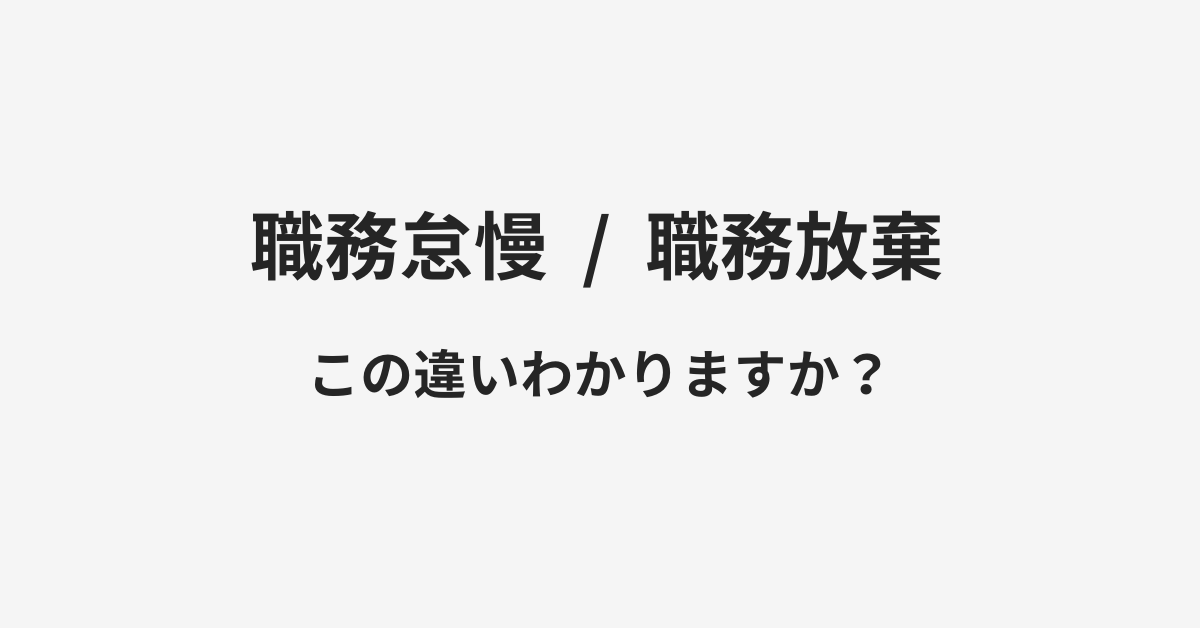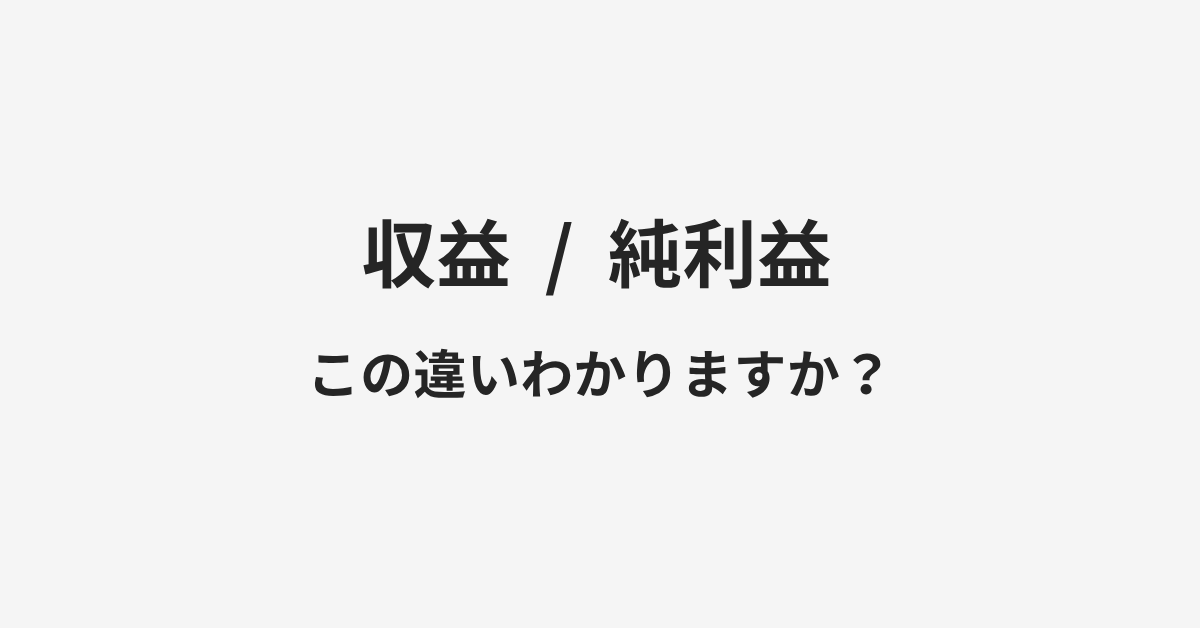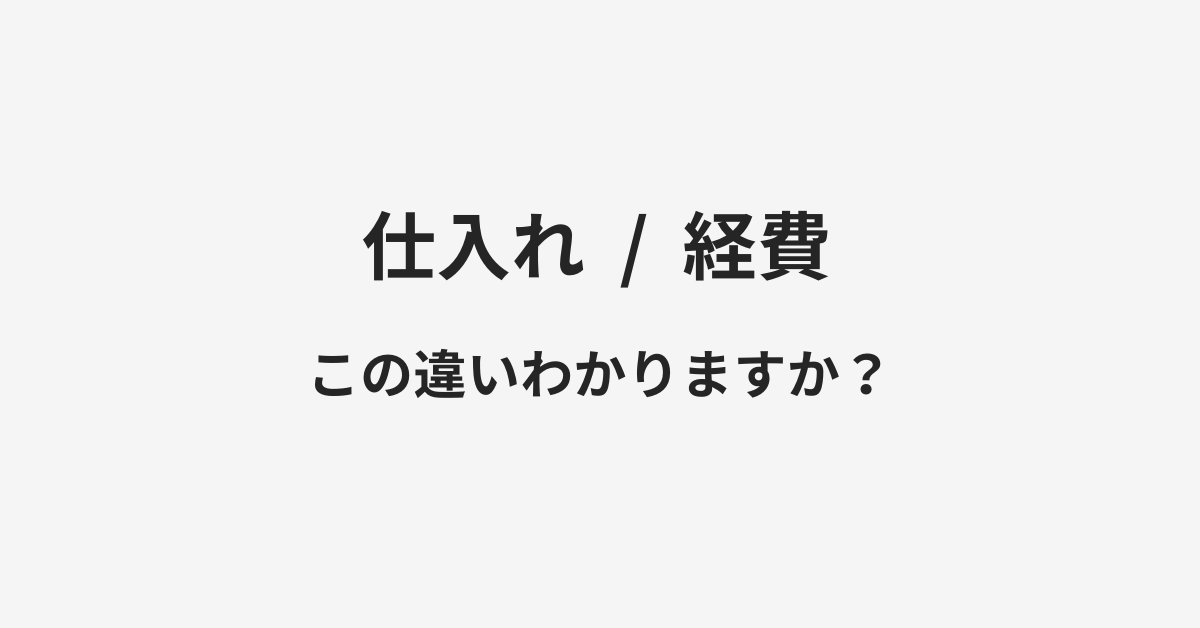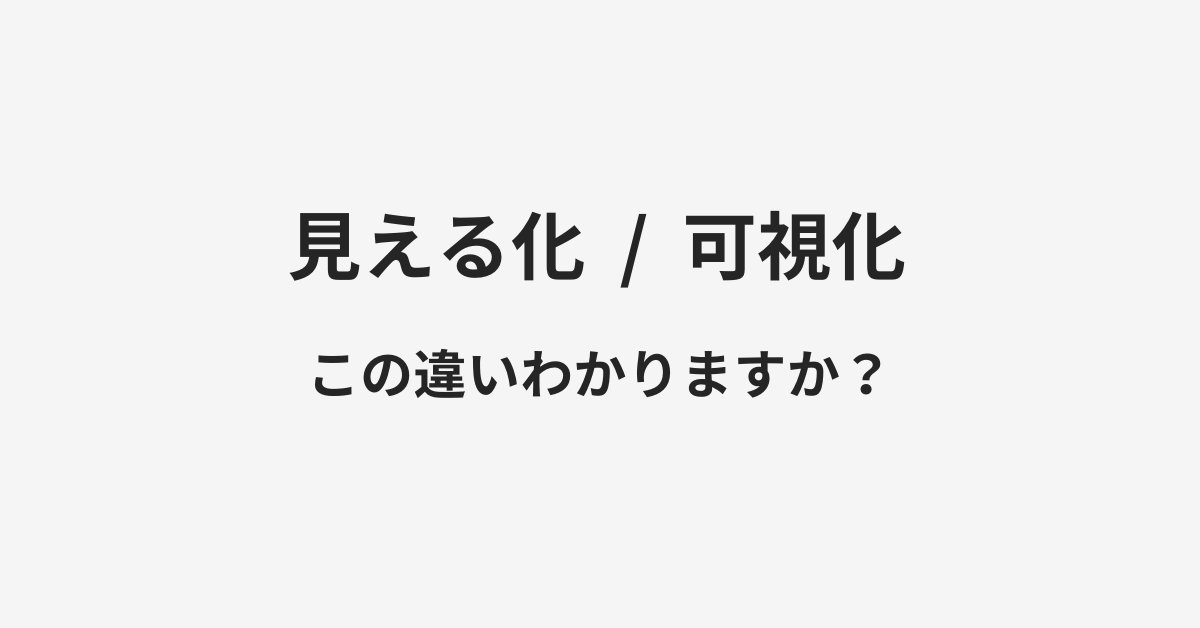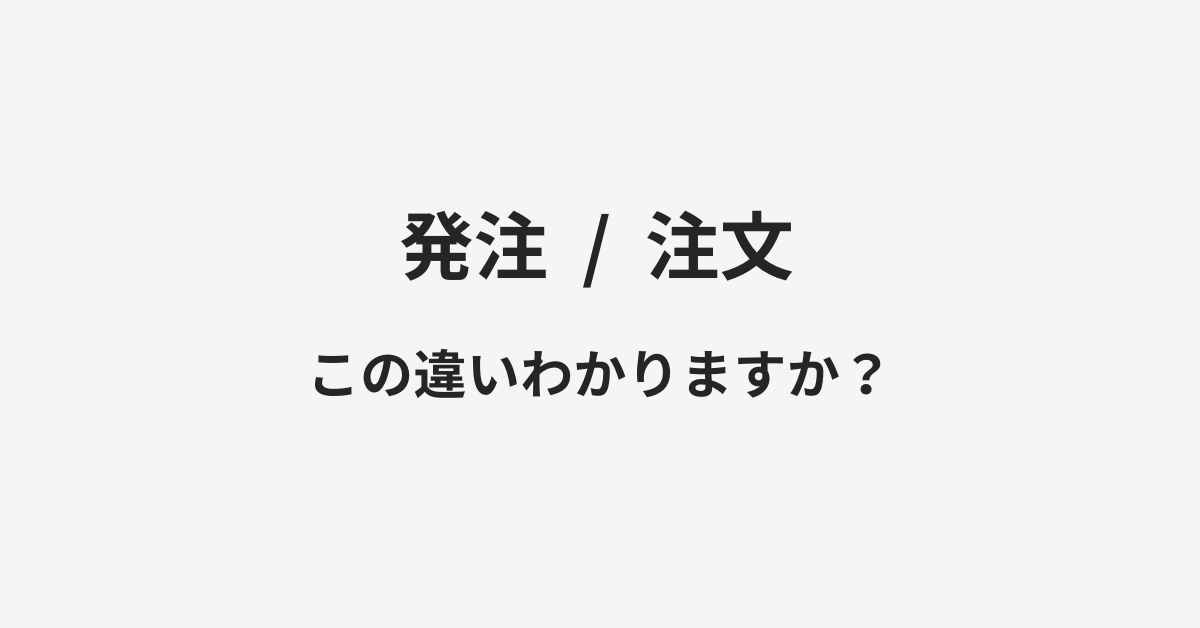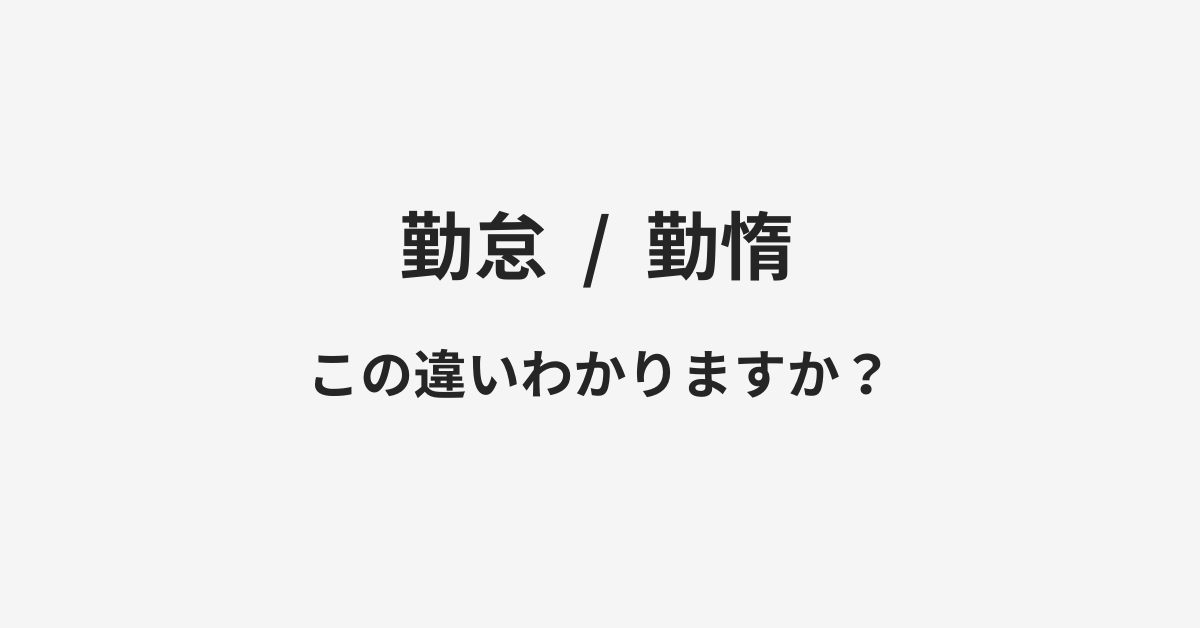【メーカー希望小売価格】と【オープン価格】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
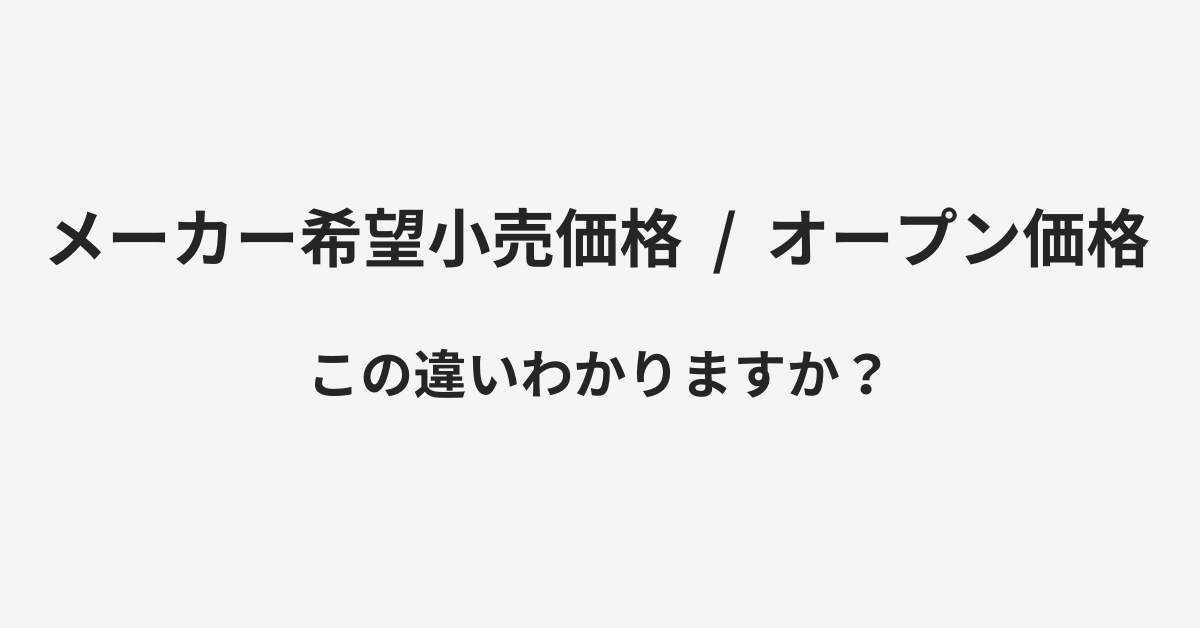
- ビジネス
- # オープン価格
- # メーカー希望小売価格
- 言葉の違い
メーカー希望小売価格とオープン価格の分かりやすい違い
メーカー希望小売価格とオープン価格は、商品の値段の決め方を表す言葉です。
メーカー希望小売価格は、商品を作った会社がこの値段で売ってほしいと決めた定価です。オープン価格は、定価を決めずに、お店が自由に値段を決められる方式です。
最近は価格競争が激しいため、家電製品などではオープン価格が主流になっています。
メーカー希望小売価格とは?
メーカー希望小売価格とは、製造業者が小売店に対して推奨する販売価格で、一般的に定価標準小売価格とも呼ばれる価格設定方式です。
商品のパッケージやカタログに記載され、消費者に対して価格の目安を提供します。ただし、独占禁止法により拘束力はなく、小売店は自由に販売価格を設定できます。書籍や新聞など再販売価格維持制度の対象商品を除き、実売価格は希望小売価格から割引されることが一般的です。高級ブランド品や化粧品など、ブランド価値維持が重要な商品で採用されることが多いです。
価格統制の手段としてではなく、あくまで参考価格として機能しています。
メーカー希望小売価格の例文
- ( 1 ) 新製品のメーカー希望小売価格を3万円に設定しましたが、実売は2万円台を想定しています。
- ( 2 ) メーカー希望小売価格からの値引率を、販促ツールとして活用しています。
- ( 3 ) 高級ブランドは、メーカー希望小売価格の維持によりブランド価値を守っています。
- ( 4 ) メーカー希望小売価格があることで、消費者は商品価値を判断しやすくなります。
- ( 5 ) 量販店でも、メーカー希望小売価格での販売を求められる商品があります。
- ( 6 ) メーカー希望小売価格の改定には、市場への事前告知が必要です。
メーカー希望小売価格の会話例
オープン価格とは?
オープン価格とは、メーカーが希望小売価格を設定せず、小売店が市場動向や競争状況に応じて自由に価格を決定できる価格設定方式です。
1990年代以降、家電製品やパソコンなどで急速に普及し、現在では多くの商品カテゴリーで採用されています。価格競争が激しい市場において、メーカーが実勢価格とかけ離れた希望小売価格を設定することの無意味さから生まれました。小売店は仕入れ価格に基づいて、独自の価格戦略を展開でき、消費者は店舗間の価格比較により最安値を選択できます。
ただし、価格の不透明性や極端な安売りによるブランド毀損のリスクもあり、メーカーと小売店の関係性が重要になります。
オープン価格の例文
- ( 1 ) 新型テレビはオープン価格なので、各店舗で価格競争が激化しています。
- ( 2 ) オープン価格商品は、仕入れ交渉力が収益性を大きく左右します。
- ( 3 ) オープン価格により、ネット通販と実店舗の価格差が明確になりました。
- ( 4 ) オープン価格商品の適正マージン確保が、小売店の経営課題です。
- ( 5 ) メーカーとしては、オープン価格でも最低販売価格のガイドラインを示したいです。
- ( 6 ) オープン価格化により、価格.comなどの比較サイトの影響力が増大しました。
オープン価格の会話例
メーカー希望小売価格とオープン価格の違いまとめ
メーカー希望小売価格とオープン価格は、価格決定権の所在と市場での機能が大きく異なります。
メーカー希望小売価格は価格の目安を示し、オープン価格は市場原理に委ねる方式です。商品特性、市場環境、ブランド戦略により使い分けられ、消費者にとっても購買行動に影響を与えます。
企業は自社商品の特性と市場ポジションを考慮し、適切な価格設定方式を選択する必要があります。
メーカー希望小売価格とオープン価格の読み方
- メーカー希望小売価格(ひらがな):めーかーきぼうこうりかかく
- メーカー希望小売価格(ローマ字):me-ka-kiboukourikakaku
- オープン価格(ひらがな):おーぷんかかく
- オープン価格(ローマ字):o-punnkakaku