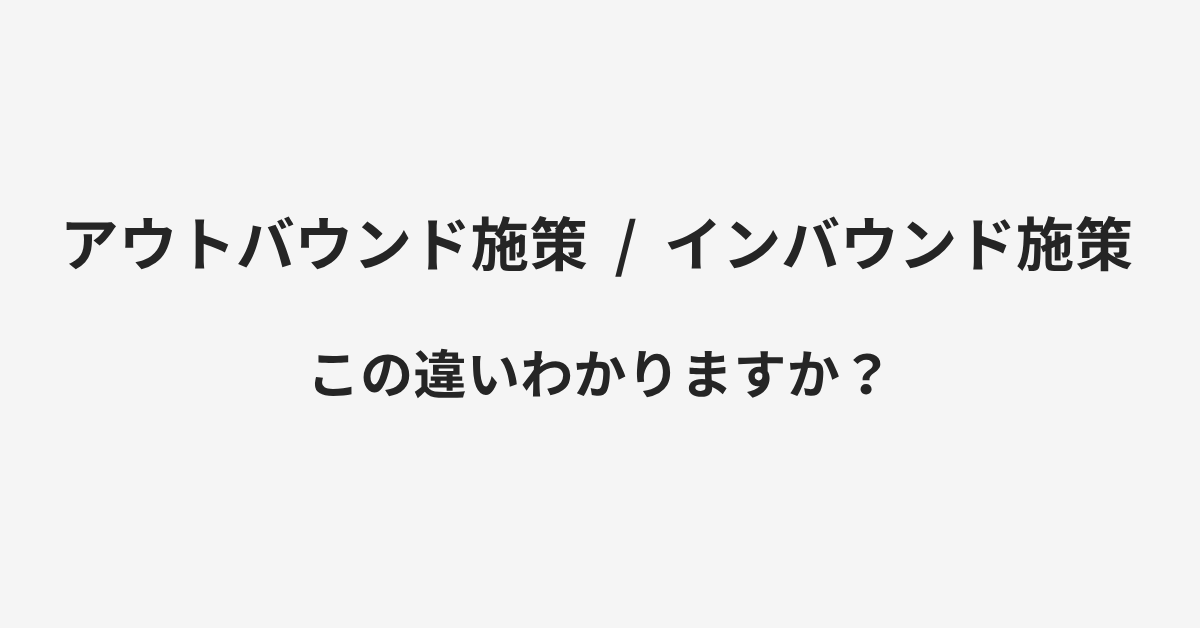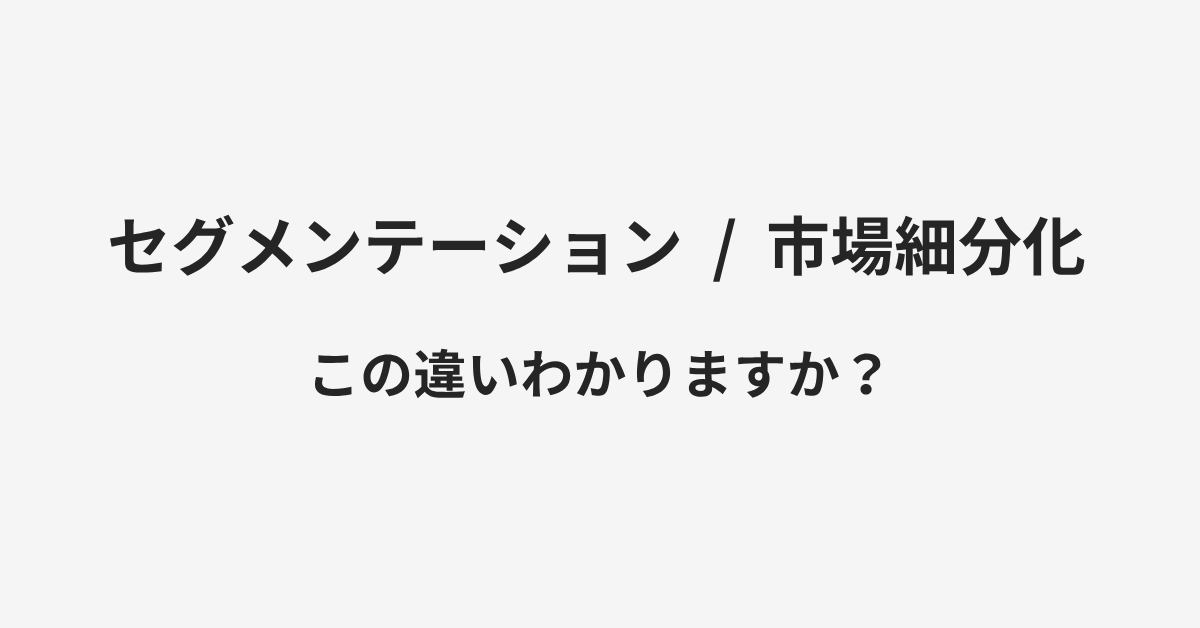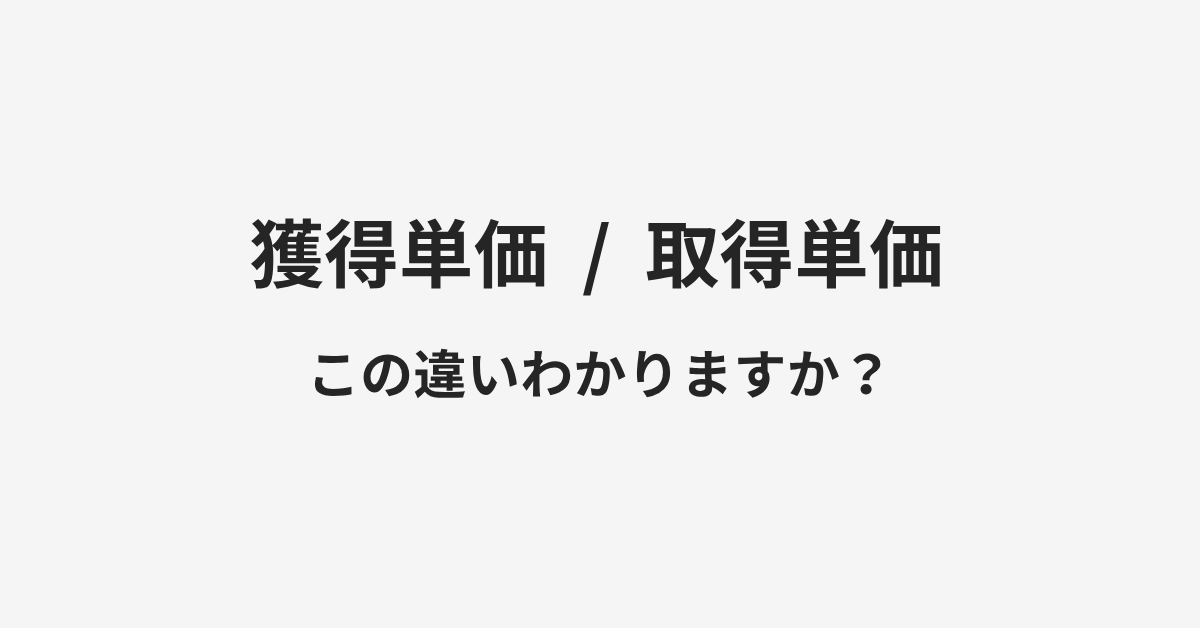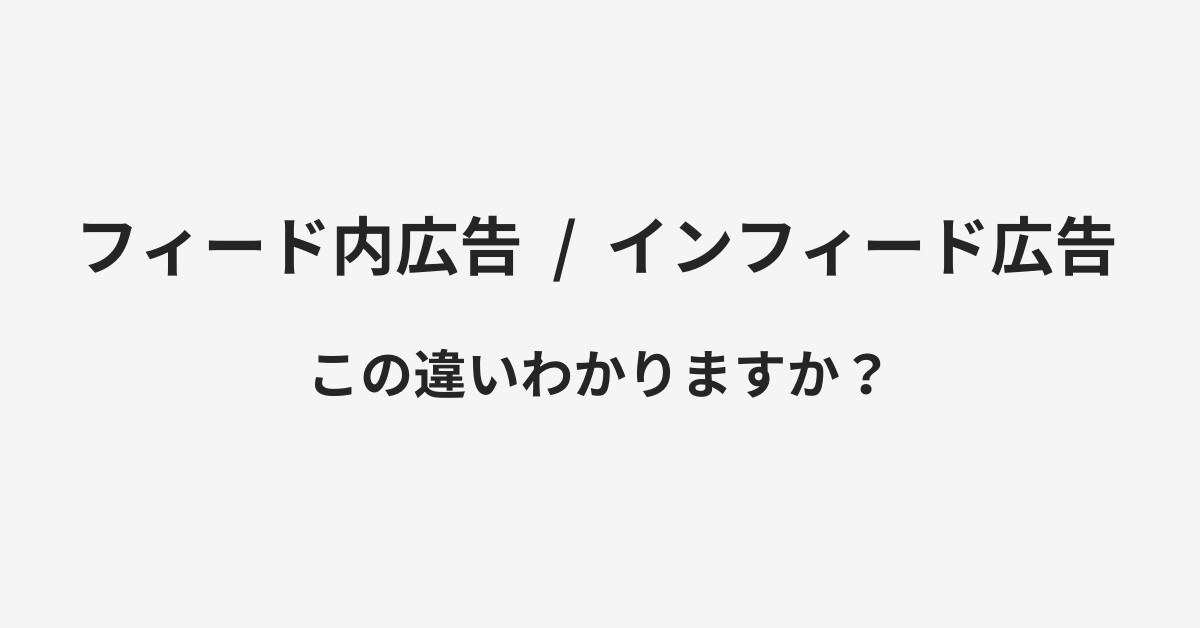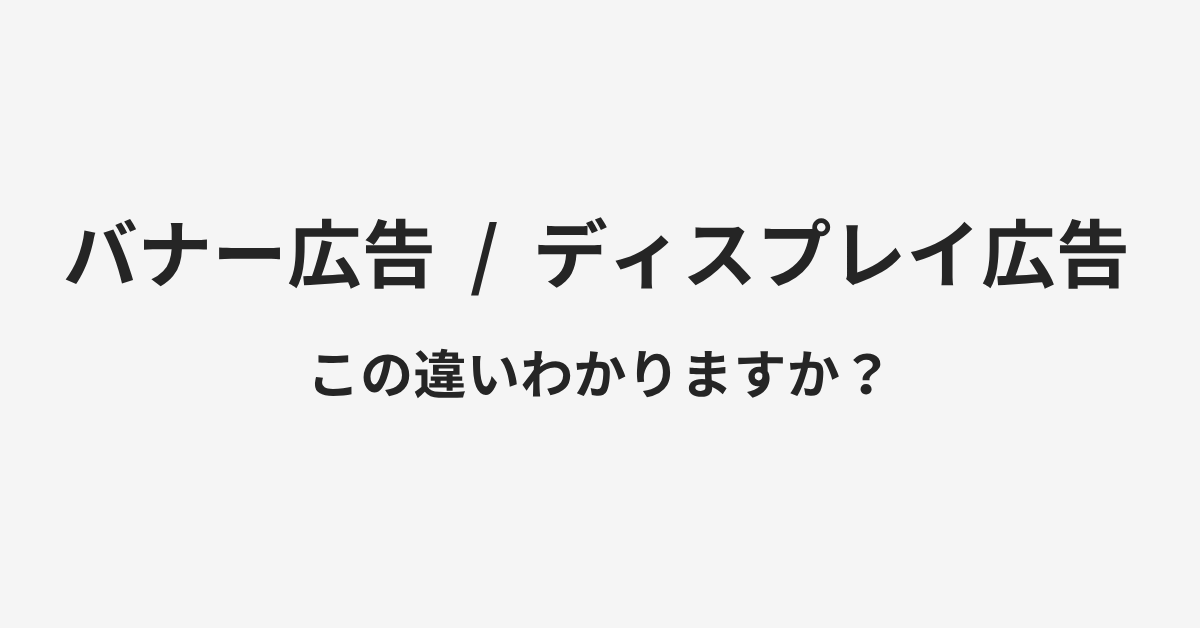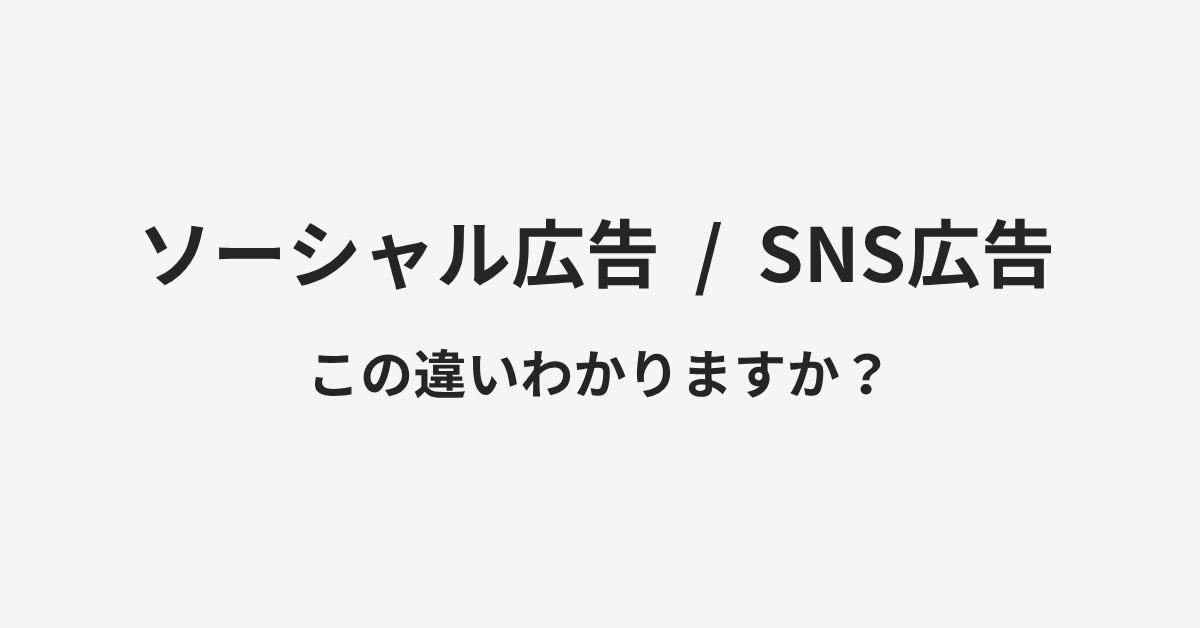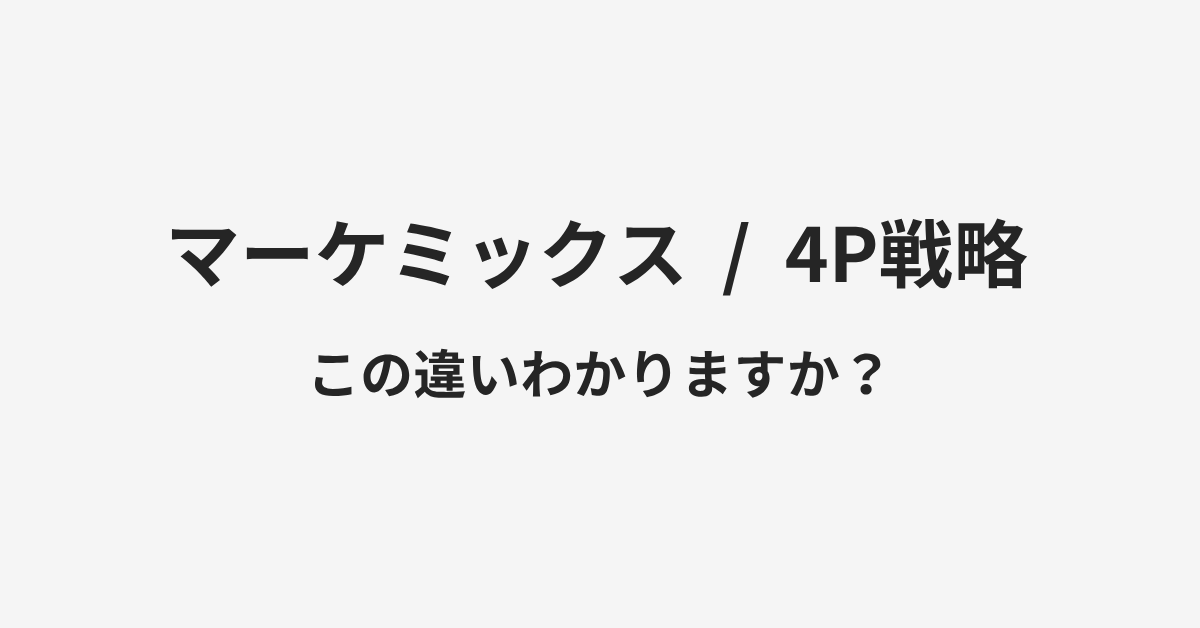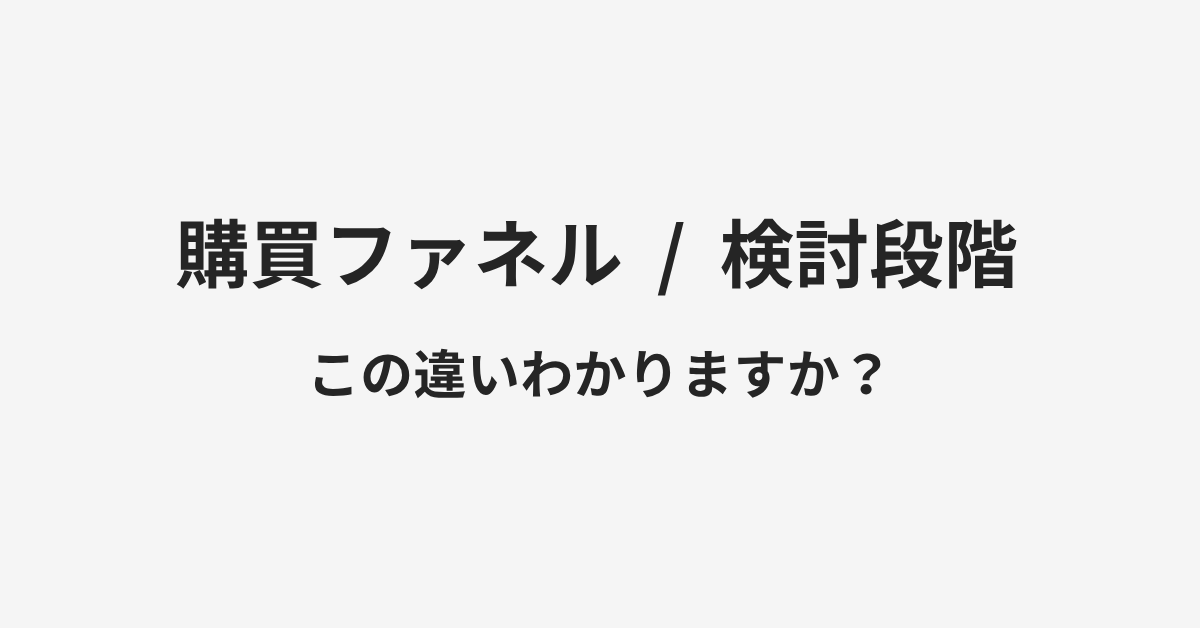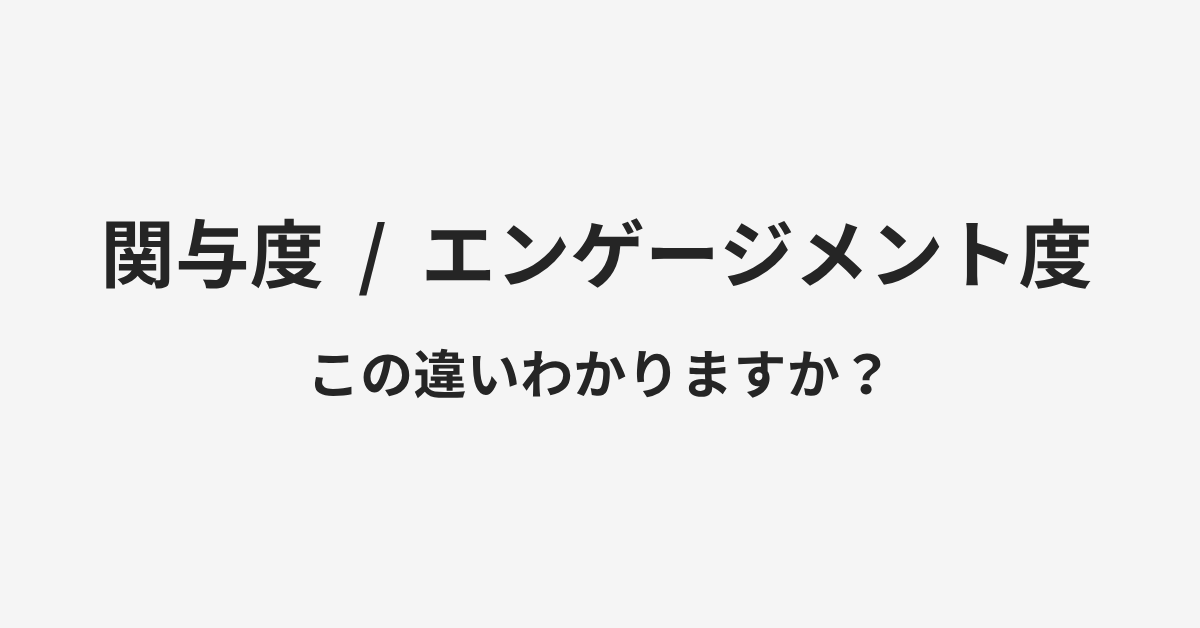【有望顧客】と【未熟顧客】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
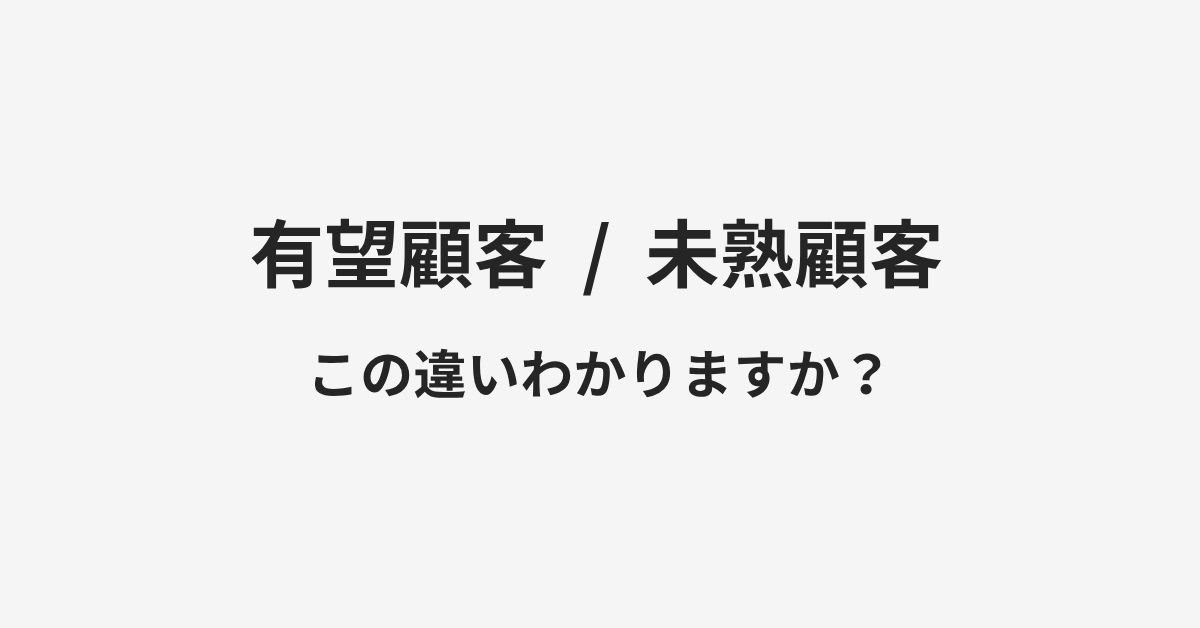
有望顧客と未熟顧客の分かりやすい違い
有望顧客は、購買の可能性が高く、すぐに営業がアプローチすべき見込み客のことです。予算があり、決裁権を持ち、ニーズが明確な状態の顧客を指します。
未熟顧客は、まだ購買の準備ができていない見込み客です。情報収集段階で、予算やタイミングが不明確なため、時間をかけて育成する必要があります。
有望顧客は今すぐ客、未熟顧客はそのうち客という違いがあり、アプローチ方法が異なります。
有望顧客とは?
有望顧客(ホットリード/SQL:Sales Qualified Lead)とは、購買意欲が高く、短期間での成約が期待できる質の高い見込み客を指します。BANT条件(Budget:予算、Authority:決裁権、Need:ニーズ、Timeframe:導入時期)を満たし、具体的な課題解決を求めている段階にあります。
リードスコアが高く、営業リソースを優先的に配分すべき対象です。有望顧客の特徴として、複数回のコンテンツ閲覧、価格ページ訪問、デモリクエスト、見積もり依頼などの行動が見られます。営業アプローチでは、具体的な提案、ROI提示、導入支援の説明など、クロージングに向けた活動が中心となります。
CRMでの適切な管理により、有望顧客の取りこぼしを防ぎ、営業効率を最大化できます。成約率は一般的に20-30%と高く、売上への直接的な貢献が期待されます。
有望顧客の例文
- ( 1 ) 有望顧客の定義を明確化し、営業への引き渡し基準を設定したことで、商談化率が向上しました
- ( 2 ) AIによる有望顧客の自動判定により、営業の生産性が35%向上しています
- ( 3 ) 有望顧客専任チームの設置により、クロージング率が50%以上に改善されました
- ( 4 ) 有望顧客の行動パターン分析から、最適なアプローチタイミングを特定しました
- ( 5 ) リアルタイムで有望顧客を検知し、営業に即座にアラートを送るシステムを構築しました
- ( 6 ) 有望顧客のニーズに特化した提案テンプレートにより、成約期間が短縮されました
有望顧客の会話例
未熟顧客とは?
未熟顧客(コールドリード/MQL:Marketing Qualified Lead)とは、将来的な購買可能性はあるものの、現時点では購買準備が整っていない見込み客を指します。課題認識が曖昧、予算未確定、意思決定プロセス初期段階など、すぐには商談化できない状態にあります。
しかし、適切なナーチャリングにより、将来の有望顧客に転換する可能性を秘めています。未熟顧客には、教育的コンテンツ、事例紹介、ウェビナー招待など、価値提供を中心としたコミュニケーションが効果的です。性急な営業アプローチは逆効果となり、関係性を損なうリスクがあります。
MA(マーケティングオートメーション)を活用した長期的な育成が重要です。統計的に、B2Bリードの約80%は未熟顧客であり、その中の20-30%が18-24ヶ月後に購買に至るとされ、戦略的な育成プログラムの価値は高いです。
未熟顧客の例文
- ( 1 ) 未熟顧客向けナーチャリングプログラムにより、6ヶ月後の商談化率が3倍に向上しました
- ( 2 ) 未熟顧客の段階的な教育により、質の高い有望顧客への転換に成功しています
- ( 3 ) 未熟顧客データベースから、将来の市場トレンドと新規ニーズを発見しました
- ( 4 ) 未熟顧客とのエンゲージメント継続により、競合からの乗り換えを実現しています
- ( 5 ) 業界別の未熟顧客育成シナリオを開発し、効率的なリード育成を実現しました
- ( 6 ) 未熟顧客の離脱防止施策により、長期的な商談パイプラインを確保しています
未熟顧客の会話例
有望顧客と未熟顧客の違いまとめ
有望顧客と未熟顧客は、購買準備度によって分類される見込み客の対照的なカテゴリーです。適切な識別と異なるアプローチの実施が、効率的な顧客獲得の鍵となります。
実務では、リードスコアリングにより両者を自動判別し、有望顧客は営業へ、未熟顧客はマーケティングで育成という役割分担を明確にすることが重要です。
両カテゴリーの適切な管理により、短期の売上確保と長期のパイプライン構築を両立させ、持続的な事業成長を実現できます。
有望顧客と未熟顧客の読み方
- 有望顧客(ひらがな):ゆうぼうこきゃく
- 有望顧客(ローマ字):yuuboukokyaku
- 未熟顧客(ひらがな):みじゅくこきゃく
- 未熟顧客(ローマ字):mijukukokyaku