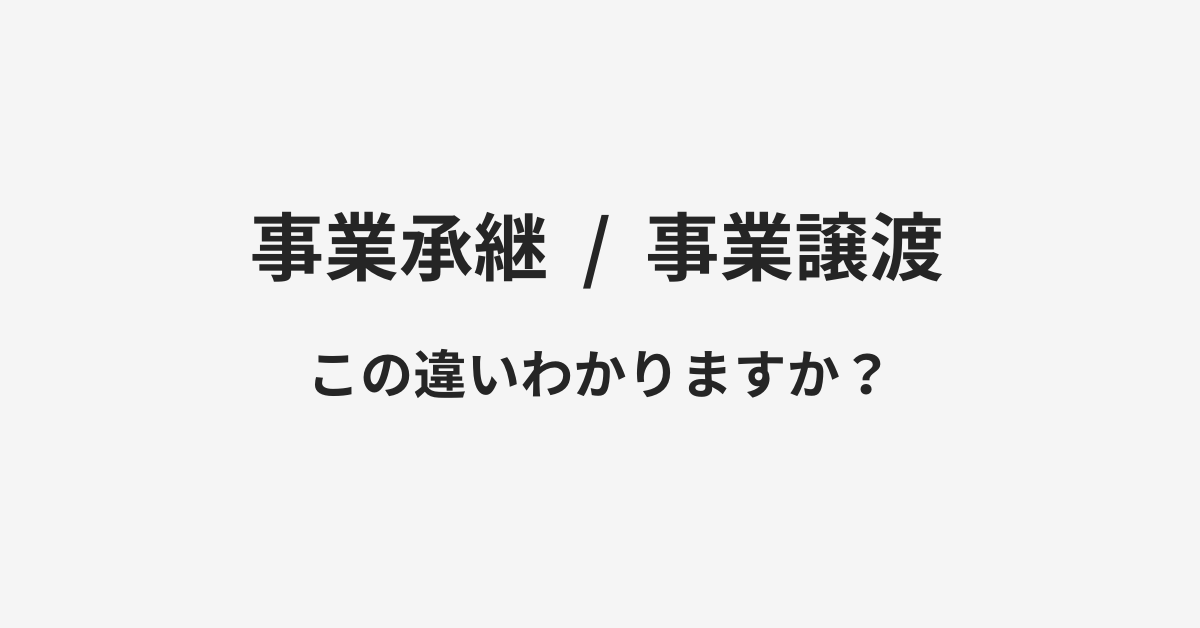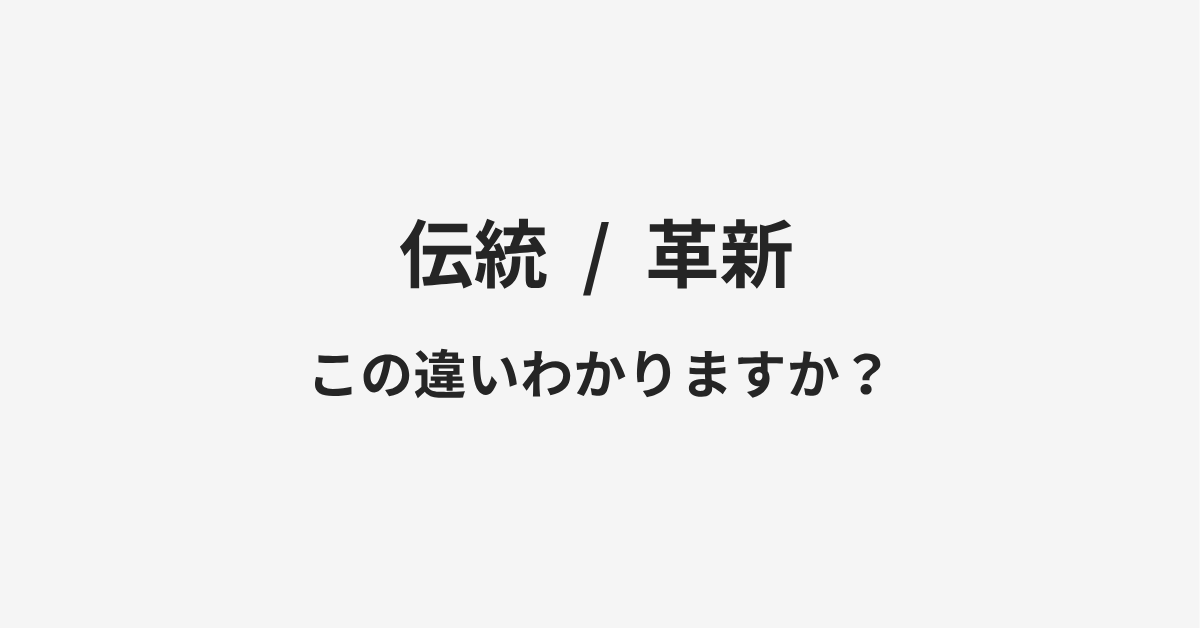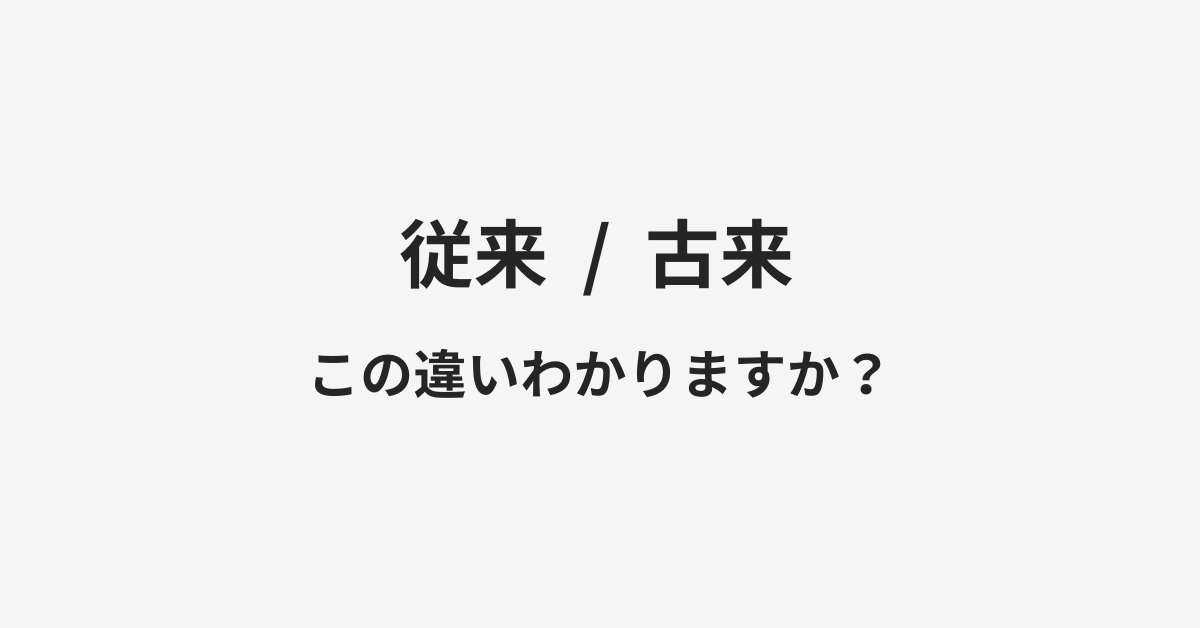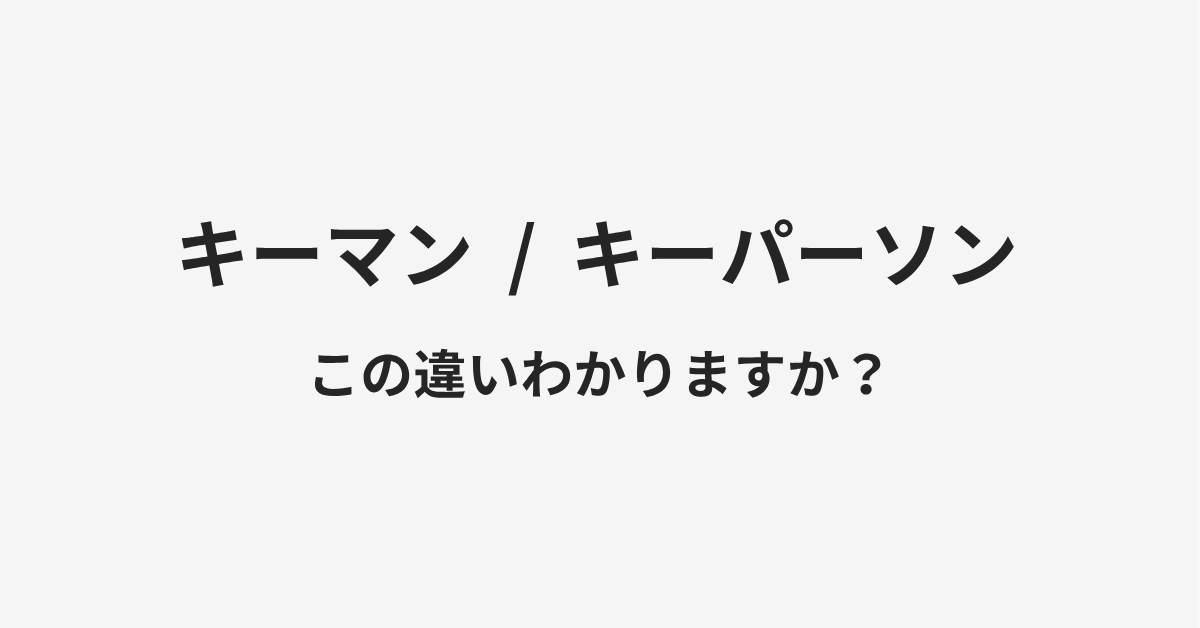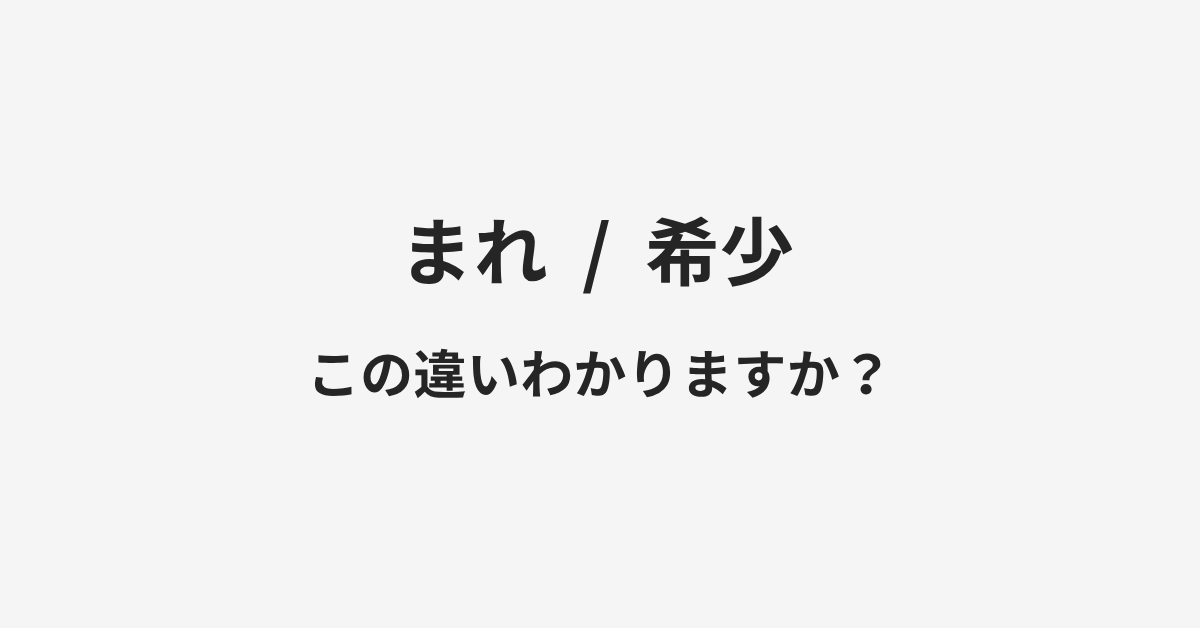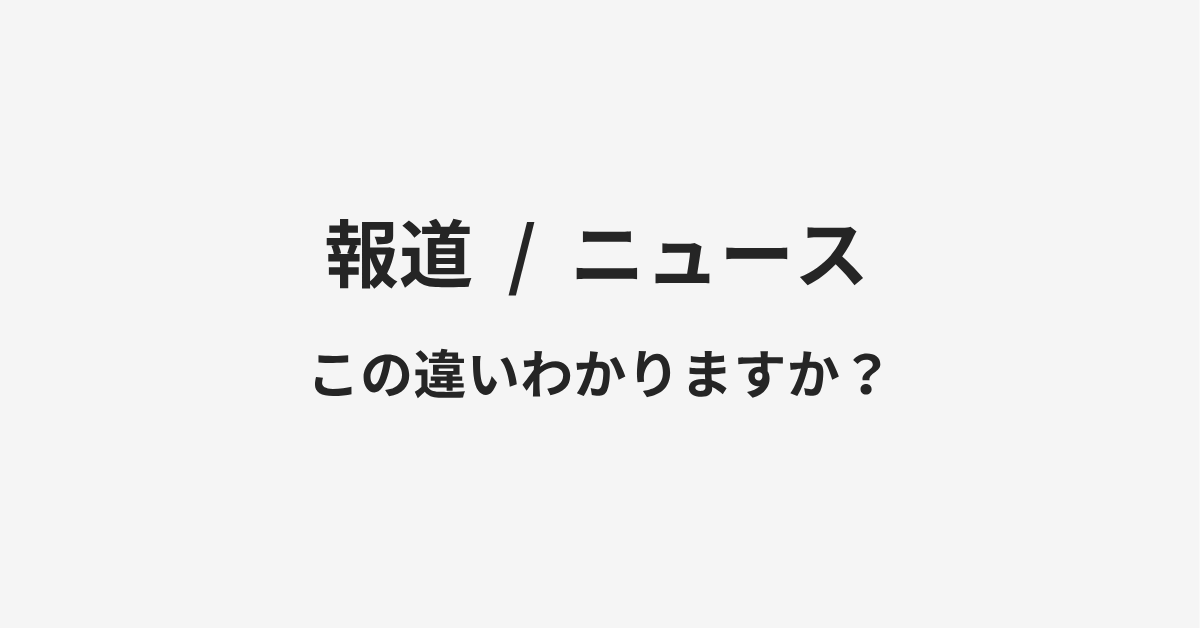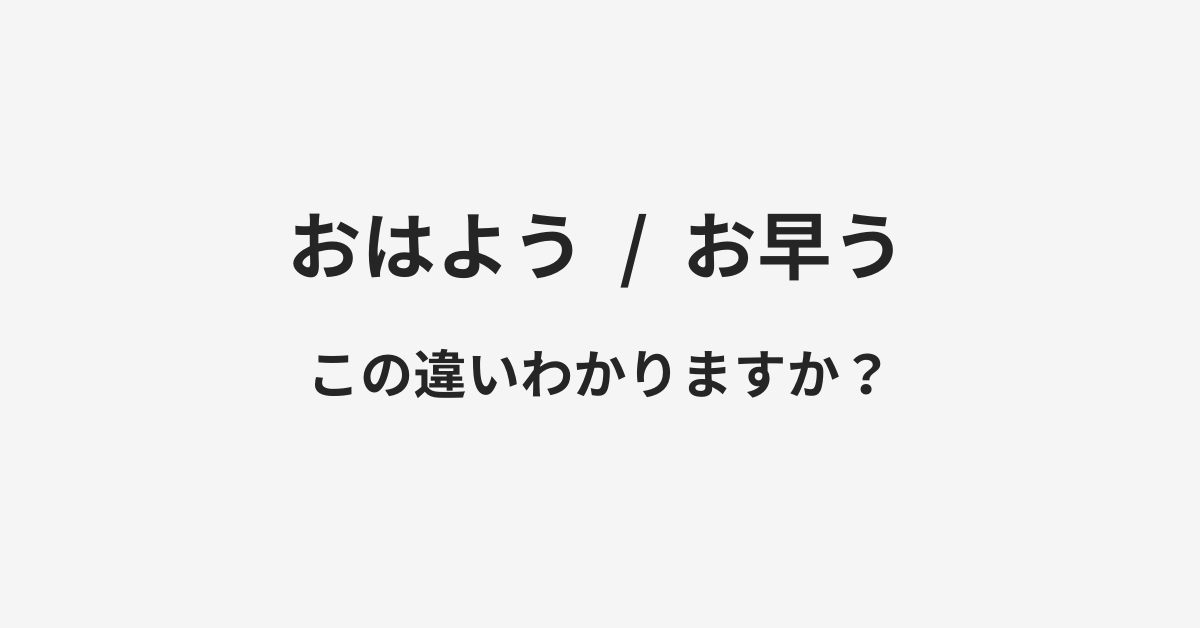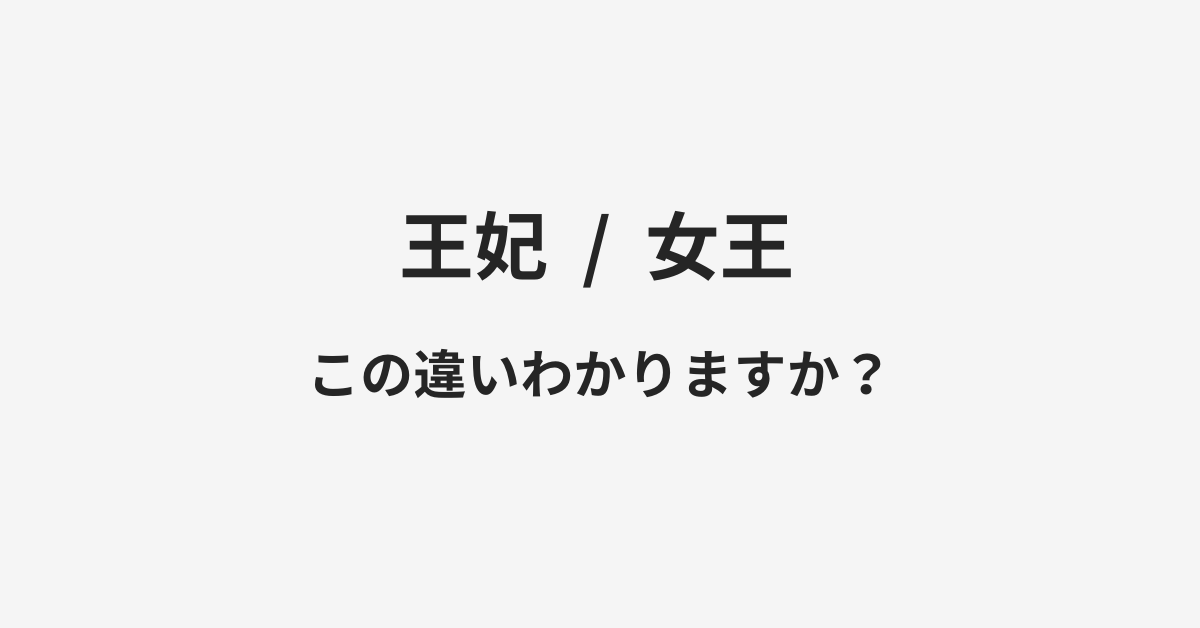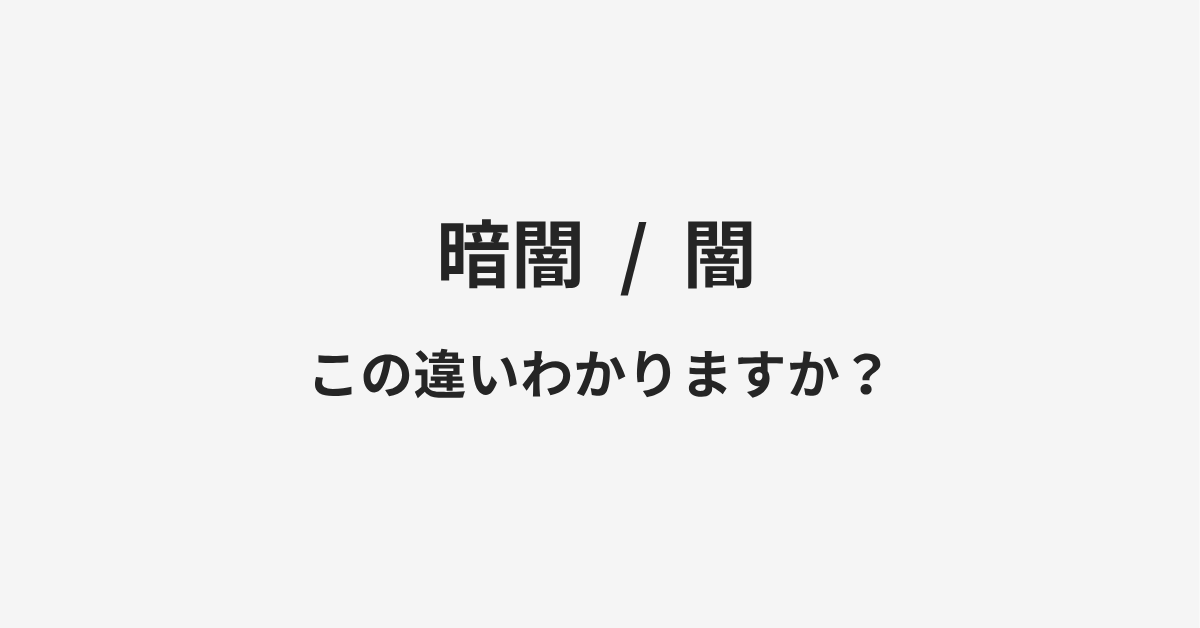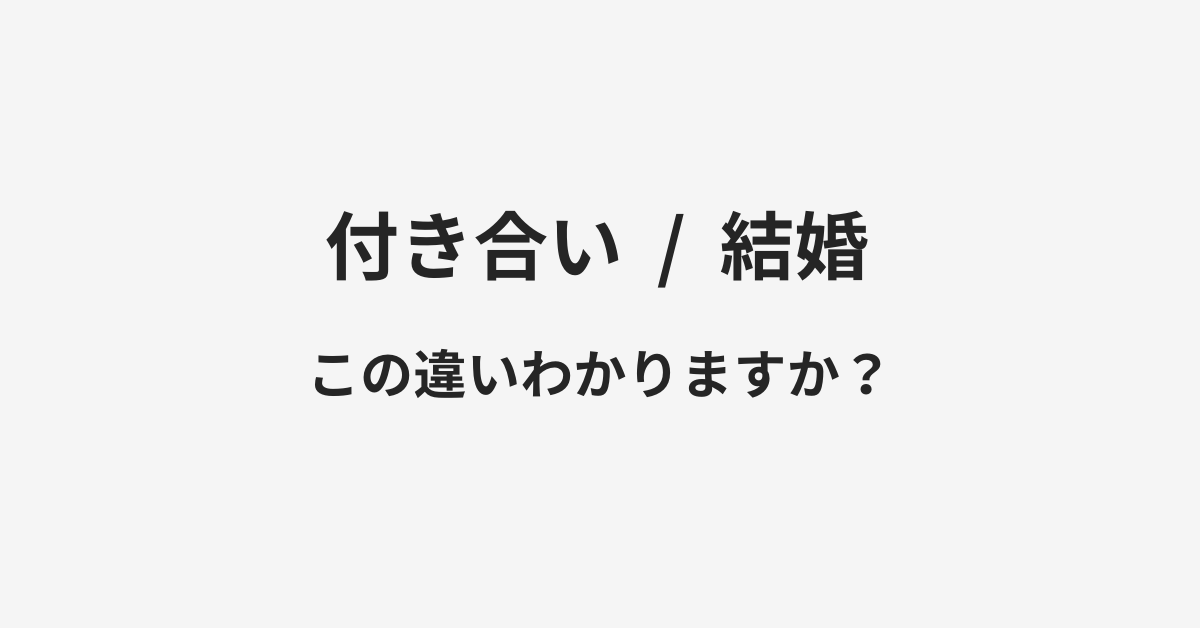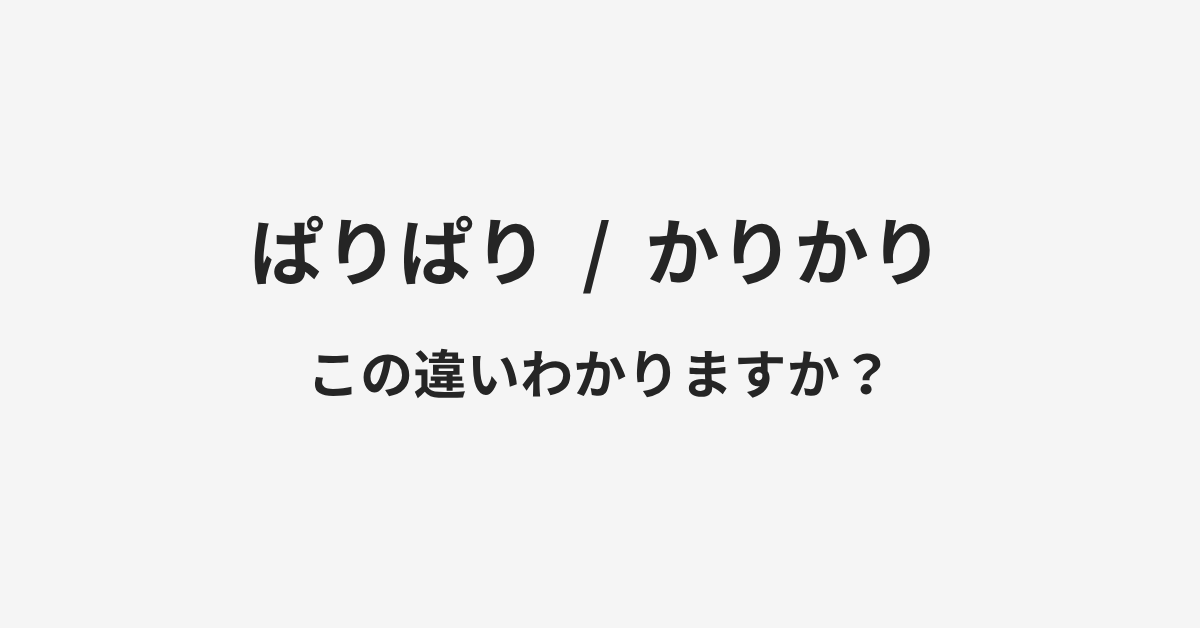【継承】と【集約】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
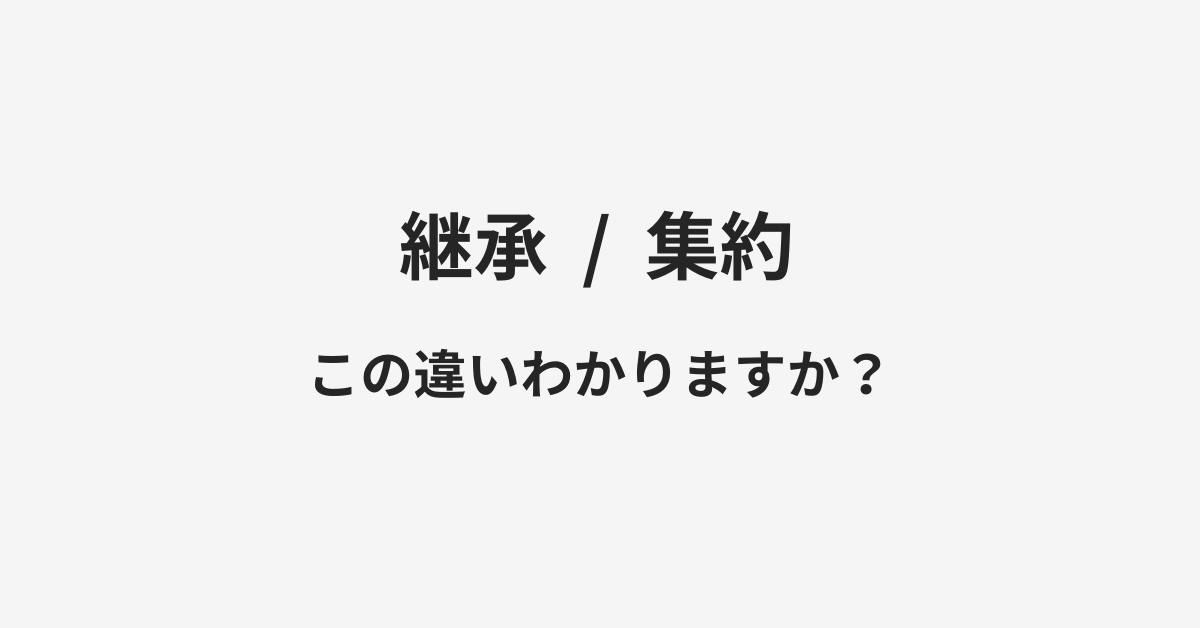
継承と集約の分かりやすい違い
継承は、伝統や技術、財産などを前の世代から受け継ぐことです。文化を継承する、家業を継承するのように、価値あるものを次世代に引き継ぐ時に使います。
集約は、散らばっているものを一つにまとめることです。情報を集約する、意見を集約するのように、バラバラなものを整理して一つにする時に使います。
継承は世代間で引き継ぐ、集約は一つにまとめるという違いがあります。
継承とは?
継承とは、先代や前任者から、財産、地位、伝統、技術、文化などを受け継ぐことを意味します。継は続ける、承は受けるという意味で、価値あるものを次の世代や後継者に引き渡し、絶やさずに続けていくことを表します。
家業の継承、伝統芸能の継承、企業の事業継承など、様々な分野で使われます。単に引き継ぐだけでなく、受け継いだものを守り、発展させていく責任も含まれます。日本では特に、技術や文化の継承が重視される傾向があります。
少子高齢化により、後継者不足で継承が困難になるケースも増えており、社会問題となっています。継承には、技術や知識だけでなく、精神や理念を伝えることも重要とされています。
継承の例文
- ( 1 ) 伝統工芸の技術を継承する若者が減っています。
- ( 2 ) 父から会社を継承することになりました。
- ( 3 ) 文化遺産を次世代に継承する責任があります。
- ( 4 ) 師匠から秘伝の技を継承しました。
- ( 5 ) 継承者を育成することが急務です。
- ( 6 ) 代々継承されてきた家訓を大切にしています。
継承の会話例
集約とは?
集約とは、分散している複数のものを一か所に集めて、整理・統合することを意味します。情報、意見、資源、機能など、様々なものを効率的にまとめる行為を指し、無駄を省いて管理しやすくすることが目的です。データを集約する、工場を集約する、意見を集約するなど、ビジネスや行政の場面でよく使われます。
集約により、コスト削減、効率向上、管理の簡素化などのメリットが得られます。現代のIT化により、情報の集約はより重要になっています。
集約には、単に集めるだけでなく、整理・分析して価値を高めるプロセスも含まれます。ビッグデータの活用、業務の効率化、組織の再編など、現代社会の様々な課題解決に集約の考え方が活用されています。
集約の例文
- ( 1 ) 各部署の報告を一つに集約してください。
- ( 2 ) 工場を3か所から1か所に集約します。
- ( 3 ) アンケート結果を集約して発表します。
- ( 4 ) 情報を集約することで、全体像が見えてきました。
- ( 5 ) 複数の機能を一つのアプリに集約しました。
- ( 6 ) 意見を集約して、最終案を作成します。
集約の会話例
継承と集約の違いまとめ
継承は世代や人から人へ価値あるものを受け継ぐことで、伝統、技術、財産などを次に引き渡すことです。時間的な流れと責任が伴います。
集約は散在するものを一つにまとめることで、効率化や整理を目的とします。情報やリソースを整理統合し、管理しやすくすることです。
簡単に言えば、継承は代々受け継ぐ、集約はバラバラをまとめるという違いで、継承は縦の流れ、集約は横の整理といえます。
継承と集約の読み方
- 継承(ひらがな):けいしょう
- 継承(ローマ字):keishou
- 集約(ひらがな):しゅうやく
- 集約(ローマ字):shuuyaku