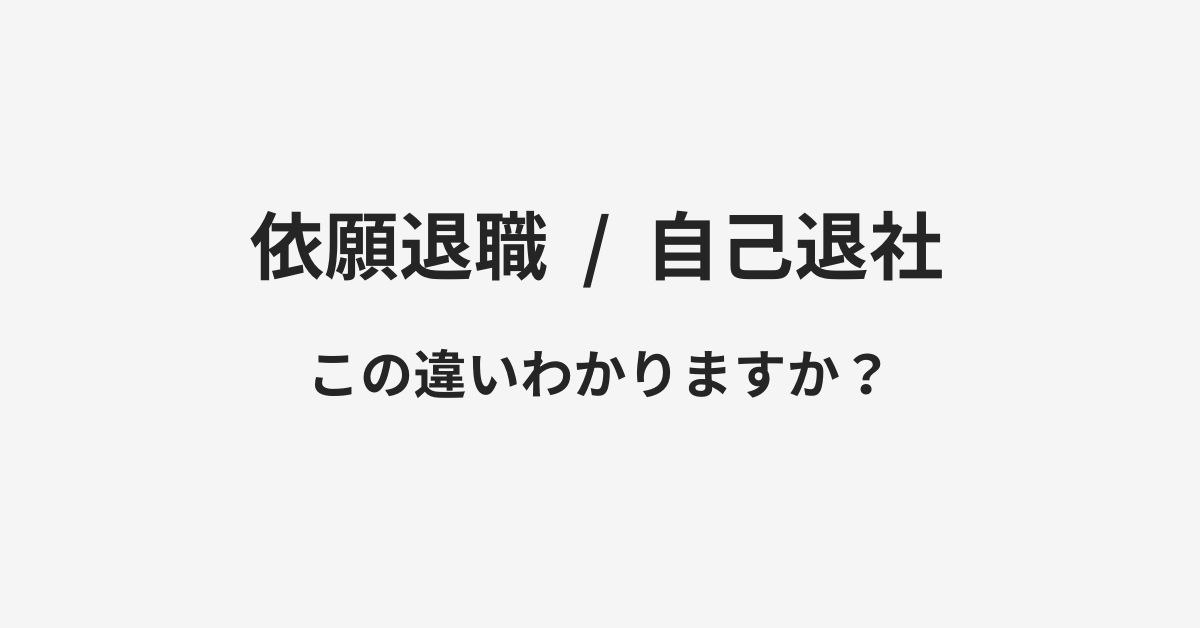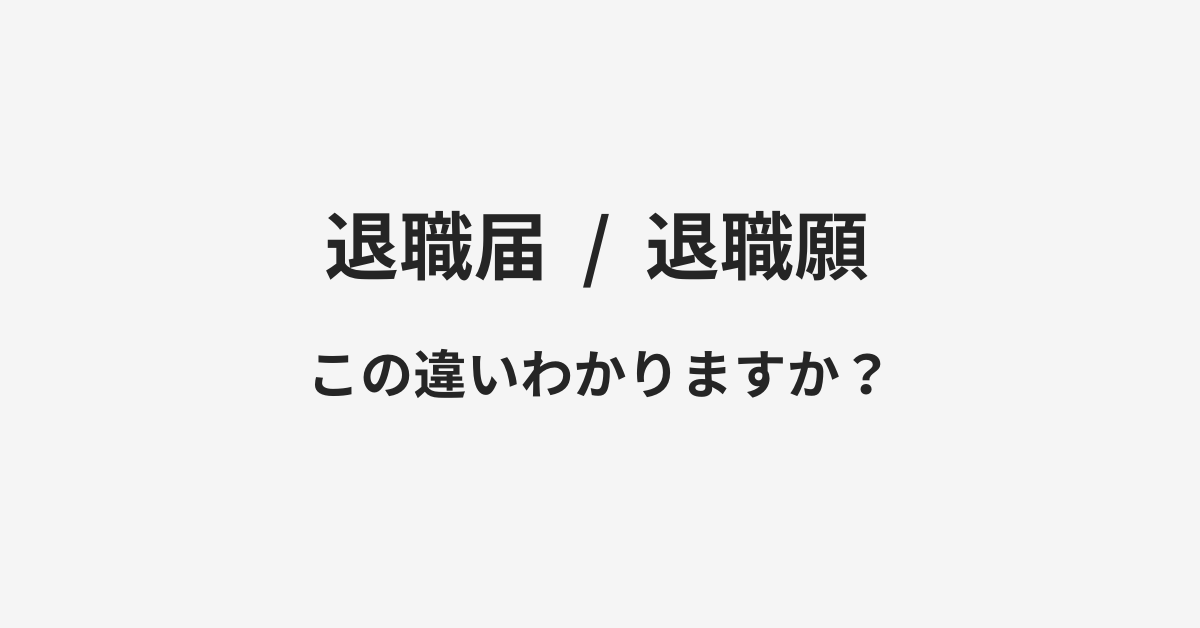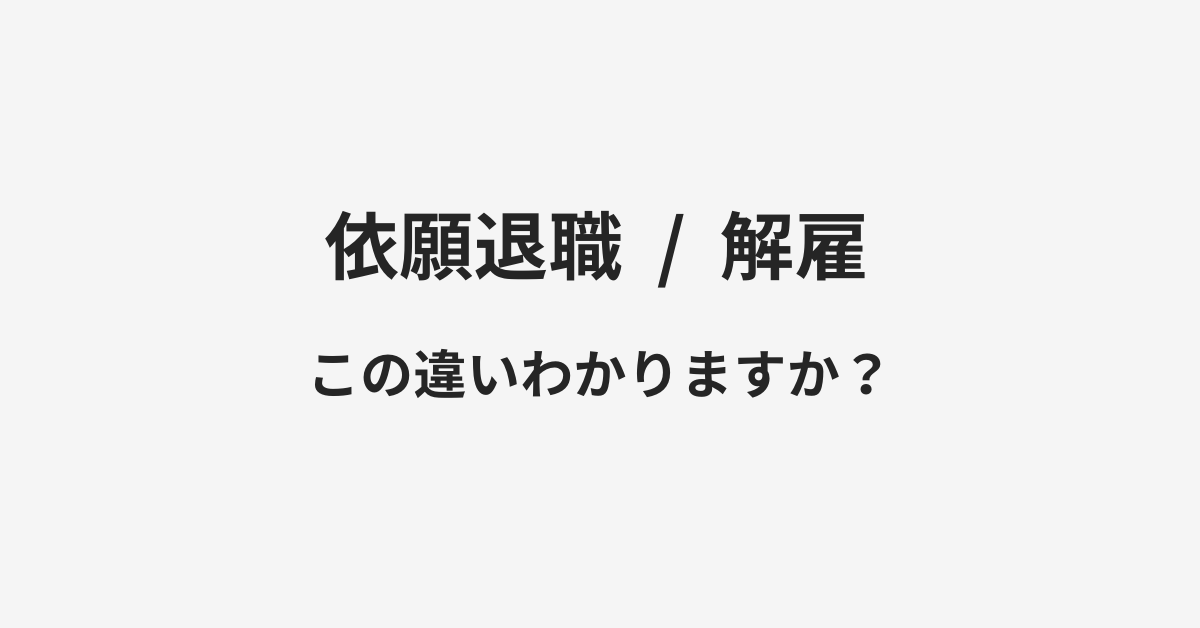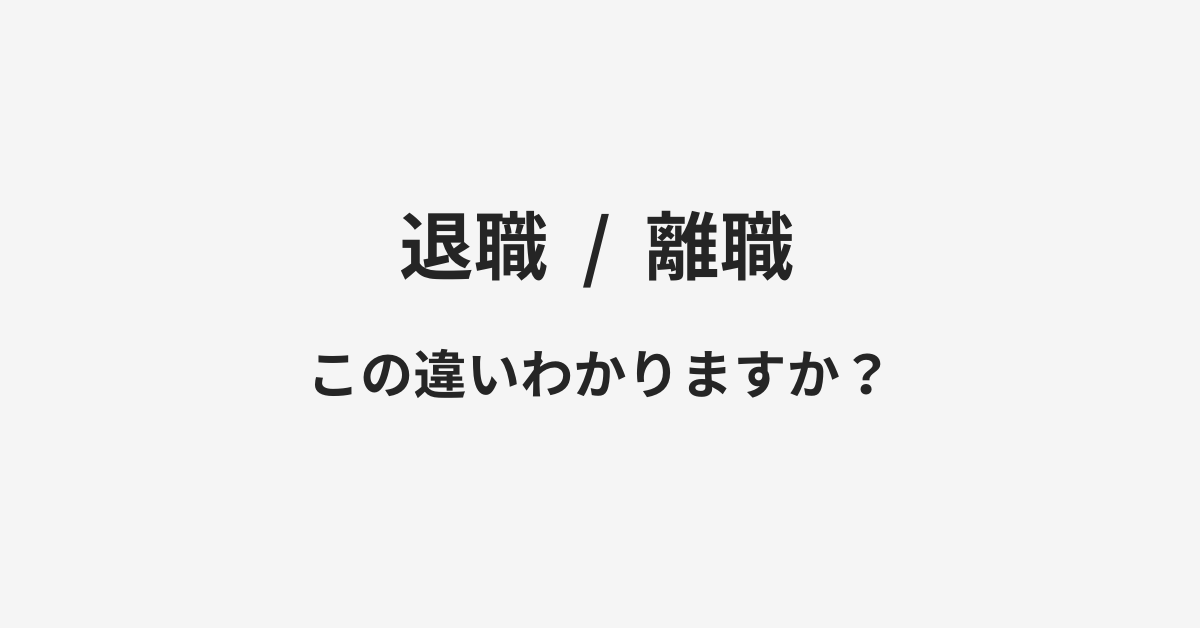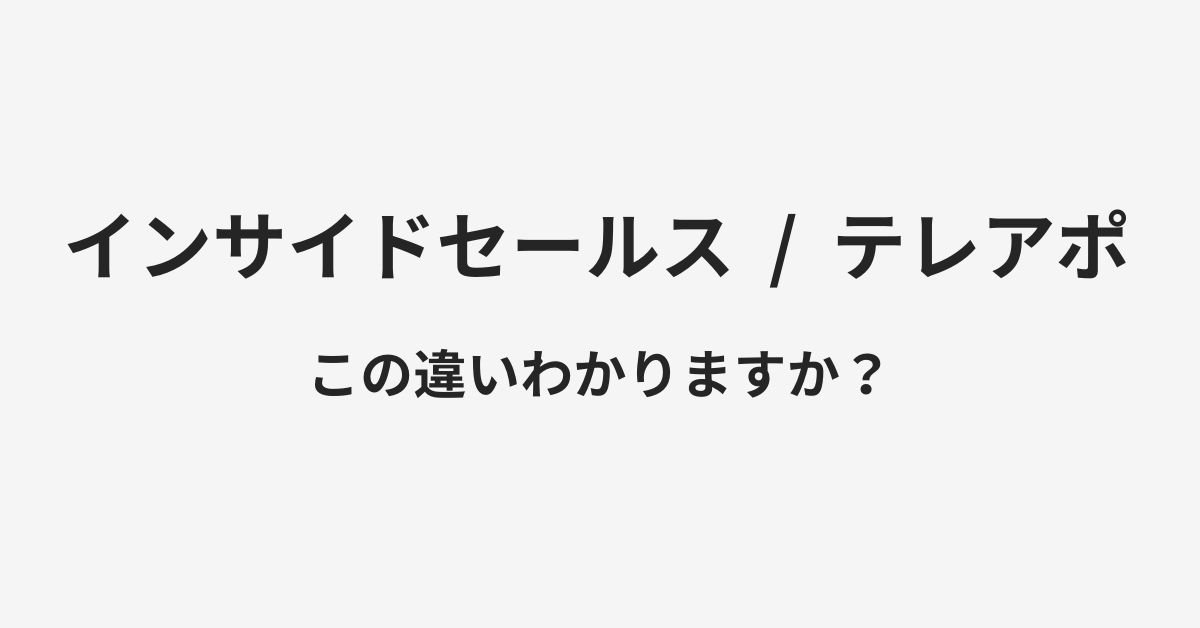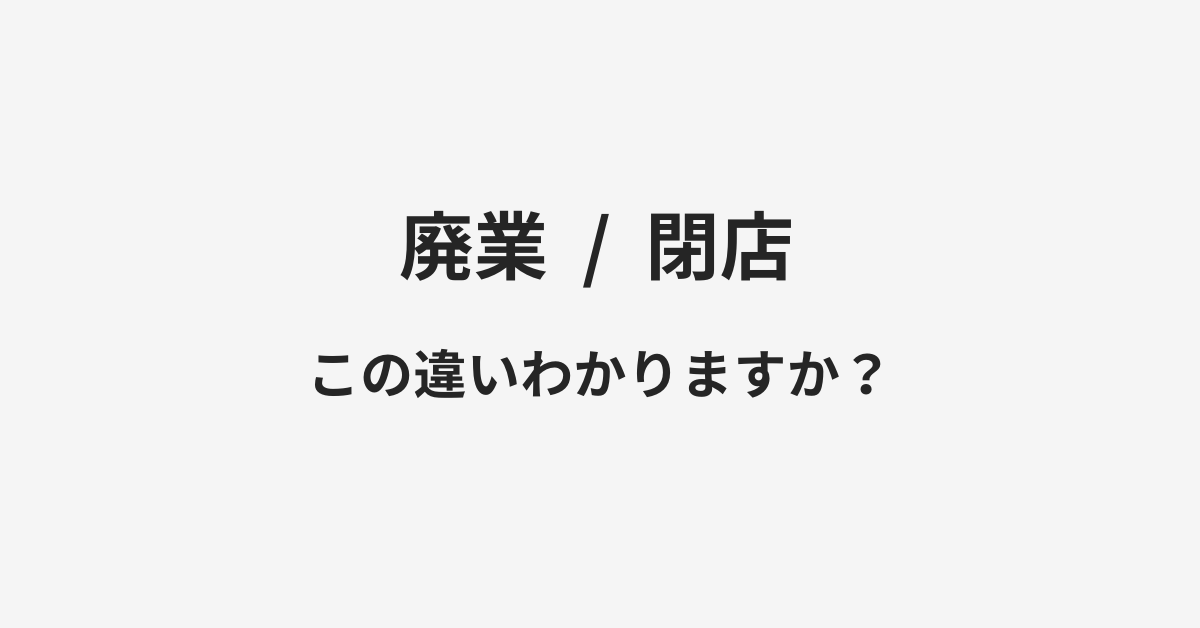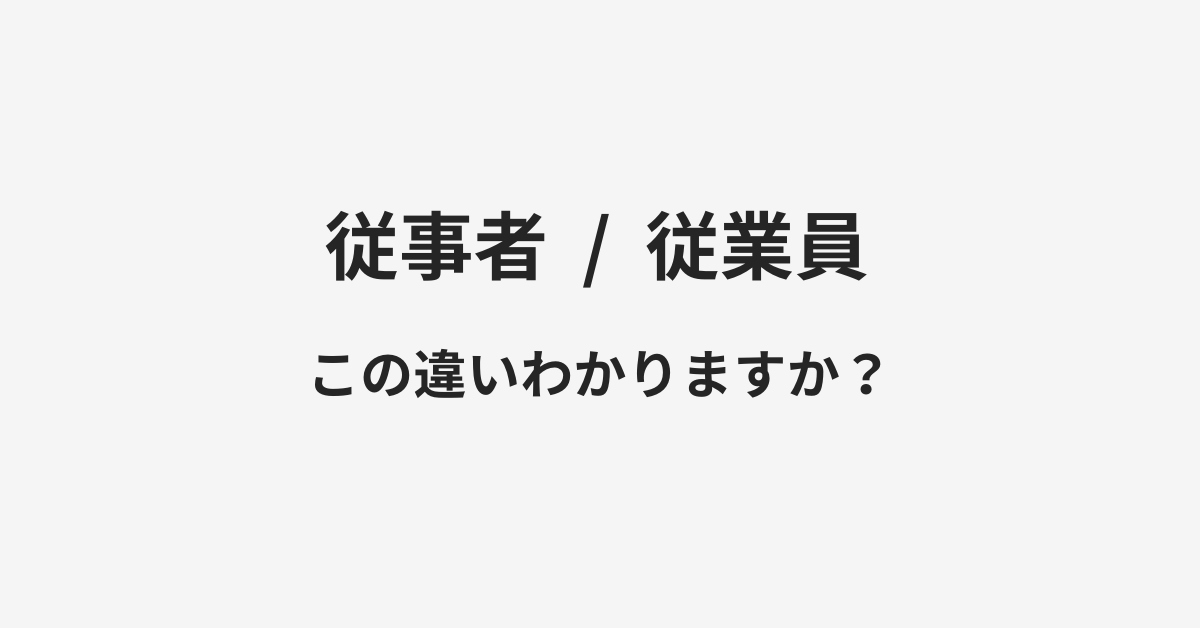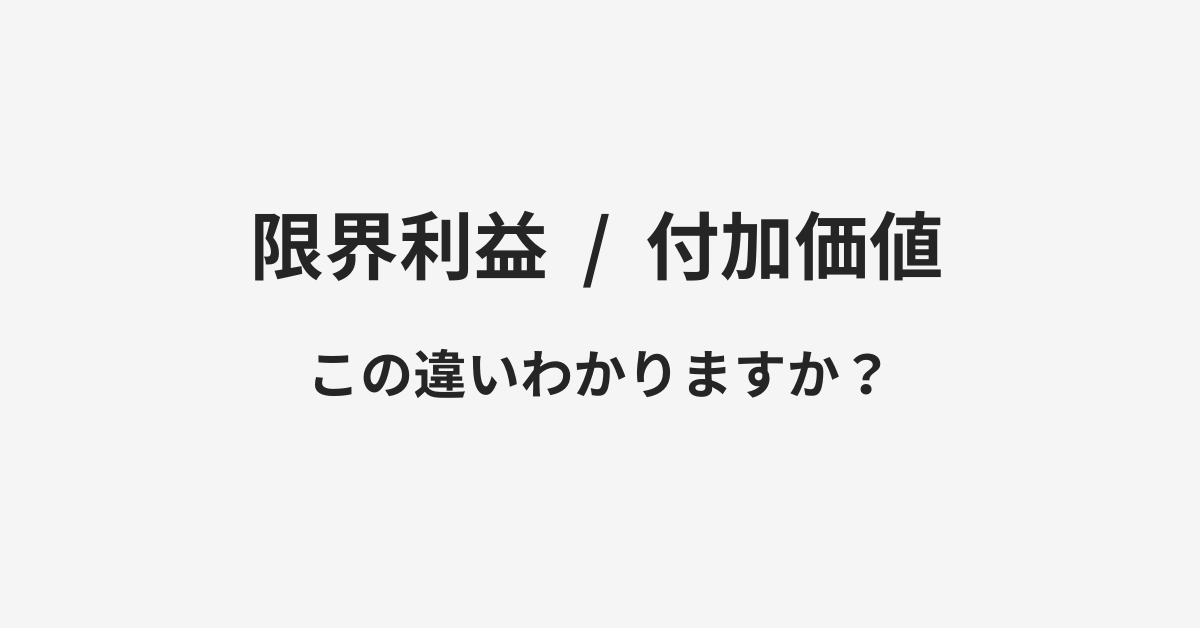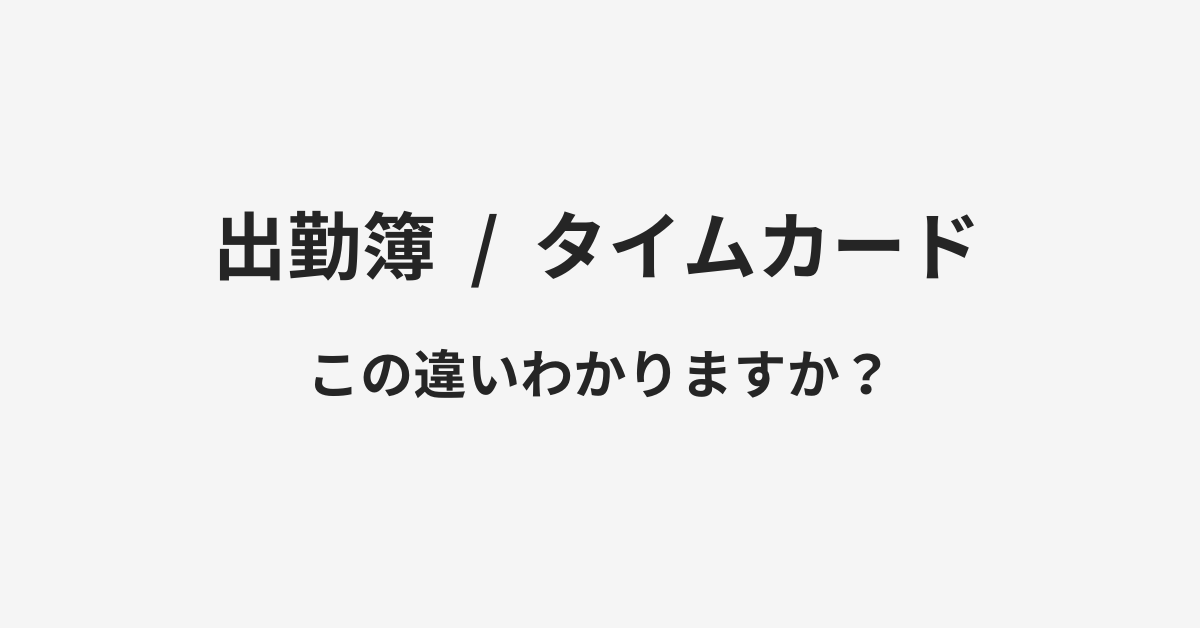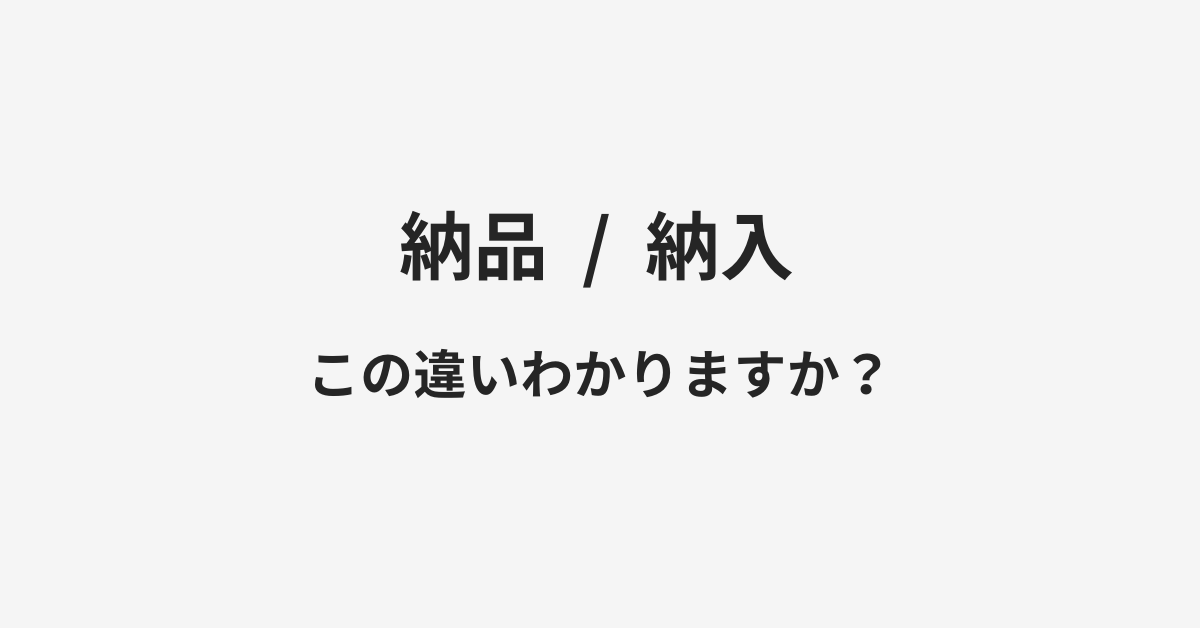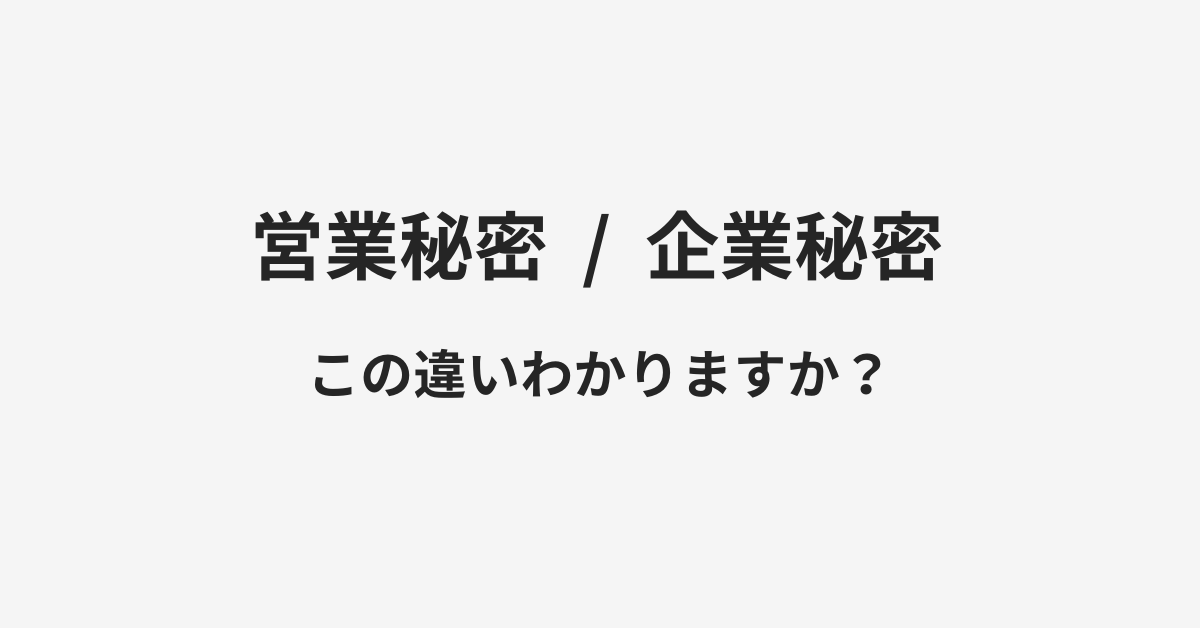【退職勧告】と【退職勧奨】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
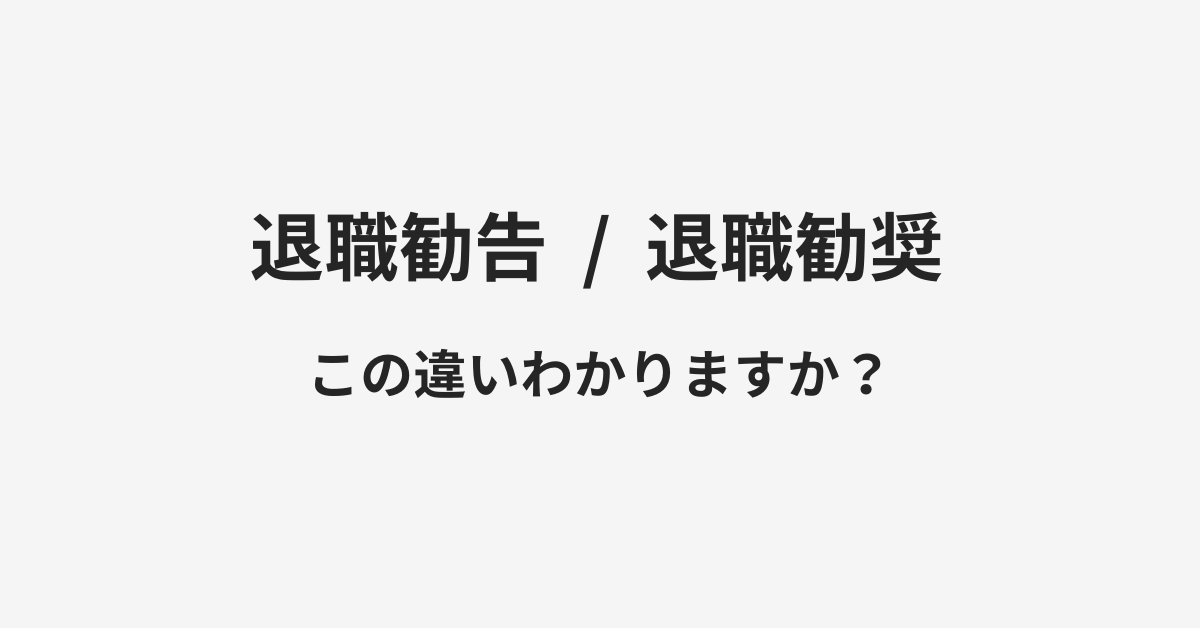
退職勧告と退職勧奨の分かりやすい違い
退職勧告と退職勧奨は、どちらも従業員に退職を促す行為ですが、その強制力と法的性質に大きな違いがあります。
退職勧告は一方的で強制的な印象を与える表現で、退職勧奨は双方の合意形成を目指す穏やかな働きかけです。実際の法的効力に違いはありませんが、受け取る印象が大きく異なります。
労務管理において、この違いを理解することは、適法な人員整理と従業員の権利保護の両立に重要です。
退職勧告とは?
退職勧告とは、使用者が従業員に対して退職を強く求める行為を指す表現ですが、法的には退職勧奨と同じ意味です。勧告という言葉が持つ強制的なニュアンスから、あたかも従わなければならないような印象を与えますが、実際には従業員には応じる義務はありません。解雇とは異なり、あくまでも退職のお願いに過ぎません。
退職勧告という表現は、実務上は避けるべきとされています。強圧的な印象を与え、パワーハラスメントや違法な退職強要と受け取られるリスクがあります。また、勧告に従わない場合は解雇するなどの脅しを伴う場合は、違法行為となる可能性が高いです。
もし退職勧告を受けた場合は、即答を避け、冷静に対応することが重要です。退職の意思がない場合は明確に拒否でき、不当な圧力を受けた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することができます。
退職勧告の例文
- ( 1 ) 上司から突然退職勧告を受けて、困惑しています。
- ( 2 ) 退職勧告に従わなければ解雇すると言われました。
- ( 3 ) 書面で退職勧告書を渡され、署名を求められています。
- ( 4 ) 退職勧告を拒否したら、異動を命じられました。
- ( 5 ) 執拗な退職勧告により、精神的に追い詰められています。
- ( 6 ) 退職勧告の違法性について、労働基準監督署に相談しました。
退職勧告の会話例
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、使用者が従業員に対して自主的な退職を促す行為で、解雇ではなく合意退職を目指すものです。業績不振、組織再編、能力不足、勤務態度などを理由に行われますが、従業員には応じる義務はなく、拒否することができます。適法に行われる限り、それ自体は違法ではありません。
適切な退職勧奨の要件には、任意性の確保、適切な説明、十分な検討期間の付与、過度な圧力の禁止などがあります。退職条件として、割増退職金、再就職支援、有給休暇の買い上げなどを提示することもあります。ただし、執拗な勧奨、人格否定、隔離などは違法な退職強要となります。
企業にとっては、解雇に比べて紛争リスクが低く、円満な解決が期待できます。従業員にとっても、自己都合退職より有利な条件で退職できる可能性があります。ただし、安易な退職勧奨は組織のモラール低下を招くため、慎重な判断が必要です。
退職勧奨の例文
- ( 1 ) 業績不振により、一部の社員に退職勧奨を実施することになりました。
- ( 2 ) 退職勧奨の面談では、今後のキャリアについても相談に乗ります。
- ( 3 ) 退職勧奨に応じていただければ、割増退職金を支給します。
- ( 4 ) 複数回の退職勧奨を行いましたが、合意には至りませんでした。
- ( 5 ) 退職勧奨のガイドラインを作成し、適切な運用を心がけています。
- ( 6 ) 退職勧奨後、円満に退職合意書を締結できました。
退職勧奨の会話例
退職勧告と退職勧奨の違いまとめ
退職勧告と退職勧奨の本質的な違いは、言葉の印象と使用の適切性です。法的には同じ意味ですが、退職勧告は強制的で不適切、退職勧奨は標準的で適切な表現とされています。
実務上は、退職勧奨という用語を使用し、従業員の任意性を尊重した対応が求められます。退職勧告という表現は、トラブルの元となるため避けるべきです。
どちらの場合も、従業員には拒否する権利があり、不当な圧力は違法となります。企業は適法な範囲で、従業員は自身の権利を理解した上で、対応することが重要です。
退職勧告と退職勧奨の読み方
- 退職勧告(ひらがな):たいしょくかんこく
- 退職勧告(ローマ字):taishokukannkoku
- 退職勧奨(ひらがな):たいしょくかんしょう
- 退職勧奨(ローマ字):taishokukannshou