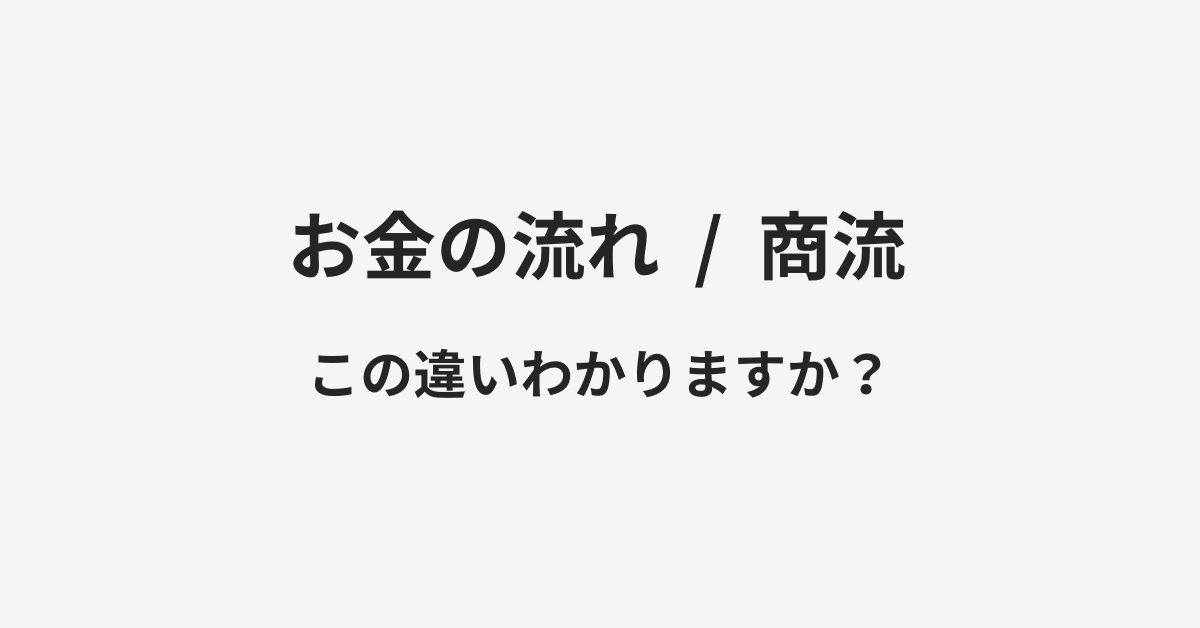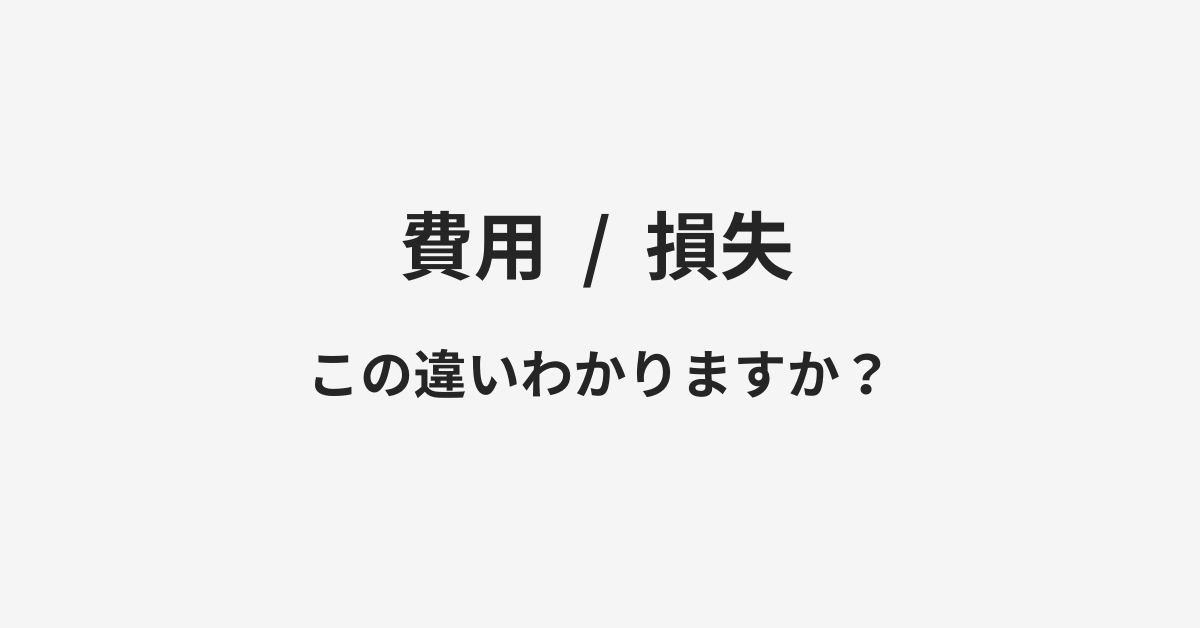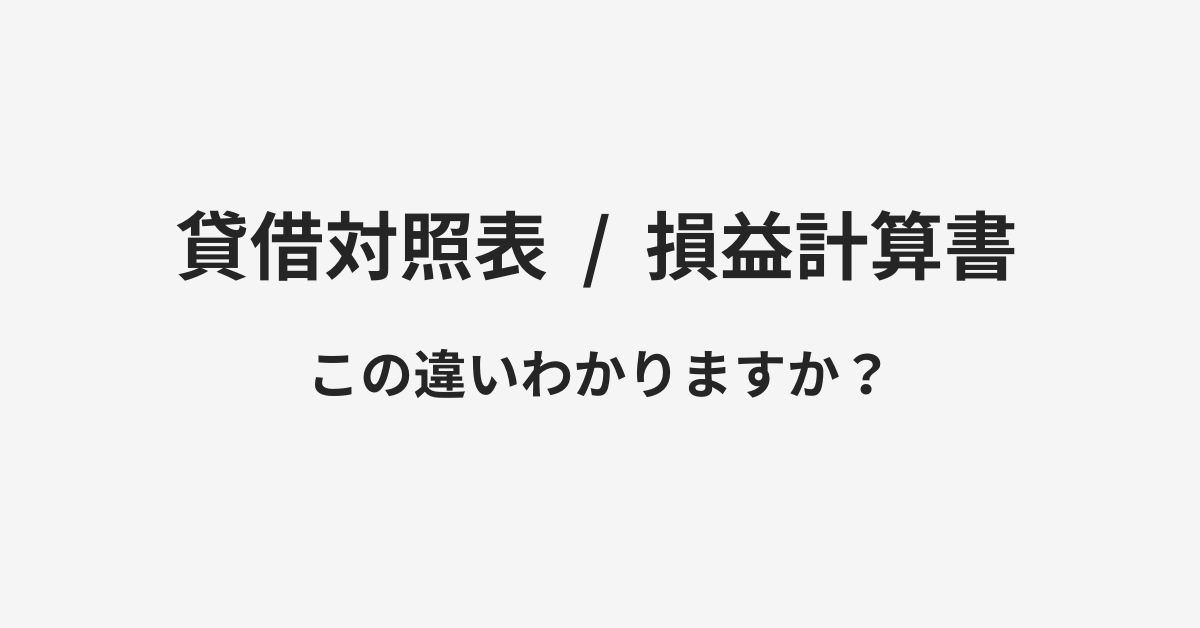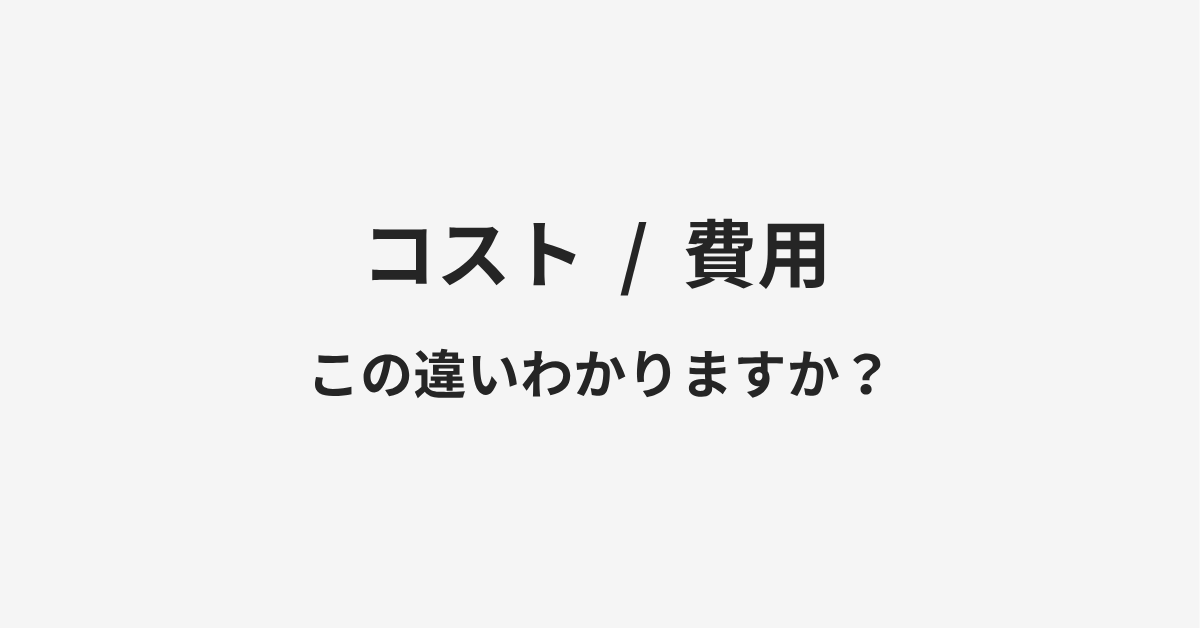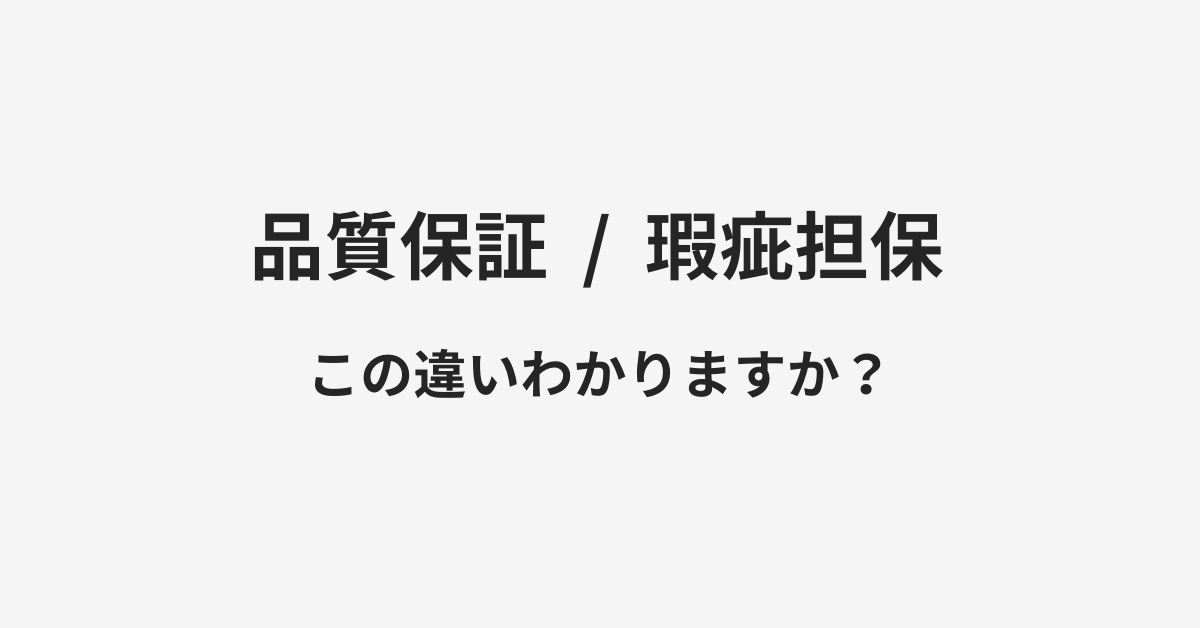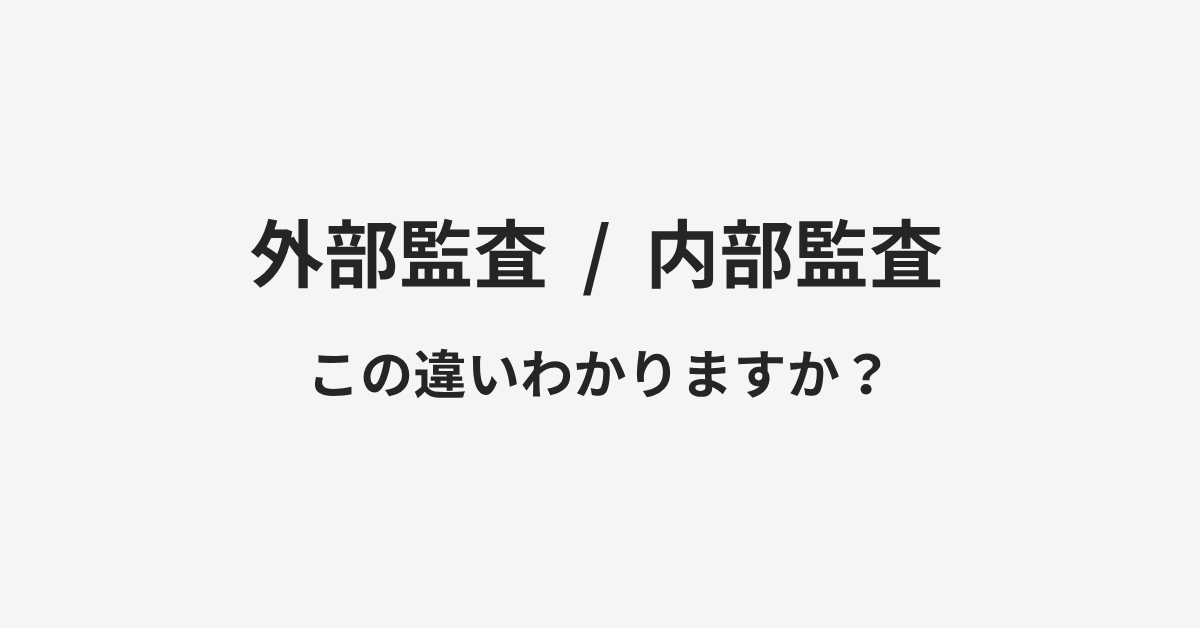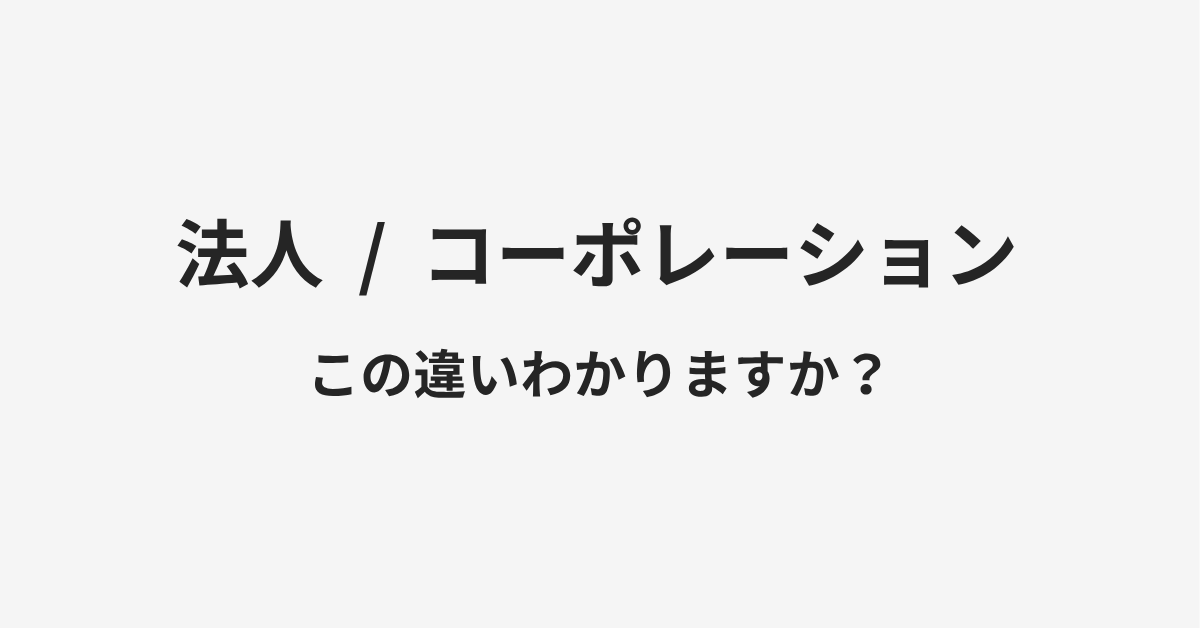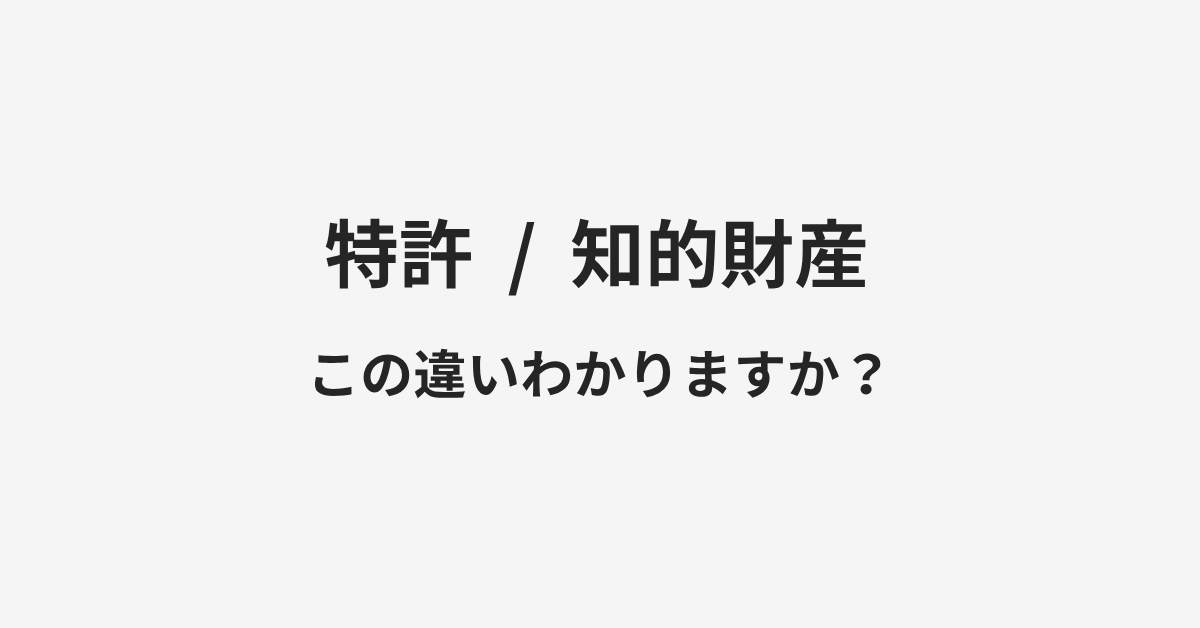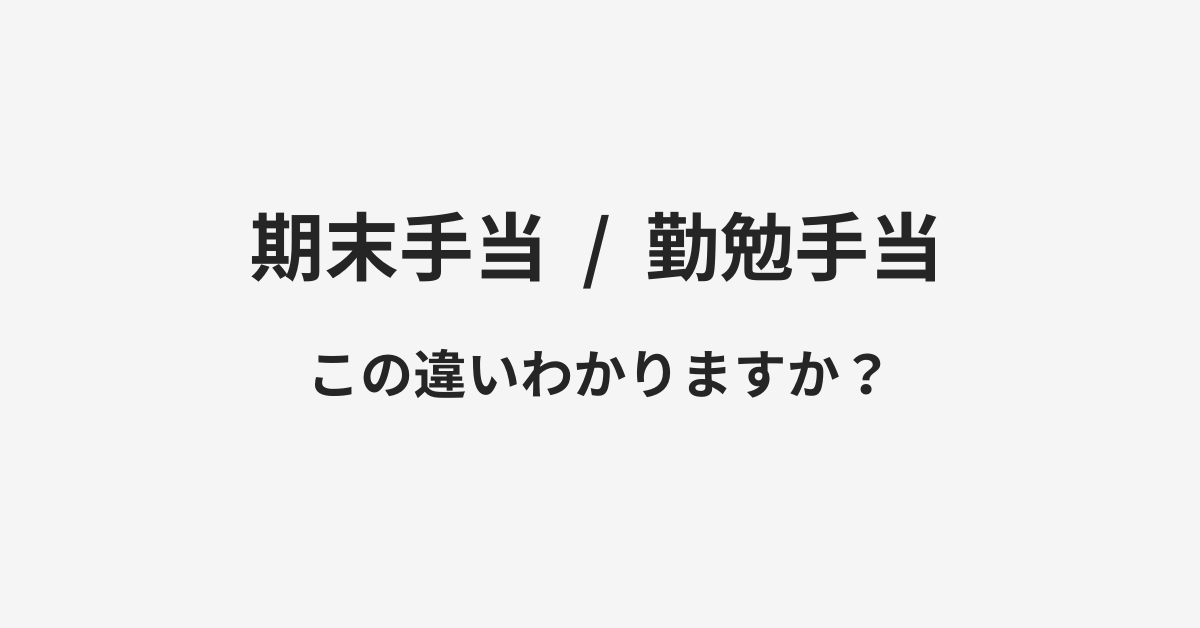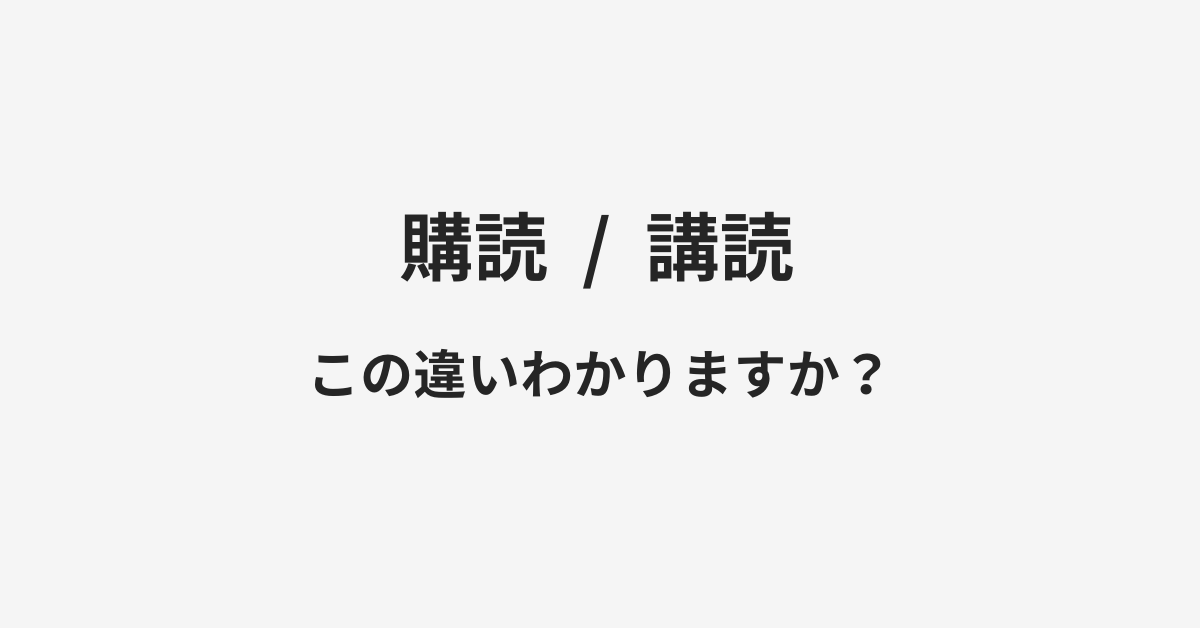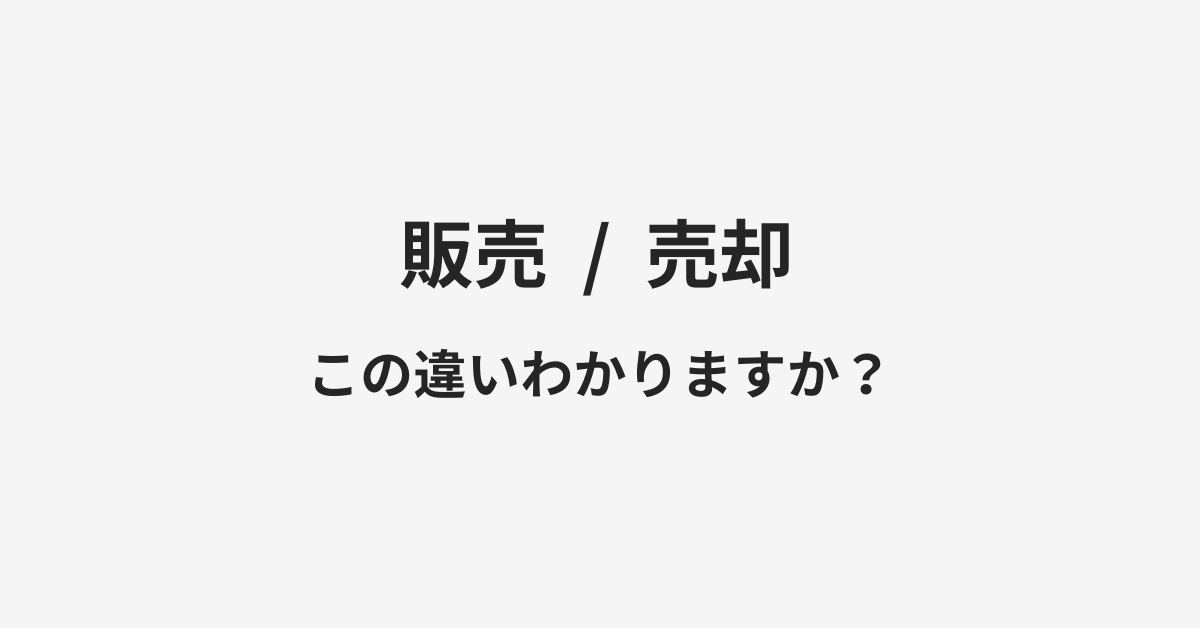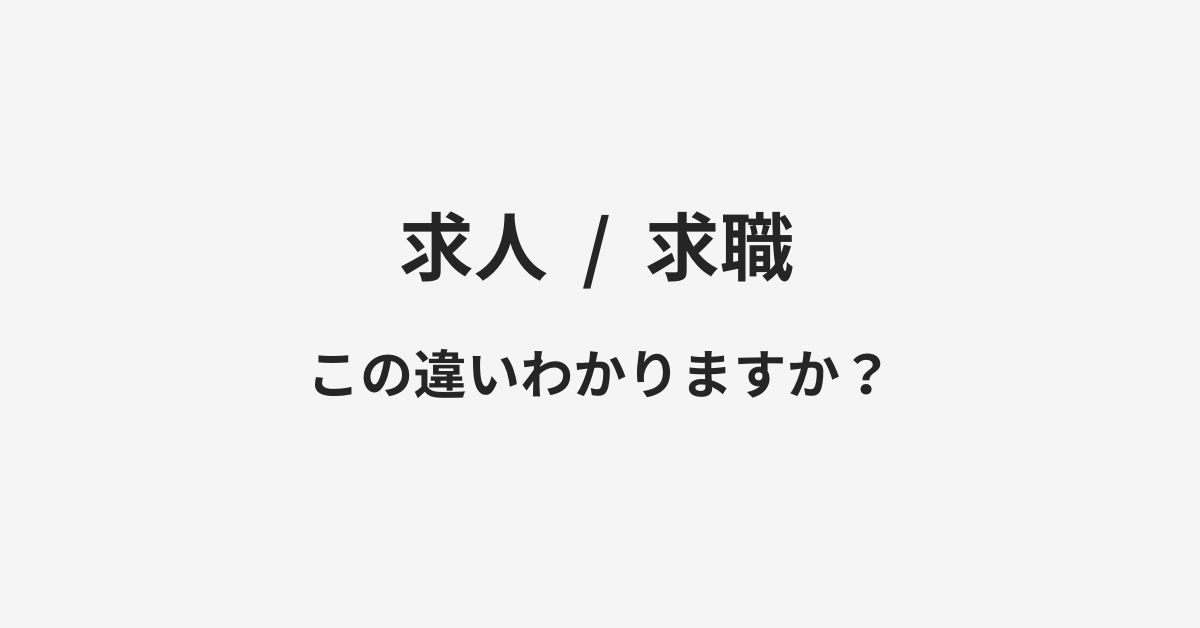【収支】と【損益】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
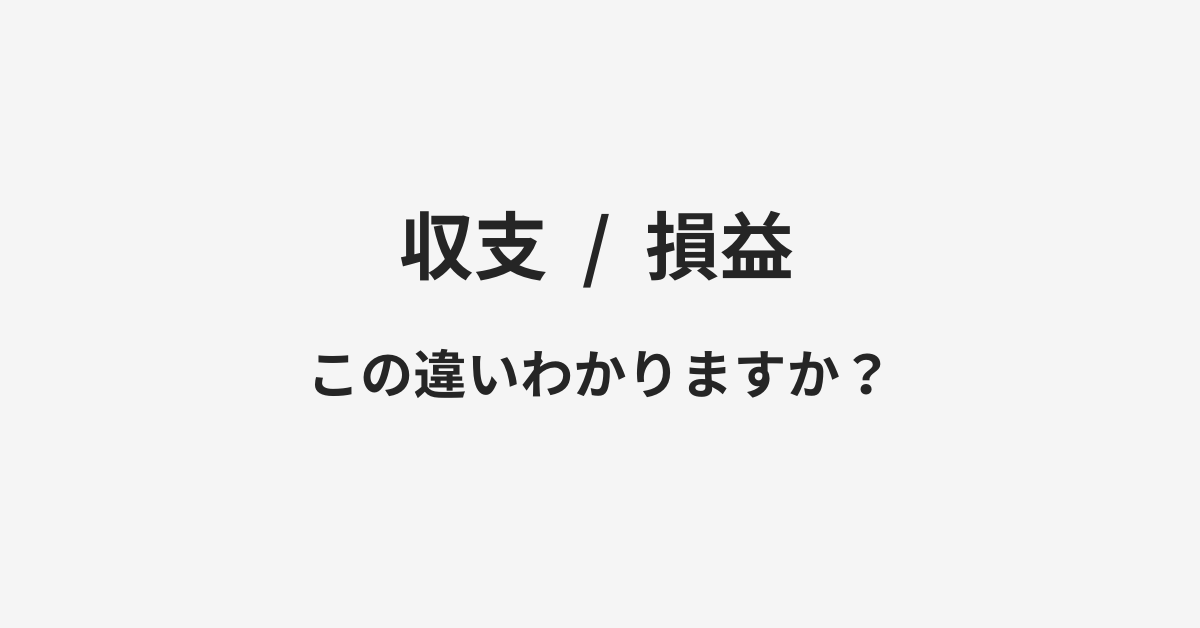
収支と損益の分かりやすい違い
収支と損益は、どちらも企業の財務状況を表す重要な概念ですが、その意味と用途には大きな違いがあります。
収支は実際の現金の流れを追跡し、資金繰りの管理に使用されます。一方、損益は会計期間における企業の経営成績を示し、収益性の評価に用いられます。
ビジネスにおいては、この二つの概念を正しく理解し、使い分けることが健全な経営判断を行う上で不可欠です。
収支とは?
収支とは、一定期間における現金や預金などの実際の入金(収入)と出金(支出)の状況を表す概念です。キャッシュフロー計算書に反映され、企業の資金繰りや流動性を把握する上で重要な指標となります。
収支管理では、売上の回収時期や仕入代金の支払時期など、実際の現金の動きに着目します。黒字倒産を防ぐためにも、収支の把握は経営において極めて重要で、特に中小企業では日々の収支管理が生命線となることもあります。
ビジネスにおいては、収支予測を立てることで資金不足を事前に察知し、銀行借入や支払条件の交渉など、適切な資金調達計画を立てることができます。収支計画は経営の安定性を保つ基盤となります。
収支の例文
- ( 1 ) 今月の収支は、大口の入金により黒字となりました。
- ( 2 ) 設備投資により、第3四半期の収支が一時的に悪化する見込みです。
- ( 3 ) 日次の収支管理を徹底し、資金ショートを未然に防いでいます。
- ( 4 ) 収支予測表を作成し、今後6ヶ月間の資金繰りを確認しました。
- ( 5 ) プロジェクト単位で収支を管理し、採算性を検証しています。
- ( 6 ) 収支改善のため、売掛金の早期回収に取り組んでいます。
収支の会話例
損益とは?
損益とは、一定期間における収益と費用の差額を表し、企業の経営成績を示す概念です。損益計算書(P/L)に表示され、売上高から各種費用を差し引いて、最終的な利益または損失を算出します。
損益は発生主義会計に基づいて計算されるため、実際の現金の動きとは必ずしも一致しません。例えば、商品を掛け売りした場合、現金は受け取っていなくても売上として計上されます。このため、利益が出ていても資金繰りが厳しいという状況が生じることがあります。
企業経営においては、損益分析により収益性や効率性を評価し、経営改善の方向性を見出すことができます。部門別や製品別の損益管理により、より精緻な経営判断が可能となります。
損益の例文
- ( 1 ) 第2四半期の損益は、売上増加により前年同期比20%改善しました。
- ( 2 ) 新規事業の初期投資により、今期の損益は赤字となる見通しです。
- ( 3 ) 部門別損益管理を導入し、不採算部門の特定に成功しました。
- ( 4 ) 原価削減努力により、営業損益が3期連続で改善しています。
- ( 5 ) 損益分岐点分析を行い、必要売上高を明確にしました。
- ( 6 ) 四半期ごとの損益レビューで、経営課題の早期発見に努めています。
損益の会話例
収支と損益の違いまとめ
収支と損益の最大の違いは、現金の実際の動きを見るか、会計上の成績を見るかという点にあります。収支は資金繰りの健全性を、損益は事業の収益性を示します。
健全な企業経営のためには、両方の視点が必要です。利益が出ていても資金繰りが悪化すれば倒産リスクがあり、逆に一時的に収支が良くても損益が悪化していれば持続可能性に問題があります。
経営者や財務担当者は、収支と損益の両面から企業の状態を把握し、バランスの取れた経営判断を行うことが求められます。
収支と損益の読み方
- 収支(ひらがな):しゅうし
- 収支(ローマ字):shuushi
- 損益(ひらがな):そんえき
- 損益(ローマ字):sonneki