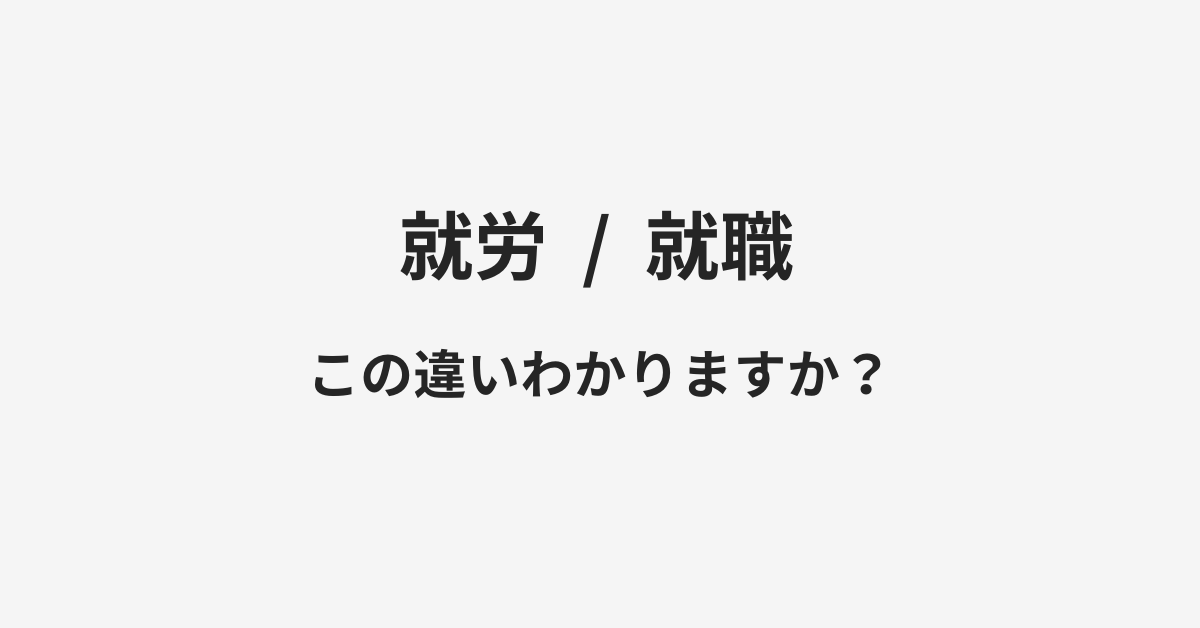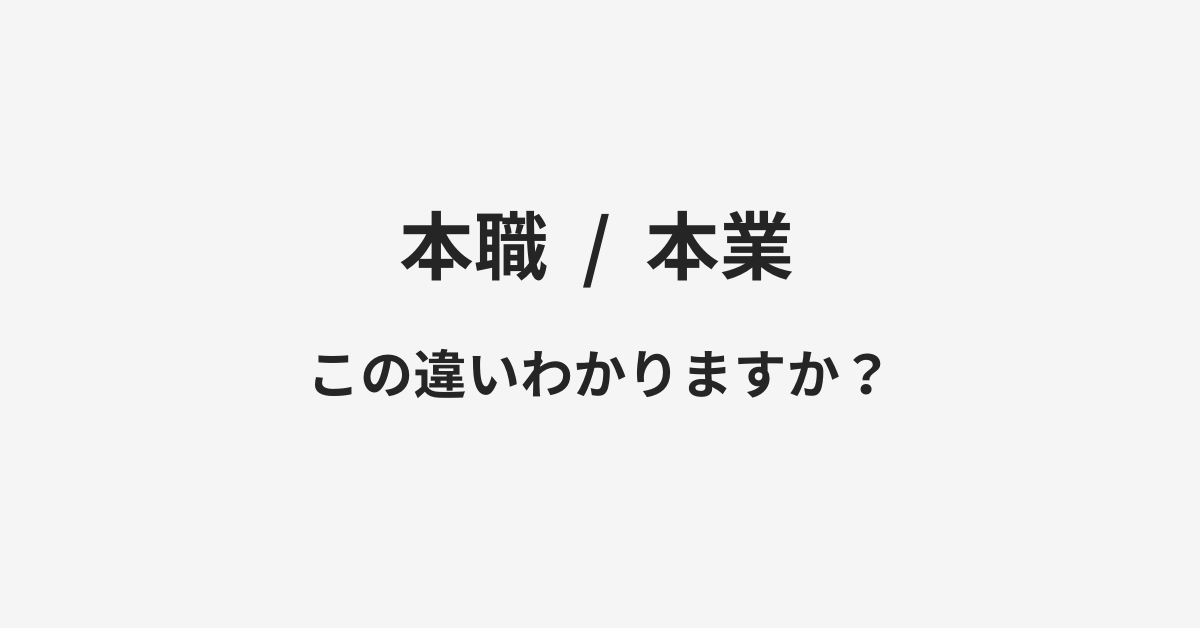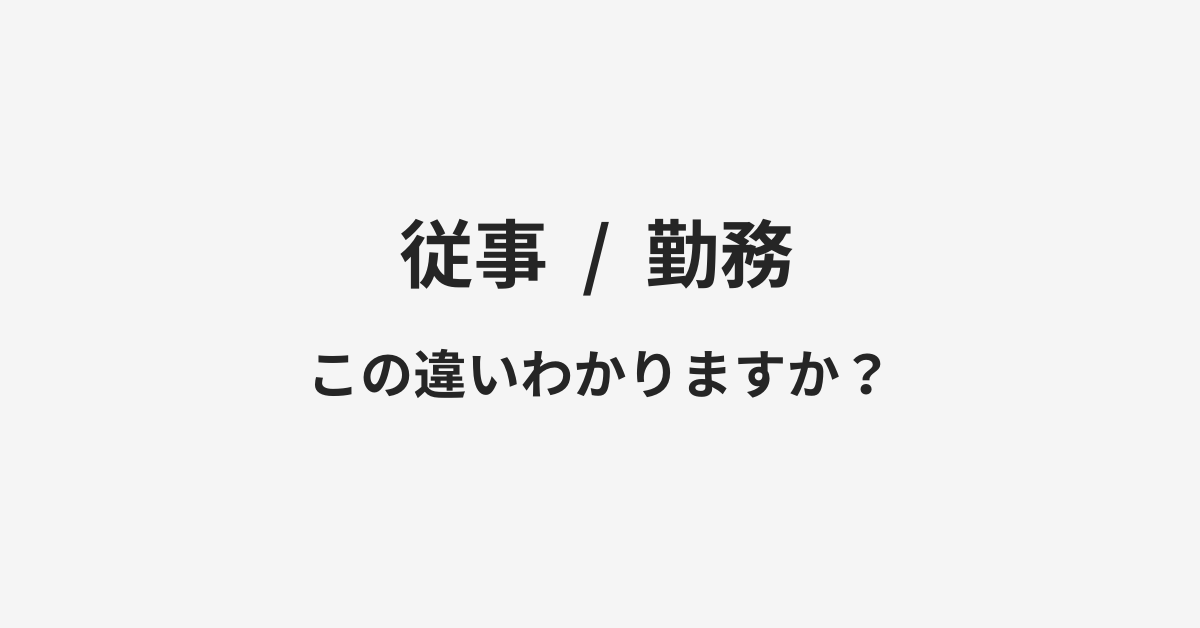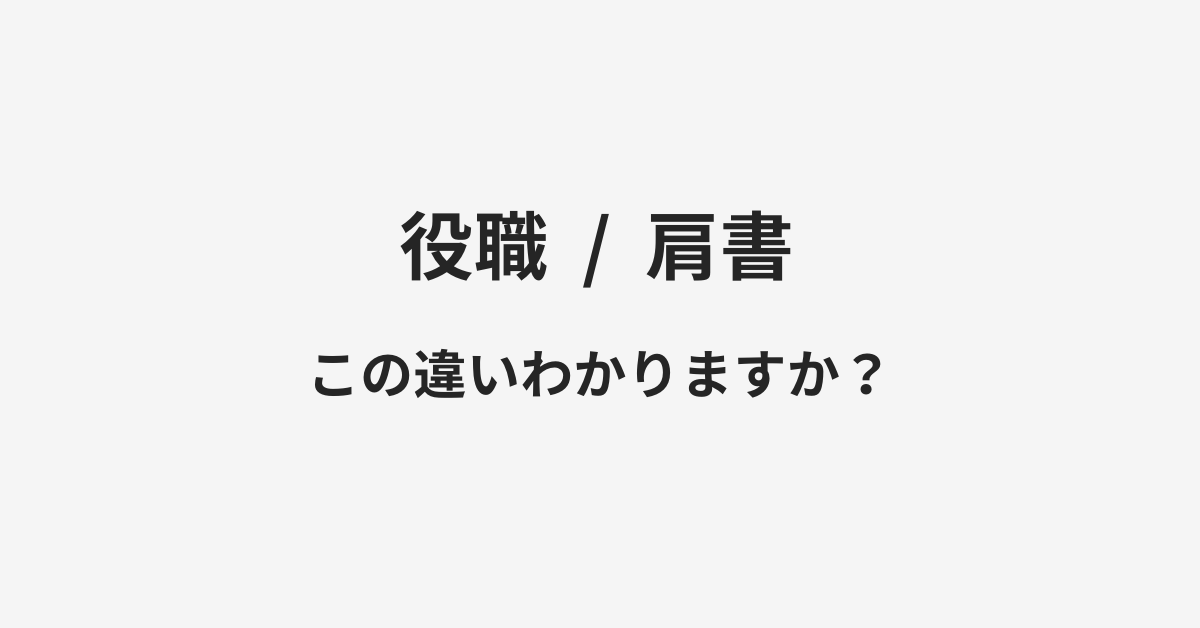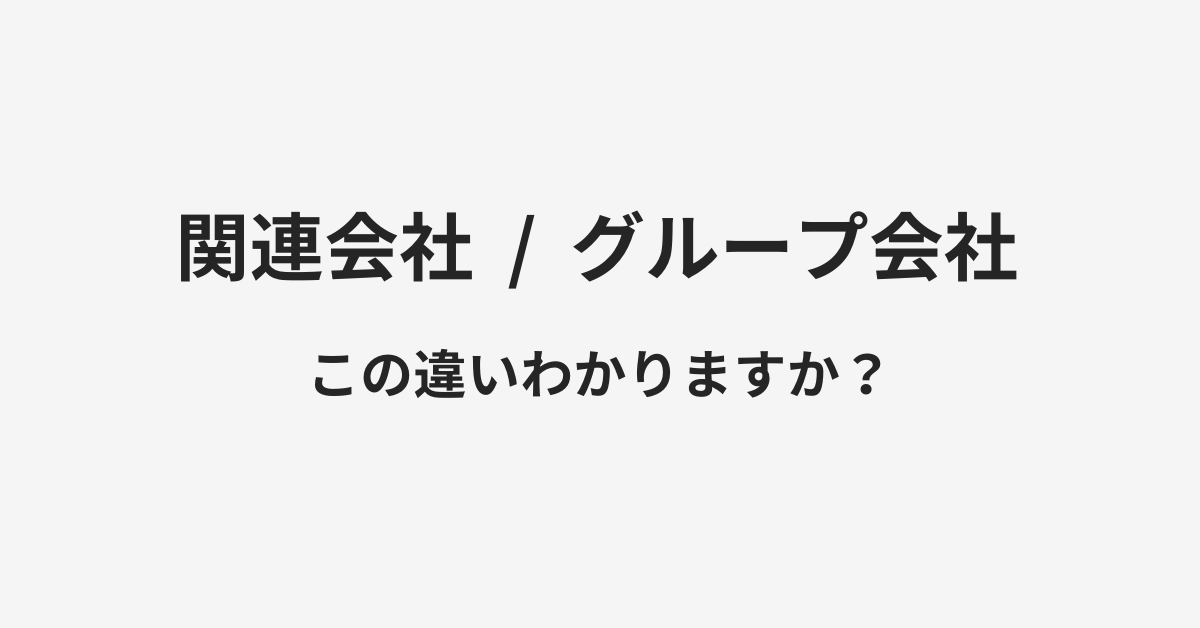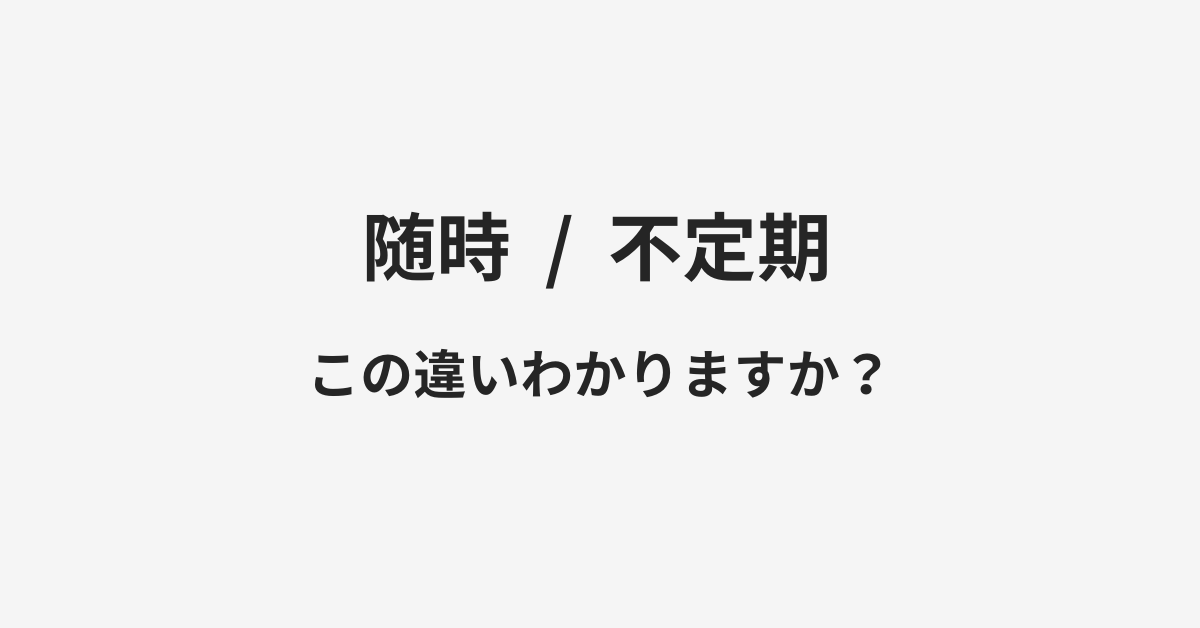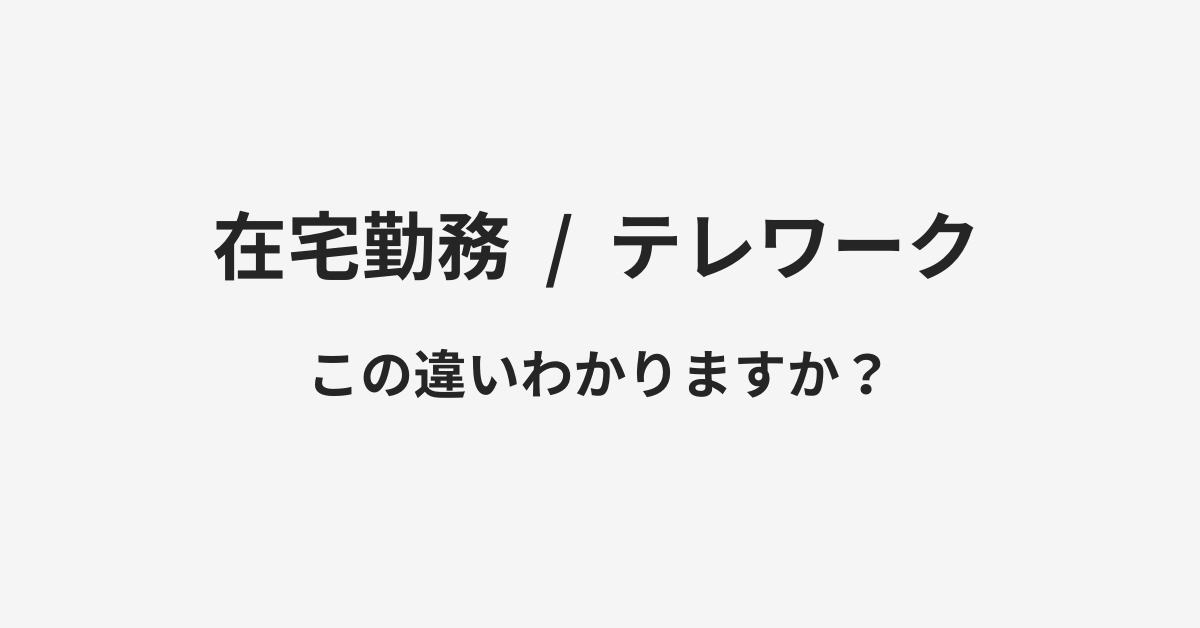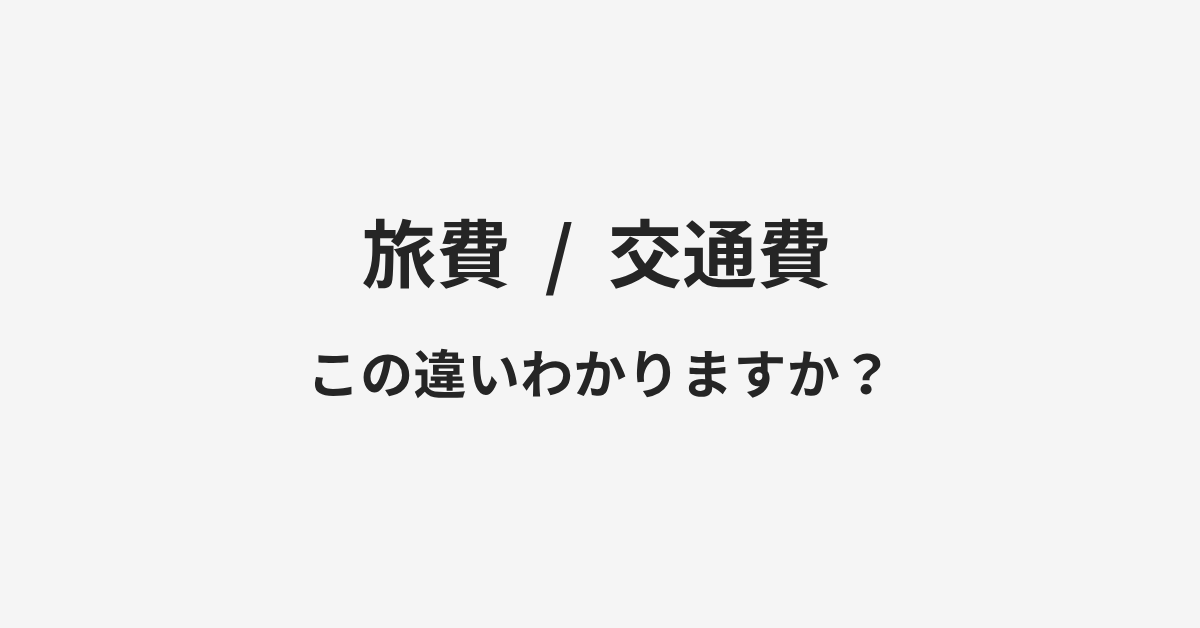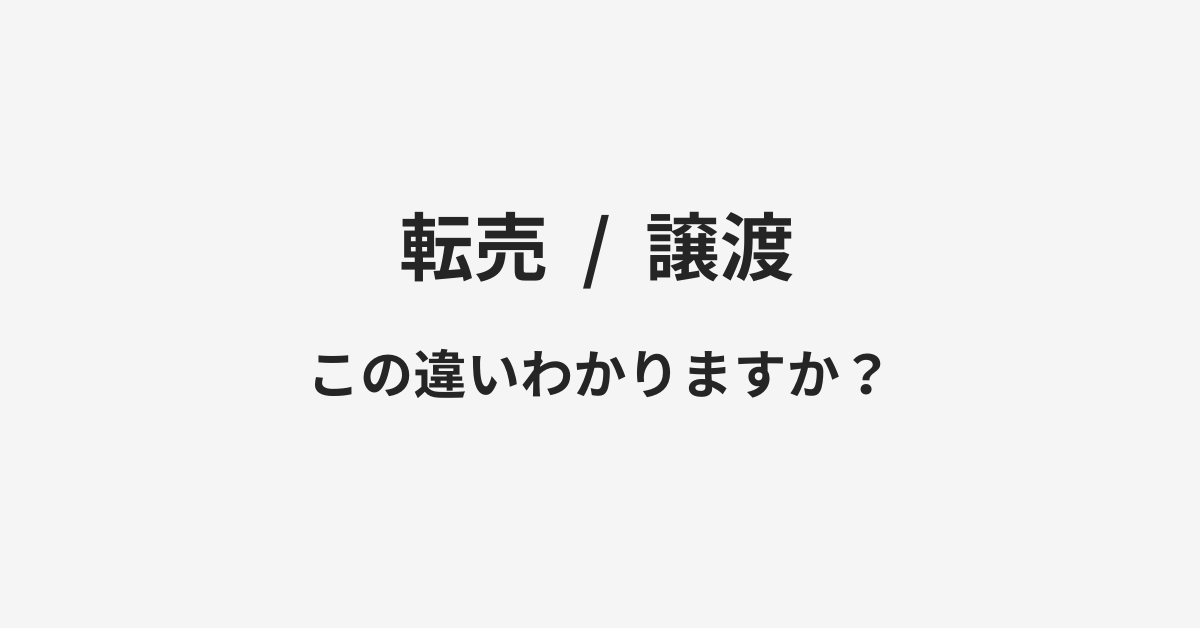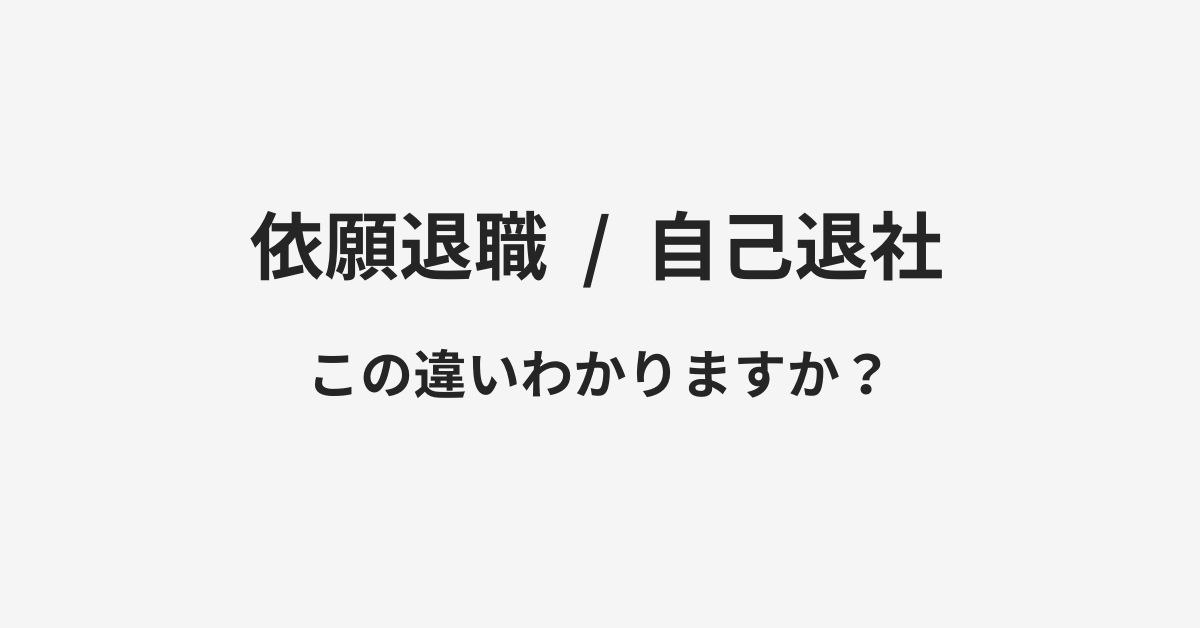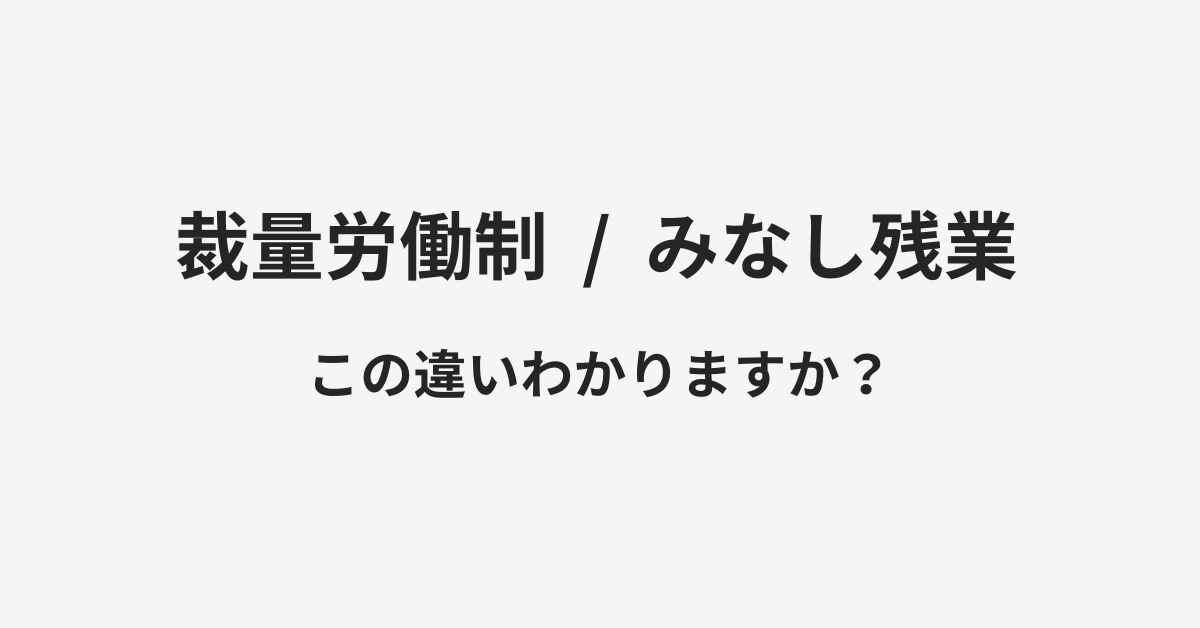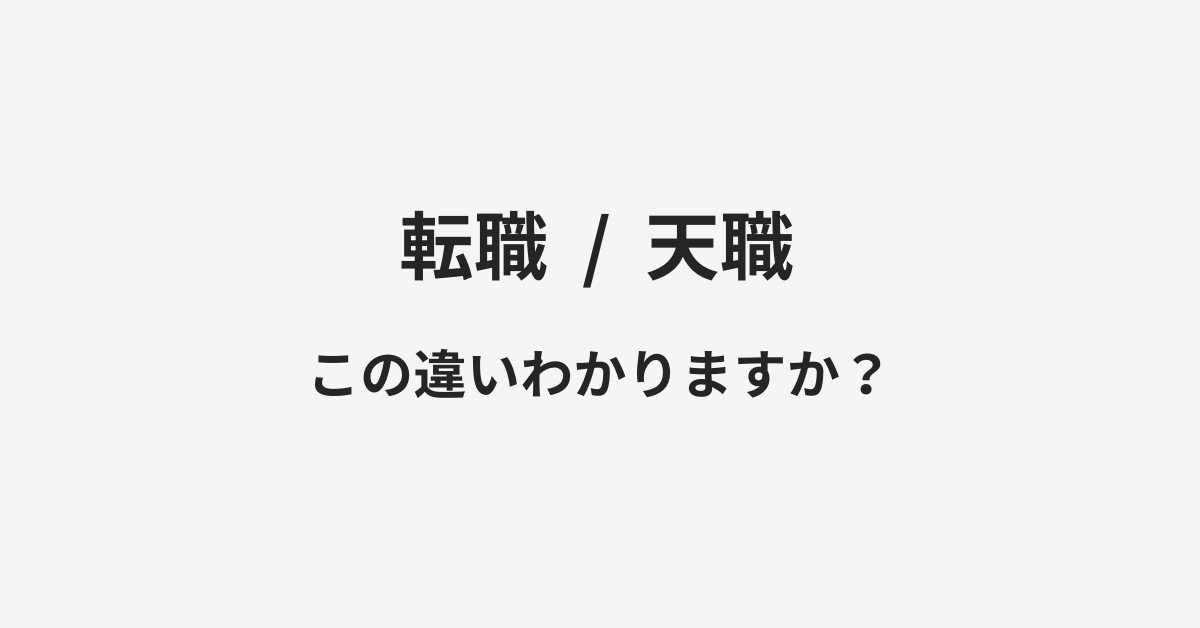【職能給】と【職務給】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
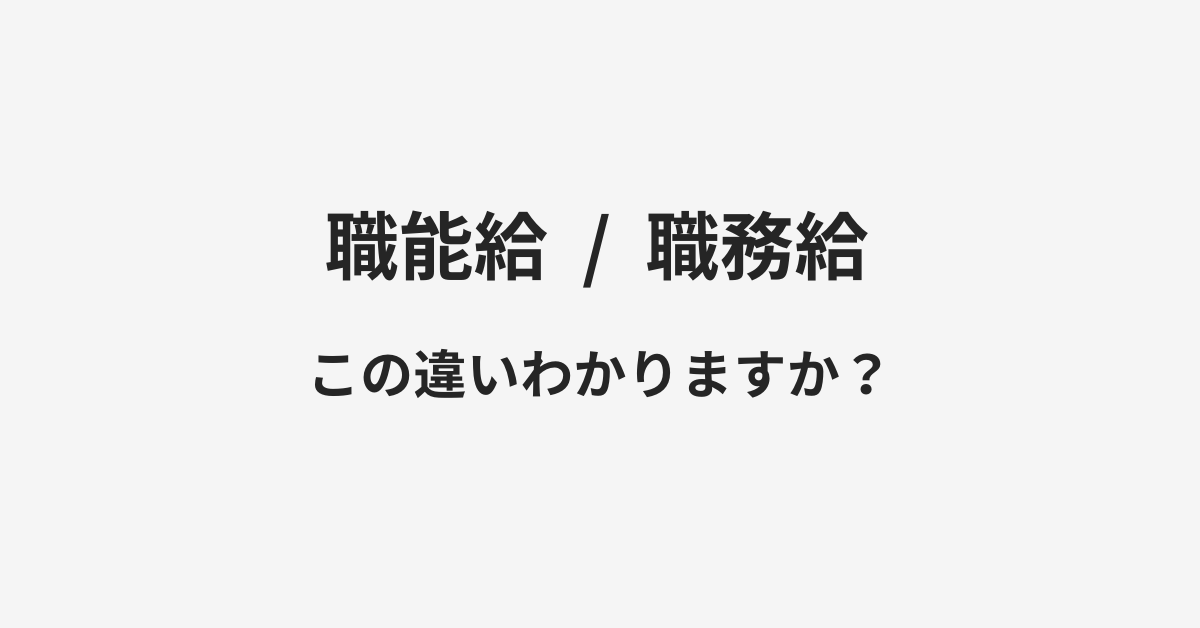
職能給と職務給の分かりやすい違い
職能給と職務給は、どちらも賃金決定の基準ですが、その着眼点が根本的に異なります。
職能給は従業員個人の能力、スキル、経験年数などを評価して賃金を決定する「人」基準の制度です。一方、職務給は担当する仕事の難易度、責任の重さ、必要な専門性などを評価する「仕事」基準の制度です。
日本企業の人事制度改革において、従来の職能給から職務給への移行が議論される中、両制度の特性を理解することが重要です。
職能給とは?
職能給とは、従業員が保有する職務遂行能力に応じて賃金を決定する制度です。日本の多くの企業で採用されており、年功序列型賃金の基盤となっています。能力の向上は経験年数に比例するという考え方に基づき、勤続年数、資格、スキルレベル、潜在能力などを総合的に評価します。職能資格制度と連動し、等級に応じた賃金テーブルが設定されます。
職能給のメリットは、長期的な人材育成に適していることです。従業員は様々な部署を経験しながら能力を高め、ゼネラリストとして成長できます。配置転換が容易で、組織の柔軟性が保たれます。また、能力は下がらないという前提のため、賃金の下方硬直性があり、従業員の生活の安定に寄与します。
一方、デメリットとして、年功的運用になりやすく、実際の仕事内容と賃金のミスマッチが生じることがあります。能力評価が曖昧になりがちで、人件費が高止まりする傾向もあります。グローバル競争の激化により、成果との連動性を高める必要性が指摘されています。
職能給の例文
- ( 1 ) 職能給制度により、経験年数に応じて着実に昇給しています。
- ( 2 ) 職能資格制度で3級に昇格し、職能給が月額2万円アップしました。
- ( 3 ) 職能給の評価基準を見直し、能力開発へのインセンティブを強化します。
- ( 4 ) ジョブローテーションによる職能向上を、職能給に反映させています。
- ( 5 ) 職能給制度の下でも、成果連動部分を導入してメリハリをつけました。
- ( 6 ) 50代以降の職能給カーブを緩やかにし、人件費の適正化を図ります。
職能給の会話例
職務給とは?
職務給とは、従業員が担当する職務(ジョブ)の内容、難易度、責任の重さに応じて賃金を決定する制度です。欧米企業で一般的な制度で、「同一労働同一賃金」の原則に基づいています。職務分析により各ポジションの職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し、職務の価値を客観的に評価して賃金を設定します。
職務給の特徴は、仕事の内容が明確で、その仕事に必要なスキルと責任に見合った賃金が支払われることです。専門性の高い人材の処遇に適しており、外部労働市場との比較も容易です。職務が変わらない限り賃金も変わらないため、人件費の予測可能性が高く、組織のフラット化にも対応しやすいです。
課題としては、職務記述書の作成と更新に手間がかかること、部門を超えた協力が得にくいこと、昇進ポストが限られるためキャリアの停滞が起きやすいことなどがあります。日本企業が導入する際は、ジョブ型雇用への転換、評価制度の見直し、従業員の意識改革が必要となります。
職務給の例文
- ( 1 ) 営業職の職務給を改定し、市場価値に見合った水準に引き上げました。
- ( 2 ) 職務記述書に基づき、各ポジションの職務給レンジを設定しています。
- ( 3 ) 同じ職務であれば、新卒も中途も同じ職務給となります。
- ( 4 ) 高度な専門職には、職務給により competitive な処遇を実現しています。
- ( 5 ) 職務給制度導入により、スペシャリストのキャリアパスが明確になりました。
- ( 6 ) グローバル基準の職務評価により、職務給の妥当性を検証しました。
職務給の会話例
職能給と職務給の違いまとめ
職能給と職務給の最大の違いは、賃金決定の基準が「人」か「仕事」かという点です。職能給は従業員の能力成長を前提とした人的資本重視の制度、職務給は職務の市場価値を反映した合理的な制度といえます。
運用面でも大きな違いがあり、職能給は配置転換が容易でゼネラリスト育成に適していますが、職務給は専門性の追求に適しています。また、職能給は年功的になりやすい一方、職務給は実力主義的な運用が可能です。
今後の人事制度設計では、両制度の長所を組み合わせたハイブリッド型の導入も検討されています。企業の事業特性、人材戦略、組織文化に応じて、最適な制度を選択することが重要です。
職能給と職務給の読み方
- 職能給(ひらがな):しょくのうきゅう
- 職能給(ローマ字):shokunoukyuu
- 職務給(ひらがな):しょくむきゅう
- 職務給(ローマ字):shokumukyuu