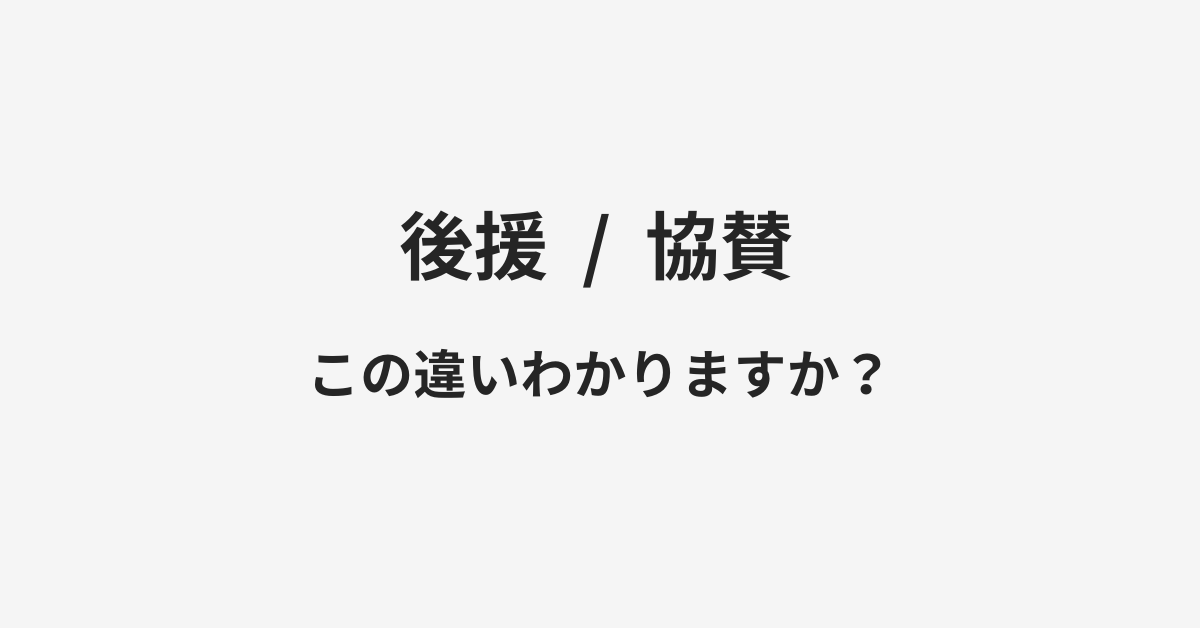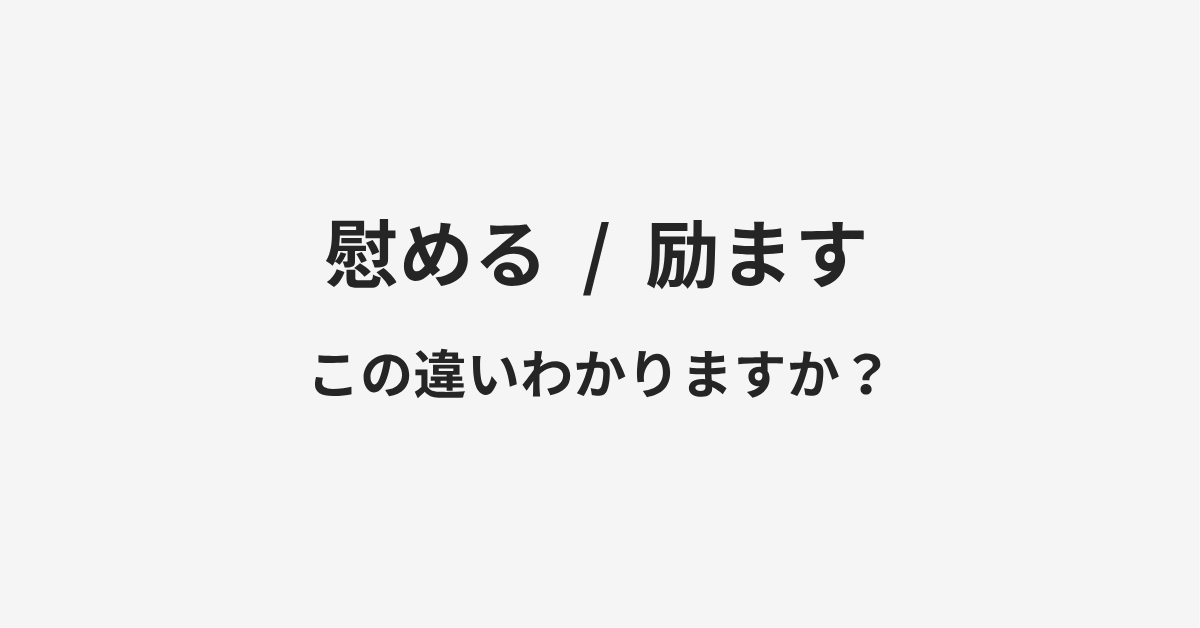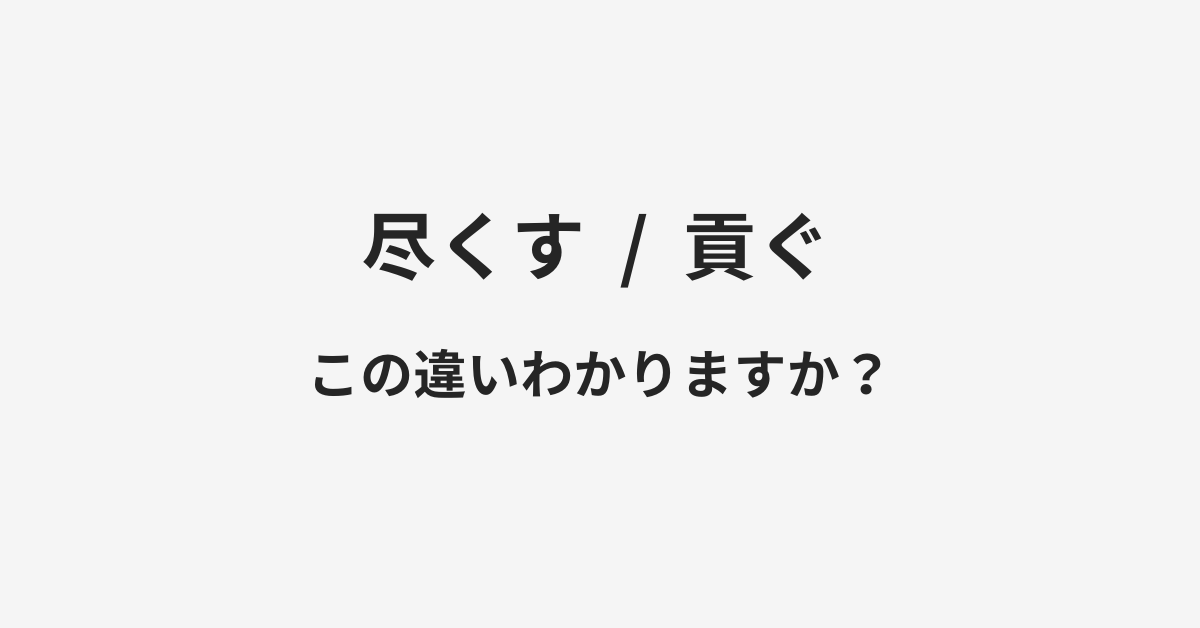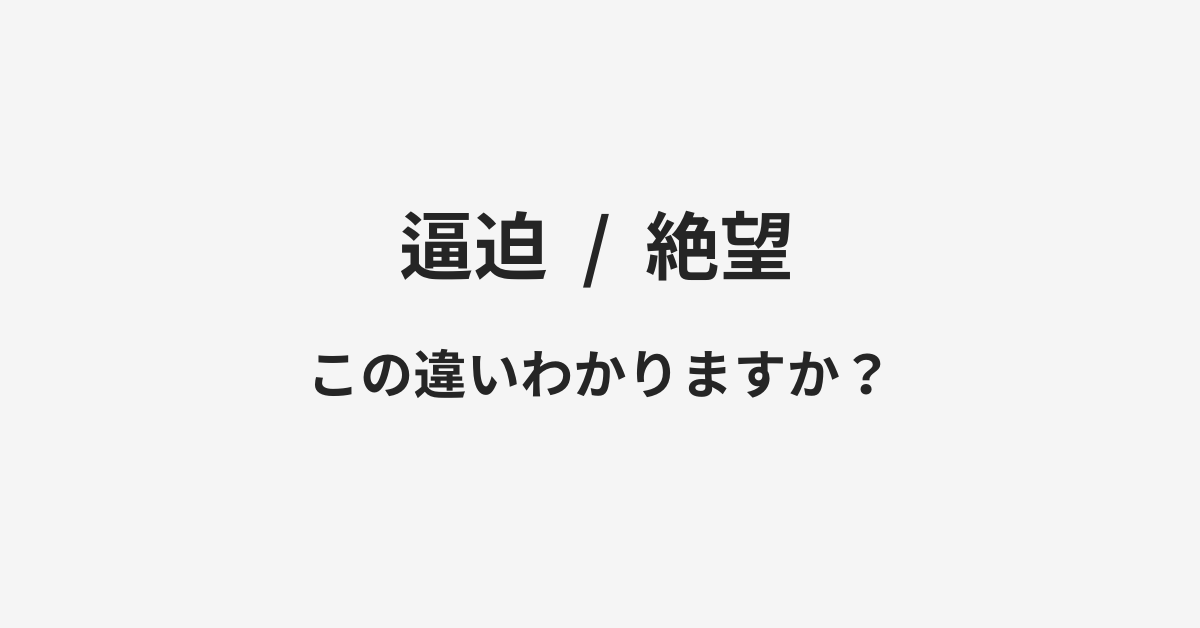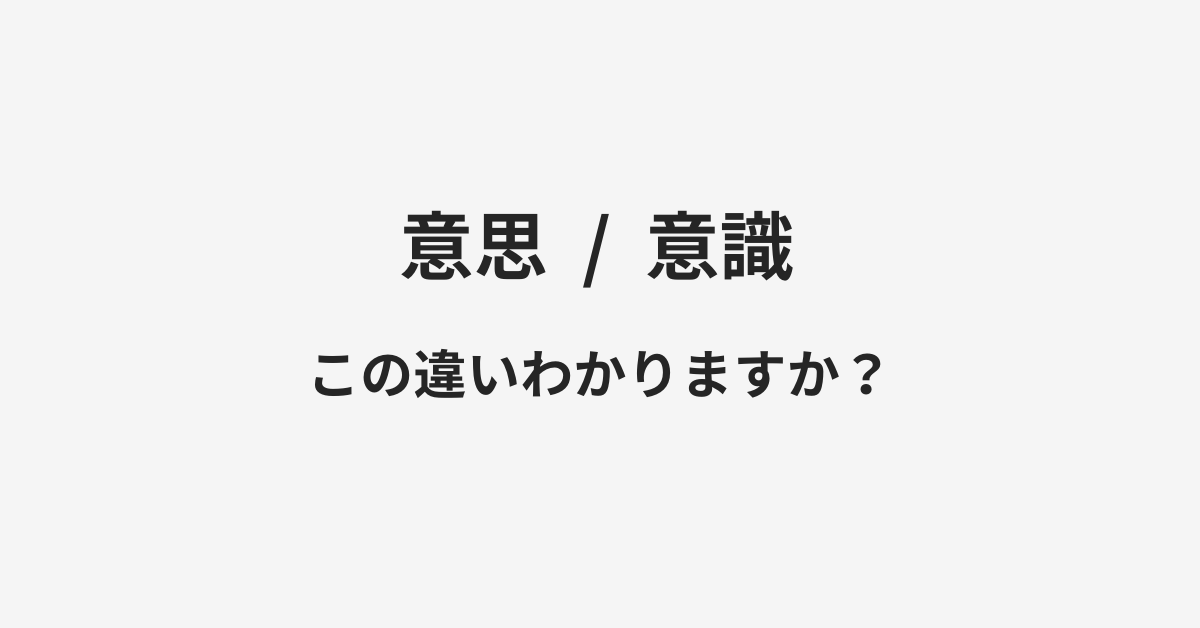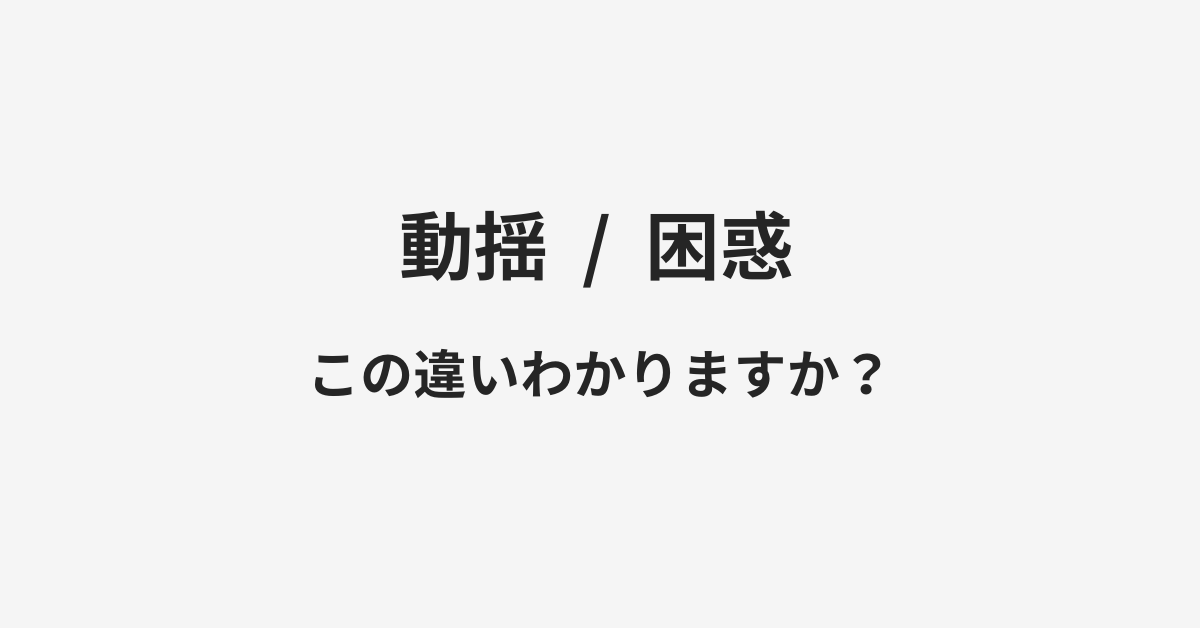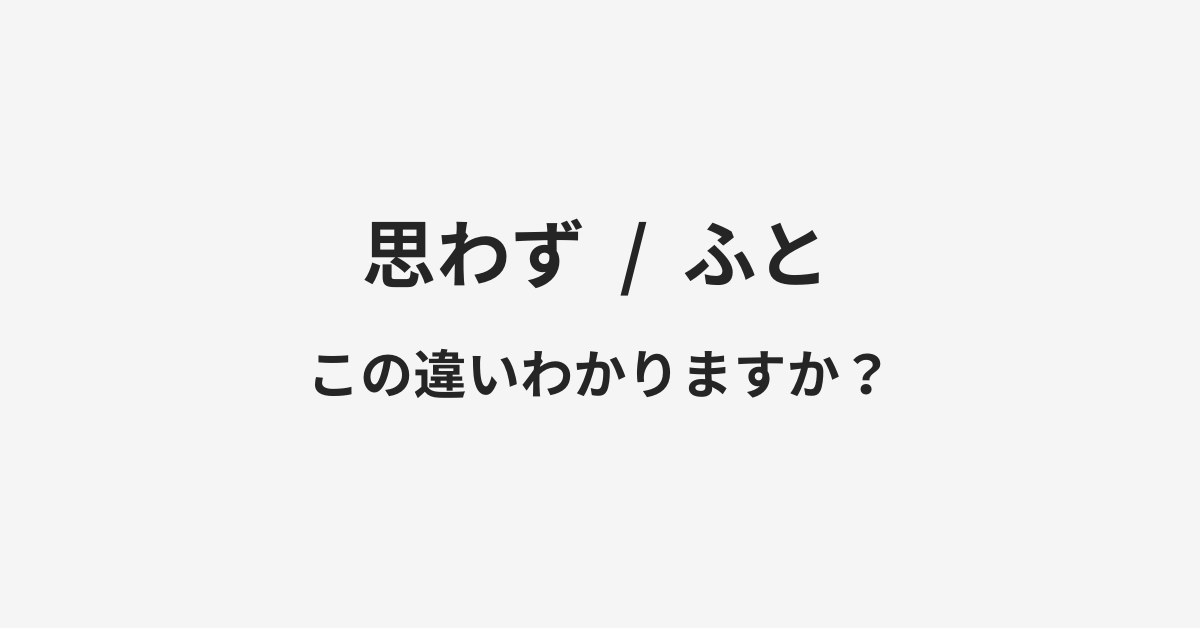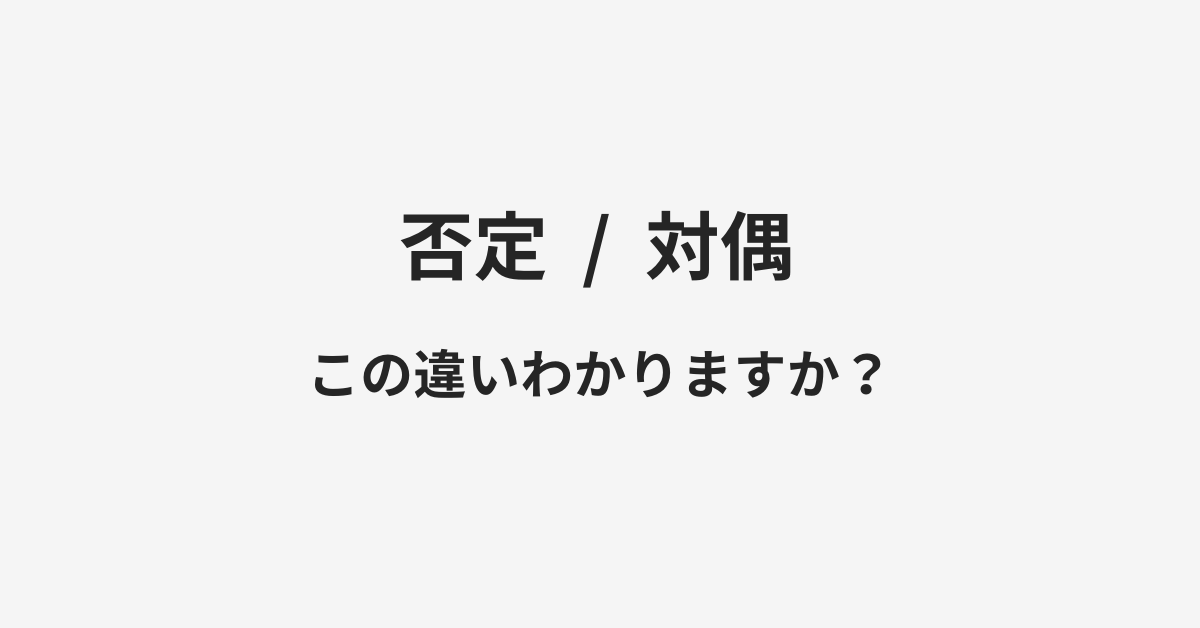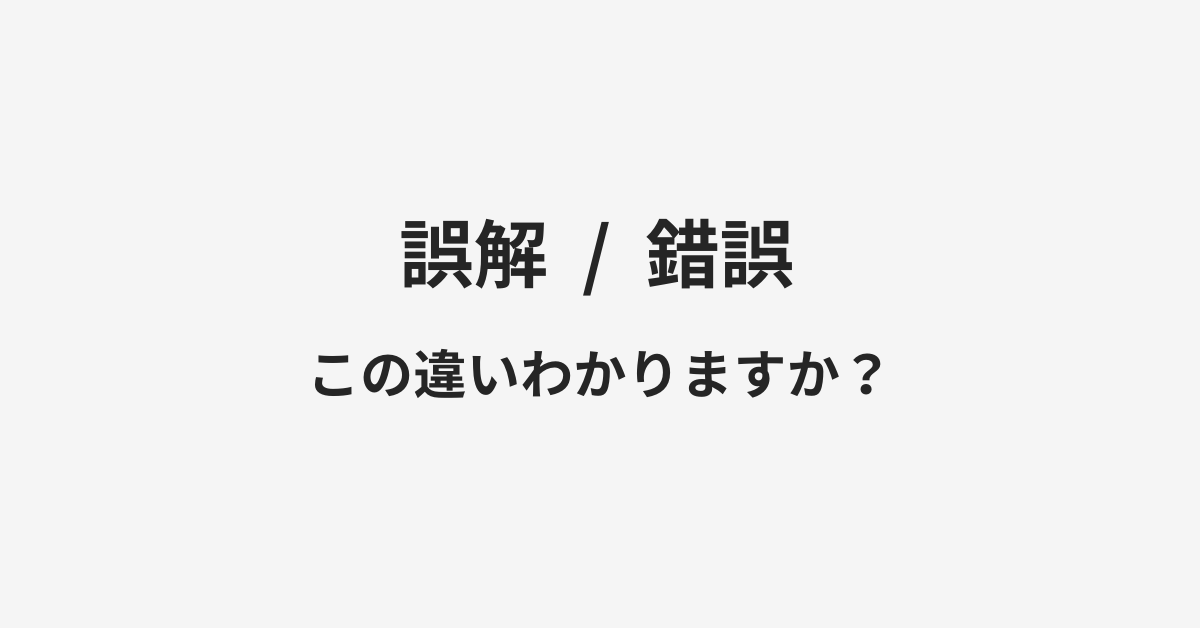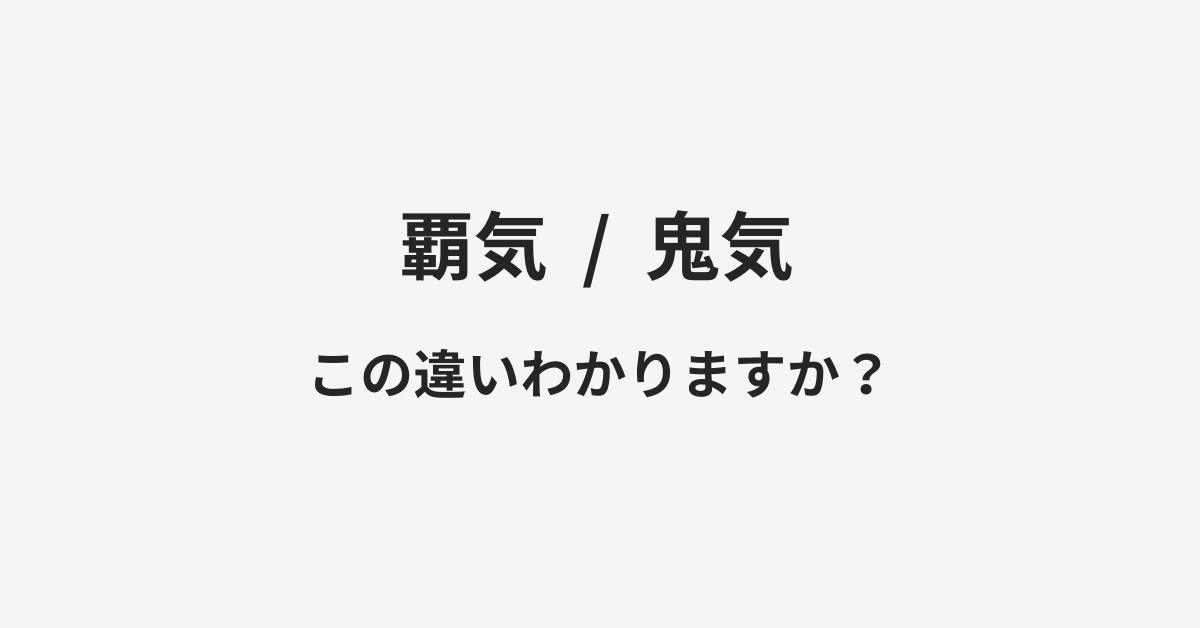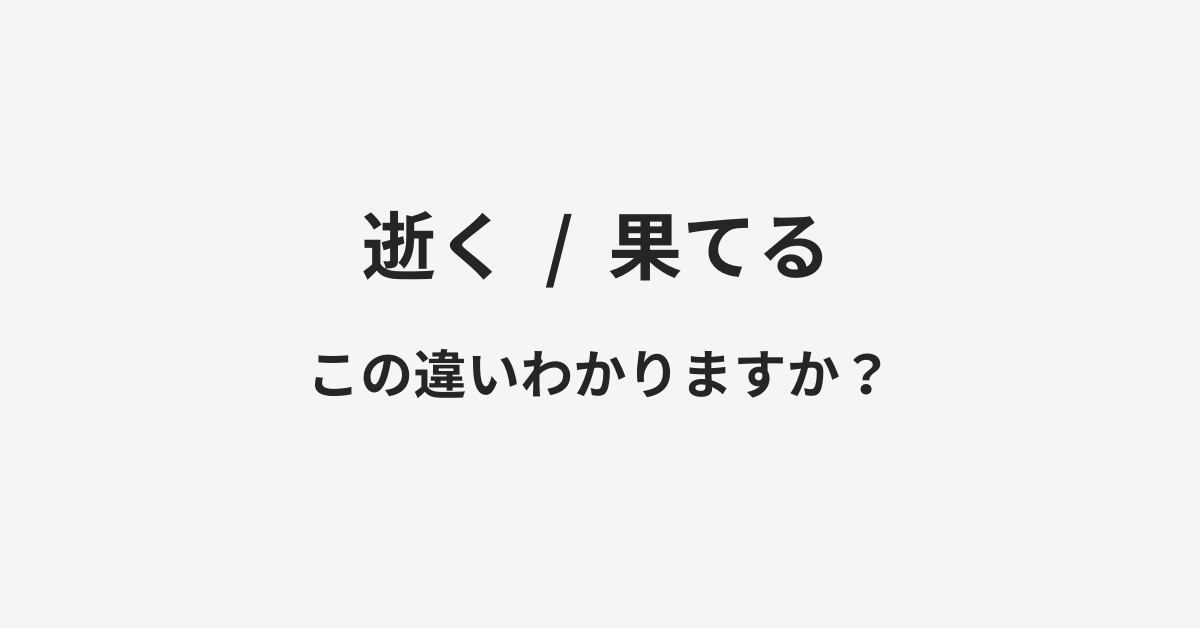【助けてもらう】と【助けを借りる】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
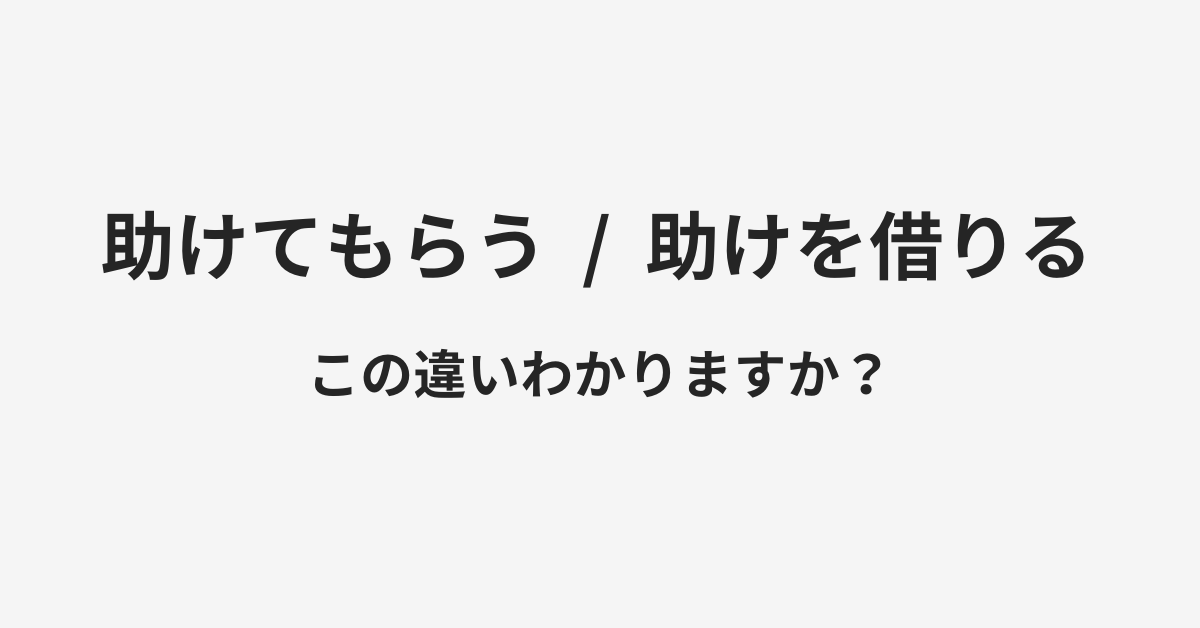
助けてもらうと助けを借りるの分かりやすい違い
助けてもらうと助けを借りるは、どちらも他者の支援を受けることですが、心理的な意味合いが異なります。助けてもらうは相手の好意や思いやりによる支援を受け入れることで、感謝の気持ちが中心です。
助けを借りるは一時的な支援として捉え、将来的に返す意識があります。
メンタルヘルスの観点から、どちらも他者とつながる大切な行為で、適切に使い分けることで健全な相互支援関係を築けます。
助けてもらうとは?
助けてもらうとは、他者からの支援や援助を受け入れることを表す表現で、相手の好意や思いやりに基づく行為として捉えられます。受動的なニュアンスがあり、相手の自発的な申し出や、こちらからお願いした結果として支援を受ける状況を指します。感謝の気持ちが強く表れる表現です。
心理学的には、助けてもらうことを受け入れる能力は、健全な依存性と信頼関係の表れです。プライドや自立への過度なこだわりから助けを拒否することは、かえって心理的な負担を増大させます。適切に助けてもらうことは、社会的なつながりを強化し、孤立感を防ぐ重要な要素となります。
メンタルヘルスにおいて、助けてもらうことへの抵抗を克服することは重要です。うつ病や不安障害などの精神的な困難を抱えている時、他者からの支援を受け入れることは回復への第一歩となります。助けてもらうことは弱さではなく、自己ケアの一部として捉えることが大切です。
助けてもらうの例文
- ( 1 ) カウンセラーに助けてもらうことで、一人では気づけなかった自分の強さを発見できました。
- ( 2 ) 家族に助けてもらうことを素直に受け入れられるようになり、関係が深まりました。
- ( 3 ) 友人に助けてもらうことへの抵抗がなくなり、本当の意味での信頼関係を築けました。
- ( 4 ) 医療チームに助けてもらうことで、回復への道筋が見えてきました。
- ( 5 ) 同じ悩みを持つ仲間に助けてもらうことで、孤独感から解放されました。
- ( 6 ) セラピストに助けてもらうことを通じて、自己受容の大切さを学びました。
助けてもらうの会話例
助けを借りるとは?
助けを借りるとは、他者の支援を一時的に利用することを表す表現で、将来的に何らかの形で返す意識を含んでいます。より能動的で対等な関係性を意識した表現であり、相互扶助の精神に基づいています。自立性を保ちながら、必要な時に支援を求める姿勢を表します。心理学的に見ると、助けを借りるという考え方は、自己効力感を維持しながら他者と協力する健全な姿勢を示します。
完全な自立と適切な相互依存のバランスを取ることができ、対等な人間関係の構築につながります。この姿勢は、長期的な心理的健康と社会的な適応に寄与します。メンタルヘルスの文脈では、助けを借りるという枠組みは、支援を求めることへの心理的ハードルを下げる効果があります。
一時的なものとして捉えることで、自尊心を保ちながら必要な支援を受けることができます。また、将来他者を助ける機会を意識することで、社会的なつながりの中での自己価値を維持できます。
助けを借りるの例文
- ( 1 ) 友人に助けを借りることで、一時的な困難を乗り越えることができました。
- ( 2 ) 専門家に助けを借りる決断をしたことで、自立への第一歩を踏み出せました。
- ( 3 ) 同僚に助けを借りることで、仕事のストレスを分かち合えるようになりました。
- ( 4 ) カウンセリングで助けを借りることは、自分への投資だと考えるようになりました。
- ( 5 ) ピアサポーターに助けを借りることで、対等な立場での支援を経験できました。
- ( 6 ) 一時的に助けを借りることで、将来は他者を助ける側になりたいと思えるようになりました。
助けを借りるの会話例
助けてもらうと助けを借りるの違いまとめ
助けてもらうと助けを借りるの違いは、支援に対する心理的な捉え方にあります。助けてもらうは感謝と受容、助けを借りるは対等性と返済意識を含みます。
メンタルヘルスでは、状況に応じて両方の姿勢を使い分けることが重要です。どちらも他者とのつながりを深め、孤立を防ぐ大切な行為です。
プライドに縛られず、適切に支援を求めることは、心の健康を保つ上で欠かせないスキルです。
助けてもらうと助けを借りるの読み方
- 助けてもらう(ひらがな):たすけてもらう
- 助けてもらう(ローマ字):tasuketemorau
- 助けを借りる(ひらがな):たすけをかりる
- 助けを借りる(ローマ字):tasukewokariru