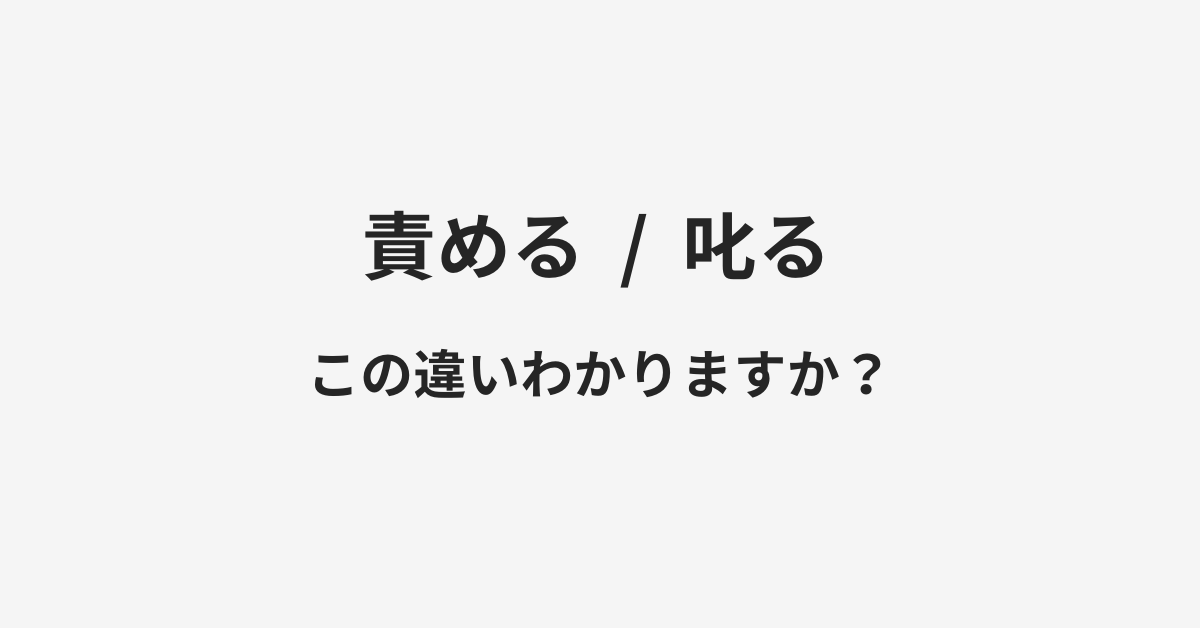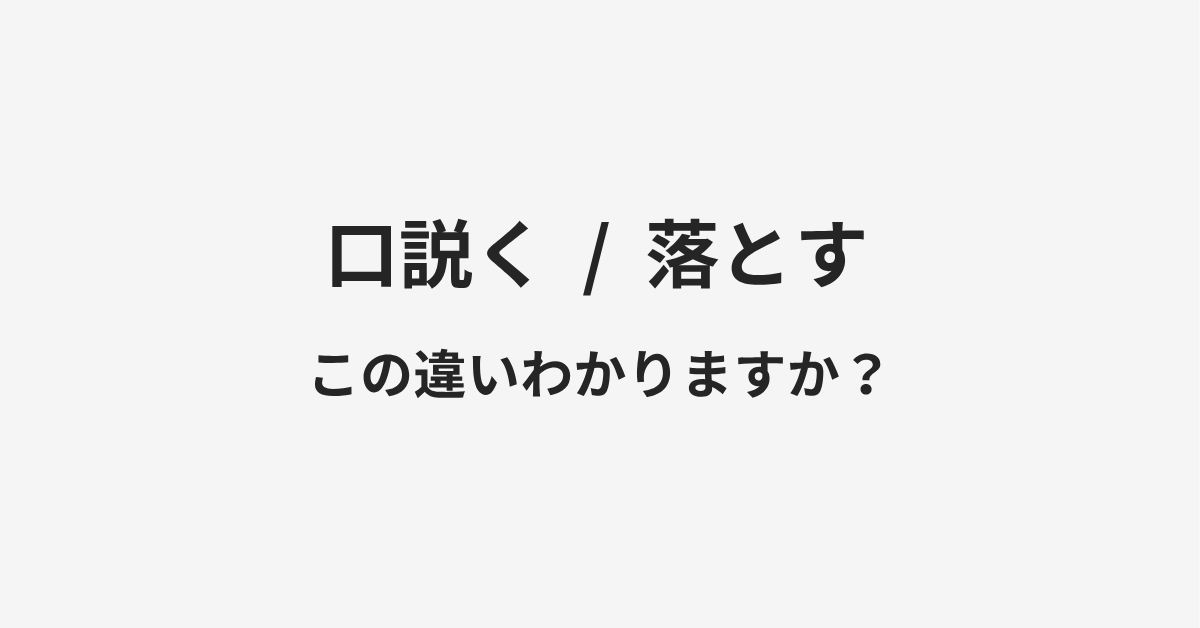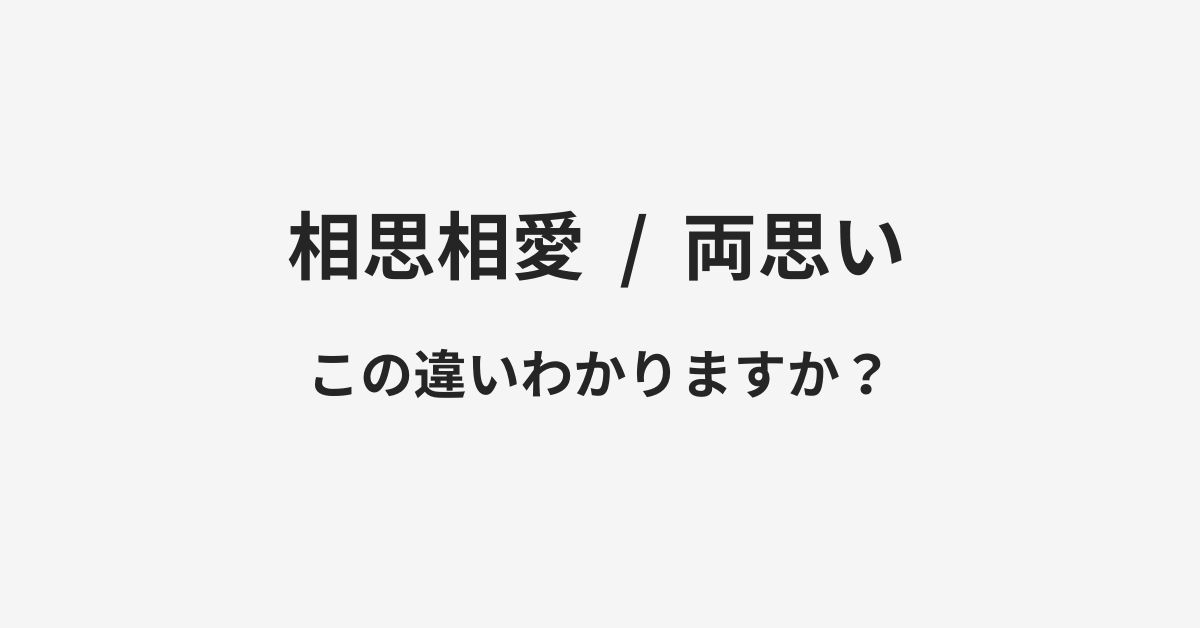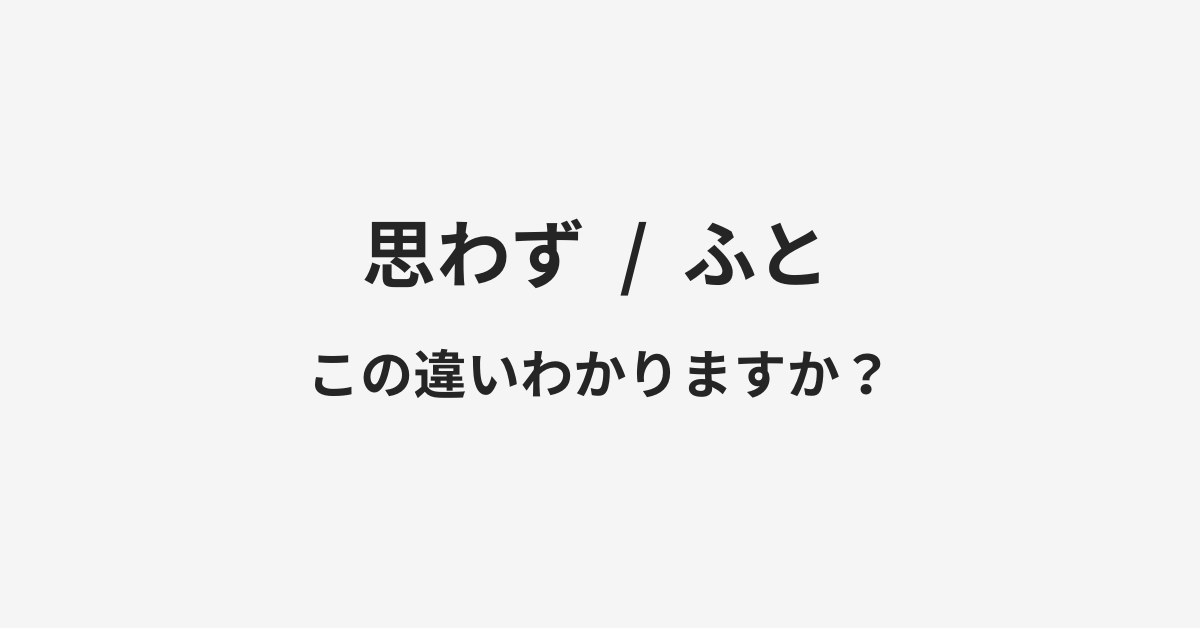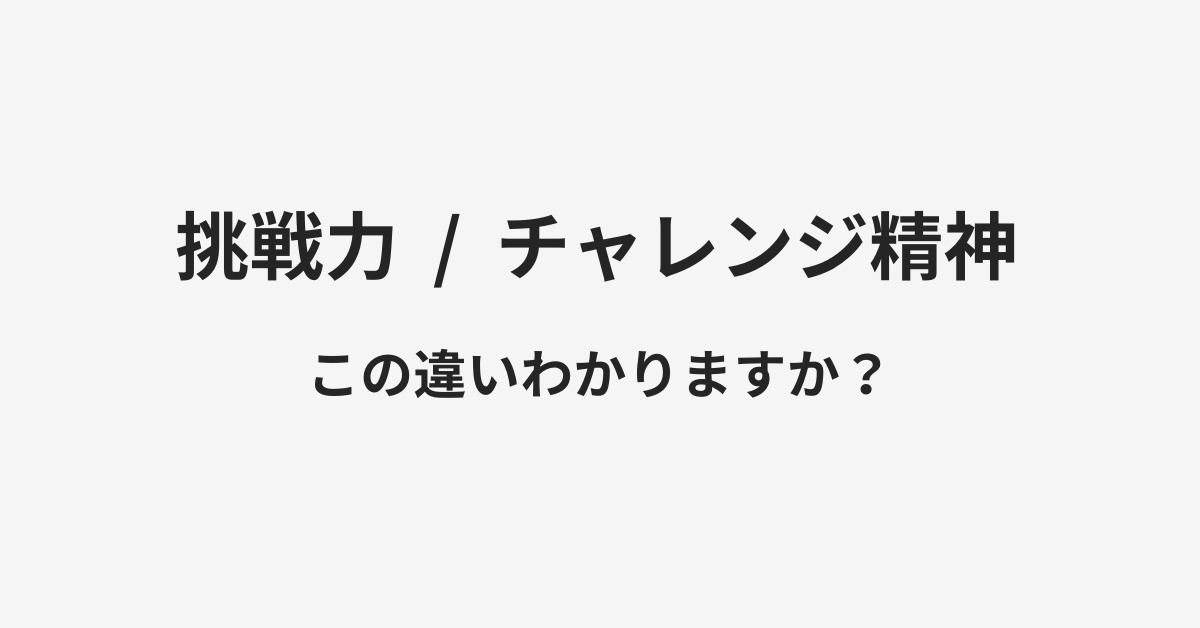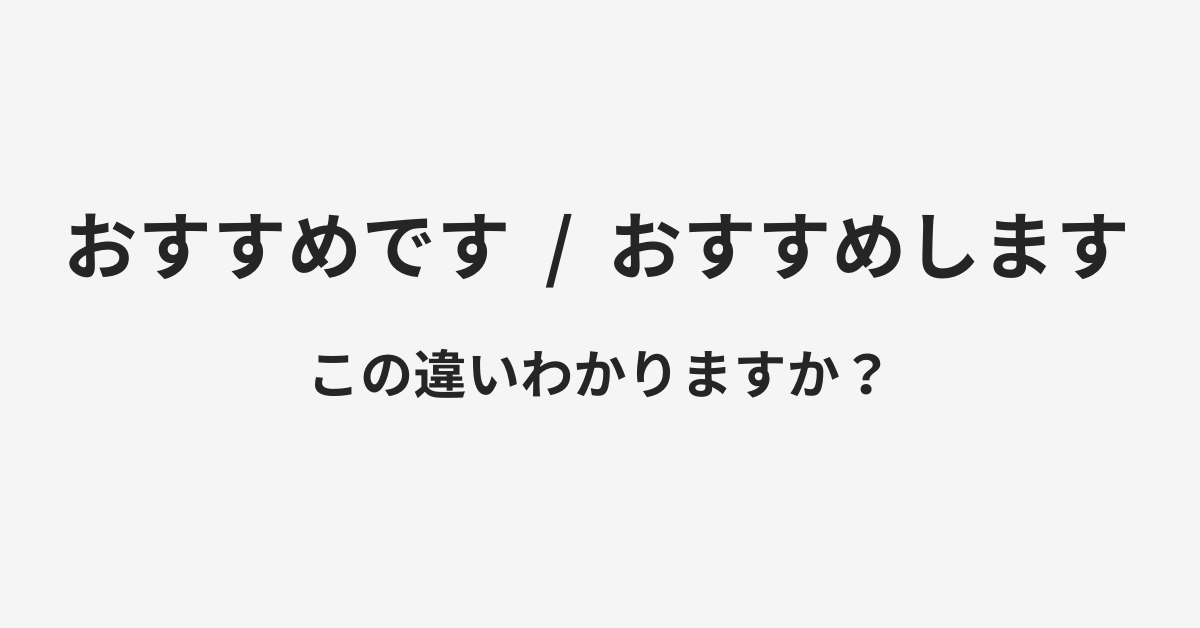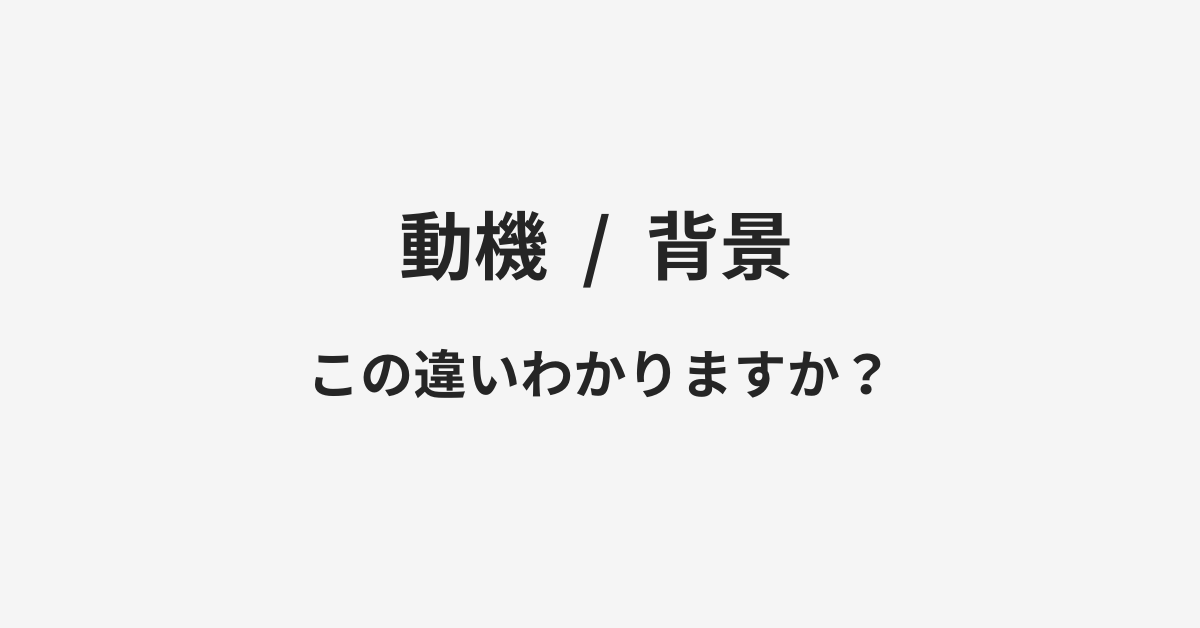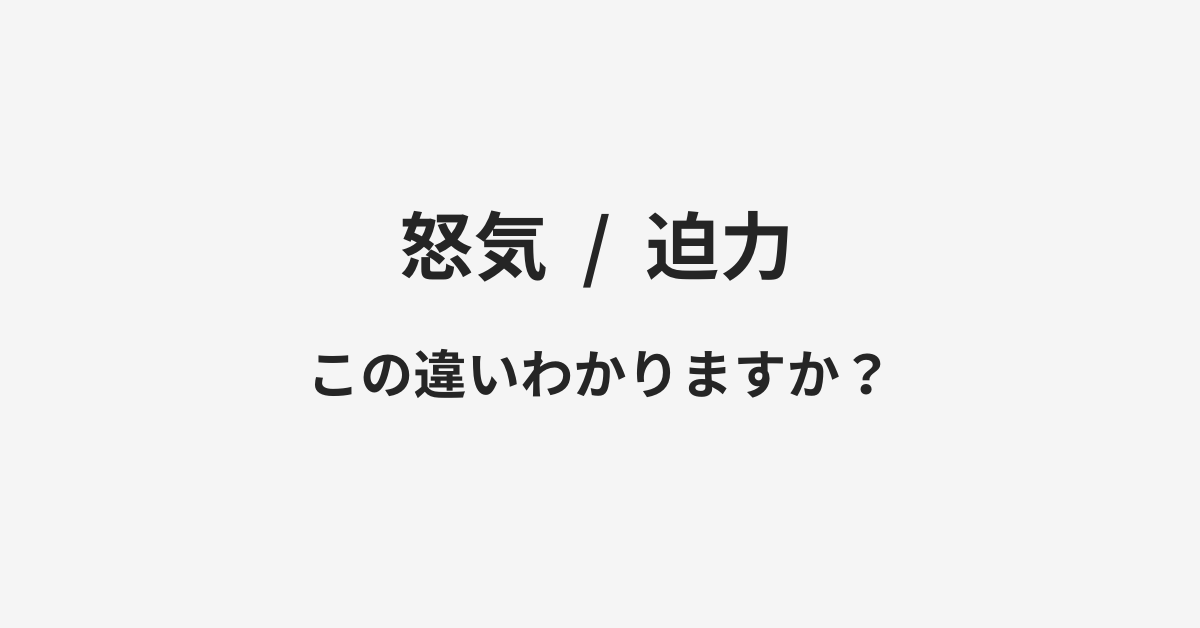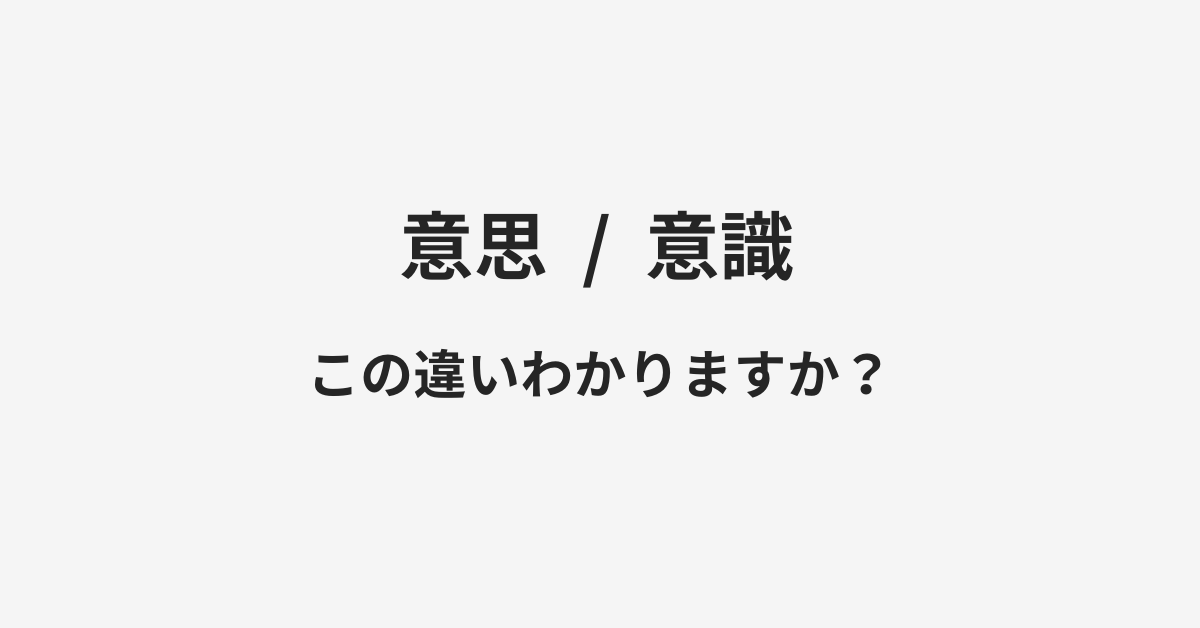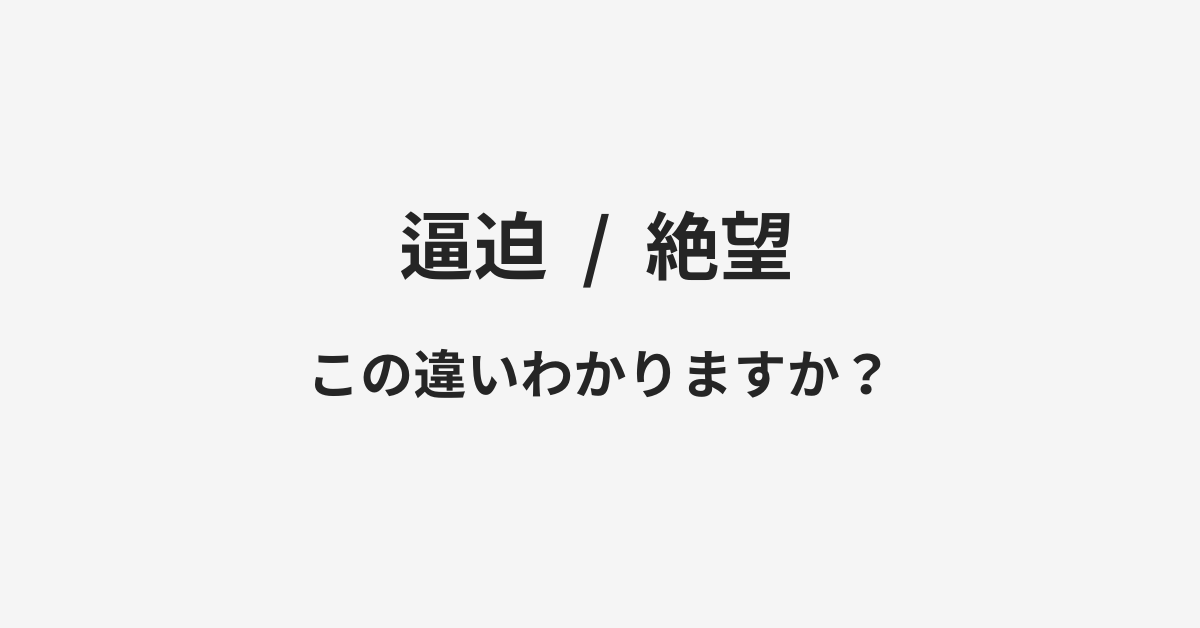【叱る】と【説教】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
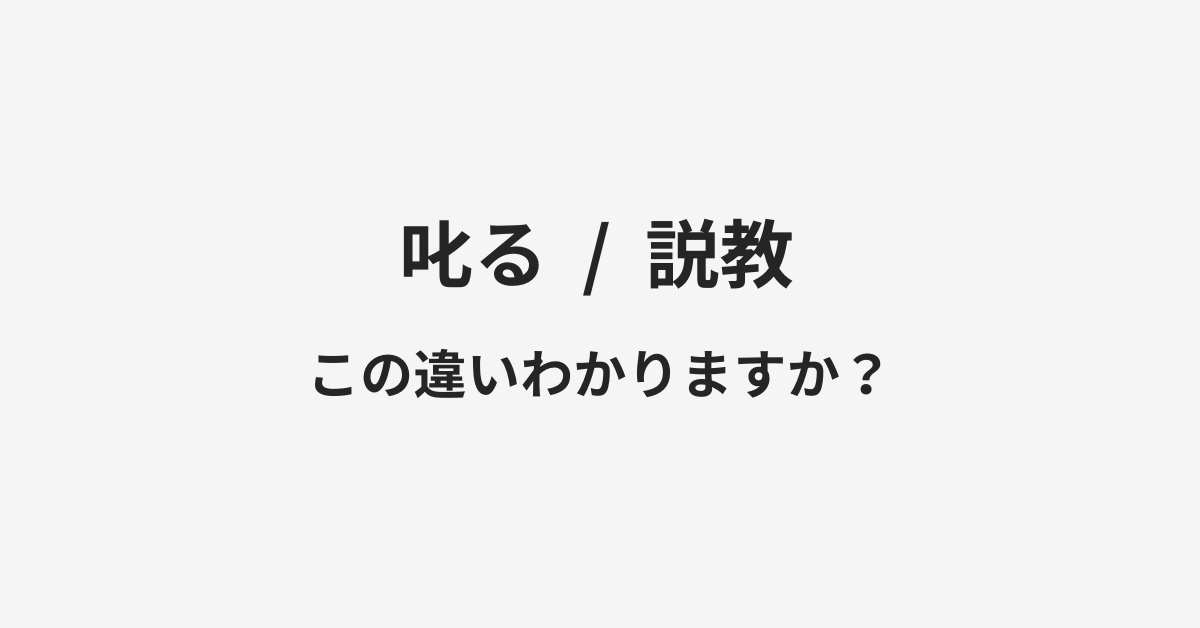
叱ると説教の分かりやすい違い
叱ると説教は、どちらも相手の行動を正そうとする行為ですが、その方法と影響が大きく異なります。叱るは相手を思いやり、具体的な行動について短く的確に注意することです。
一方、説教は長時間にわたって道理を説き、相手の人格まで否定することがあります。心の健康を考えると、適切に叱ることは成長の機会となりますが、説教は自己肯定感を低下させ、精神的なダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。
叱るとは?
叱るとは、相手の成長や改善を願って、具体的な行動や問題点について短く的確に注意を与えることです。愛情や思いやりが根底にあり、相手の人格を否定せず、行動の修正を促すことが目的となります。心理学的に見ると、適切な叱り方は相手の自己効力感を保ちながら、建設的な変化を促すことができます。
叱る際は感情的にならず、具体的で実現可能な改善点を示すことが重要です。また、叱った後のフォローも大切で、相手の努力を認めることで信頼関係を維持できます。
メンタルヘルスの観点から、適切に叱ることは健全な人間関係の構築に役立ちます。相手の成長を支援し、お互いの心理的安全性を保ちながら、より良い関係性を築くことができるのです。
叱るの例文
- ( 1 ) 上司が私のミスについて叱ってくれたおかげで、自分の課題が明確になり、前向きに改善に取り組めています。
- ( 2 ) 母が優しく叱ってくれたことで、自分の行動を振り返り、家族への感謝の気持ちが深まりました。
- ( 3 ) カウンセラーが適切に叱ってくれたことで、自己破壊的な行動パターンに気づくことができました。
- ( 4 ) 友人が愛情を持って叱ってくれたおかげで、ネガティブな思考の癖を改善する勇気が持てました。
- ( 5 ) 先輩が具体的に叱ってくれたことで、仕事のストレス対処法を学び、メンタルが安定してきました。
- ( 6 ) パートナーが優しく叱ってくれることで、自分の感情コントロールの問題に向き合えるようになりました。
叱るの会話例
説教とは?
説教とは、長時間にわたって道理や正論を説き、相手の考え方や人格まで批判する行為です。多くの場合、説教する側の自己満足や優越感が動機となり、相手の気持ちや状況を考慮しない一方的なコミュニケーションになりがちです。心理的な影響として、説教を受けた人は自己肯定感の低下、無力感、反発心などを感じることがあります。
特に繰り返し説教を受けると、うつ状態や不安障害のリスクが高まる可能性があります。説教は相手の防御反応を引き起こし、本来の目的である行動改善にはつながりにくいのです。
メンタルヘルスを守るためには、説教ではなく対話を心がけることが大切です。相手の話を聞き、共感を示しながら、一緒に解決策を考えることで、健康的な関係性を保つことができます。
説教の例文
- ( 1 ) 父から長時間の説教を受け続けて、自己肯定感が完全に失われ、うつ状態になってしまいました。
- ( 2 ) 上司の説教が毎日続き、職場に行くのが怖くなって、パニック発作を起こすようになりました。
- ( 3 ) 親からの説教で人格を否定され続け、自分には価値がないと思い込むようになってしまいました。
- ( 4 ) パートナーの説教がエスカレートして、精神的に追い詰められ、不眠症になってしまいました。
- ( 5 ) 友人からの説教で傷つき、人間関係が怖くなって、社会的に孤立してしまいました。
- ( 6 ) 先生の説教がトラウマになり、自分の意見を言えなくなって、不安障害を発症しました。
説教の会話例
叱ると説教の違いまとめ
叱ると説教の最大の違いは、相手への配慮と目的にあります。叱るは相手の成長を願う愛情から生まれ、具体的で建設的な指摘となります。一方、説教は自己満足的で、相手の心理的負担を考慮しない一方的な批判になりがちです。
メンタルヘルスの維持には、適切な叱り方を身につけ、説教を避けることが重要です。
健全な人間関係と心の健康を保つためには、相手を尊重し、成長を支援する姿勢で接することが大切です。
叱ると説教の読み方
- 叱る(ひらがな):しかる
- 叱る(ローマ字):shikaru
- 説教(ひらがな):せっきょう
- 説教(ローマ字):sekkyou