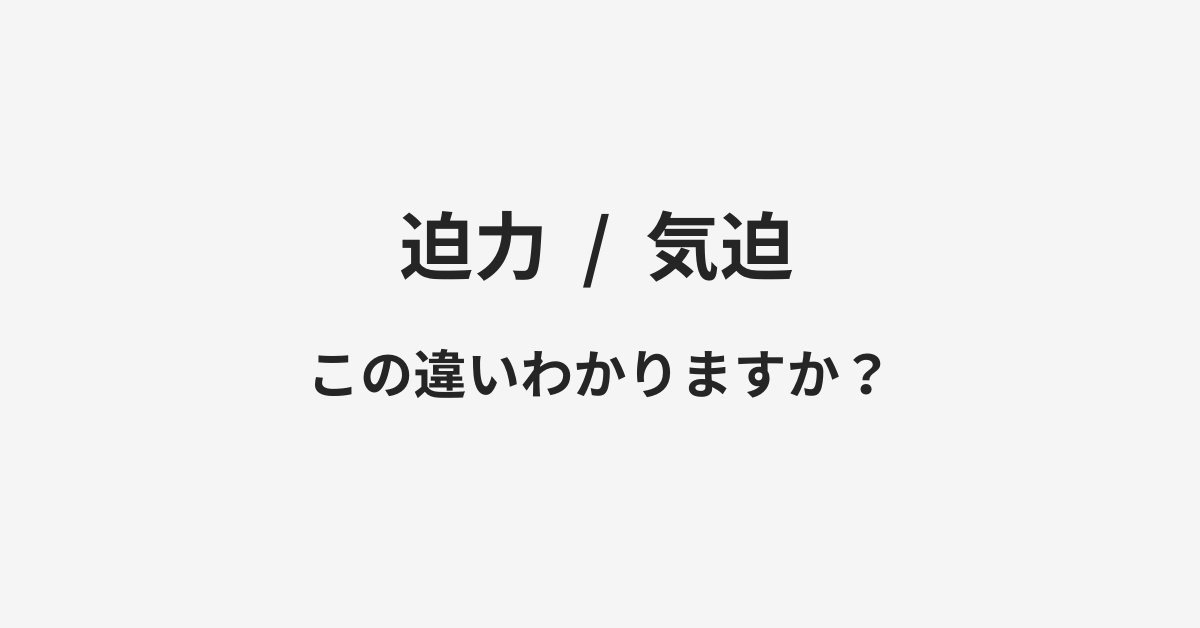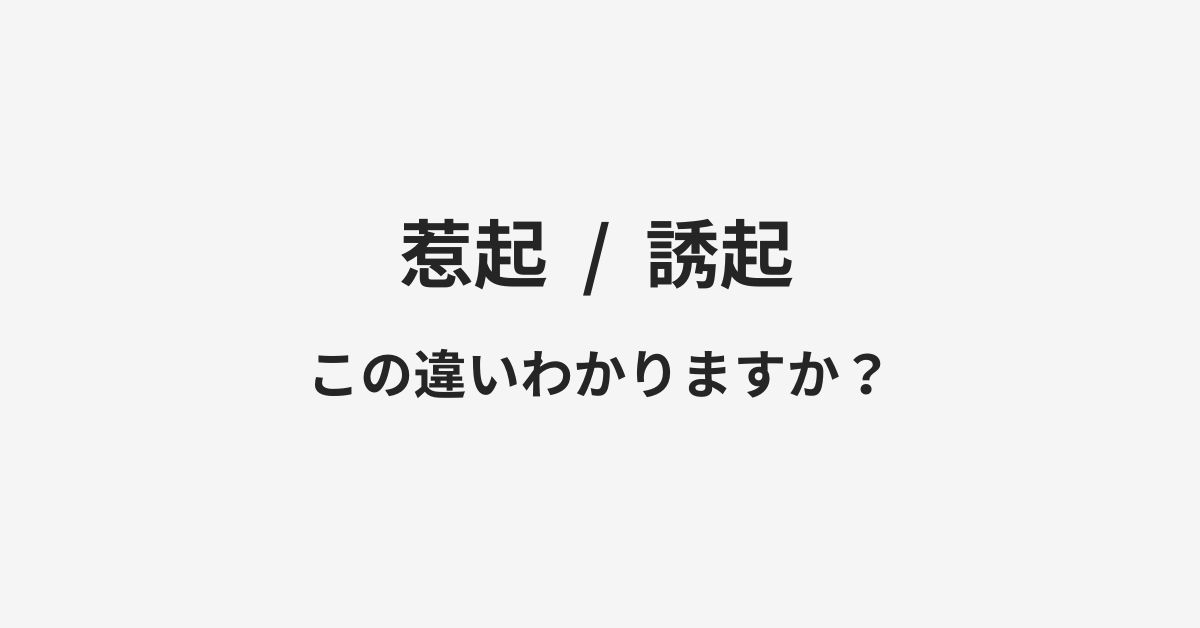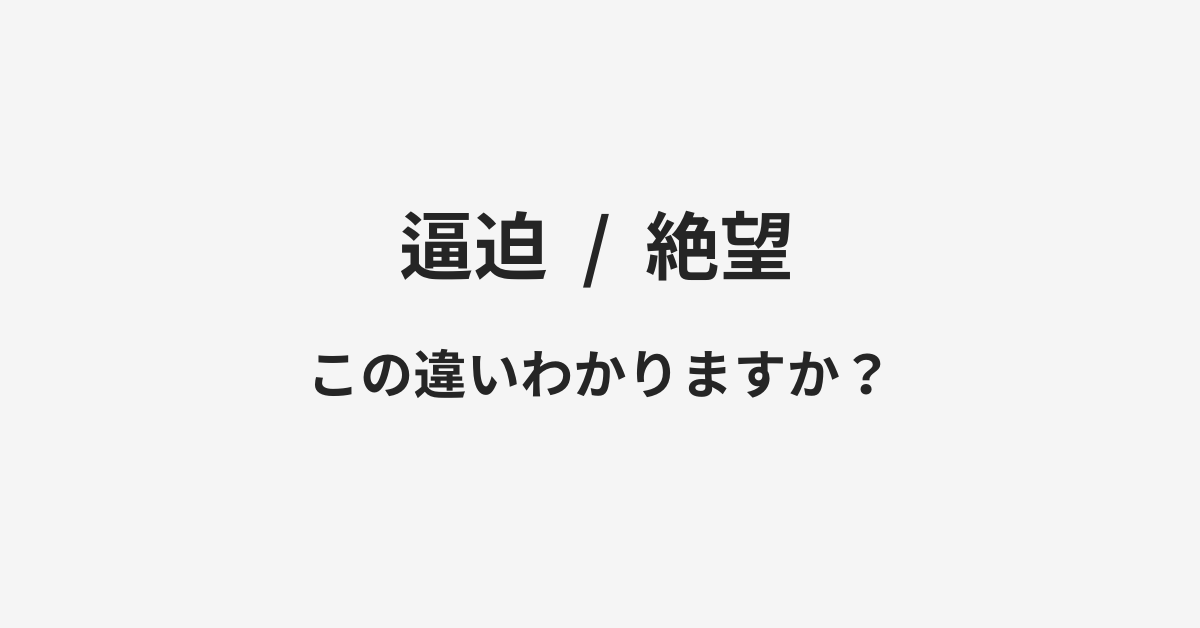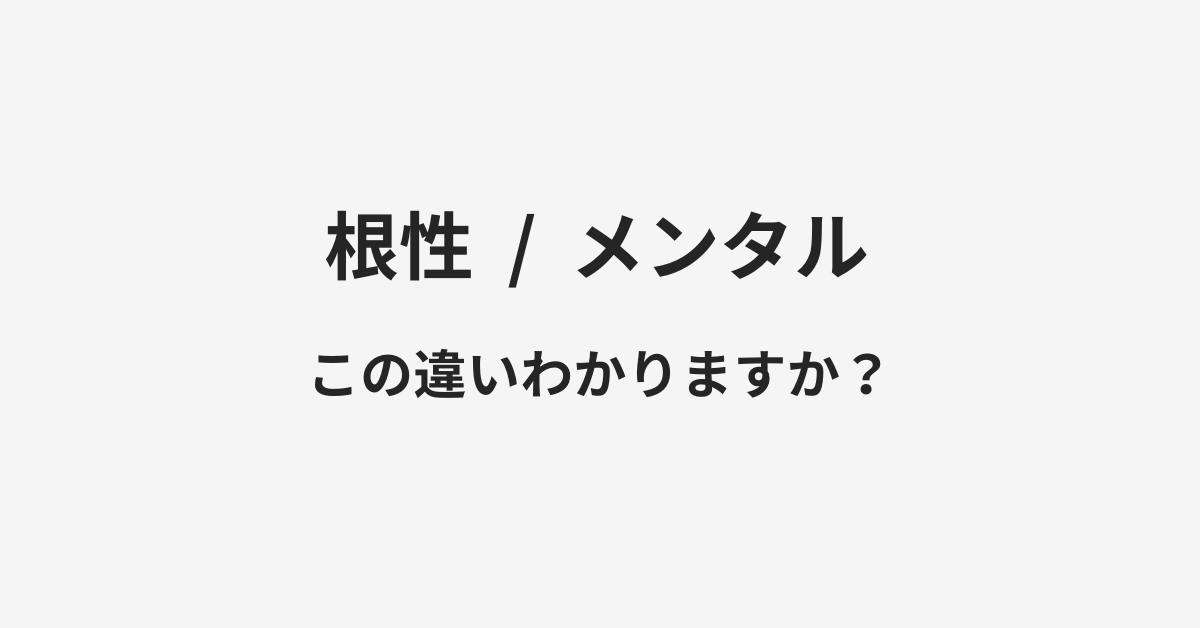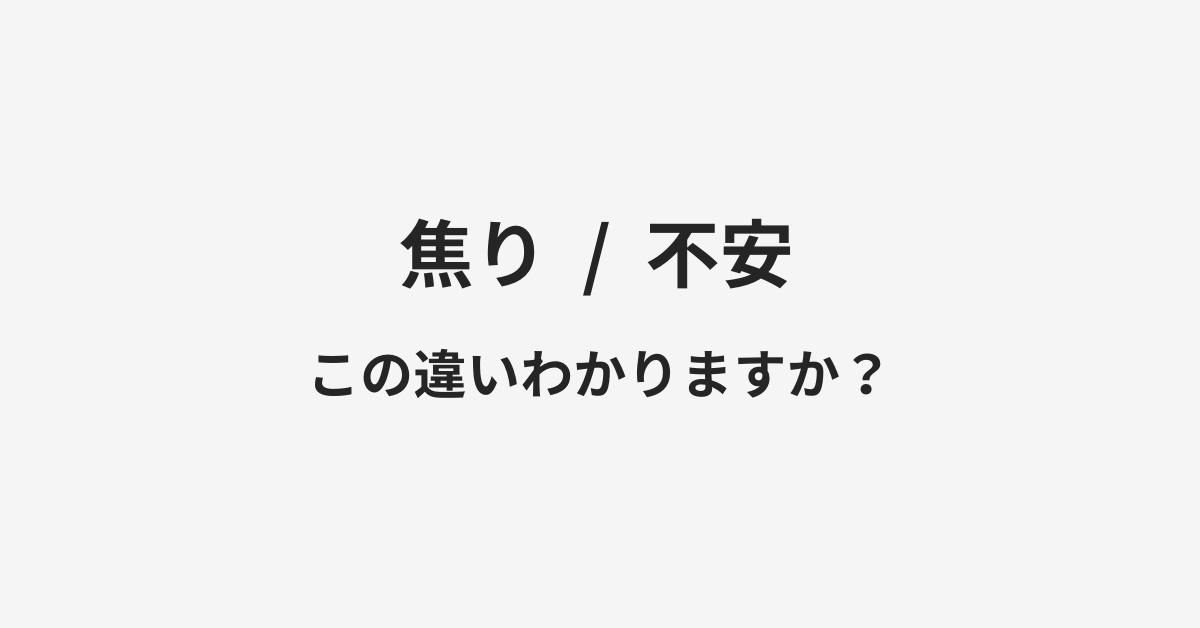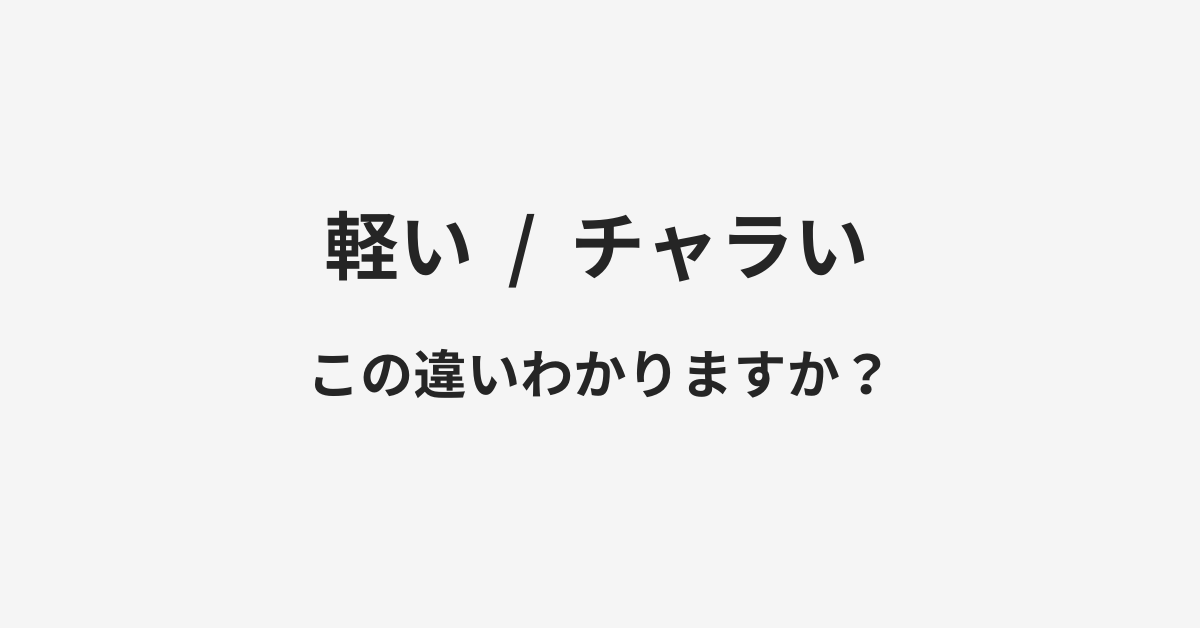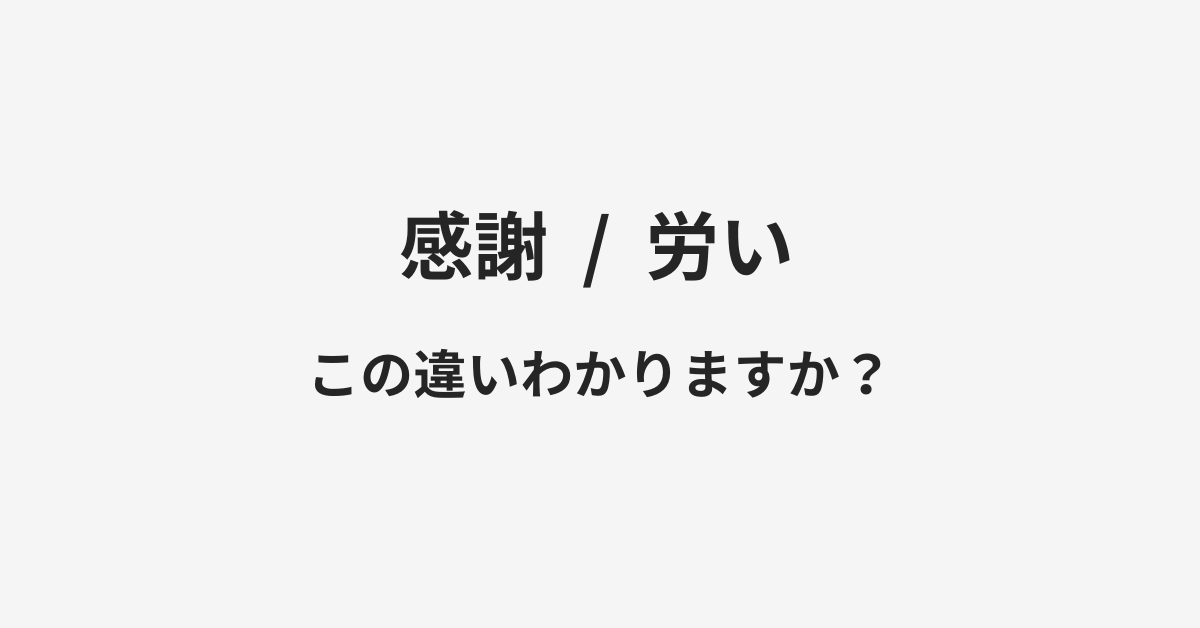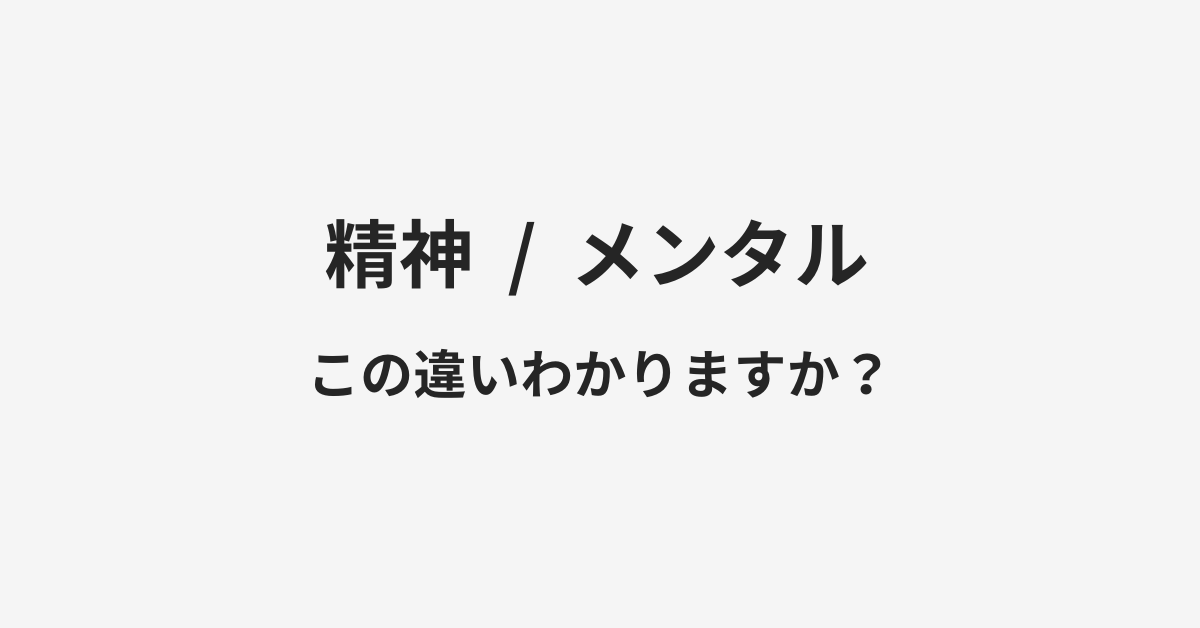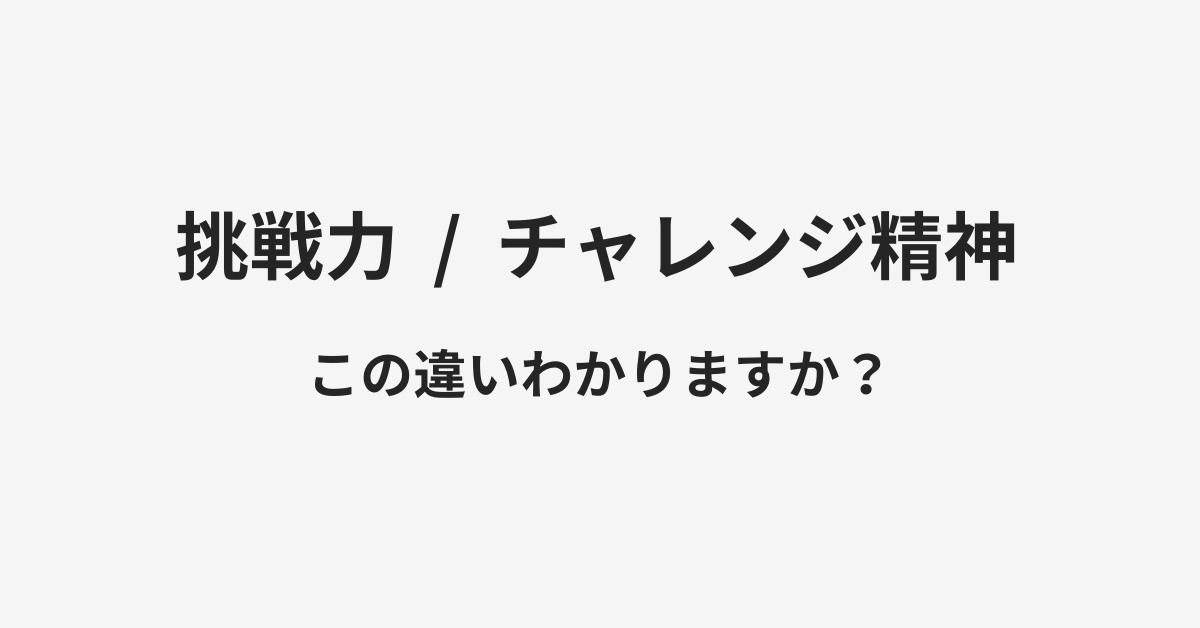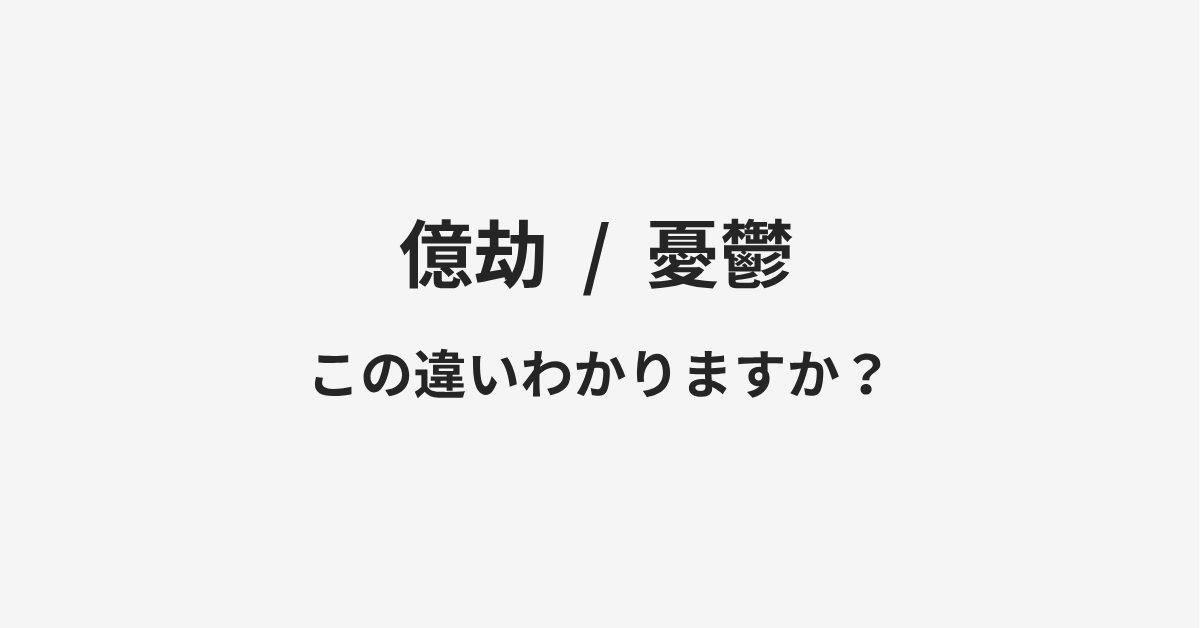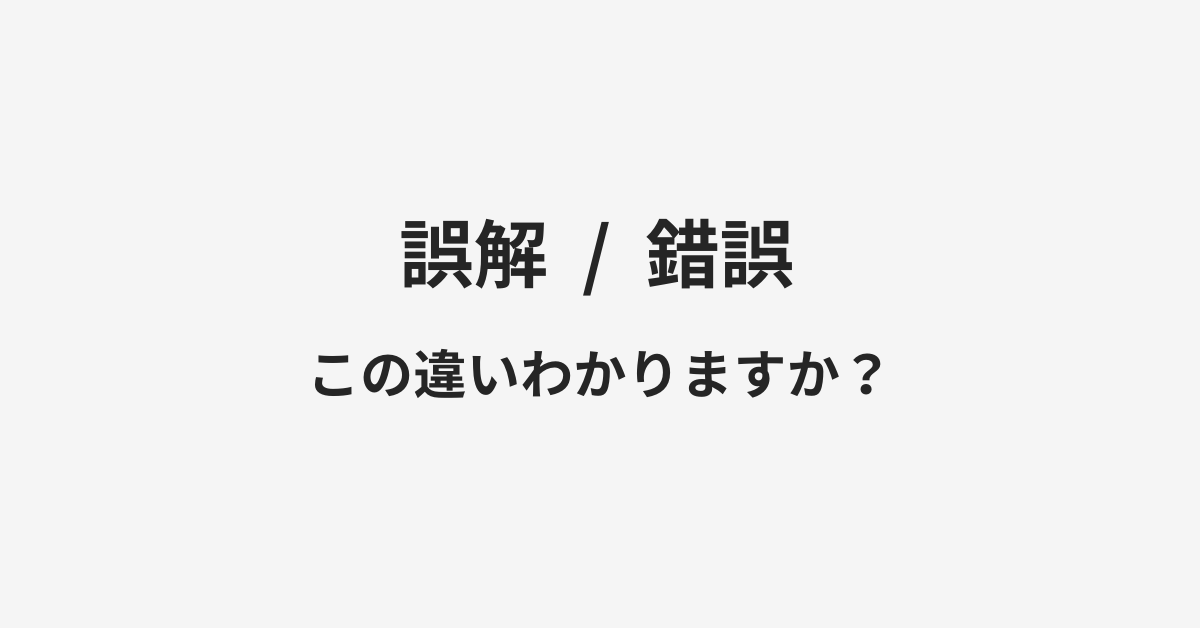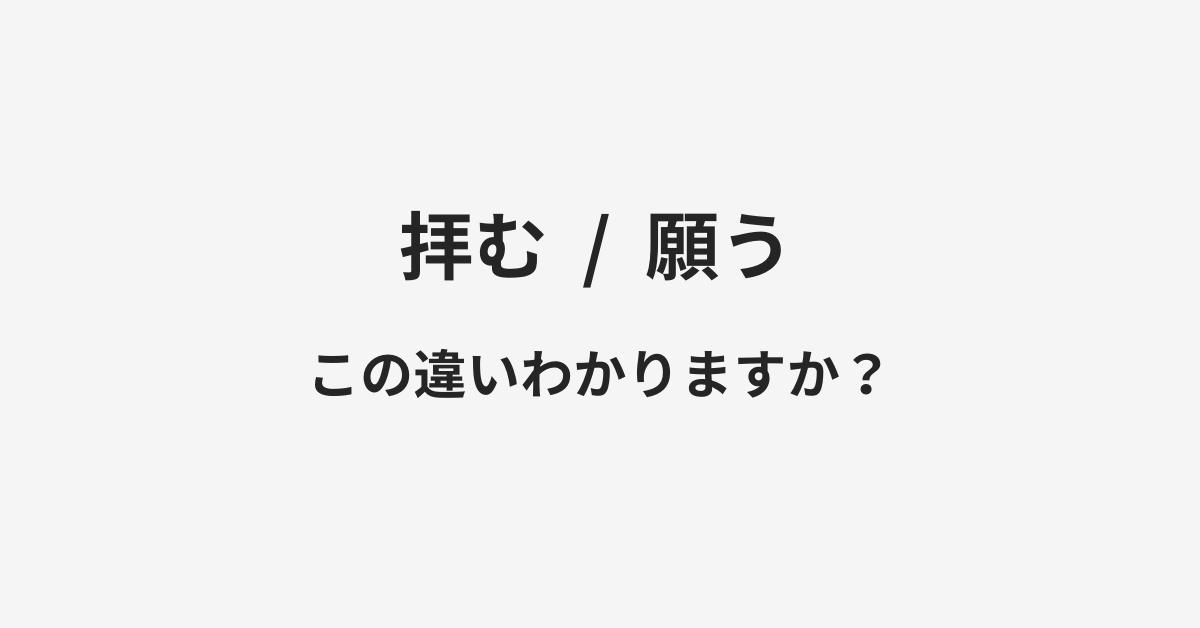【威圧】と【気迫】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
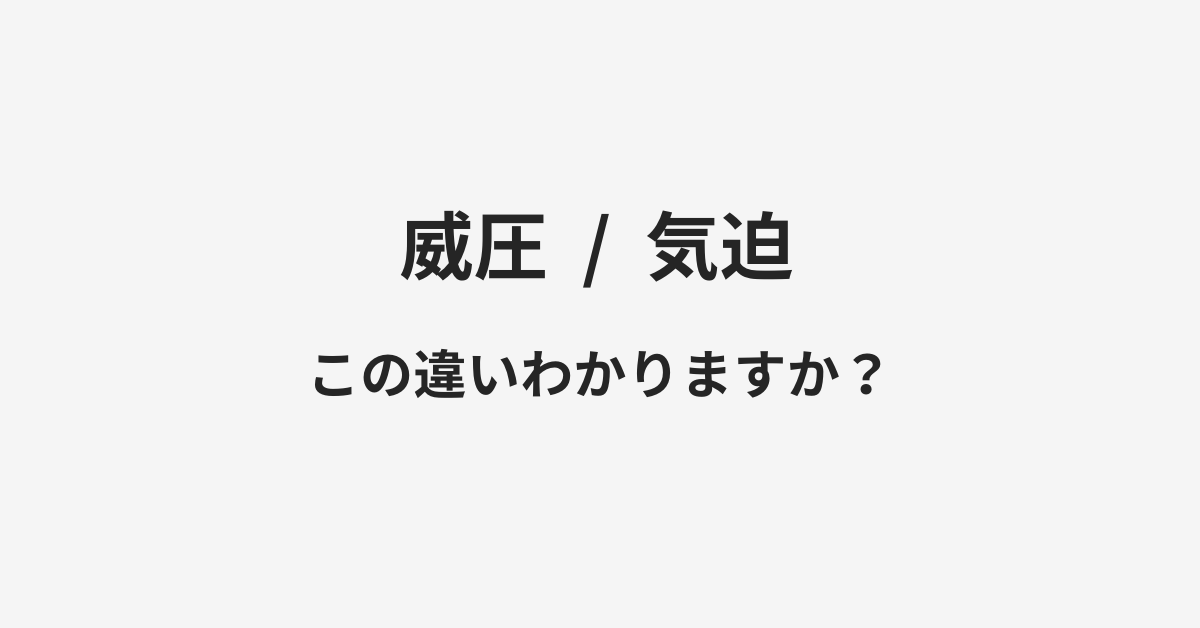
威圧と気迫の分かりやすい違い
威圧と気迫は、どちらも強い存在感を示しますが、その本質と影響が大きく異なります。
威圧は相手を恐怖で支配しようとする攻撃的な力です。気迫は内なる信念と意志から生まれる精神的な強さです。
メンタルヘルスでは、威圧は心理的虐待につながり、気迫は健全な自己主張と回復への原動力となります。
威圧とは?
威圧とは、強い力や権威を使って相手を圧倒し、恐怖や不安を与えることで支配しようとする行為や雰囲気を指します。物理的な大きさ、声の大きさ、態度、地位などを利用して、相手を委縮させ、従わせようとする支配的なコミュニケーション方法です。
心理学的には、威圧は支配欲求、不安、劣等感の補償などから生じることが多いです。威圧する側は一時的な優越感を得ますが、真の信頼関係は築けません。威圧される側は、恐怖、無力感、自己肯定感の低下などを経験し、トラウマになることもあります。
メンタルヘルスへの影響は深刻で、継続的な威圧はパワーハラスメント、モラルハラスメントとなり、うつ病、不安障害、PTSDなどを引き起こす可能性があります。健全な関係には、威圧ではなく相互尊重に基づくコミュニケーションが必要です。
威圧の例文
- ( 1 ) 上司の威圧的な態度に怯えて、職場でのびのびと働けません。
- ( 2 ) 威圧的な家庭環境で育ったトラウマが、今も人間関係に影響しています。
- ( 3 ) 医師の威圧的な説明方法に傷つき、セカンドオピニオンを求めました。
- ( 4 ) 威圧されると頭が真っ白になり、自分の意見が言えなくなってしまいます。
- ( 5 ) パートナーの威圧的な言動から逃れ、自分を取り戻すことができました。
- ( 6 ) 威圧ではなく対話を選ぶことで、健全な関係を築けるようになりました。
威圧の会話例
気迫とは?
気迫とは、強い意志と信念から生まれる、内面的な精神力や迫力を指します。外的な力に頼らず、自己の内なる強さから湧き出るエネルギーであり、困難に立ち向かう勇気や、目標を達成しようとする強い決意を表現します。真の強さの表れです。
心理学的には、気迫は高い自己効力感、内的動機づけ、レジリエンスと関連しています。気迫のある人は、他者を威圧するのではなく、自分自身の限界に挑戦し、周囲にポジティブな影響を与えます。この内なる強さは、困難を乗り越える原動力となります。
メンタルヘルスにおいて、健全な気迫を持つことは重要です。回復への気迫、生きることへの気迫は、治療効果を高め、困難を乗り越える力となります。ただし、過度な気迫は自己や他者への過剰な要求につながるため、バランスが大切です。
気迫の例文
- ( 1 ) 回復への強い気迫を持ち続けたことで、困難な治療を乗り越えられました。
- ( 2 ) カウンセラーの静かな気迫に励まされ、自分も頑張ろうと思えました。
- ( 3 ) 気迫を持って自己主張したことで、初めて自分の意見が通りました。
- ( 4 ) うつ病と闘う気迫を失いかけた時、仲間の存在が支えになりました。
- ( 5 ) 小さな一歩でも前進する気迫が、着実な回復につながっています。
- ( 6 ) 気迫を持ちながらも、休む勇気も大切だと学びました。
気迫の会話例
威圧と気迫の違いまとめ
威圧と気迫の決定的な違いは、力の源と方向性です。威圧は外向きの支配欲、気迫は内なる精神力の表出です。
メンタルヘルスでは、威圧的な環境から身を守り、健全な気迫を育てることが大切です。真の強さは他者を恐れさせることではなく、自己を信じることから生まれます。
心の健康には、威圧に屈しない強さと、適切な気迫を持って人生に向き合う姿勢が重要です。
威圧と気迫の読み方
- 威圧(ひらがな):いあつ
- 威圧(ローマ字):iatsu
- 気迫(ひらがな):きはく
- 気迫(ローマ字):kihaku