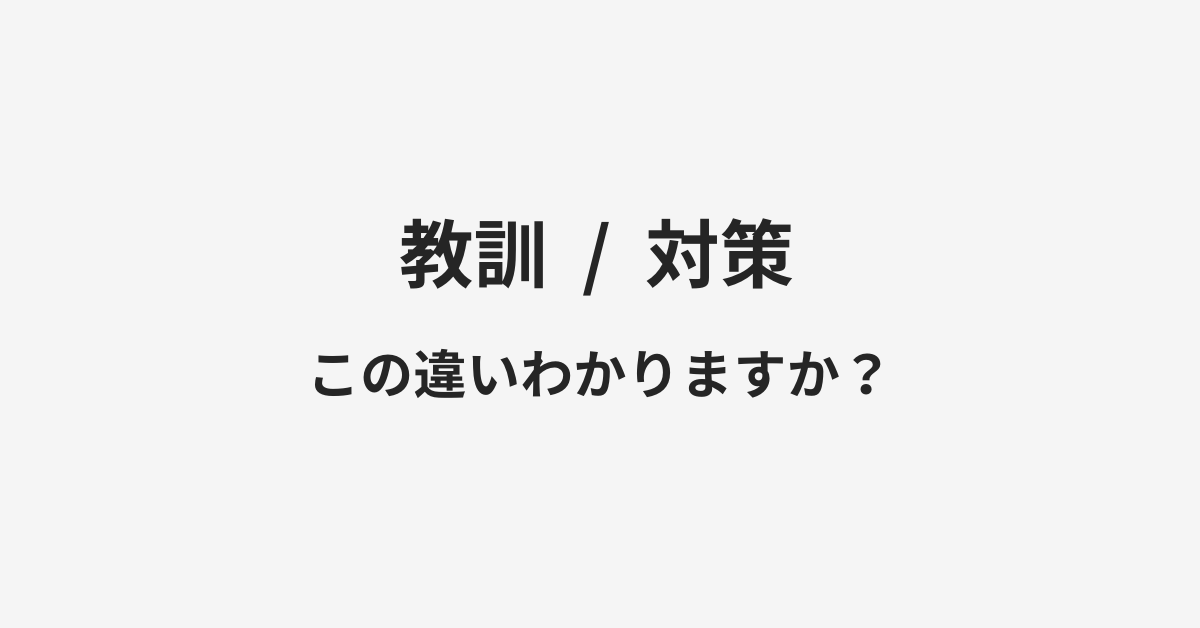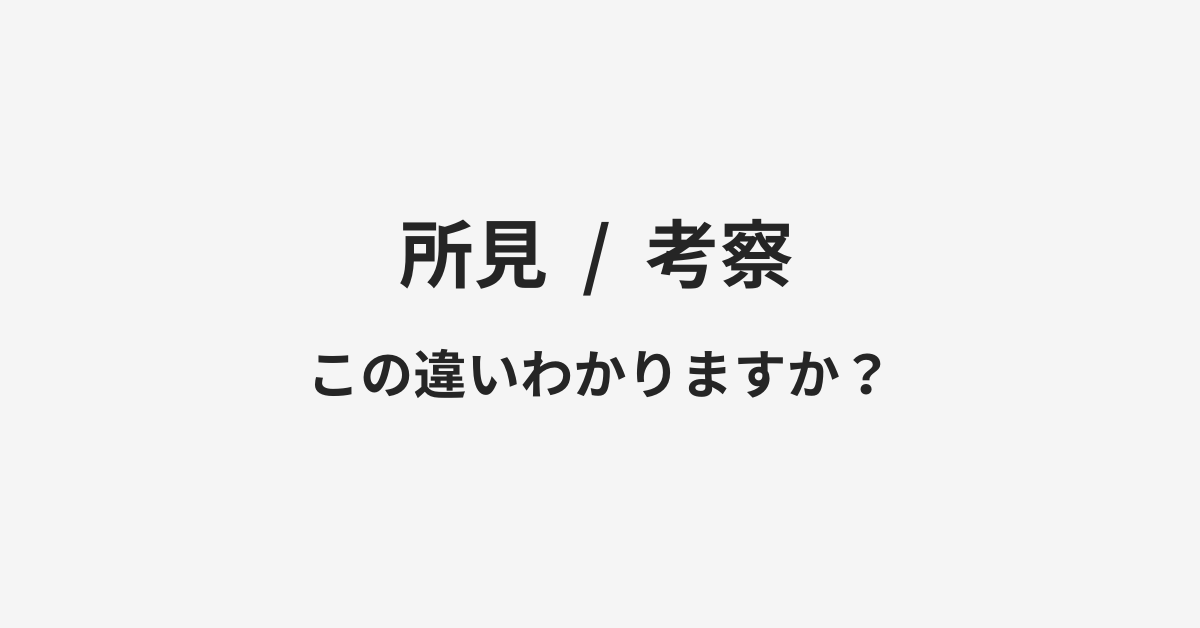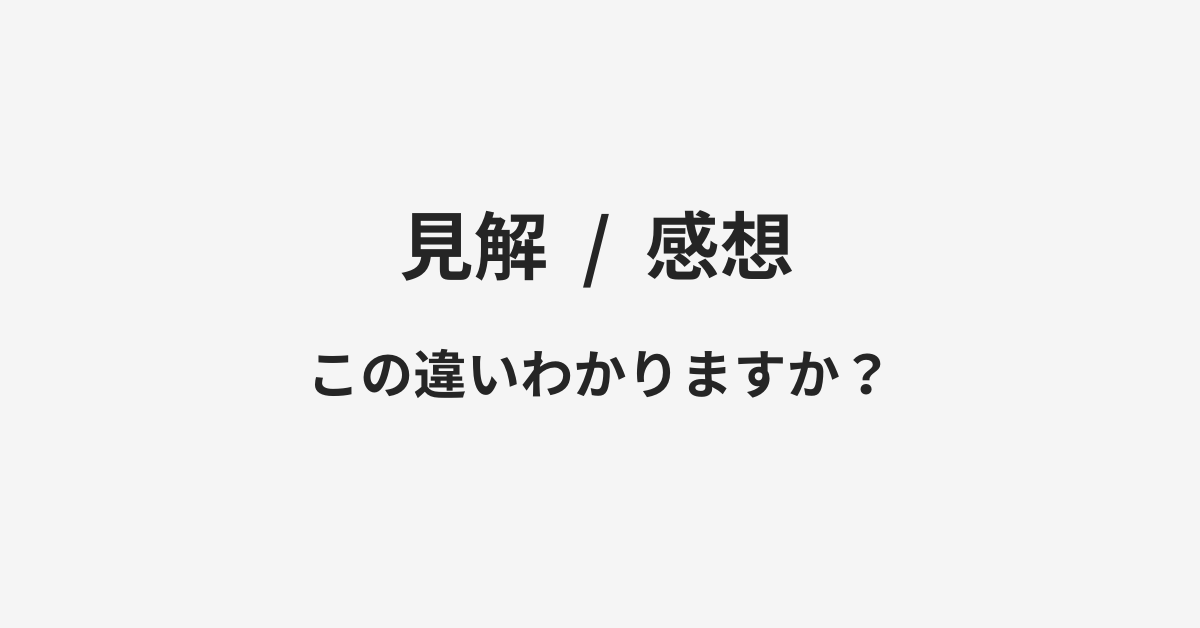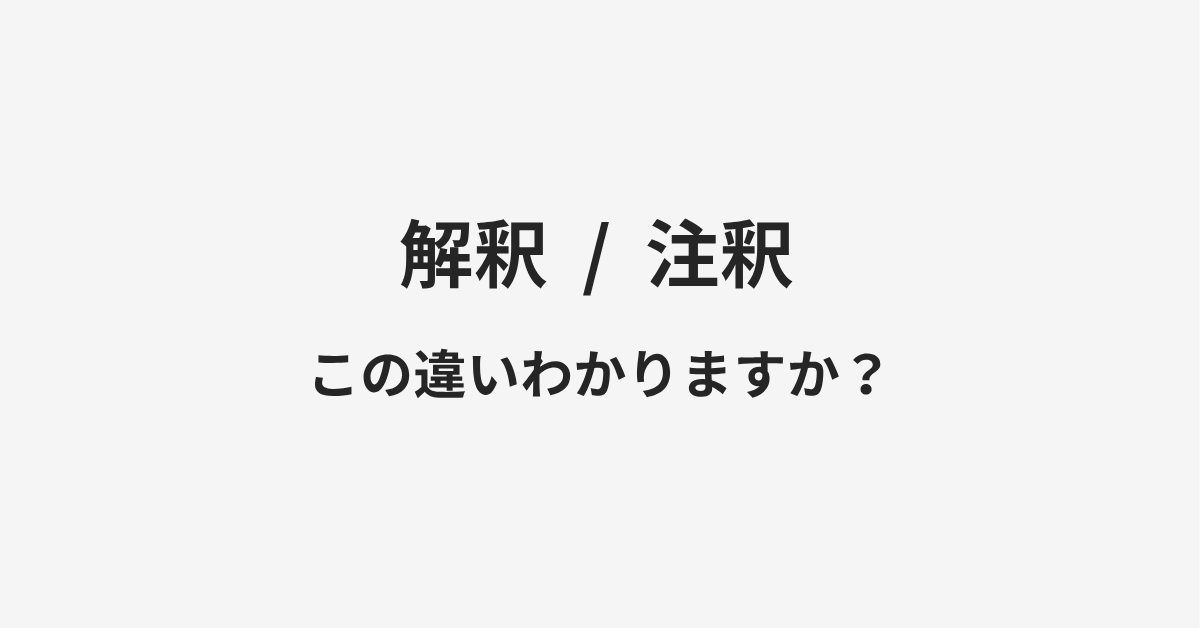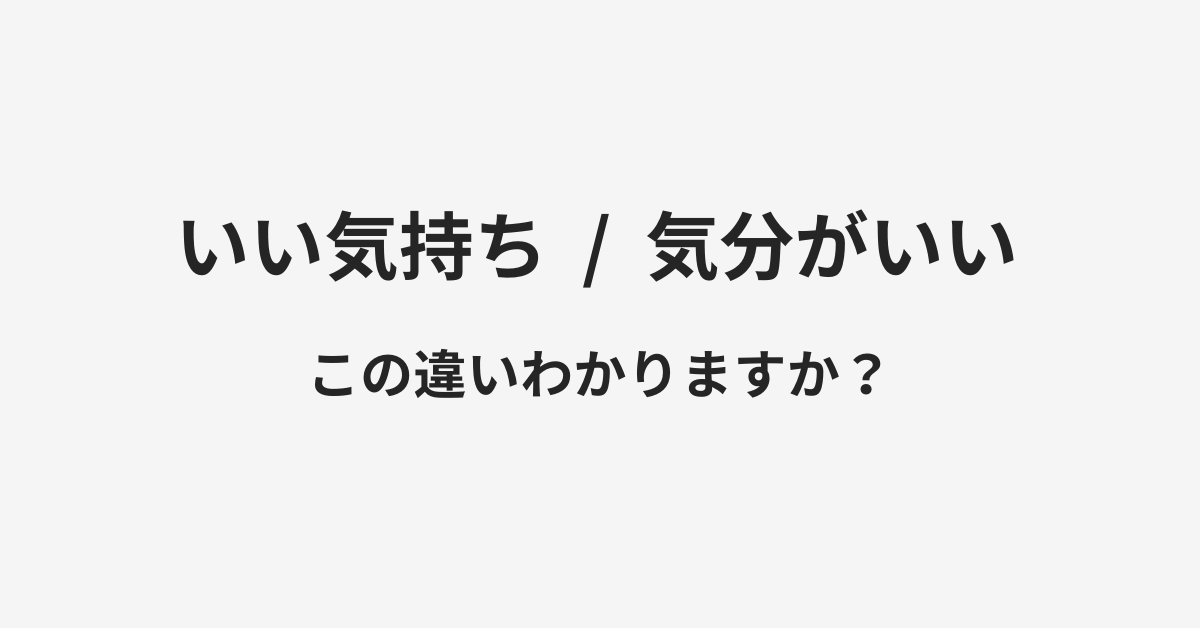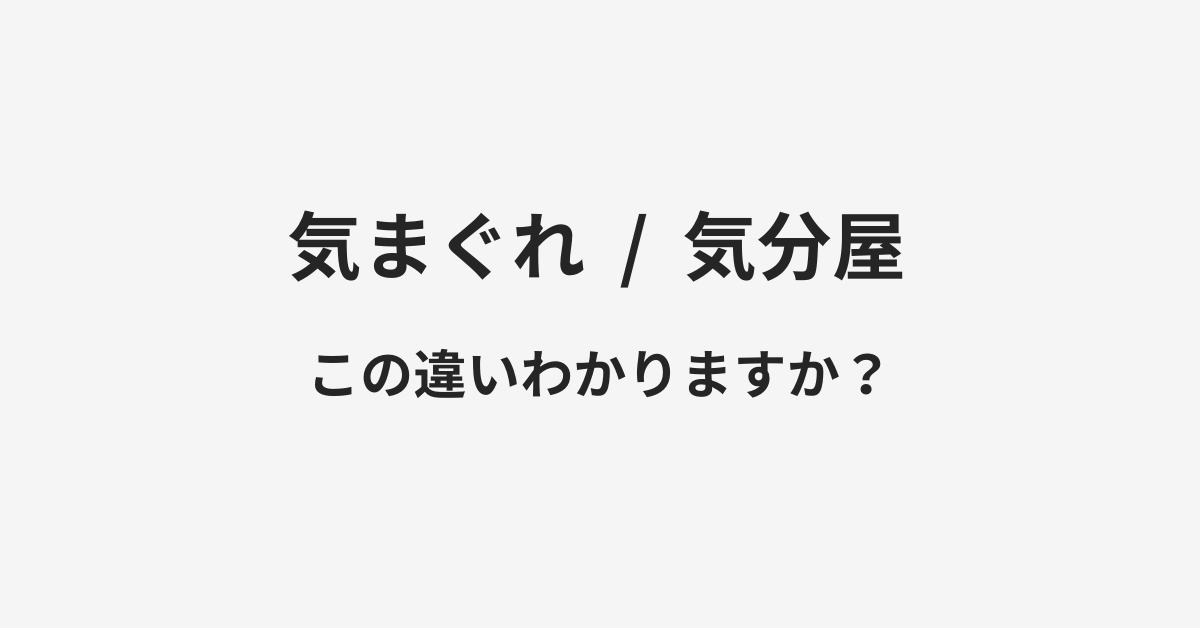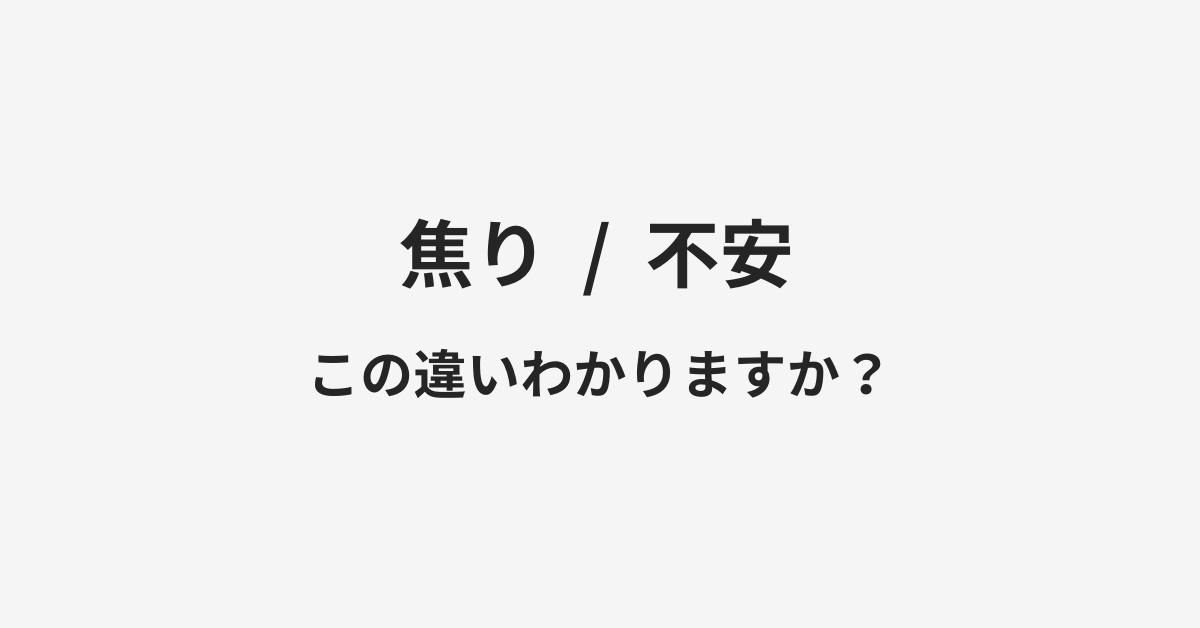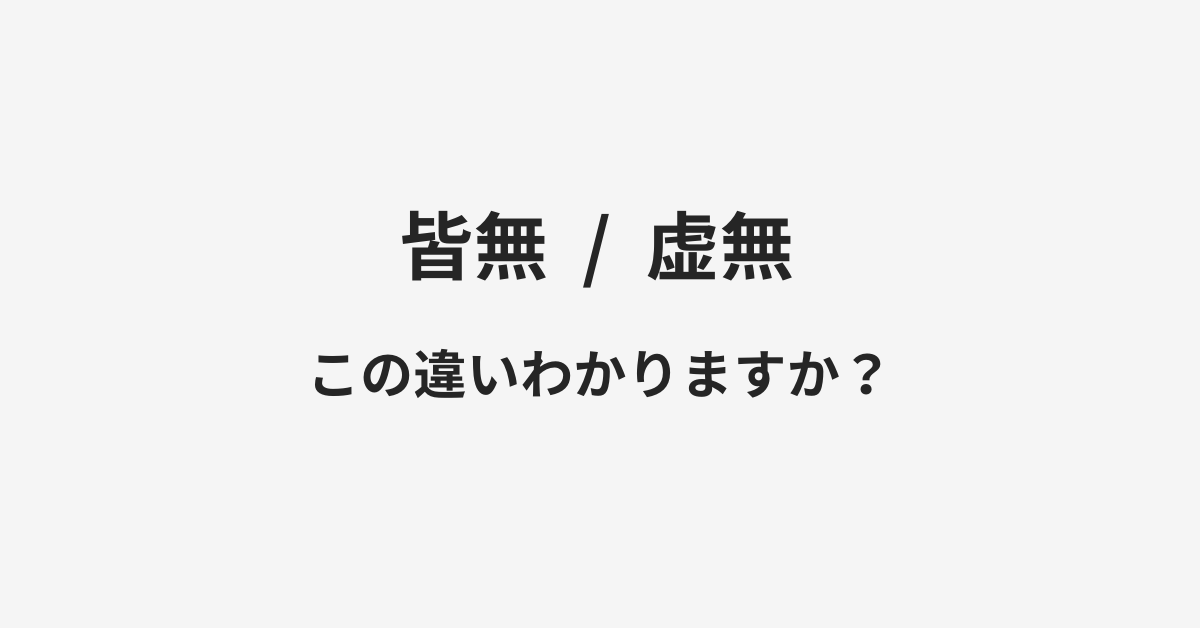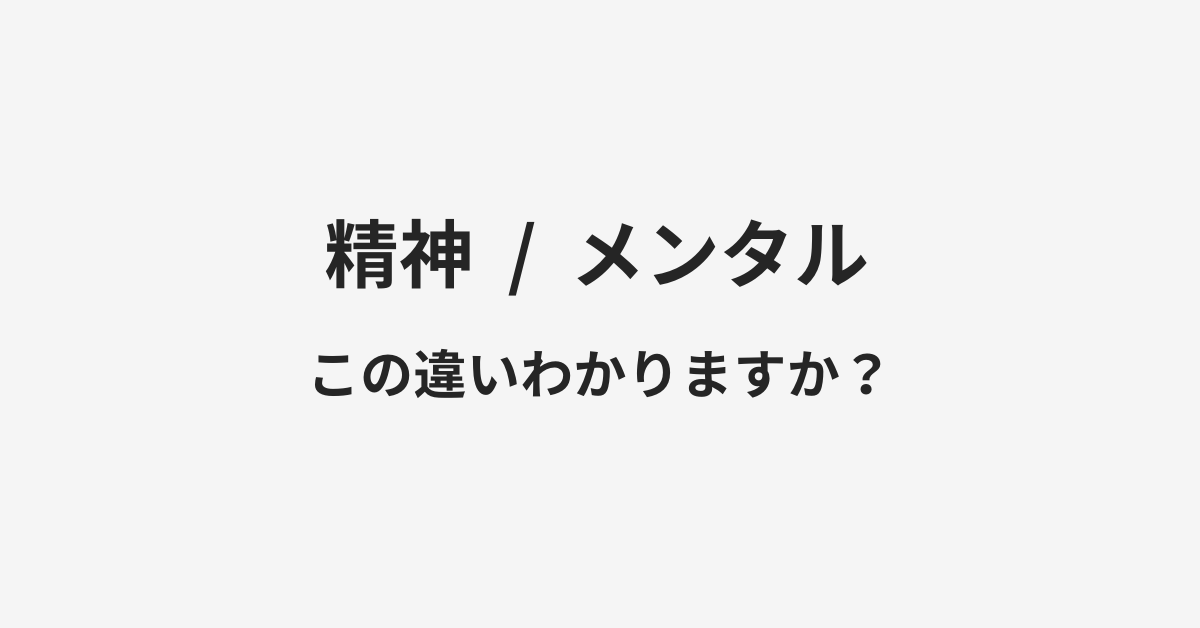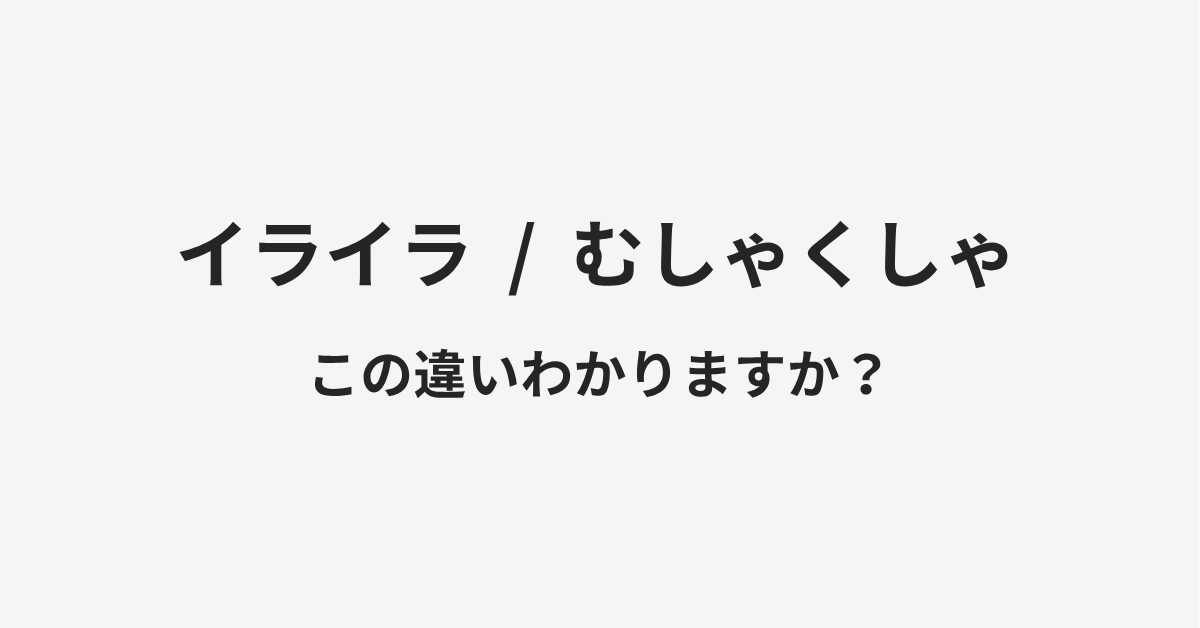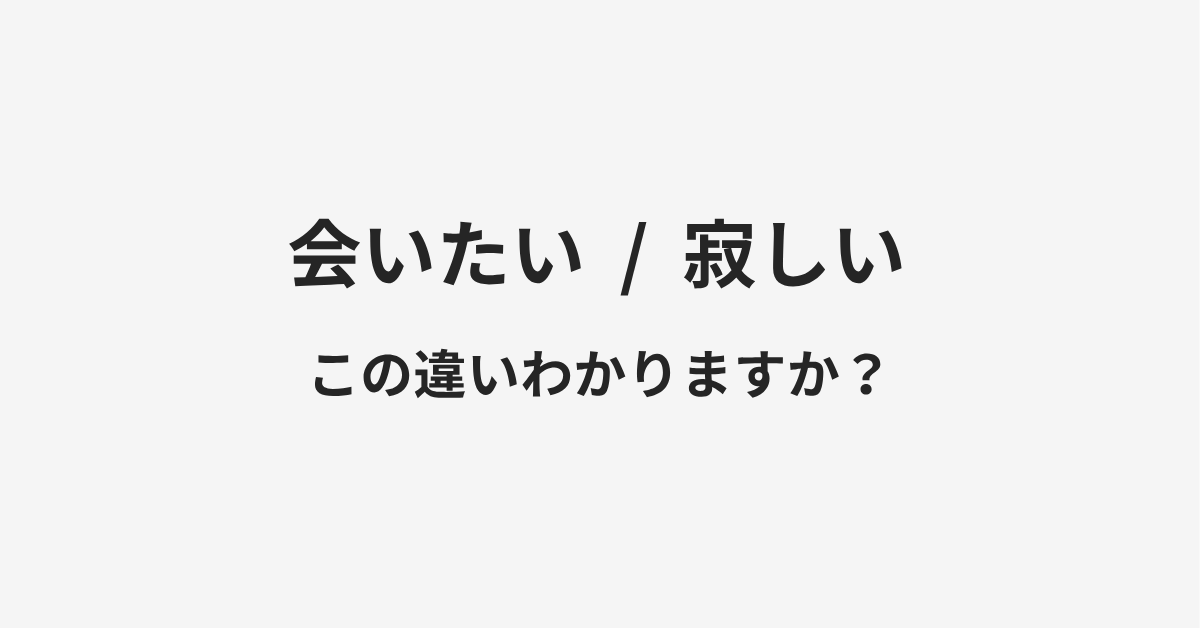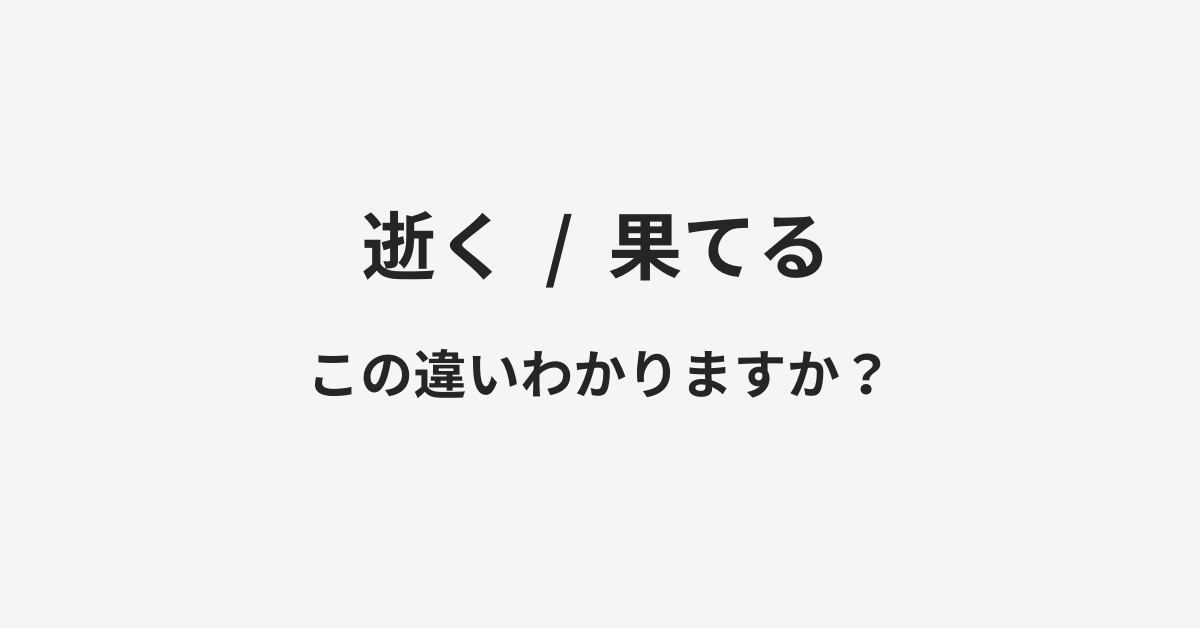【反省】と【教訓】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

反省と教訓の分かりやすい違い
反省と教訓は、どちらも過去の経験から学ぶことですが、その性質と方向性が異なります。
反省は過去の行動や判断を振り返り、悔いや自責の念を含む内省的な行為です。一方、教訓は経験から得た学びを将来に活かすための知恵や指針です。
メンタルヘルスでは、反省を教訓に変換することで、自己批判から建設的な成長へとシフトし、心の健康を保つことができます。
反省とは?
反省とは、自分の過去の行動、言動、判断を振り返り、その是非を考える内省的な行為です。多くの場合、「もっとこうすればよかった」という後悔や自責の念を伴います。自己批判的な要素が強く、感情的な側面が大きいのが特徴です。
心理学的には、適度な反省は自己認識を深め、行動修正につながる重要なプロセスです。しかし、過度な反省は反芻思考となり、うつや不安の原因となることがあります。特に完璧主義的な傾向がある人は、些細なことでも深く反省しすぎて、自己肯定感を低下させてしまう傾向があります。
メンタルヘルスの観点から、反省は「適度」であることが重要です。自分の行動を客観的に振り返ることは大切ですが、自己批判に終始せず、次にどうするかという建設的な方向に意識を向けることが、心の健康を保つ上で必要です。
反省の例文
- ( 1 ) 昨夜の行動を深く反省し、家族に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
- ( 2 ) ストレスで感情的になってしまったことを反省し、カウンセリングを受けることにしました。
- ( 3 ) 自分の完璧主義的な態度を反省し、もっと柔軟になる必要があると気づきました。
- ( 4 ) 過去の対人関係での失敗を反省しすぎて、新しい関係を築くのが怖くなってしまいました。
- ( 5 ) 仕事でのミスを何度も反省し、眠れない夜が続いています。
- ( 6 ) 反省ばかりしていた自分に気づき、前を向く努力を始めました。
反省の会話例
教訓とは?
教訓とは、経験や出来事から学んだ、将来に活かすべき知恵や指針を指します。失敗や成功から抽出された普遍的な学びであり、同じ過ちを繰り返さないため、またはより良い結果を得るための指標となります。感情よりも理性的な側面が強く、実践的な性格を持ちます。
心理学的に見ると、教訓を得ることは認知的な成長プロセスです。経験を抽象化し、一般化することで、新しい状況にも応用できる知識として定着させます。これは適応的な学習の一形態であり、レジリエンス(回復力)を高める重要な要素となります。
メンタルヘルスにおいて、経験を教訓として捉えることは、トラウマや失敗からの回復に重要な役割を果たします。辛い経験も「学び」として再構成することで、その経験に新たな意味を見出し、成長の糧とすることができます。これは認知行動療法でも用いられるリフレーミングの技法と関連しています。
教訓の例文
- ( 1 ) 失敗から得た教訓は、無理をしすぎないことの大切さでした。
- ( 2 ) うつ病の経験から、早めに助けを求めることの重要性という教訓を得ました。
- ( 3 ) 人間関係のトラブルから、境界線を引くことの必要性という教訓を学びました。
- ( 4 ) パニック発作の経験が、ストレス管理の重要性という教訓になりました。
- ( 5 ) 過去の依存症から、自己ケアを優先することの大切さという教訓を得ました。
- ( 6 ) カウンセリングを通じて、感情を抑圧しないという大切な教訓を学びました。
教訓の会話例
反省と教訓の違いまとめ
反省と教訓の最大の違いは、時間軸と感情の質にあります。反省は過去に向かう自己批判的な感情、教訓は未来に向かう建設的な知恵です。
メンタルヘルスの維持には、反省を適度に行い、それを教訓に昇華させることが重要です。過度な反省は心の負担となりますが、教訓として整理することで前向きな力に変換できます。
健康的な心の在り方は、失敗や過ちを責め続けるのではなく、そこから学びを得て成長することにあります。
反省と教訓の読み方
- 反省(ひらがな):はんせい
- 反省(ローマ字):hannsei
- 教訓(ひらがな):きょうくん
- 教訓(ローマ字):kyoukunn