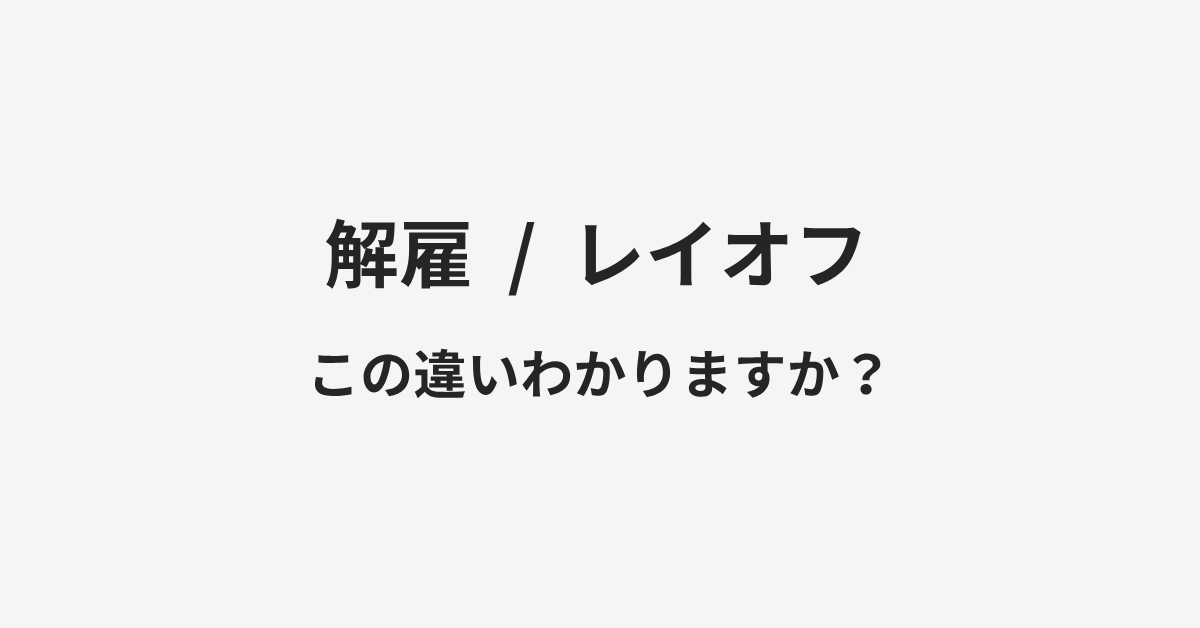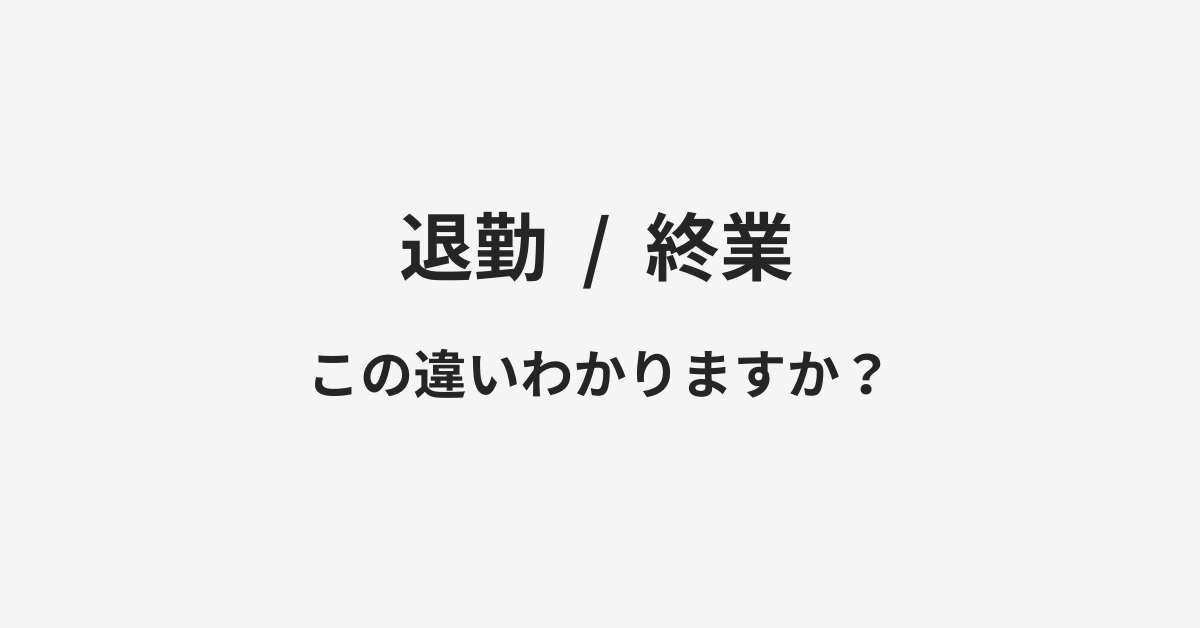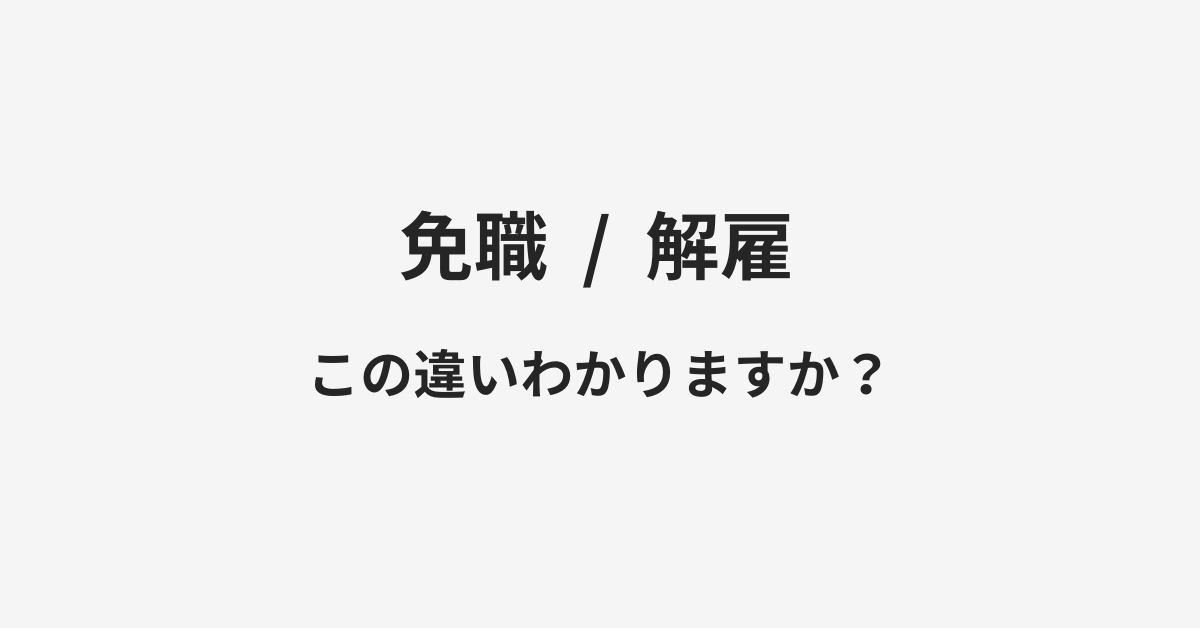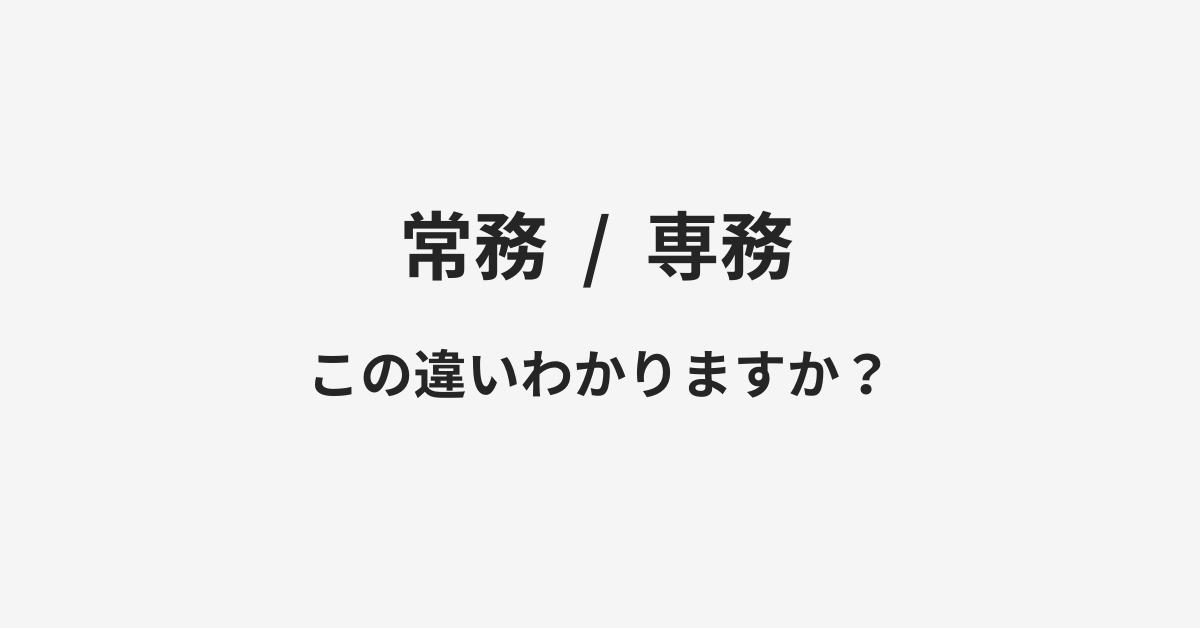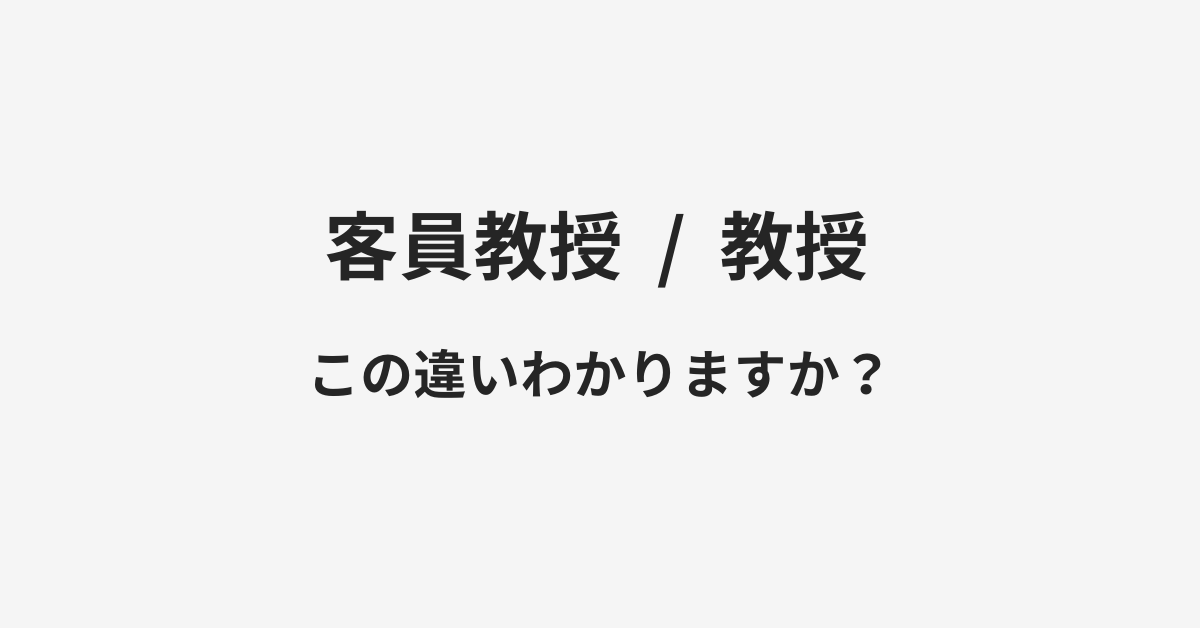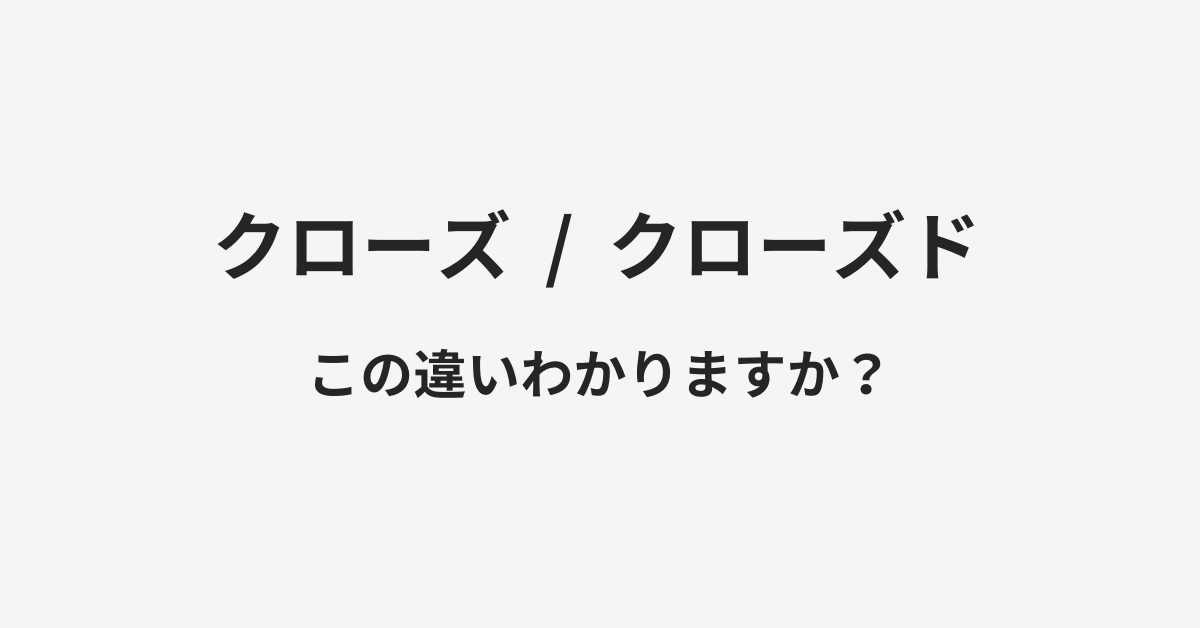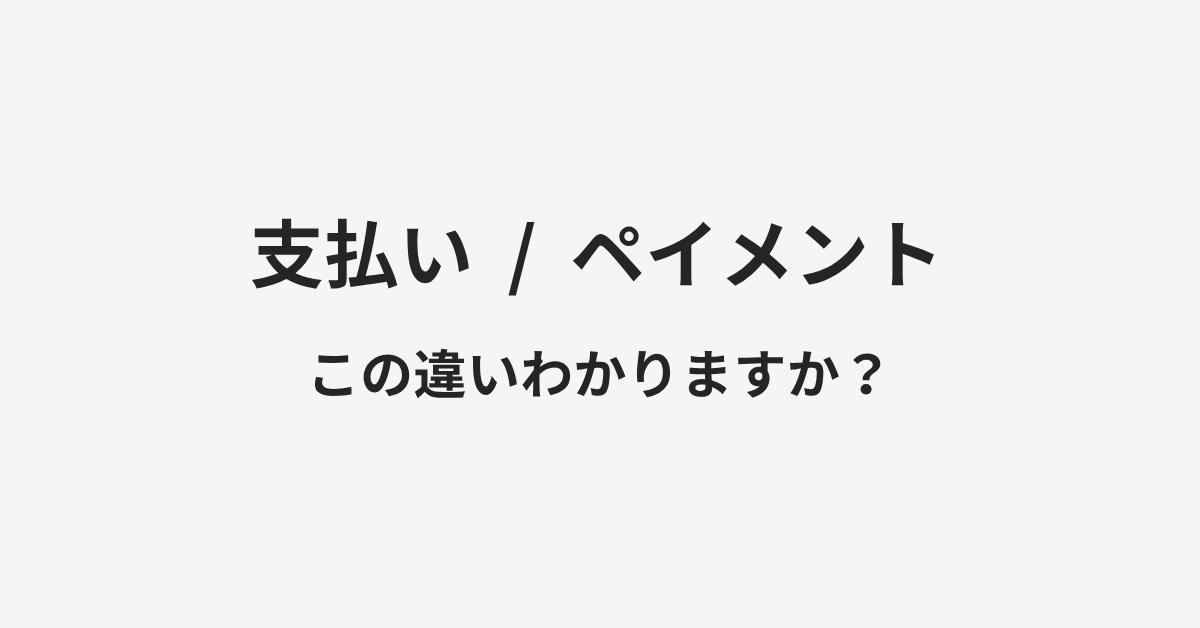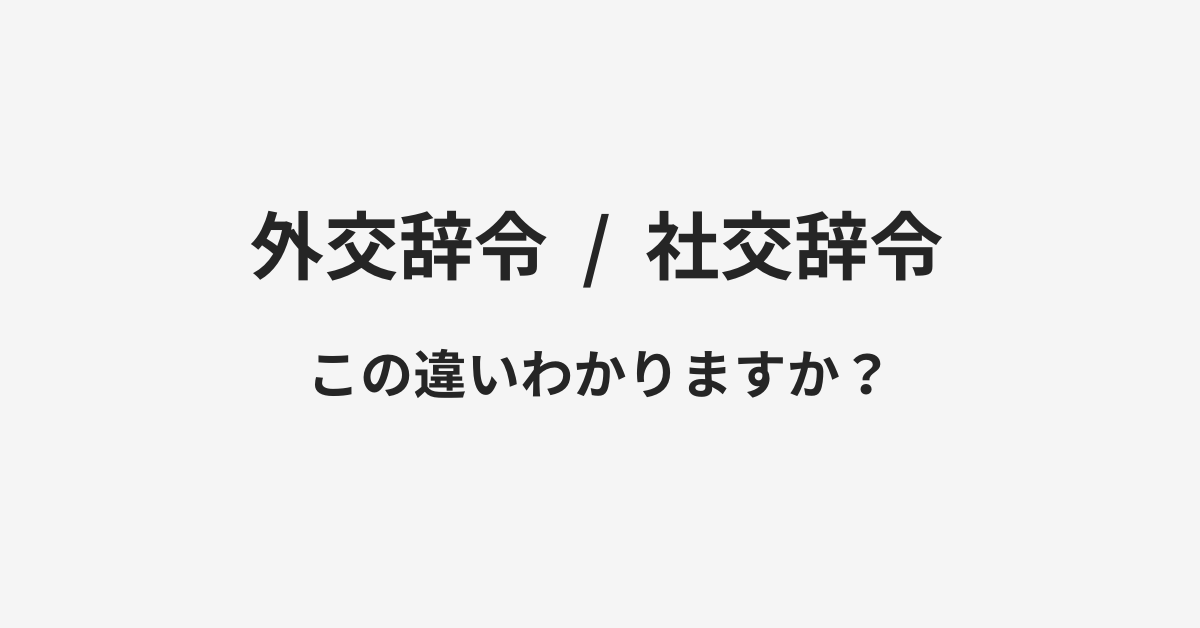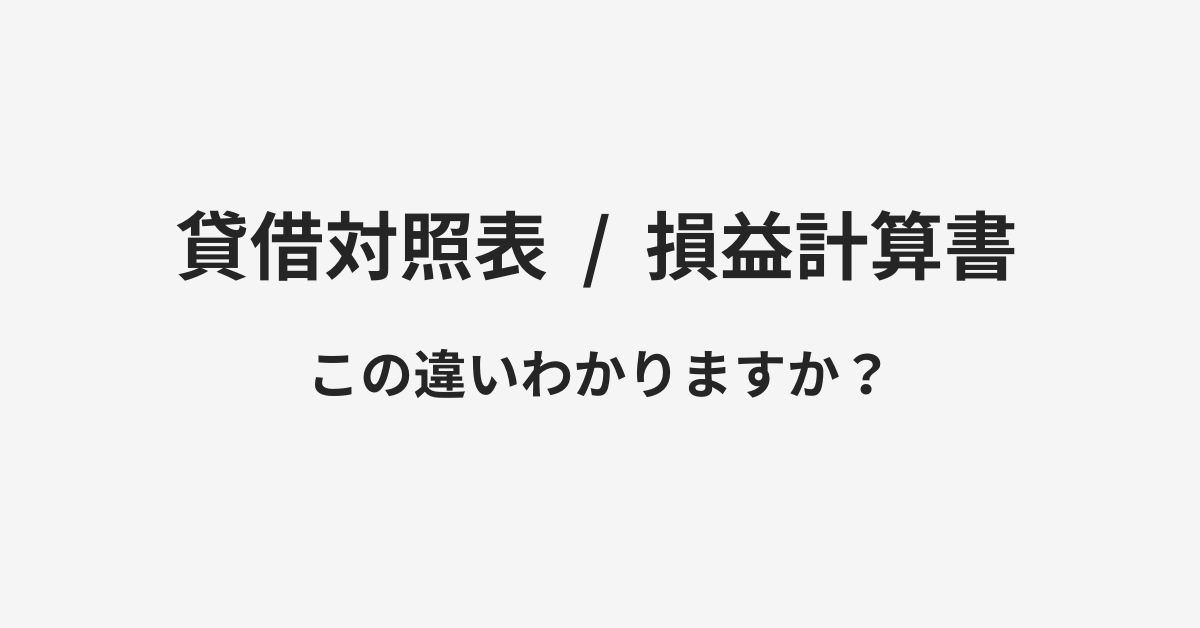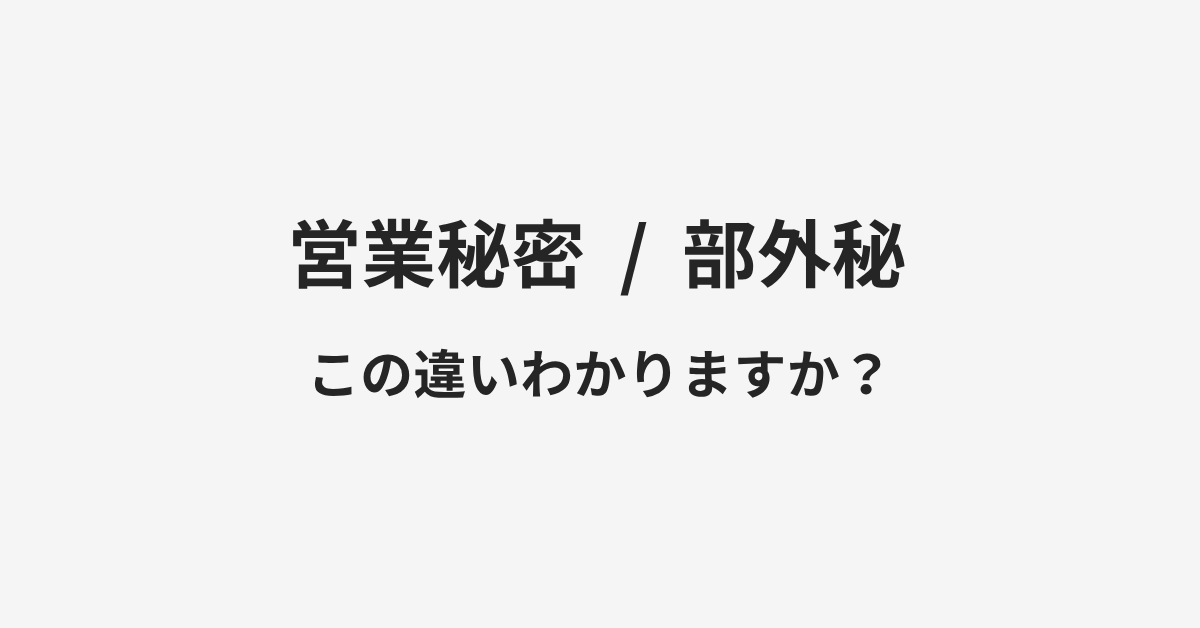【雇い止め】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
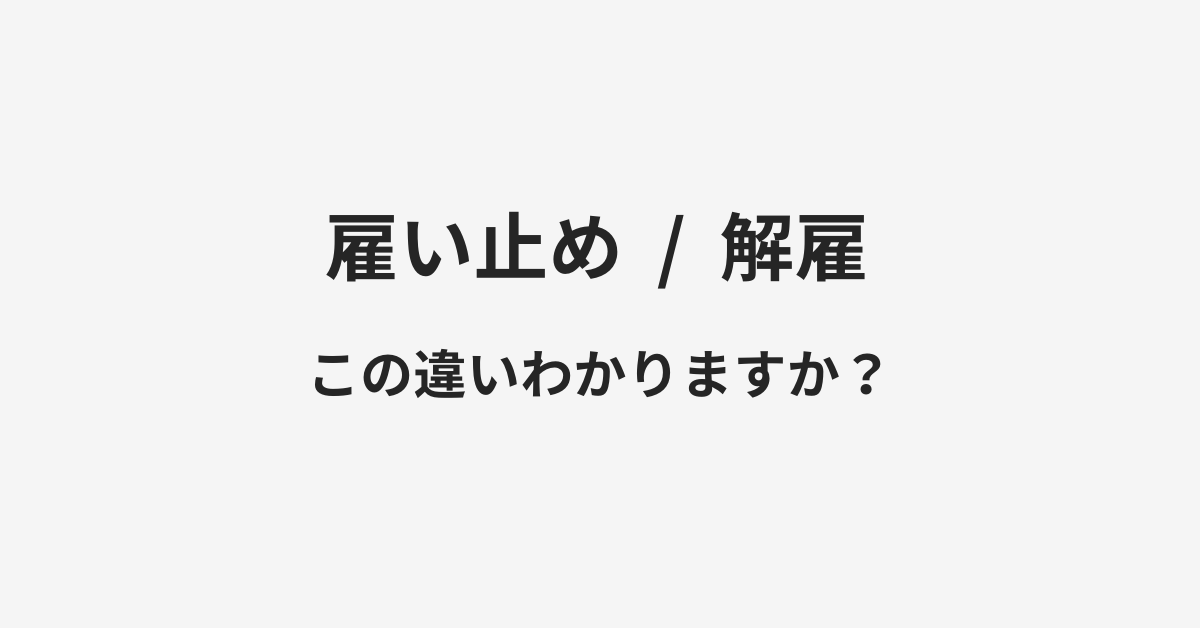
雇い止めと解雇の分かりやすい違い
雇い止めと解雇は、どちらも仕事を失うことですが、やめさせ方が違います。雇い止めは、期限のある契約が終わったときに更新しないことです。
解雇は、契約期間の途中で会社が一方的にやめさせることです。
雇い止めは契約切れ、解雇はクビというイメージで覚えると分かりやすいでしょう。
雇い止めとは?
雇い止めとは、有期労働契約(契約社員、パート、アルバイトなど)において、契約期間満了時に契約を更新しないことを指します。法的には契約の自然終了ですが、何度も更新されていた場合は、労働者保護の観点から制限があります。
雇い止めには合理的な理由が必要な場合があり、特に5年を超えて反復更新されている場合や、更新への合理的期待がある場合は、解雇と同様の規制を受けます。30日前の予告や雇い止め理由の明示が求められることもあります。
2013年の労働契約法改正により、5年を超えて更新された有期契約労働者は、無期転換申込権を得られるようになりました。これにより、安易な雇い止めは困難になっています。
雇い止めの例文
- ( 1 ) 契約期間満了により、今回は雇い止めとさせていただきます。
- ( 2 ) 5年を超える前に雇い止めすることで、無期転換を回避しています。
- ( 3 ) 雇い止めの合理的理由を説明し、労働者の理解を得ました。
- ( 4 ) 雇い止め予告を30日前に行い、法的要件を満たしています。
- ( 5 ) 不当な雇い止めとして、労働審判を申し立てられました。
- ( 6 ) 雇い止め後の失業保険について、説明会を開催しました。
雇い止めの会話例
解雇とは?
解雇とは、使用者が労働契約を一方的に終了させることで、労働者にとって最も厳しい処分です。普通解雇、整理解雇(リストラ)、懲戒解雇の3種類があり、それぞれ要件が異なります。日本では解雇規制が厳しく、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
解雇には30日前の予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが義務付けられています(懲戒解雇で労基署の認定を受けた場合を除く)。不当解雇と判断されれば、職場復帰や損害賠償を求められます。
整理解雇では、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続きの妥当性の4要件を満たす必要があります。安易な解雇は企業の信用失墜にもつながるため、慎重な判断が求められます。
解雇の例文
- ( 1 ) 業績不振により、やむを得ず5名を解雇することになりました。
- ( 2 ) 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払いました。
- ( 3 ) 懲戒解雇処分について、顧問弁護士と慎重に検討しています。
- ( 4 ) 解雇回避努力として、希望退職者の募集から始めました。
- ( 5 ) 不当解雇で訴えられ、多額の賠償金支払いを命じられました。
- ( 6 ) 解雇権濫用にならないよう、段階的な指導記録を残しています。
解雇の会話例
雇い止めと解雇の違いまとめ
雇い止めと解雇の最大の違いは、契約終了のタイミングと法的性質です。雇い止めは期間満了での不更新、解雇は期間中の強制終了です。
法的保護の程度も異なり、解雇はより厳格な要件が必要ですが、実質的に期待権がある雇い止めは解雇に準じた扱いを受けます。
どちらも労働者の生活に大きな影響を与えるため、適法性と配慮が求められます。
雇い止めと解雇の読み方
- 雇い止め(ひらがな):やといどめ
- 雇い止め(ローマ字):yatoidome
- 解雇(ひらがな):かいこ
- 解雇(ローマ字):kaiko