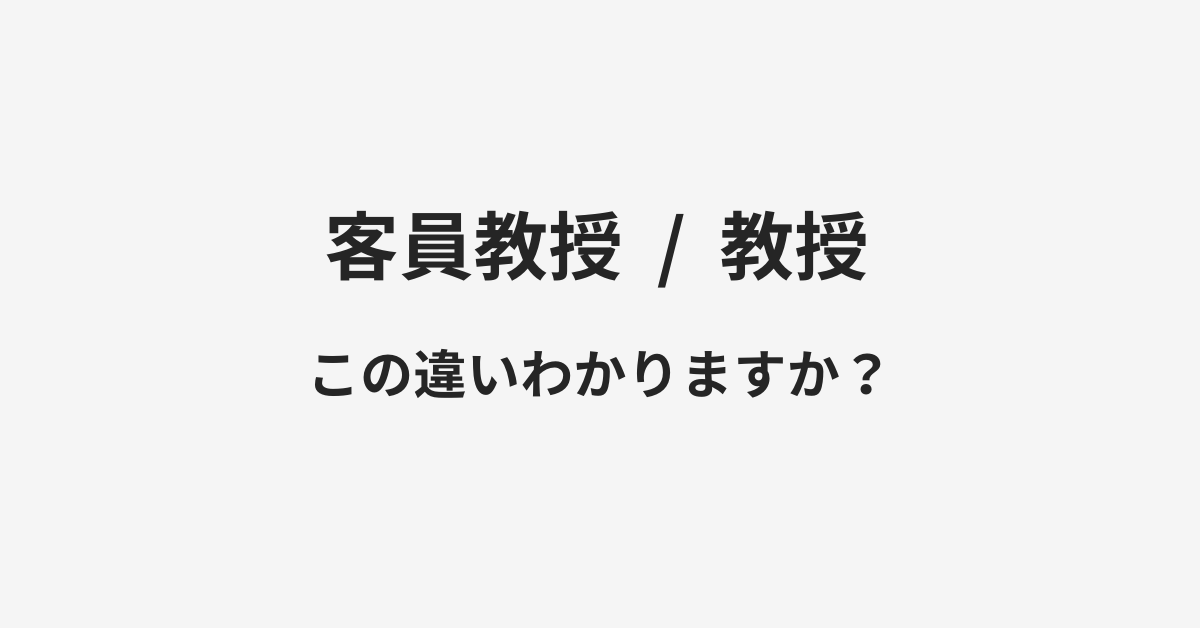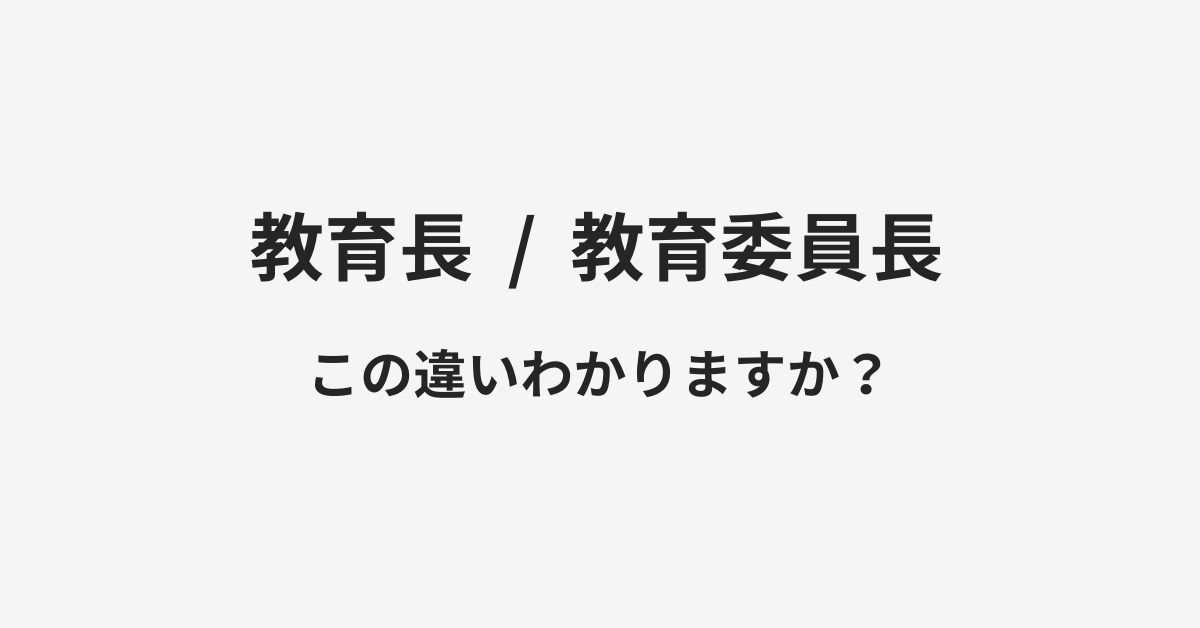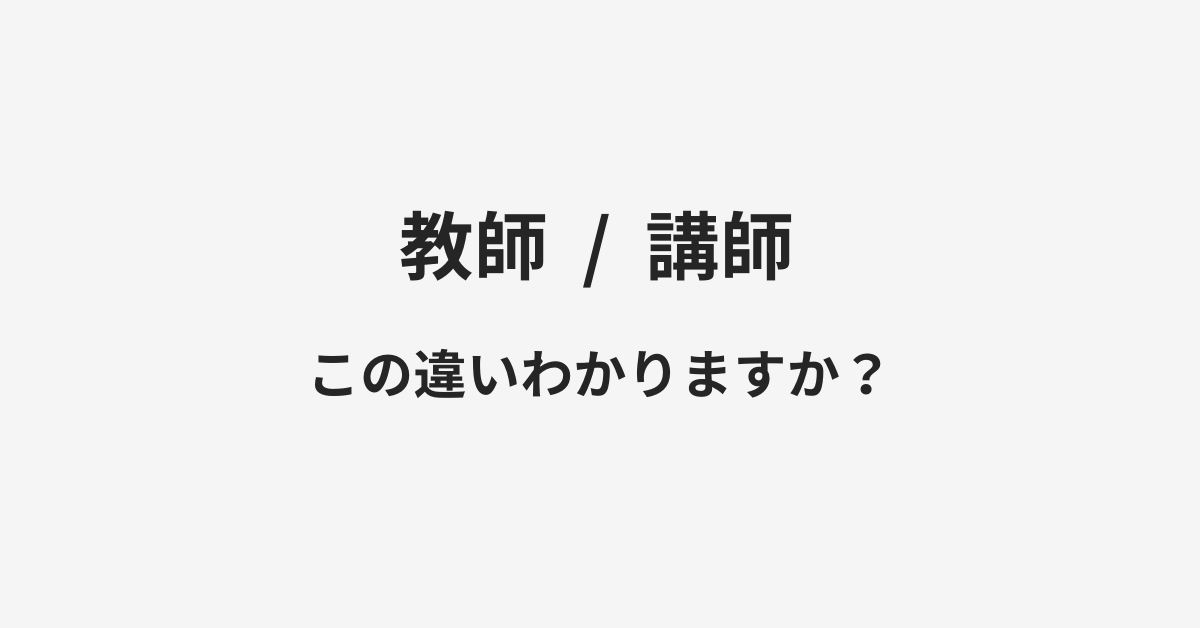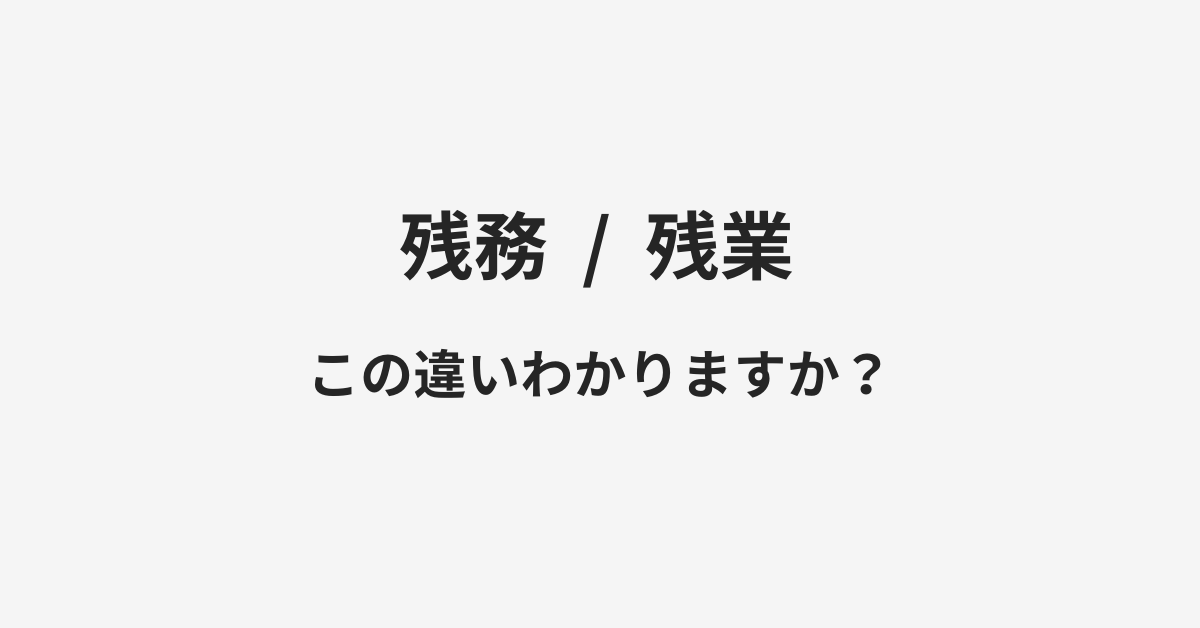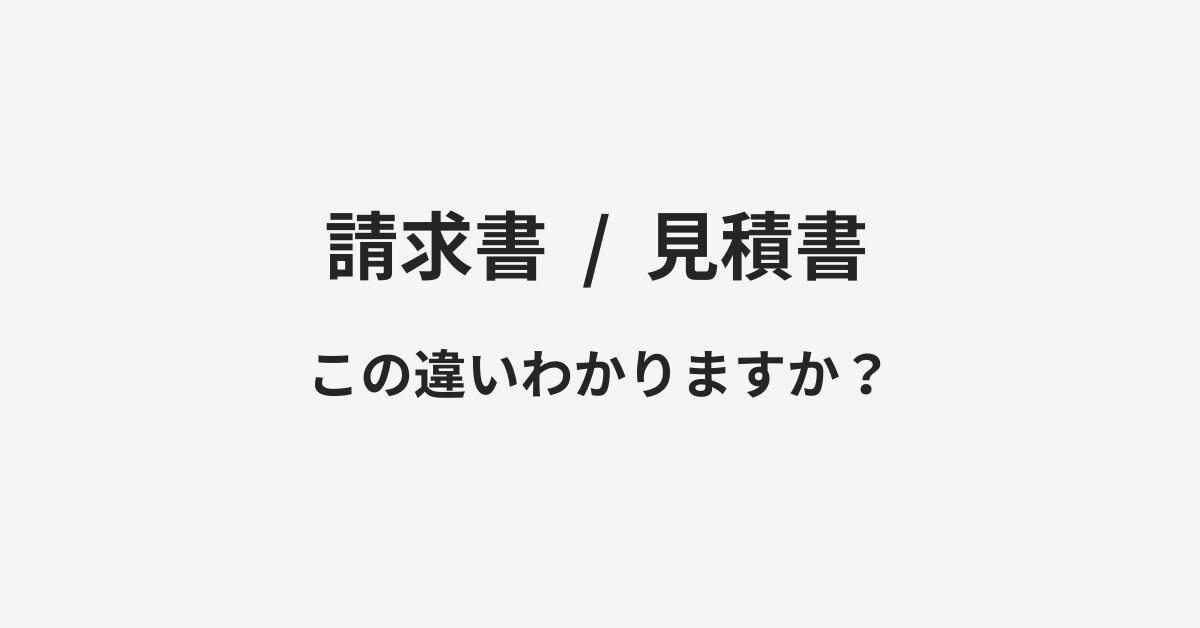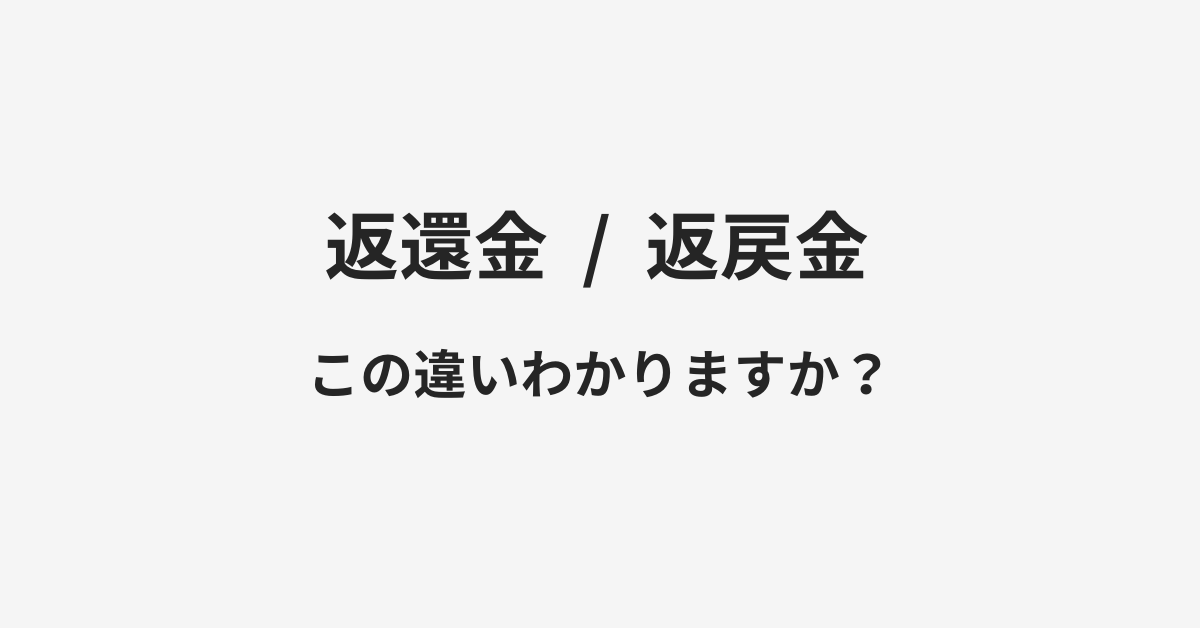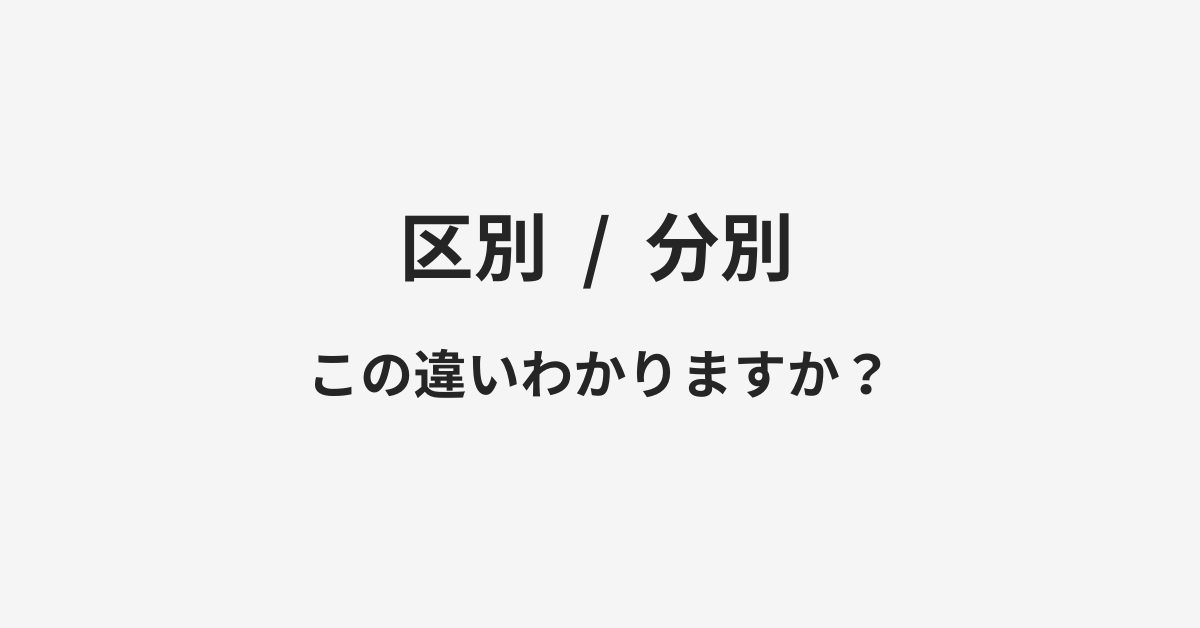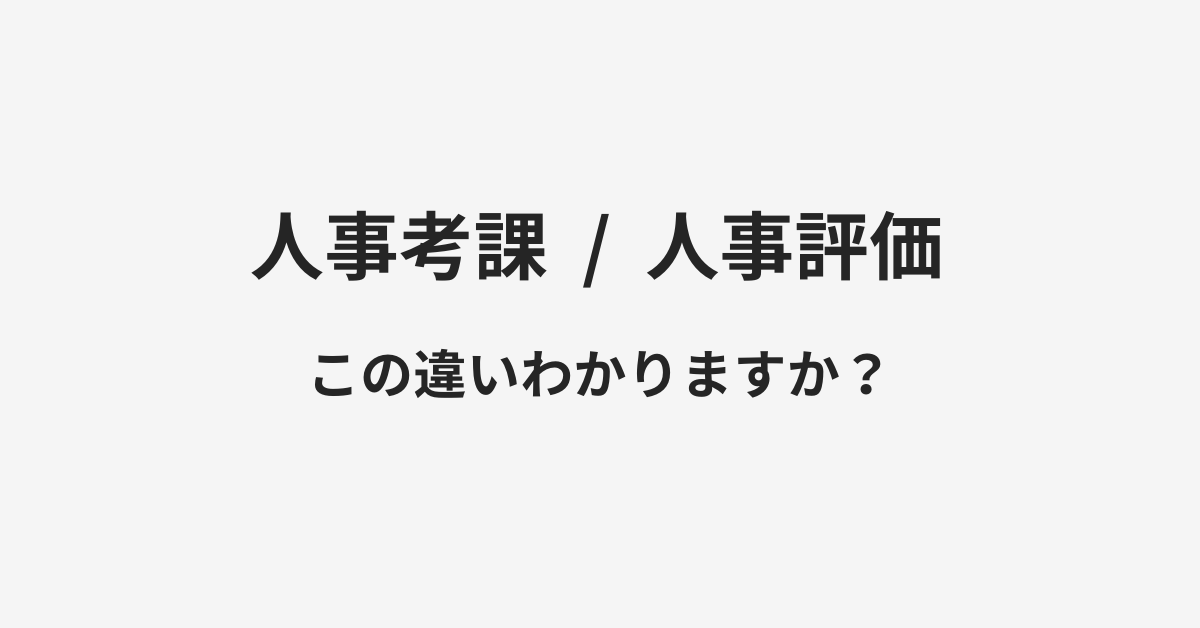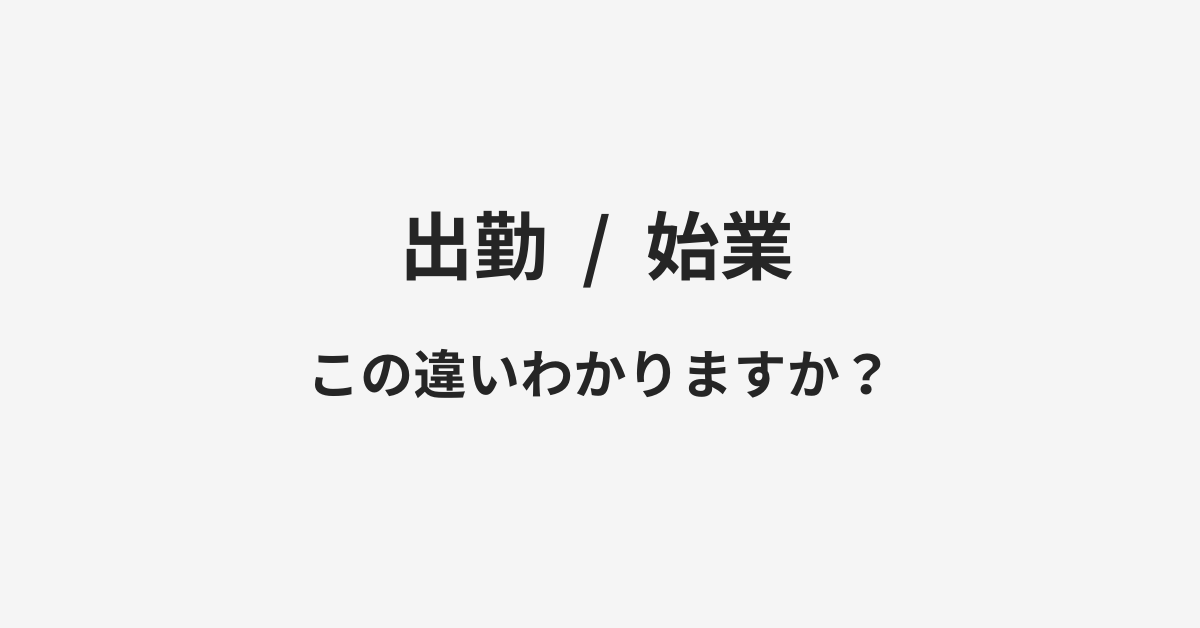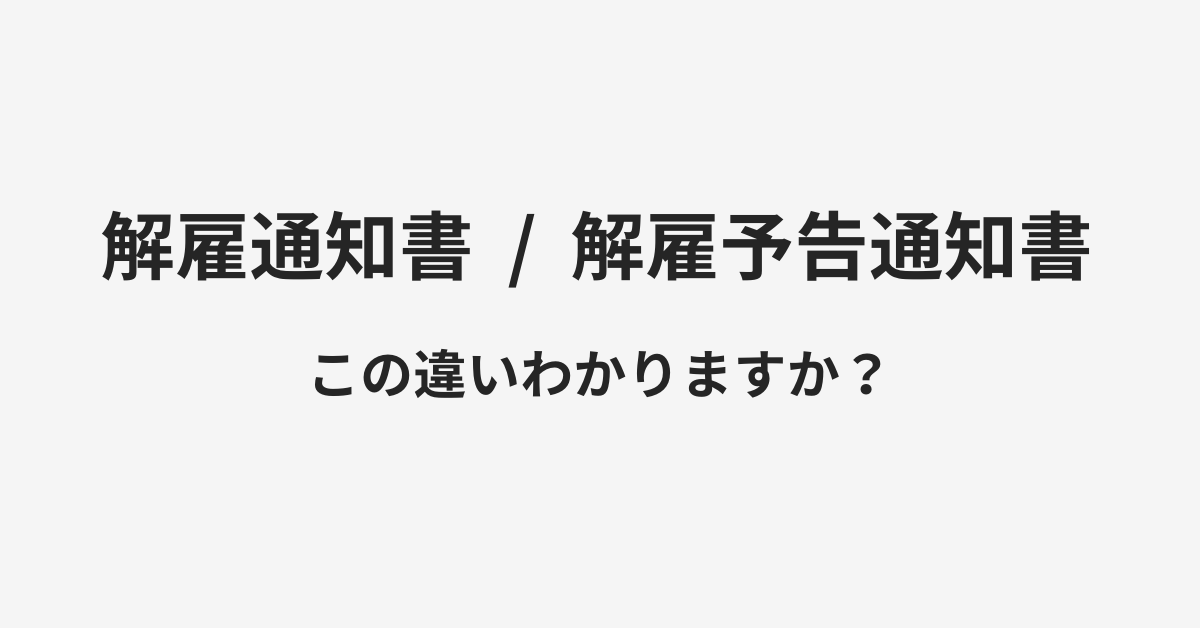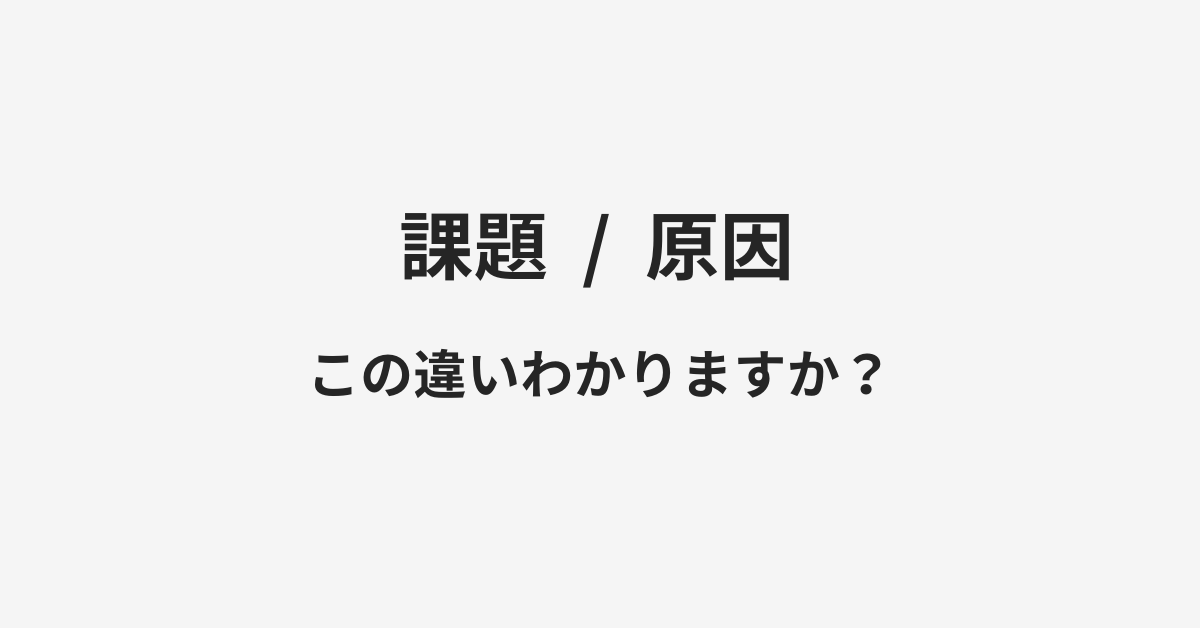【助教授】と【助教】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
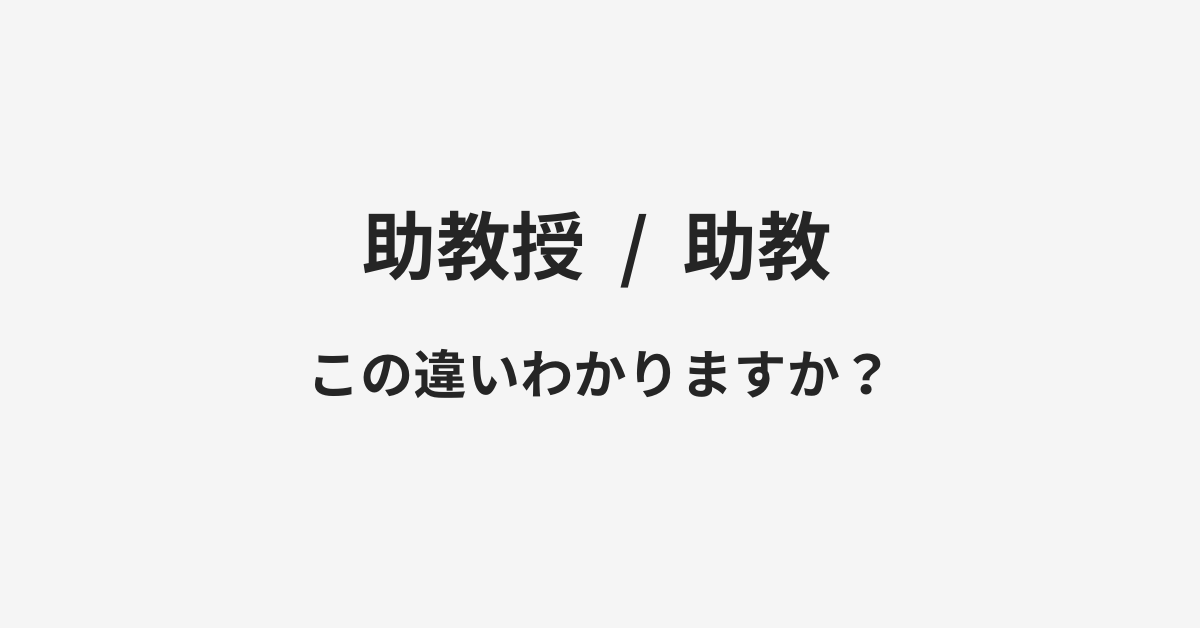
助教授と助教の分かりやすい違い
助教授と助教は、どちらも大学の教員職ですが、制度改正により位置づけが大きく異なります。助教授は2007年3月まで存在した職位で、現在の准教授に相当します。
助教は2007年4月から新設された職位で、従来の助手に相当する若手研究者のポストです。
大学との産学連携や共同研究において、相手の職位を正しく理解することは、適切なコミュニケーションに重要です。
助教授とは?
助教授とは、2007年3月31日まで日本の大学に存在した教員職位で、教授に次ぐ地位でした。学校教育法の改正により廃止され、現在は准教授という名称に変更されています。助教授は独立して研究室を持ち、学生指導や講義を担当する中堅教員として、大学教育の中核を担っていました。英語表記はAssociate Professorでした。
助教授の役割は、教授を補佐しながらも、独自の研究活動と教育活動を行うことでした。博士号取得後、講師を経て助教授に昇進するのが一般的なキャリアパスで、その後教授を目指すという流れが確立されていました。研究費の獲得、論文発表、学会活動など、教授とほぼ同等の責任を負っていました。
名称変更の背景には、国際的な職位の明確化がありました。助という文字が補助的な印象を与えるため、独立した研究者としての地位を明確にする准教授への変更が行われました。現在50代以上の研究者の経歴には助教授の肩書きが残っており、准教授と同等と理解する必要があります。
助教授の例文
- ( 1 ) 父が大学の助教授だった頃の話を聞くと、今とは違う時代を感じます。
- ( 2 ) 履歴書に元助教授と書かれていれば、現在の准教授相当と理解できます。
- ( 3 ) 助教授時代の研究成果が、現在の産学連携の基礎となっています。
- ( 4 ) 当時の助教授は、今の准教授より権限が大きかったように思います。
- ( 5 ) 名誉教授の経歴を見ると、助教授から教授への昇進が記されています。
- ( 6 ) 助教授という呼称がなくなって、もう15年以上経つんですね。
助教授の会話例
助教とは?
助教とは、2007年4月から導入された大学教員の職位で、従来の助手に相当する若手研究者のポストです。博士号取得直後の研究者が最初に就く教員職として位置づけられ、教授、准教授、講師に次ぐ職階となっています。任期付きポストが多く、3〜5年の任期で雇用されることが一般的です。英語表記はAssistant Professorです。
助教の主な職務は、研究活動と教育補助です。自身の研究を進めながら、講義の補助、実験・実習の指導、学生の研究指導補助などを行います。独立した研究室は持たないことが多く、教授や准教授の研究室に所属して活動します。研究資金は、科研費の若手研究などに応募して獲得することが求められます。
企業との関係では、助教は最先端の研究に携わる若手研究者として、共同研究や技術相談の窓口となることがあります。専門性は高いものの、決定権限は限定的なため、重要な案件では上位の教員との連携が必要です。任期制により人材の流動性が高いことも特徴です。
助教の例文
- ( 1 ) 新任の助教として、研究と教育の両立に奮闘しています。
- ( 2 ) 助教のポストを得て、ようやく研究者としてのキャリアをスタートできました。
- ( 3 ) 任期付き助教として3年間の成果が問われるため、プレッシャーを感じています。
- ( 4 ) 助教として企業との共同研究に参画し、実践的な経験を積んでいます。
- ( 5 ) 来年度から助教に昇進することが決まり、準備を進めています。
- ( 6 ) 優秀な助教を採用できたことで、研究室の活性化が図られています。
助教の会話例
助教授と助教の違いまとめ
助教授と助教の最大の違いは、職階と時代です。助教授は准教授相当の中堅ポストでしたが、助教は最下位の若手ポストです。この違いを混同すると、大きな誤解を生む可能性があります。権限と責任も大きく異なり、助教授(現准教授)は独立した研究者として研究室運営が可能でしたが、助教は通常、上位教員の指導下で活動します。
また、助教授は終身雇用が一般的でしたが、助教は任期付きが主流です。
産学連携においては、助教は専門的な技術相談に対応できますが、契約締結などの決定は上位教員が行うことが一般的です。年齢や経験も考慮し、適切なコミュニケーションを図ることが重要です。
助教授と助教の読み方
- 助教授(ひらがな):じょきょうじゅ
- 助教授(ローマ字):jokyouju
- 助教(ひらがな):じょきょう
- 助教(ローマ字):jokyou