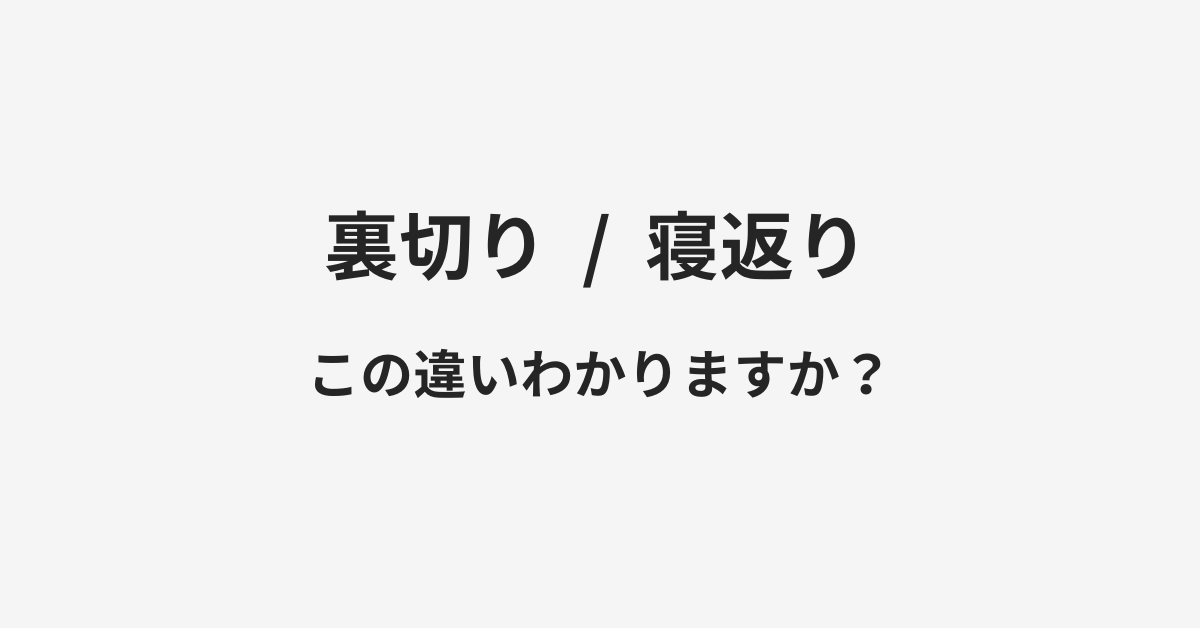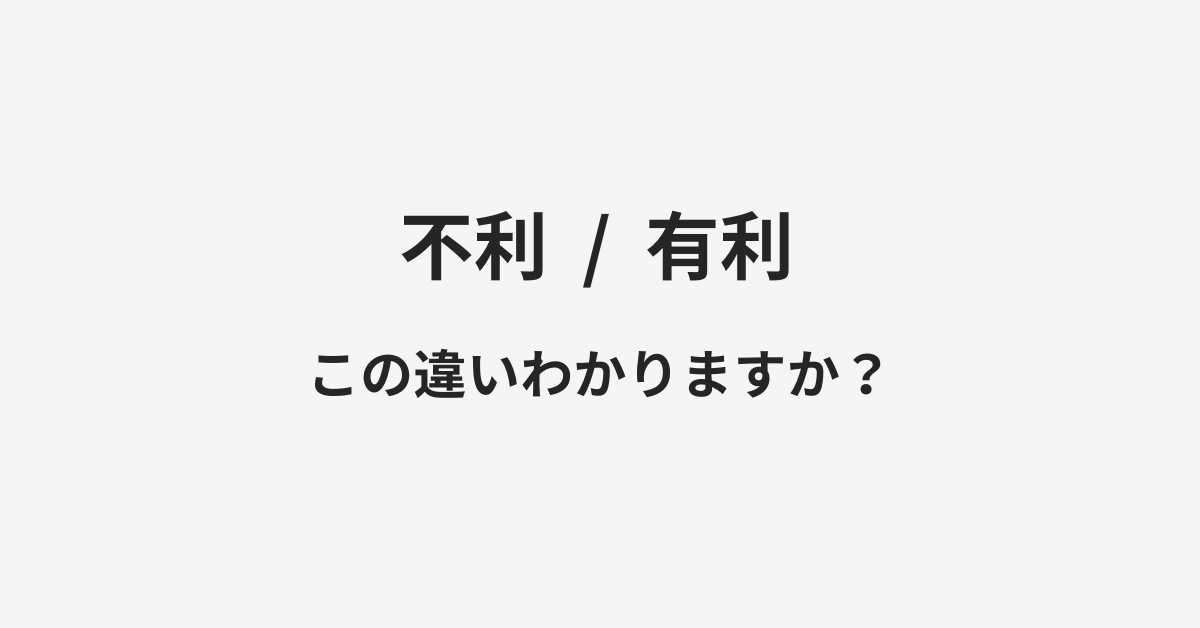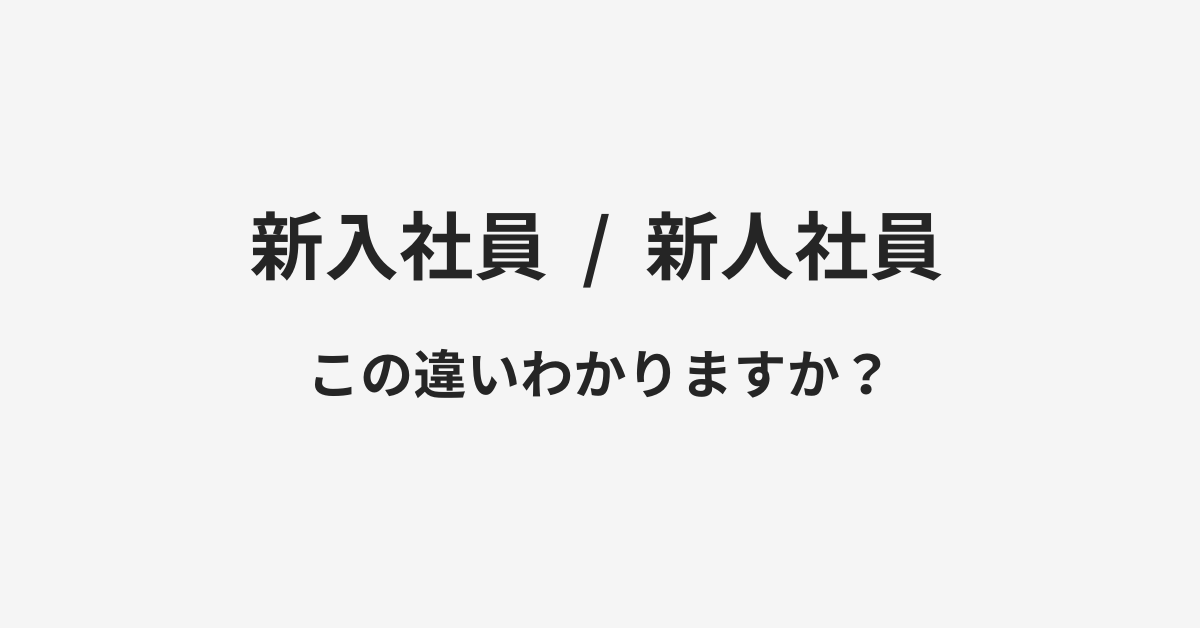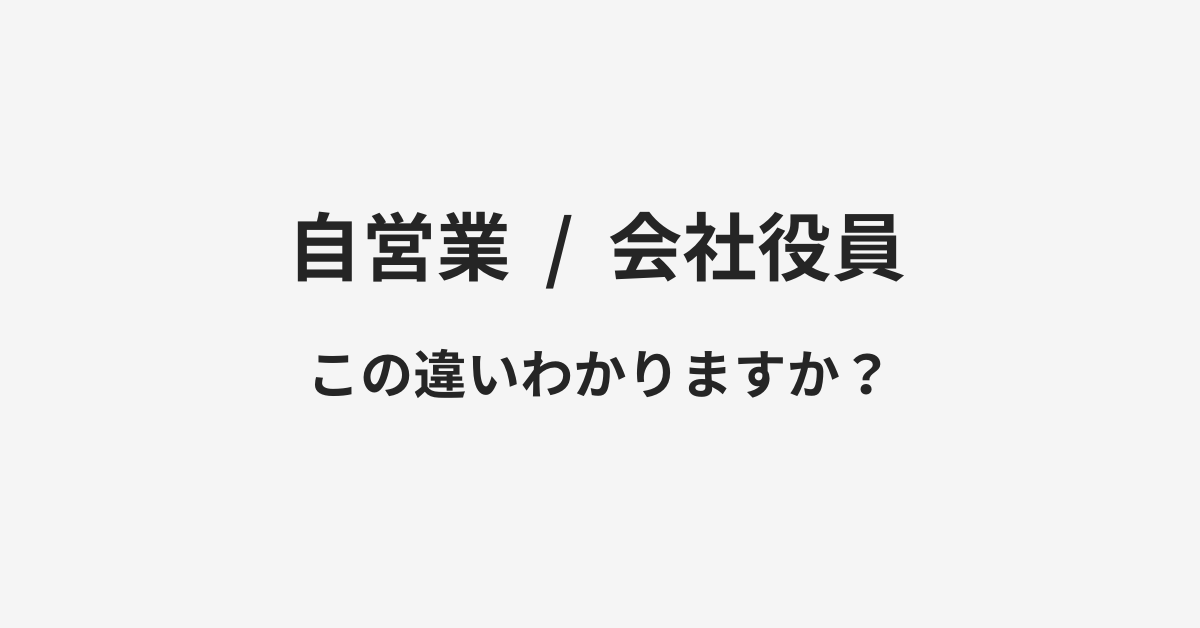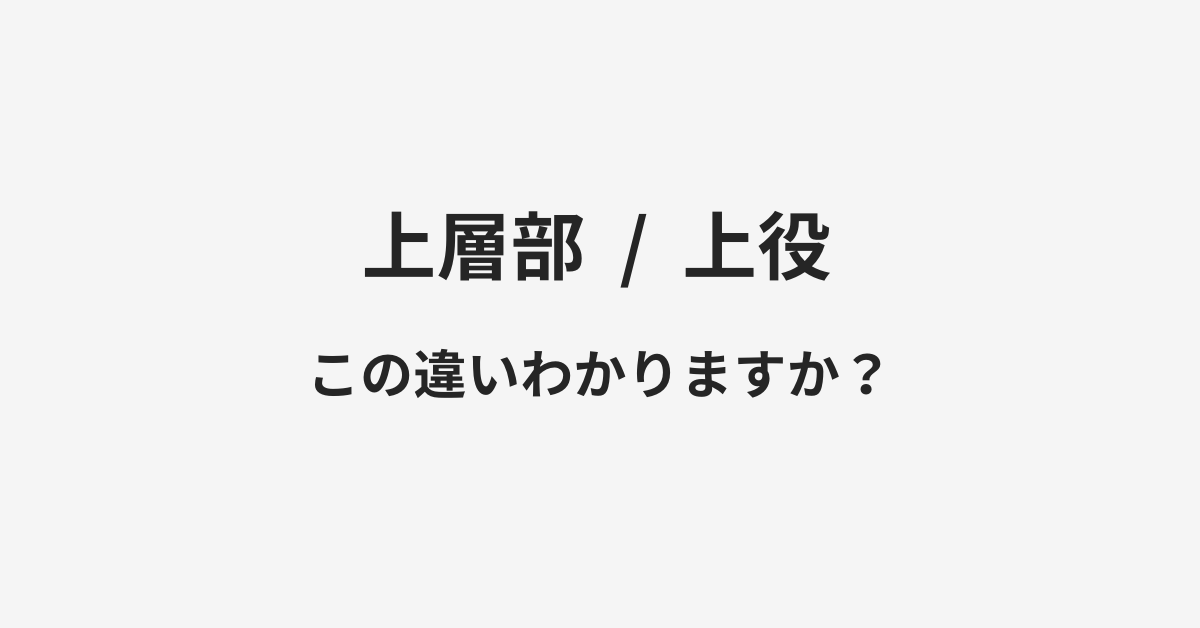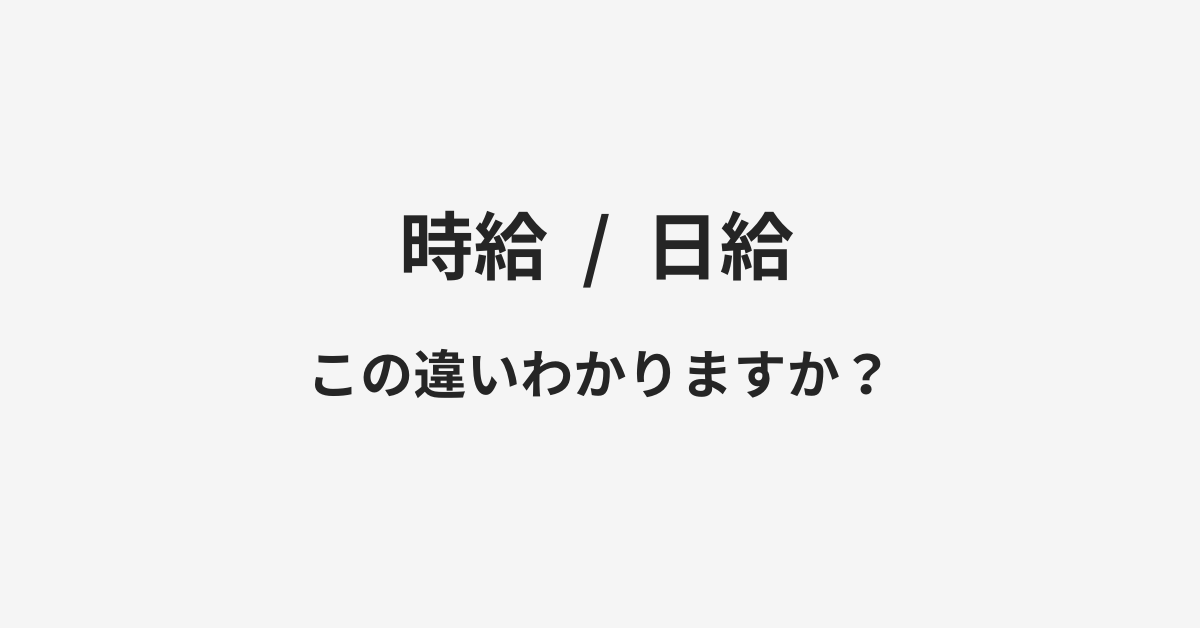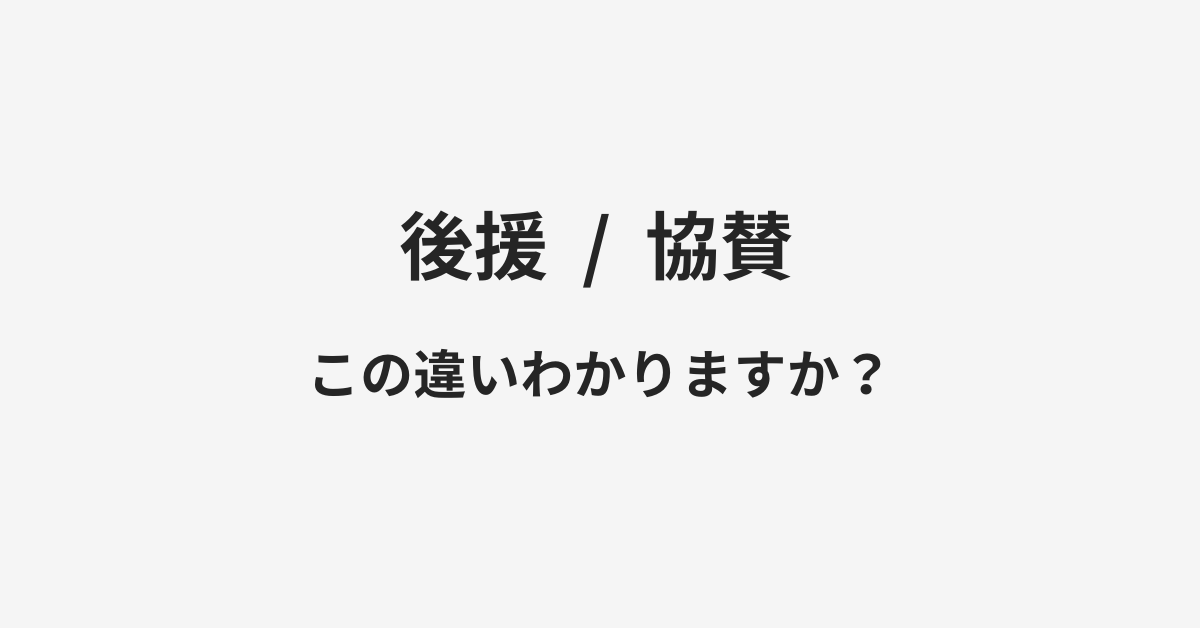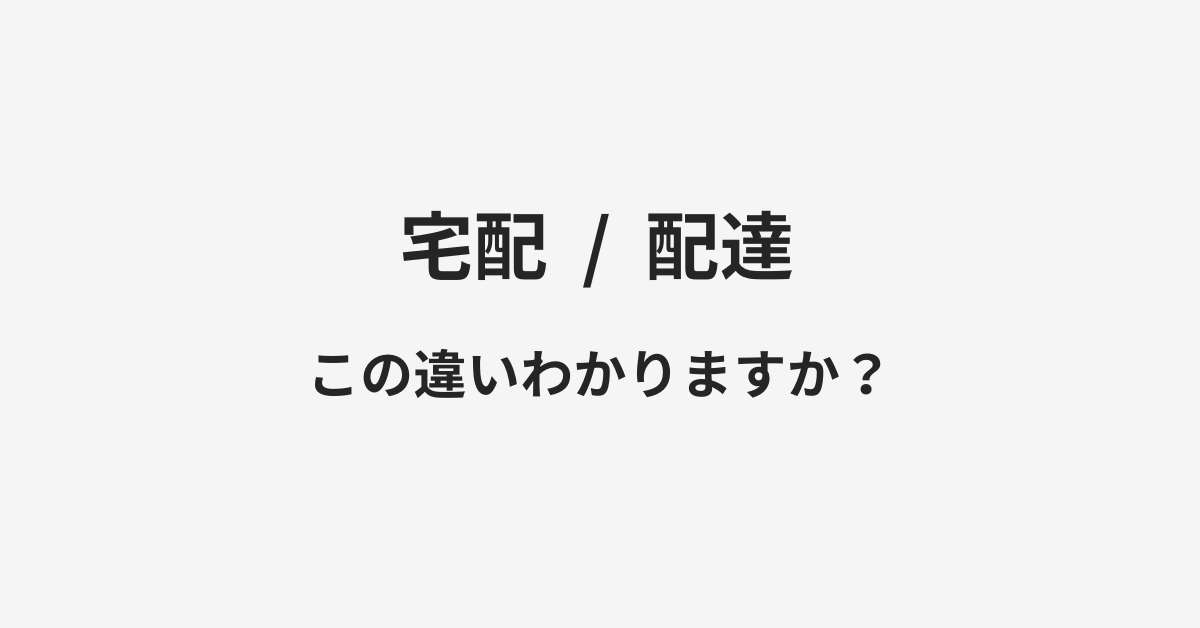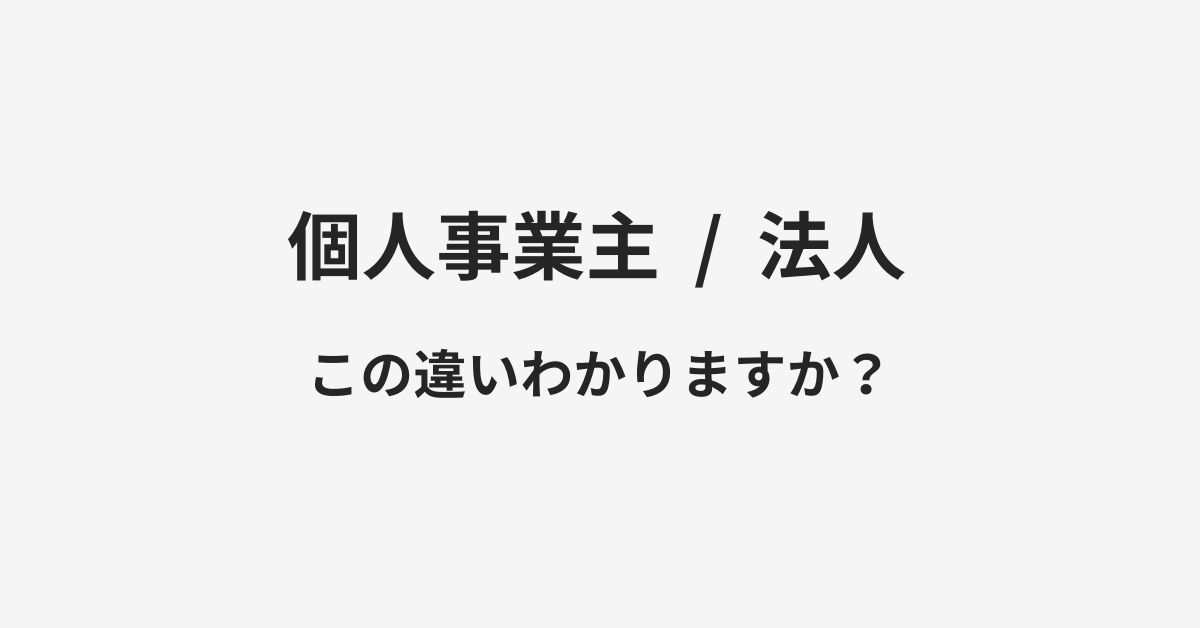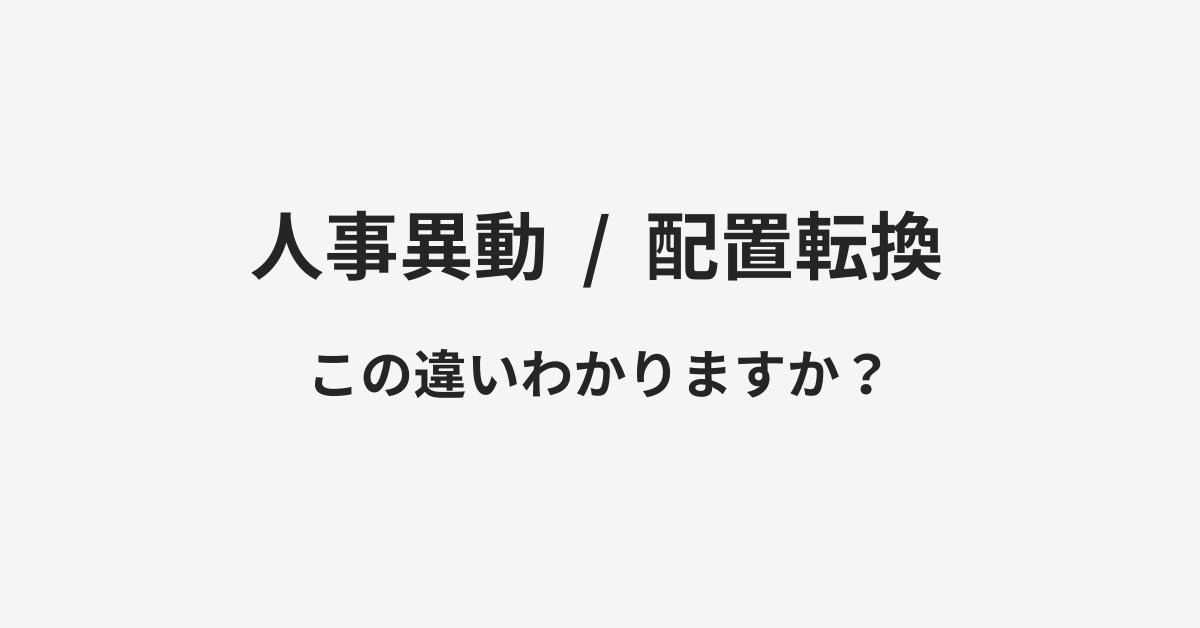【下克上】と【謀反】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
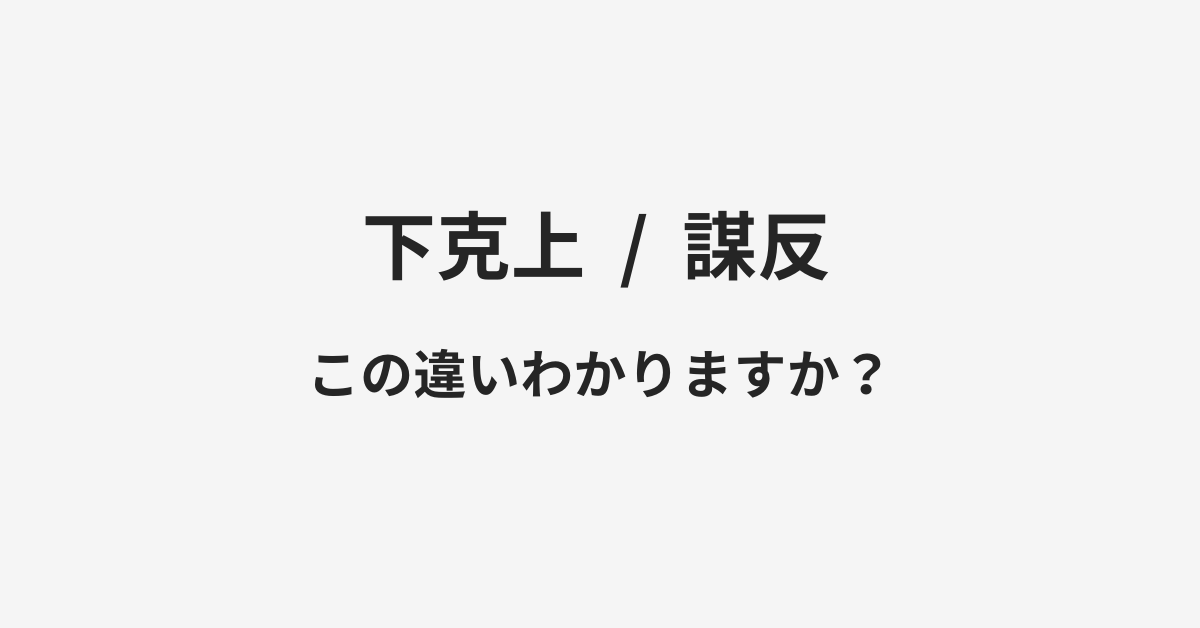
下克上と謀反の分かりやすい違い
下克上と謀反は、どちらも既存の秩序に対する行動ですが、評価が異なります。
下克上は実力による正当な成功で、肯定的に使われることが多い言葉です。
謀反は組織への裏切りや反逆を意味し、否定的なニュアンスを持ちます。
下克上とは?
下克上とは、もともと戦国時代に下位の者が上位の者を実力で倒して地位を奪うことを指しましたが、現代のビジネスシーンでは、若手や中小企業が実力で大手や先輩を超えることを表す前向きな言葉として使われます。新規参入企業が既存大手を追い抜く、若手社員が実績で先輩を超えるなど、実力主義の象徴として肯定的に捉えられます。
ビジネスにおける下克上は、イノベーションや競争原理の健全な結果として評価されます。スタートアップが大企業を脅かす、地方企業が都市部の企業を凌駕するなど、努力と創意工夫による成功を指します。
組織内でも、能力のある若手の抜擢は組織活性化につながると考えられています。業界で下克上を起こす、実力による下克上のように、正当な競争による成功を表現する際に使用される言葉です。
下克上の例文
- ( 1 ) スタートアップが大手企業のシェアを奪う下克上が起きている。
- ( 2 ) 営業成績で新人が先輩を抜く下克上は、組織に活力を与えます。
- ( 3 ) 地方の中小企業が革新的な技術で業界に下克上を起こした。
- ( 4 ) 実力主義の会社では、下克上的な昇進も珍しくありません。
- ( 5 ) ベンチャー企業による下克上が、産業構造を変革しています。
- ( 6 ) 若手の下克上的な活躍が、会社の成長を牽引している。
下克上の会話例
謀反とは?
謀反とは、組織や上司、会社に対する反逆や裏切り行為を指す否定的な言葉です。ビジネスシーンでは、会社の方針に反する行動、上司の指示に従わない行為、競合他社への情報漏洩、社内での反対派形成など、組織の秩序を乱す行為全般を指します。
忠誠心の欠如や倫理違反を含む概念です。謀反は組織の一体性を損ない、チームワークを破壊する行為として強く批判されます。内部告発と謀反の境界は微妙ですが、私利私欲や悪意に基づく行動は謀反とみなされます。
日本の企業文化では特に忌避される行為で、信頼関係の破壊につながります。謀反を企てる、謀反者として処分されるのように、組織への背信行為を表現する際に使用される言葉です。
謀反の例文
- ( 1 ) 部長に対する謀反を企てたグループが、処分を受けました。
- ( 2 ) 会社の方針に反する謀反的な行動は、懲戒対象となります。
- ( 3 ) 競合他社と内通する謀反行為が発覚し、解雇処分となった。
- ( 4 ) 経営陣への謀反は、組織の崩壊を招く危険な行為です。
- ( 5 ) 部下の謀反により、プロジェクトが頓挫してしまいました。
- ( 6 ) 謀反の疑いをかけられ、左遷されることになった。
謀反の会話例
下克上と謀反の違いまとめ
下克上と謀反は、既存秩序への挑戦という点では共通しますが、その手段と評価が大きく異なります。下克上は正当な競争と実力による成功で、イノベーションの源として肯定的に評価されます。
謀反は不正な手段による反逆で、組織破壊行為として否定的に捉えられます。
ビジネスでは、健全な競争による下克上は歓迎されますが、謀反は避けるべき行為です。
下克上と謀反の読み方
- 下克上(ひらがな):げこくじょう
- 下克上(ローマ字):gekokujou
- 謀反(ひらがな):むほん
- 謀反(ローマ字):muhonn