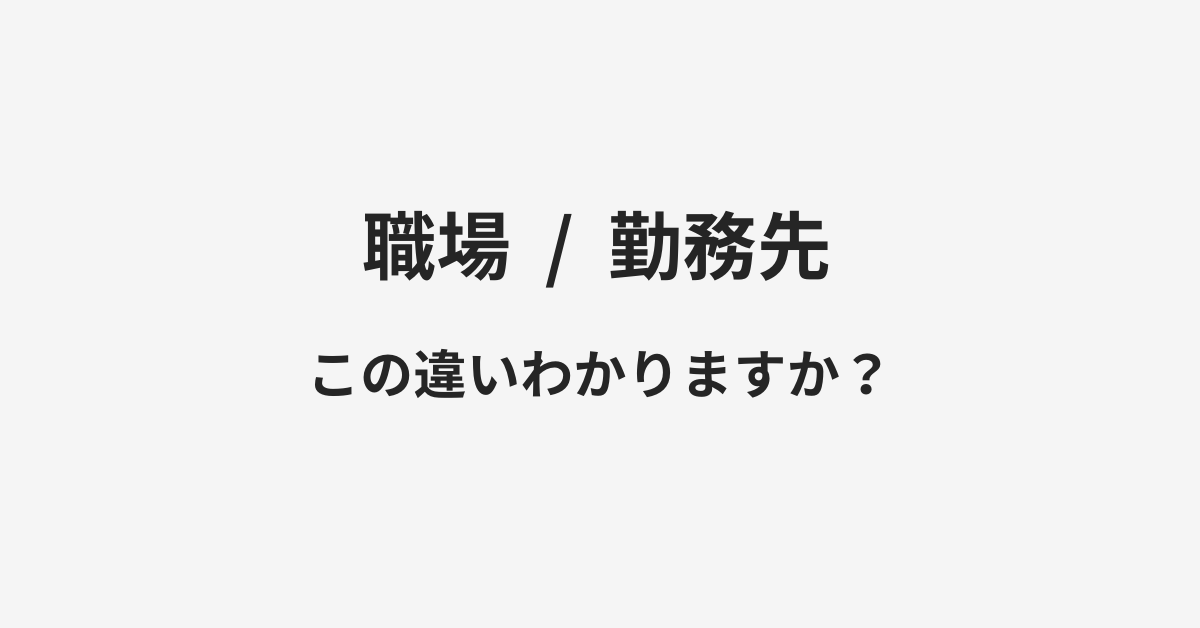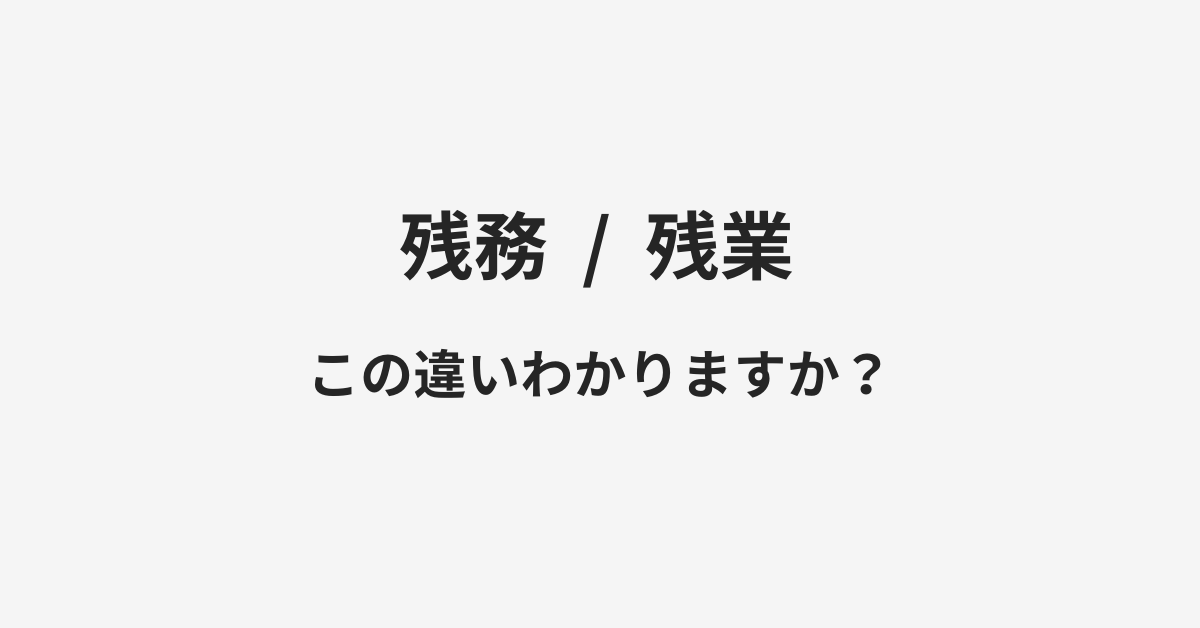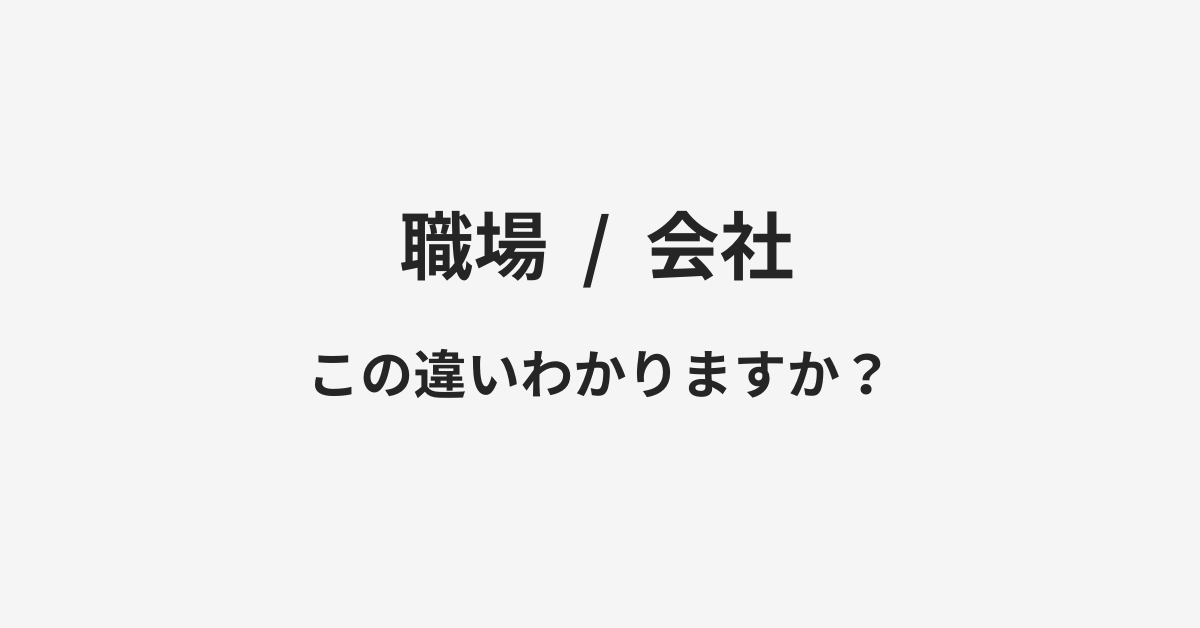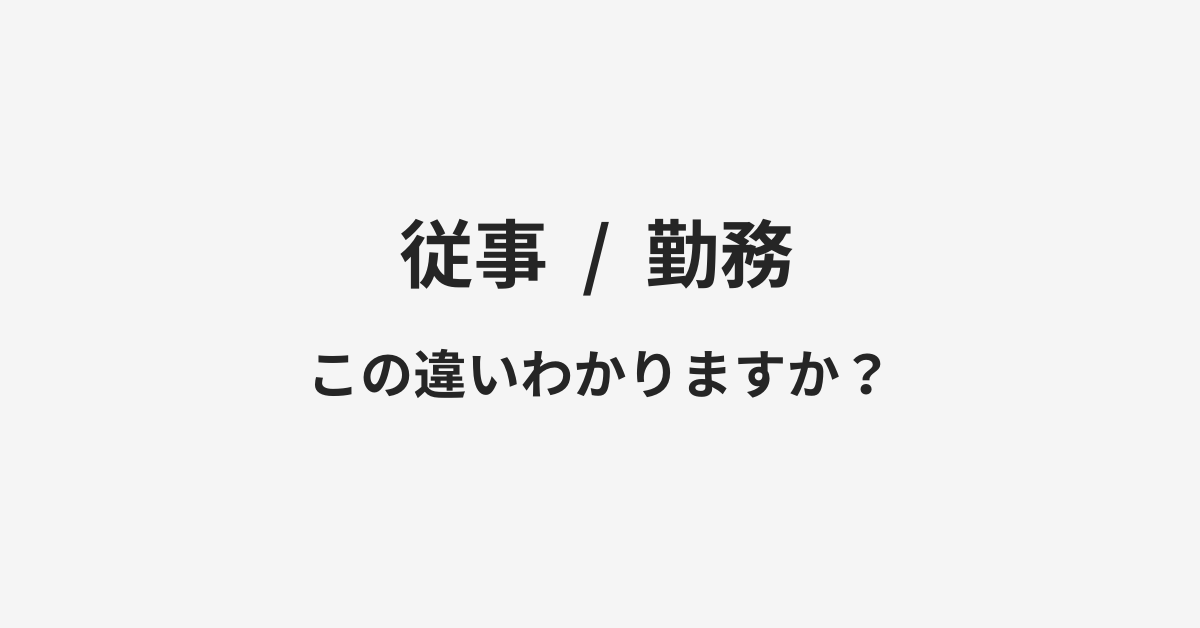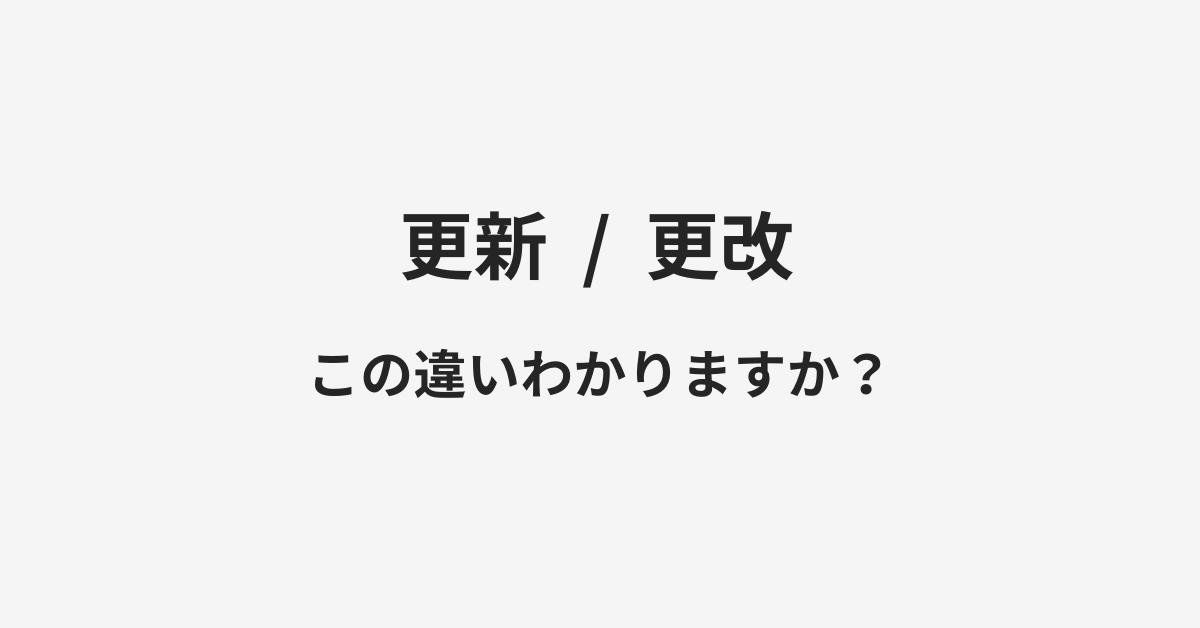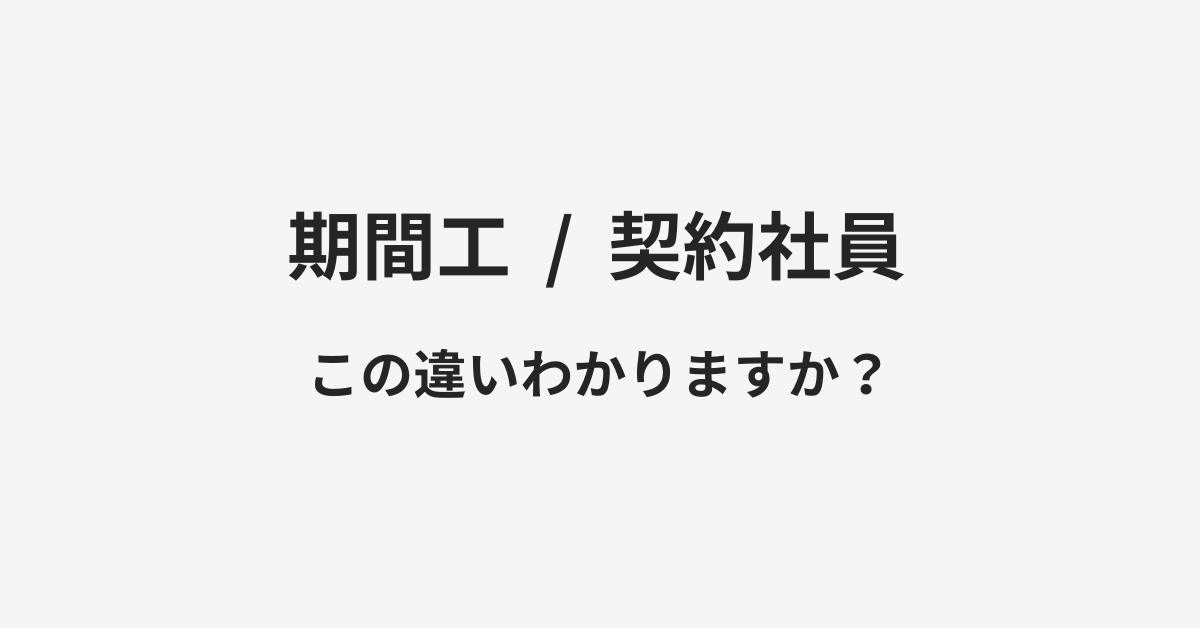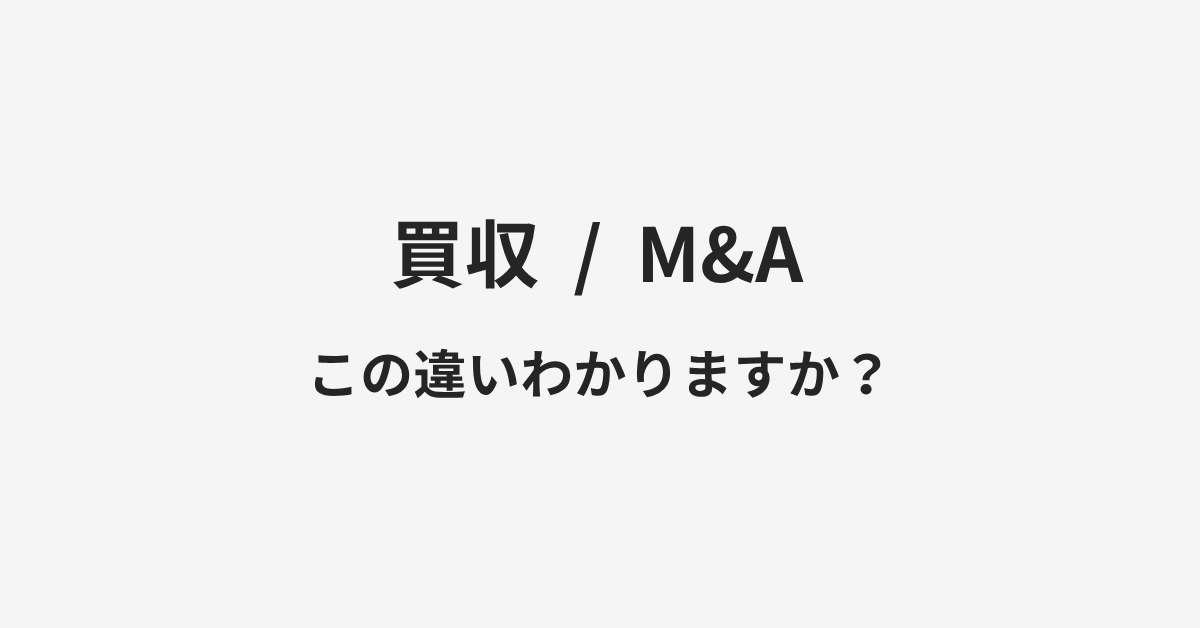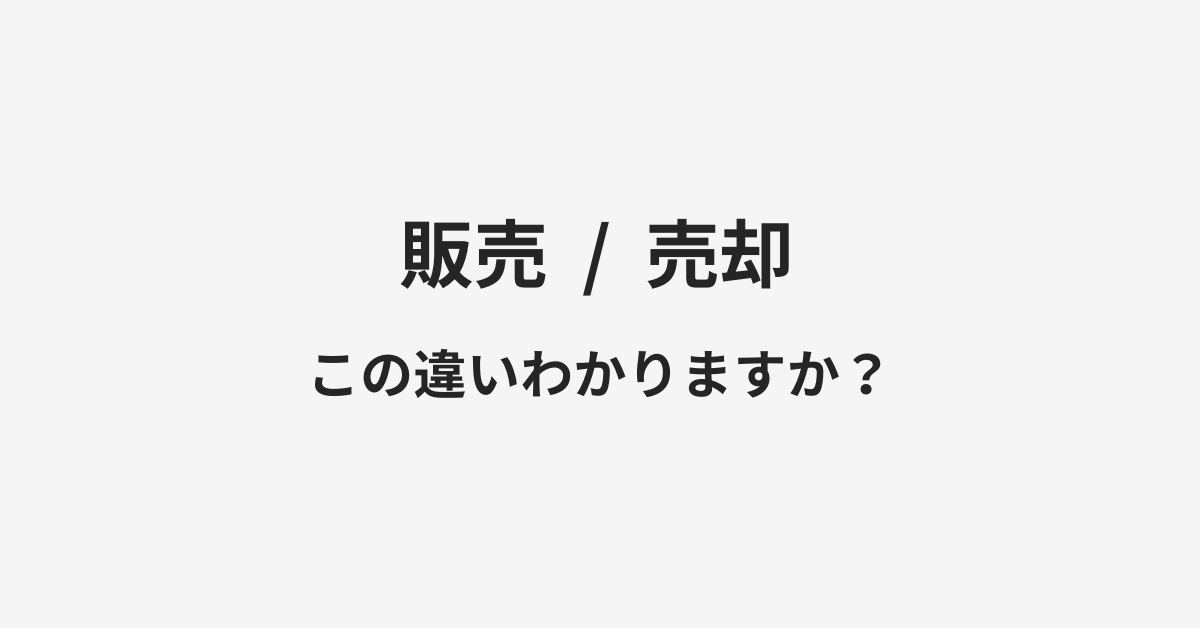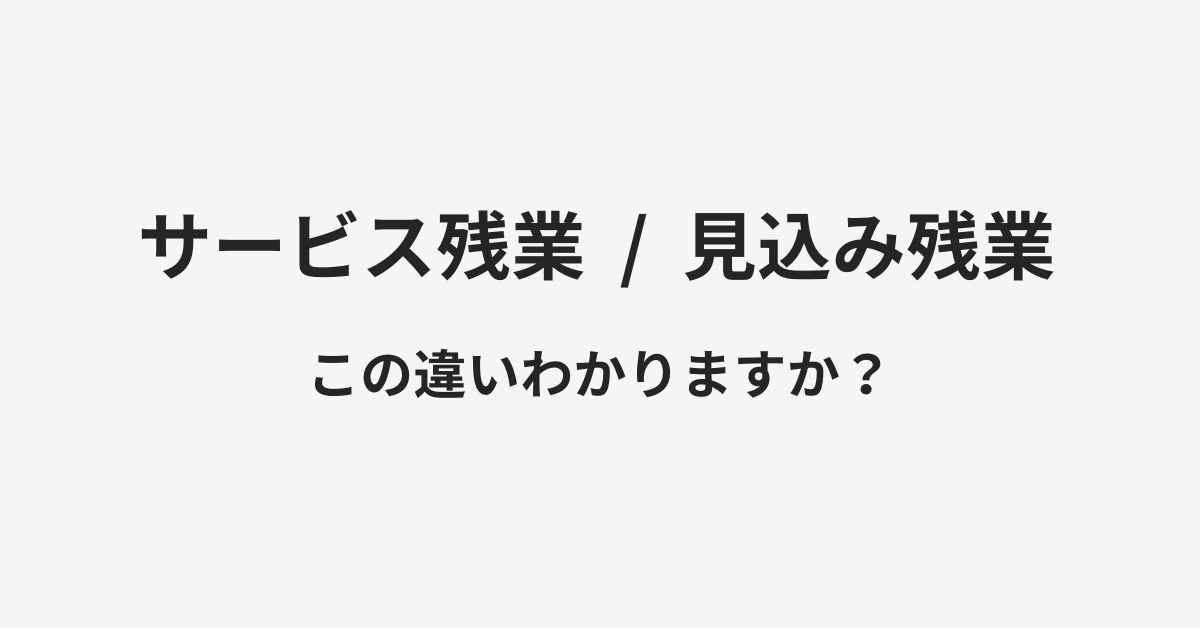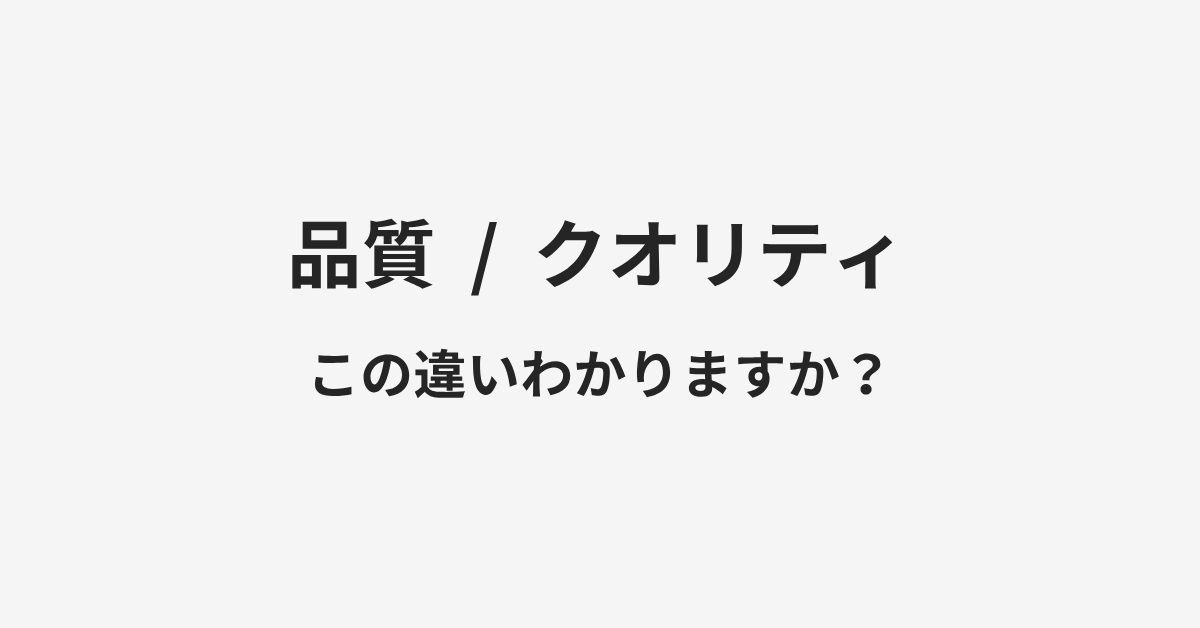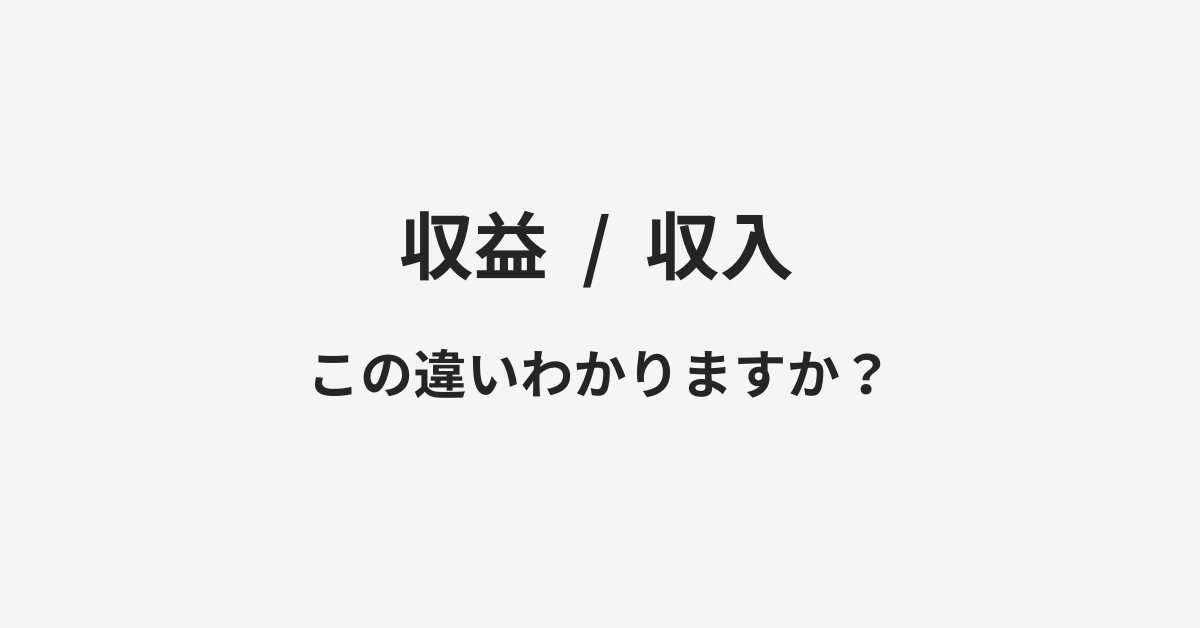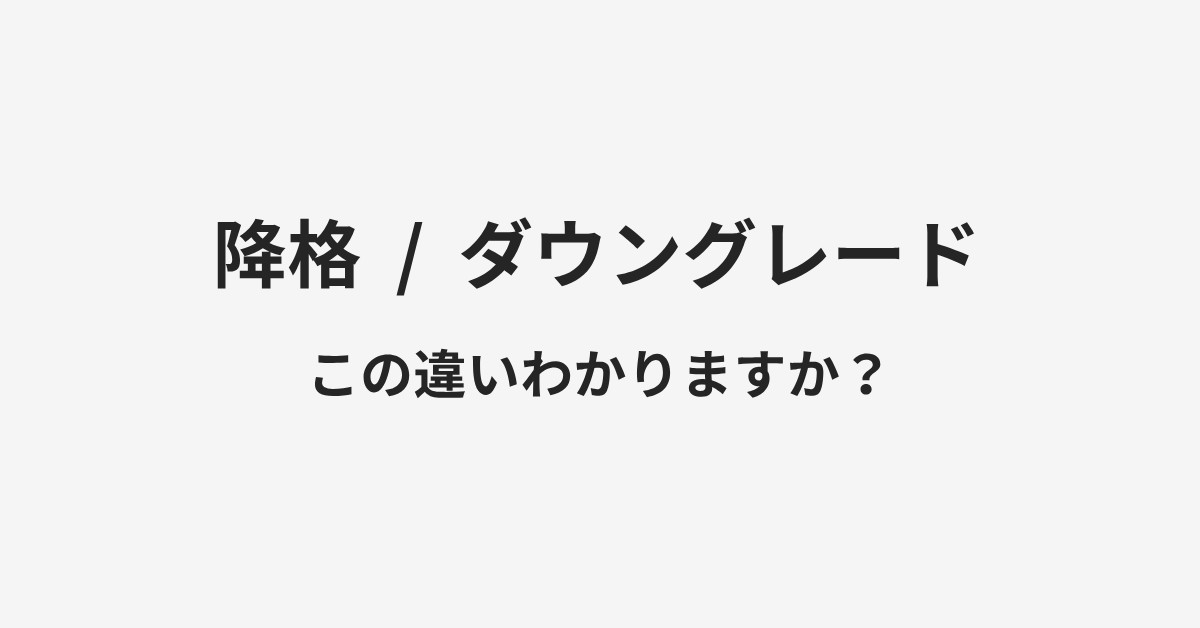【出勤】と【出社】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
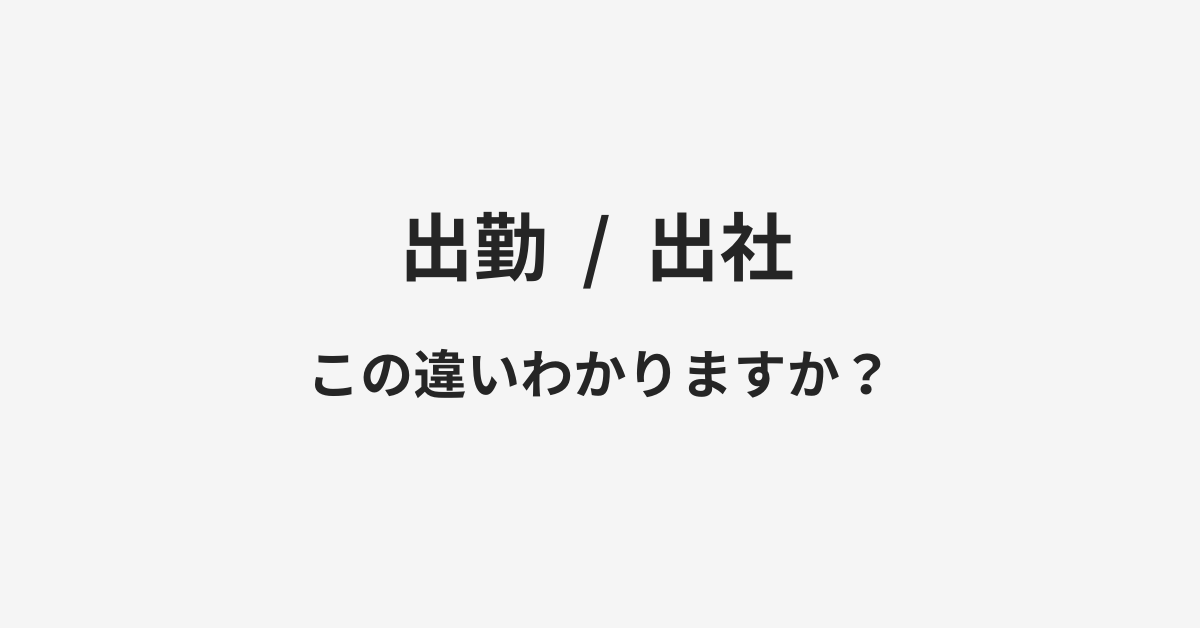
出勤と出社の分かりやすい違い
出勤と出社は、どちらも仕事に行くことを表しますが、場所の特定性が異なります。
出勤は、職場がどこであっても仕事を始めることを指します。出社は、具体的に会社のオフィスに行くことを意味します。
テレワーク時代では、在宅でも出勤と言いますが、出社とは言いません。この使い分けが重要になっています。
出勤とは?
出勤とは、勤務を開始することを指す広義の用語で、勤務場所を問いません。在宅勤務、サテライトオフィス、客先常駐、現場作業など、あらゆる形態の労働開始を含みます。勤怠管理上、最も基本的な概念として使用されています。
労働時間の起点として、出勤時刻の記録は給与計算の基礎となります。フレックスタイム制やリモートワークの普及により、出勤の形態は多様化しています。
出勤率は人事評価の指標の一つで、健康経営の観点からも重視されます。働き方改革により、出勤の概念自体が柔軟に解釈されるようになり、成果重視の評価へとシフトしています。
出勤の例文
- ( 1 ) 本日の出勤予定者は、在宅勤務も含めて50名です。
- ( 2 ) 出勤時間を柔軟に設定できるフレックスタイム制を導入しました。
- ( 3 ) 体調不良による出勤停止措置を、感染防止のため実施しています。
- ( 4 ) 出勤簿のデジタル化により、勤怠管理が効率化されました。
- ( 5 ) リモートでの出勤も、通常勤務と同等に評価されます。
- ( 6 ) 出勤率98%以上の社員に、皆勤手当を支給しています。
出勤の会話例
出社とは?
出社とは、物理的に会社のオフィスに行くことを指す具体的な行動です。本社、支社、営業所など、企業が保有・賃借する施設への移動を意味します。リモートワークと対比される概念として、重要性が再認識されています。
出社によるメリットは、対面コミュニケーション、偶発的な情報交換、組織文化の醸成などがあります。ハイブリッドワークでは、出社日の戦略的な設定が生産性向上の鍵となっています。
出社率の管理は、オフィススペースの最適化やコスト削減にも関連します。企業は出社の必要性を見極め、従業員のワークライフバランスと業務効率の両立を図っています。
出社の例文
- ( 1 ) 週3日の出社を基本とするハイブリッドワークを採用しています。
- ( 2 ) 出社時の検温・消毒を、引き続き徹底してください。
- ( 3 ) 出社不要の業務については、在宅勤務を推奨しています。
- ( 4 ) 出社日には部署全体でのミーティングを設定しています。
- ( 5 ) 緊急事態宣言中は、出社率を30%以下に抑制しました。
- ( 6 ) 出社時の交通費は、実費精算に変更されました。
出社の会話例
出勤と出社の違いまとめ
出勤と出社の違いは、働き方の多様化により明確になりました。出勤は働くことそのもの、出社は会社に行く行為を指します。
適切な使い分けは、勤怠管理やコミュニケーションの正確性を高めます。特にハイブリッドワーク環境では、この区別が重要です。
企業は両概念を理解し、柔軟な働き方を実現する制度設計が求められています。
出勤と出社の読み方
- 出勤(ひらがな):しゅっきん
- 出勤(ローマ字):shukkinn
- 出社(ひらがな):しゅっしゃ
- 出社(ローマ字):shussha