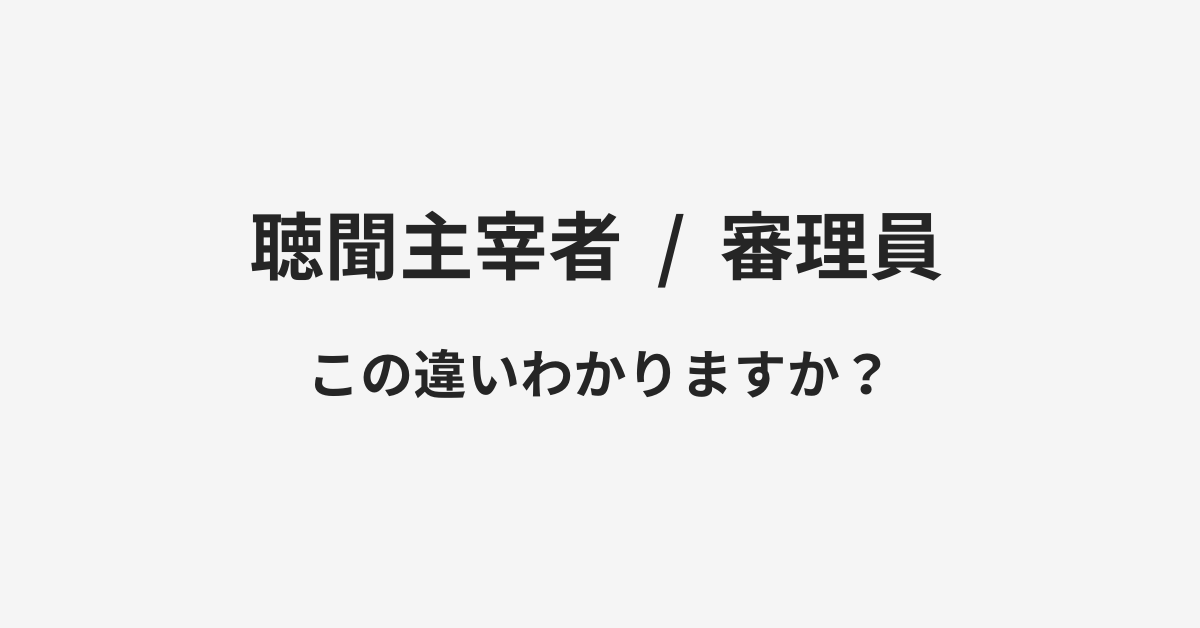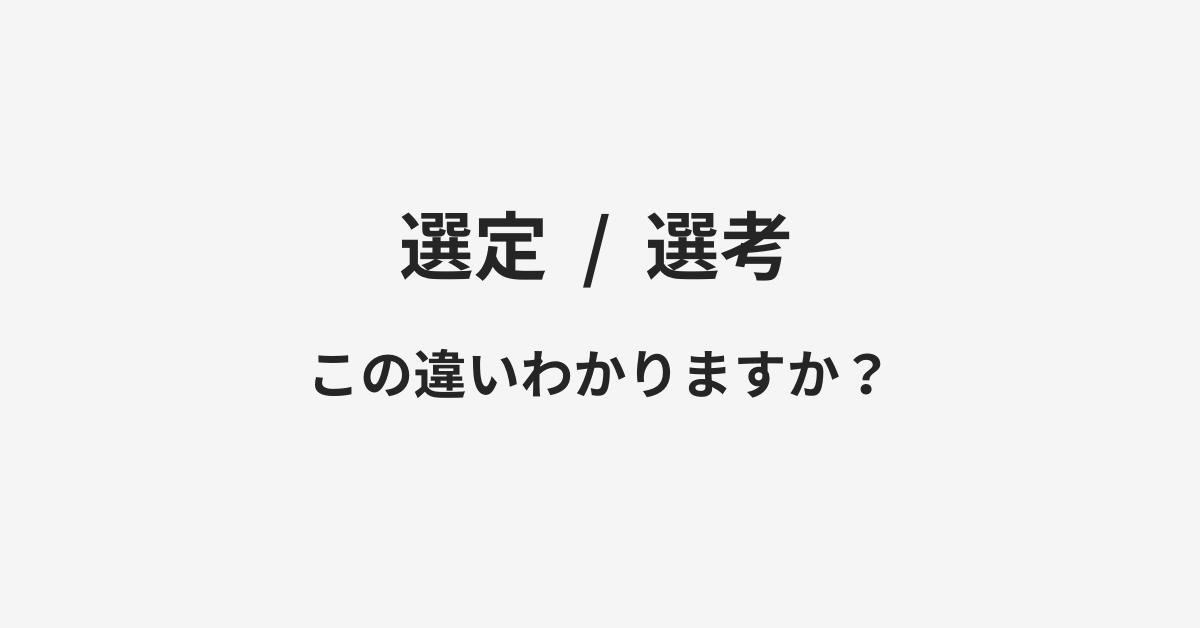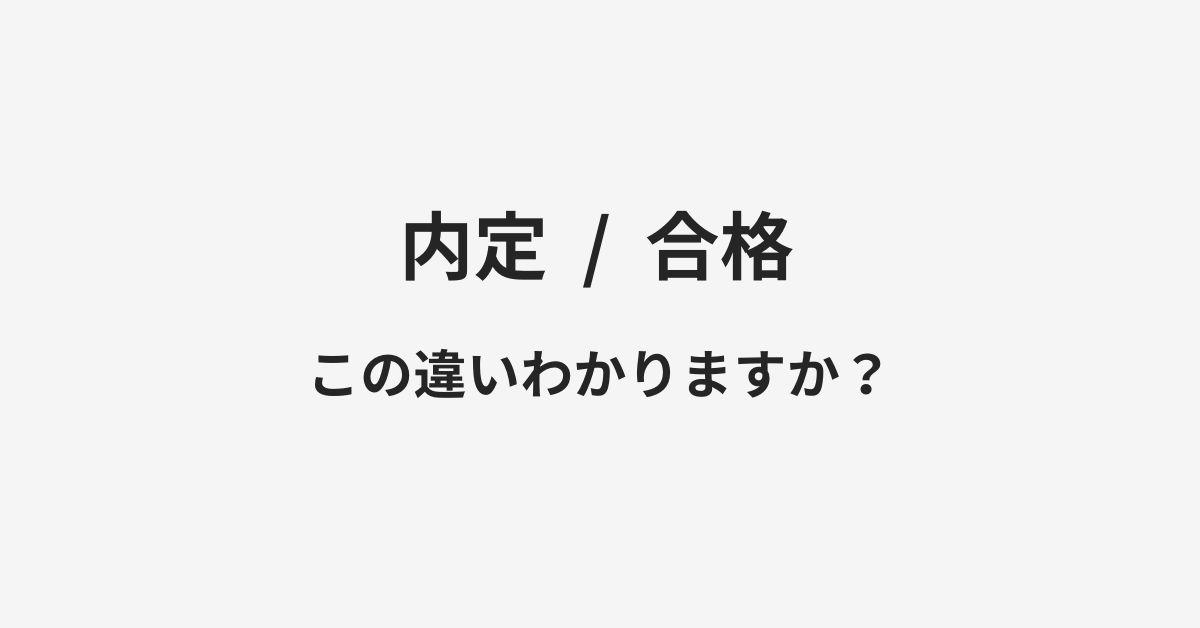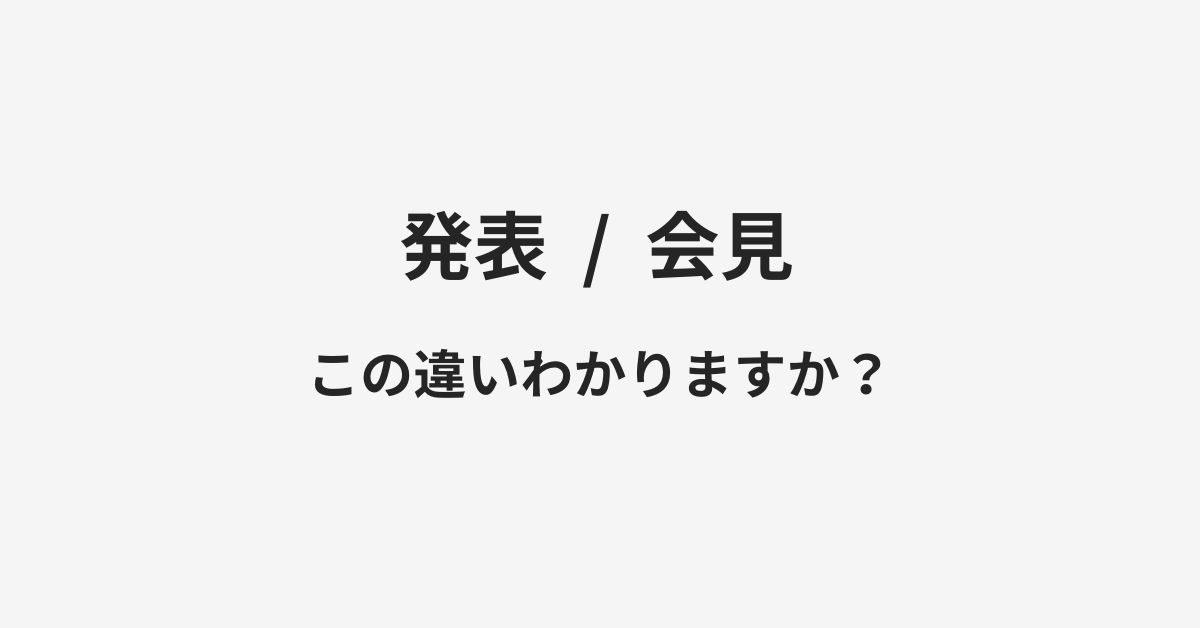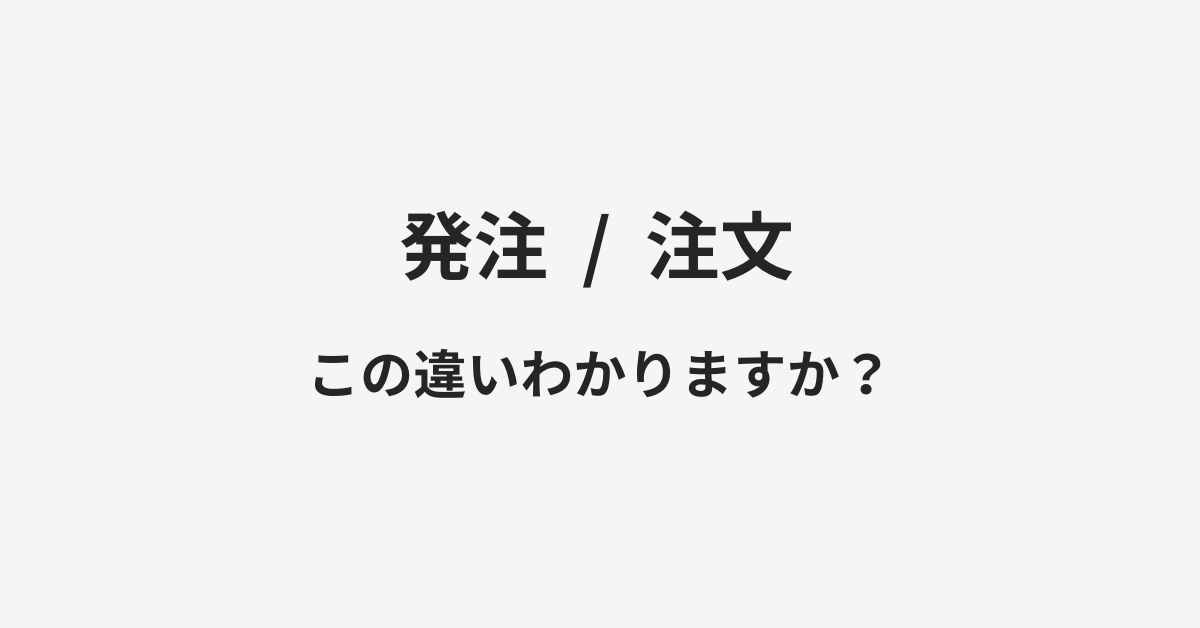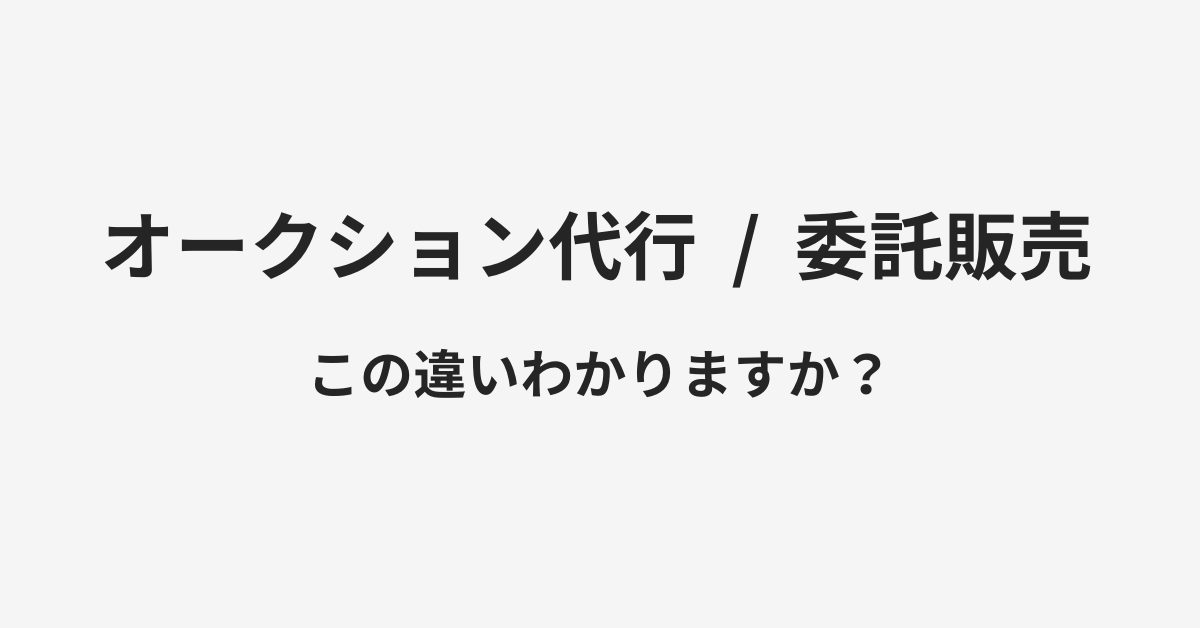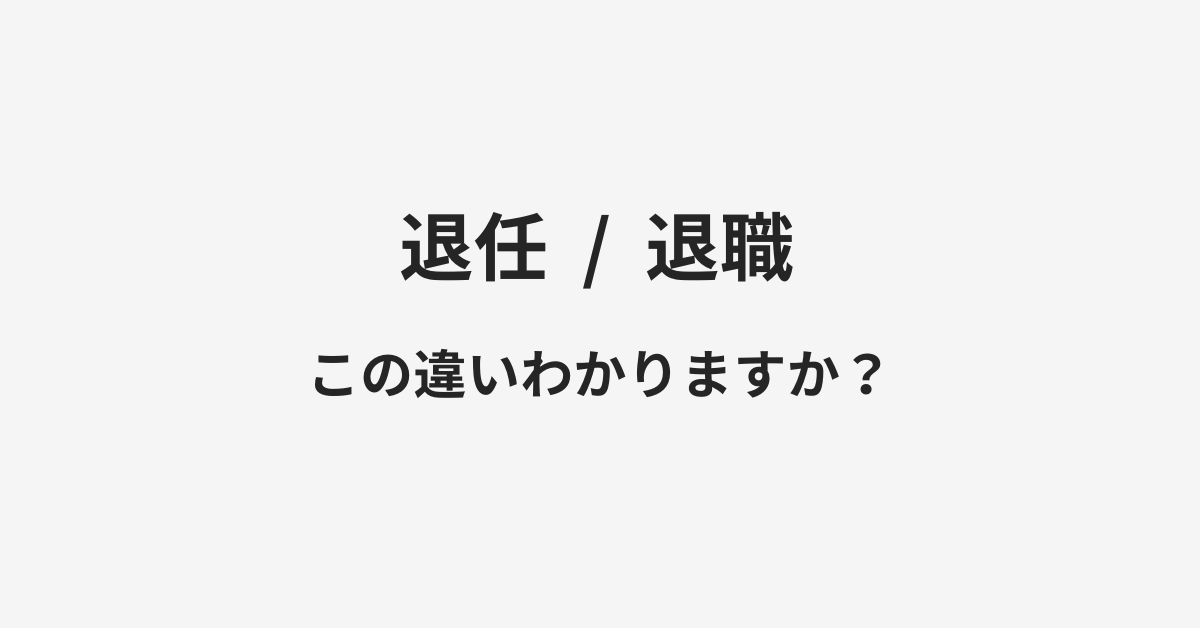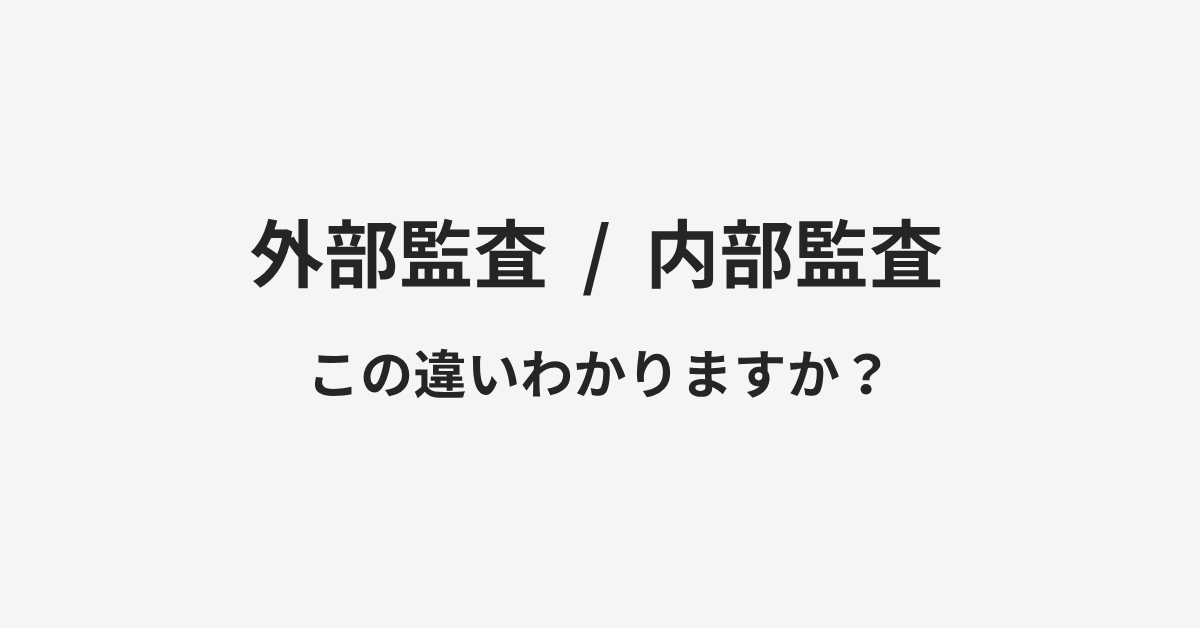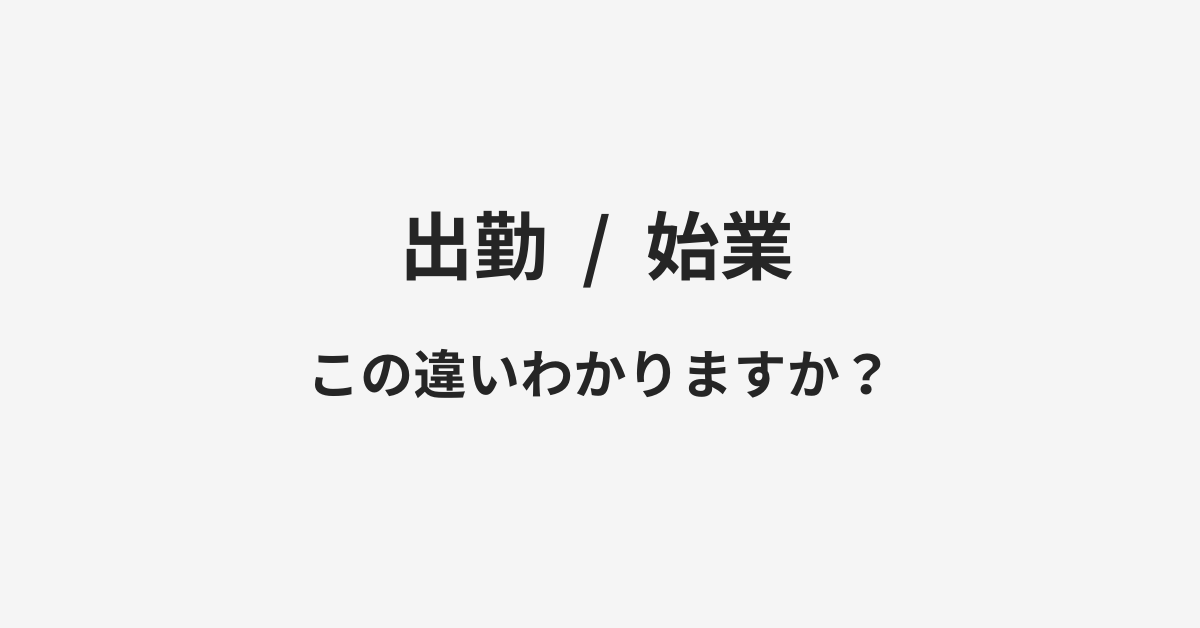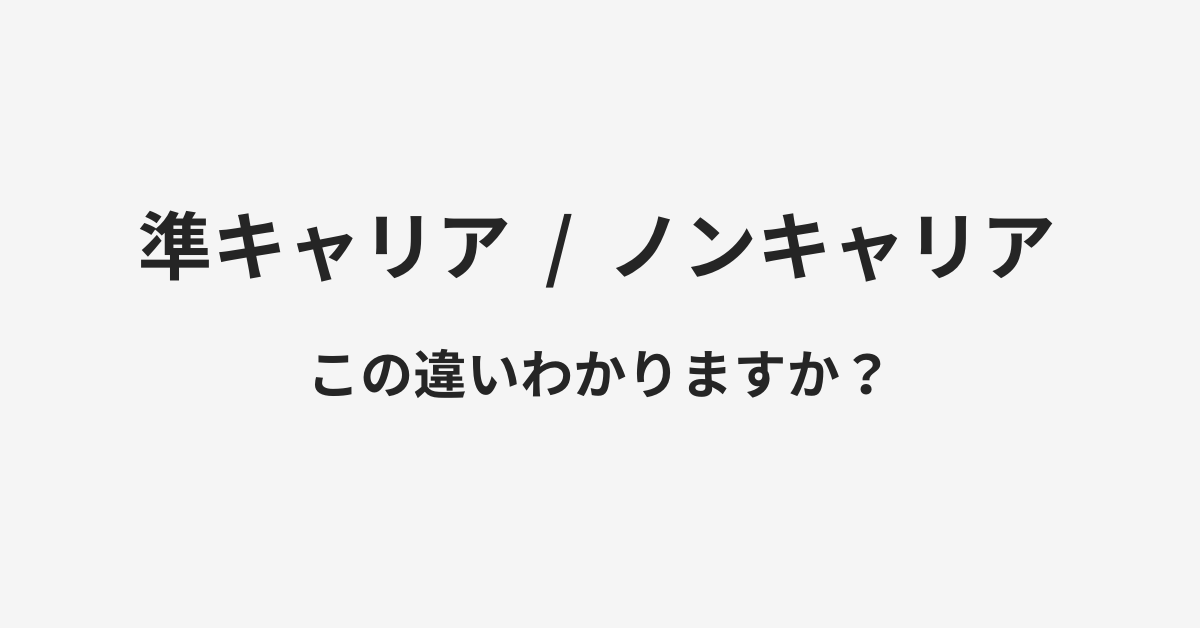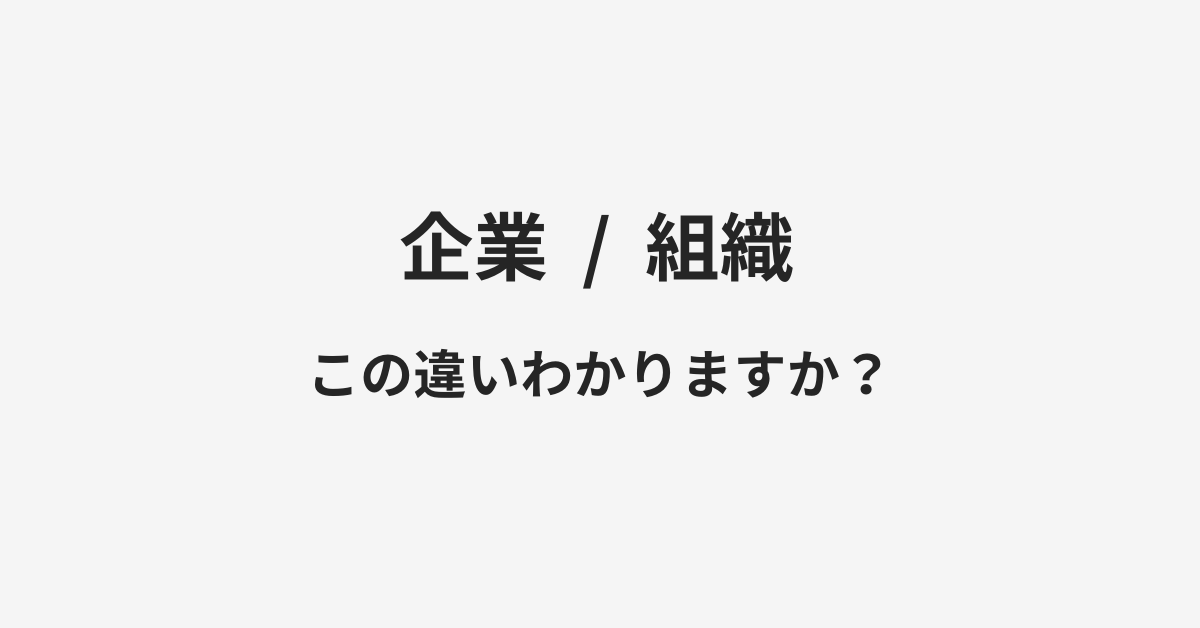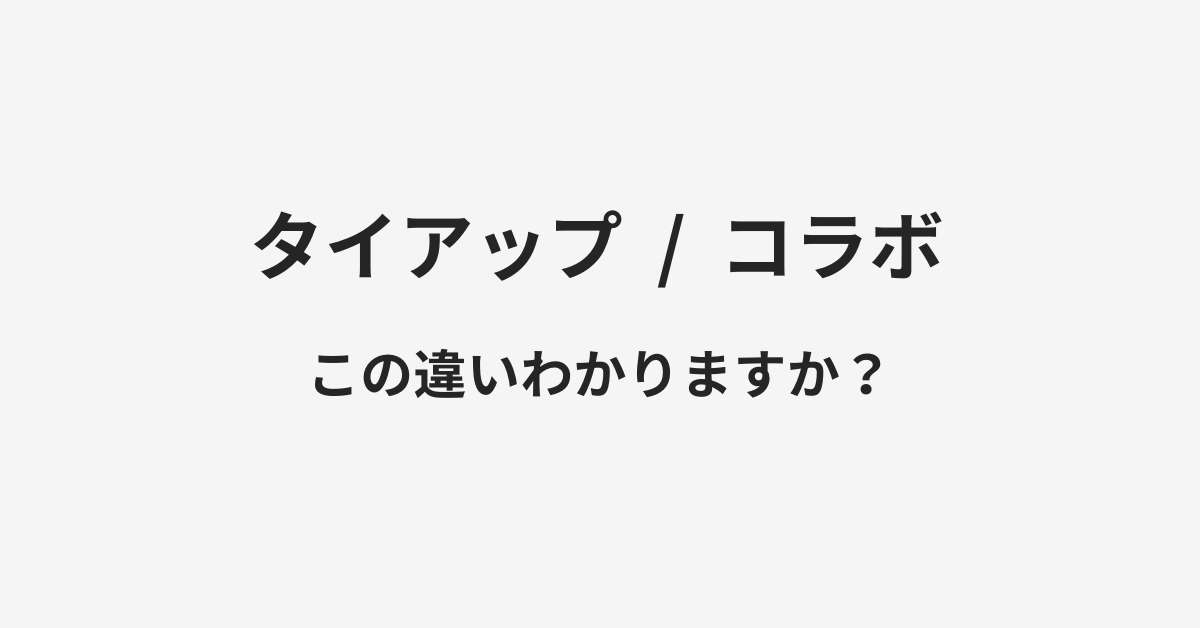【稟議】と【決裁】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
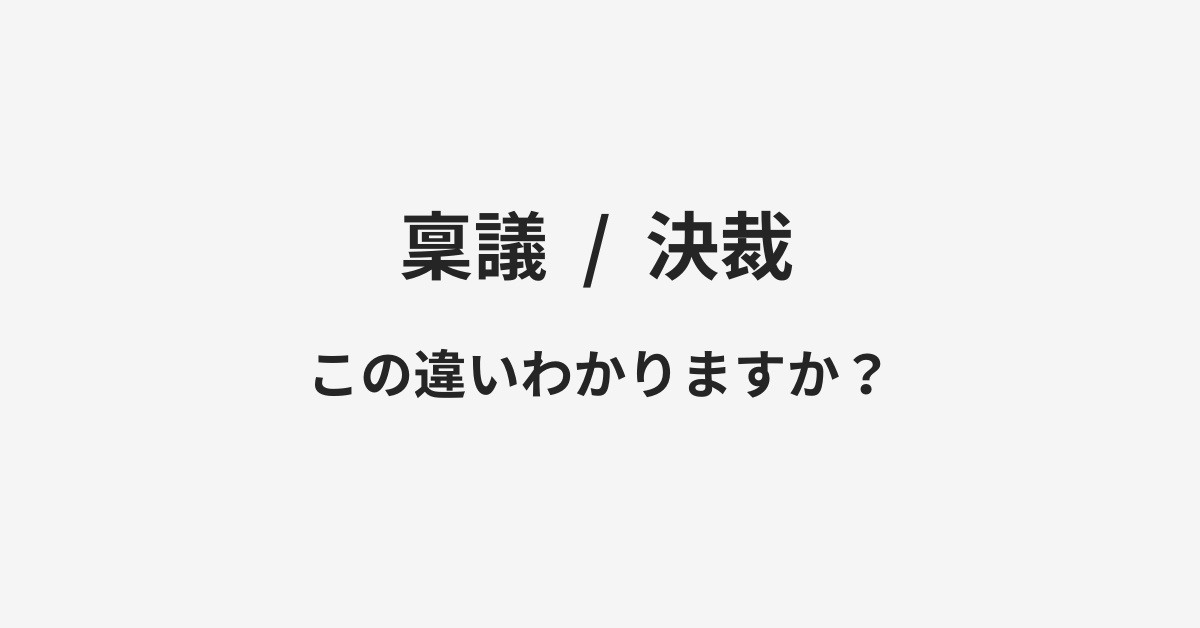
稟議と決裁の分かりやすい違い
稟議と決裁は、どちらも組織の意思決定に関わりますが、範囲が異なります。
稟議は承認を得るための申請・回覧プロセス全体を指します。
決裁は権限者による最終的な承認行為で、稟議の最終段階です。
稟議とは?
稟議とは、組織において、ある事項について担当者が案を作成し、関係部署や上位者に順次回覧して承認を得ていく意思決定プロセスです。稟議書という文書を作成し、予算執行、契約締結、人事異動などの重要事項について、複数の関係者の確認と承認を経て最終決定に至ります。
日本企業特有の意思決定方式として知られ、関係者の合意形成を重視する文化を反映しています。稟議により責任の分散と、多角的な検討が可能になりますが、意思決定に時間がかかるというデメリットもあります。電子稟議システムの導入により効率化が進んでいます。
「稟議を上げる」「稟議書を回す」のように、承認を得るためのプロセス全体を表現する際に使用される言葉です。
稟議の例文
- ( 1 ) 設備投資の稟議を上げるため、投資効果の試算を詳細に行いました。
- ( 2 ) 稟議書には、目的、効果、予算、リスクを明記する必要があります。
- ( 3 ) 電子稟議システムの導入で、承認プロセスが2週間から3日に短縮されました。
- ( 4 ) 稟議規程に基づき、金額に応じた承認ルートが定められています。
- ( 5 ) 緊急案件は、稟議を簡略化して迅速に処理する仕組みがあります。
- ( 6 ) 稟議書の書き方研修を実施し、承認を得やすい提案力を養成しています。
稟議の会話例
決裁とは?
決裁とは、組織において権限を持つ者が、申請や提案に対して最終的な承認や決定を下す行為です。社長決裁、部長決裁など、決裁権限は職位により定められており、金額や重要度に応じて決裁権限者が異なります。決裁により、組織としての正式な意思決定となります。
決裁は稟議プロセスの最終段階であり、決裁権者は提案内容を総合的に判断して承認、条件付き承認、差し戻し、却下などの決定を行います。決裁印の押印や電子決裁により、正式な承認の証跡を残します。迅速な決裁は業務効率に直結します。
「社長の決裁を仰ぐ」「決裁権限を委譲する」のように、最終的な承認行為を表現する際に使用される言葉です。
決裁の例文
- ( 1 ) 部長決裁で承認された案件を、本日から実行に移します。
- ( 2 ) 1000万円以上の案件は、社長決裁が必要となります。
- ( 3 ) 決裁権限を課長に委譲し、意思決定の迅速化を図りました。
- ( 4 ) 決裁待ちの案件が滞留しないよう、週2回の決裁日を設けています。
- ( 5 ) 条件付き決裁となったため、指摘事項を修正して再提出します。
- ( 6 ) 電子決裁により、出張中でも迅速な決裁が可能になりました。
決裁の会話例
稟議と決裁の違いまとめ
稟議と決裁は、組織の意思決定において密接に関連しながらも、異なる概念です。
稟議は提案から承認までのプロセス全体を指し、複数の関係者による検討と合意形成を含みます。決裁は権限者による最終承認という一点に焦点を当てた行為です。
効率的な組織運営には、適切な稟議プロセスと迅速な決裁の両立が重要です。
稟議と決裁の読み方
- 稟議(ひらがな):りんぎ
- 稟議(ローマ字):rinngi
- 決裁(ひらがな):けっさい
- 決裁(ローマ字):kessai