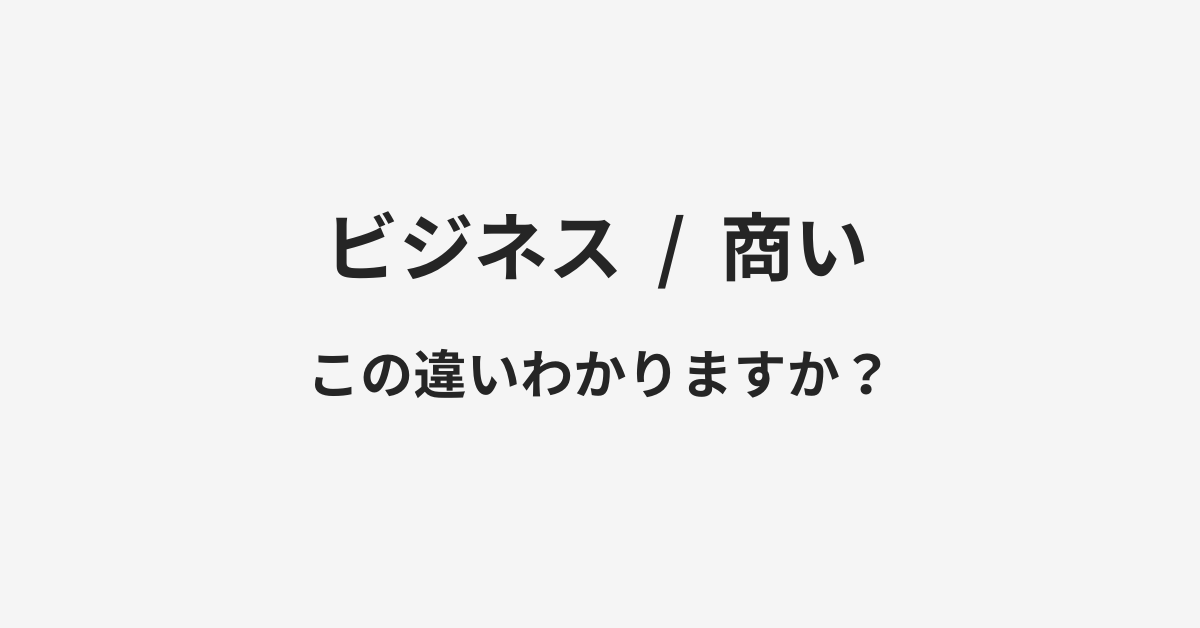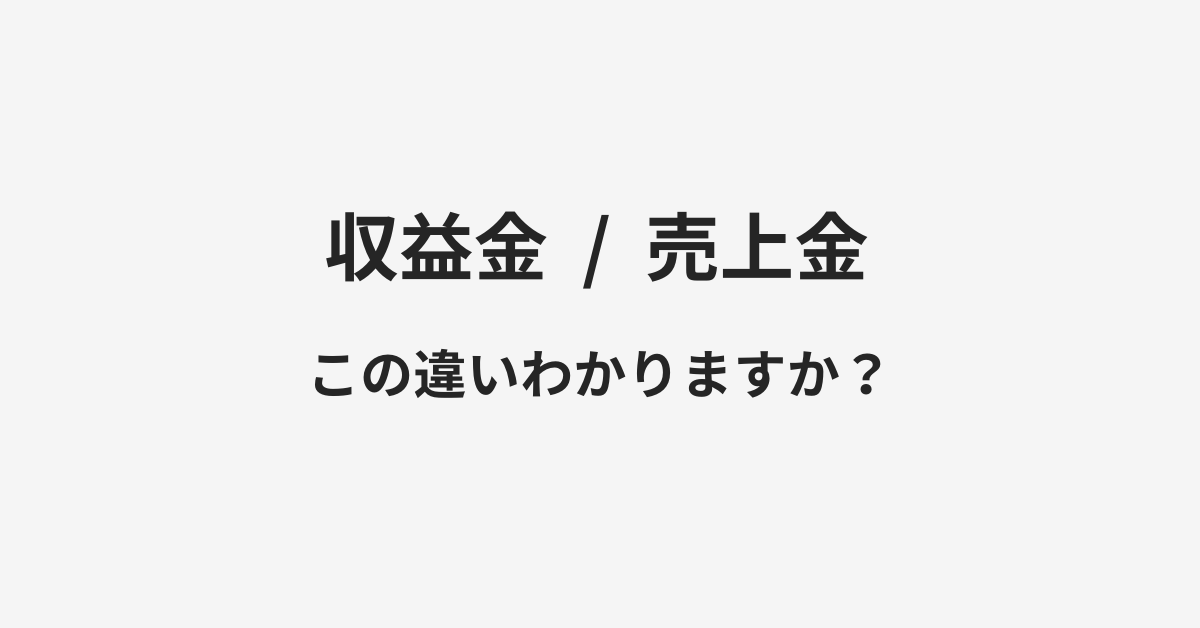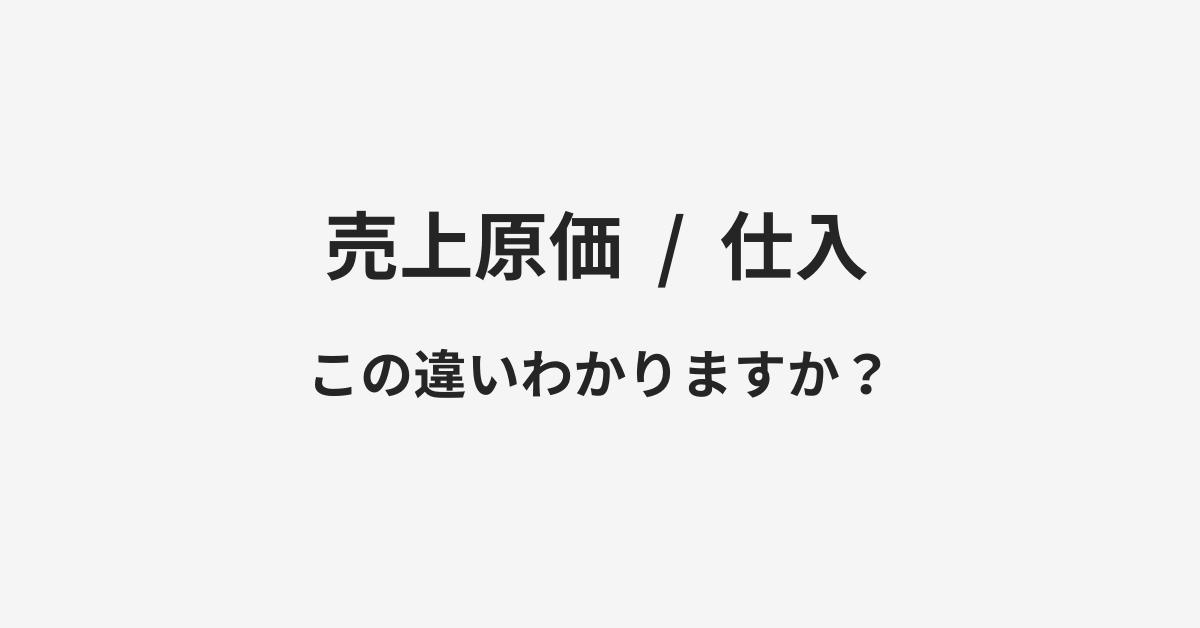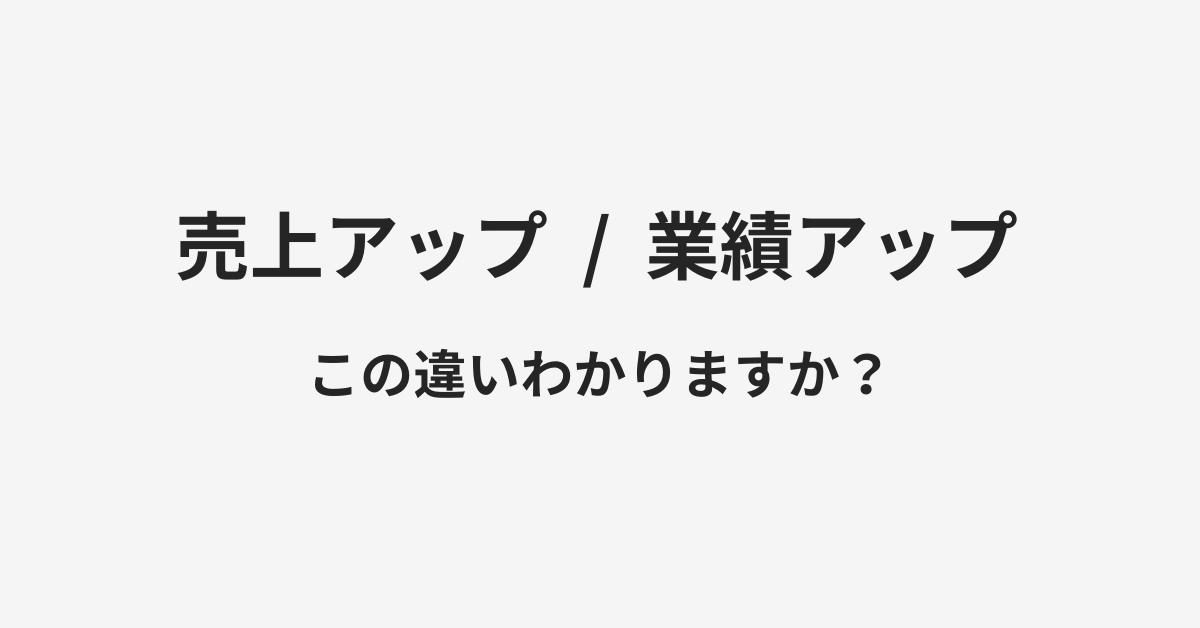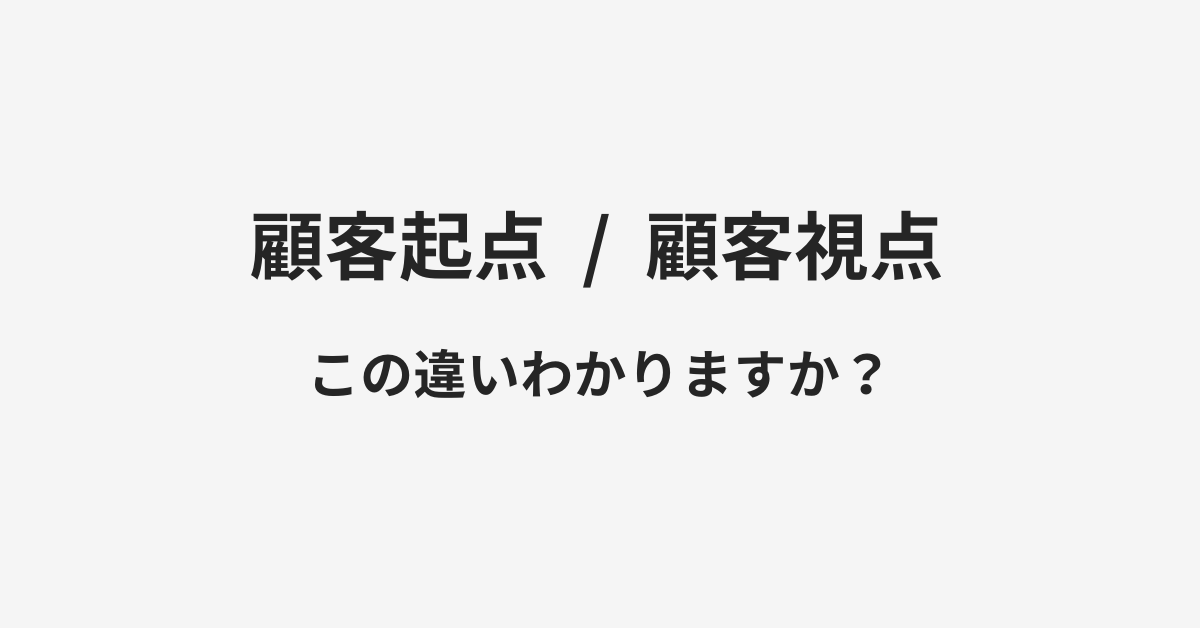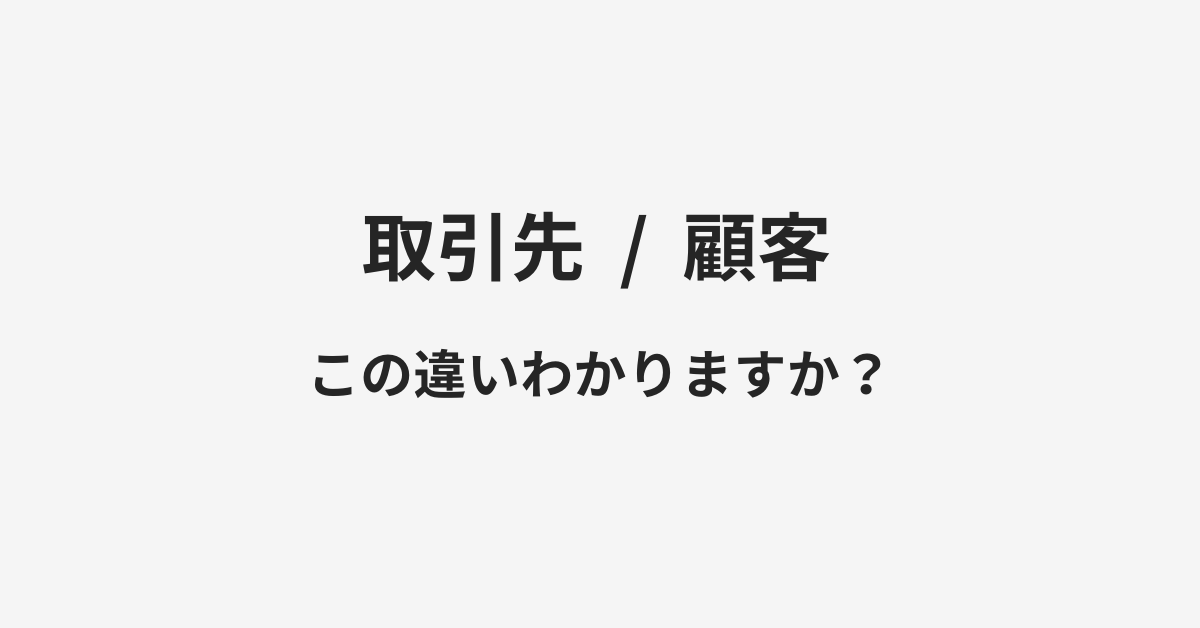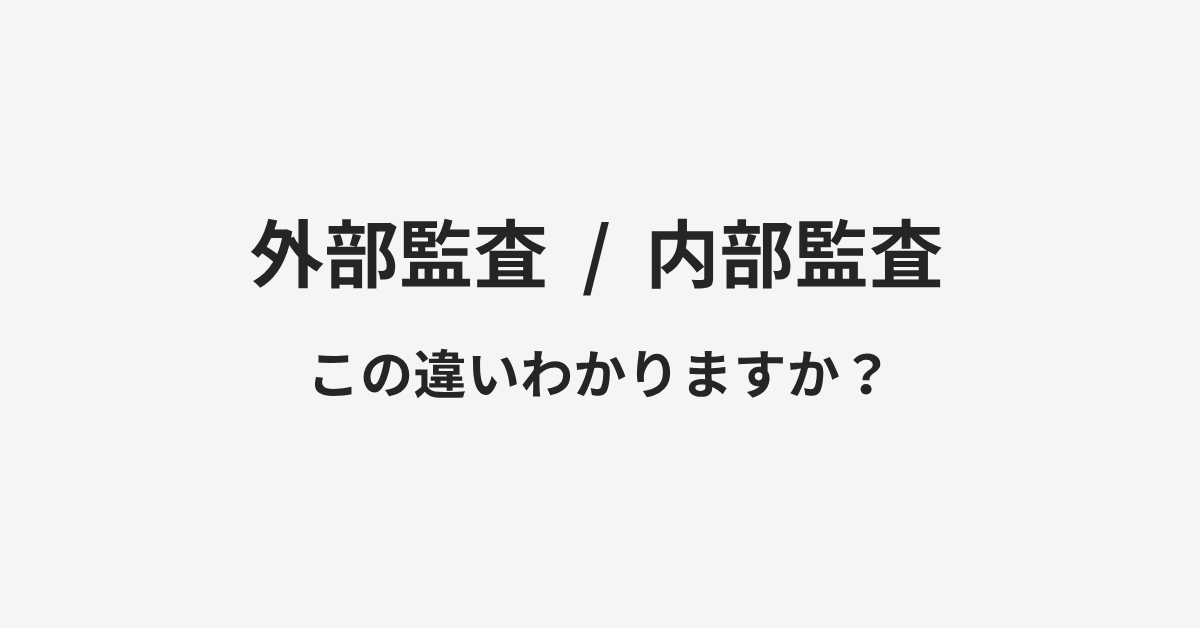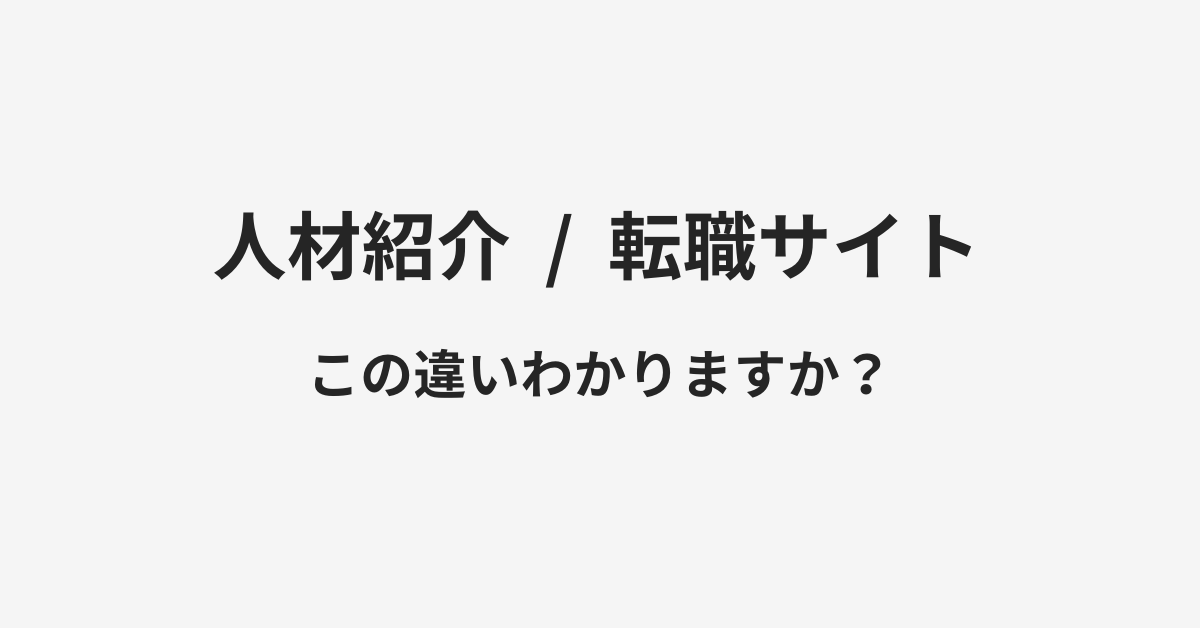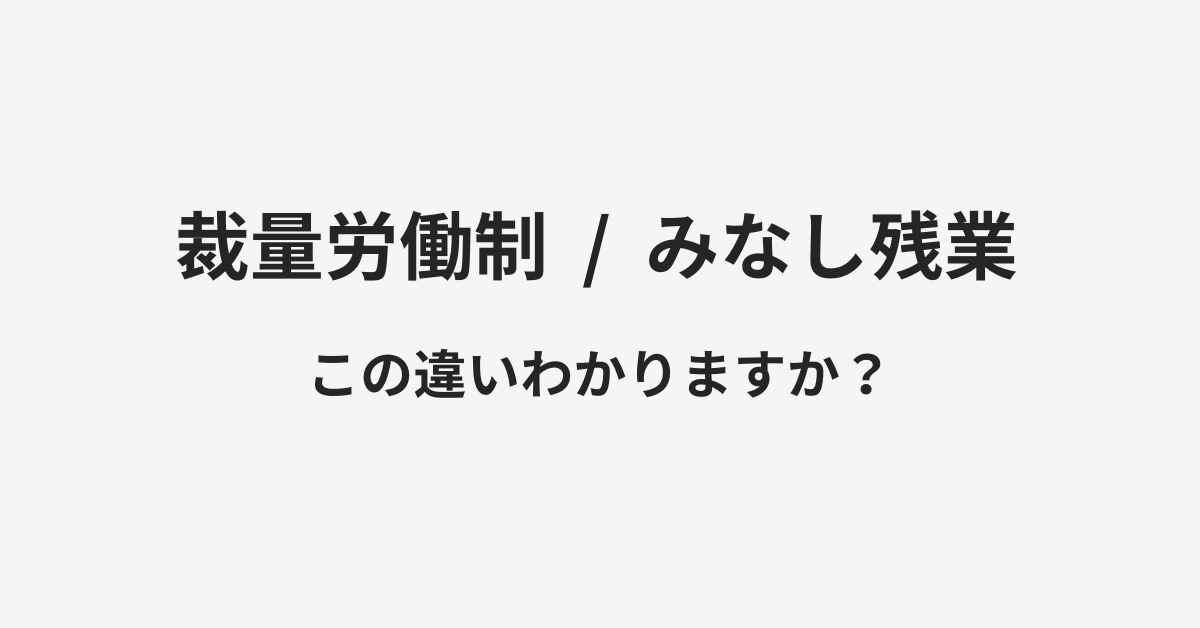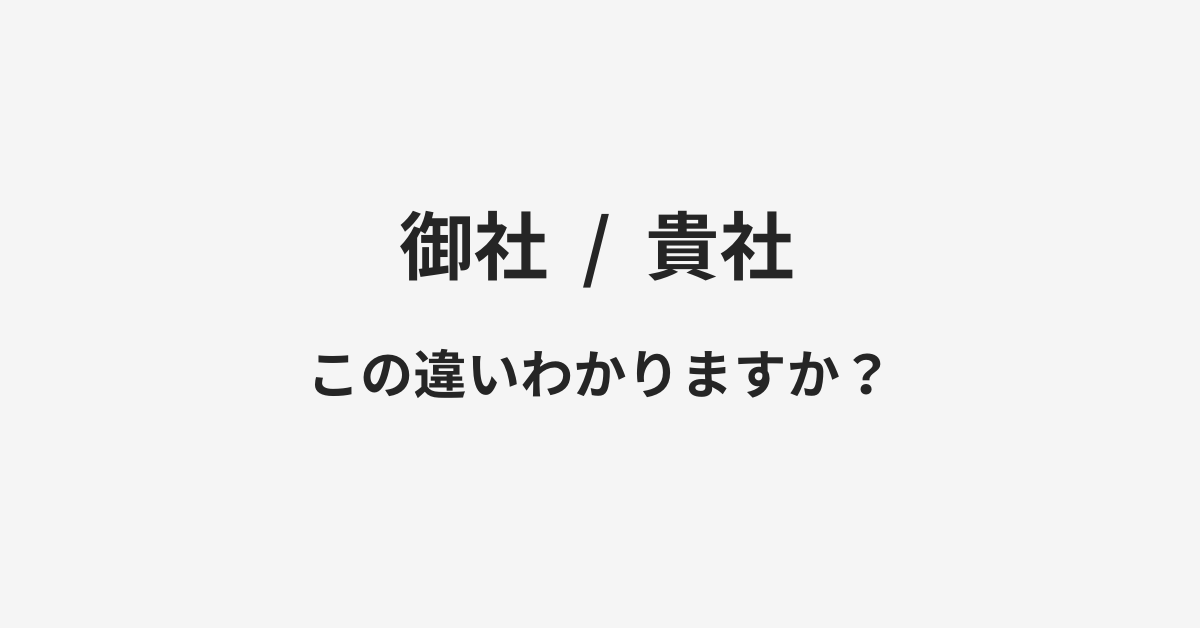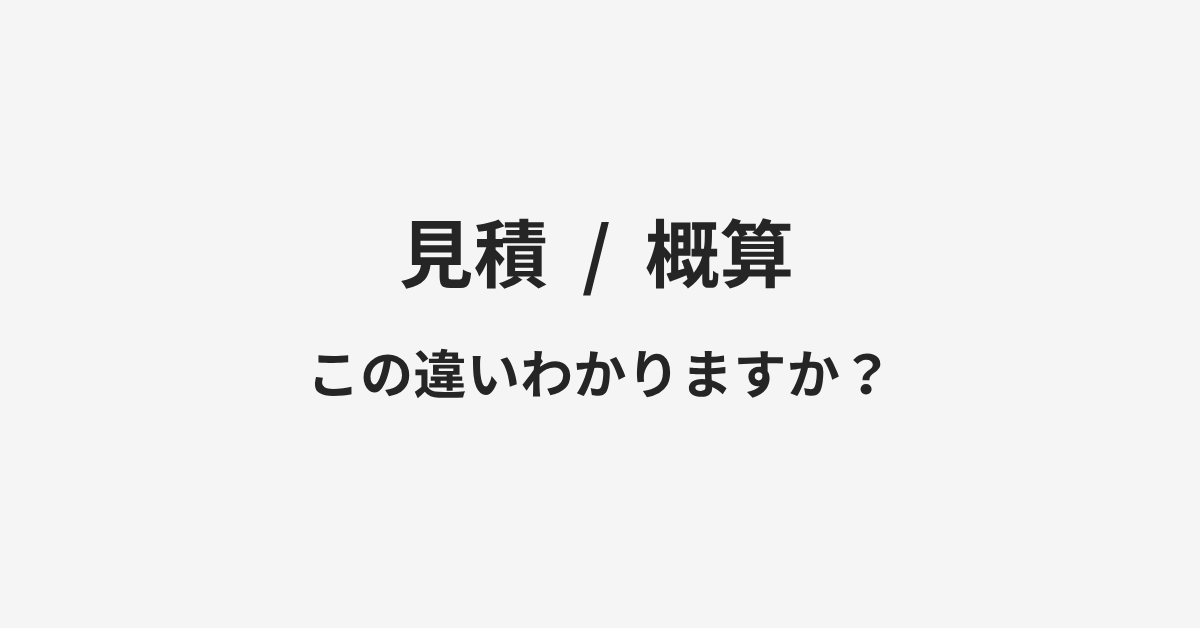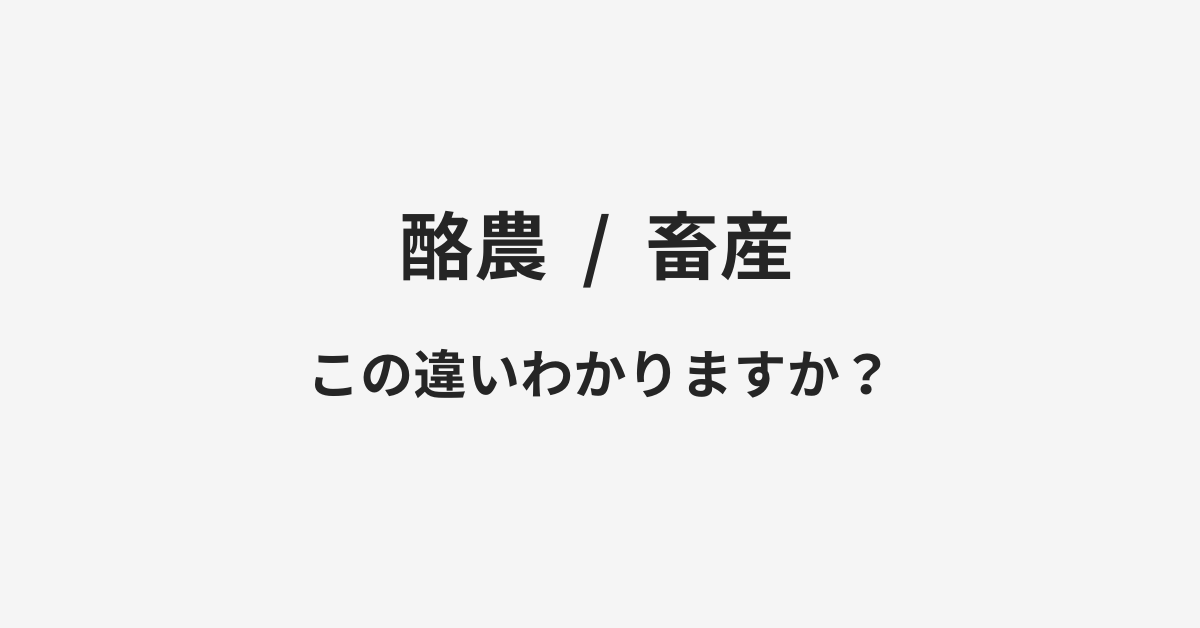【年商】と【売上高】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
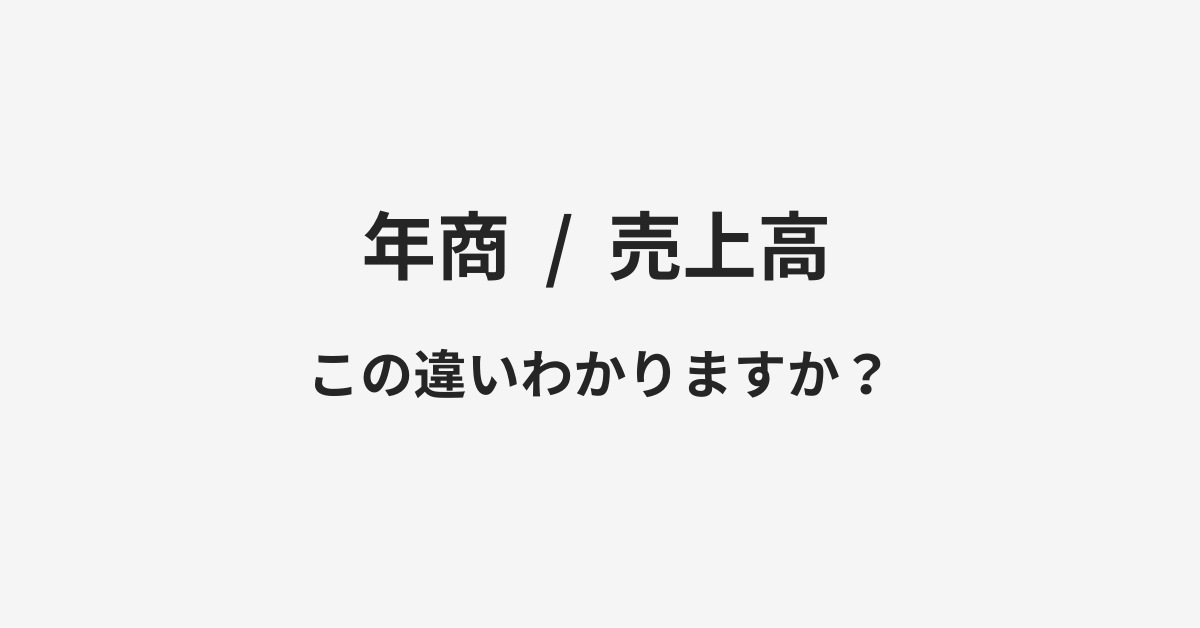
年商と売上高の分かりやすい違い
年商と売上高は、どちらも企業の1年間の売上を表しますが、その用途と正確性に違いがあります。
年商は事業規模を大まかに示す一般的な表現で、売上高は財務諸表に記載される正式な会計用語です。年商は概算値、売上高は監査済みの正確な数値という違いがあります。
ビジネスコミュニケーションにおいて、この違いを理解することは、適切な情報伝達と信頼性の確保に重要です。
年商とは?
年商とは、企業が1年間に売り上げた金額の総額を指す一般的な表現です。年間商い高の略で、事業規模を簡潔に表す際に使用されます。中小企業の紹介、営業トーク、メディア報道などで年商10億円の企業といった形で用いられ、企業の大まかな規模感を伝える指標となります。
年商は概算値で示されることが多く、約50億円100億円超といった表現が一般的です。税込・税抜の区別が曖昧な場合もあり、厳密性よりも分かりやすさを重視した表現といえます。創業間もない企業では、月商から年商を推計することもあります。
ビジネスの現場では、取引先の信用調査、市場規模の把握、競合分析などで年商が参考指標として活用されます。ただし、年商が大きくても利益が出ていない場合もあるため、企業評価には他の指標も併せて検討する必要があります。
年商の例文
- ( 1 ) 当社の年商は約30億円で、地域では中堅企業に位置付けられます。
- ( 2 ) 年商100億円を目標に、新規事業の立ち上げを進めています。
- ( 3 ) M&A対象企業の年商規模は、10億円以上を想定しています。
- ( 4 ) 創業5年で年商50億円を達成し、急成長を遂げています。
- ( 5 ) 年商ベースで見ると、前年比120%の成長を実現しました。
- ( 6 ) 取引先の年商を調査し、与信限度額を設定しています。
年商の会話例
売上高とは?
売上高とは、企業会計において、商品・サービスの販売によって得られた収益を表す正式な勘定科目です。損益計算書の最上段に記載され、企業の事業活動の成果を示す最も基本的な指標です。会計基準に従って厳密に計算され、監査対象となる重要な財務数値です。
売上高の計上は、実現主義の原則に基づき、商品の引渡しやサービスの提供が完了した時点で認識されます。売上値引き、返品、割戻しなどは売上高から控除されます。連結売上高、単体売上高、セグメント別売上高など、様々な切り口で分析されます。
投資家、金融機関、取引先などのステークホルダーは、売上高を企業評価の重要指標として注視します。売上高成長率、売上高営業利益率などの経営指標も、売上高を基に算出されます。
売上高の例文
- ( 1 ) 第3四半期の売上高は、前年同期比で15%増加しました。
- ( 2 ) 連結売上高1,000億円の達成に向けて、中期経営計画を策定しました。
- ( 3 ) セグメント別売上高を分析し、事業ポートフォリオを最適化します。
- ( 4 ) 売上高営業利益率10%を目指し、収益性改善に取り組んでいます。
- ( 5 ) 四半期ごとの売上高推移をモニタリングし、業績管理を行っています。
- ( 6 ) 売上高の計上基準を見直し、収益認識の適正化を図りました。
売上高の会話例
年商と売上高の違いまとめ
年商と売上高の主な違いは、使用場面と正確性にあります。年商は日常的なビジネス会話での概算表現、売上高は財務報告での正確な数値という使い分けがあります。
信頼性も異なり、売上高は監査済みの公式数値、年商は未監査の概算値であることが多いです。年商約100億円と売上高103.5億円では、後者の方が信頼性が高いです。
実務では、正式な文書や財務分析では売上高、一般的な説明や営業活動では年商を使用することが適切です。目的に応じた使い分けが重要です。
年商と売上高の読み方
- 年商(ひらがな):ねんしょう
- 年商(ローマ字):nennshou
- 売上高(ひらがな):うりあげだか
- 売上高(ローマ字):uriagedaka