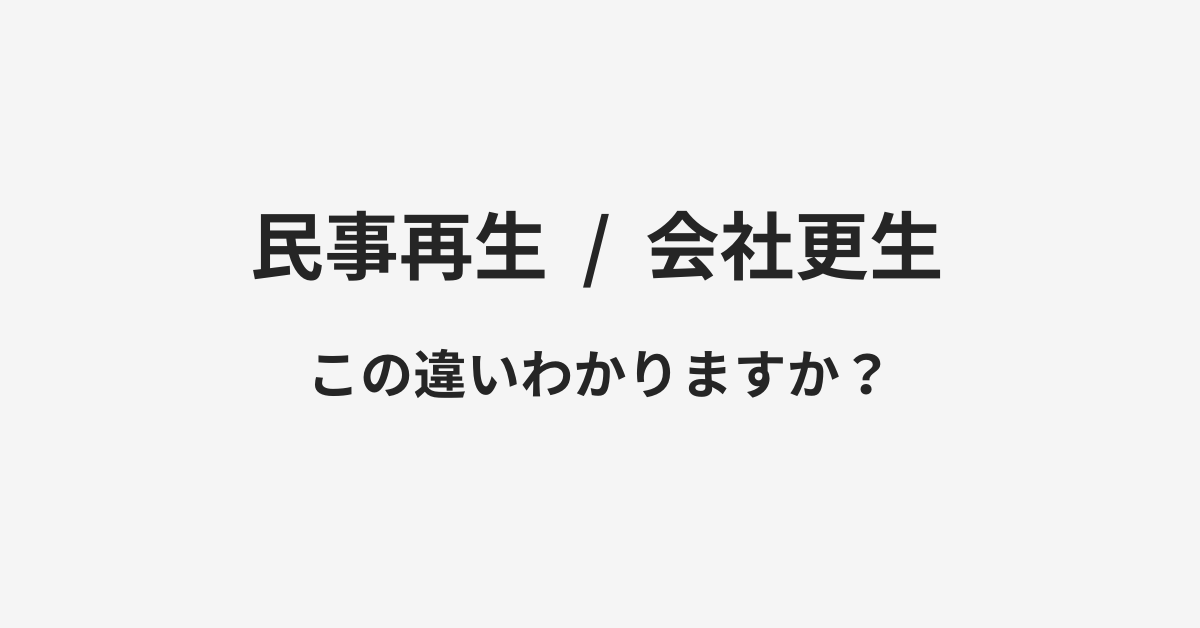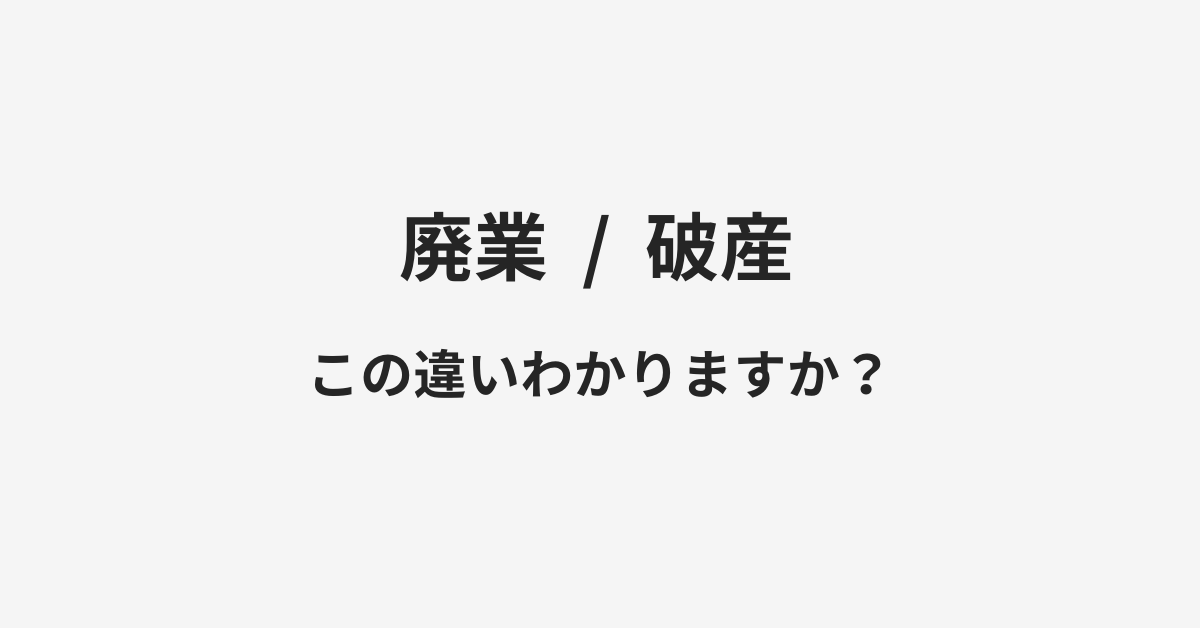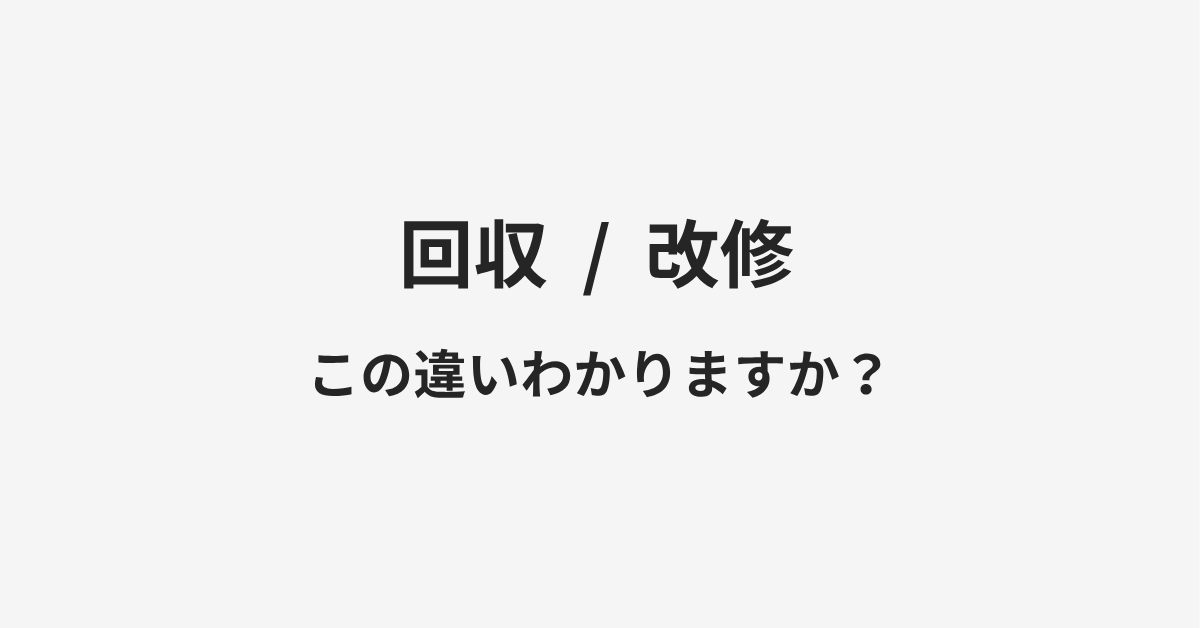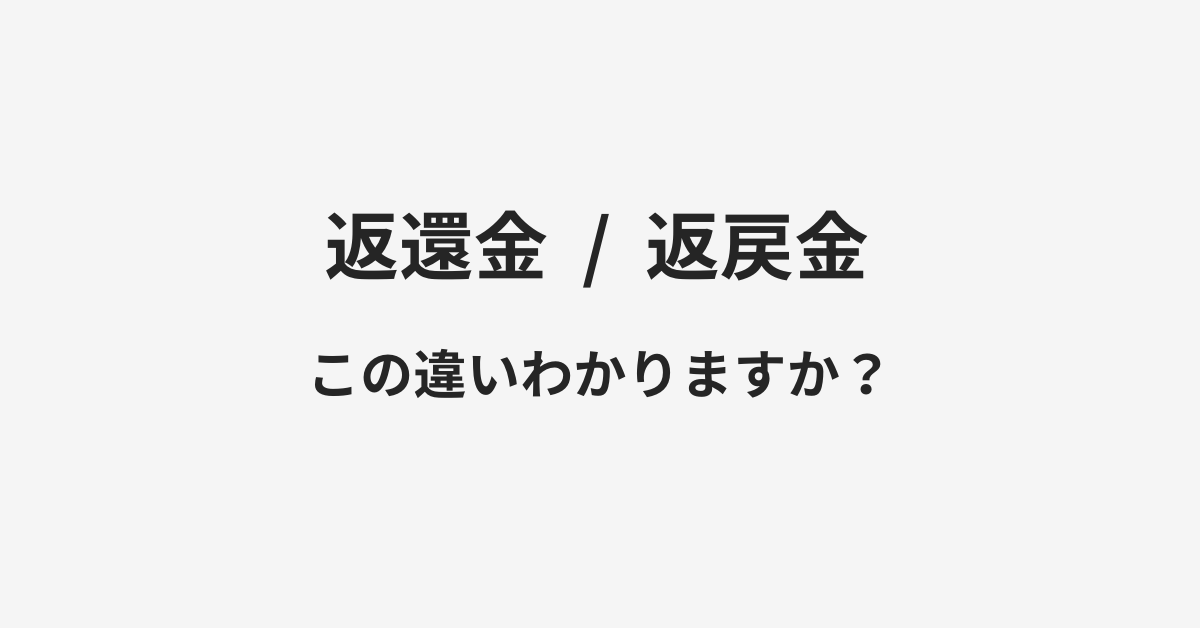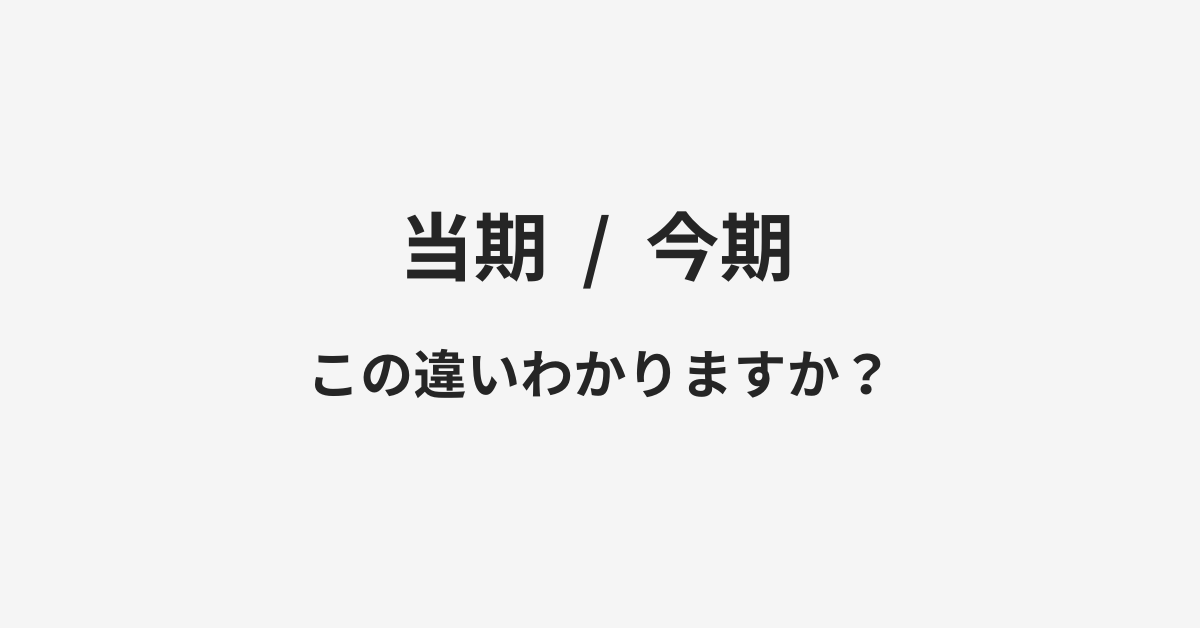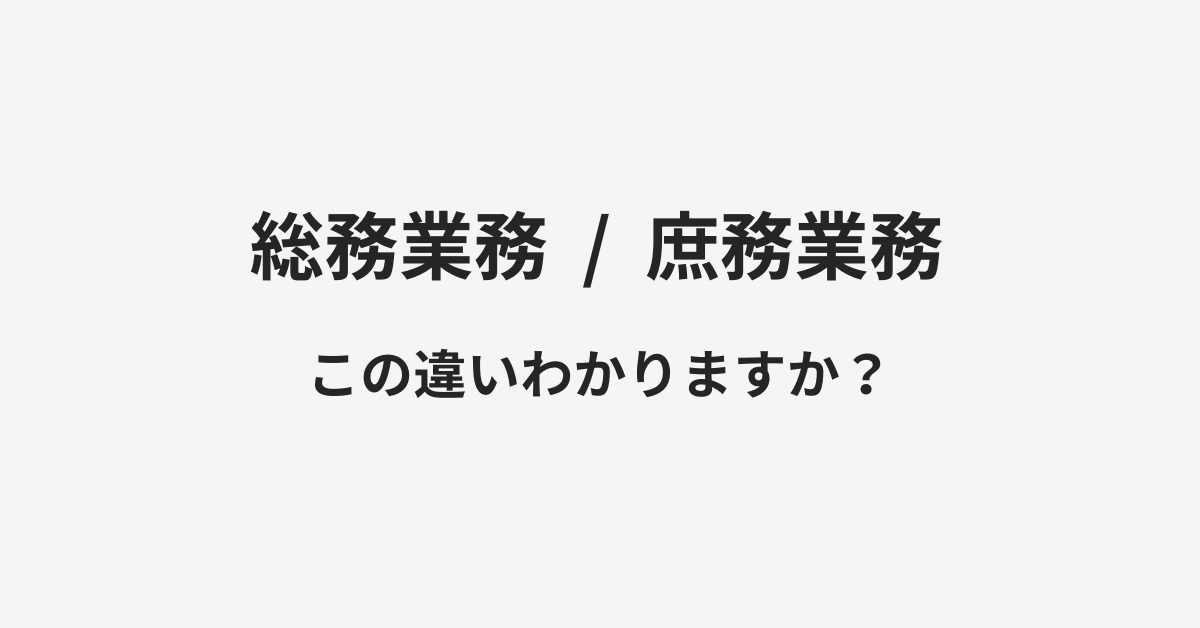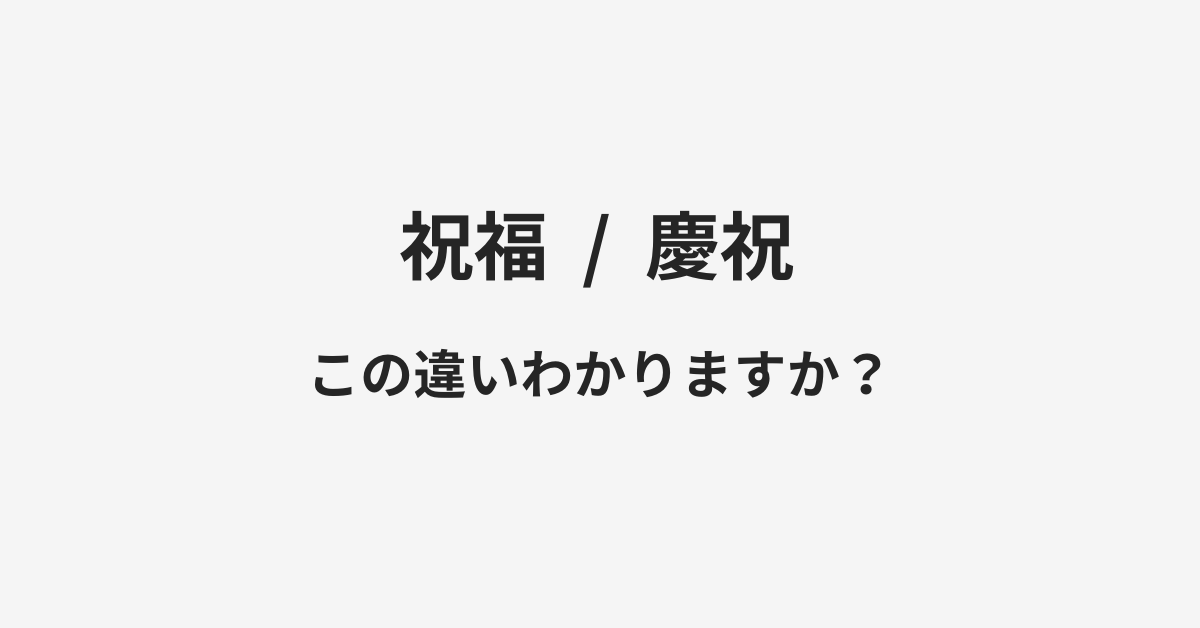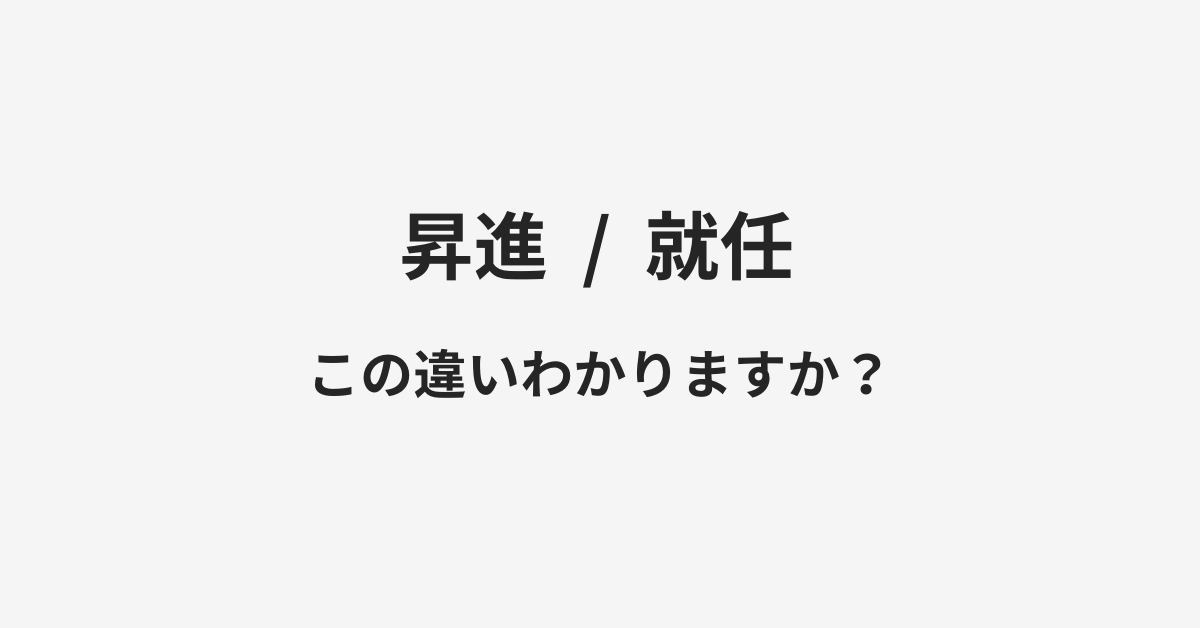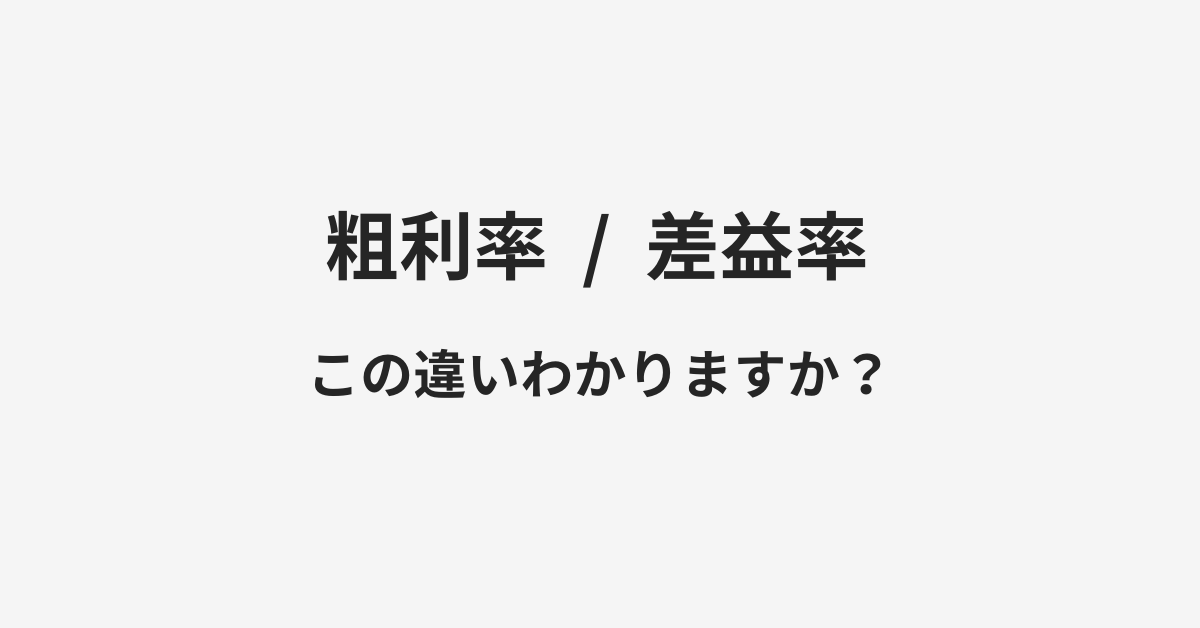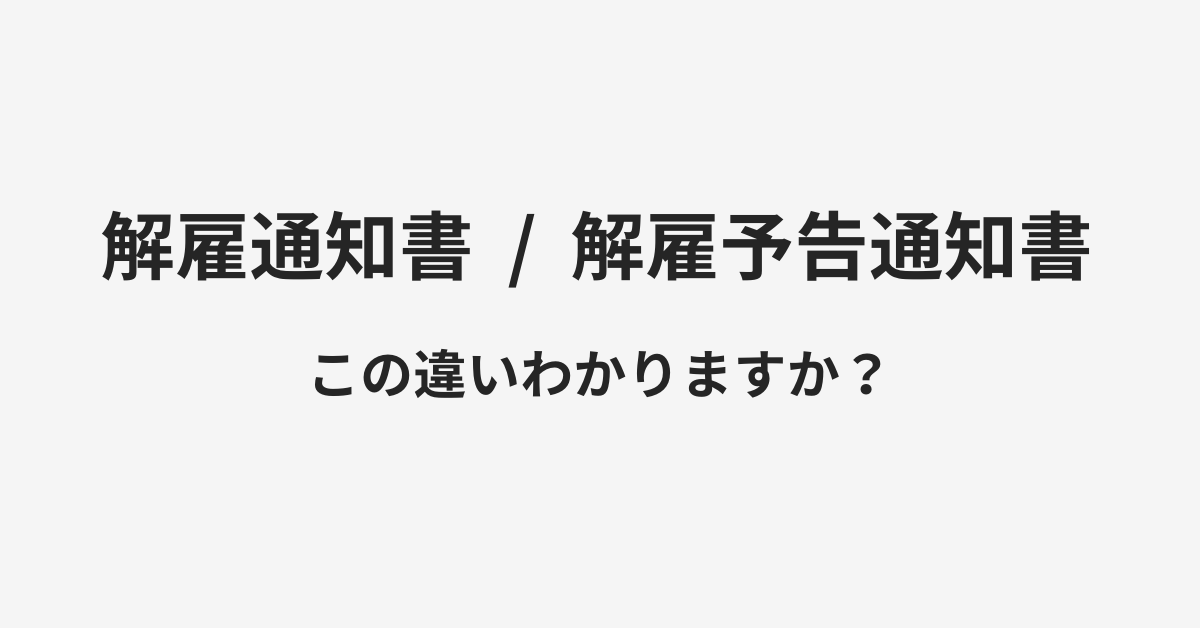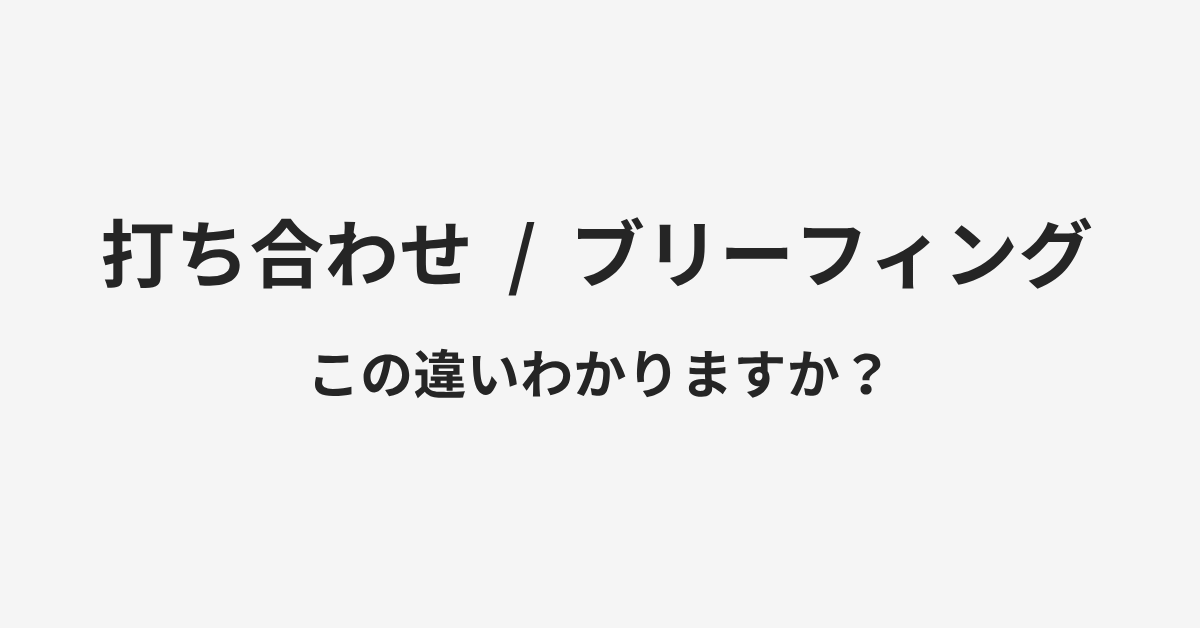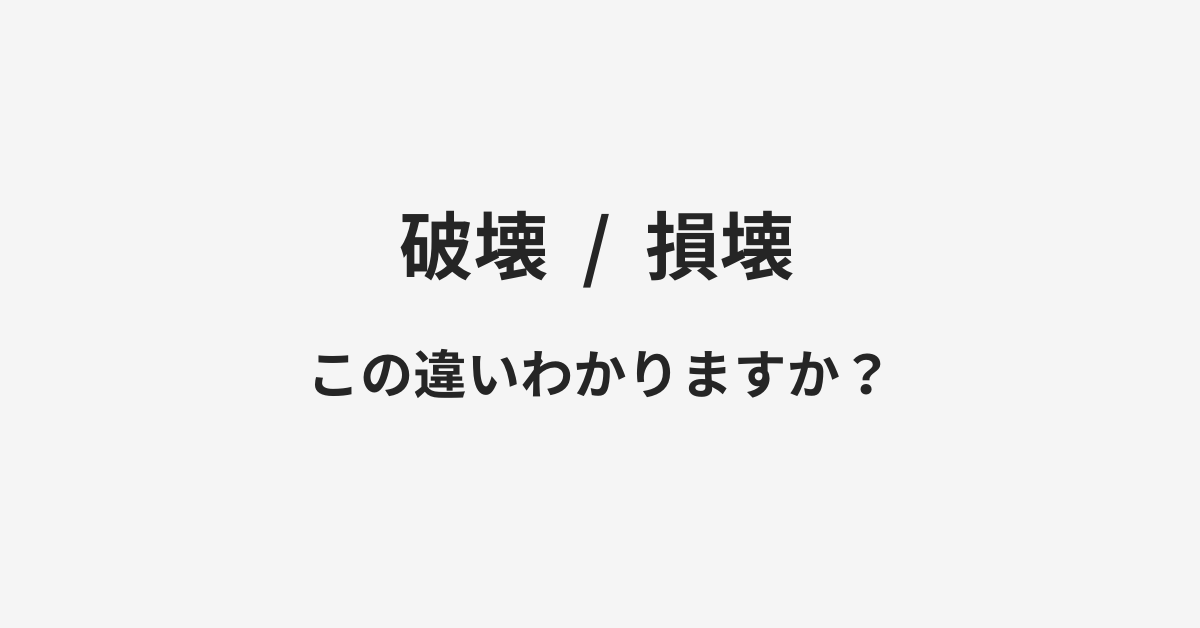【民事再生】と【破産】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
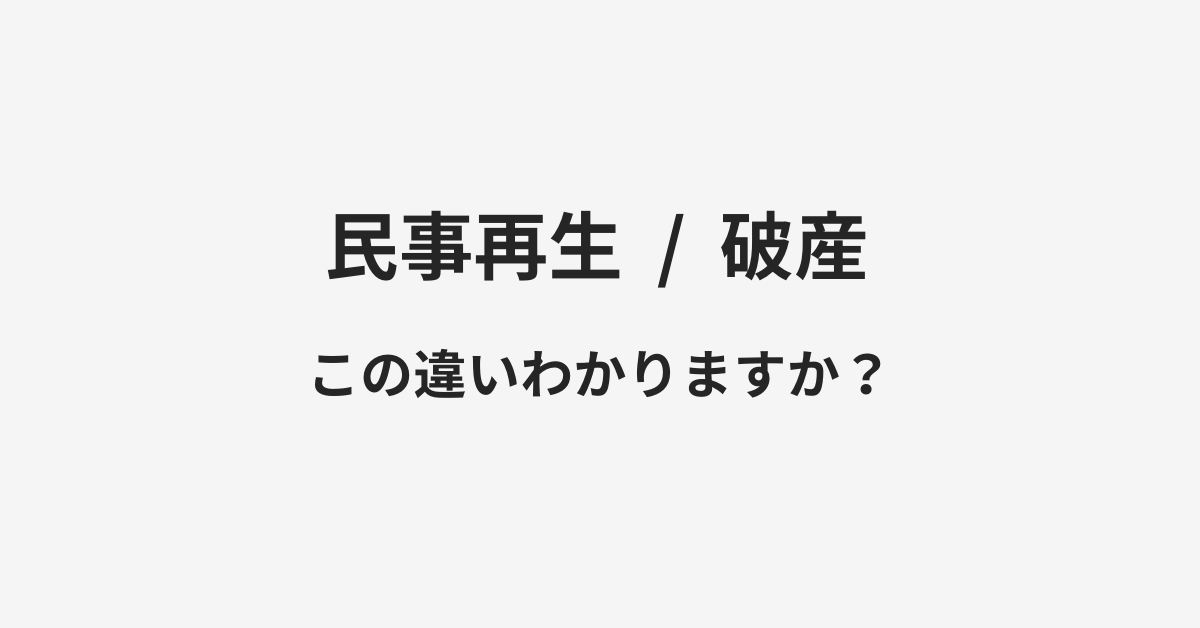
民事再生と破産の分かりやすい違い
民事再生と破産は、どちらも経営困難に陥った企業が利用する法的手続きですが、その目的と結果が大きく異なります。
民事再生は企業の再建を目指す手続きで、事業を継続しながら債務を整理します。これに対して破産は企業の清算を目的とし、事業を停止して財産を換金し、債権者に配当する手続きです。
経営者にとって、民事再生は企業存続の最後のチャンスであり、破産は事業継続を断念する最終手段となります。どちらを選択するかは、企業の再建可能性によって決まります。
民事再生とは?
民事再生とは、経営困難に陥った企業が、裁判所の監督のもとで事業を継続しながら、債権者との合意に基づいて債務を圧縮し、経営の再建を図る法的手続きです。民事再生法に基づいて行われ、企業の存続と雇用の維持を前提としています。
この手続きでは、再生計画案を作成し、債権者集会での可決と裁判所の認可を得ることで、債務の一部免除や支払期限の延長が可能になります。経営陣は原則として退陣せず、事業運営を継続できるため、取引先との関係も維持しやすいという特徴があります。
民事再生は、一時的な資金繰りの悪化や過大な債務負担に苦しむものの、事業自体には収益力があり、再建の見込みがある企業にとって有効な選択肢となります。手続き期間は通常6か月程度と比較的短期間で完了します。
民事再生の例文
- ( 1 ) 当社は民事再生手続きの申請を決定し、事業継続を前提とした再建計画の策定に着手しました。
- ( 2 ) 製造業のA社が民事再生法の適用を申請し、主力事業に経営資源を集中する再生計画案を発表しました。
- ( 3 ) 民事再生手続き開始後も、取引先との契約は継続され、通常通りの営業活動を行っています。
- ( 4 ) 小売業のB社は、民事再生により不採算店舗を整理し、3年後に経常黒字化を達成しました。
- ( 5 ) 民事再生手続きにおいて、債権者の同意を得て債務の70%カットに成功し、財務体質が大幅に改善されました。
- ( 6 ) 建設会社のC社は、民事再生を経て新たなスポンサー企業の支援を受け、事業再建に成功しました。
民事再生の会話例
破産とは?
破産とは、債務超過に陥り支払不能となった企業が、裁判所の監督のもとで事業を停止し、保有する財産をすべて換金して債権者に公平に配当する法的手続きです。破産法に基づいて行われ、企業は最終的に消滅することになります。
破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人が企業の財産を管理・処分し、債権者への配当を行います。経営者は経営権を失い、従業員は原則として解雇されます。取引先との契約も終了し、事業の継続は不可能となります。
破産は、事業の再建が困難で、これ以上の経営継続が債権者や従業員、取引先に更なる損害を与える可能性がある場合の最終手段です。手続きには通常1年以上かかり、配当率も低くなることが多いため、債権者にとっても厳しい結果となります。
破産の例文
- ( 1 ) 老舗企業のD社が破産手続き開始を申請し、全従業員300名の解雇を発表しました。
- ( 2 ) 破産管財人が選任され、会社資産の調査と換価処分の準備が開始されました。
- ( 3 ) E社の破産により、売掛金の回収が困難となり、当社も貸倒引当金を計上することになりました。
- ( 4 ) 破産手続きにおける債権者集会で、配当率は10%程度になる見込みであることが報告されました。
- ( 5 ) F社は破産申請と同時に事業を停止し、全店舗が即日閉鎖されました。
- ( 6 ) 破産したG社の知的財産権が競売にかけられ、同業他社が落札しました。
破産の会話例
民事再生と破産の違いまとめ
民事再生と破産の最も重要な違いは、企業の存続可能性にあります。民事再生は企業を存続させながら再建を図るのに対し、破産は企業を消滅させて清算することを目的とします。
手続き面でも、民事再生では経営陣が引き続き事業運営を行えますが、破産では破産管財人に経営権が移ります。また、民事再生は6か月程度で完了しますが、破産は1年以上かかることが一般的です。
企業が経営危機に直面した際は、まず民事再生による再建の可能性を検討し、それが困難な場合に破産を選択するという順序で検討することが、ステークホルダーへの責任を果たす上で重要です。
民事再生と破産の読み方
- 民事再生(ひらがな):みんじさいせい
- 民事再生(ローマ字):minnjisaisei
- 破産(ひらがな):はさん
- 破産(ローマ字):hasann