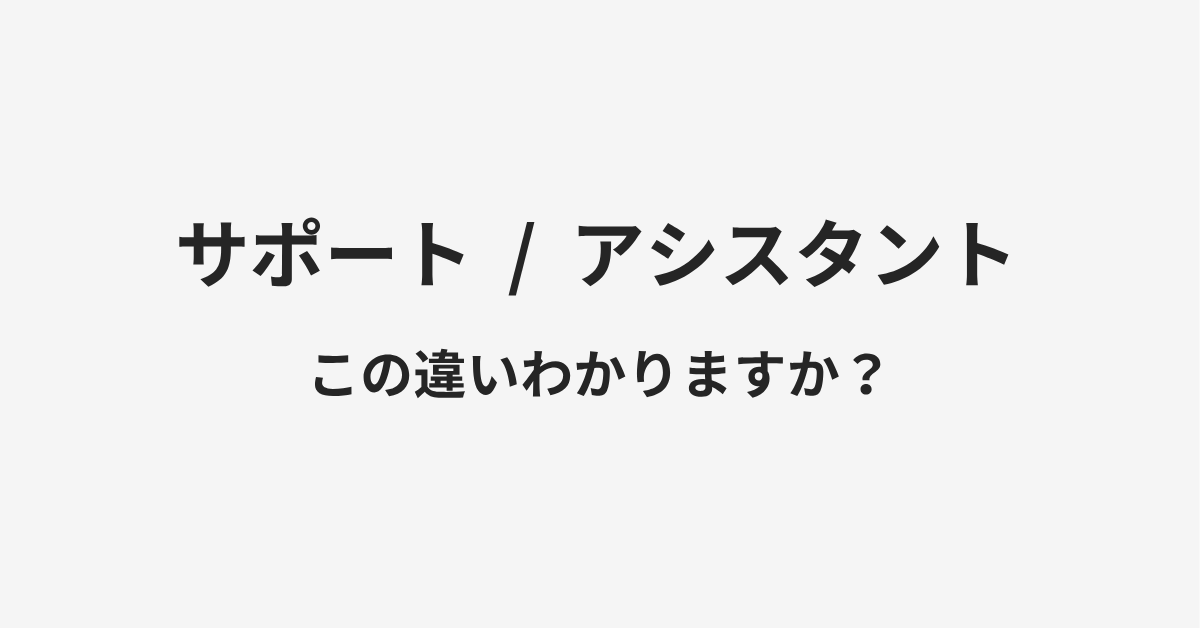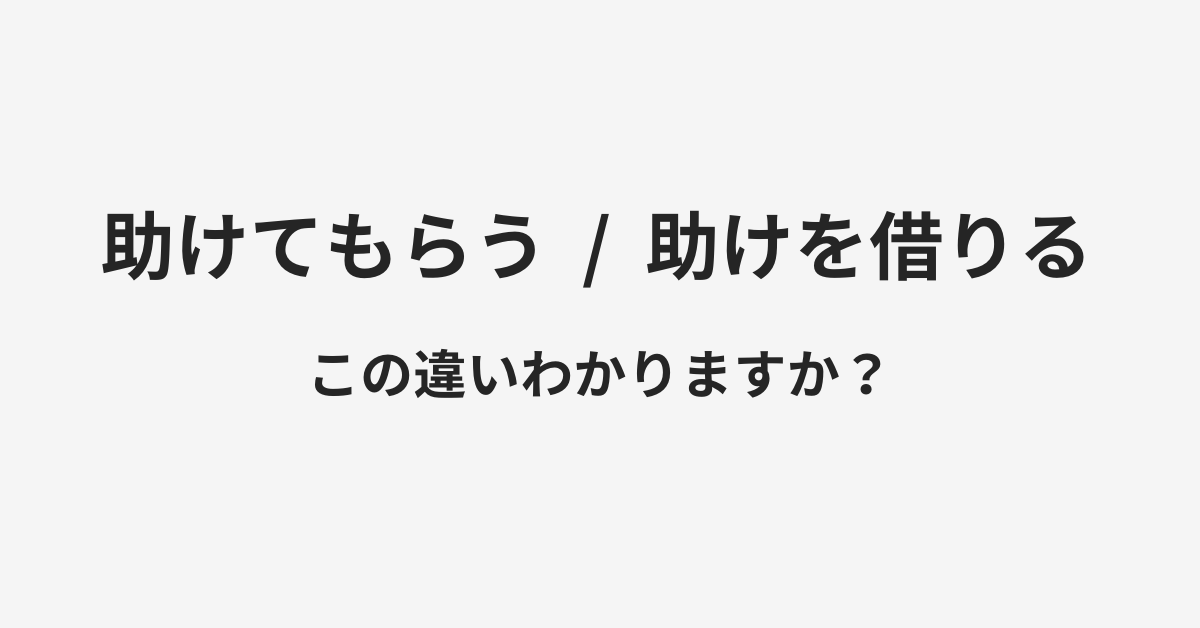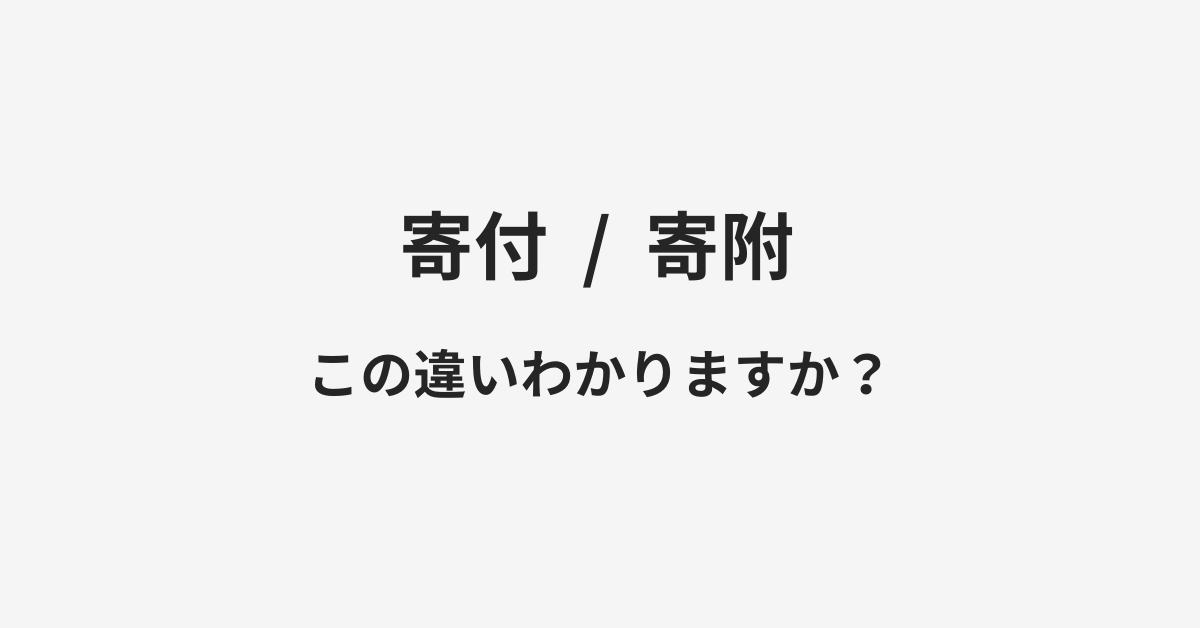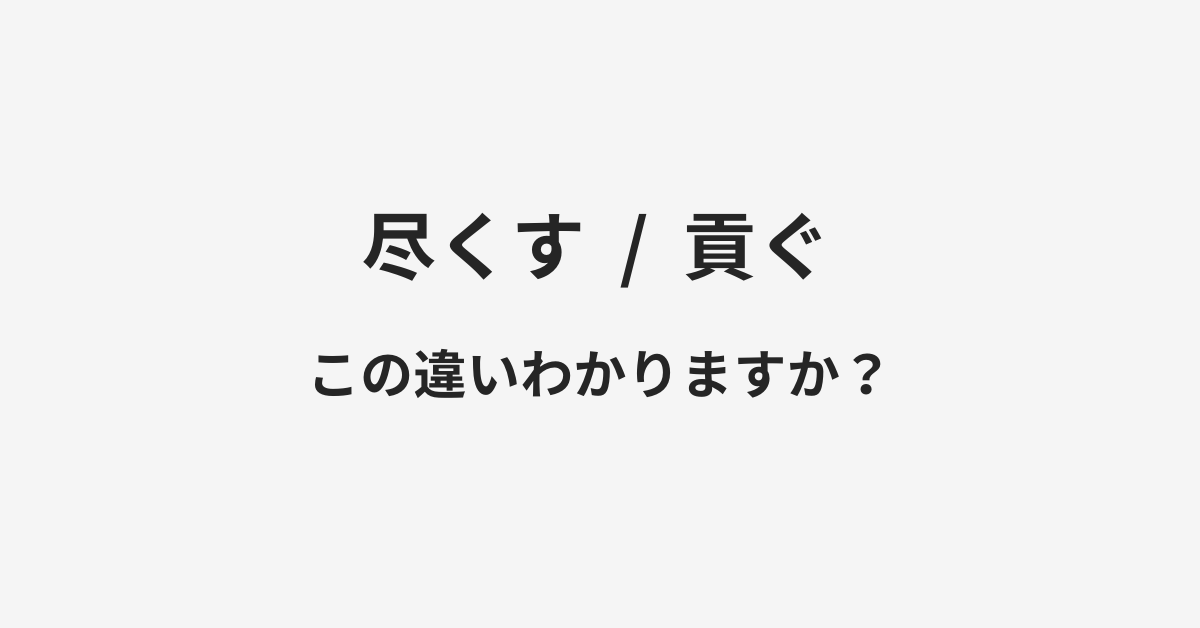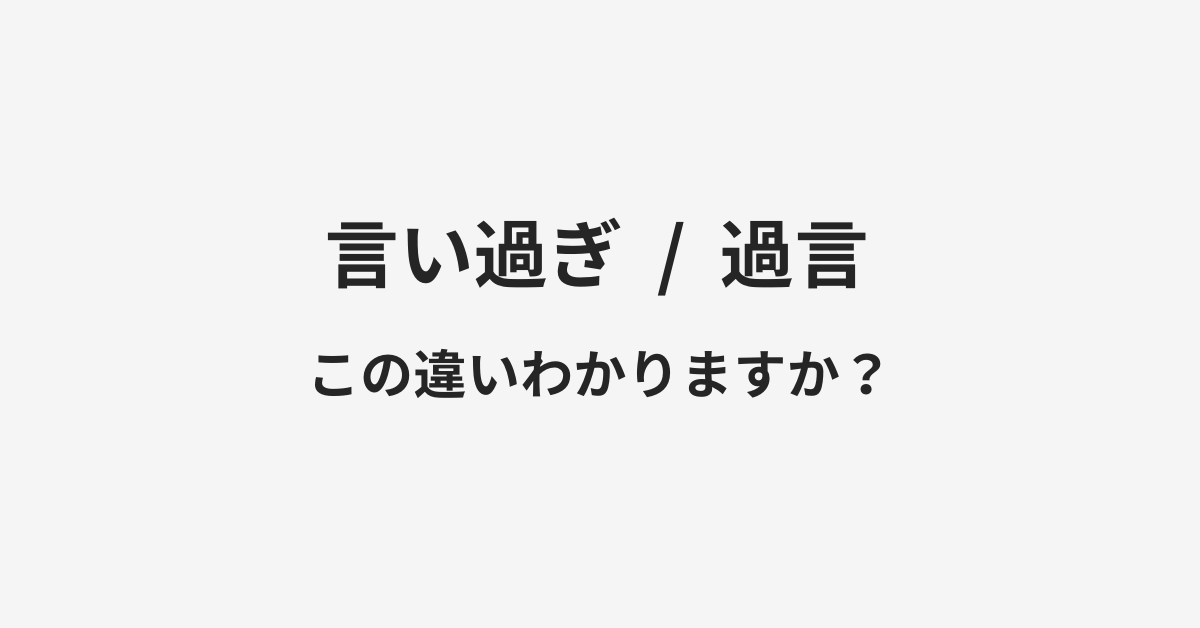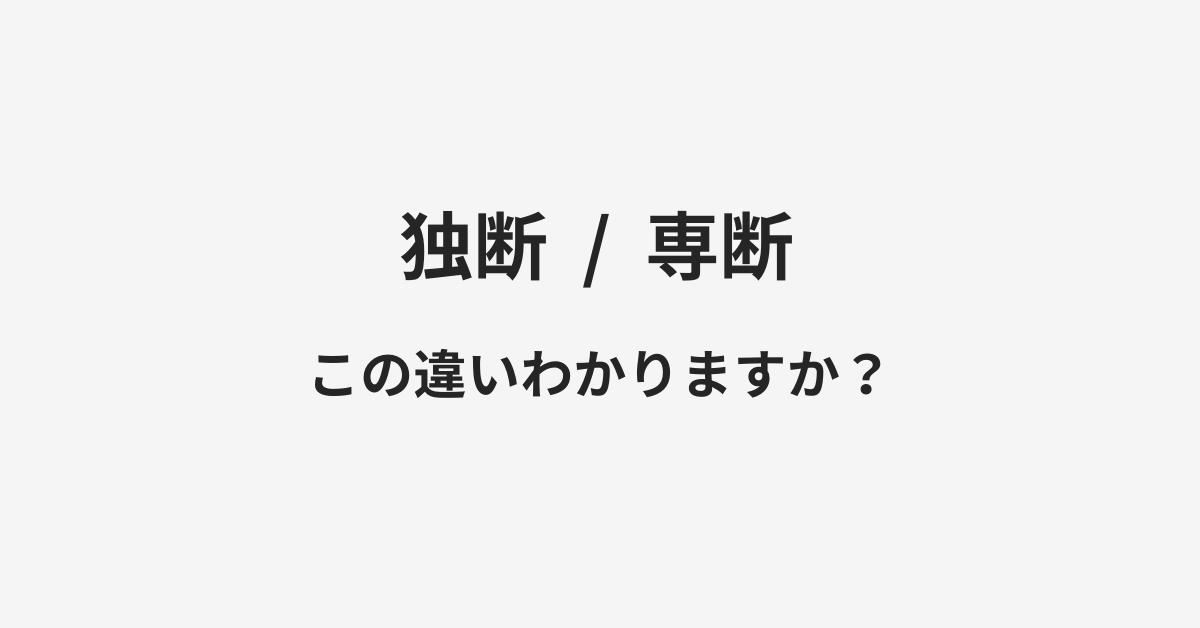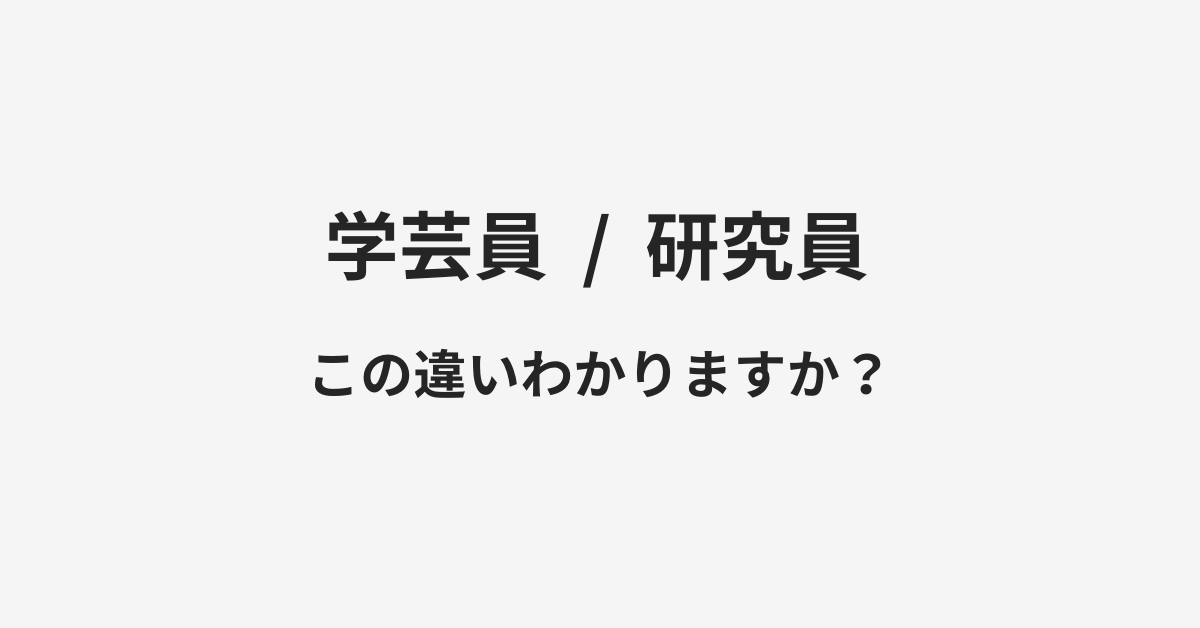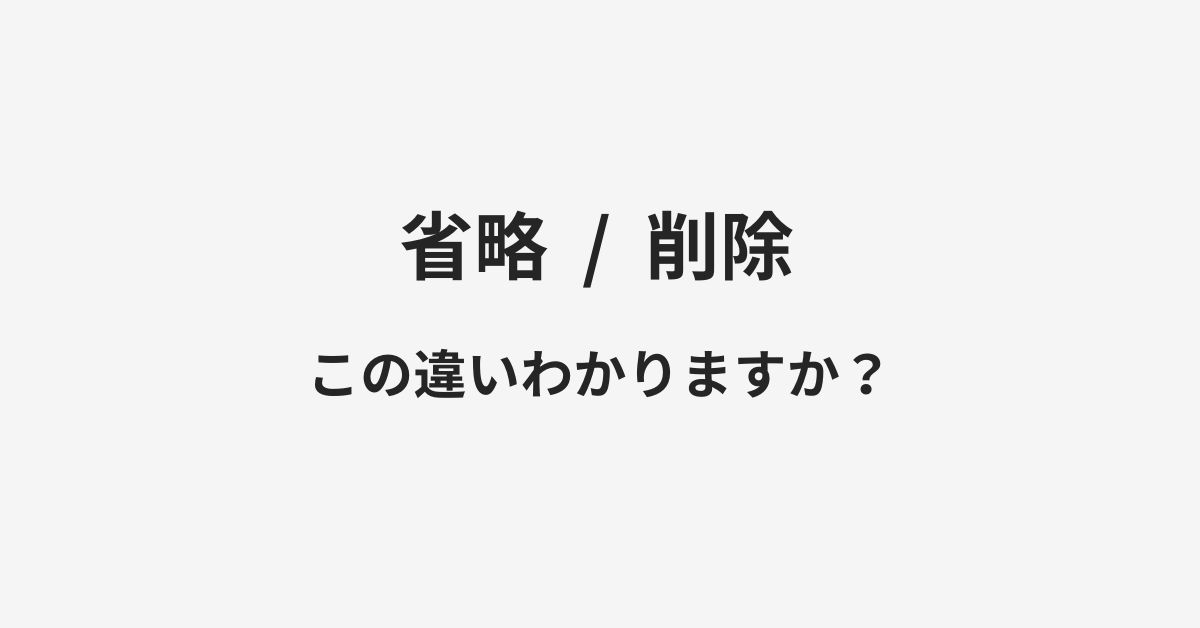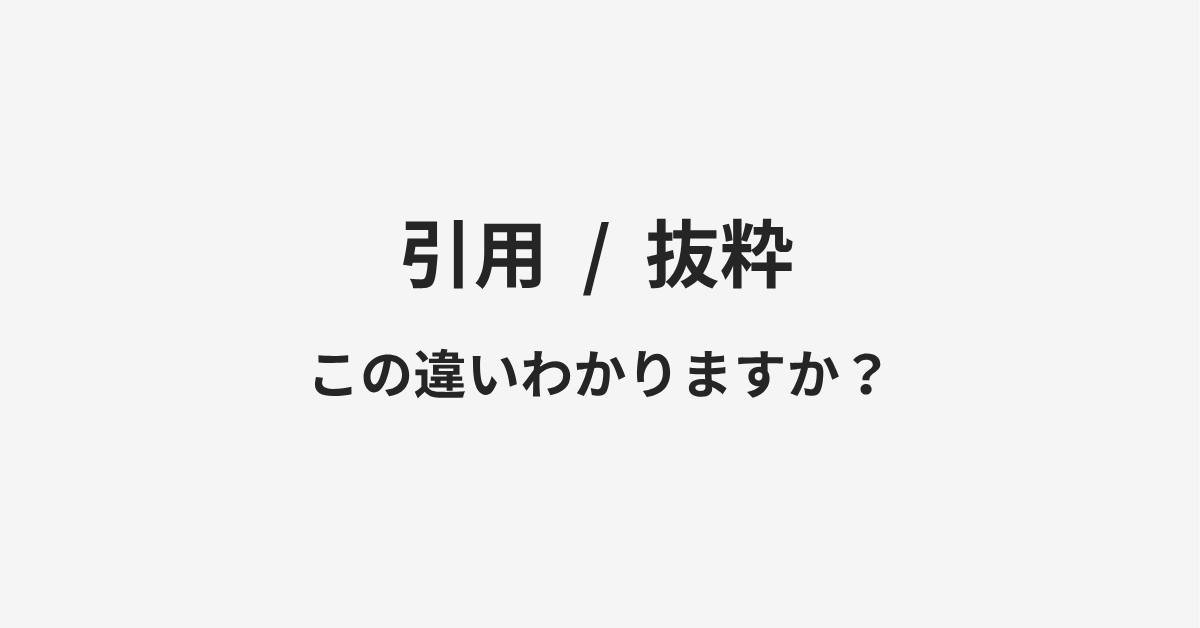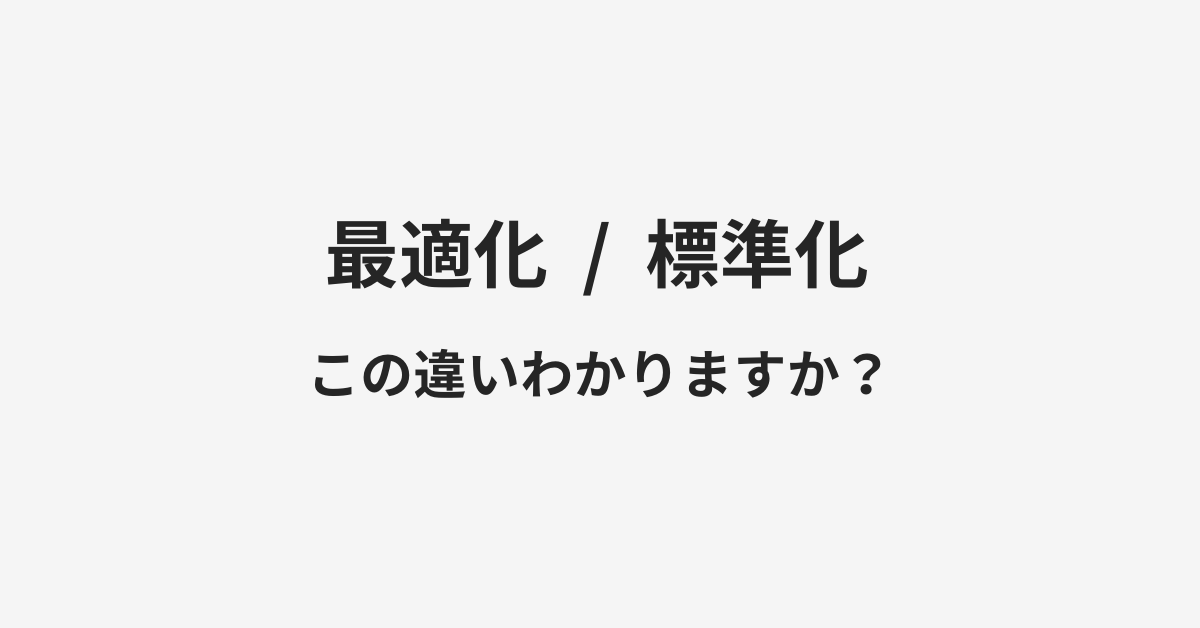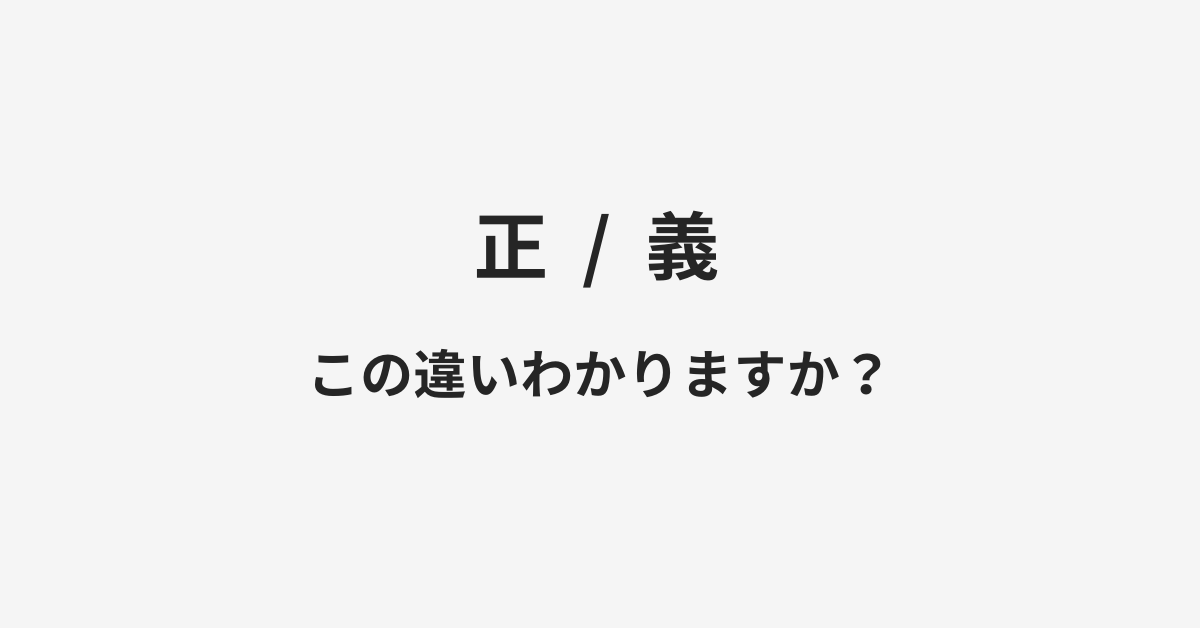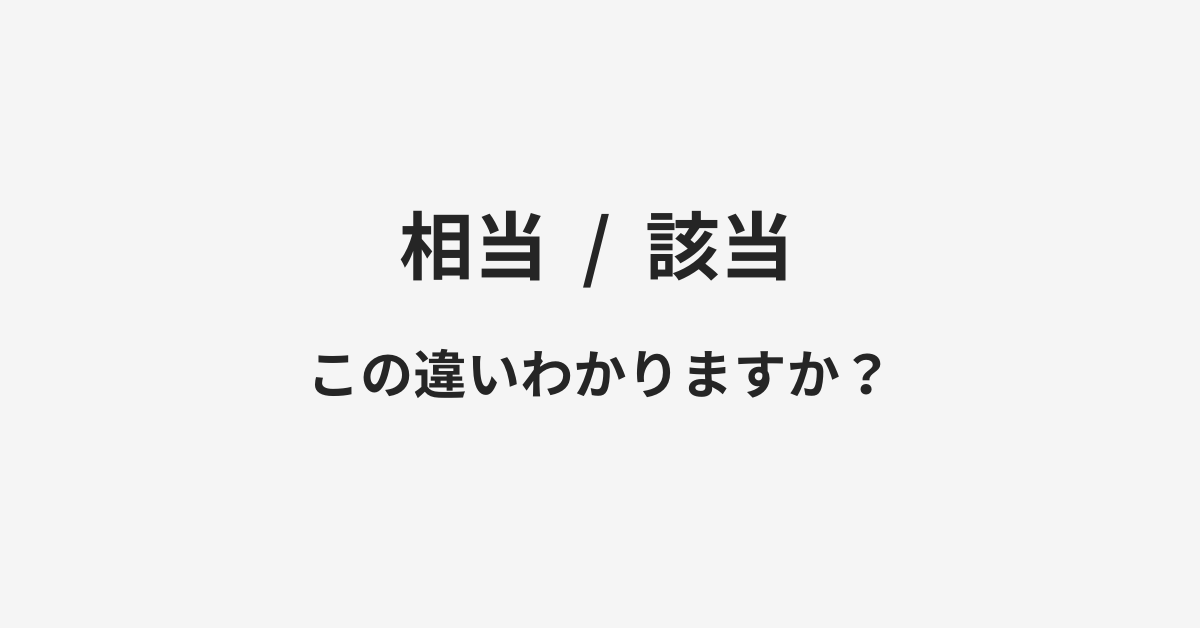【縁の下の力持ち】と【内助の功】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

縁の下の力持ちと内助の功の分かりやすい違い
縁の下の力持ちと内助の功は、どちらも陰で支える存在ですが、対象が異なります。
縁の下の力持ちは誰でも、内助の功は妻が夫を支える場合に使います。
スタッフは「縁の下の力持ち」、妻の支えは「内助の功」という使い分けです。
縁の下の力持ちとは?
縁の下の力持ちとは、表舞台には出ないが、陰で重要な役割を果たし、全体を支えている人のことを指します。建物の縁の下で建物を支える力持ちのように、目立たないが欠かせない存在を表す慣用句です。性別、年齢、関係性を問わず、裏方として活躍する人全般に使えます。
「彼は縁の下の力持ちだ」「縁の下の力持ちとして支える」「縁の下の力持ち的存在」など、陰の功労者を称える時に使います。謙虚で献身的な人への賞賛の言葉です。
舞台スタッフ、事務職員、サポート役など、表に出ないが重要な仕事をする人を評価する時に使われる、温かみのある表現です。
縁の下の力持ちの例文
- ( 1 ) 総務部は会社の縁の下の力持ちだ。
- ( 2 ) 彼女は縁の下の力持ちとしてチームを支えた。
- ( 3 ) 縁の下の力持ちの存在に感謝している。
- ( 4 ) 裏方スタッフは縁の下の力持ちだ。
- ( 5 ) 縁の下の力持ちがいるから成功できる。
- ( 6 ) 自分も縁の下の力持ちとして貢献したい。
縁の下の力持ちの会話例
内助の功とは?
内助の功とは、妻が家庭を守り、夫の仕事や活動を陰から支えることで、夫の成功に貢献することを指す慣用句です。伝統的な夫婦の役割分担を前提とした表現で、主に妻の献身的なサポートを称える時に使われます。現代では性別役割の固定化という観点から、使用に配慮が必要な場合もあります。
「内助の功あって」「妻の内助の功」「内助の功に感謝」など、夫の成功の陰に妻の支えがあることを表現します。主に年配の方が使うことが多い表現です。
家事全般、精神的サポート、社交面での支援など、妻が夫を支える様々な形を表す伝統的な表現として、特定の文脈で使われます。
内助の功の例文
- ( 1 ) 社長の成功は妻の内助の功があってこそだ。
- ( 2 ) 内助の功に支えられて研究を続けられた。
- ( 3 ) 妻の内助の功なくして今の自分はない。
- ( 4 ) 内助の功という言葉は時代遅れかもしれない。
- ( 5 ) 彼は内助の功に感謝していた。
- ( 6 ) 内助の功を認めることも大切だ。
内助の功の会話例
縁の下の力持ちと内助の功の違いまとめ
縁の下の力持ちは性別・関係不問の陰の支え手、内助の功は妻の夫への支えです。
縁の下の力持ちは現代的で広く使える、内助の功は伝統的で限定的な表現です。
職場では縁の下の力持ち、夫婦関係では状況に応じて使い分けましょう。
縁の下の力持ちと内助の功の読み方
- 縁の下の力持ち(ひらがな):えんのしたのちからもち
- 縁の下の力持ち(ローマ字):ennnoshitanochikaramochi
- 内助の功(ひらがな):ないじょのこう
- 内助の功(ローマ字):naijonokou