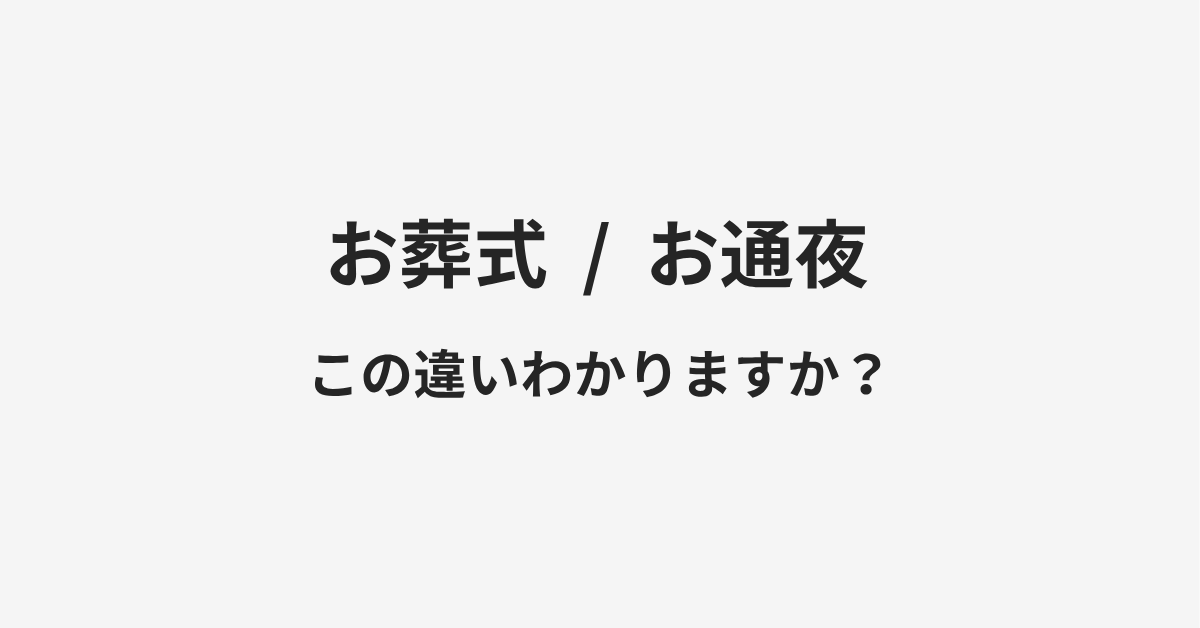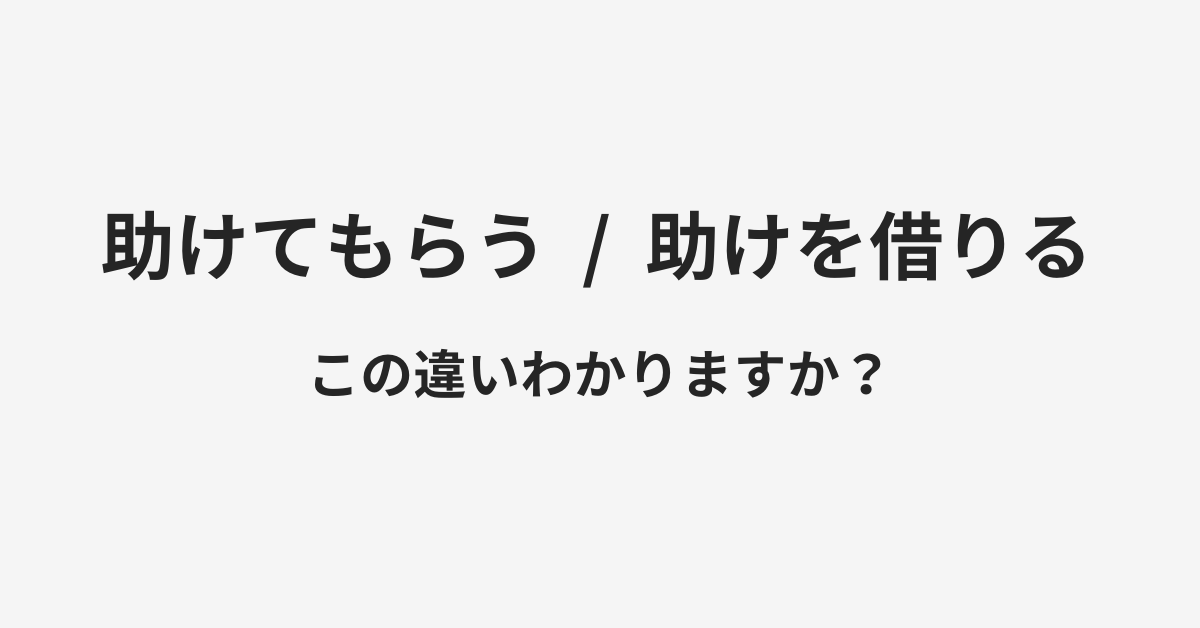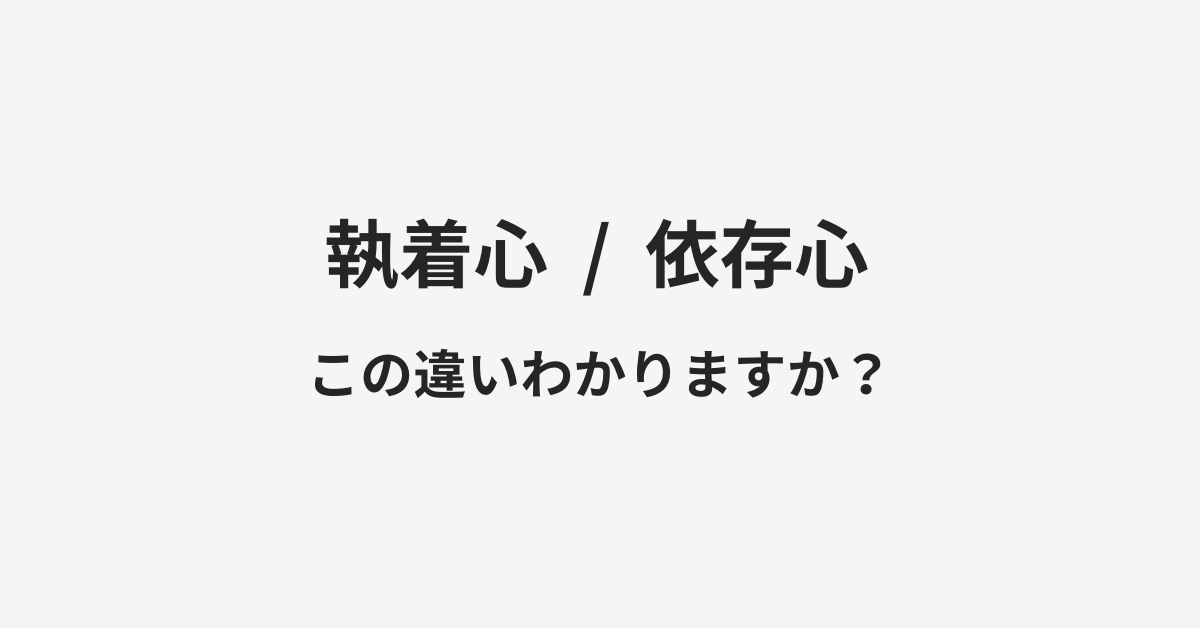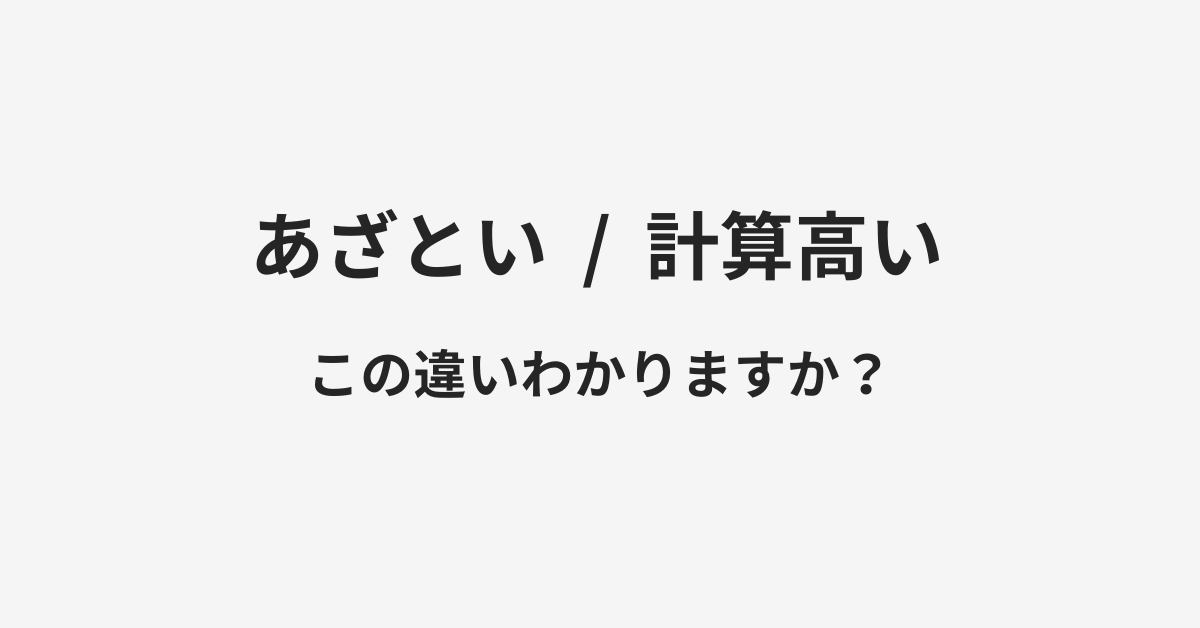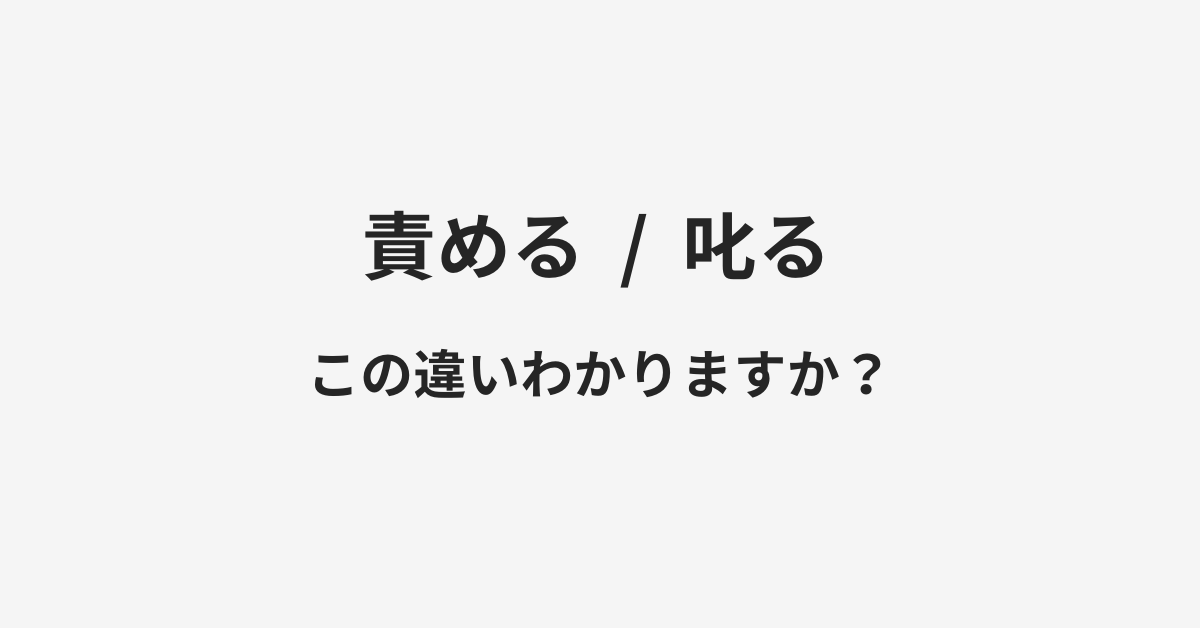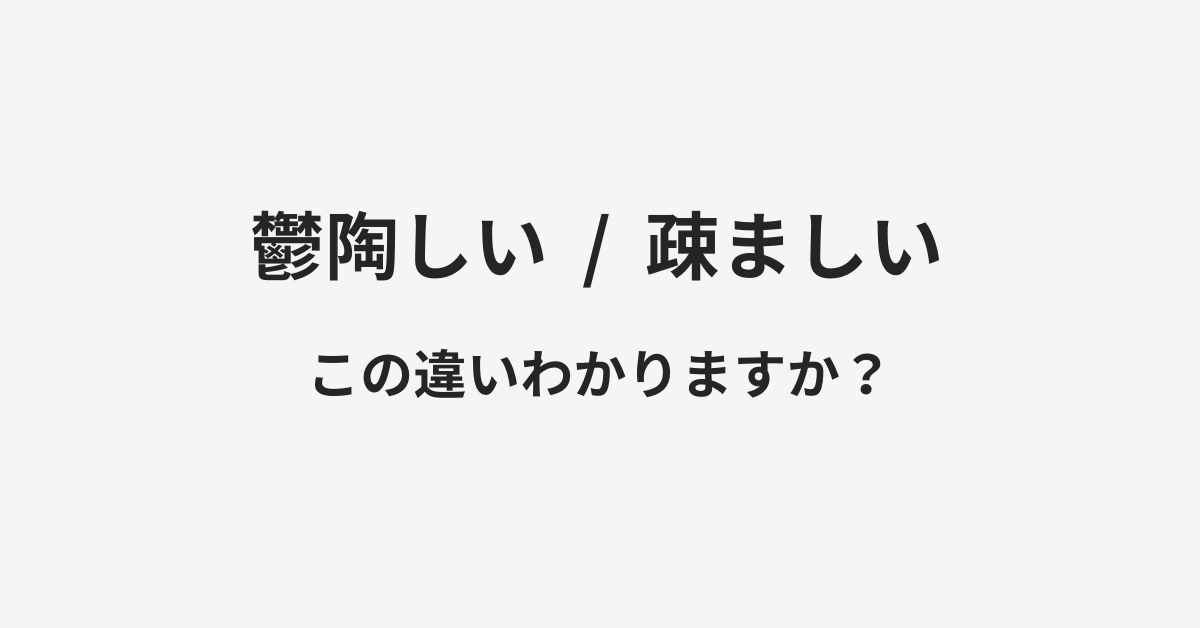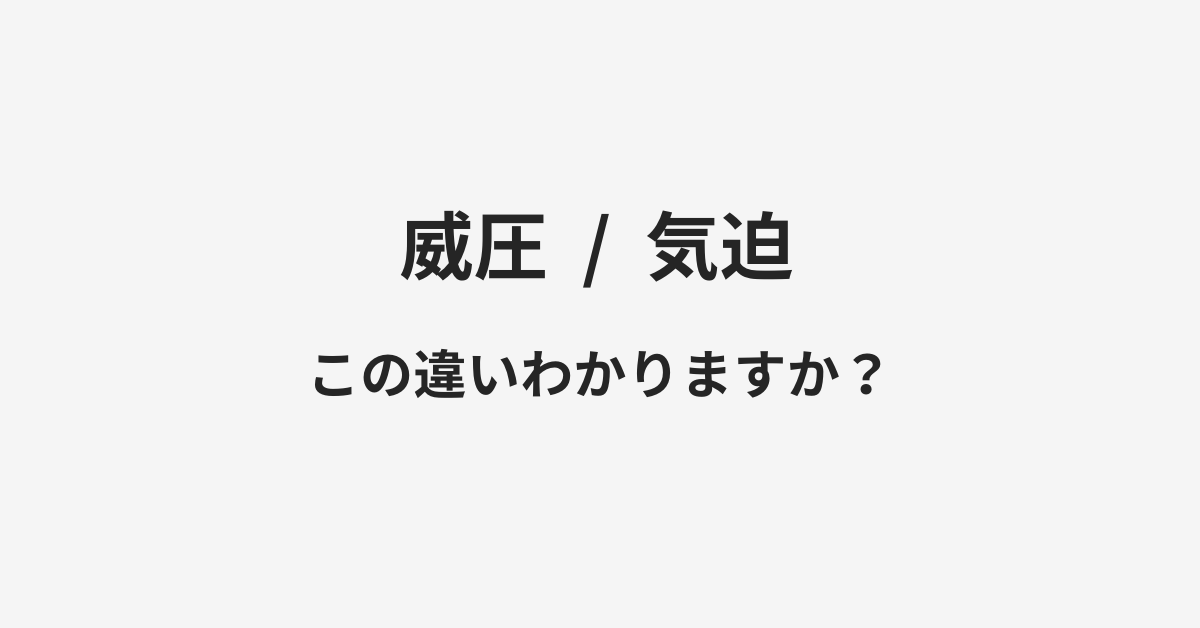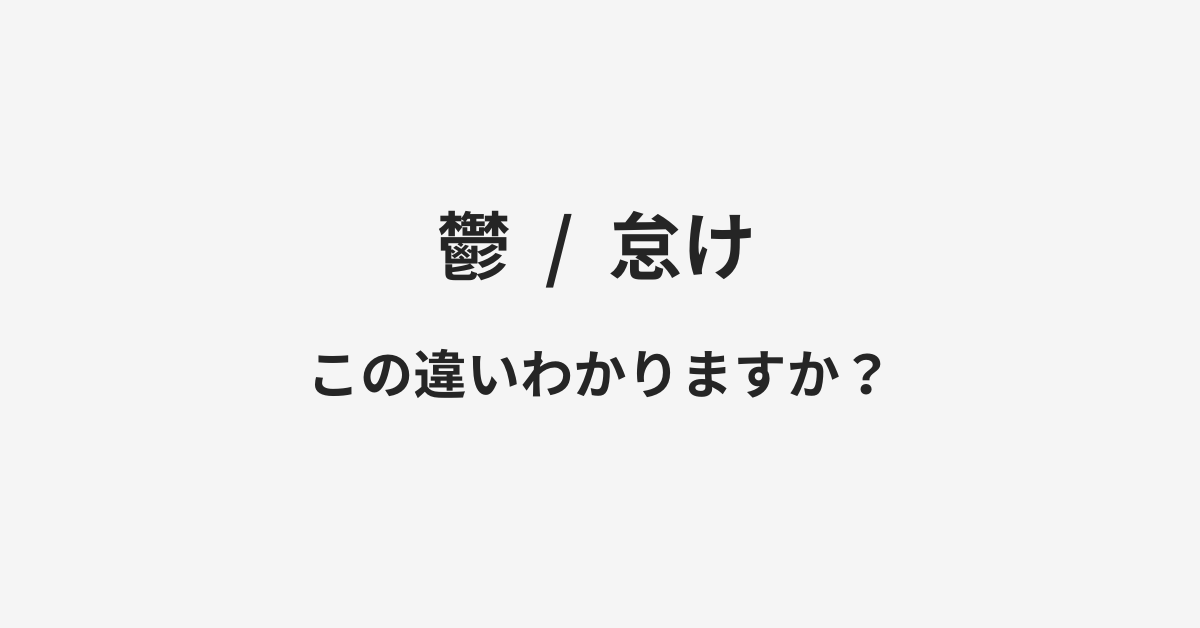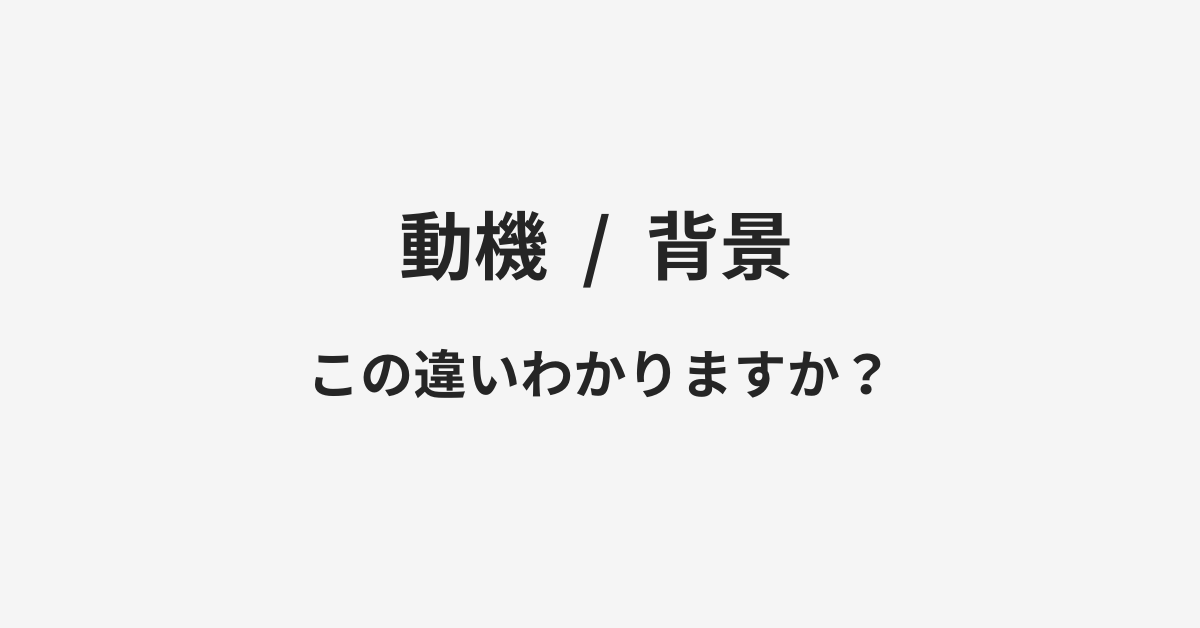【逝く】と【果てる】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
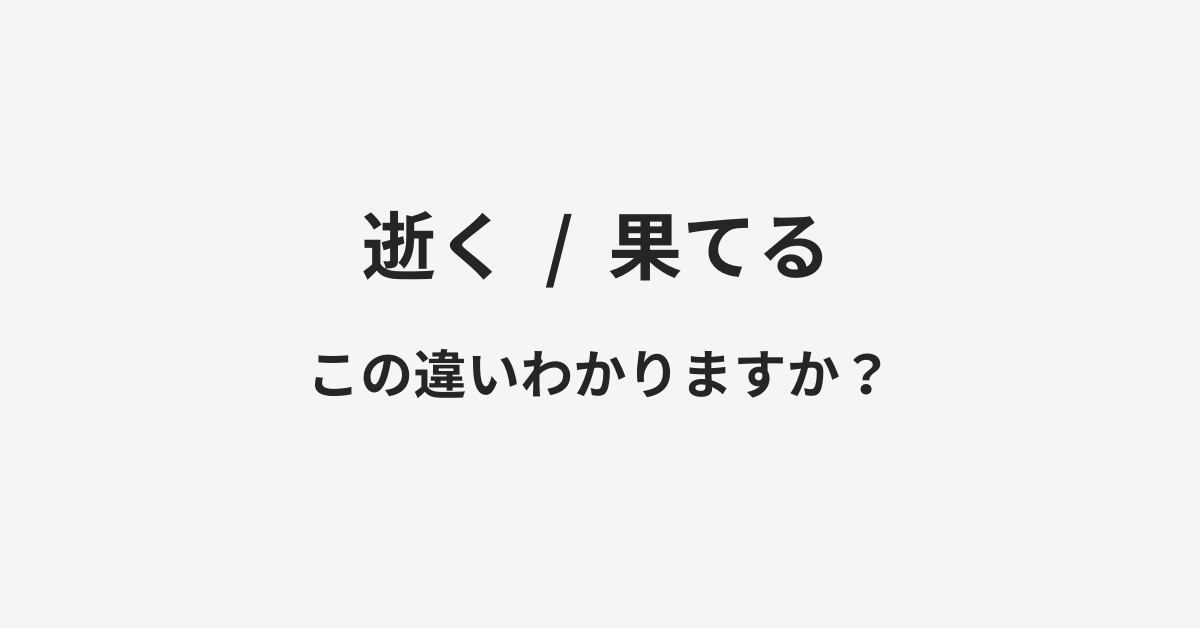
逝くと果てるの分かりやすい違い
逝くと果てるは、どちらも終わりを表しますが、その意味合いと尊厳が異なります。逝くは死を婉曲的かつ尊重を込めて表現する言葉です。
果てるは限界まで消耗して終わりを迎える、より直接的な表現です。メンタルヘルスでは、死についての適切な言葉選びが、遺族の心の癒しや、終末期の尊厳ある対話に重要な意味を持ちます。
逝くとは?
逝くとは、死ぬことを婉曲的に、そして敬意を込めて表現する言葉です。亡くなるよりもさらに文学的で、故人への尊重と、残された人々の悲しみへの配慮が込められています。静かに、穏やかに、尊厳を持って人生を終えるというニュアンスを含んでいます。心理学的には、死を直接的に表現することへの文化的なタブーと、喪失への心理的防衛が、このような婉曲表現を生み出します。
逝くという表現は、死の衝撃を和らげ、受け入れやすくする言語的な緩衝材として機能します。グリーフケアにおいても、適切な言葉選びは重要です。メンタルヘルスの観点から、逝くという表現は、死別の悲しみを抱える人々への配慮を示します。
この言葉を使うことで、故人への敬意を表しながら、遺族の感情に寄り添うことができます。また、終末期ケアにおいても、尊厳ある死について語る際の大切な表現となります。
逝くの例文
- ( 1 ) 祖母が静かに逝き、家族みんなで温かく見送ることができました。
- ( 2 ) 大切な人が逝ってしまいましたが、美しい思い出が心の支えになっています。
- ( 3 ) 友人が若くして逝き、命の尊さを改めて実感しました。
- ( 4 ) ペットが老衰で逝きましたが、最期まで愛情を注げたことに感謝しています。
- ( 5 ) 恩師が逝かれて悲しいですが、教えは私の中で生き続けています。
- ( 6 ) 母が苦しまずに逝けたことが、せめてもの救いです。
逝くの会話例
果てるとは?
果てるとは、力や命が尽きて終わりを迎えることを表す、より直接的で生々しい表現です。長い苦闘や消耗の末に、限界に達して倒れる、息絶えるというニュアンスを含みます。戦いや苦難の中で力尽きるという、劇的で悲壮な終わり方を連想させる言葉です。心理学的には、果てるという表現は、死を過程として捉える視点を含んでいます。
徐々に消耗し、最終的に限界を迎えるという時間的経過を意識させます。この表現は、死の現実的で身体的な側面を強調し、美化や理想化を避ける傾向があります。メンタルヘルスケアにおいて、果てるという表現は慎重に扱う必要があります。
特に自殺念慮を持つ人々に対しては、この言葉が絶望感を強化する可能性があります。一方で、介護疲れや看病疲れを表現する際には、その過酷さを正直に認識する言葉として機能することもあります。
果てるの例文
- ( 1 ) 長い闘病の末に果てた時、やっと苦しみから解放されたと感じました。
- ( 2 ) 介護疲れで私も果てそうでしたが、サポートを受けて持ちこたえました。
- ( 3 ) うつ病との闘いで果てそうになりましたが、治療で回復できました。
- ( 4 ) 過労で果てる寸前でしたが、休職して自分を取り戻せました。
- ( 5 ) 希望が果てたと思った時、カウンセリングで新しい道が見えました。
- ( 6 ) 心が果てそうな時、支援グループの存在が救いになりました。
果てるの会話例
逝くと果てるの違いまとめ
逝くと果てるの違いは、尊厳と消耗、静謐と激烈の違いです。逝くは敬意ある表現、果てるは現実的で直接的な表現です。メンタルヘルスでは、状況と相手の心理状態に応じた言葉選びが重要です。
グリーフケアでは逝く、介護の現実では果てるが適切な場合があります。
死生観を語る際の言葉の選択は、話者の価値観と聞き手への配慮を反映し、心の癒しにも影響を与えます。
逝くと果てるの読み方
- 逝く(ひらがな):いく
- 逝く(ローマ字):iku
- 果てる(ひらがな):はてる
- 果てる(ローマ字):hateru