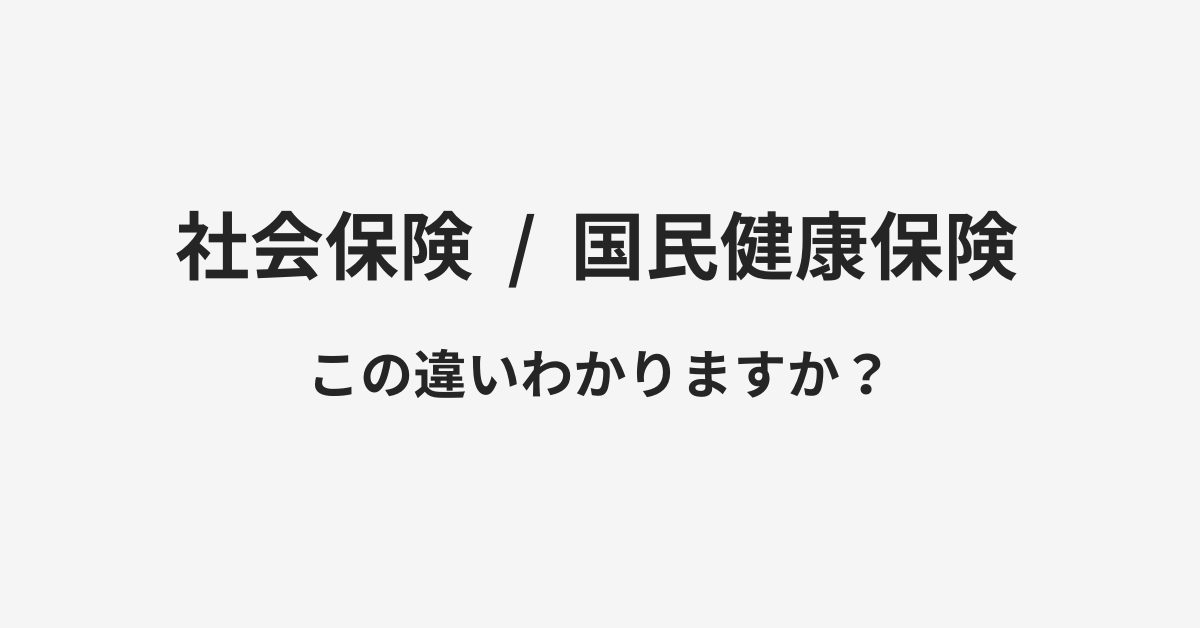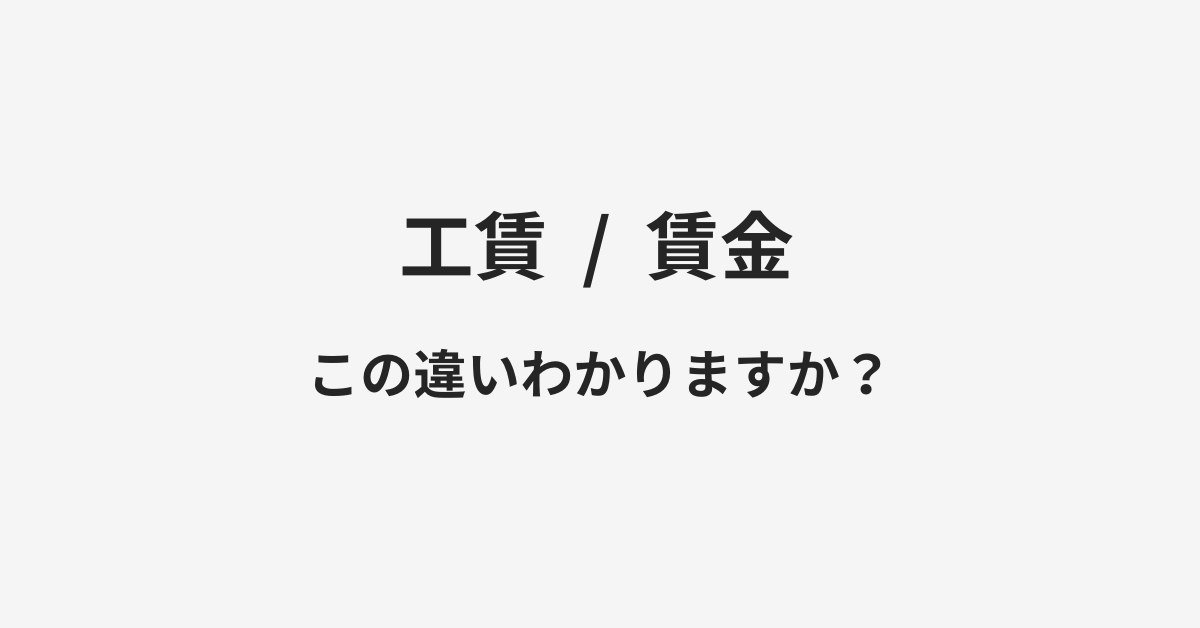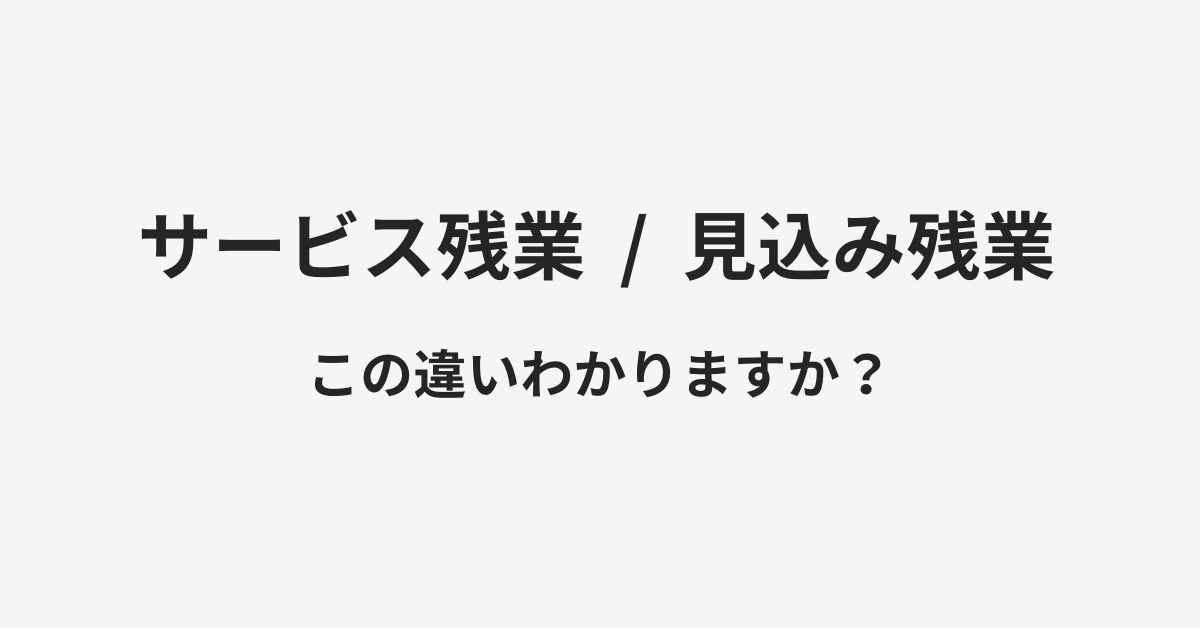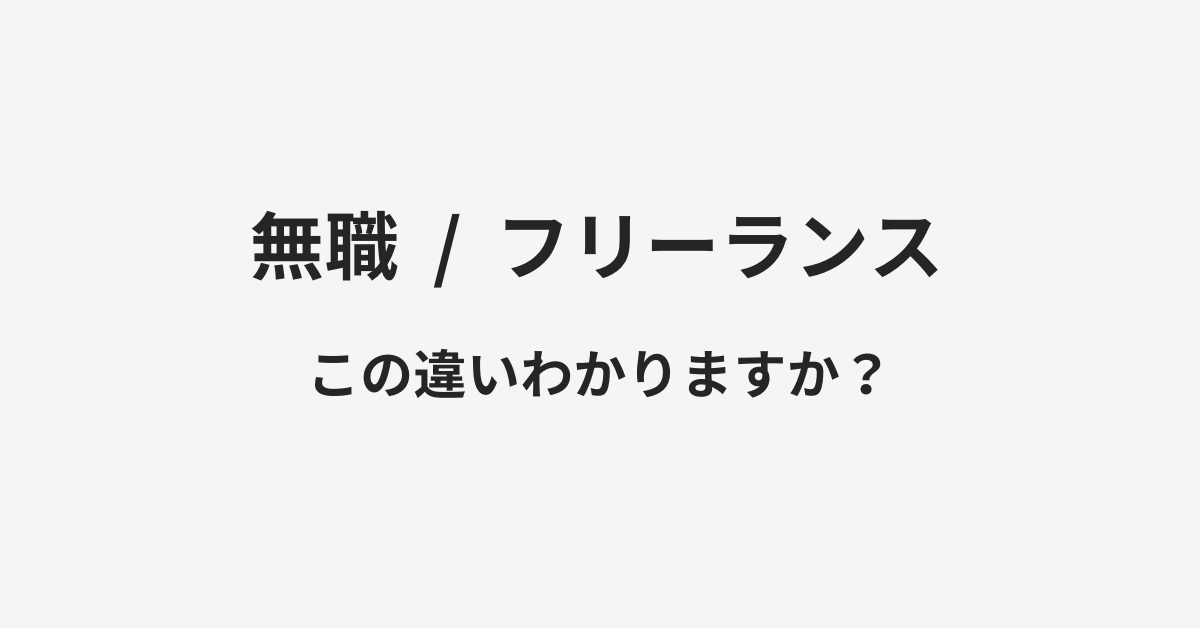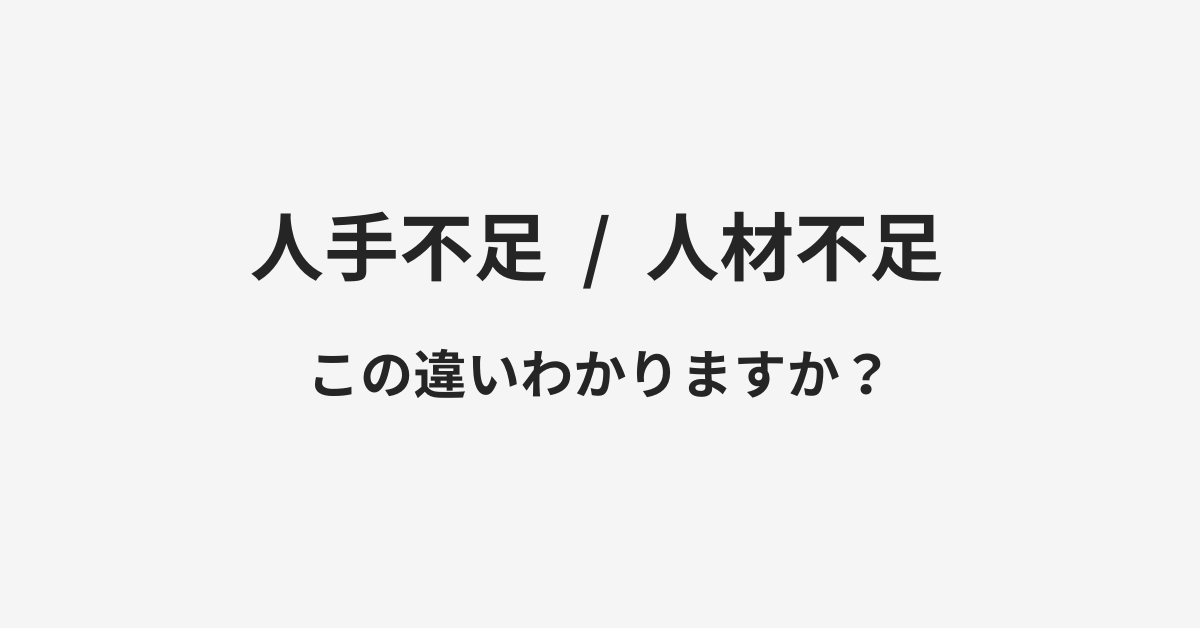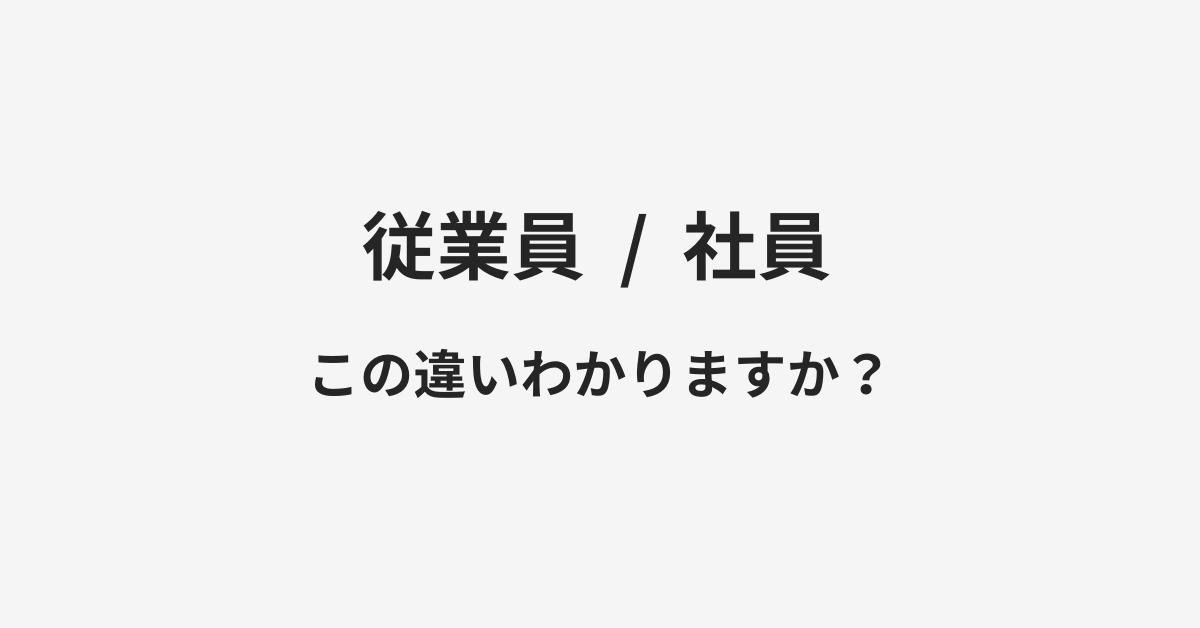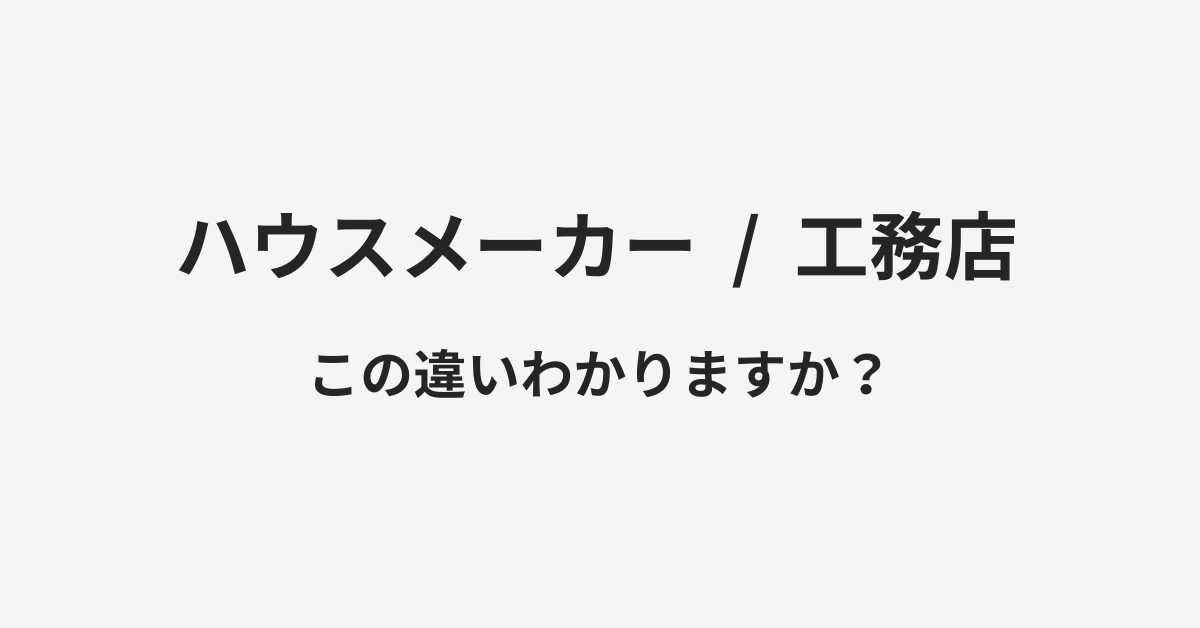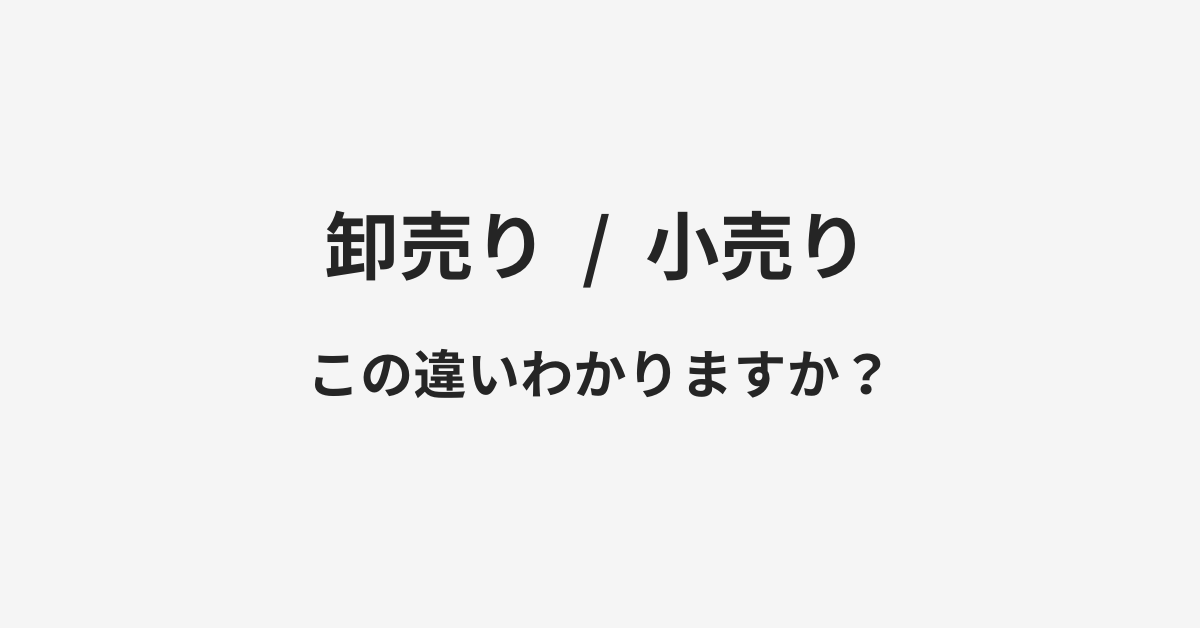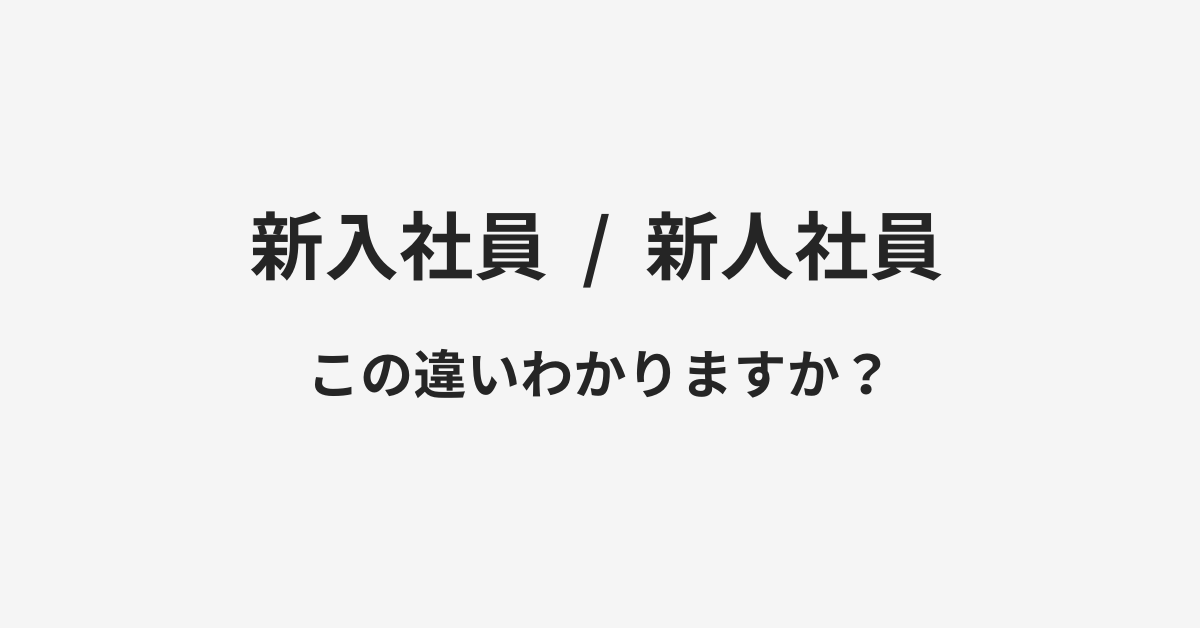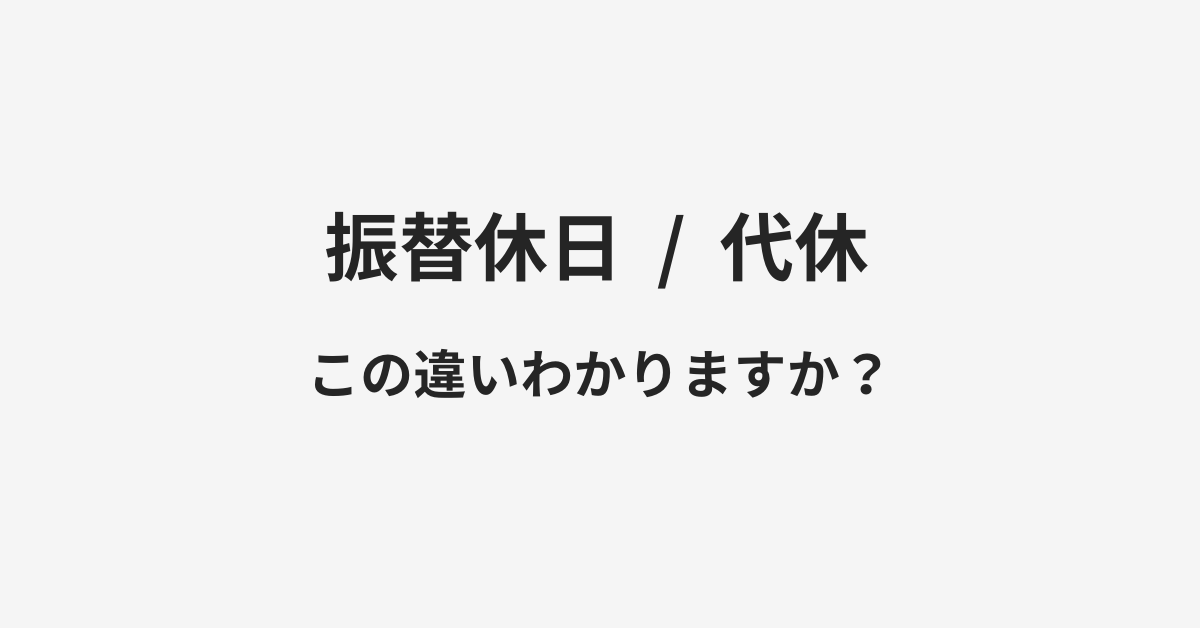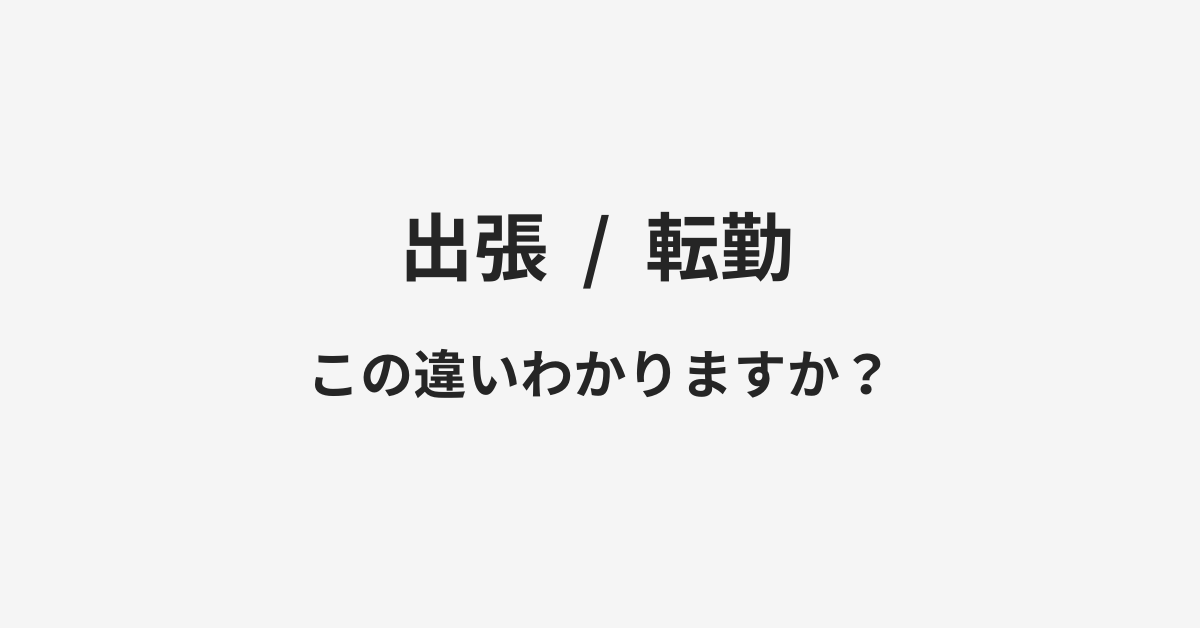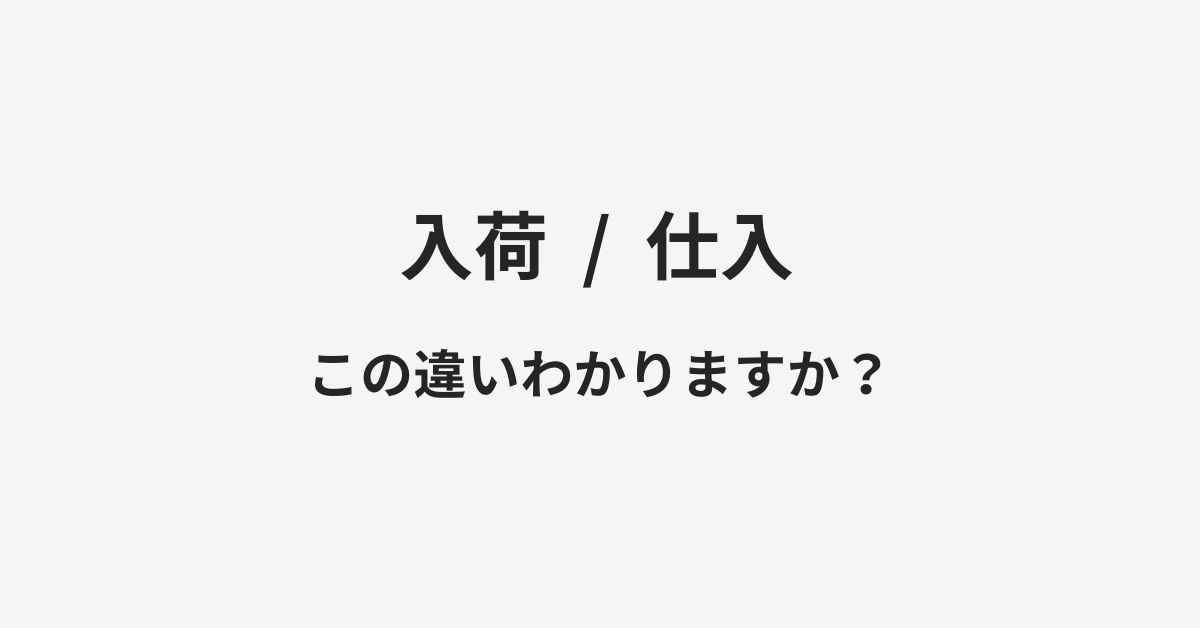【雇用保険】と【共済組合】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
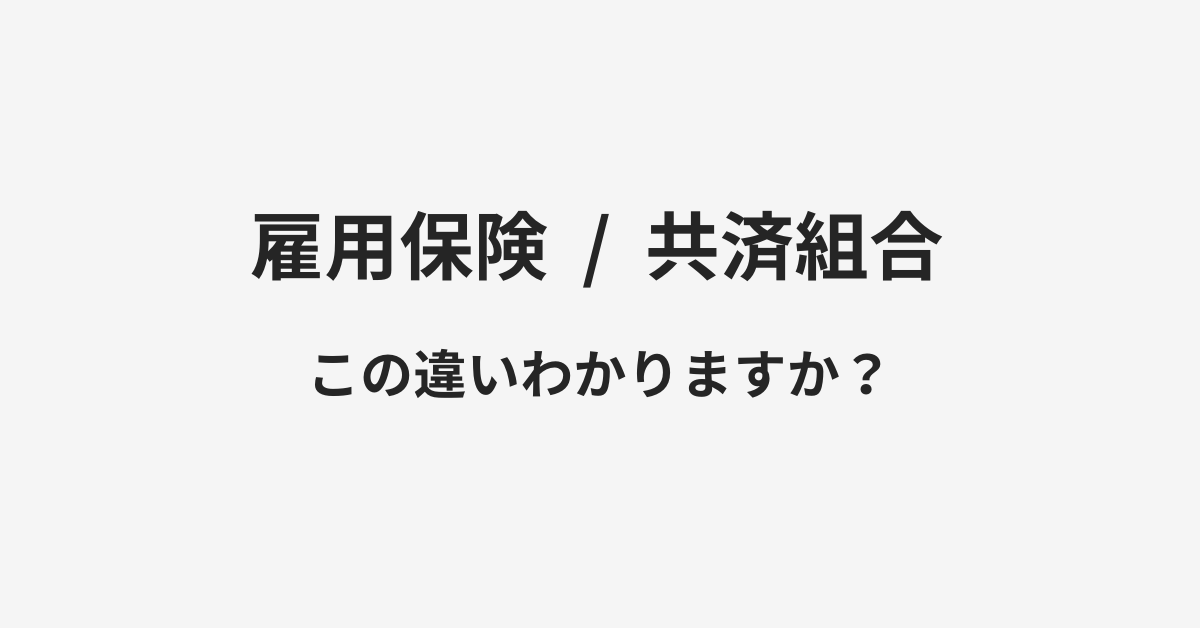
雇用保険と共済組合の分かりやすい違い
雇用保険と共済組合は、どちらも働く人のための社会保障制度ですが、その対象者と保障内容が大きく異なります。
雇用保険は主に民間企業の従業員が加入し、失業時の生活保障を中心とした制度です。一方、共済組合は公務員や私学教職員などが加入し、健康保険と年金を含む総合的な保障を提供します。
企業の人事担当者は、従業員の身分に応じて適切な社会保険制度を理解し、正確な手続きを行うことが求められます。
雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者が失業した場合や育児・介護で休業する場合に、生活の安定と再就職の促進を図るための公的保険制度です。正式には雇用保険法に基づく強制保険で、週20時間以上働く労働者は原則として加入義務があります。保険料は労使で負担し、失業等給付、育児休業給付、教育訓練給付などが支給されます。
主な給付として、失業時の基本手当(失業保険)があり、離職前の賃金の50〜80%が90〜330日間支給されます。また、育児休業給付金は休業開始から180日まで賃金の67%、以降は50%が支給されます。教育訓練給付では、指定講座の受講費用の一部が支給され、スキルアップを支援します。
事業主には、従業員の雇用保険加入手続き、保険料の徴収と納付、離職証明書の作成などの義務があります。加入漏れは遡及適用され、保険料の追徴や罰則の対象となるため、適切な管理が必要です。ハローワークが窓口となり、各種手続きを行います。
雇用保険の例文
- ( 1 ) 雇用保険の加入手続きを行い、新入社員の被保険者証を交付しました。
- ( 2 ) 育児休業に入るため、雇用保険の育児休業給付金を申請します。
- ( 3 ) 雇用保険料率が改定されたので、給与計算システムを更新しました。
- ( 4 ) 退職者の雇用保険被保険者離職票を作成し、本人に送付しました。
- ( 5 ) 雇用保険の教育訓練給付を使って、MBA取得を目指します。
- ( 6 ) パートタイマーも週20時間以上なら雇用保険加入が必要です。
雇用保険の会話例
共済組合とは?
共済組合とは、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員などが加入する相互扶助の精神に基づく社会保障制度です。健康保険、年金保険、福祉事業を一体的に運営し、組合員とその家族の生活を総合的に保障します。国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済の3つに大別され、それぞれ独立した組織として運営されています。
共済組合の特徴は、短期給付(健康保険)と長期給付(年金)を同一組織が運営することです。医療費の給付、出産・死亡時の給付に加え、保養施設の運営、貸付事業、健康増進事業なども行います。掛金率は一般的に協会けんぽより低く、付加給付も充実しています。
組合員資格は、該当する職に就いた時点で自動的に取得し、退職により喪失します。任意継続組合員制度により、退職後も一定期間は短期給付を継続できます。年金は厚生年金に上乗せされる職域加算があり、民間より手厚い給付となっています。
共済組合の例文
- ( 1 ) 地方公務員共済組合の組合員として、充実した福利厚生を受けています。
- ( 2 ) 共済組合の保養施設を利用して、家族でリフレッシュしました。
- ( 3 ) 私学共済に加入しており、医療費の付加給付が手厚くて助かります。
- ( 4 ) 共済組合の住宅貸付制度を利用して、マイホームを購入しました。
- ( 5 ) 定年退職後も共済組合の任意継続組合員として医療保障を継続します。
- ( 6 ) 共済組合主催の健康セミナーに参加し、生活習慣の改善に取り組みます。
共済組合の会話例
雇用保険と共済組合の違いまとめ
雇用保険と共済組合の最大の違いは、加入対象者と保障範囲です。雇用保険は民間企業等の労働者が加入し失業時の保障が中心ですが、共済組合は公務員等が加入し医療・年金・福祉を総合的に保障します。
制度の仕組みも異なり、雇用保険は全国統一の制度ですが、共済組合は職域ごとに独立した組織が運営します。また、雇用保険は雇用に関するリスクに特化していますが、共済組合は生活全般をカバーする包括的な制度です。
転職時の取り扱いも重要な違いで、民間企業間の転職では雇用保険が継続しますが、民間と公務員間の転職では制度自体が変わるため、注意が必要です。
雇用保険と共済組合の読み方
- 雇用保険(ひらがな):こようほけん
- 雇用保険(ローマ字):koyouhokenn
- 共済組合(ひらがな):きょうさいくみあい
- 共済組合(ローマ字):kyousaikumiai