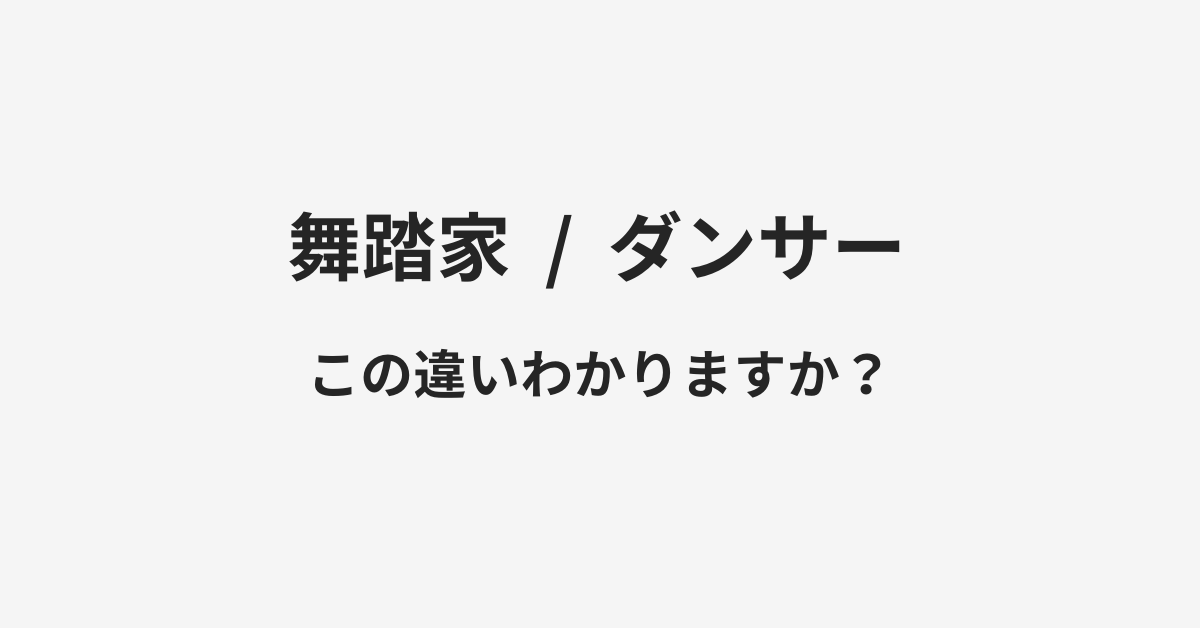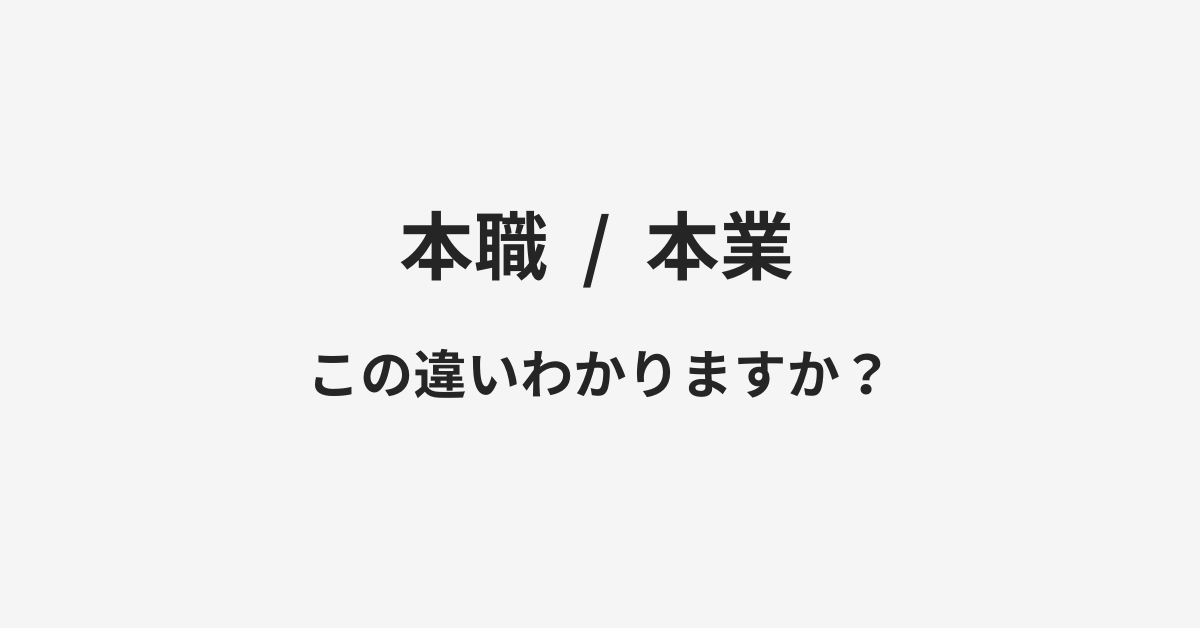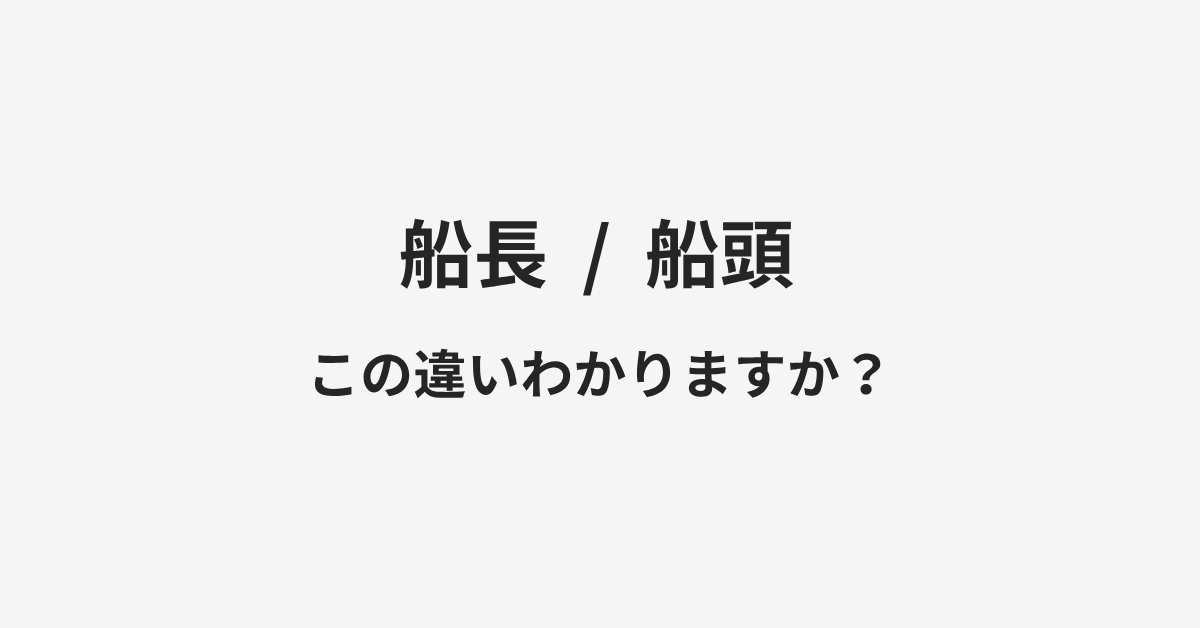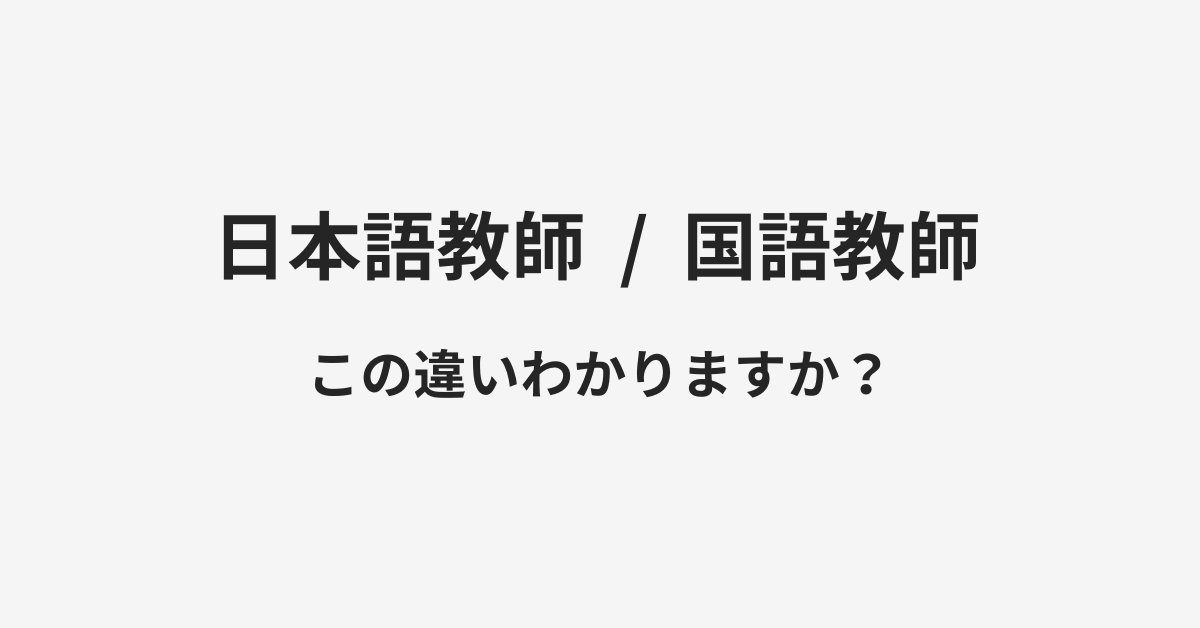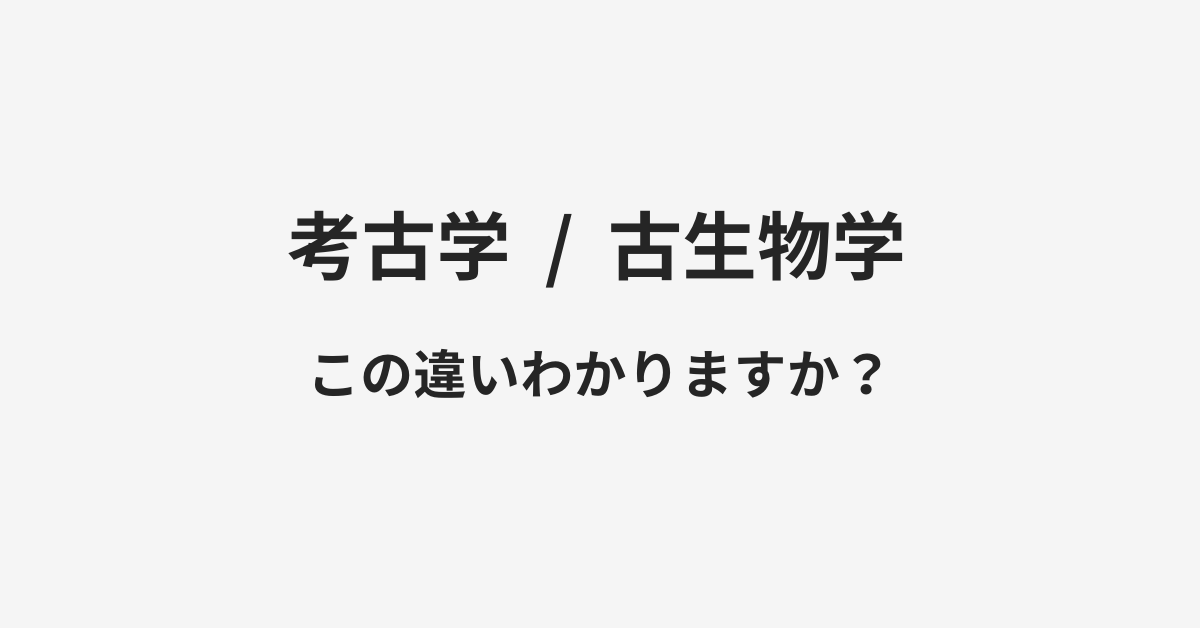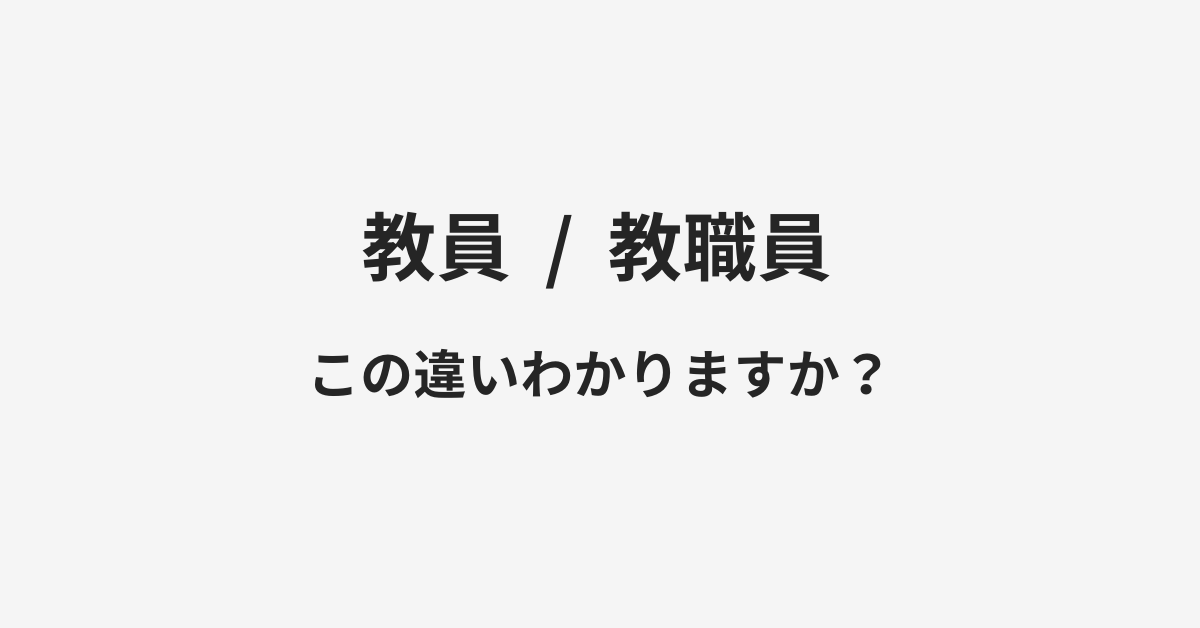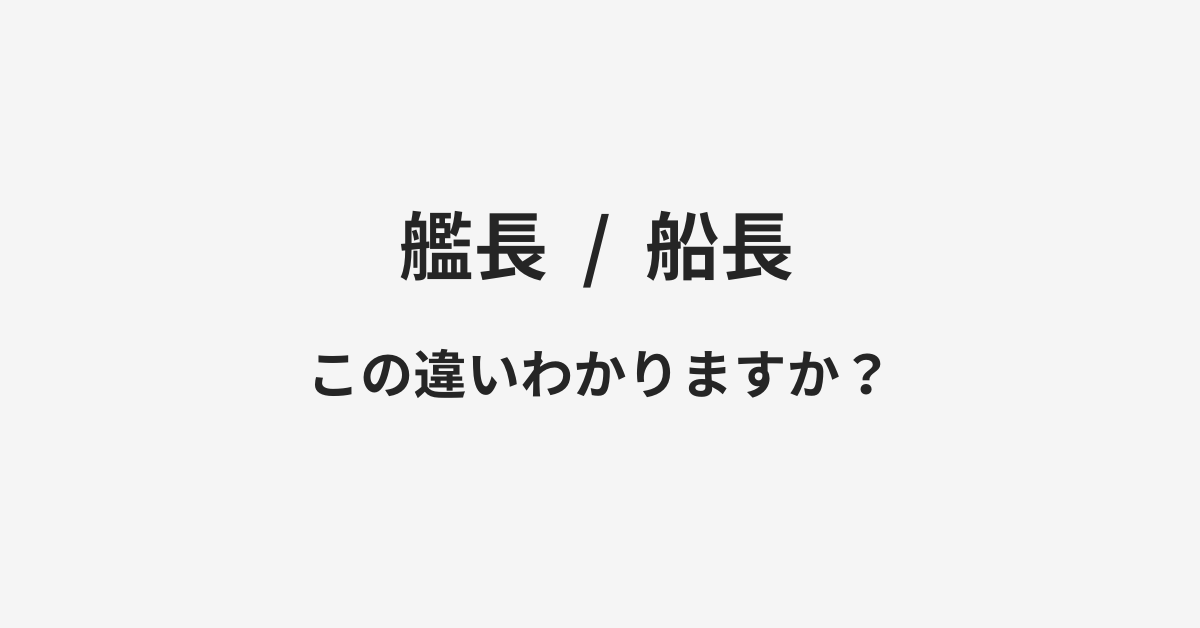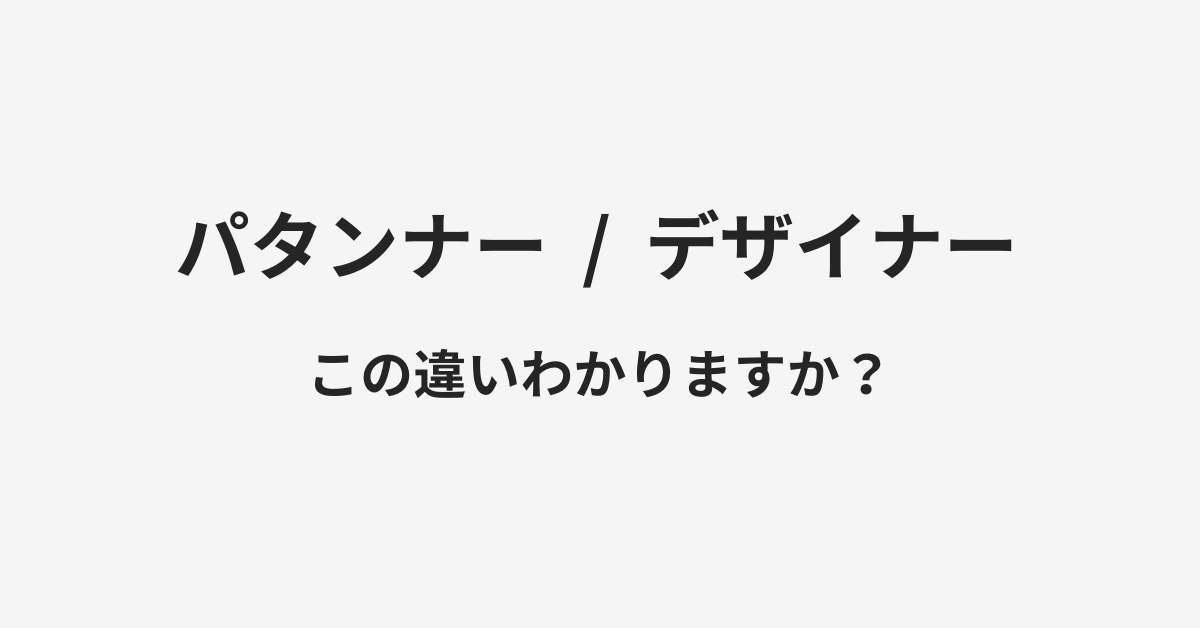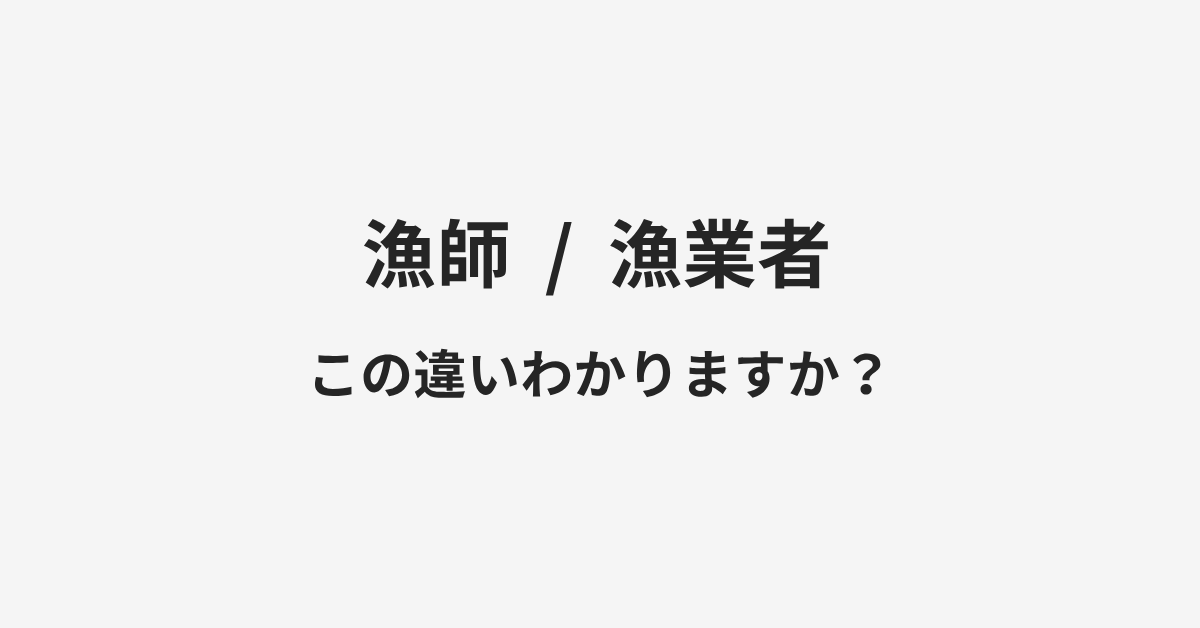【舞妓】と【芸妓】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
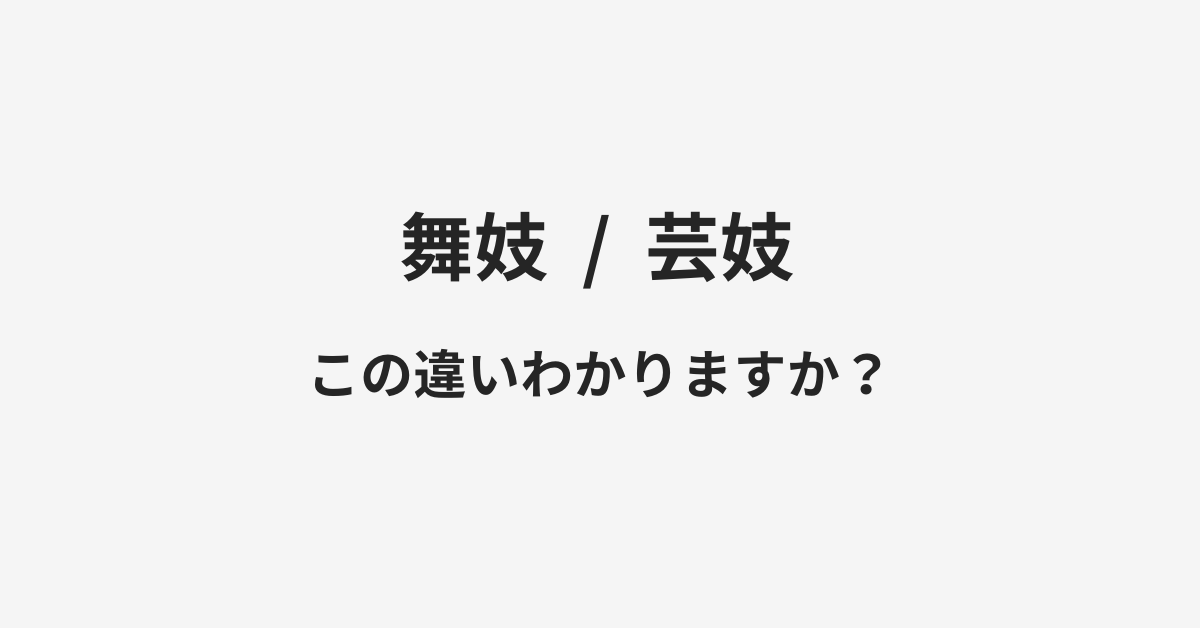
舞妓と芸妓の分かりやすい違い
舞妓と芸妓は、どちらも京都の花街でお客様をもてなす伝統的な職業ですが、年齢と立場が異なります。舞妓は15歳から20歳頃までの若い女性で、華やかな着物と長い帯、花かんざしを付けた見習いの立場です。
一方、芸妓は20歳を過ぎて一人前になった女性で、落ち着いた着物姿でお座敷での芸を披露するプロフェッショナルです。
舞妓とは?
舞妓とは、京都の花街(祇園、宮川町、上七軒、先斗町、祇園東)で芸妓になるための修行をする15-20歳頃の女性です。華やかな着物に長いだらり帯、白塗りの化粧、花かんざしが特徴的です。お座敷で舞踊を披露し、お客様をもてなしながら、芸事の修練を積みます。
舞妓になるには、中学卒業後に置屋(おきや)に住み込み、厳しい修行を始めます。京舞、三味線、唄、茶道、お座敷での作法など、伝統芸能を習得します。先輩の芸妓や女将から指導を受け、約5年間の修行期間を経て芸妓となります。
収入は置屋が管理し、必要経費を除いた分が支給されます。華やかに見えますが、早朝からの稽古、夜遅くまでのお座敷と、心身ともにハードな仕事です。しかし、日本の伝統文化を体現し、守り継ぐ貴重な存在として、誇りを持って働いています。
舞妓の例文
- ( 1 ) 舞妓として、毎日早朝から京舞のお稽古に励んでいます。
- ( 2 ) 新人舞妓として、先輩の芸妓さんからお座敷での作法を学んでいます。
- ( 3 ) 舞妓として初めてのお座敷で緊張しましたが、お客様に喜んでいただけました。
- ( 4 ) 舞妓の仕事は大変ですが、日本の伝統文化を守る誇りを感じています。
- ( 5 ) 舞妓として、季節の花かんざしを身に着けるのが楽しみです。
- ( 6 ) 店出しから3年目の舞妓として、後輩の指導も任されるようになりました。
舞妓の会話例
芸妓とは?
芸妓(京都では芸子とも)とは、舞妓の修行を終えて一人前となった女性芸能者です。20歳を過ぎてから芸妓となり、より洗練された芸でお座敷を盛り上げます。着物は地味で上品なものとなり、かつらから自髪での日本髪や洋髪に変わります。舞踊、唄、三味線などの芸を極めたプロフェッショナルです。
芸妓は置屋から独立することも可能で、自分で営業し、収入を管理します。お座敷では、舞妓の指導役も務め、花街の伝統を次世代に伝える重要な役割を担います。茶屋との信頼関係を築き、常連客を持つことが成功の鍵です。
キャリアとしては、芸の道を究めて名妓と呼ばれる存在になる、置屋の女将として後進を育てる、引退後も花街に関わる仕事を続けるなど、様々な道があります。60歳を過ぎても現役で活躍する芸妓もおり、生涯を通じて芸を磨き続ける職業です。
芸妓の例文
- ( 1 ) 芸妓として独立し、自分のペースでお座敷を務められるようになりました。
- ( 2 ) ベテラン芸妓として、舞妓の教育にも力を入れています。
- ( 3 ) 芸妓として、海外のお客様に日本文化を紹介する機会も増えました。
- ( 4 ) 芸妓になって10年、常連のお客様との信頼関係を大切にしています。
- ( 5 ) 芸妓として、伝統を守りながらも新しい演目にも挑戦しています。
- ( 6 ) 60歳を過ぎても現役の芸妓として、後進の手本となれるよう精進しています。
芸妓の会話例
舞妓と芸妓の違いまとめ
舞妓と芸妓は、京都花街における修行段階の違いを表す言葉です。舞妓は見習い期間の若い女性、芸妓は一人前のプロフェッショナルです。
どちらも日本の伝統文化を守り、体現する貴重な存在で、厳しい修行と日々の鍛錬により、お座敷という特別な空間で最高のおもてなしを提供します。
この伝統的なキャリアパスは、現代でも京都の花街で脈々と受け継がれています。
舞妓と芸妓の読み方
- 舞妓(ひらがな):まいこ
- 舞妓(ローマ字):maiko
- 芸妓(ひらがな):げいこ
- 芸妓(ローマ字):geiko