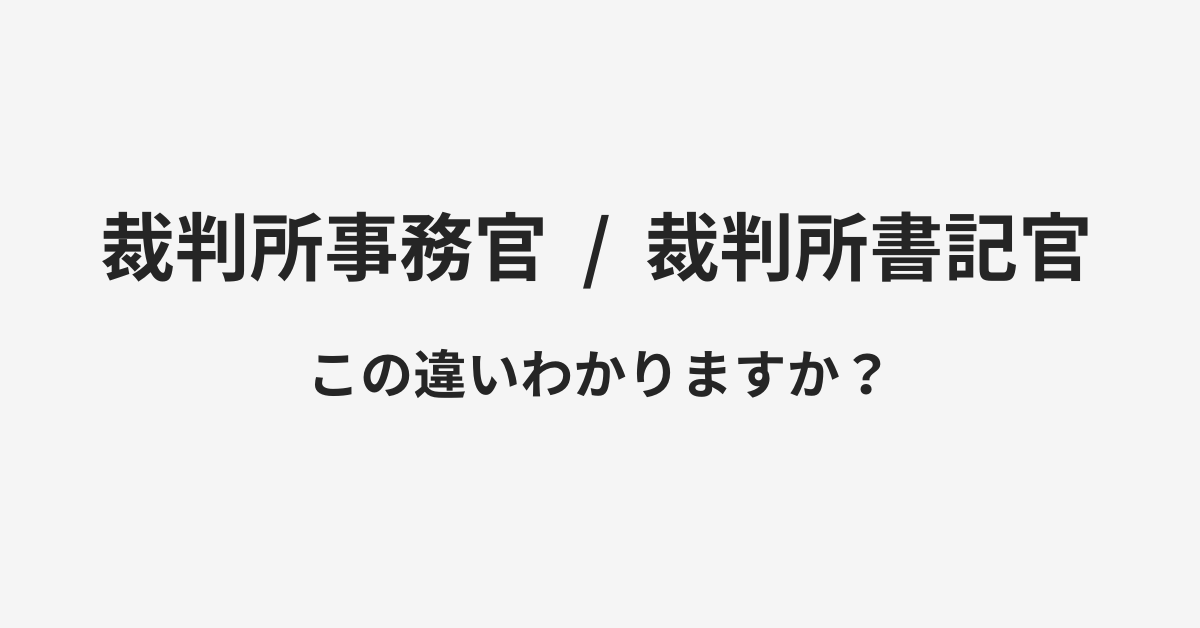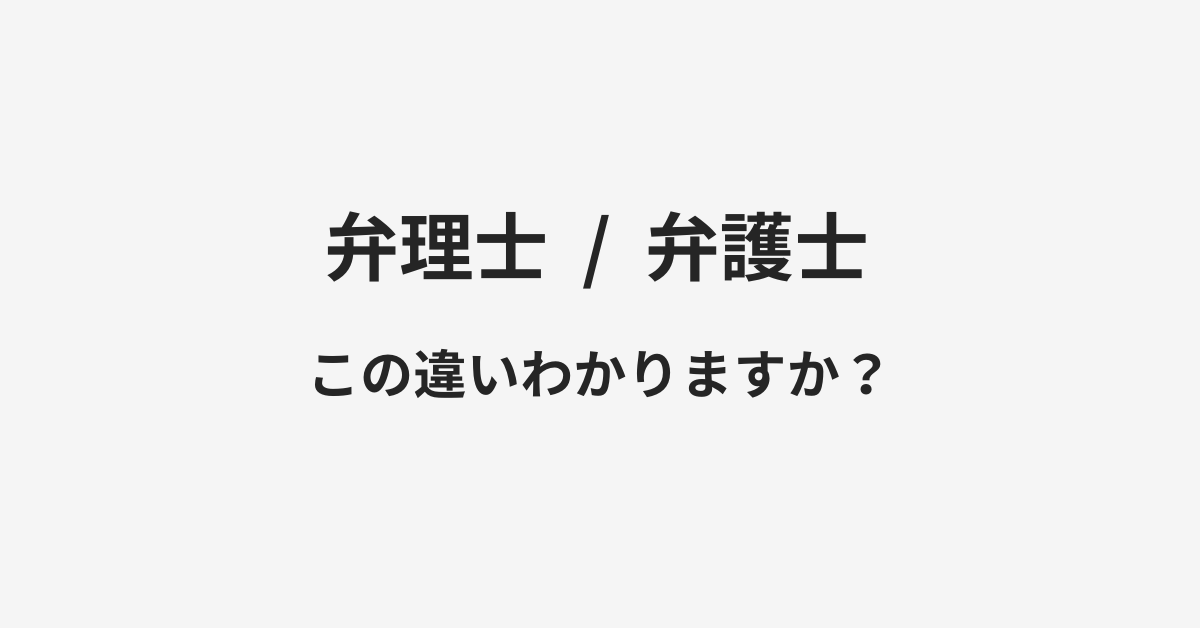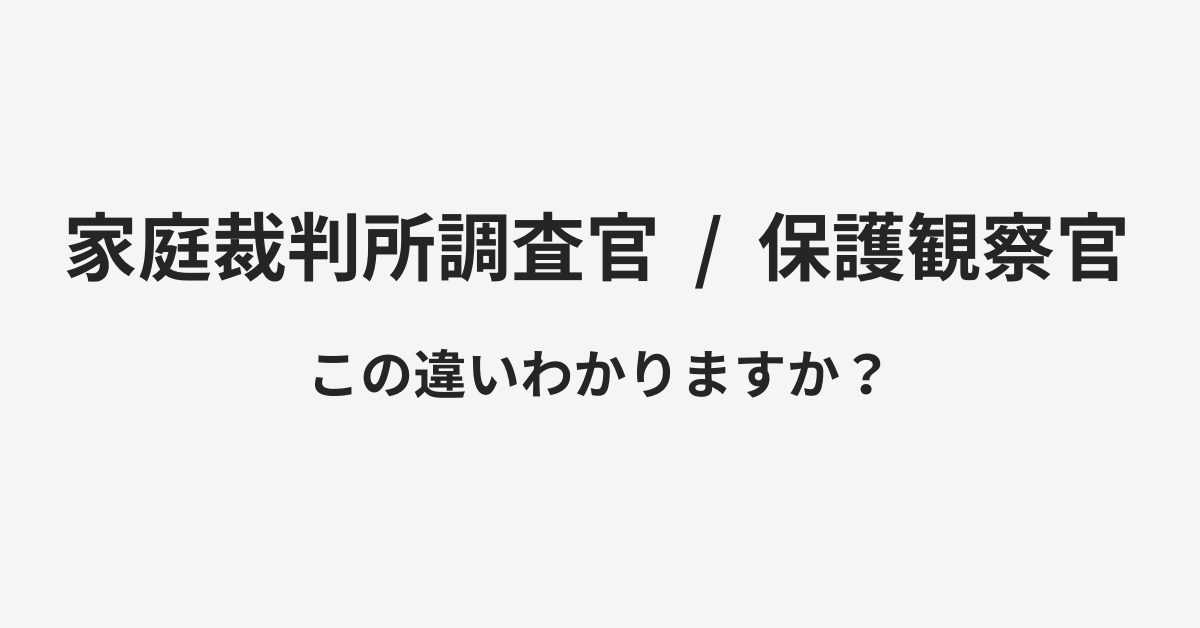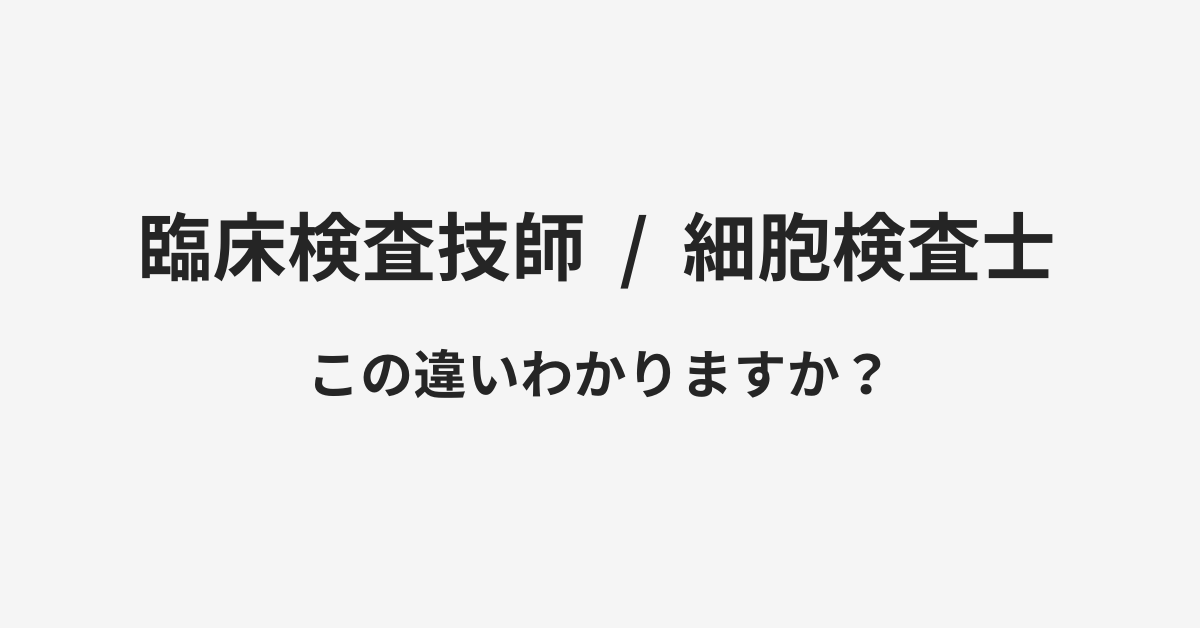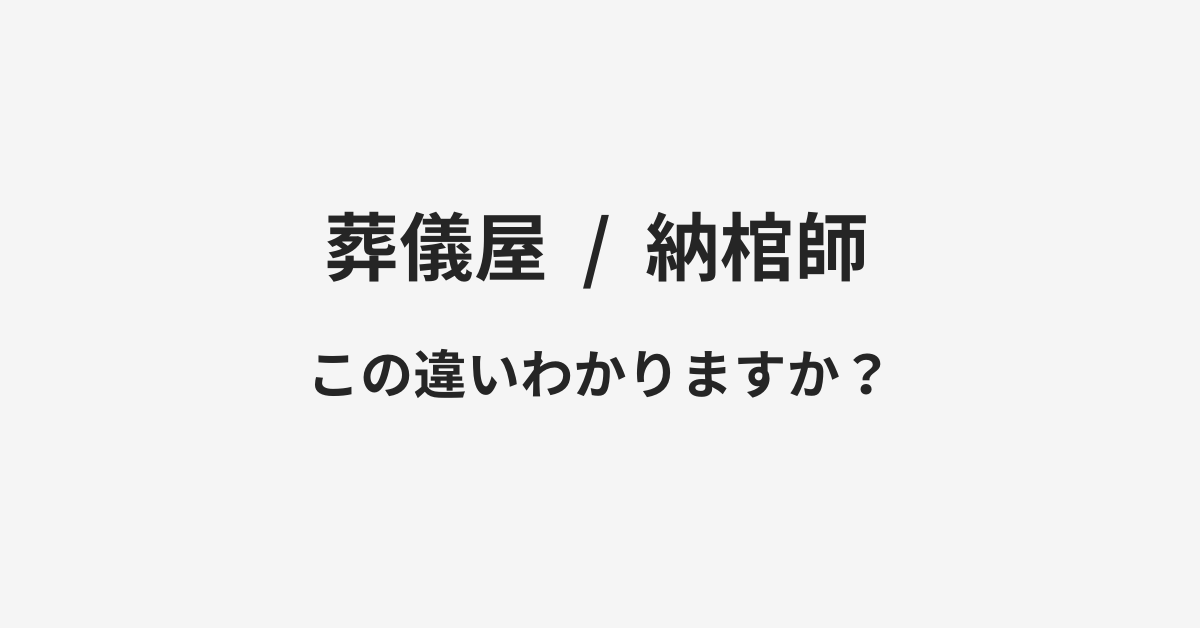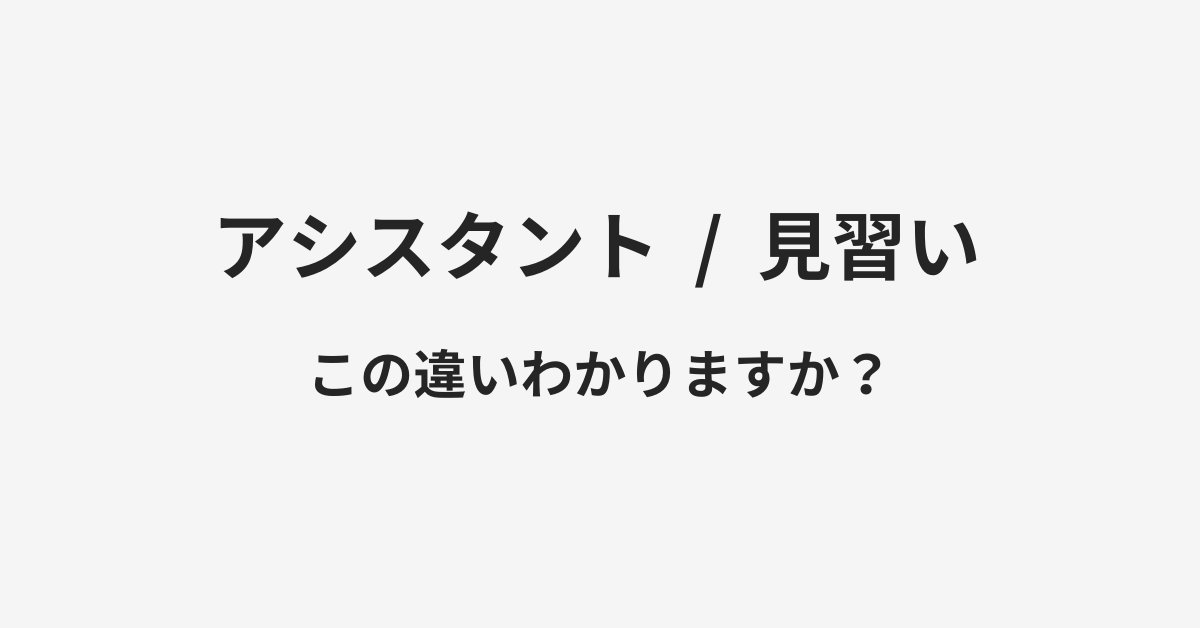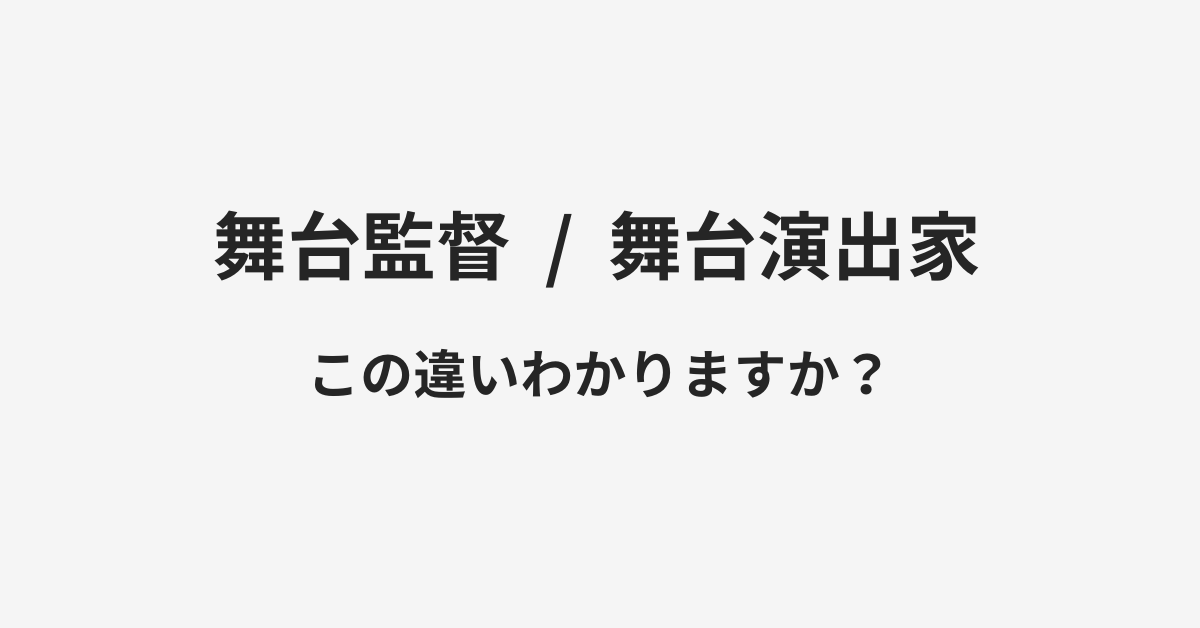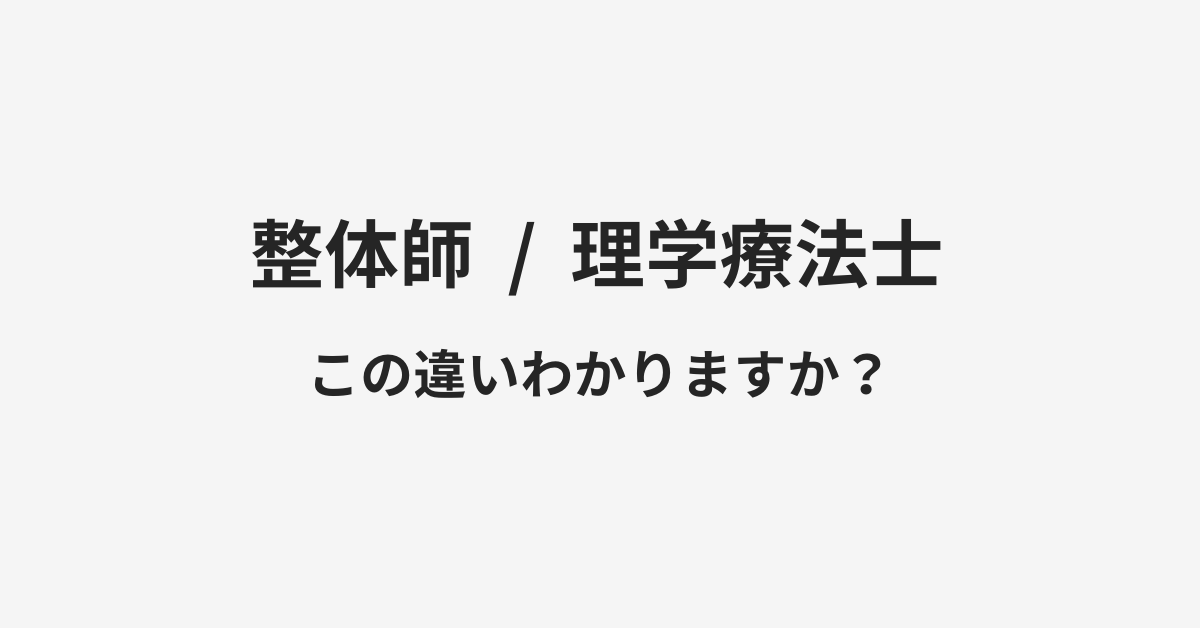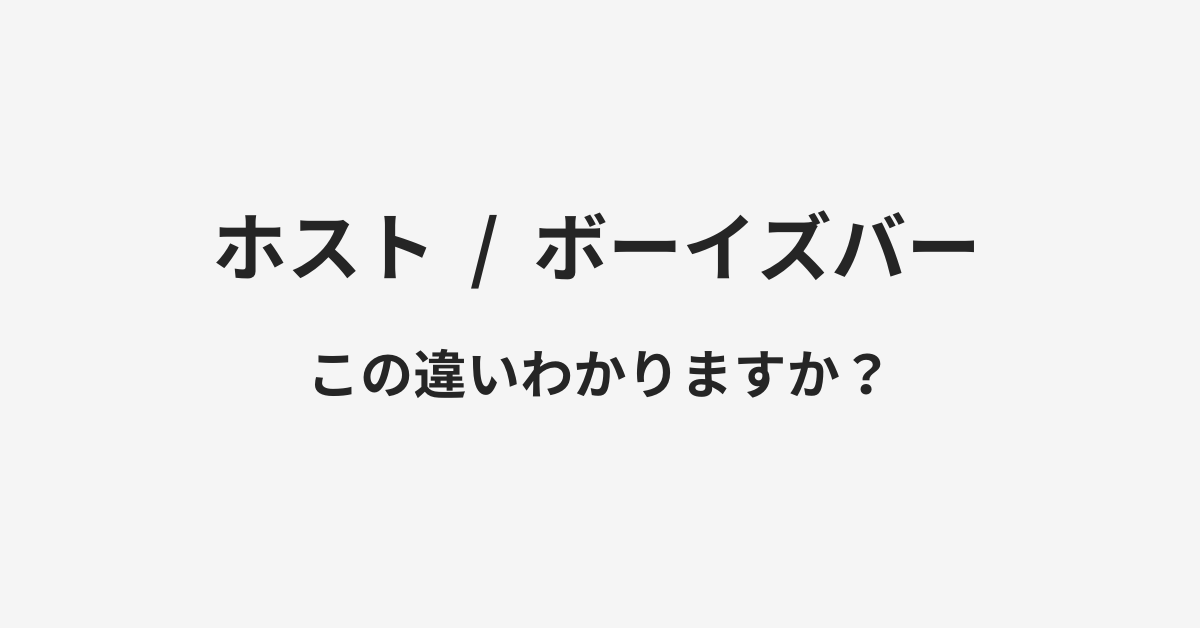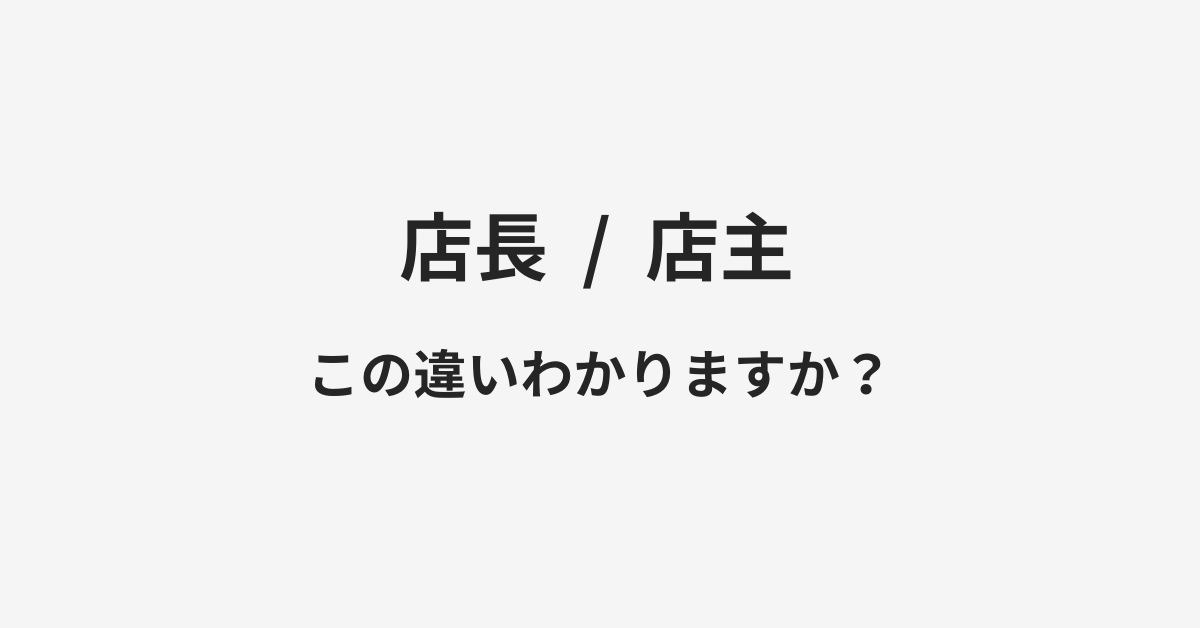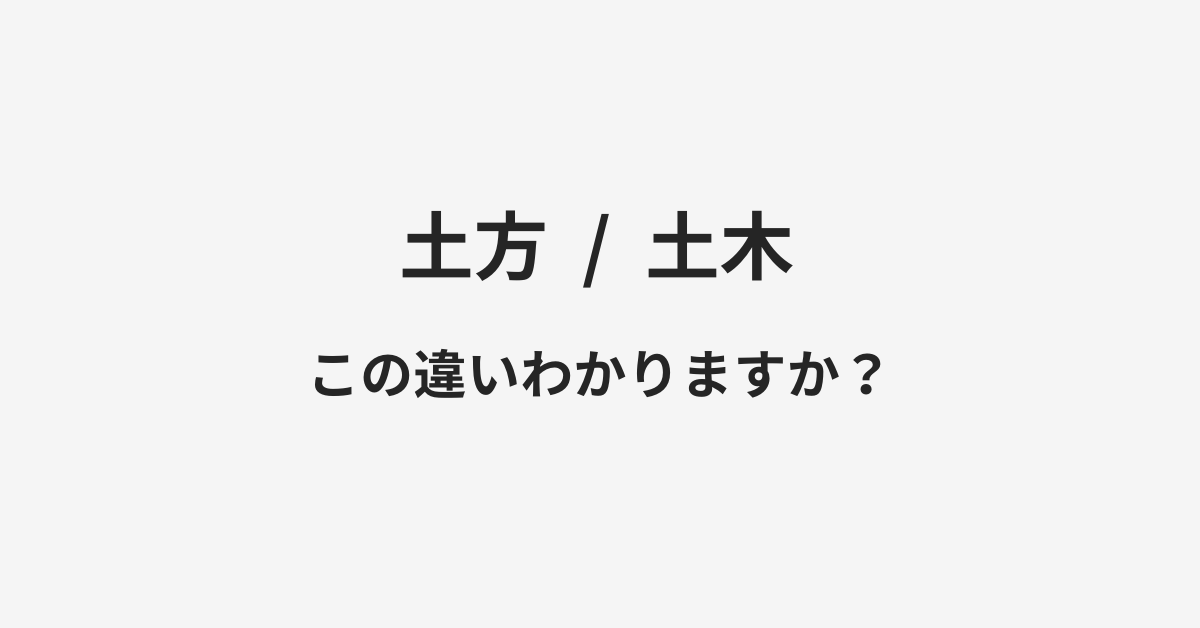【検察官】と【検察事務官】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
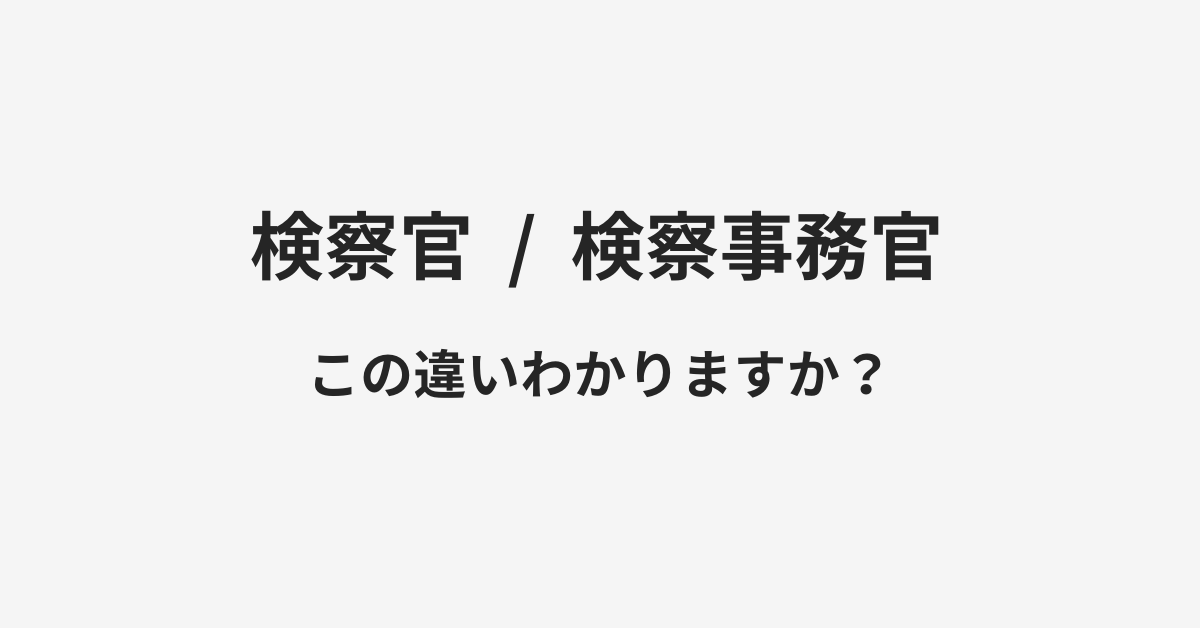
検察官と検察事務官の分かりやすい違い
検察官と検察事務官は、どちらも検察庁で犯罪の捜査や裁判に関わる仕事をしますが、資格と権限が大きく異なります。
検察官は、司法試験に合格した法律のプロで、犯人を裁判にかけるかどうかを決める権限を持っています。
一方、検察事務官は検察官の仕事を手伝う職員で、捜査の実務や事務作業を担当します。
検察官とは?
検察官とは、刑事事件の捜査を指揮し、起訴・不起訴を決定する権限を持つ法曹資格者です。司法試験合格後、司法修習を経て任官される国家公務員で、検事とも呼ばれます。被疑者の取調べ、証拠の評価、公判での立証など、刑事司法の中核を担います。公益の代表者として、適正な刑罰権の行使を通じて社会正義を実現する重要な職責を負います。
検察官になるには、司法試験(合格率3-4%)に合格し、司法修習(1年間)を経て、検察官志望者の中から採用される必要があります。法的思考力、正義感、冷静な判断力、コミュニケーション能力が求められます。激務ですが、やりがいは大きい職業です。
全国の検察庁に配属され、3年程度で転勤を繰り返します。初任給は月額23万円程度ですが、経験により年収800-1500万円以上になります。検事正、検事長、検事総長というキャリアパスがあり、法務省や内閣法制局への出向もあります。
検察官の例文
- ( 1 ) 検察官として、重要経済事件の捜査を指揮し、真相解明に全力を尽くしています。
- ( 2 ) 若手検察官として、先輩検事の指導を受けながら、日々の事件処理に奮闘しています。
- ( 3 ) 検察官として、被害者の声に耳を傾け、適正な処分を心がけています。
- ( 4 ) 特捜部の検察官として、政治家や企業の不正を徹底的に追及しています。
- ( 5 ) 検察官として公判に立ち、被告人の罪を立証するため緻密な立証活動を行っています。
- ( 6 ) 女性検察官として、性犯罪被害者に寄り添った捜査を実践しています。
検察官の会話例
検察事務官とは?
検察事務官とは、検察庁において検察官の捜査・公判活動を補佐する専門職員です。被疑者の取調べ補助、証拠品の管理、捜査書類の作成、令状請求手続き、公判立会いなど、検察実務の重要な部分を担当します。検察官の指揮下で働きますが、独自に被疑者の取調べを行う権限も与えられています。
検察事務官になるには、国家公務員採用試験(一般職)に合格し、検察庁に採用される必要があります。採用後は検察事務官研修を受け、実務を学びます。法律知識、事務処理能力、対人スキルが必要です。検察官と二人三脚で事件を解決する、やりがいのある仕事です。
全国の検察庁で勤務し、年収は400-700万円程度です。副検事(検察官の一種)への道も開かれており、一定の経験を積めば内部試験により検察官になることも可能です。捜査・公判部門のほか、総務・会計部門でも活躍でき、安定したキャリアを築けます。
検察事務官の例文
- ( 1 ) 検察事務官として、検察官と協力して被疑者の取調べを行っています。
- ( 2 ) ベテラン検察事務官として、若手検察官に実務のノウハウを伝授しています。
- ( 3 ) 検察事務官として、膨大な証拠品の管理と分析に携わっています。
- ( 4 ) 捜査部門の検察事務官として、警察との連携を密にして事件解決に貢献しています。
- ( 5 ) 検察事務官から副検事試験に合格し、検察官としての道を歩み始めました。
- ( 6 ) 検察事務官として、デジタル証拠の解析など専門性の高い業務も担当しています。
検察事務官の会話例
検察官と検察事務官の違いまとめ
検察官と検察事務官は、検察庁において法的権限と役割が異なる職種です。検察官は司法試験合格者で起訴権限を持つ法曹、検察事務官は検察実務を支える専門職員です。
両者は車の両輪として協力し、刑事司法を支えています。法曹資格を取得して権限を持ちたいなら検察官、実務を通じて正義の実現に貢献したいなら検察事務官という選択になります。
検察事務官から副検事への道もあり、努力次第でキャリアアップも可能です。
検察官と検察事務官の読み方
- 検察官(ひらがな):けんさつかん
- 検察官(ローマ字):kennsatsukann
- 検察事務官(ひらがな):けんさつじむかん
- 検察事務官(ローマ字):kensatsujimu kan