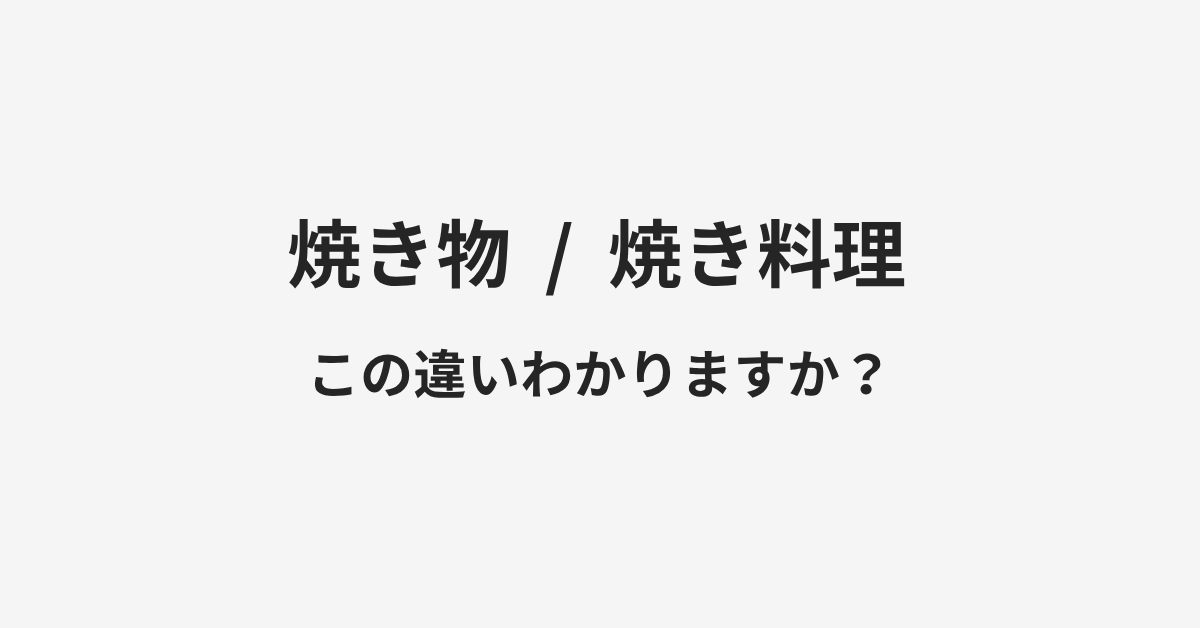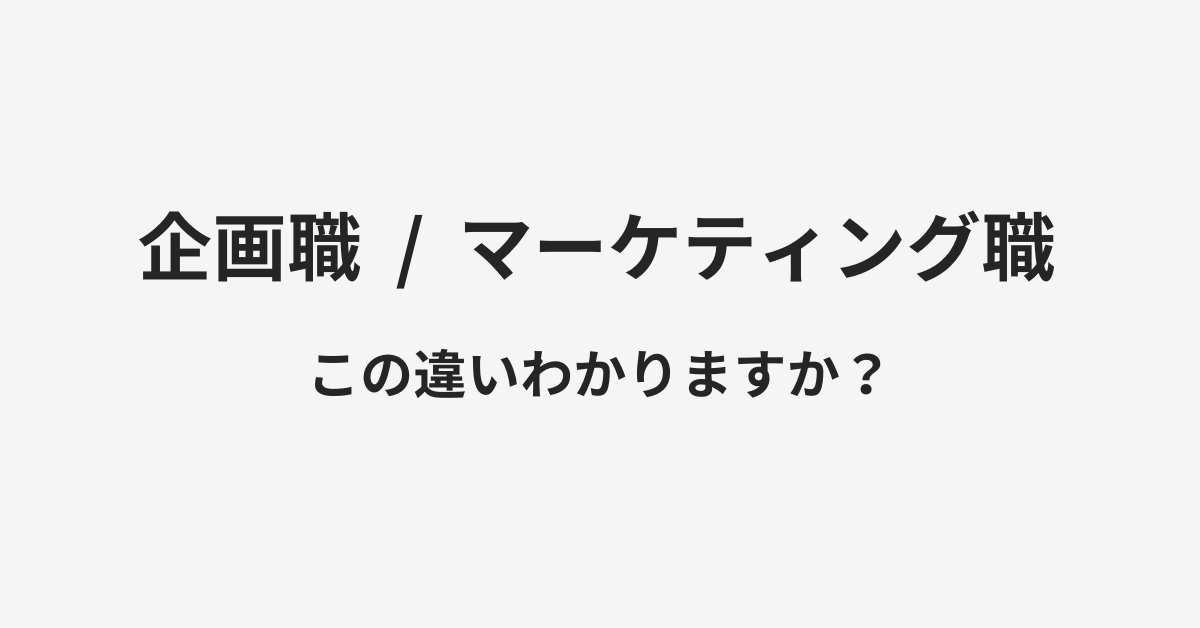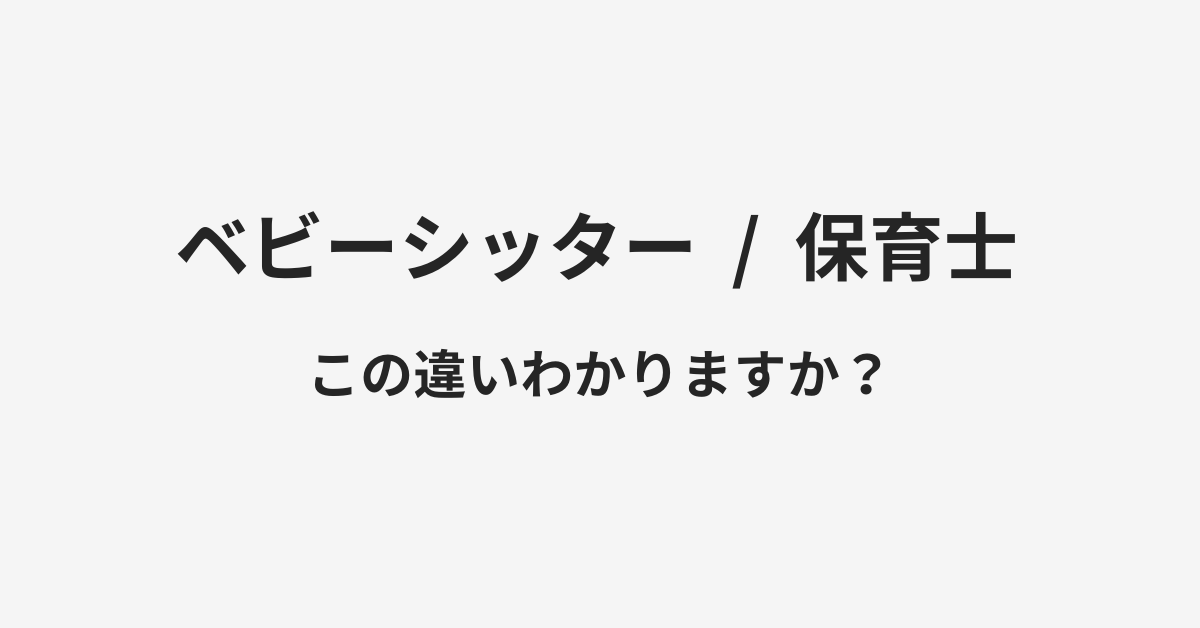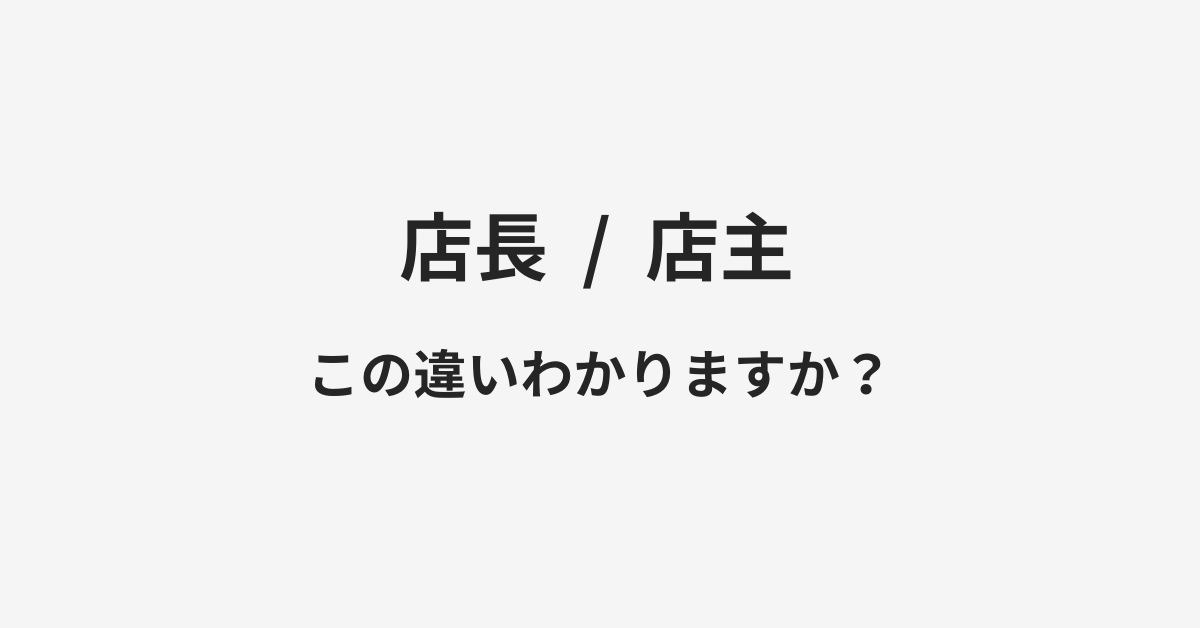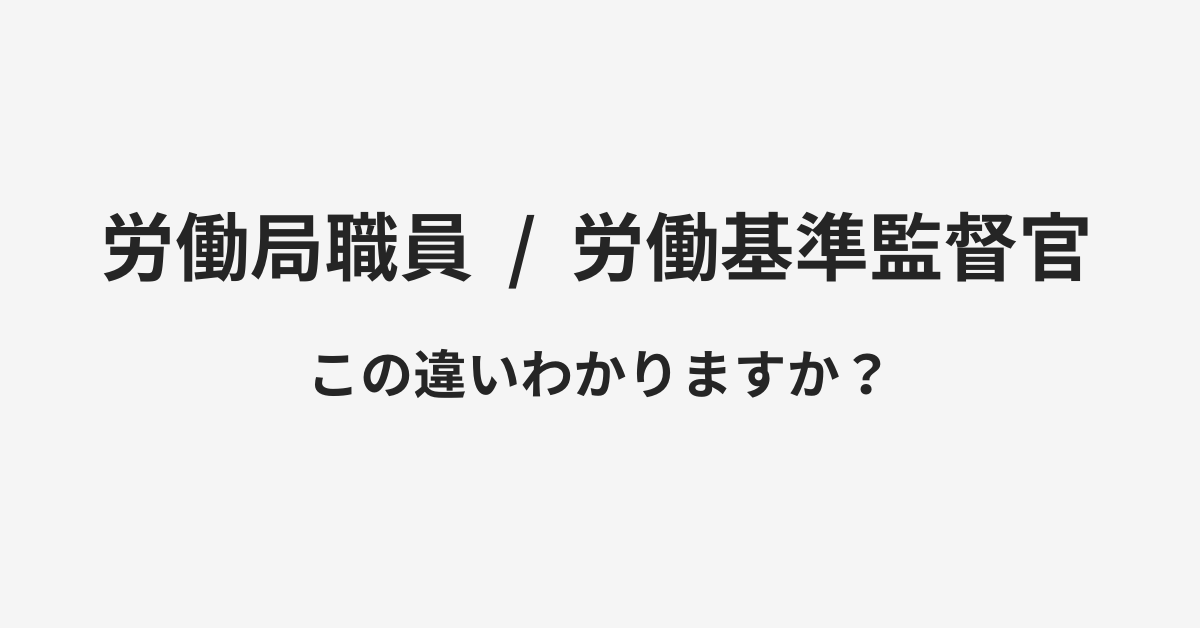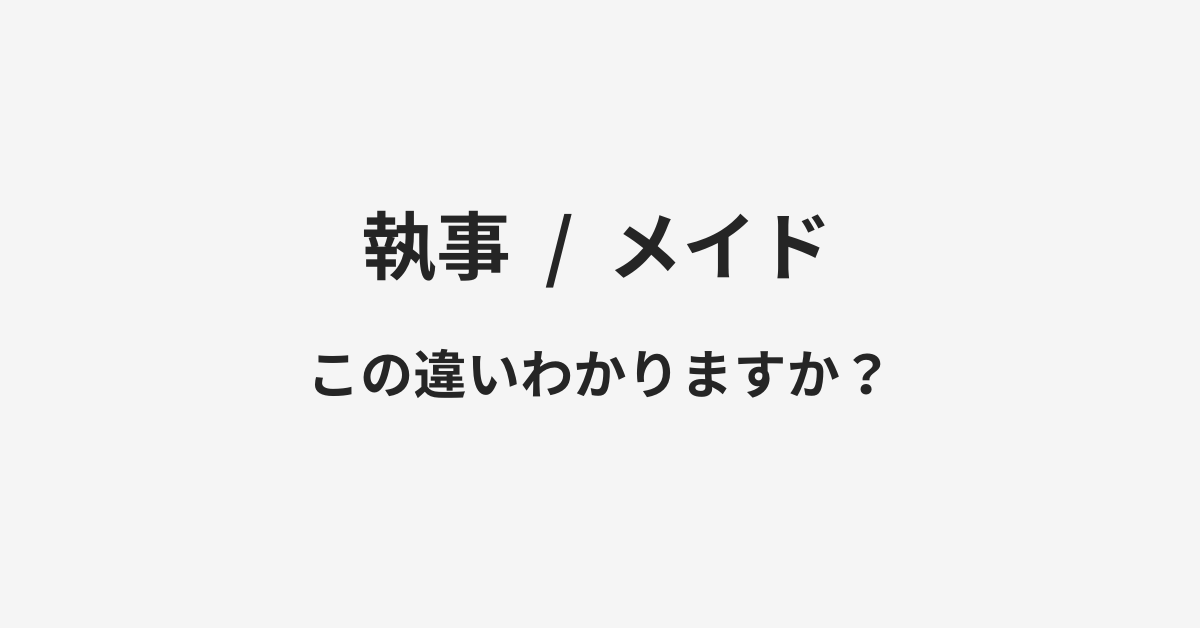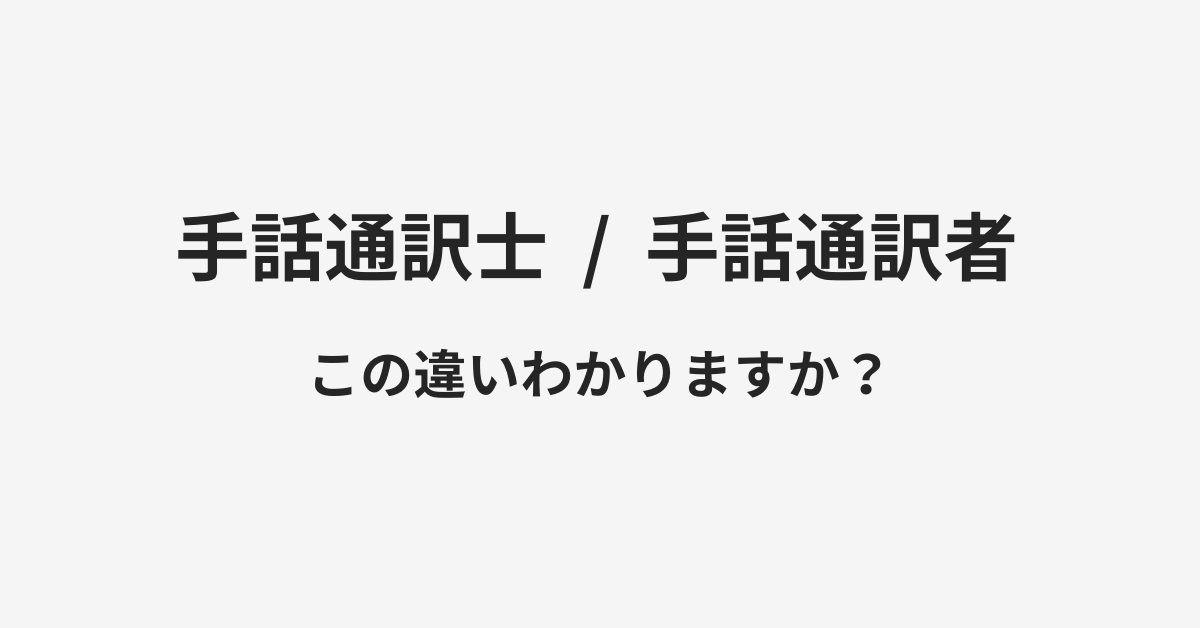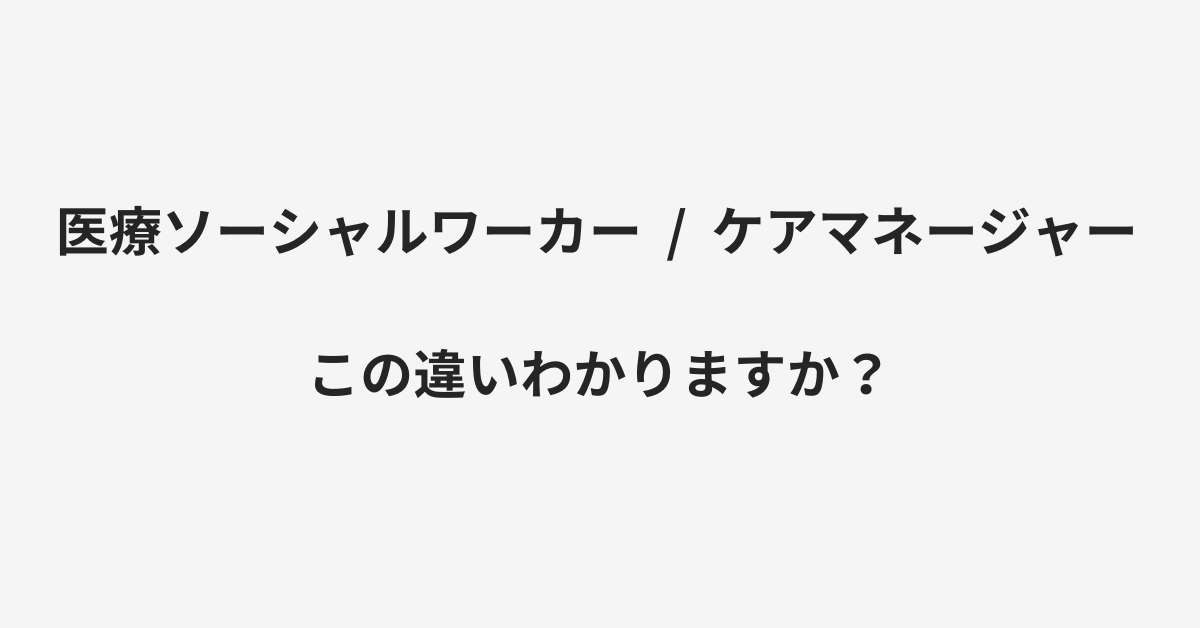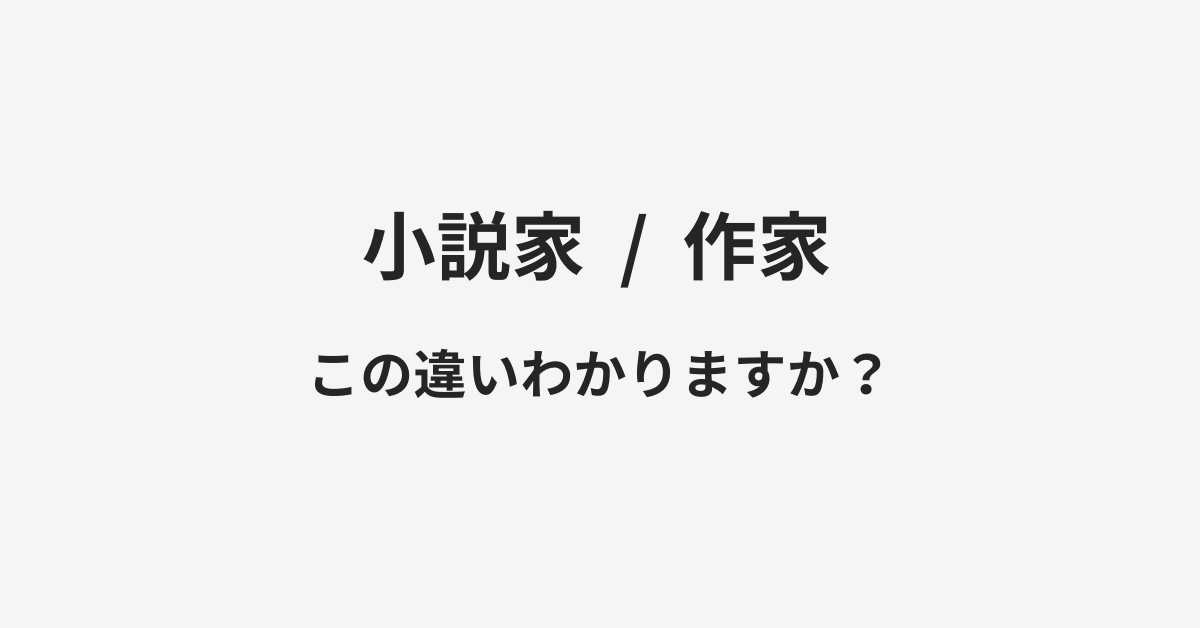【板前】と【調理師】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
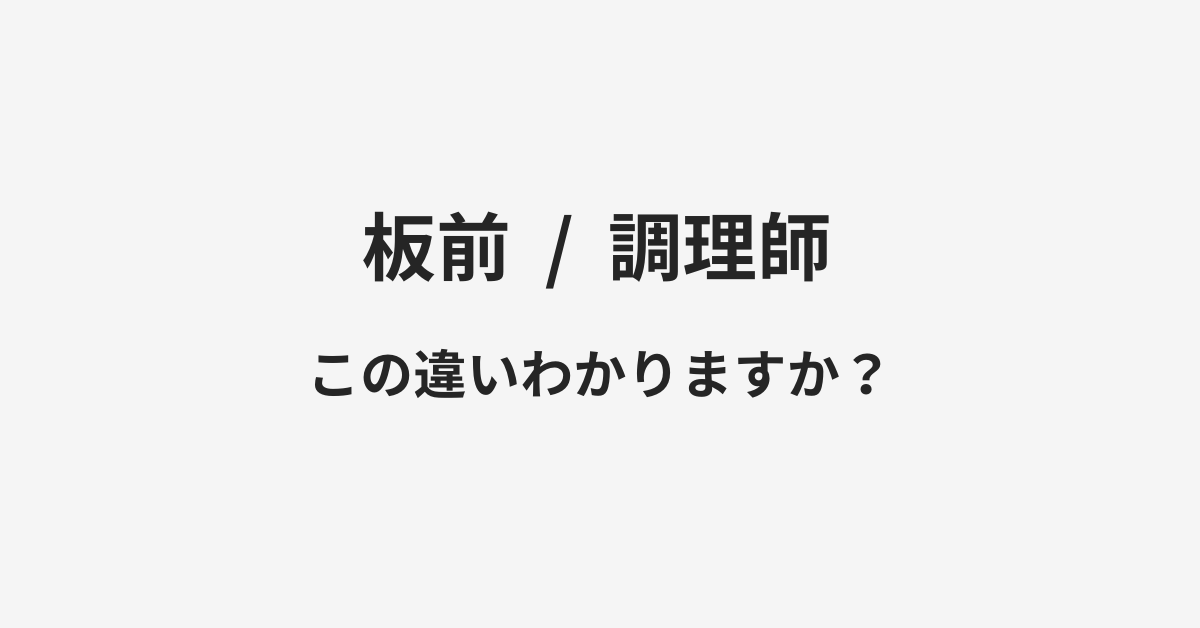
板前と調理師の分かりやすい違い
板前と調理師は、どちらも料理を作る職業ですが、その専門性と資格の有無に違いがあります。板前は主に日本料理店で働く和食の職人を指し、調理師は国家資格を持つ料理人全般を指します。
前者は伝統的な呼称で修行を重視し、後者は資格と衛生管理知識を重視するという特徴があります。
飲食業界において、この違いを理解することは、適切な人材採用とキャリア形成に重要です。
板前とは?
板前とは、日本料理店で調理を担当する料理人の呼称で、まな板の前に立つことから名付けられました。寿司職人、割烹料理人、懐石料理人など、和食の専門家を指します。単なる料理人ではなく、日本の食文化を体現する職人として、技術だけでなく所作、もてなしの心、季節感の表現なども求められます。
板前になるには、一般的に料理店での長期の修行が必要です。追い回し(下働き)から始まり、焼き場、揚げ場、煮方を経て、最終的に花板(料理長)を目指します。この修行期間は10年以上かかることも珍しくありません。調理師免許は必須ではありませんが、多くの板前は取得しています。
板前の世界は徒弟制度が色濃く残り、技術は見て盗むという伝統があります。しかし近年は、調理師学校で基礎を学んでから修行に入る人も増えています。独立開業する際は、技術力に加えて、仕入れルート、顧客基盤、資金力が必要です。
板前の例文
- ( 1 ) 一流の板前を目指して、老舗料亭で修行を積んでいます。
- ( 2 ) 板前として20年、お客様に喜ばれる料理を作り続けています。
- ( 3 ) 若手板前の育成に力を入れ、日本料理の伝統を継承しています。
- ( 4 ) 板前の技術を活かして、創作和食レストランを開業しました。
- ( 5 ) 花板として、仕入れから調理まで全体を統括しています。
- ( 6 ) 海外で板前として働き、日本料理の素晴らしさを伝えています。
板前の会話例
調理師とは?
調理師とは、調理師法に基づく国家資格を持ち、飲食店、病院、学校、企業の社員食堂などで調理業務に従事する専門職です。和食、洋食、中華、製菓など、ジャンルを問わず料理全般を扱います。食品衛生、栄養学、調理理論などの知識を持ち、安全で美味しい料理を提供する責任を負います。
調理師になるには、厚生労働大臣指定の調理師養成施設を卒業するか、2年以上の実務経験後に調理師試験に合格する必要があります。合格率は約60%で、衛生法規、公衆衛生学、栄養学、食品学、調理理論などが試験科目です。飲食店営業許可の際、調理師がいると食品衛生責任者の講習が免除されるメリットがあります。
調理師のキャリアパスは多様で、レストラン、ホテル、病院、学校給食、食品メーカーなど幅広い分野で活躍できます。専門調理師、調理技能士などの上位資格もあり、スキルアップが可能です。独立開業も選択肢の一つです。
調理師の例文
- ( 1 ) 調理師免許を取得し、ホテルのレストランで働いています。
- ( 2 ) 病院の調理師として、患者様の栄養管理に携わっています。
- ( 3 ) 調理師学校を卒業後、フレンチレストランに就職しました。
- ( 4 ) 調理師として独立し、創作料理のケータリング事業を始めました。
- ( 5 ) 学校給食の調理師として、子どもたちの食育に貢献しています。
- ( 6 ) 専門調理師の資格を目指して、技術向上に励んでいます。
調理師の会話例
板前と調理師の違いまとめ
板前と調理師の主な違いは、専門分野と資格の性質です。板前は日本料理に特化した職人的呼称、調理師は国家資格に基づく汎用的な職業名という違いがあります。キャリア形成も異なり、板前は伝統的な徒弟制度での長期修行、調理師は学校教育または実務経験を経て資格取得という道筋があります。
ただし、多くの板前も調理師免許を持っており、両者は重複することもあります。
就職や開業を考える際、日本料理の道を極めたいなら板前の修行、幅広い料理分野や安定した就職を望むなら調理師資格取得という選択になります。どちらも食文化を支える重要な職業です。
板前と調理師の読み方
- 板前(ひらがな):いたまえ
- 板前(ローマ字):itamae
- 調理師(ひらがな):ちょうりし
- 調理師(ローマ字):chourishi