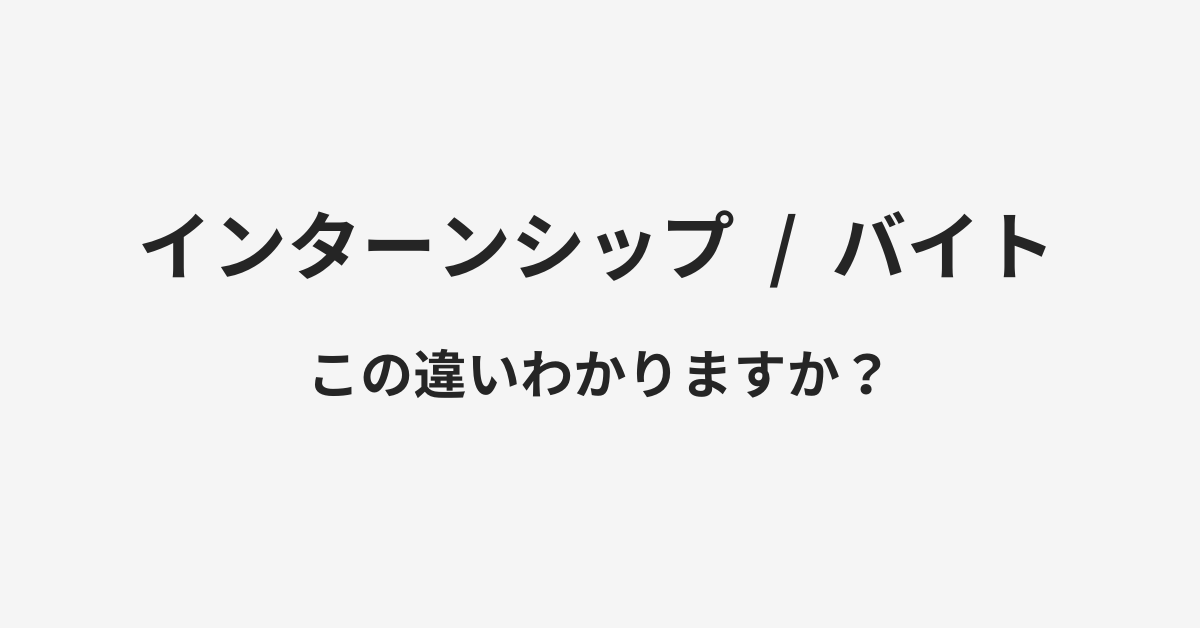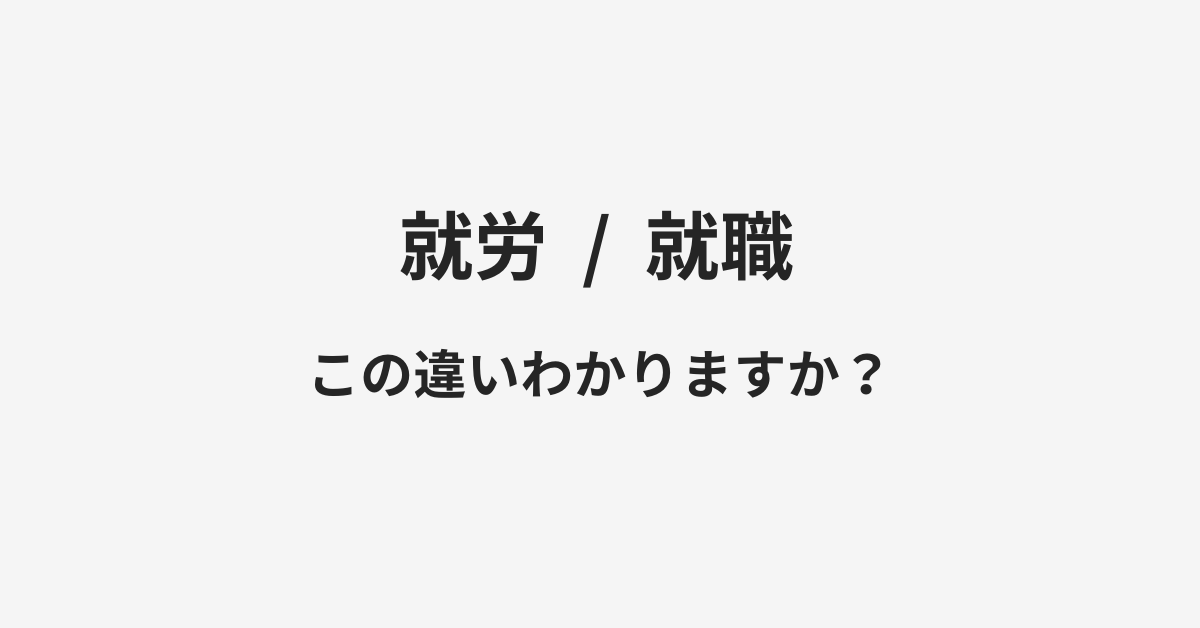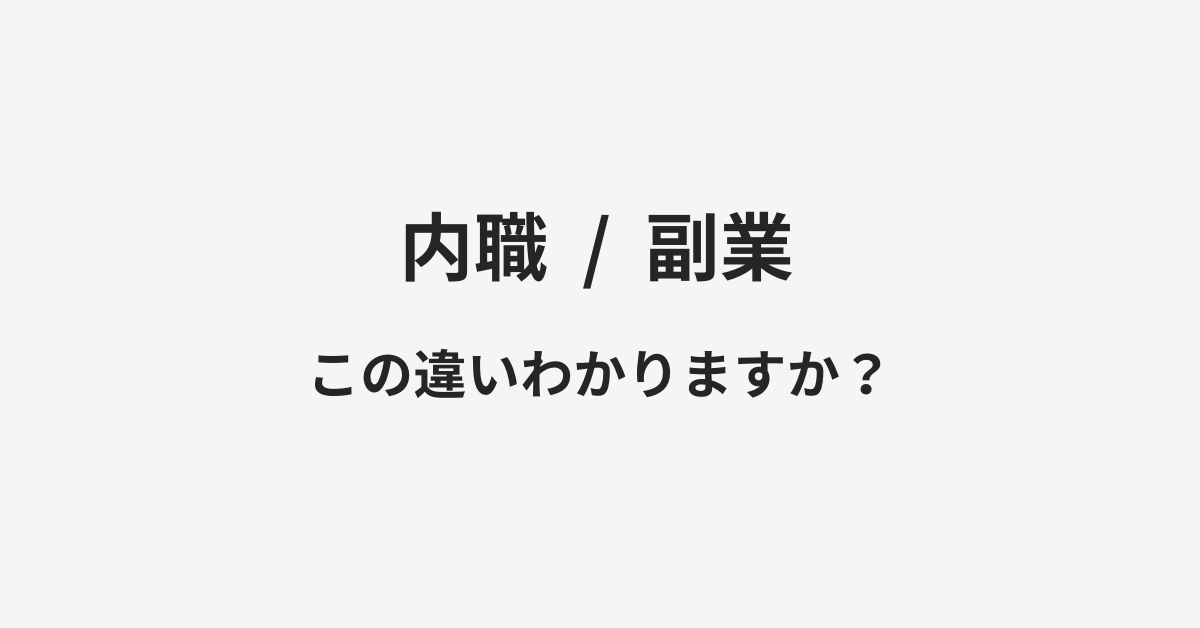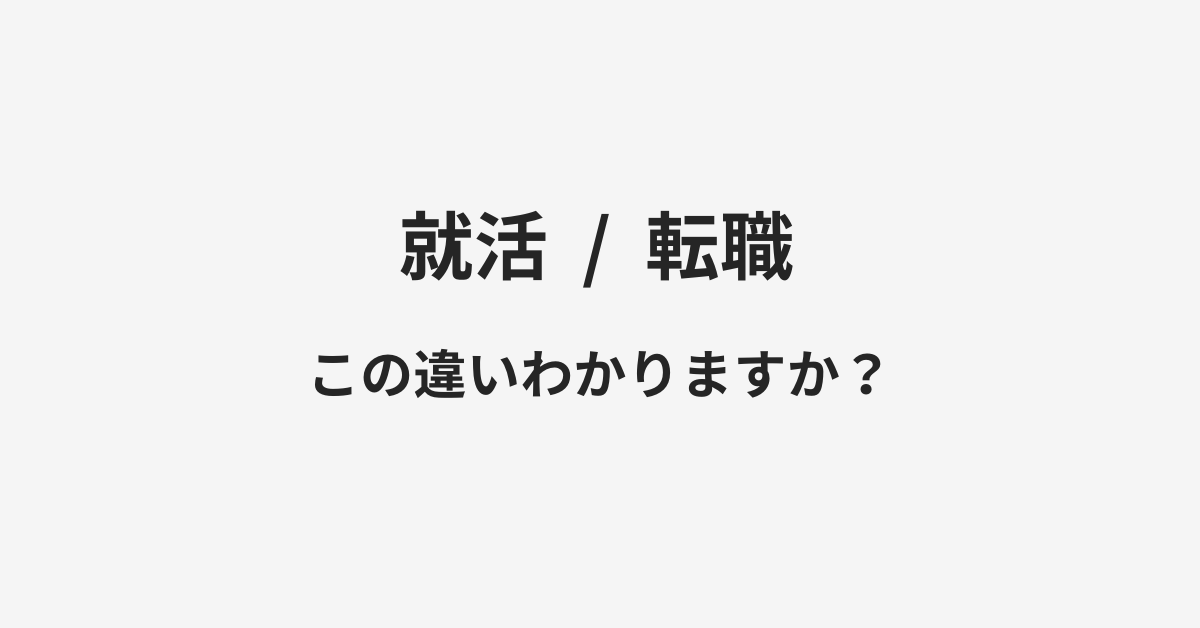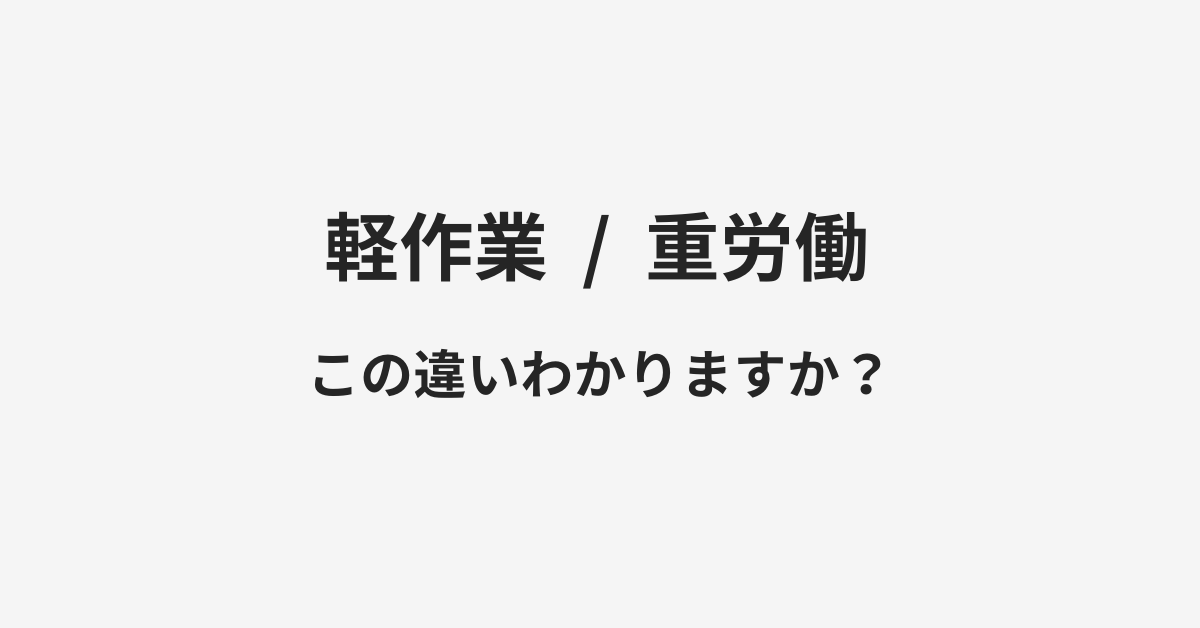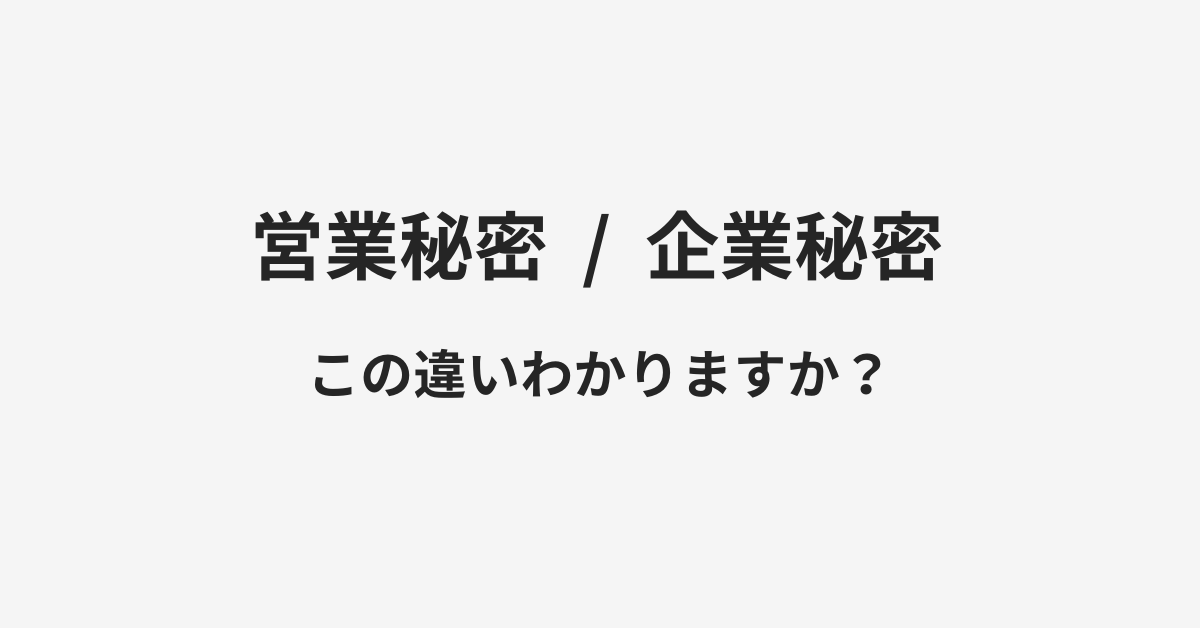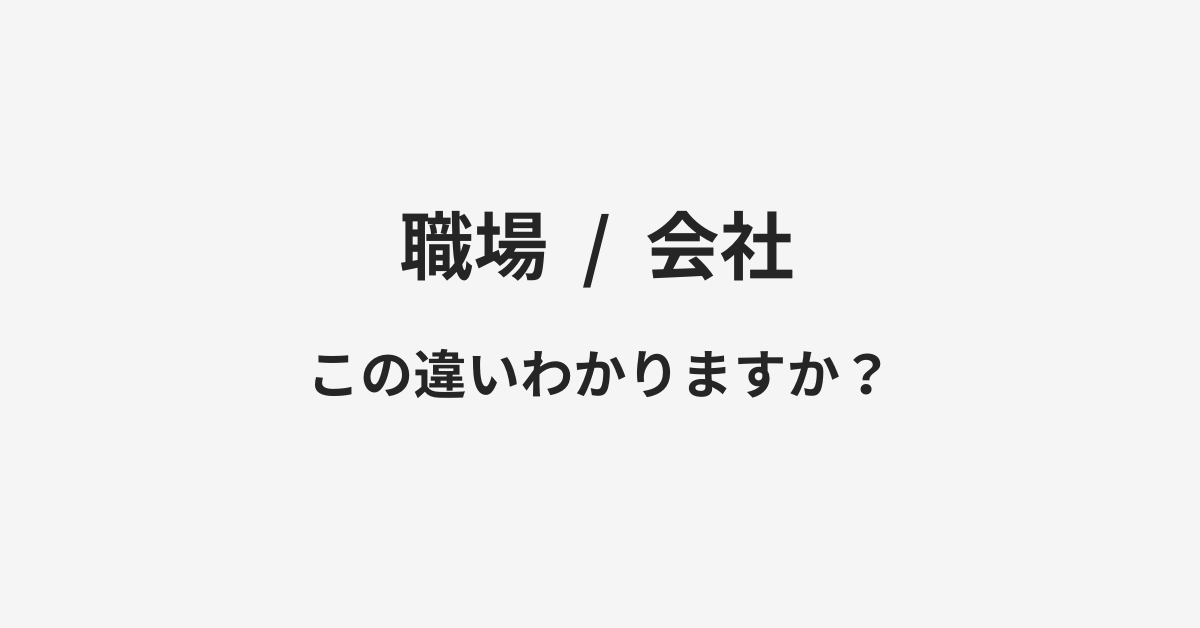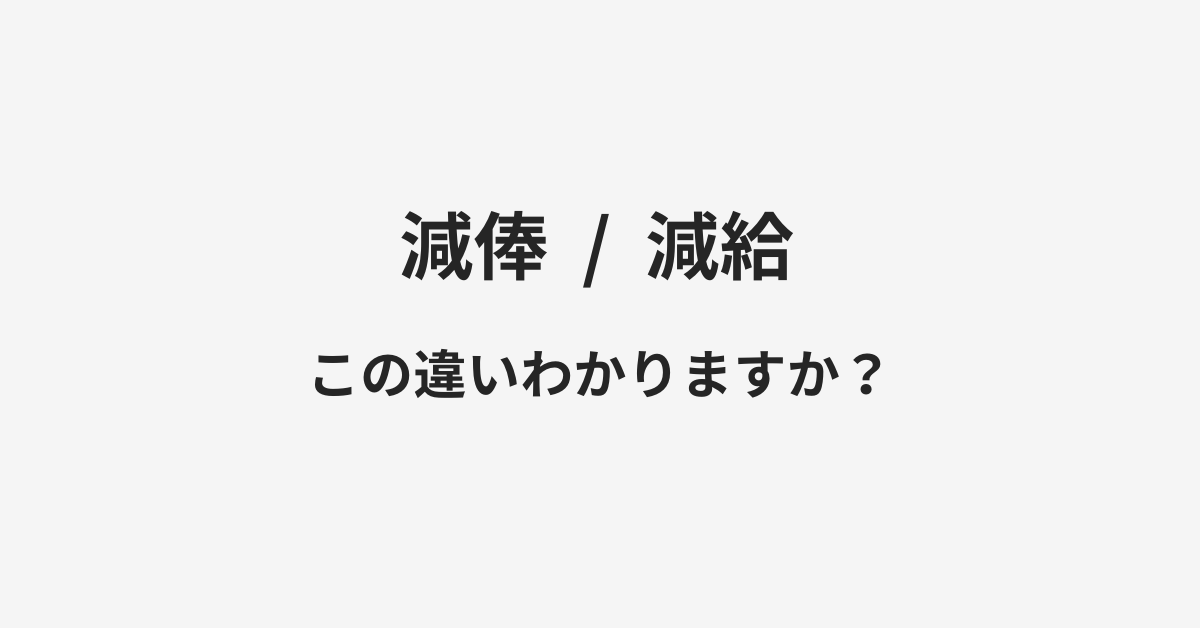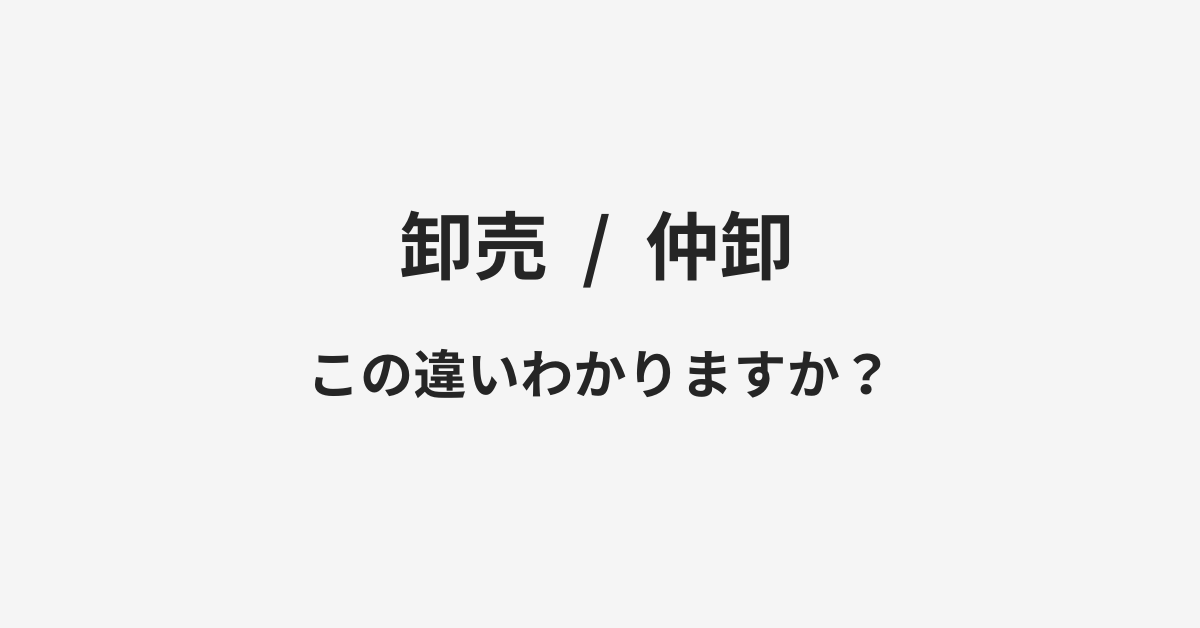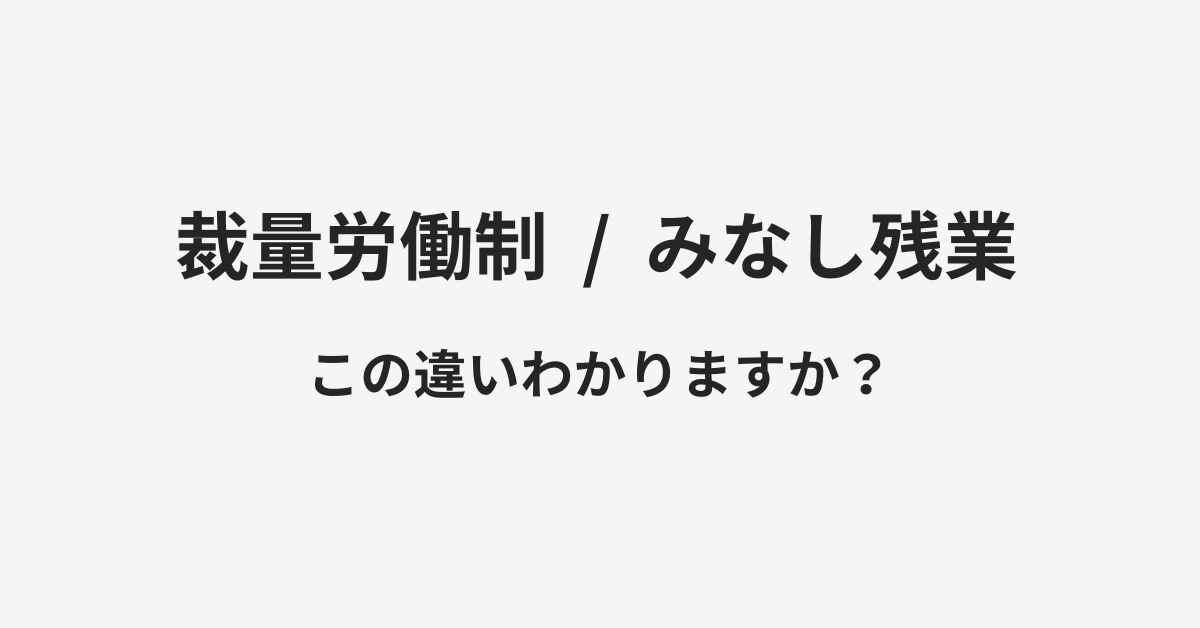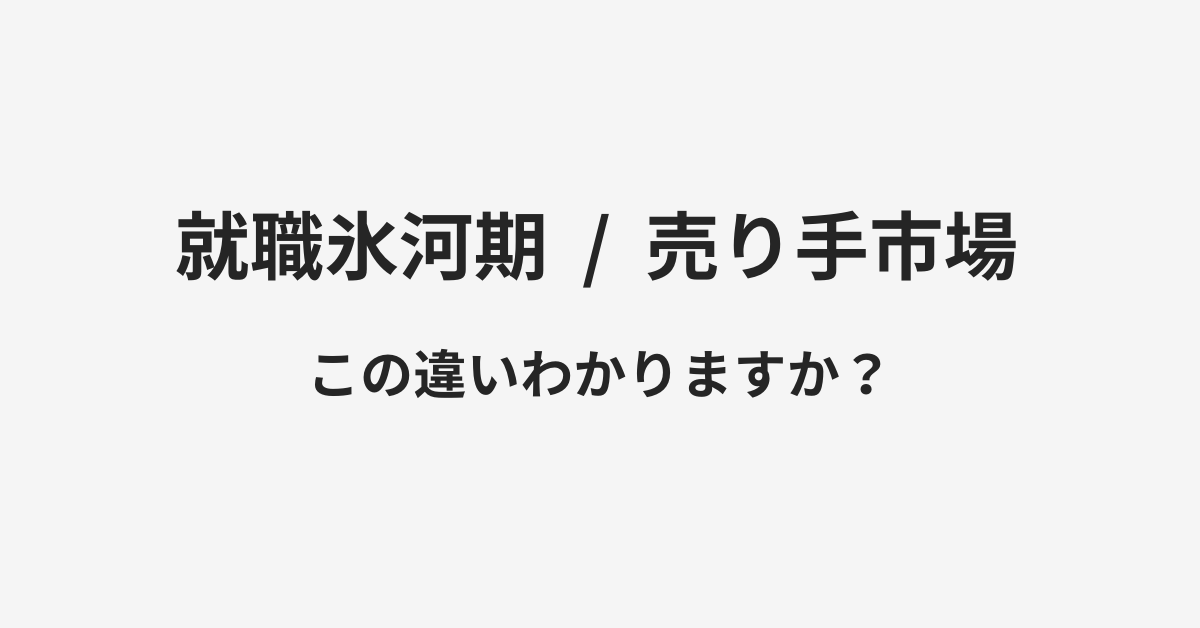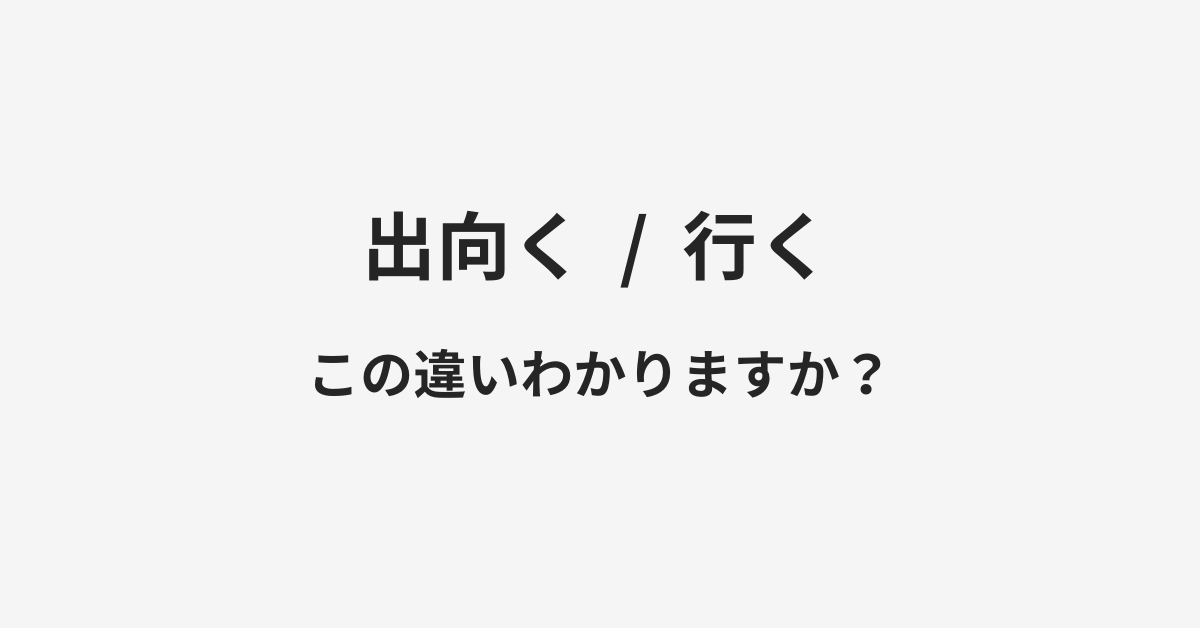【インターンシップ】と【アルバイト】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
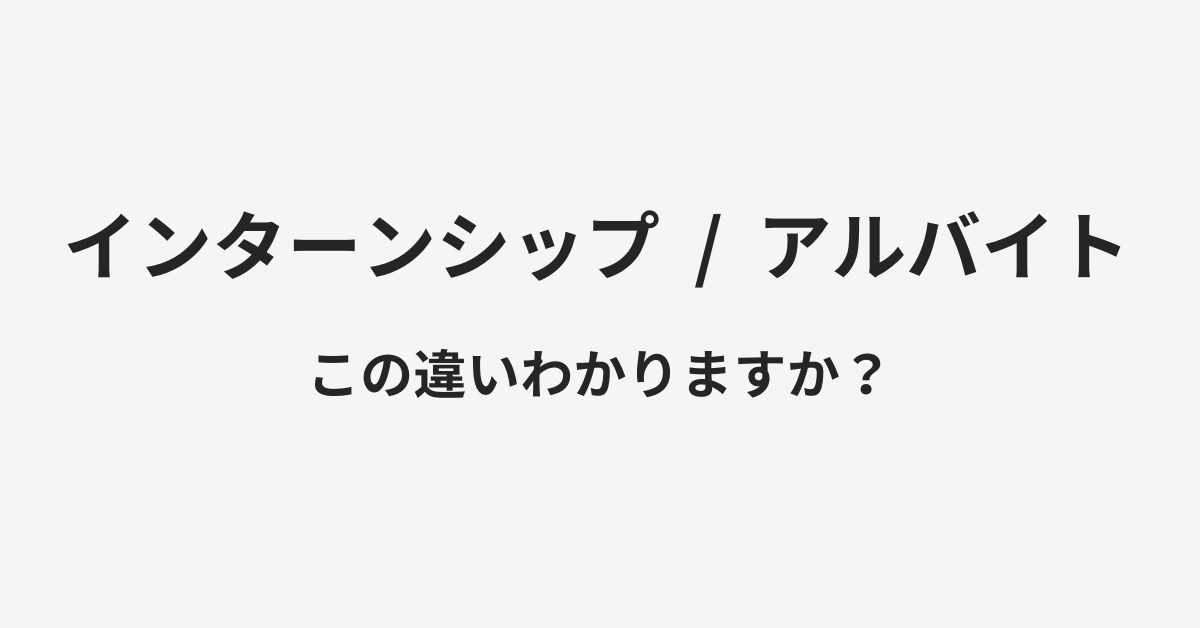
インターンシップとアルバイトの分かりやすい違い
インターンシップとアルバイトは、学生が会社で働くという点は同じですが、目的が大きく違います。
インターンシップは、仕事を体験して学ぶことが目的で、将来の就職に役立てるための活動です。アルバイトは、お金を稼ぐことが主な目的で、決められた仕事をこなす労働です。
インターンシップは学習と経験、アルバイトは労働と収入という違いがあります。
インターンシップとは?
インターンシップとは、学生が企業で一定期間、実際の業務を体験する教育的なプログラムで、職業観の醸成やキャリア形成を目的とします。
期間は1日から数か月まで様々で、就業体験を通じて業界理解、職種理解、自己理解を深めます。採用選考と連動する場合も多く、企業と学生の相互理解の機会となります。長期インターンでは実務に近い経験ができ、短期では会社説明やグループワークが中心です。有給と無給があり、教育的要素が強いほど無給の傾向があります。
近年は、オンラインインターンシップも普及し、地理的制約なく参加可能になっています。学業との両立が前提となります。
インターンシップの例文
- ( 1 ) 夏季インターンシップで、マーケティング部門の業務を体験しました。
- ( 2 ) 5日間のインターンシップを通じて、業界への理解が深まりました。
- ( 3 ) インターンシップ参加者の中から、優秀な人材を採用しています。
- ( 4 ) 長期インターンシップでは、実際のプロジェクトに参画できます。
- ( 5 ) オンラインインターンシップにより、地方学生の参加が増えました。
- ( 6 ) インターンシップは単位認定される場合もあり、大学と連携しています。
インターンシップの会話例
アルバイトとは?
アルバイトとは、学生や主婦などが本業の傍らで行う短時間・臨時的な労働で、主に収入を得ることを目的とします。
労働基準法上は正社員と同じ労働者として保護され、最低賃金以上の時給が保証されます。シフト制により、学業や生活に合わせて柔軟に働けることが特徴です。接客業、飲食業、小売業など様々な業種があり、社会経験や対人スキルの向上にもつながります。雇用契約を結び、労働の対価として確実に賃金を受け取れます。
学生にとっては生活費や学費の確保手段であり、企業にとっては柔軟な労働力として重要な存在です。社会保険加入条件を満たせば、各種保険も適用されます。
アルバイトの例文
- ( 1 ) コンビニでアルバイトをしながら、接客スキルを身につけました。
- ( 2 ) アルバイト代で学費を賄い、親の負担を軽減しています。
- ( 3 ) 深夜アルバイトは時給が25%増しになるため、効率的に稼げます。
- ( 4 ) アルバイトリーダーとして、新人の教育も担当しています。
- ( 5 ) 長期アルバイトは、有給休暇も取得できることを知りました。
- ( 6 ) アルバイトから正社員登用された先輩の話を聞き、モチベーションが上がりました。
アルバイトの会話例
インターンシップとアルバイトの違いまとめ
インターンシップとアルバイトは、目的と位置づけが根本的に異なります。
インターンシップは教育・キャリア形成が目的、アルバイトは収入確保が主目的です。インターンは就職活動の一環、アルバイトは生計を支える手段という違いがあります。
学生は目的に応じて選択し、企業も制度の違いを理解して適切に運用することが重要です。
インターンシップとアルバイトの読み方
- インターンシップ(ひらがな):いんたーんしっぷ
- インターンシップ(ローマ字):innta-nnshippu
- アルバイト(ひらがな):あるばいと
- アルバイト(ローマ字):arubaito