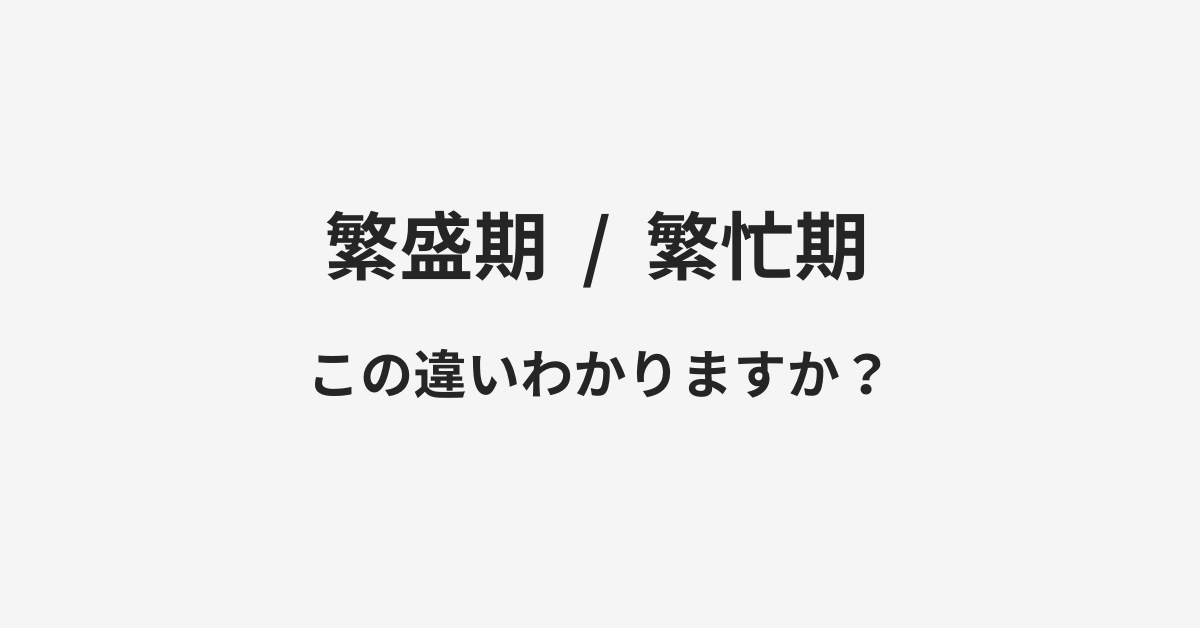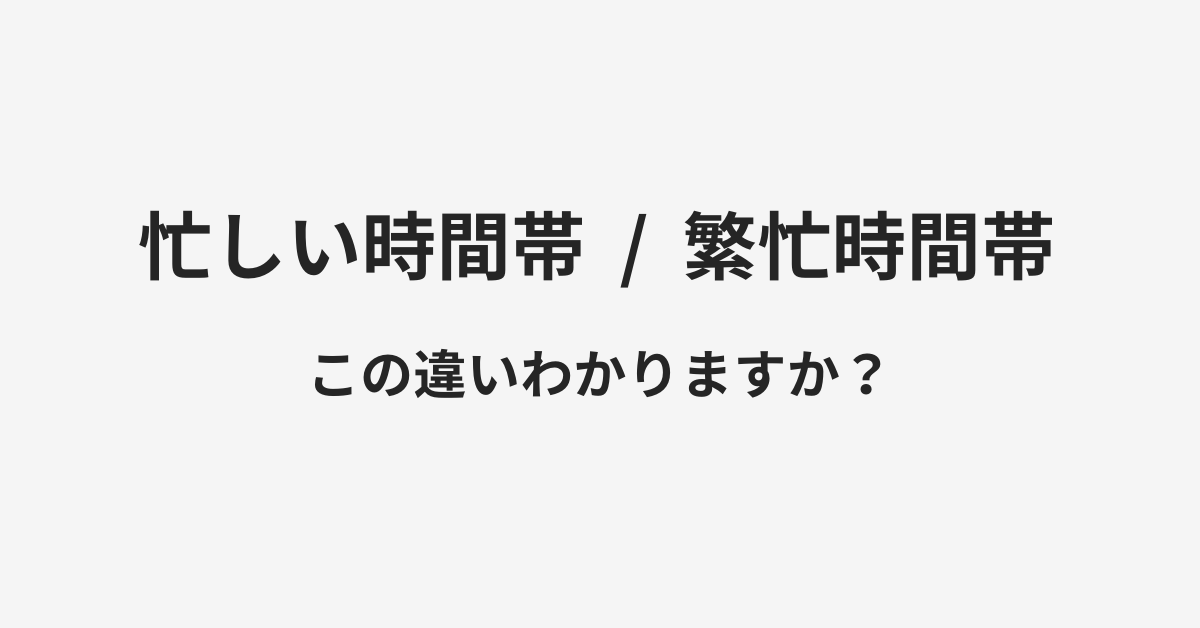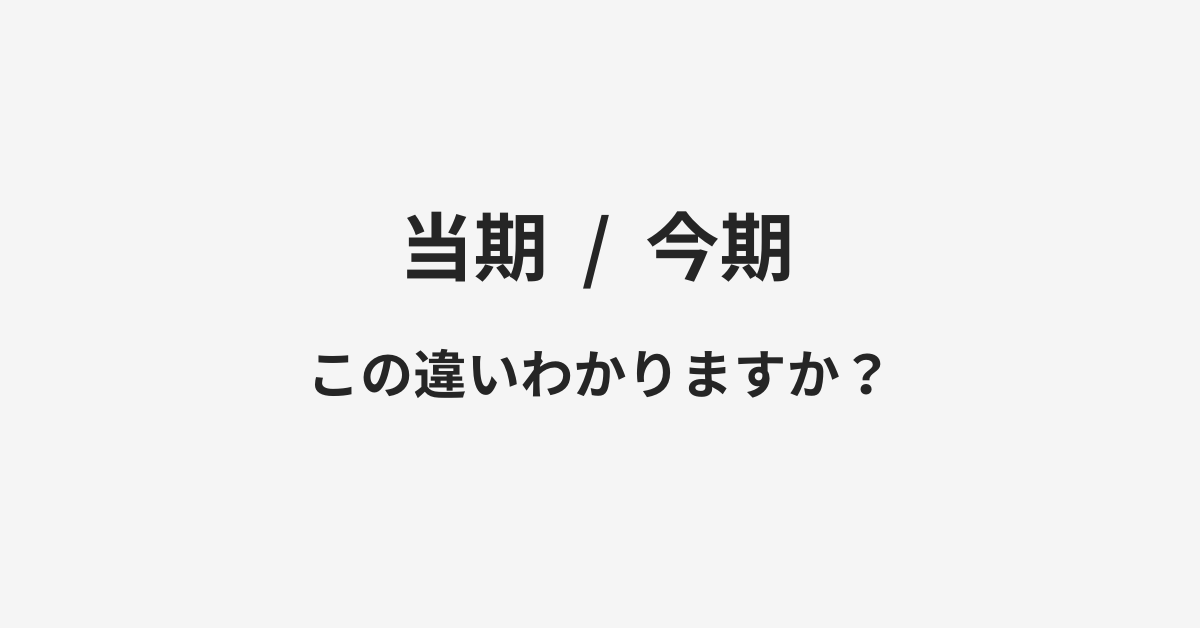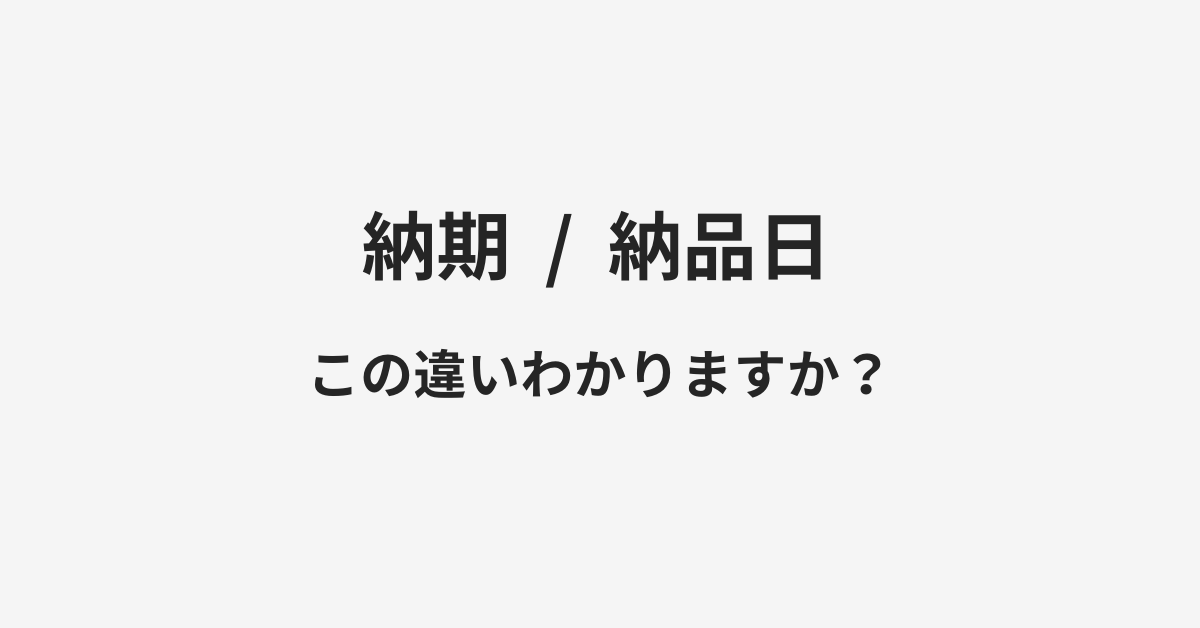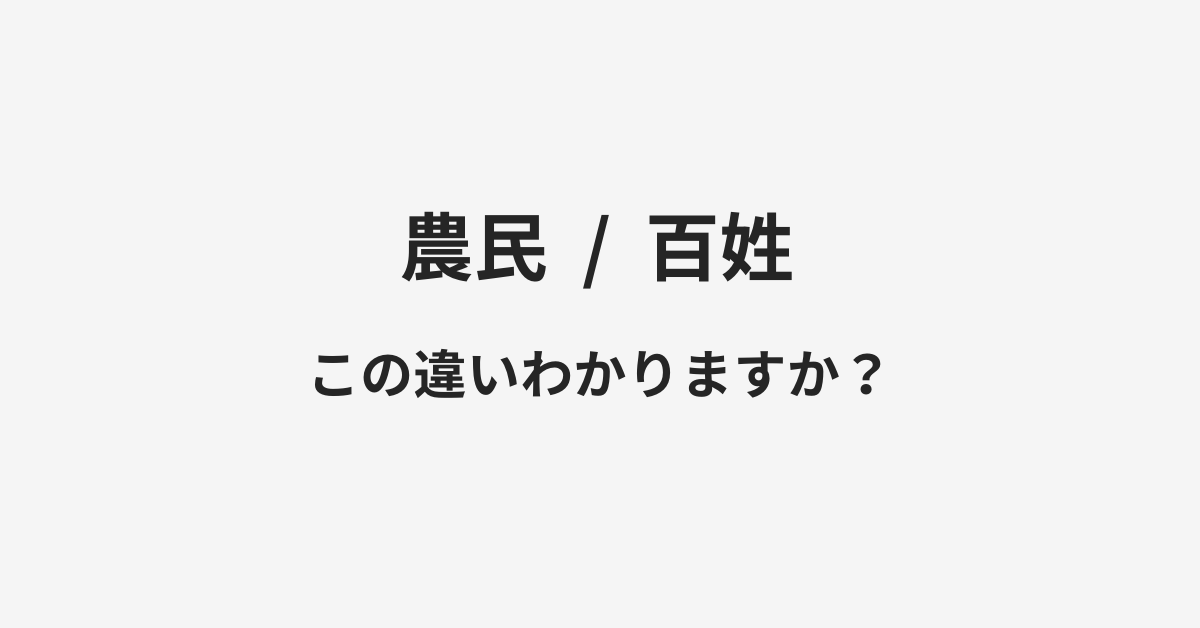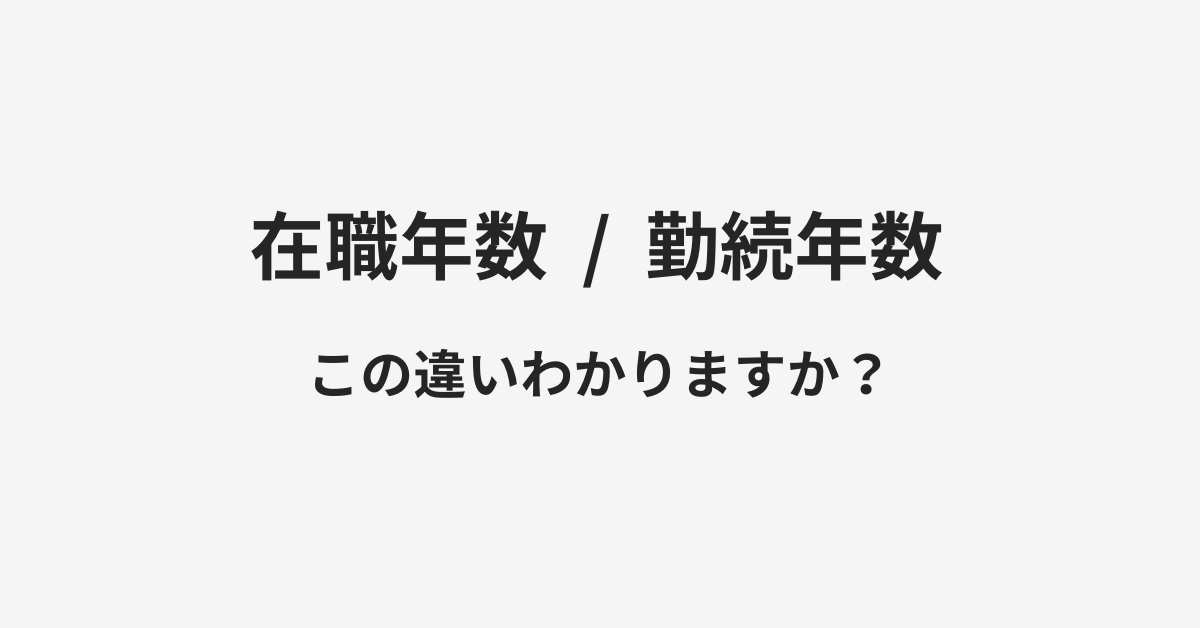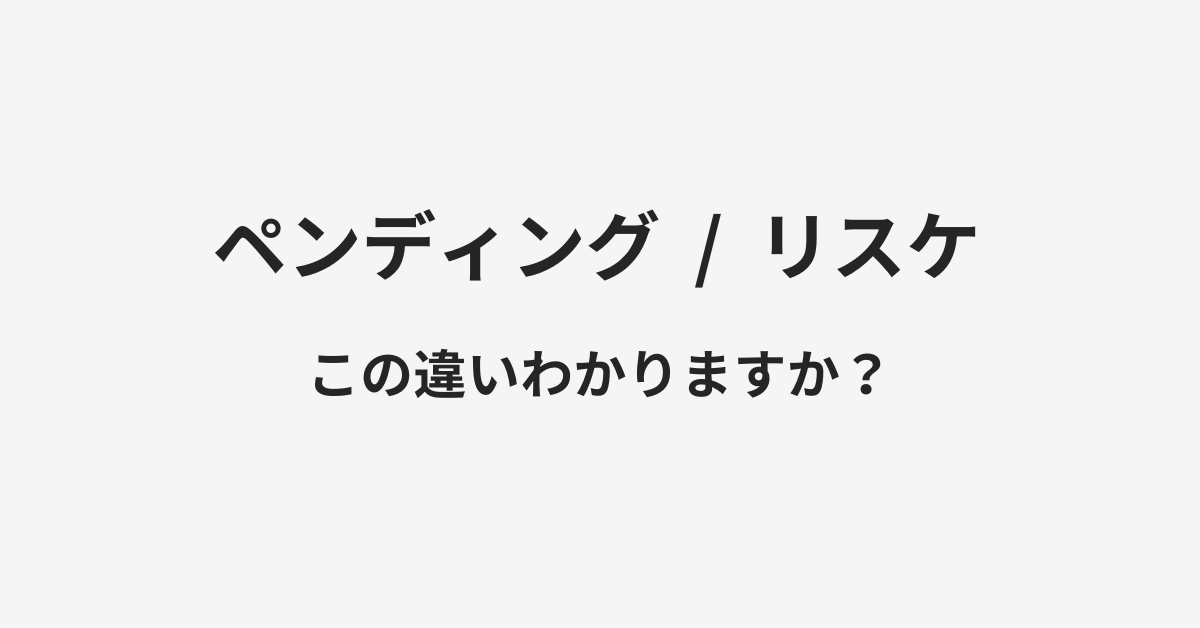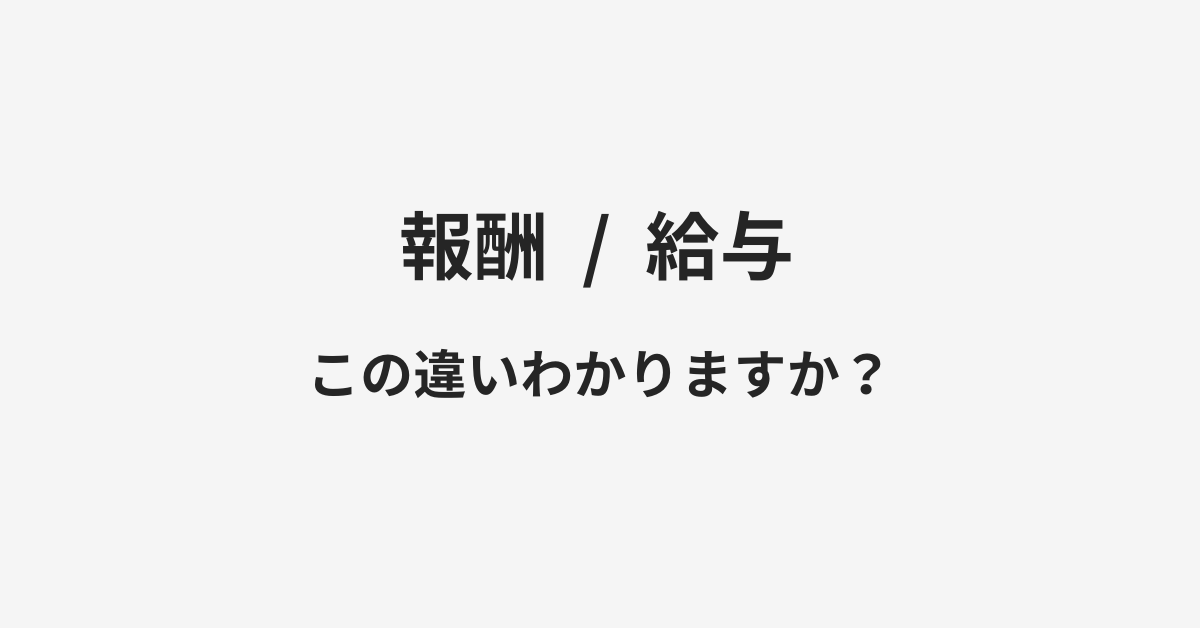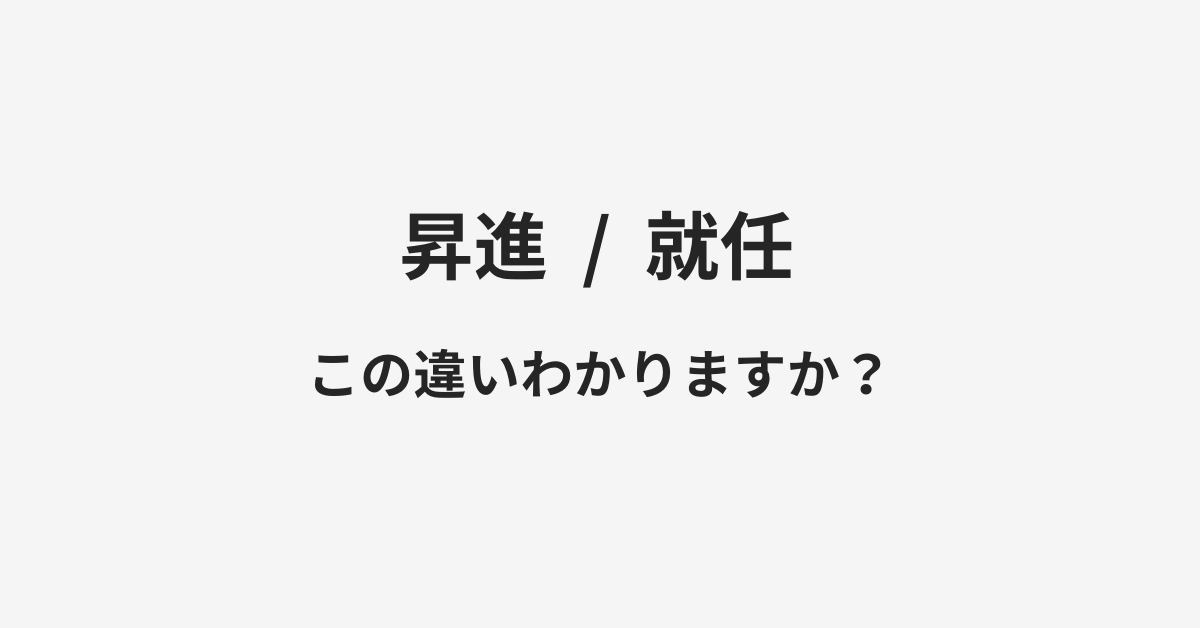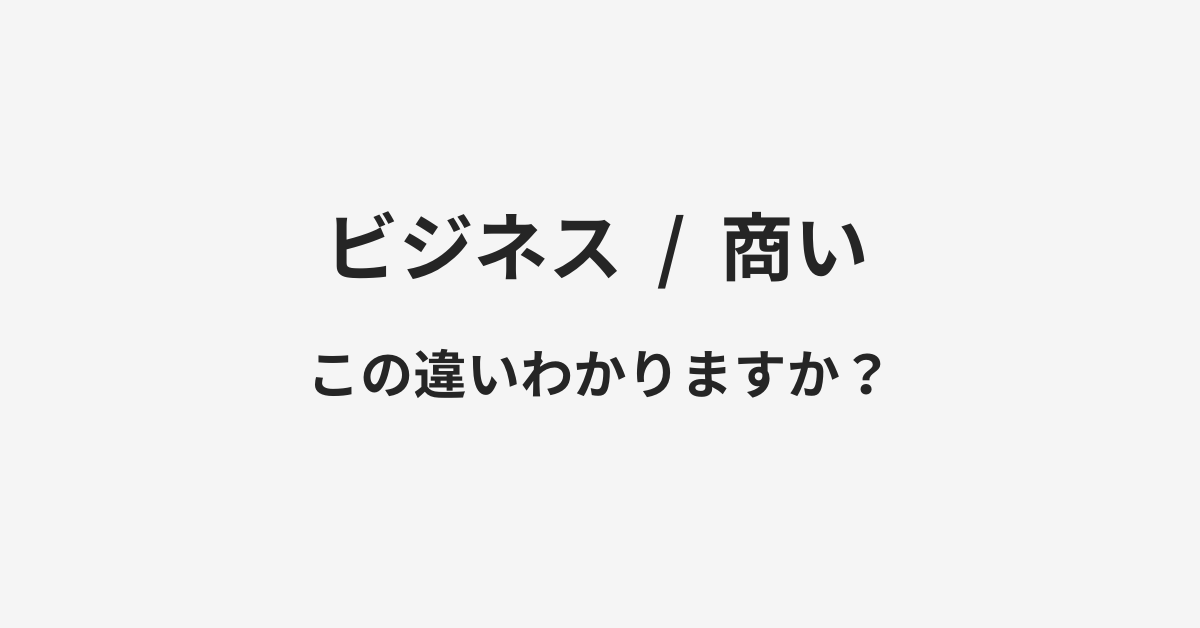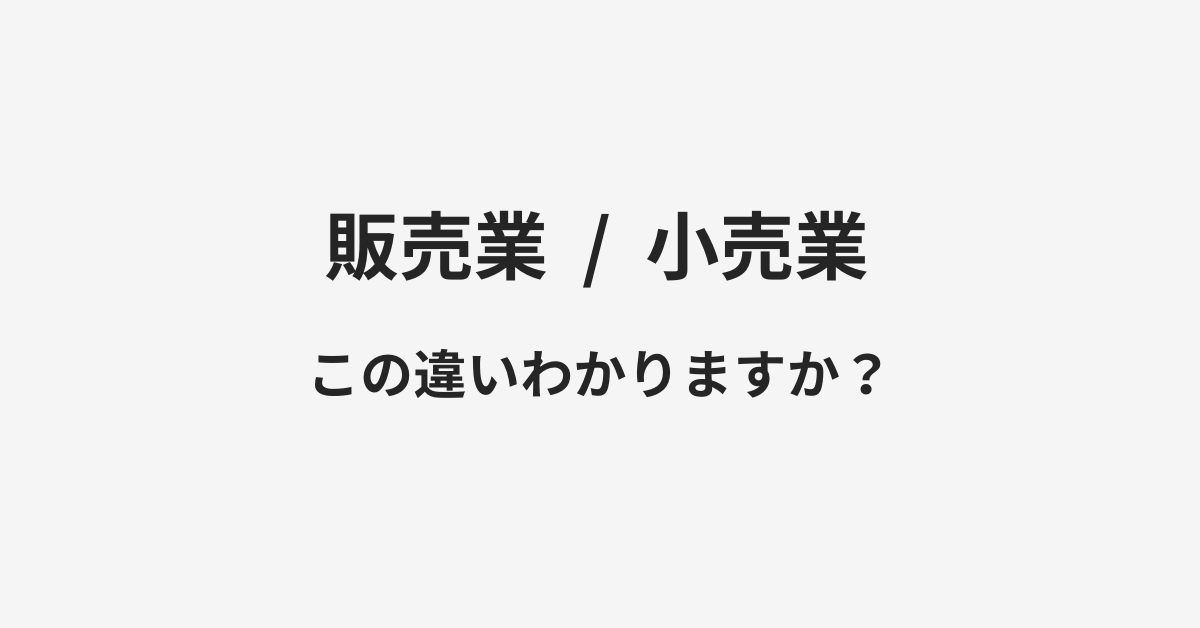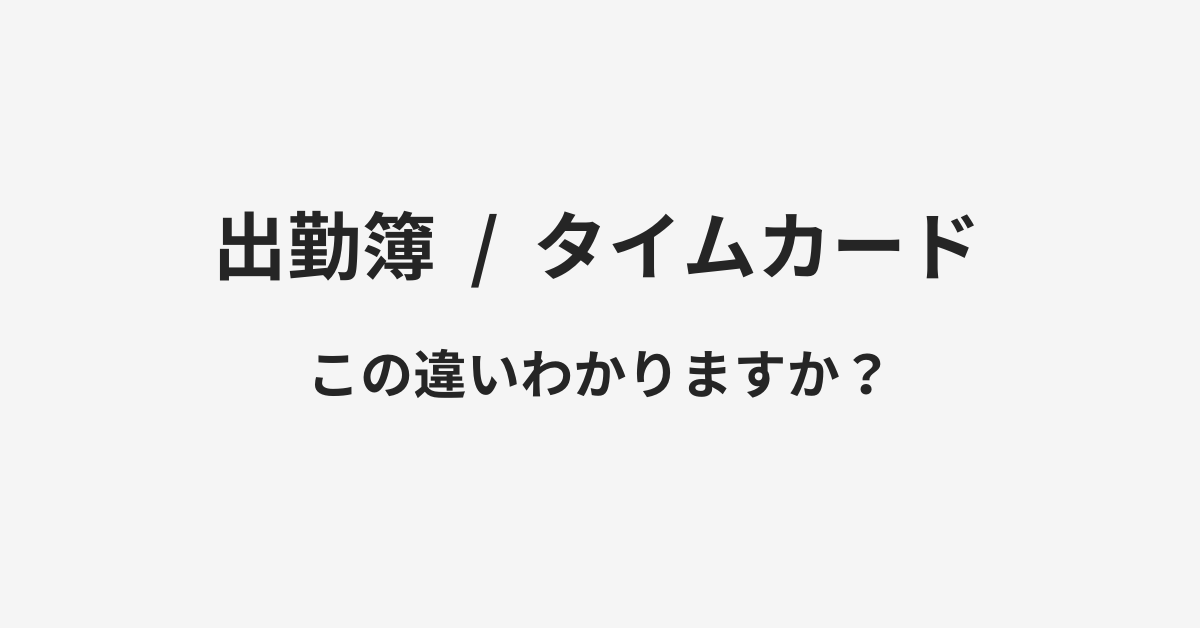【繁忙期】と【全盛期】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
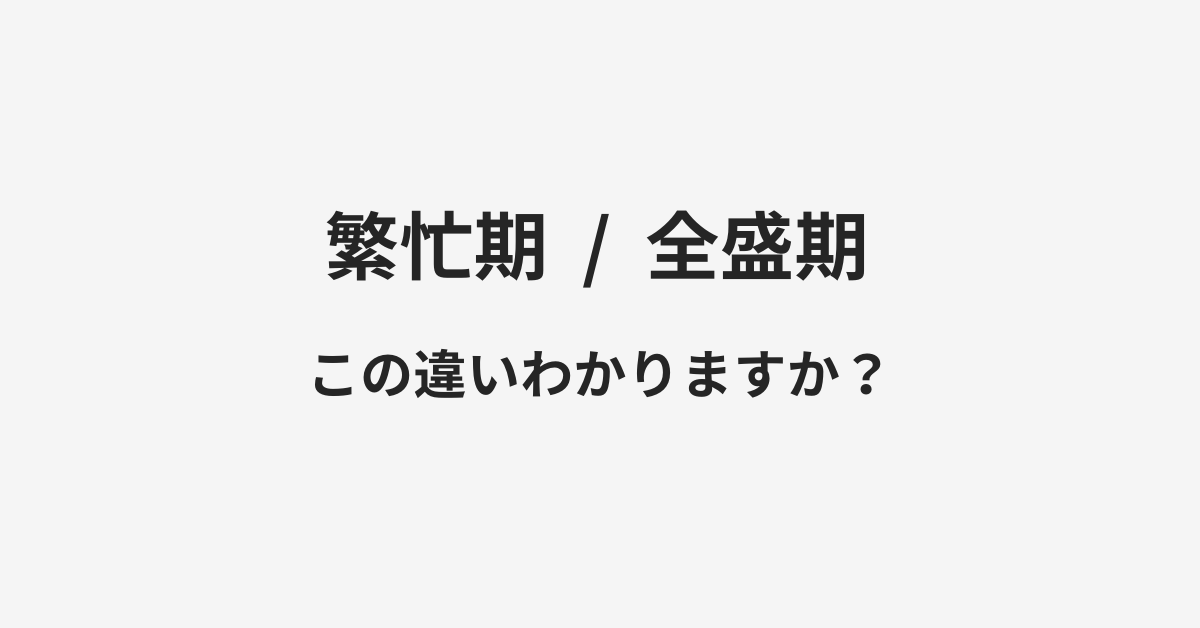
繁忙期と全盛期の分かりやすい違い
繁忙期と全盛期は、どちらも活発な時期を表しますが、その意味と使われ方が大きく異なります。
繁忙期は、仕事が特に忙しい時期のことです。例えば、年末の小売店、決算期の経理部、夏休みの観光業などが該当します。全盛期は、人や企業が最も成功し、勢いがあった時期のことです。あの会社の全盛期は1990年代だったのように、過去の最高の時期を指すことが多いです。
つまり、繁忙期は忙しい時期、全盛期は最も栄えた時期という違いがあります。
繁忙期とは?
繁忙期とは、年間を通じて業務量が特に多く、忙しさがピークに達する特定の期間を指します。業種により繁忙期は異なり、小売業の年末年始、会計事務所の確定申告時期、引越し業の3-4月、観光業の大型連休など、季節性や社会的イベントに連動することが一般的です。
繁忙期の特徴は、通常期の数倍の業務量、残業時間の増加、臨時スタッフの雇用、在庫の増強などです。適切な繁忙期対策には、事前の需要予測、人員計画、業務効率化、従業員の健康管理が不可欠です。また、繁忙期手当の支給や、閑散期での代休取得など、労務管理面での配慮も重要です。
繁忙期を乗り切るには、早期の準備、チームワークの強化、業務の優先順位付け、自動化・システム化の推進が効果的です。また、繁忙期の経験を分析し、翌年への改善につなげるPDCAサイクルの実践も重要です。
繁忙期の例文
- ( 1 ) 12月は小売業界の繁忙期なので、アルバイトを増員します。
- ( 2 ) 繁忙期に備えて、業務マニュアルの整備を進めています。
- ( 3 ) 繁忙期の残業時間が労基法の上限に近づいているため、対策が必要です。
- ( 4 ) 今年の繁忙期は例年より早く始まり、在庫が不足する事態となりました。
- ( 5 ) 繁忙期と閑散期の業務量の差を平準化する施策を検討しています。
- ( 6 ) 繁忙期手当を支給し、従業員のモチベーション維持を図っています。
繁忙期の会話例
全盛期とは?
全盛期とは、個人、企業、産業などが最も繁栄し、力や影響力がピークに達していた時期を指す言葉です。ビジネスにおいては、売上高、市場シェア、ブランド力、技術力などが最高水準にあった期間を表します。多くの場合、過去を振り返って使用され、現在との比較や歴史的評価の文脈で用いられます。
企業の全盛期は、革新的な製品・サービスの成功、カリスマ的リーダーの存在、市場環境の好条件などが重なることで訪れます。日本企業では、高度経済成長期やバブル期を全盛期とする企業が多く、当時の成功体験が企業文化に影響を与えています。
全盛期の分析は、成功要因の特定、現在への教訓の抽出、将来戦略の参考として重要です。ただし、過去の全盛期に固執することなく、環境変化に適応し、新たな成長を目指すことが企業の持続的発展には不可欠です。
全盛期の例文
- ( 1 ) 当社の全盛期は2000年代前半で、業界シェア40%を誇っていました。
- ( 2 ) 創業者が率いていた時代が、この会社の全盛期だったと言われています。
- ( 3 ) 全盛期の成功体験から学び、新たな成長戦略を構築する必要があります。
- ( 4 ) あの製品の全盛期には、1日1000個も売れていたそうです。
- ( 5 ) 業界全体の全盛期は過ぎましたが、新たなビジネスモデルで再成長を目指します。
- ( 6 ) 全盛期を知る社員から、当時の企業文化や成功要因を聞き取り調査しています。
全盛期の会話例
繁忙期と全盛期の違いまとめ
繁忙期と全盛期の違いを理解することは、適切な状況認識と表現に重要です。繁忙期は現在進行形の忙しさ、全盛期は過去の栄光という時間軸の違いが基本です。
実務では、繁忙期は業務管理や人員配置の文脈で使用され、対策や準備が必要な実践的な概念です。一方、全盛期は企業分析や歴史的評価の文脈で使用され、回顧的・分析的な概念です。
また、繁忙期は定期的に訪れる可能性がありますが、全盛期は通常一度きりか、長い周期で訪れるものです。繁忙期への対応は現在の経営課題、全盛期の分析は将来戦略の参考材料という位置づけの違いもあります。
繁忙期と全盛期の読み方
- 繁忙期(ひらがな):はんぼうき
- 繁忙期(ローマ字):hannbouki
- 全盛期(ひらがな):ぜんせいき
- 全盛期(ローマ字):zennseiki