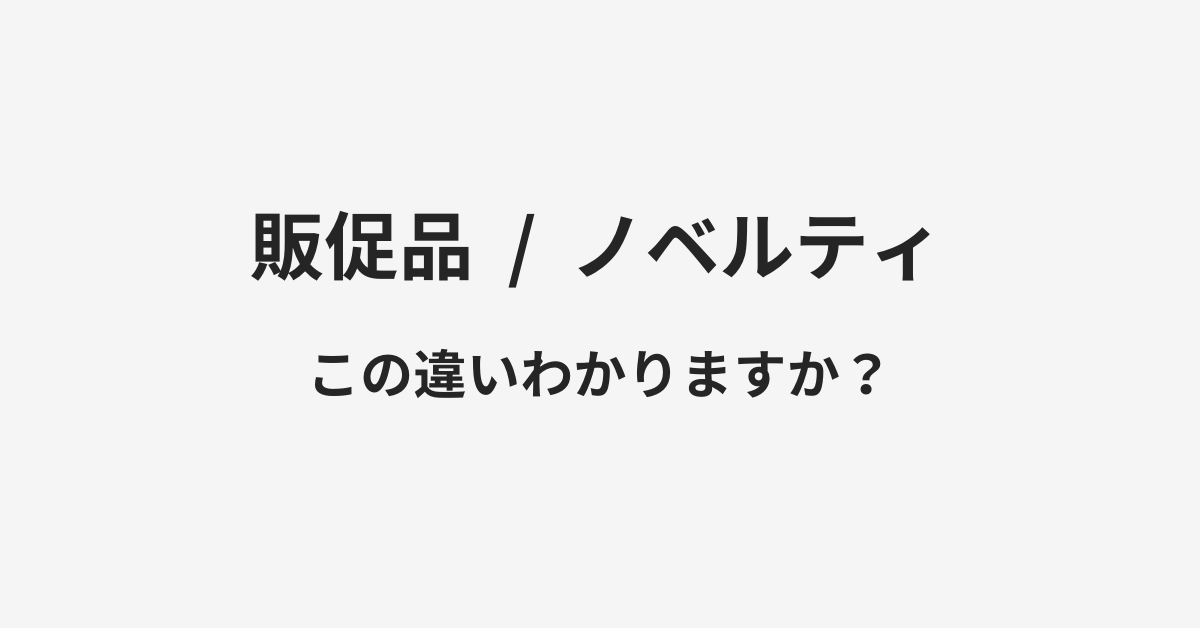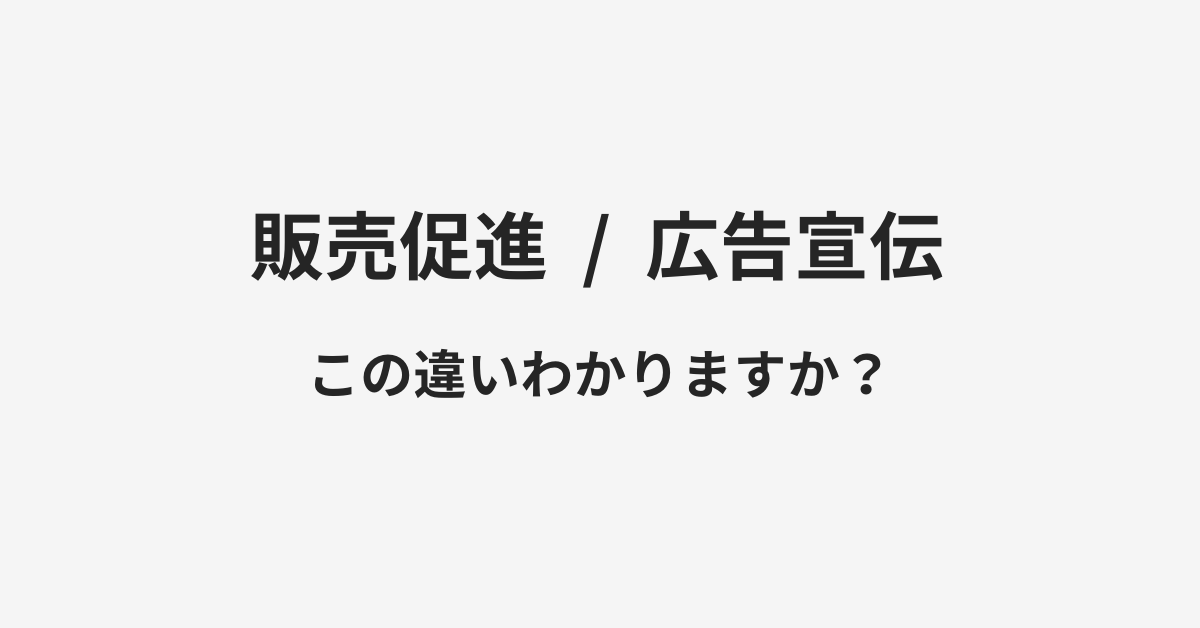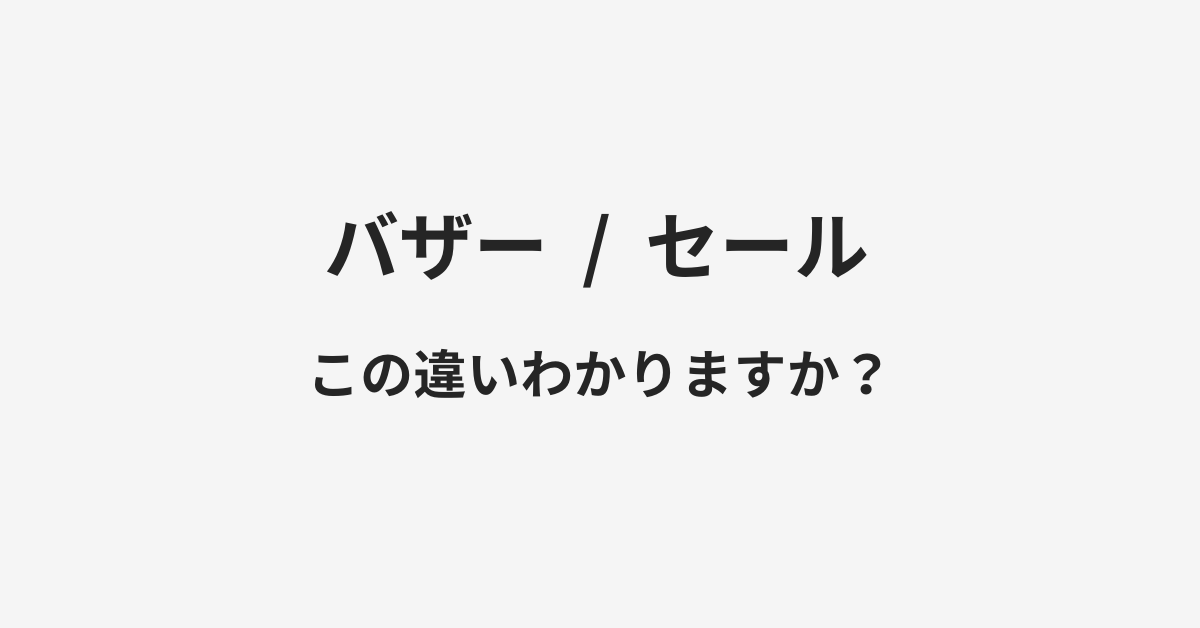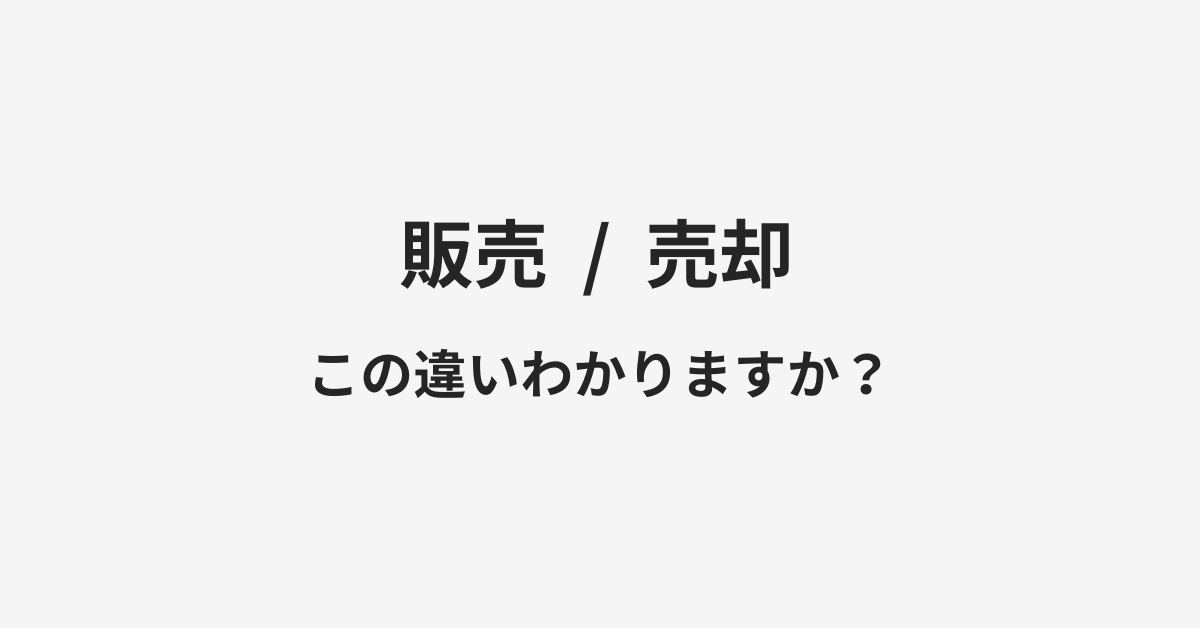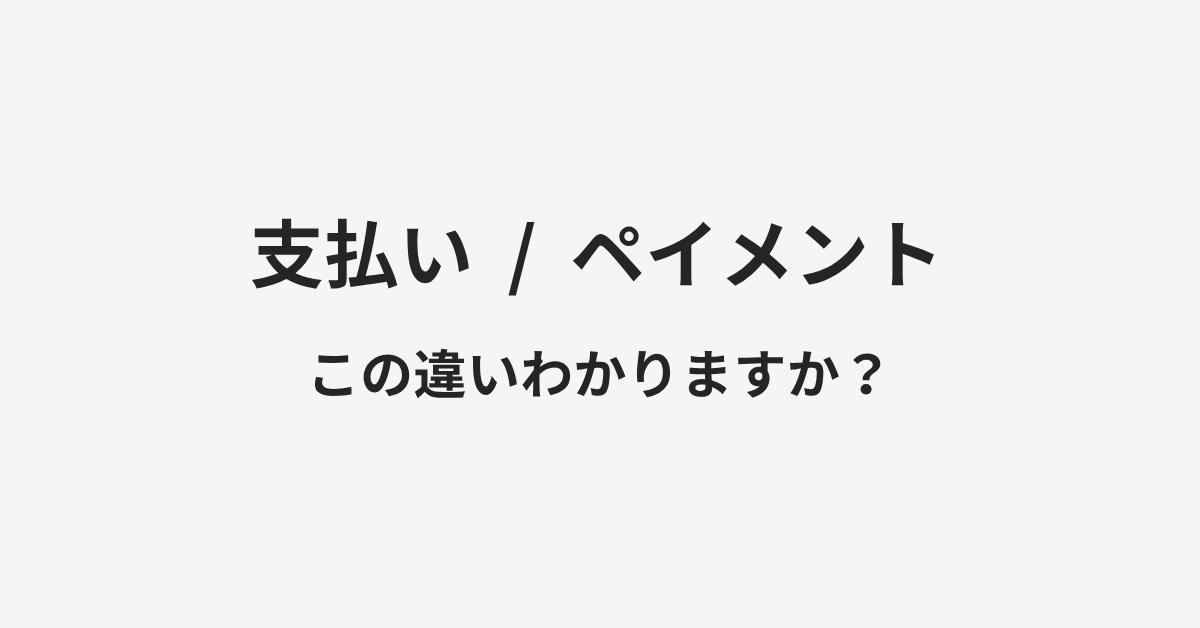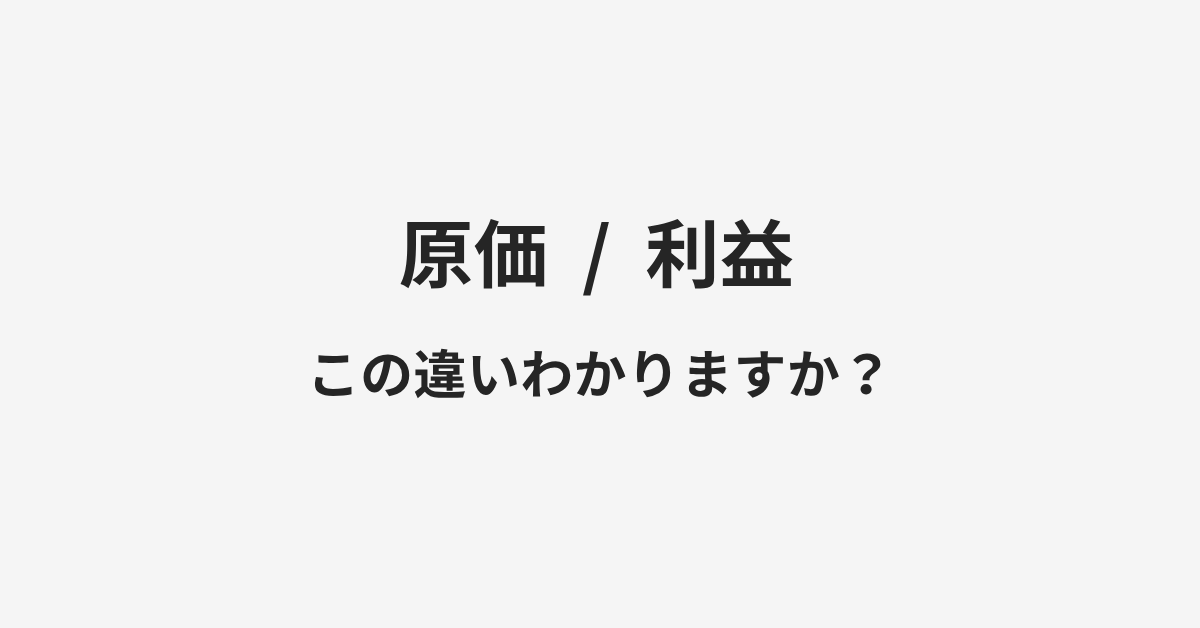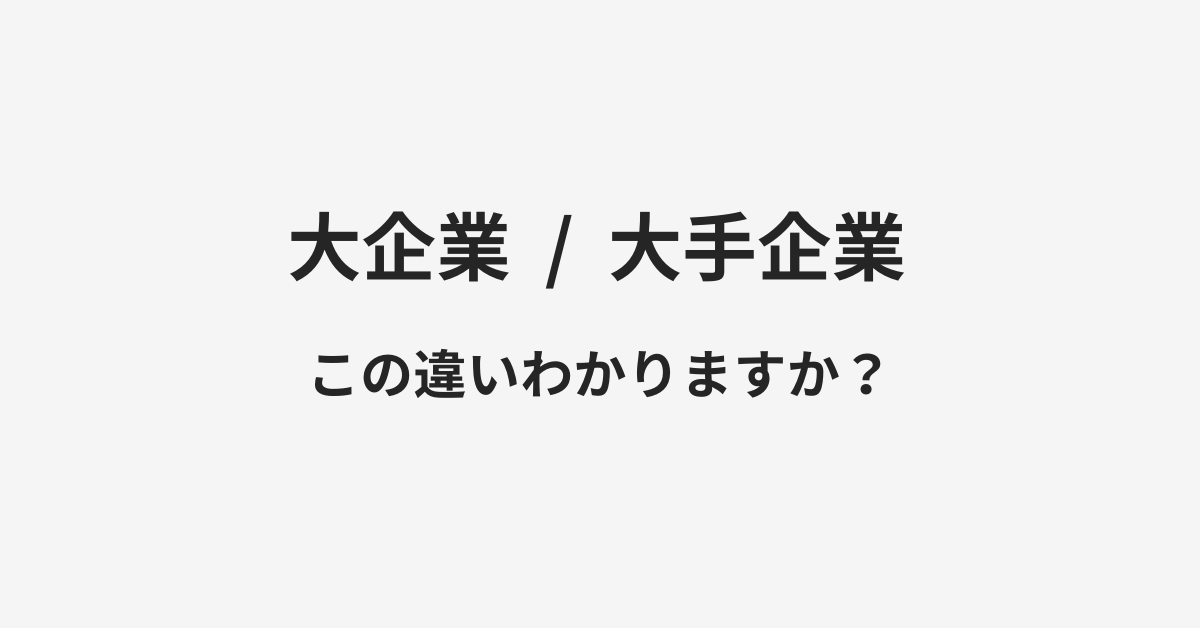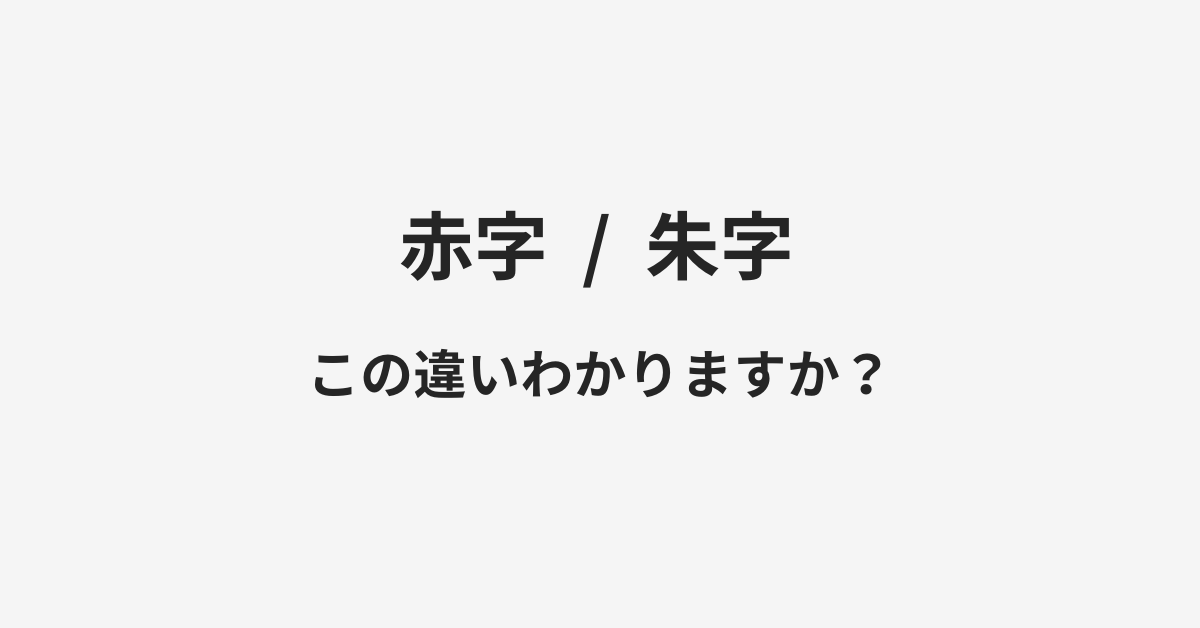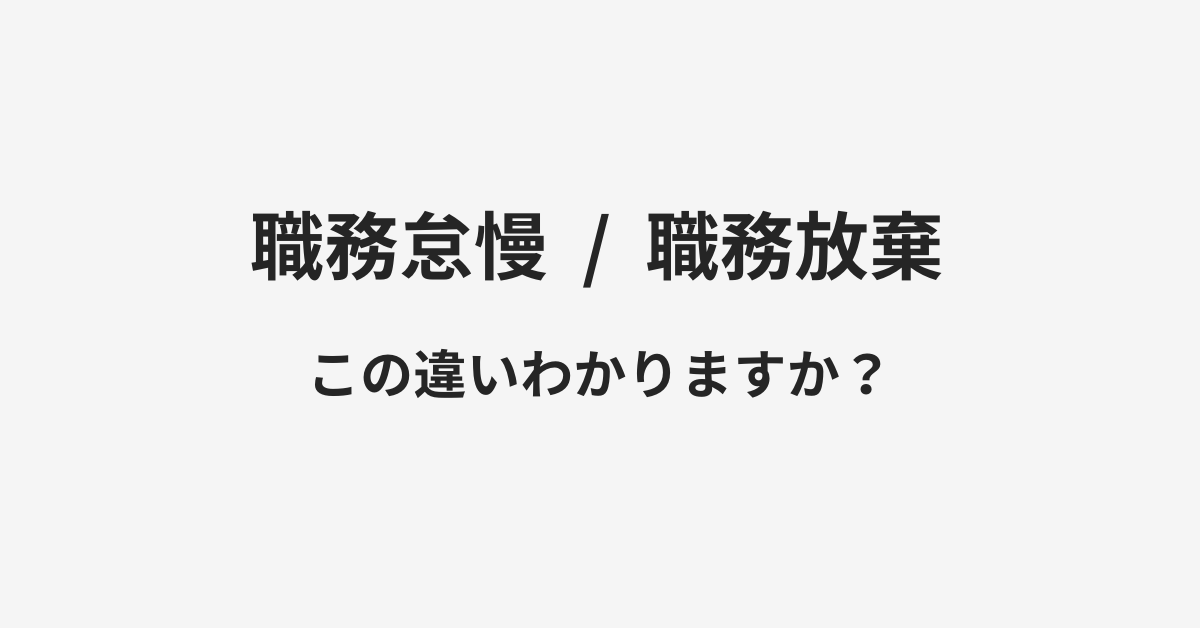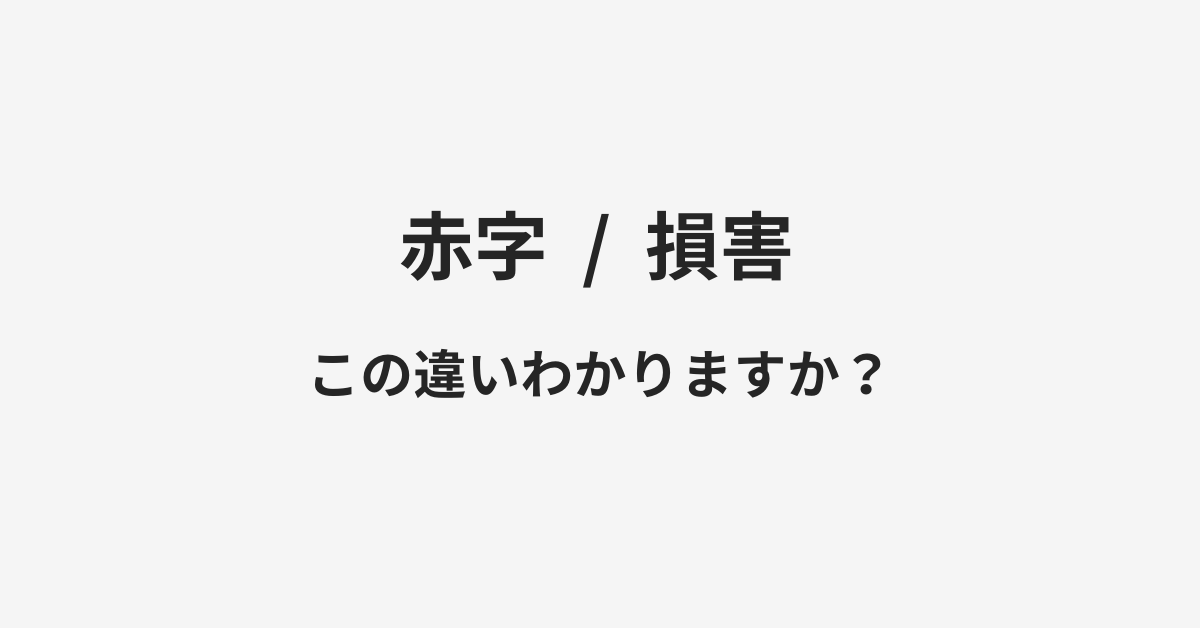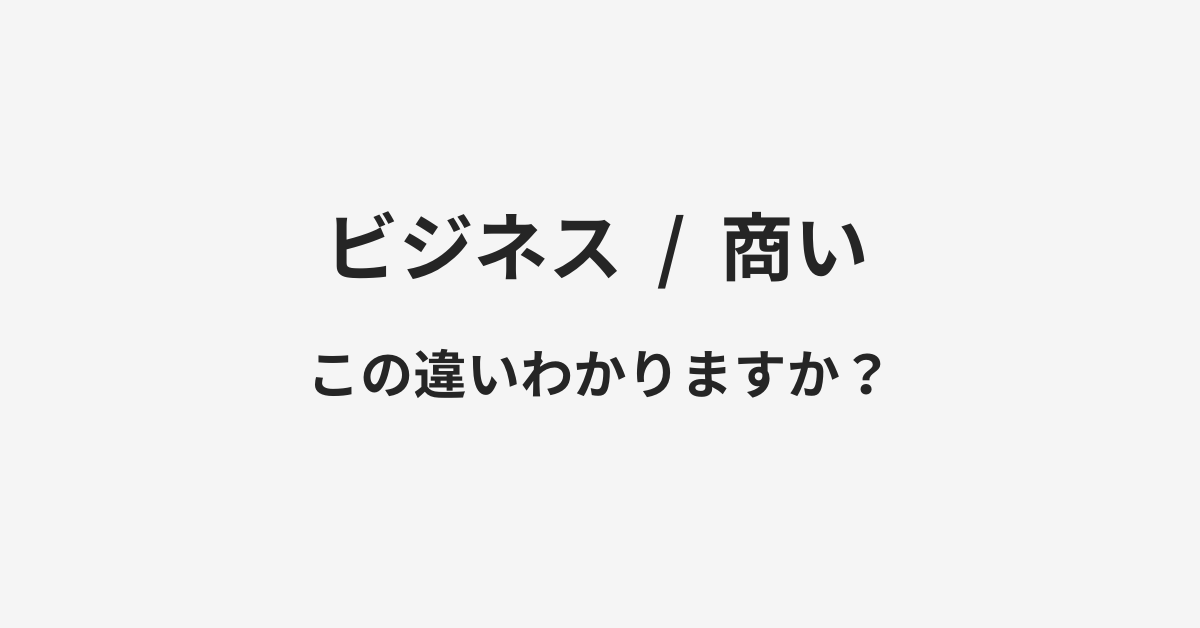【薄利多売】と【厚利多売】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
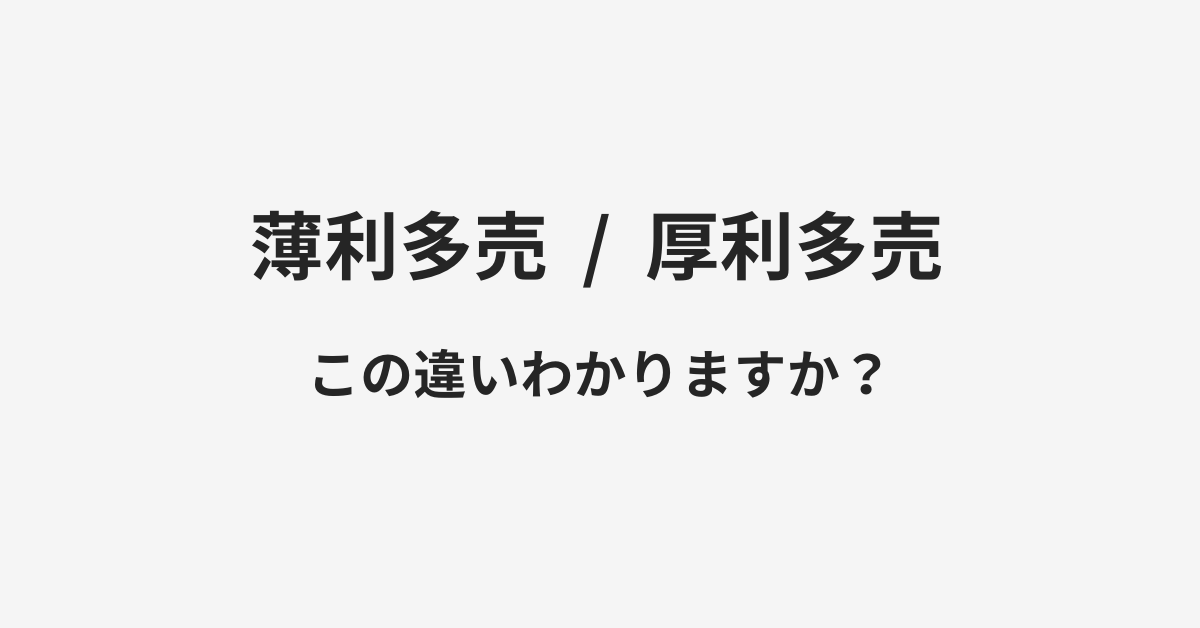
薄利多売と厚利多売の分かりやすい違い
薄利多売と厚利多売は、商品の売り方についての考え方を表す言葉です。
薄利多売は、1つの商品の利益を少なくして、たくさん売ることで全体の利益を増やす方法です。厚利多売は、1つの商品の利益を大きくしながら、それでもたくさん売る理想的な方法です。
実際のビジネスでは薄利多売が一般的ですが、ブランド力や技術力があれば厚利多売も可能になります。
薄利多売とは?
薄利多売とは、個々の商品の利益率を低く設定し、大量に販売することで総利益を確保するビジネスモデルです。
単価を下げて価格競争力を高め、市場シェアの拡大を狙う戦略で、スーパーマーケット、ディスカウントストア、ファストファッションなどで広く採用されています。薄利多売を成功させるには、仕入れコストの削減、オペレーションの効率化、在庫回転率の向上が不可欠です。規模の経済を活かせる大企業に有利な戦略ですが、価格競争の激化により収益性が低下するリスクもあります。
顧客にとっては低価格で商品を購入できるメリットがある一方、企業は常にコスト削減の圧力にさらされます。
薄利多売の例文
- ( 1 ) 当社は薄利多売戦略で、低価格を武器に市場シェアを拡大してきました。
- ( 2 ) 薄利多売モデルでは、わずかなコスト増加も収益に大きく影響します。
- ( 3 ) 競合他社との薄利多売競争が激化し、利益率が年々低下しています。
- ( 4 ) 薄利多売ビジネスを成功させるには、徹底的な業務効率化が不可欠です。
- ( 5 ) 薄利多売から脱却するため、高付加価値商品の開発に着手しました。
- ( 6 ) ECサイトの普及により、薄利多売型ビジネスがさらに加速しています。
薄利多売の会話例
厚利多売とは?
厚利多売とは、高い利益率を維持しながら大量販売も実現する、理想的だが実現困難なビジネスモデルです。
高付加価値商品やブランド力、独自技術により高価格を維持しつつ、優れたマーケティングや独占的地位により販売量も確保します。アップル社のiPhoneやルイ・ヴィトンなどの高級ブランドが代表例で、強力なブランドイメージと品質により実現しています。一般的には厚利少売になりがちですが、革新的な製品や圧倒的なブランド力があれば厚利多売も可能です。
持続的な研究開発投資とブランディングが必要で、参入障壁が高い分、成功すれば高収益を長期間維持できます。
厚利多売の例文
- ( 1 ) ブランド力を活かした厚利多売戦略により、業界トップの収益性を実現しています。
- ( 2 ) 厚利多売を実現するには、他社には真似できない独自の価値提供が必要です。
- ( 3 ) 新製品は厚利多売を目指し、高機能と優れたデザインを両立させました。
- ( 4 ) 厚利多売モデルの構築には時間がかかりますが、長期的には大きな競争優位となります。
- ( 5 ) 一部の高級ブランドは、見事に厚利多売を実現し、高い利益率を維持しています。
- ( 6 ) 厚利多売は理想ですが、現実的には厚利少売か薄利多売のどちらかになりがちです。
厚利多売の会話例
薄利多売と厚利多売の違いまとめ
薄利多売と厚利多売は、利益率と販売量の関係において対照的なビジネスモデルです。
薄利多売は現実的で多くの企業が採用する戦略ですが、厚利多売は限られた成功企業のみが実現できる理想形です。企業は自社の強み、市場環境、競合状況を分析し、適切な戦略を選択する必要があります。
どちらの戦略も一長一短があり、持続的な成功には常に戦略の見直しと改善が求められます。
薄利多売と厚利多売の読み方
- 薄利多売(ひらがな):はくりたさい
- 薄利多売(ローマ字):hakuritasai
- 厚利多売(ひらがな):こうりたさい
- 厚利多売(ローマ字):kouritasai