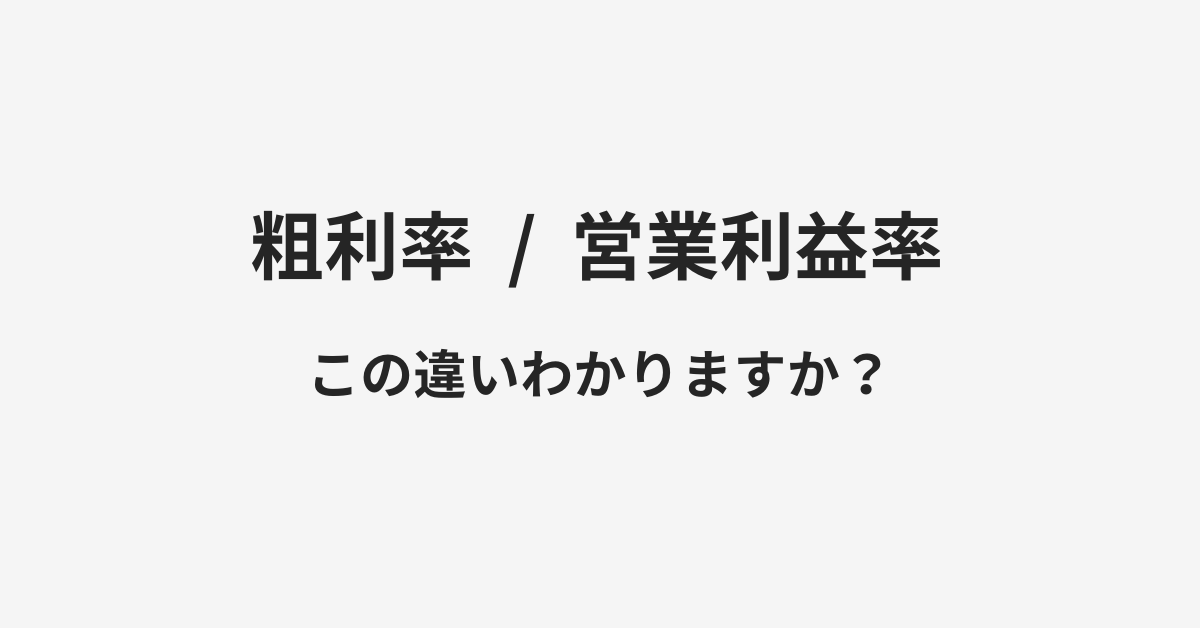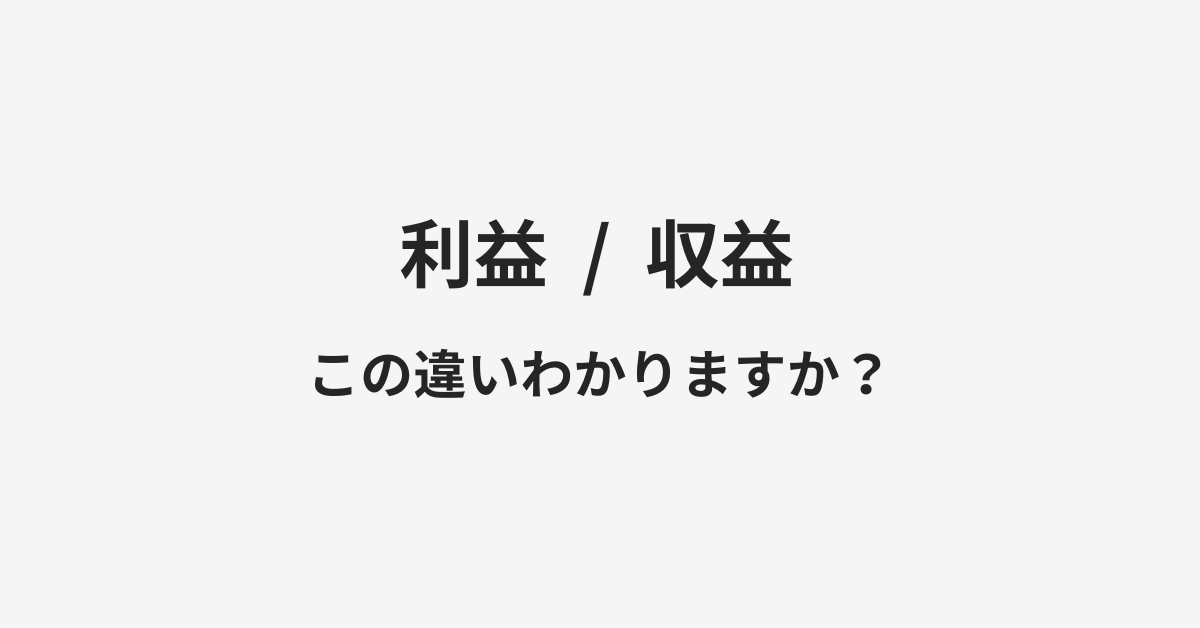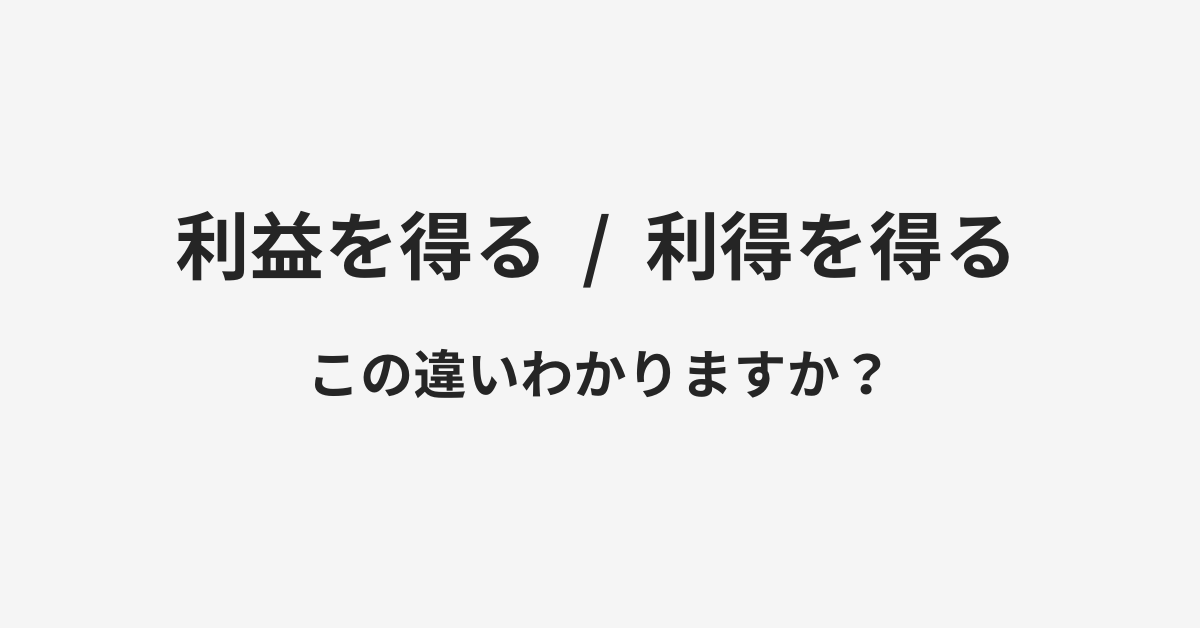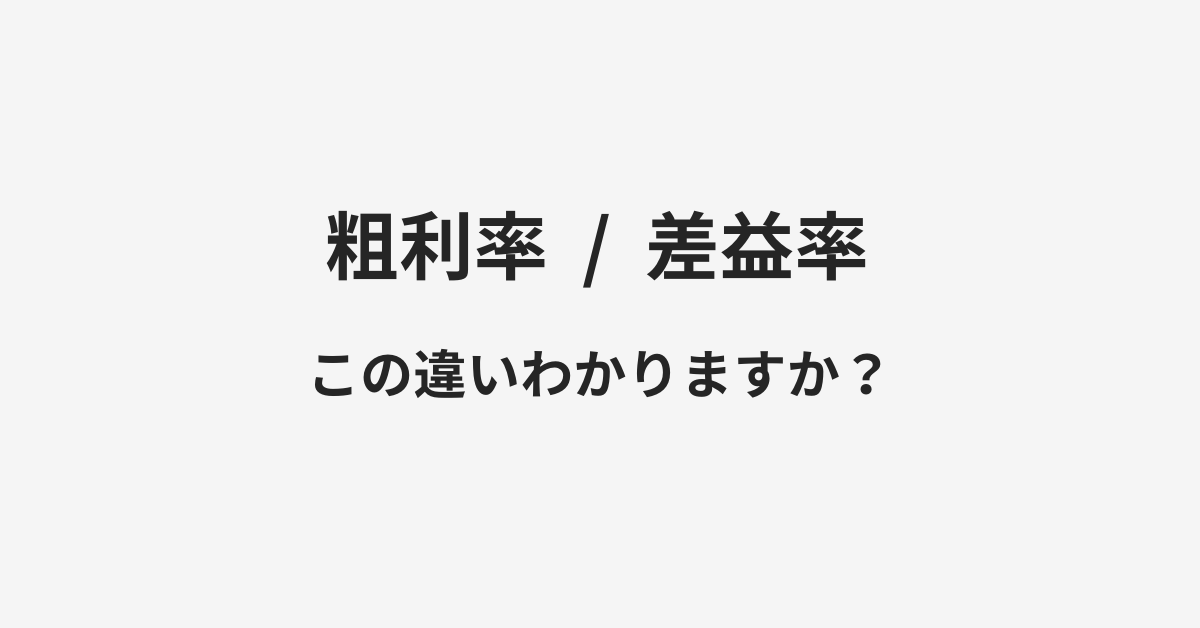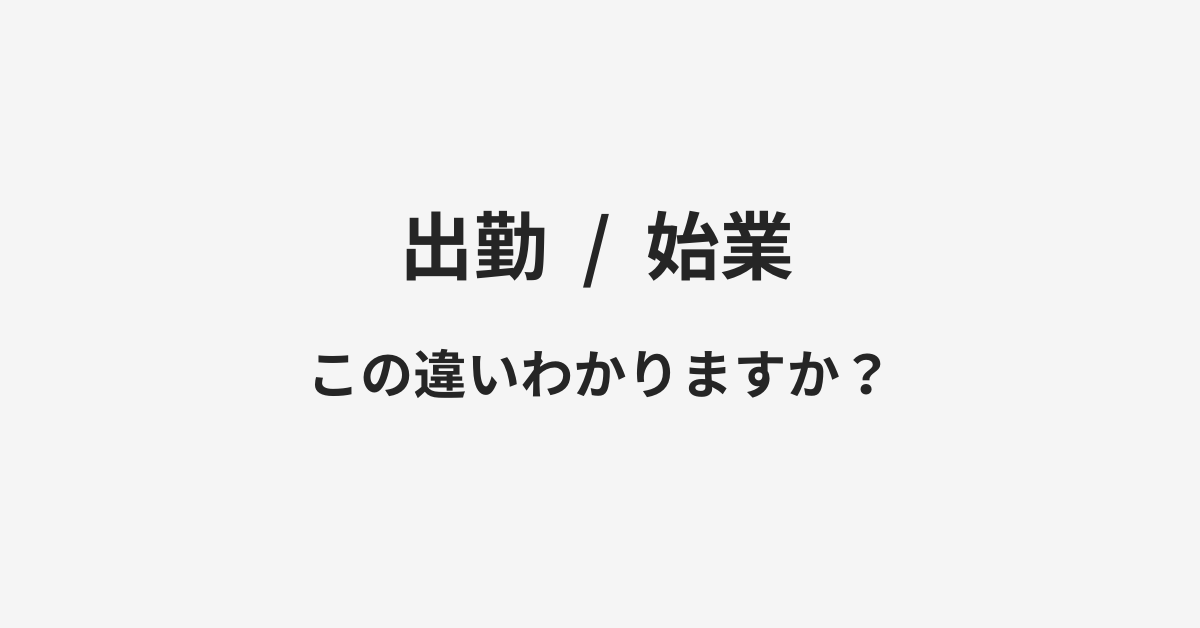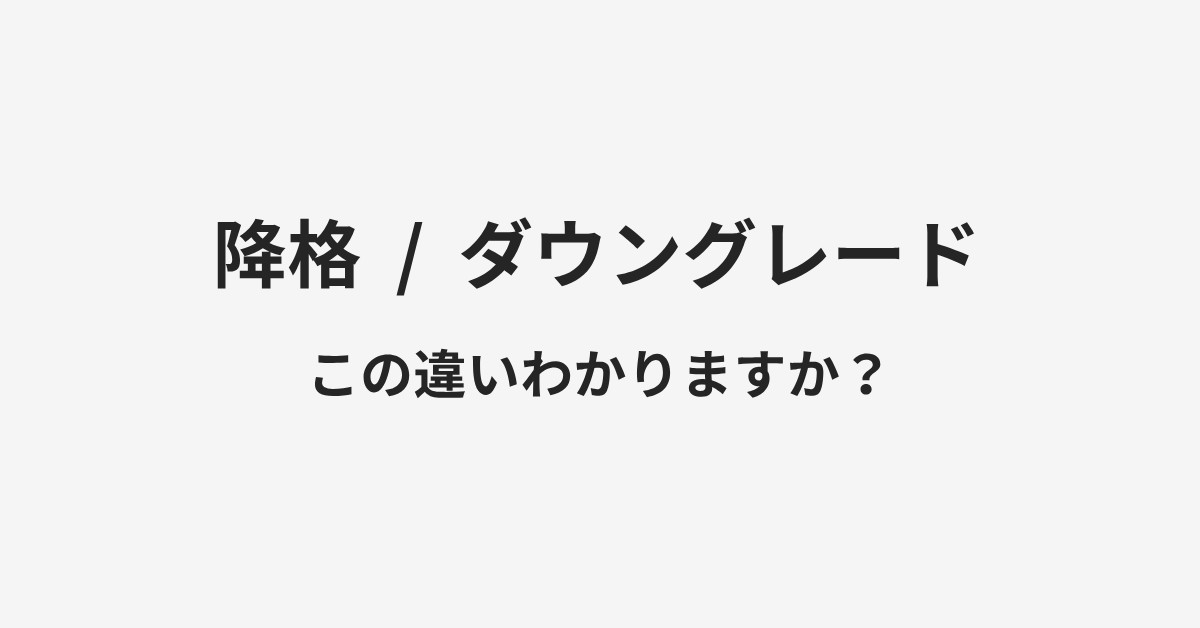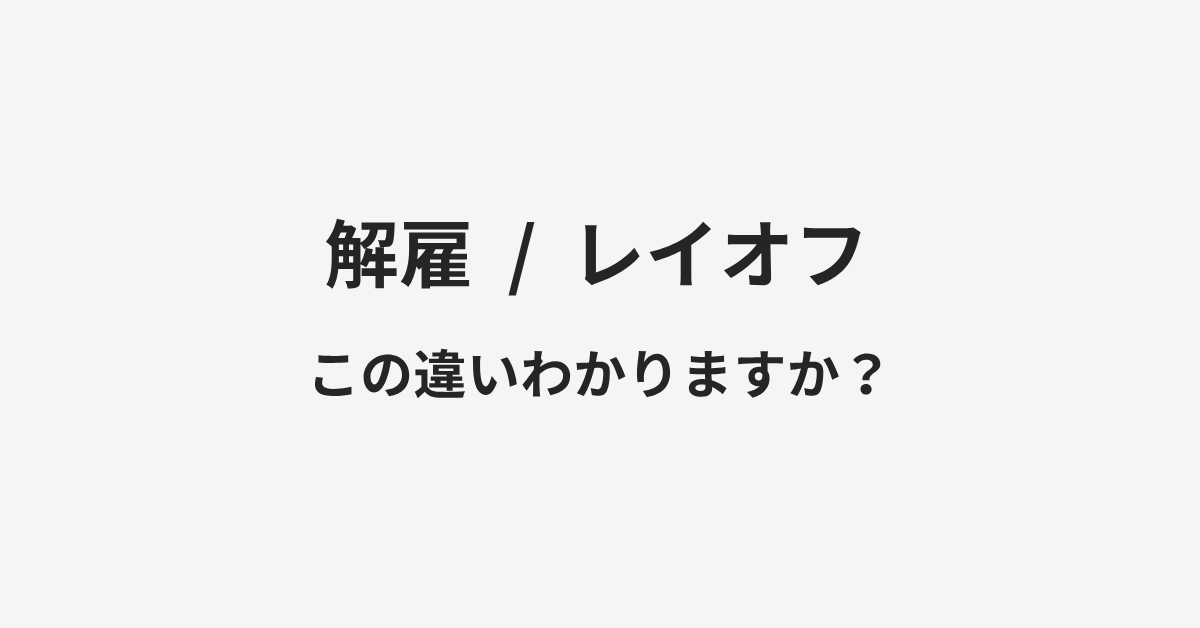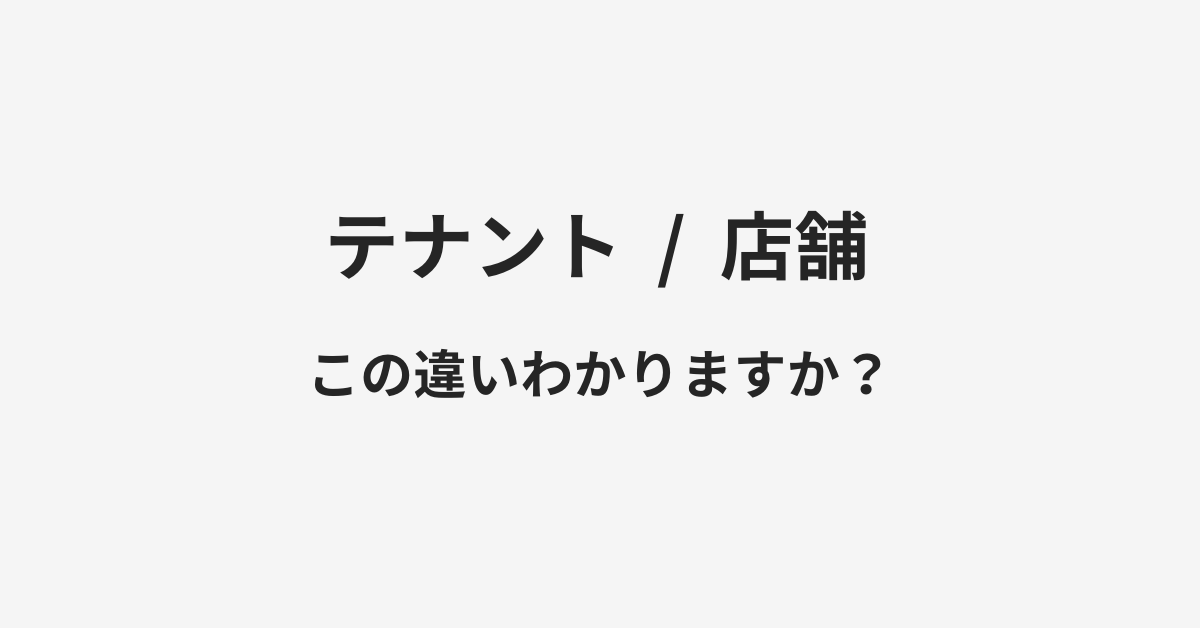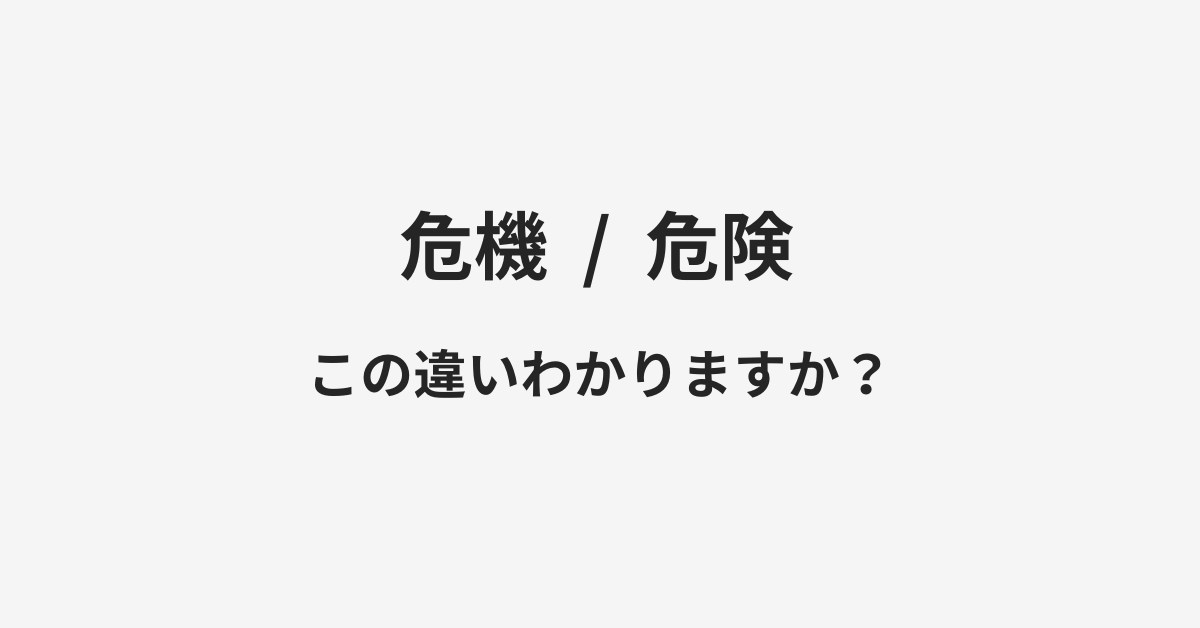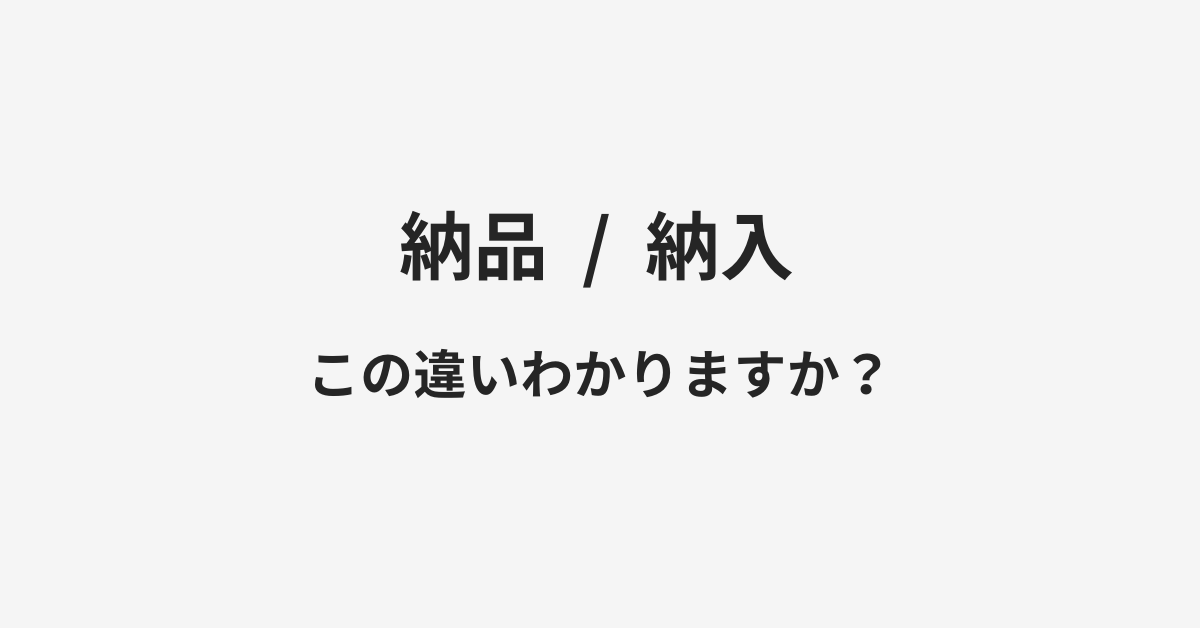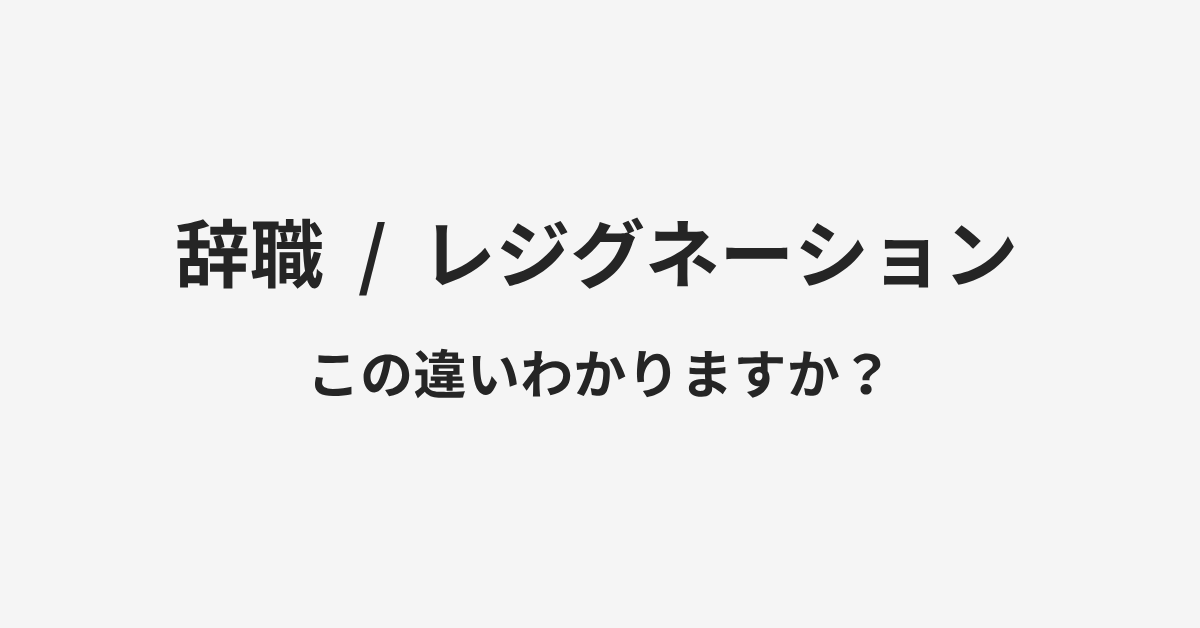【限界利益】と【付加価値】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
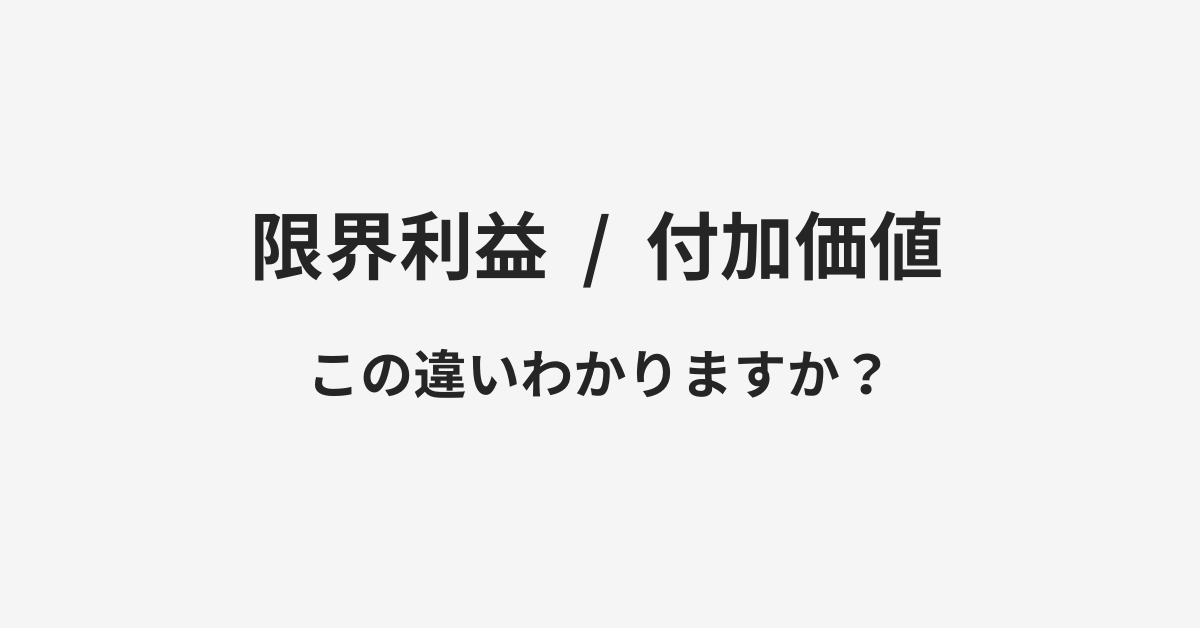
限界利益と付加価値の分かりやすい違い
限界利益と付加価値は、どちらも企業の収益力を示す重要な指標ですが、その計算方法と意味に大きな違いがあります。
限界利益は売上高から変動費を引いた短期的な収益性指標で、付加価値は企業が新たに生み出した価値の総額を示す生産性指標です。前者は損益分岐点分析、後者は生産性分析で使用されます。
経営分析において、この違いを理解することは、適切な経営判断と業績評価に不可欠です。
限界利益とは?
限界利益とは、売上高から変動費を差し引いた利益で、売上が1単位増加したときに増える利益額を示します。変動費には原材料費、外注費、販売手数料などが含まれ、固定費を回収する原資となります。限界利益率(限界利益÷売上高)は、商品やサービスの収益性を判断する重要な指標です。
限界利益は損益分岐点分析の中核概念で、限界利益=固定費となる売上高が損益分岐点です。限界利益が固定費を上回れば黒字、下回れば赤字となります。短期的な意思決定、例えば受注可否の判断、価格設定、商品ミックスの最適化などに活用されます。
管理会計では、部門別・商品別の限界利益を算出し、収益性の高い分野への経営資源配分を行います。限界利益率の改善は、変動費削減、付加価値向上、価格戦略の見直しにより実現できます。
限界利益の例文
- ( 1 ) 新商品の限界利益率は40%で、既存商品より10ポイント高い水準です。
- ( 2 ) 限界利益が月間500万円必要なため、売上目標を1,250万円に設定しました。
- ( 3 ) 価格競争により限界利益率が低下し、収益性が悪化しています。
- ( 4 ) 限界利益分析により、不採算商品の整理を進めています。
- ( 5 ) 受注判断の基準として、限界利益率25%以上を設定しています。
- ( 6 ) 部門別限界利益を算出し、事業ポートフォリオを最適化しました。
限界利益の会話例
付加価値とは?
付加価値とは、企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値の総額で、売上高から外部購入価値(原材料費、外注費など)を差し引いて算出されます。人件費、減価償却費、営業利益、金利、税金などの合計とも言えます。企業が社会に提供した真の貢献度を示す指標です。
付加価値は生産性分析の基本指標で、労働生産性=付加価値÷従業員数付加価値率=付加価値÷売上高などの形で活用されます。高付加価値化は、製品の差別化、サービスの質向上、ブランド構築などにより実現され、企業競争力の源泉となります。
経営戦略では、付加価値の最大化が重要な目標となります。単なるコスト削減ではなく、イノベーションによる価値創造、バリューチェーンの最適化、知的資産の活用などが付加価値向上の鍵となります。
付加価値の例文
- ( 1 ) 高付加価値製品の開発により、付加価値率を30%まで高めました。
- ( 2 ) 付加価値額を従業員数で割った労働生産性は、業界平均を上回っています。
- ( 3 ) OEM生産から自社ブランドへの転換で、付加価値の向上を図っています。
- ( 4 ) 付加価値分析により、外注化すべき工程を特定しました。
- ( 5 ) 知的財産の活用により、付加価値創造力を強化しています。
- ( 6 ) 付加価値ベースでの業績評価制度を導入し、生産性向上を促進しています。
付加価値の会話例
限界利益と付加価値の違いまとめ
限界利益と付加価値の主な違いは、控除する費用項目にあります。限界利益は変動費のみを控除し、付加価値は外部購入費用全般を控除します。そのため、付加価値には人件費が含まれますが、限界利益には含まれません。
使用目的も異なり、限界利益は短期的な収益性判断や損益分岐点分析に使用され、付加価値は企業の生産性評価や社会的貢献度の測定に使用されます。
経営実務では、限界利益で商品の収益性を評価し、付加価値で企業全体の生産性を評価するという使い分けが一般的です。両指標を組み合わせることで、多角的な経営分析が可能となります。
限界利益と付加価値の読み方
- 限界利益(ひらがな):げんかいりえき
- 限界利益(ローマ字):gennkairieki
- 付加価値(ひらがな):ふかかち
- 付加価値(ローマ字):fukakachi