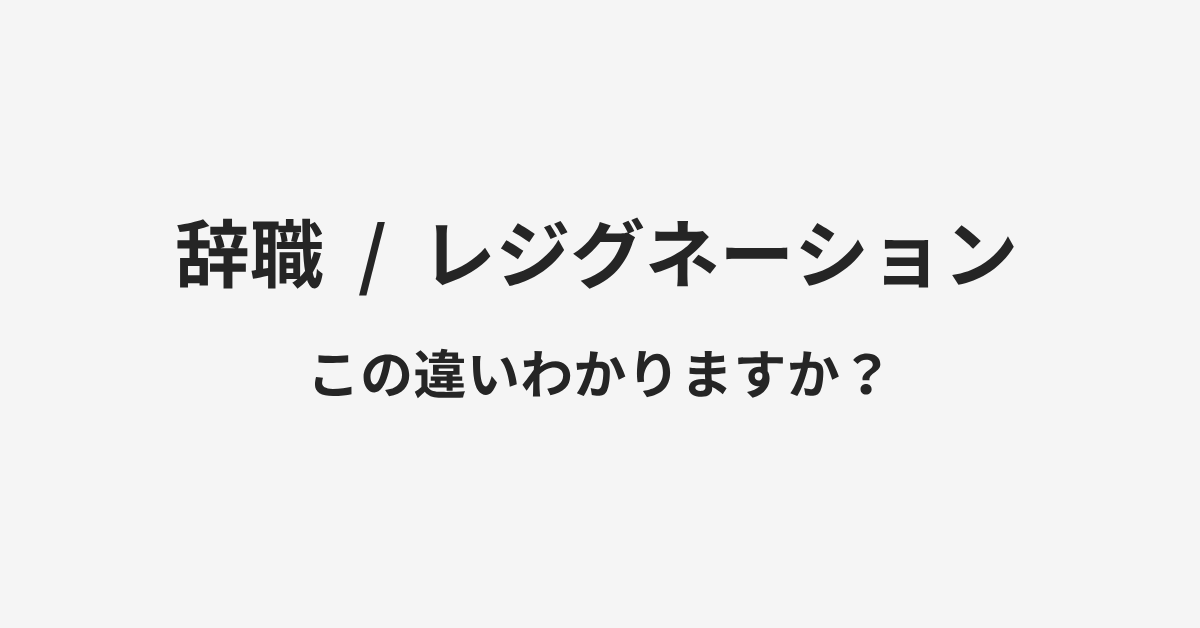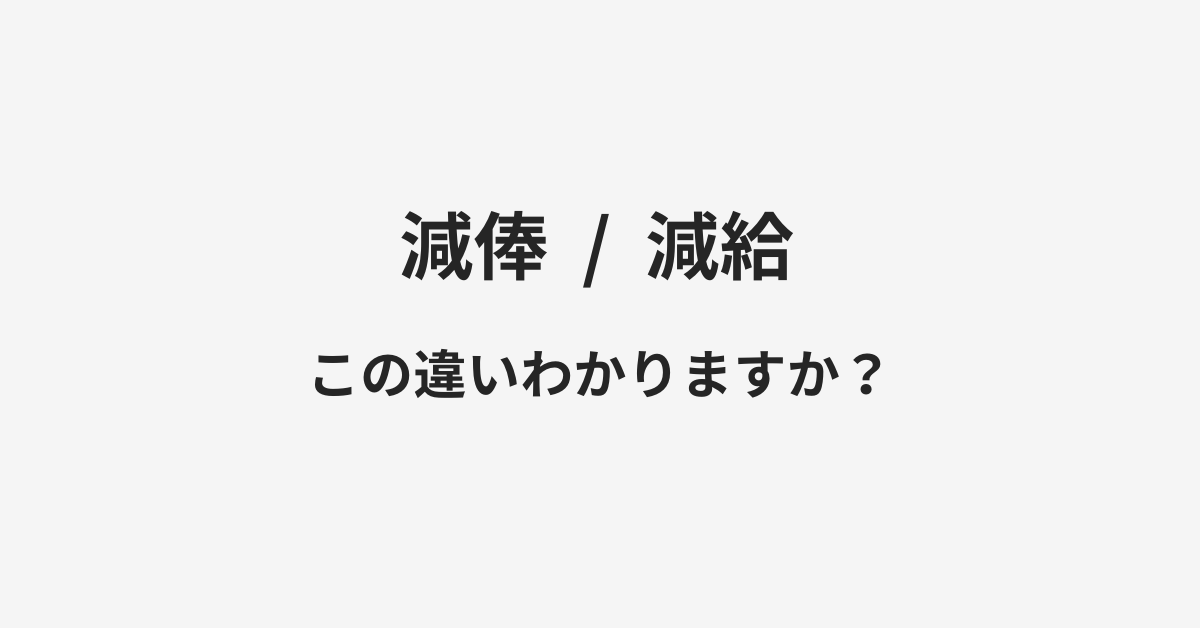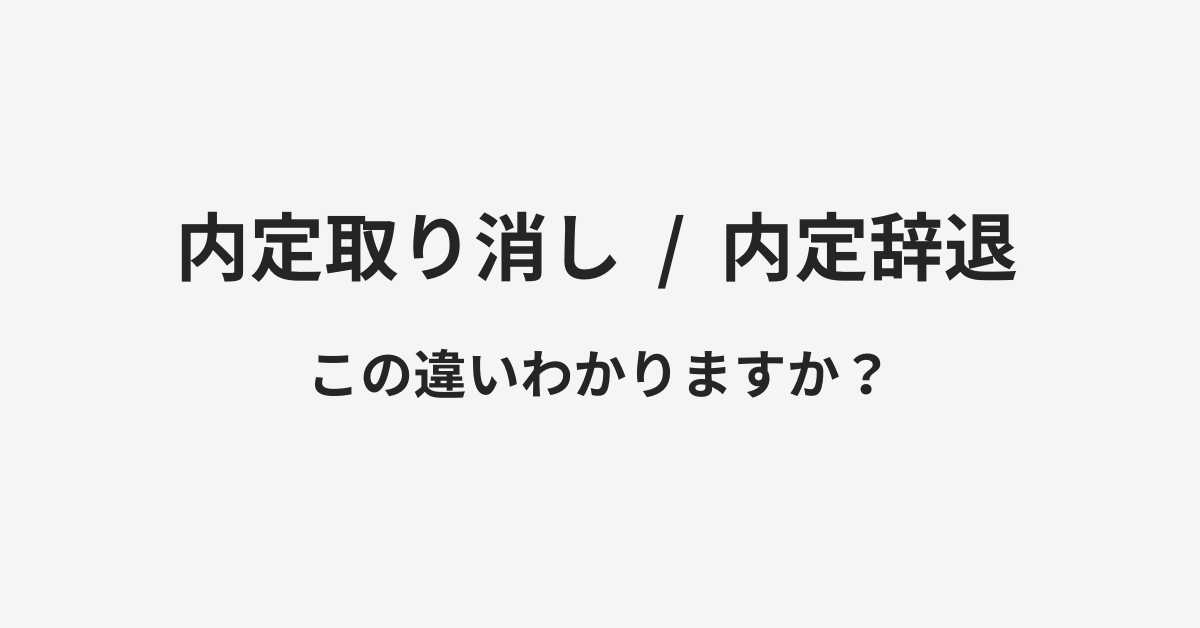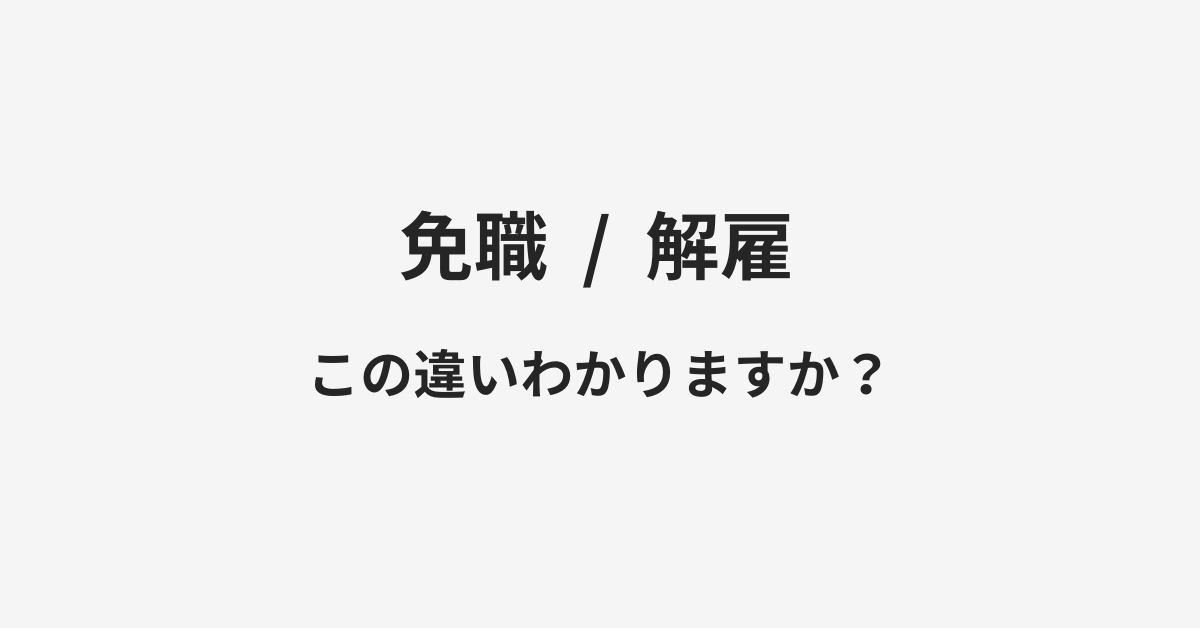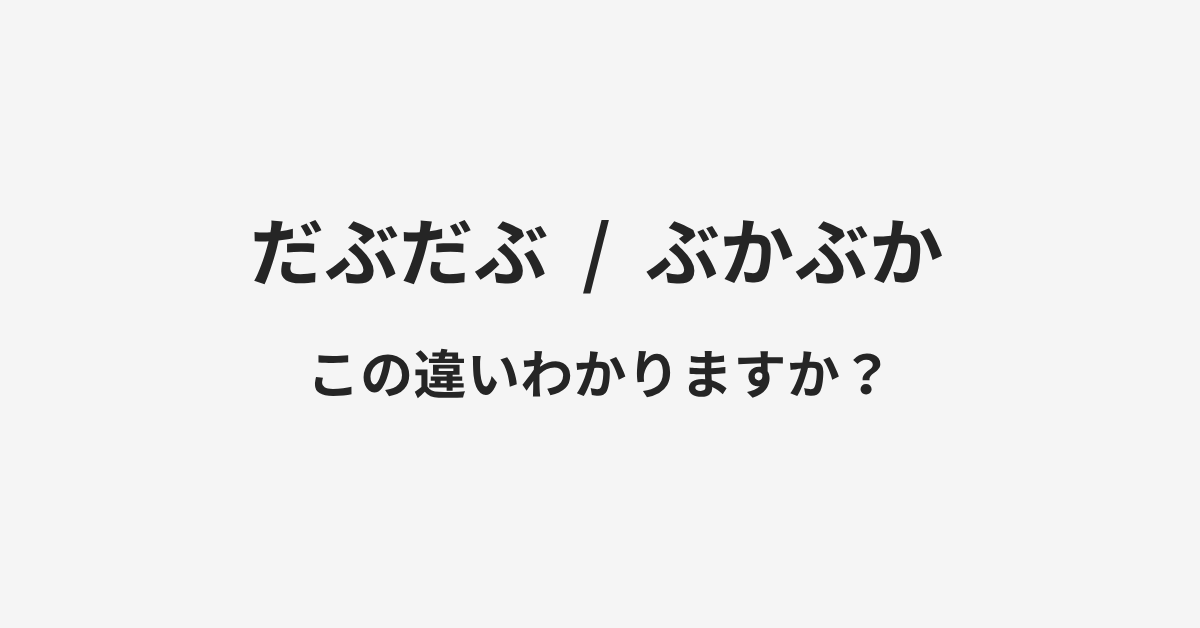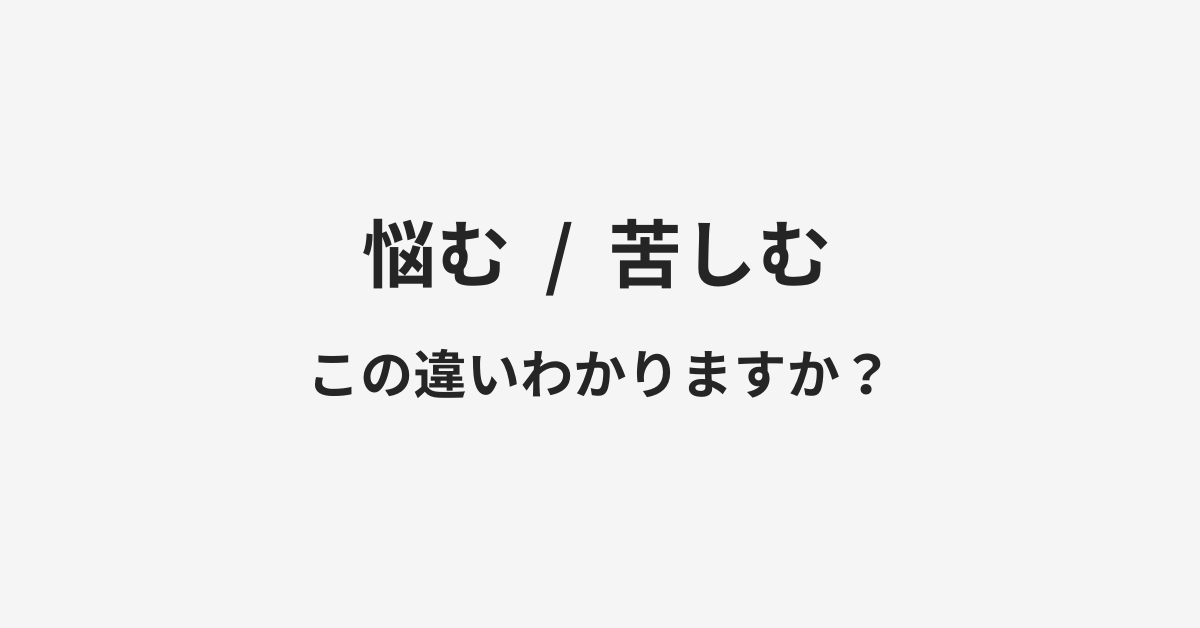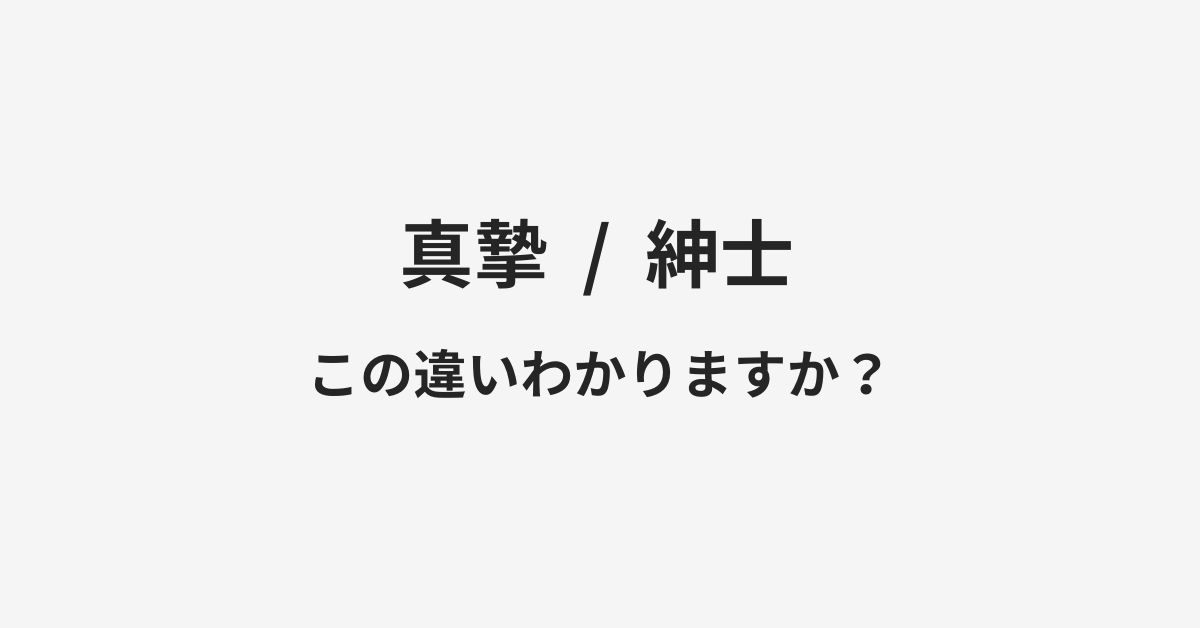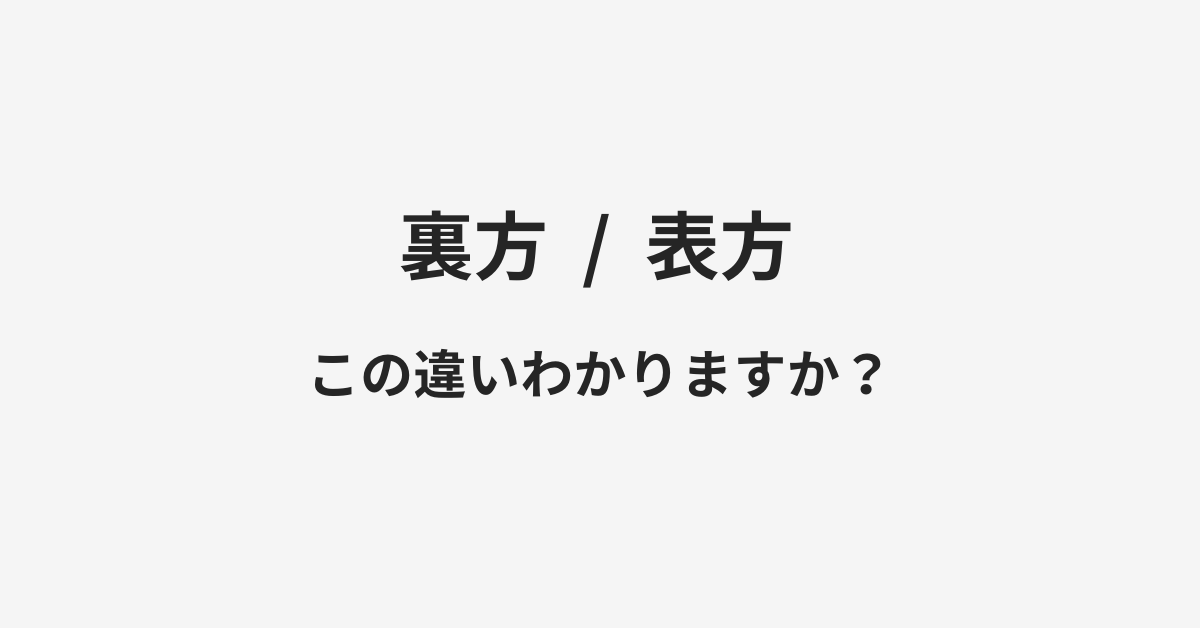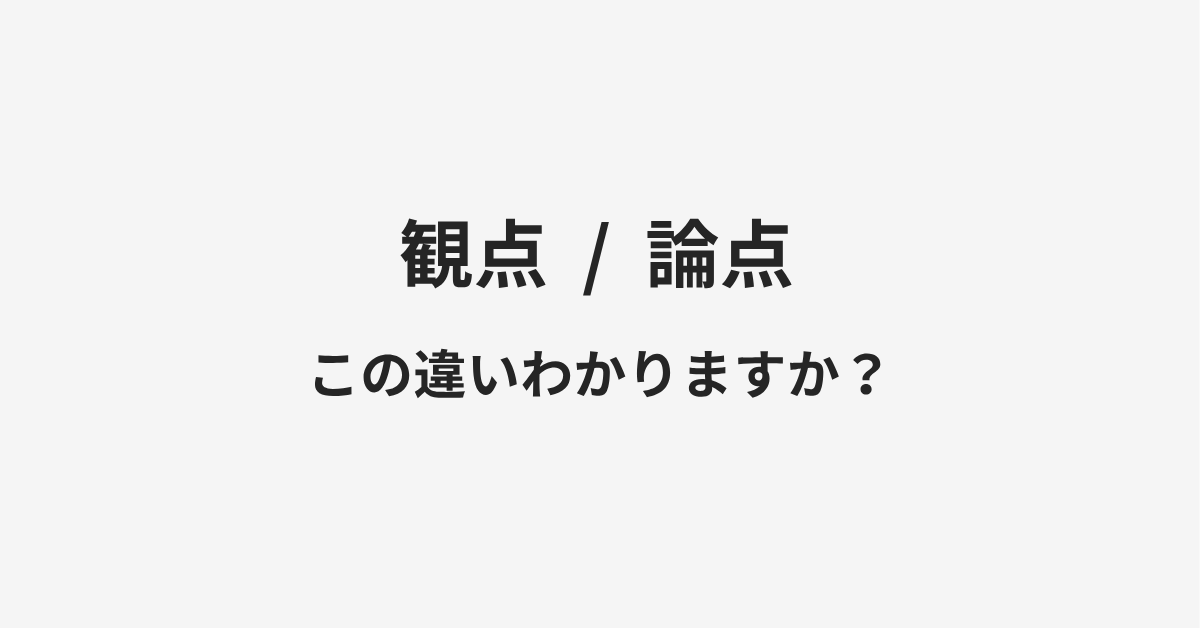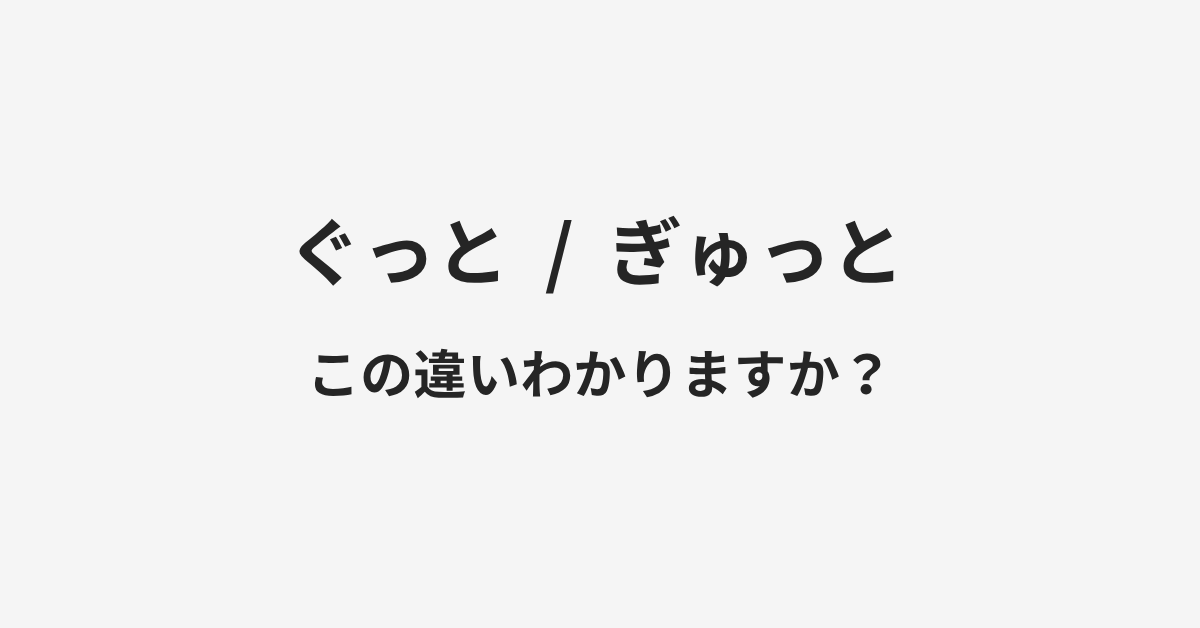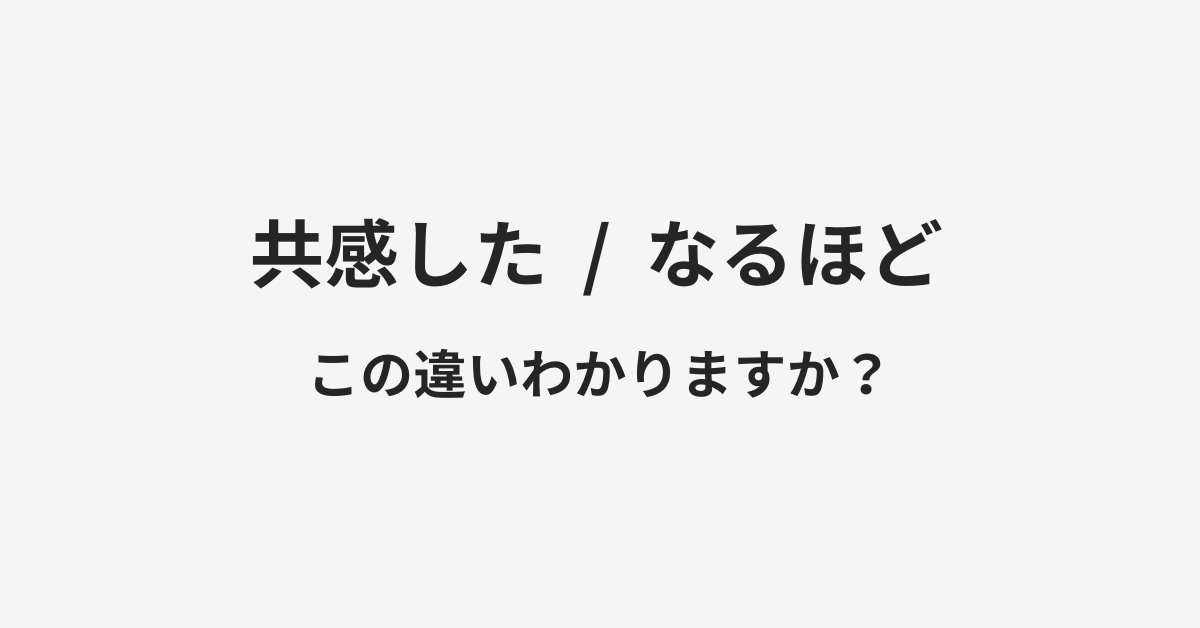【リストラ】と【解雇】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
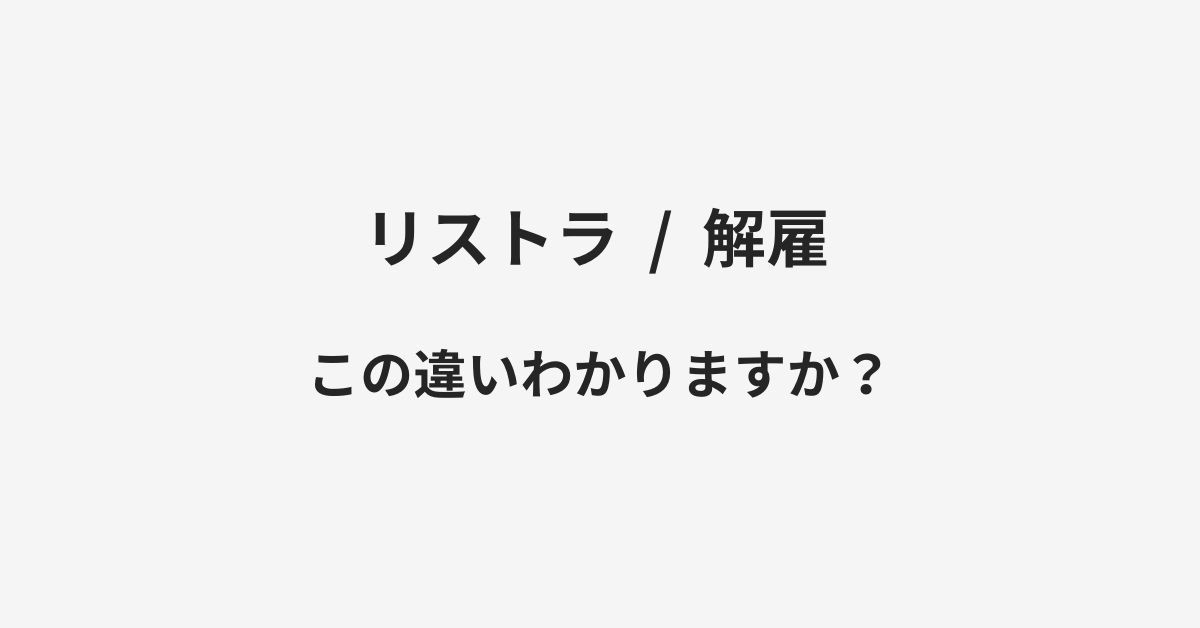
リストラと解雇の分かりやすい違い
リストラはリストラクチャリング(事業の再構築)の略で、本来は会社の組織や事業を見直して立て直すことを意味します。ただし日本では、主に人員削減や人員整理の意味で使われることが多いです。
解雇は、会社が従業員との雇用契約を一方的に終了させることです。業績不振による整理解雇、重大な違反による懲戒解雇、能力不足による普通解雇などがあります。
リストラは経営改革の一環として行われ、解雇はその手段の一つという関係にあります。
リストラとは?
リストラとは、リストラクチャリング(Restructuring)の略語で、本来は企業の事業構造を見直し、再構築することを意味します。不採算部門の整理、新規事業への転換、組織の効率化など、企業を立て直すための幅広い改革を指します。
日本では1990年代のバブル崩壊後から頻繁に使われるようになり、主に人員削減や人員整理の意味で使われることが多くなりました。しかし、本来は人員削減だけでなく、事業の統廃合、業務の効率化、新技術の導入なども含む包括的な概念です。
企業が生き残りをかけて行う経営改革の一環であり、従業員の配置転換、早期退職の募集、場合によっては解雇も含まれます。経営環境の変化に対応するための戦略的な取り組みといえます。
リストラの例文
- ( 1 ) 会社が大規模なリストラを発表し、社員に動揺が広がっています。
- ( 2 ) 不採算部門のリストラにより、収益性が改善しました。
- ( 3 ) リストラの一環として、早期退職者を募集することになりました。
- ( 4 ) 経営陣はリストラ策として、3つの工場を閉鎖する決定をしました。
- ( 5 ) リストラで配置転換になり、別の部署で働くことになりました。
- ( 6 ) バブル崩壊後、多くの企業がリストラを余儀なくされました。
リストラの会話例
解雇とは?
解雇とは、使用者(会社)が労働者(従業員)との雇用契約を一方的に終了させることを意味します。労働者の意思に関係なく、会社側の判断で雇用関係を打ち切る行為です。解雇には主に3つの種類があります。
普通解雇は能力不足や勤務態度不良などを理由とするもの、懲戒解雇は重大な規則違反や犯罪行為などを理由とするもの、整理解雇は会社の経営上の理由による人員削減です。日本では労働者の保護が手厚く、解雇には正当な理由が必要で、解雇権の濫用は認められません。
解雇予告や解雇予告手当の支払いなど、法的な手続きも定められています。不当解雇の場合は、労働審判や裁判で争うこともできます。
解雇の例文
- ( 1 ) 勤務態度が改善されないため、やむを得ず解雇することになりました。
- ( 2 ) 会社の業績悪化により、100名の整理解雇が行われました。
- ( 3 ) 重大な就業規則違反により、懲戒解雇処分となりました。
- ( 4 ) 解雇通知を受け取ってから30日後に退職することになります。
- ( 5 ) 不当解雇だと思われる場合は、労働基準監督署に相談できます。
- ( 6 ) 試用期間中でも、正当な理由なく解雇することはできません。
解雇の会話例
リストラと解雇の違いまとめ
リストラは企業の事業再構築を指す広い概念で、組織改革、事業の統廃合、業務効率化などを含みます。日本では人員削減の意味で使われることが多いですが、本来はより包括的な経営改革です。
解雇は雇用契約を会社側から終了させる具体的な行為で、整理解雇、懲戒解雇、普通解雇などの種類があります。法的な手続きや要件が明確に定められています。
つまり、リストラは経営戦略の一環としての改革全般を指し、解雇はその中で行われることがある具体的な雇用終了行為という関係にあります。
リストラと解雇の読み方
- リストラ(ひらがな):りすとら
- リストラ(ローマ字):risutora
- 解雇(ひらがな):かいこ
- 解雇(ローマ字):kaiko