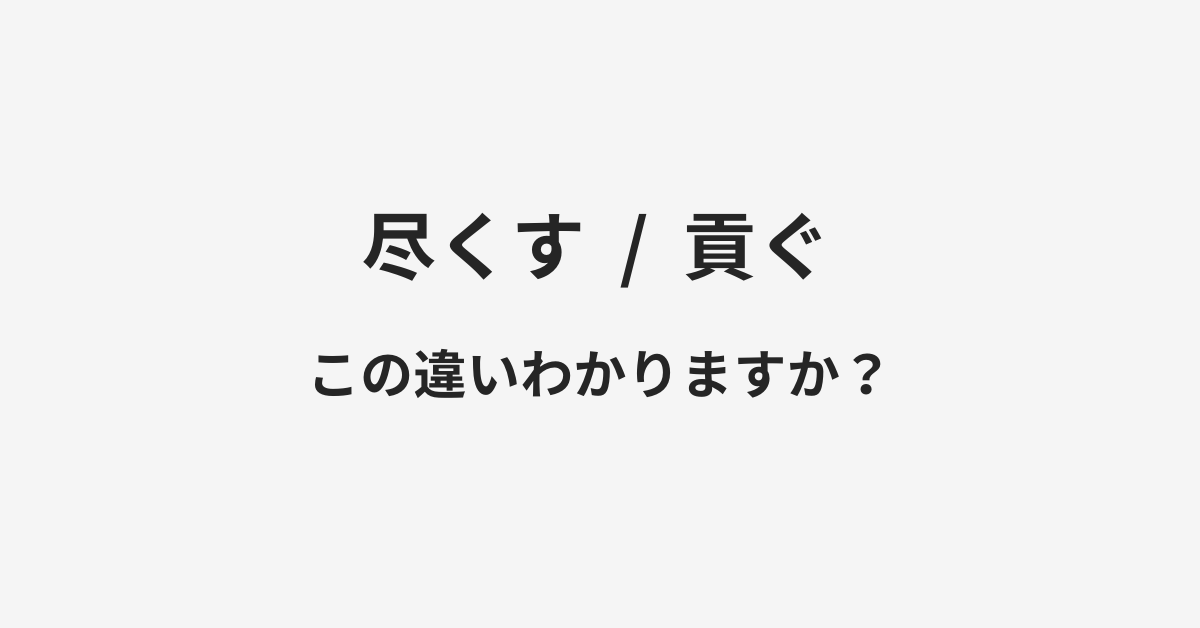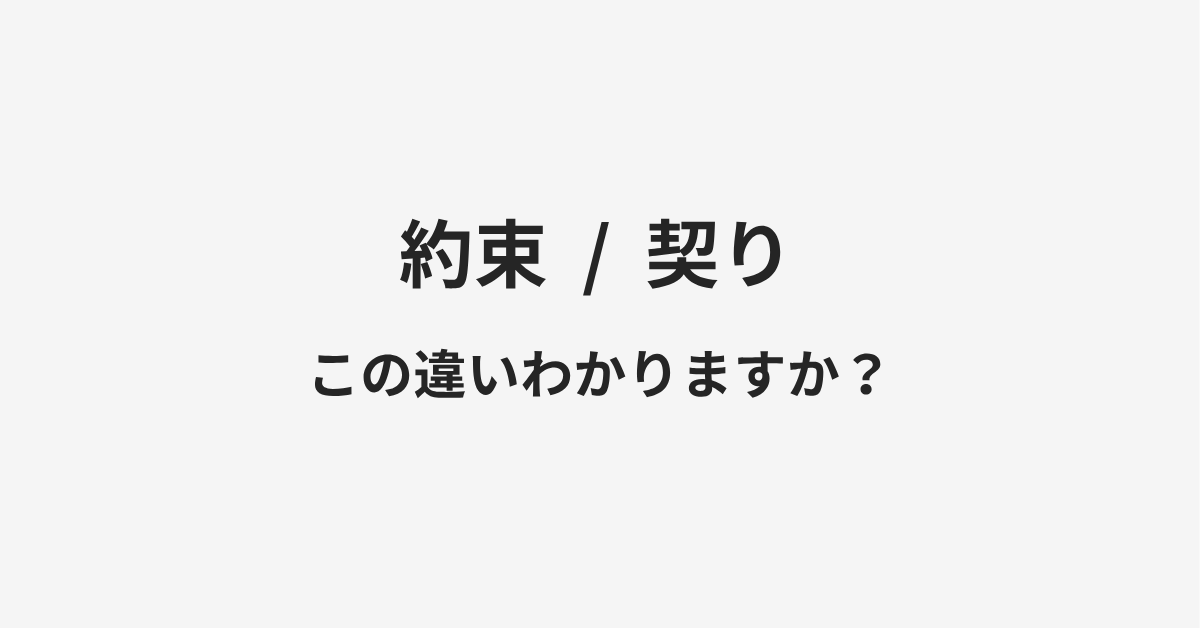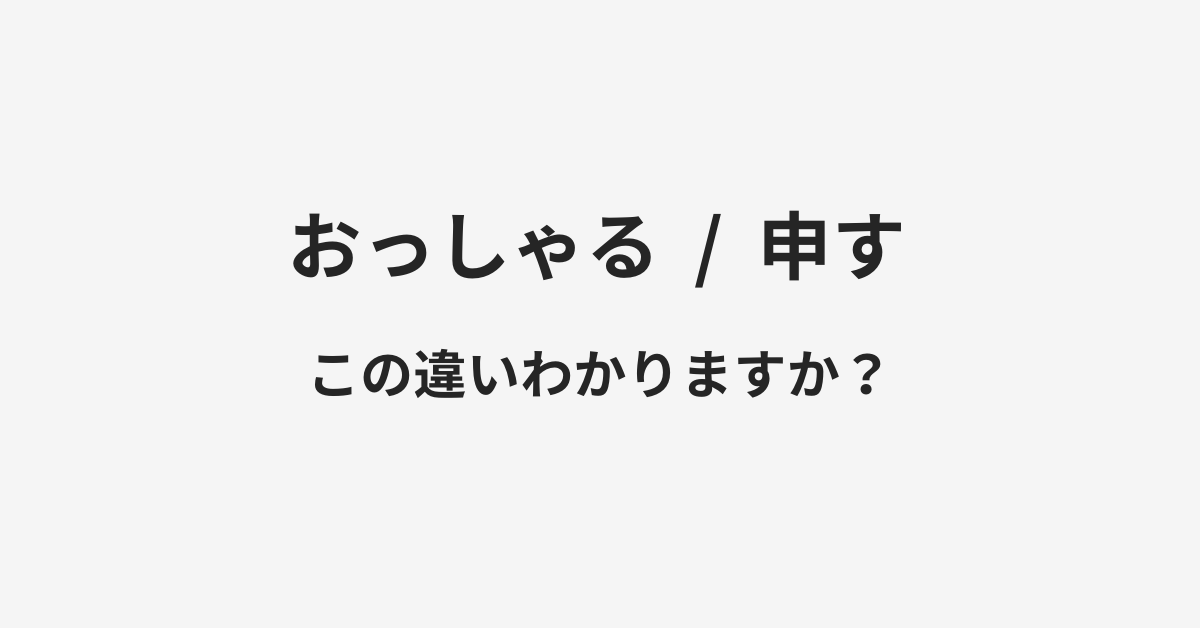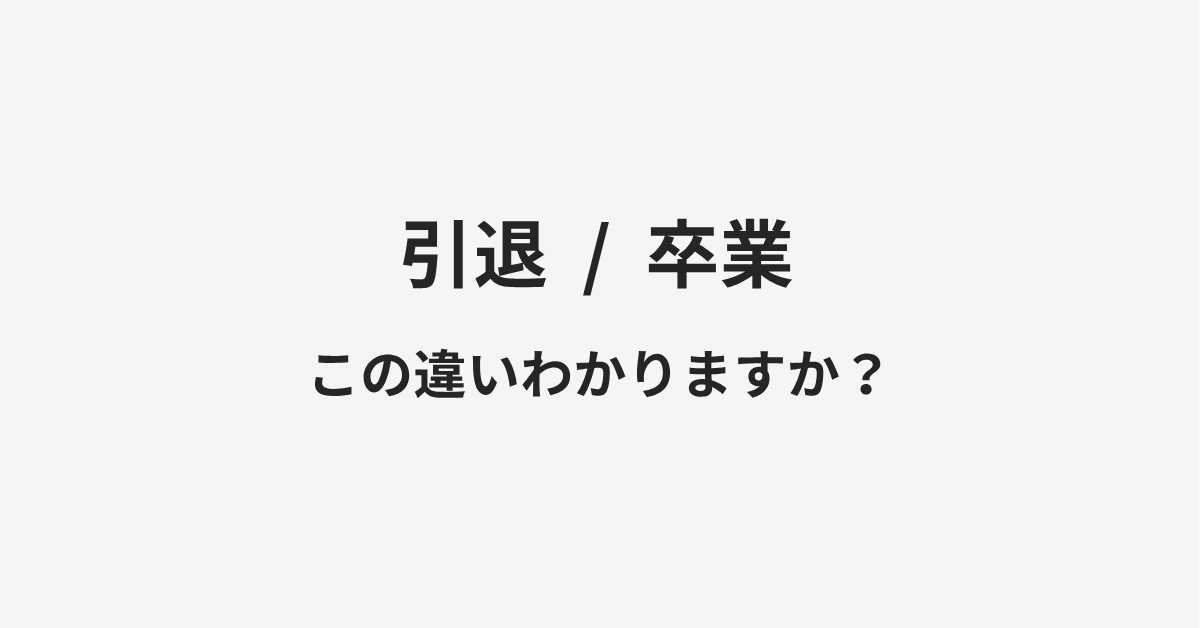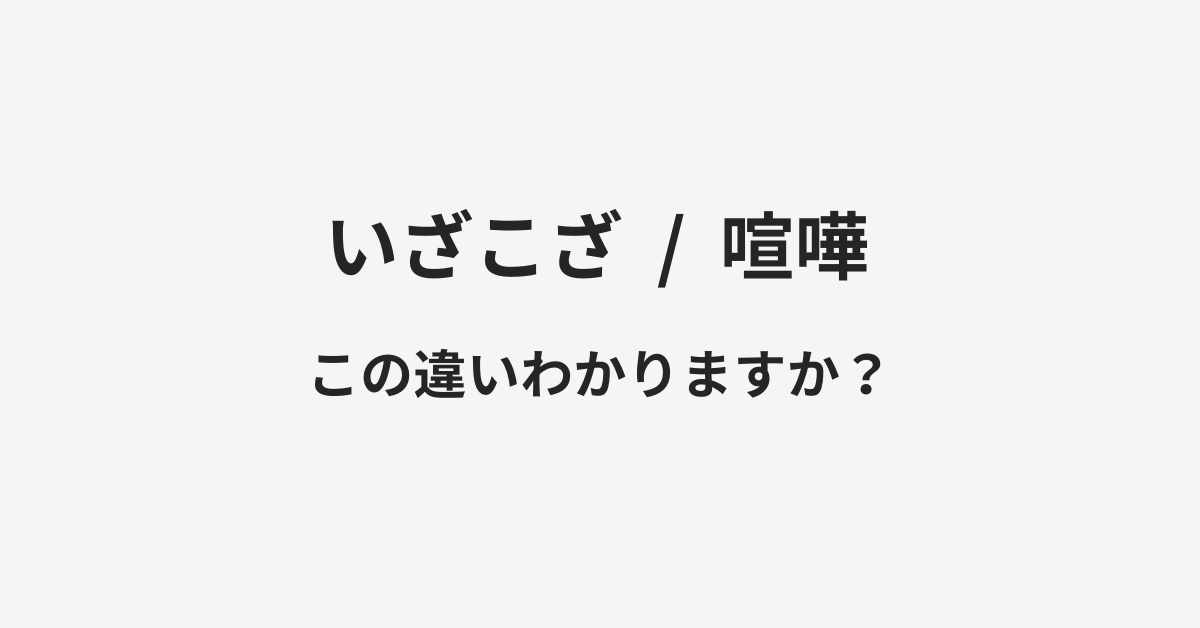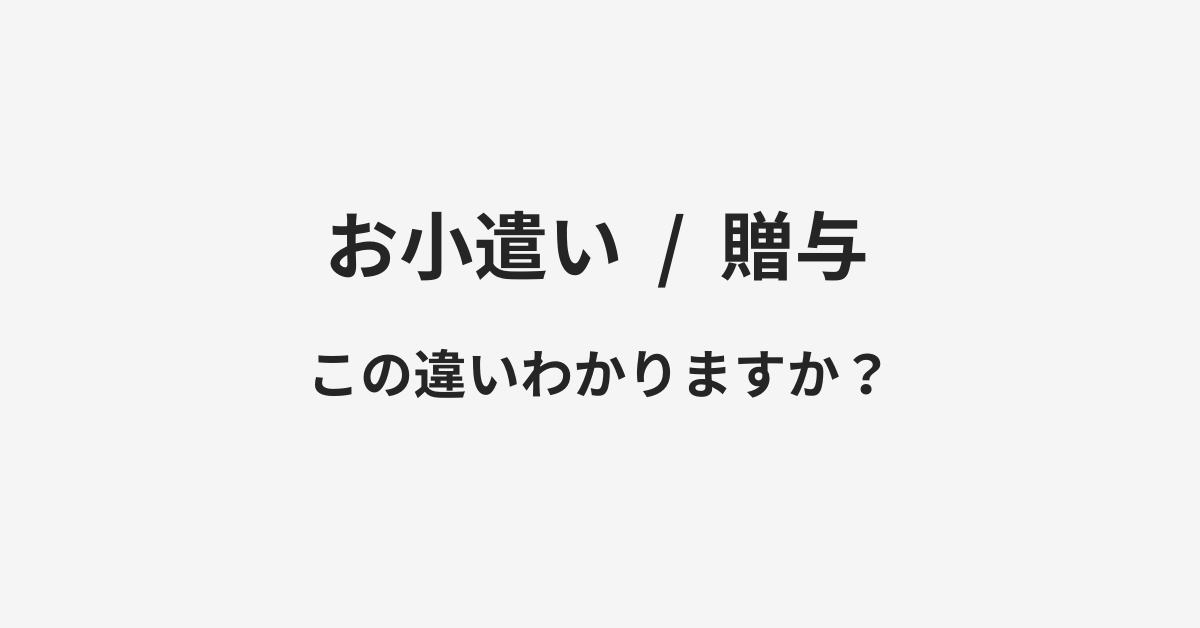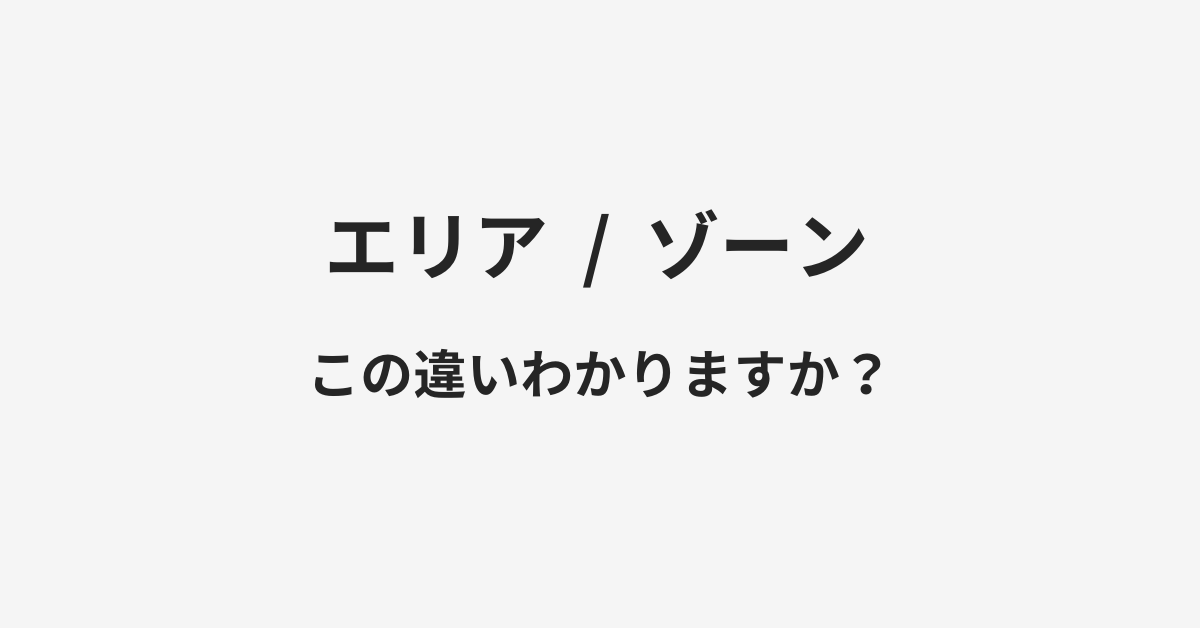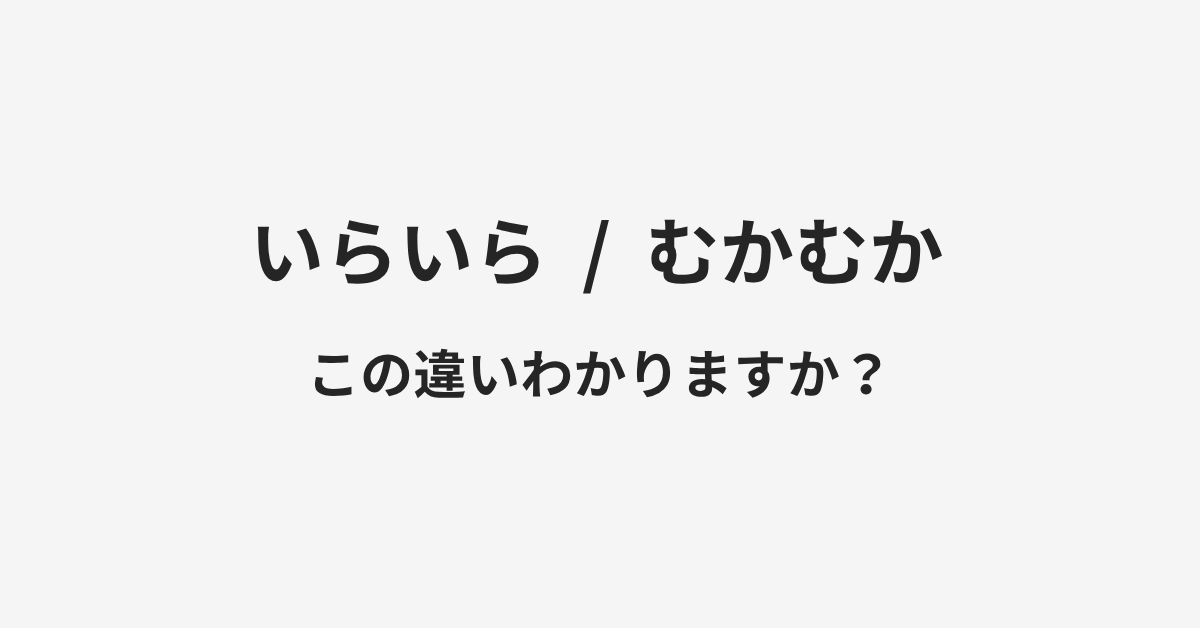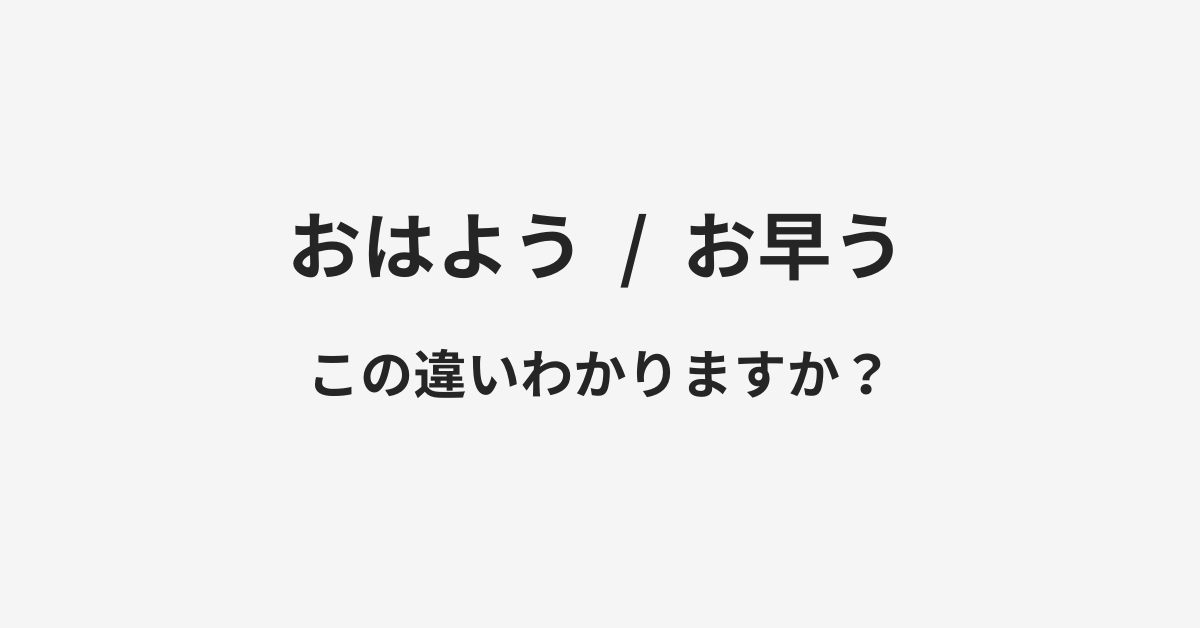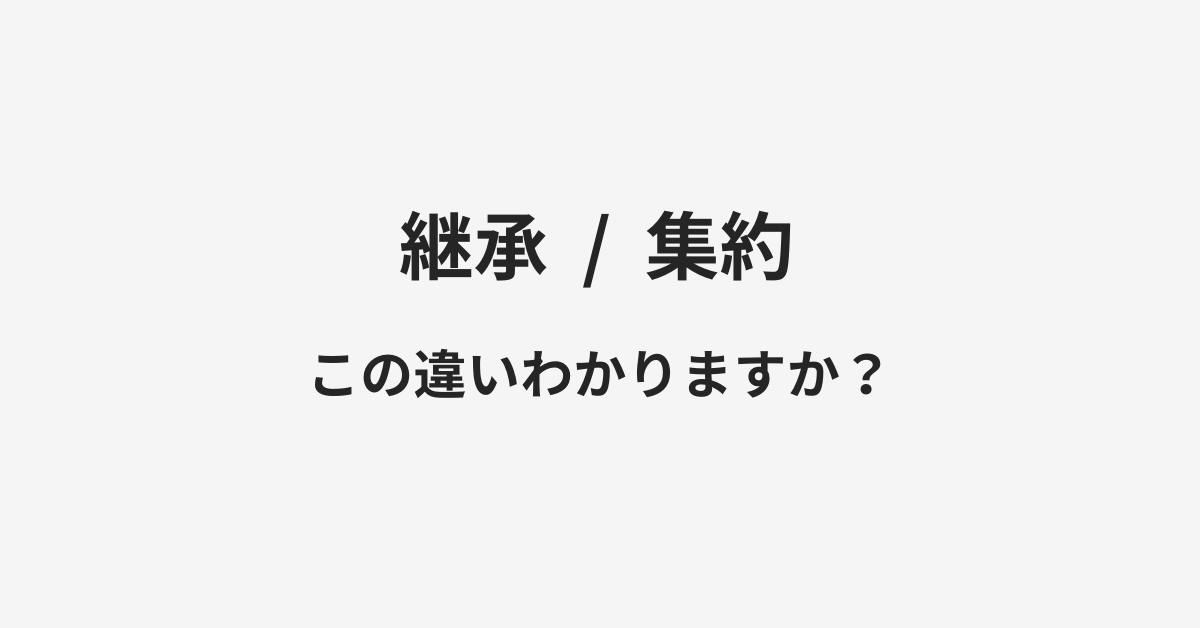【お供】と【お伴】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

お供とお伴の分かりやすい違い
お供とお伴は、どちらもついて行く意味がありますが、用途が違います。お供は神仏への供物という意味と、人に付き従う意味の両方があります。
お伴は人に付き従うことだけを意味し、特に目上の人への同行を表す丁寧な言葉です。
お供は供物・同行の両方、お伴は同行のみという違いがあります。
お供とは?
お供とは、主に二つの意味を持つ言葉です。一つは神仏や先祖に捧げる供物のことで、お供え物とも言います。仏壇にお供えする果物、お墓参りの花、神社への奉納品などが該当します。もう一つは、人に付き従って行くことで、お供するという形で使います。
供物としてのお供は、日本の宗教的・文化的習慣の重要な要素です。お盆やお彼岸、法事などでは欠かせません。一方、同行の意味でのお供は、やや古風な表現で、現代ではご一緒する、同行するという表現の方が一般的です。
お供は供えるという動詞から派生した言葉で、捧げる、差し出すという謙譲の意味が含まれています。そのため、自分の行為をへりくだって表現する際に適しています。
お供の例文
- ( 1 ) 仏壇にお供として、故人の好物を置きました。
- ( 2 ) お墓参りのお供に、新鮮な花を持参しました。
- ( 3 ) 神社への初詣で、お供としてお酒を奉納しました。
- ( 4 ) 買い物にお供しましょうか。
- ( 5 ) 子供を公園にお供させていただきます。
- ( 6 ) 先祖へのお供は、毎日欠かさず行っています。
お供の会話例
お伴とは?
お伴とは、目上の人や大切な人に付き従って一緒に行くことを意味する敬語的な表現です。お伴する、お伴させていただくという形で使い、相手への敬意を示しながら同行することを表します。ビジネスシーンや公式な場面でよく使われます。
お伴は人に対してのみ使い、神仏への供物の意味はありません。上司の出張にお伴する、社長の視察にお伴するなど、職務上の同行を表現する際に適切です。また、子供が親にお伴するような、家族間でも使える表現です。
現代のビジネスシーンでは、同行させていただく、ご一緒させていただくという表現も多く使われますが、お伴はより格式高く、相手を立てる印象を与えます。使用する相手や場面を選ぶ、やや改まった表現です。
お伴の例文
- ( 1 ) 部長の出張にお伴させていただきます。
- ( 2 ) 社長の会食にお伴することになりました。
- ( 3 ) 明日の視察には、私がお伴いたします。
- ( 4 ) お客様の工場見学にお伴させていただければ幸いです。
- ( 5 ) 専務の海外出張にお伴する準備をしています。
- ( 6 ) 恐れ入りますが、会議にお伴してもよろしいでしょうか。
お伴の会話例
お供とお伴の違いまとめ
お供とお伴は、意味の範囲と使用場面において違いがあります。お供は神仏への供物と人への同行の両方の意味を持つ多義的な言葉です。
お伴は人への同行のみを意味し、より敬語的で改まった表現です。お供は供物も同行も、お伴は同行専門という違いがあります。
仏壇に果物を置くならお供、上司に同行するならお伴が適切ですが、同行の意味では両方使えます。
お供とお伴の読み方
- お供(ひらがな):おそなえ
- お供(ローマ字):osonae
- お伴(ひらがな):おとも
- お伴(ローマ字):otomo