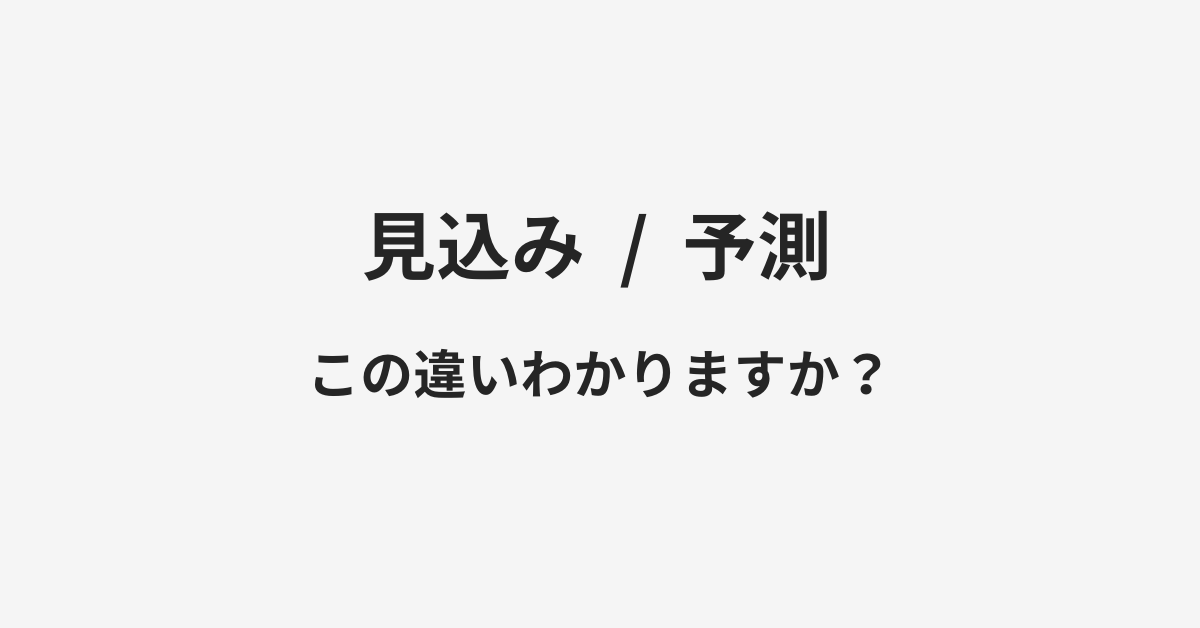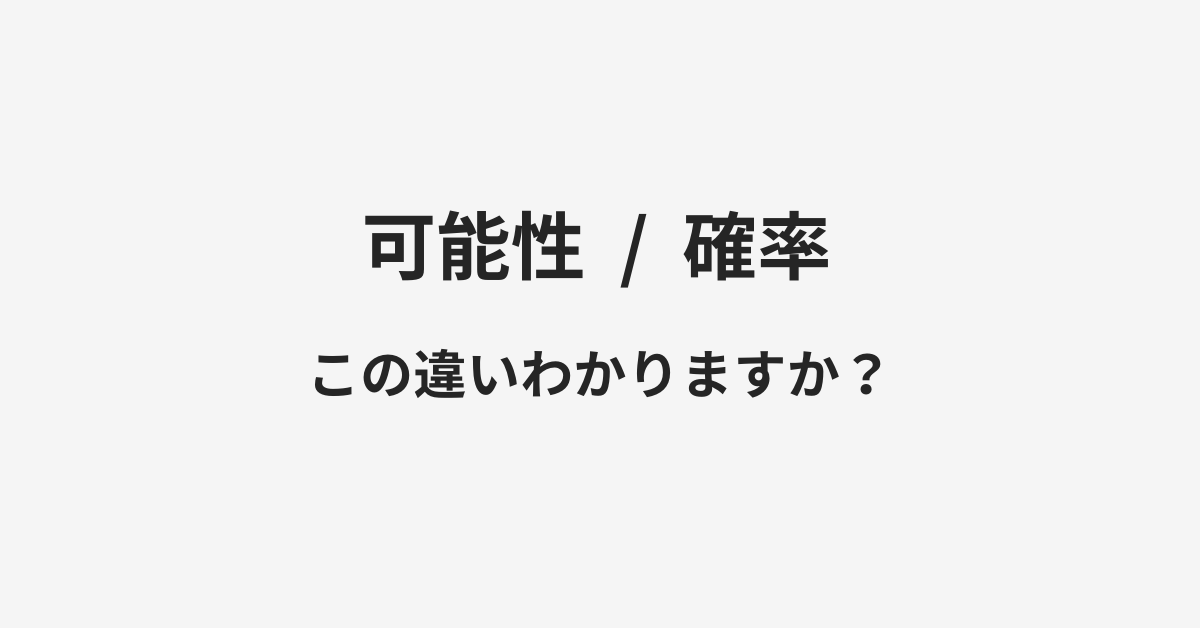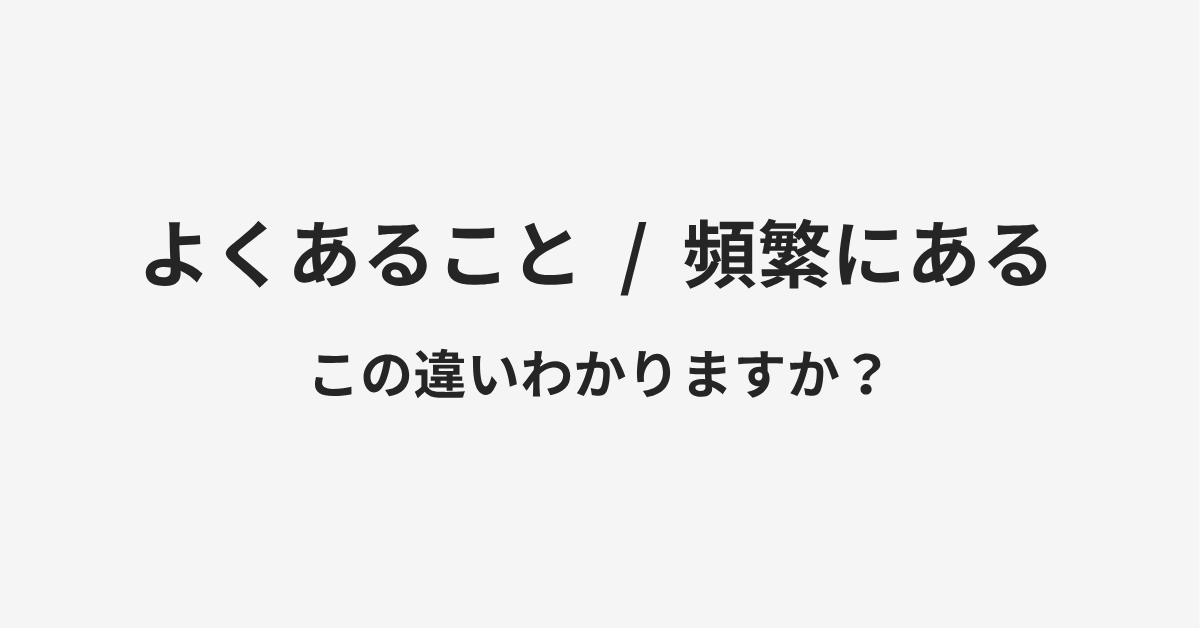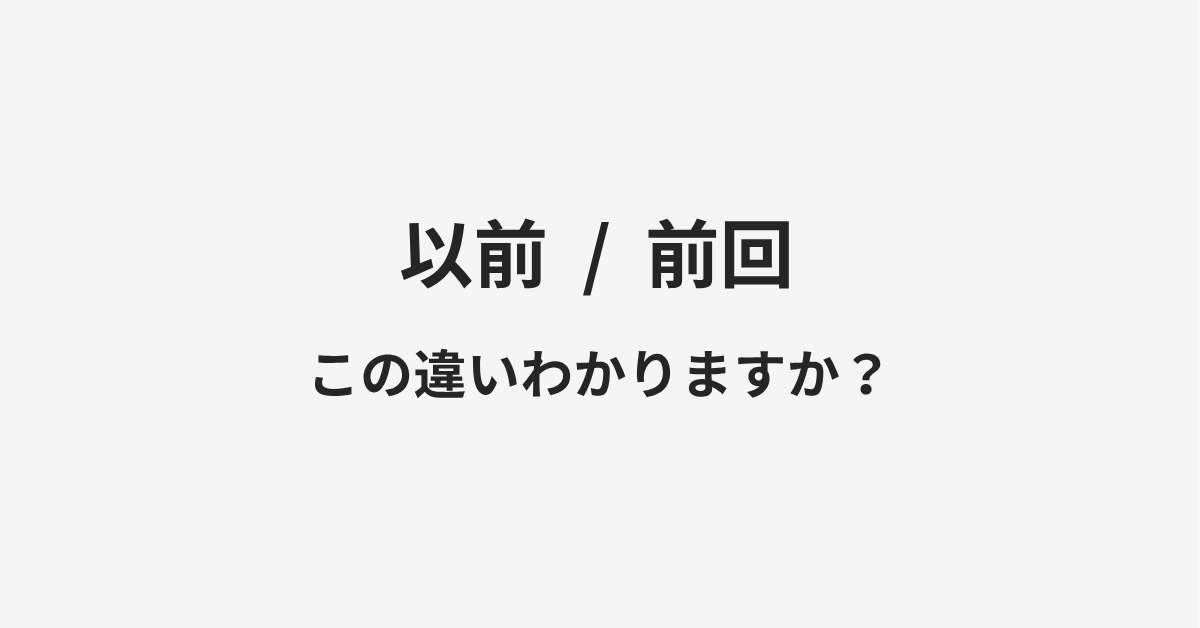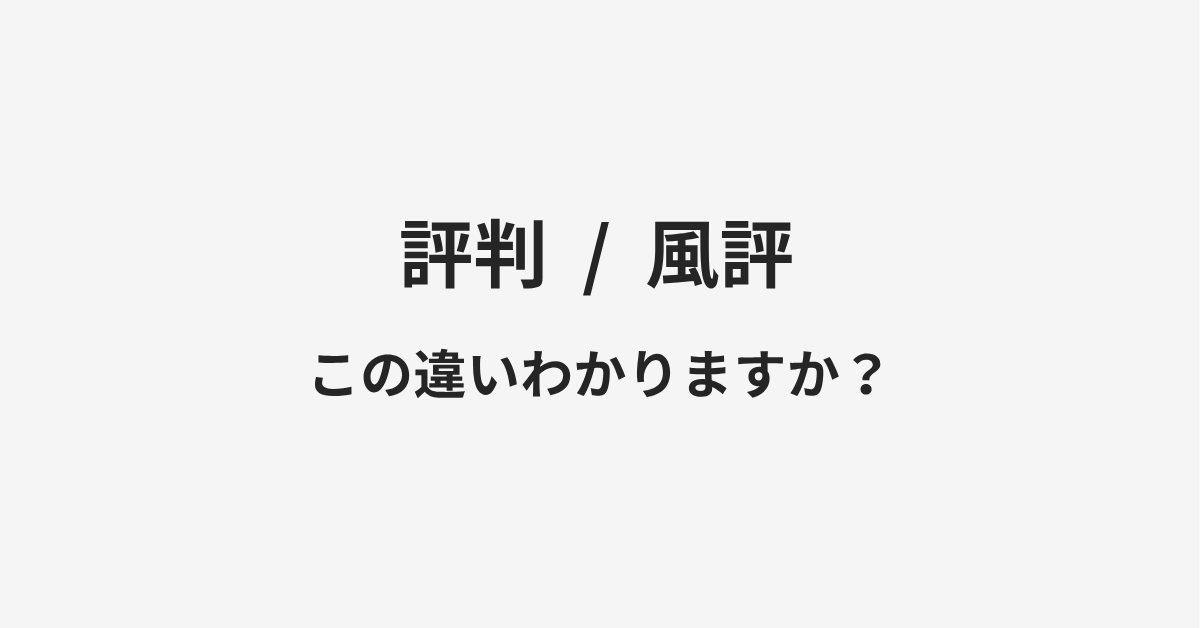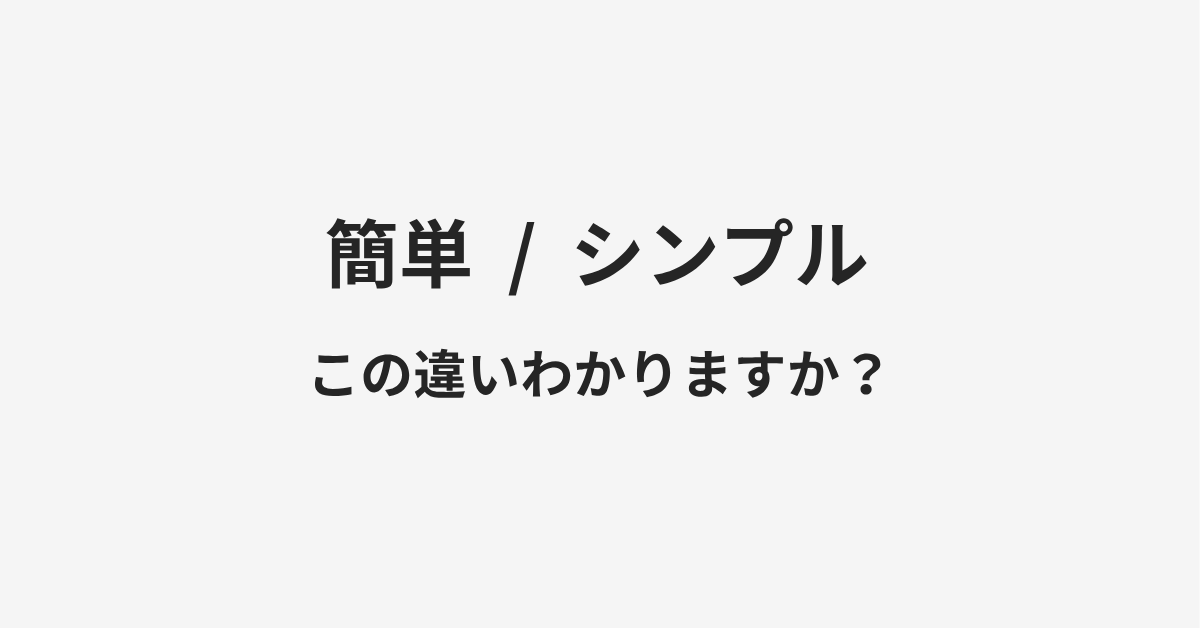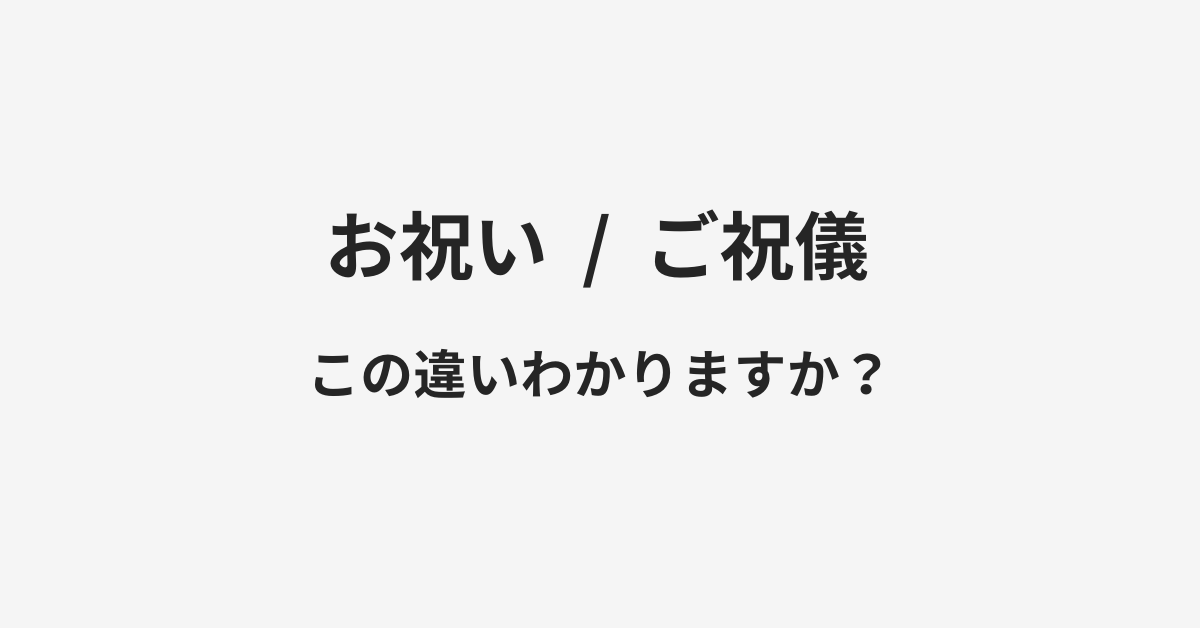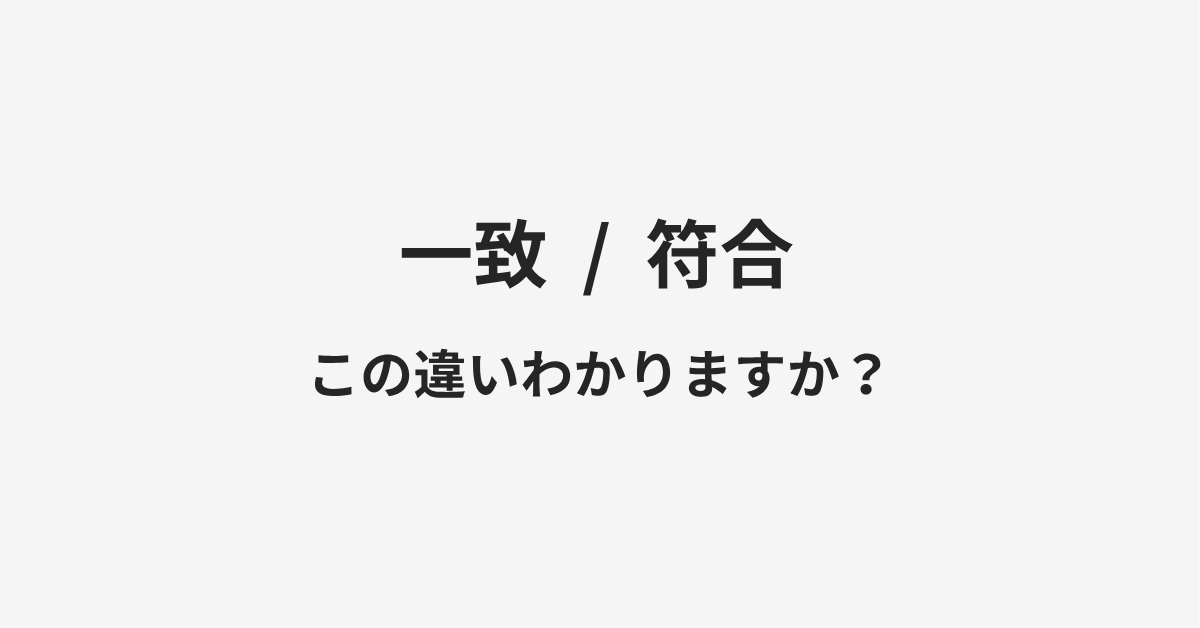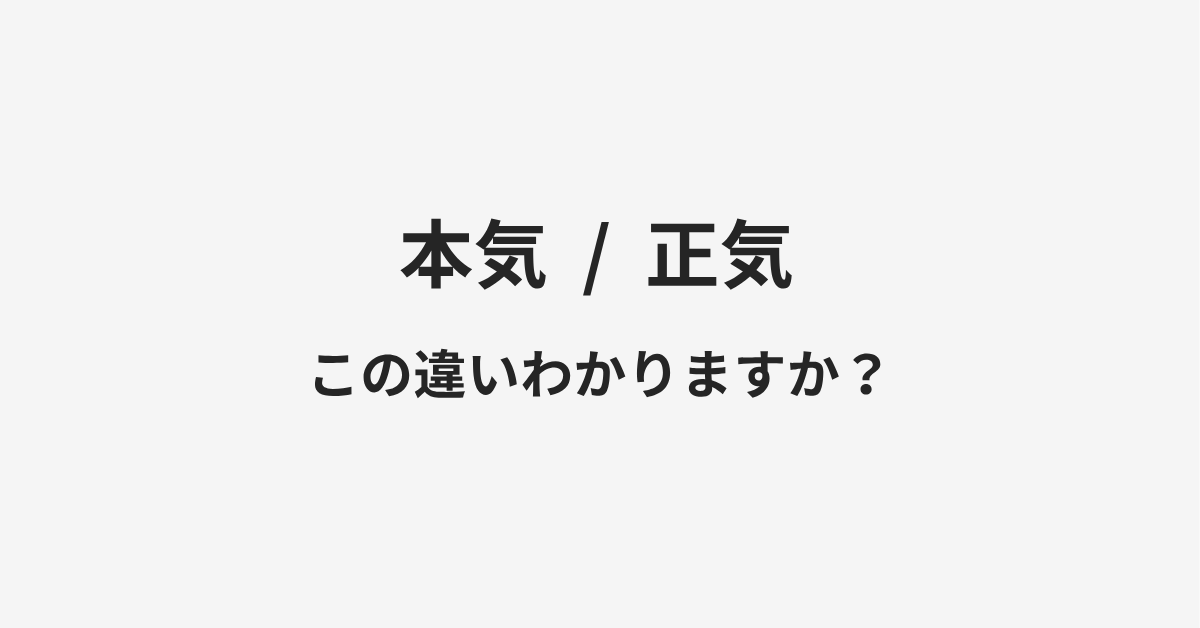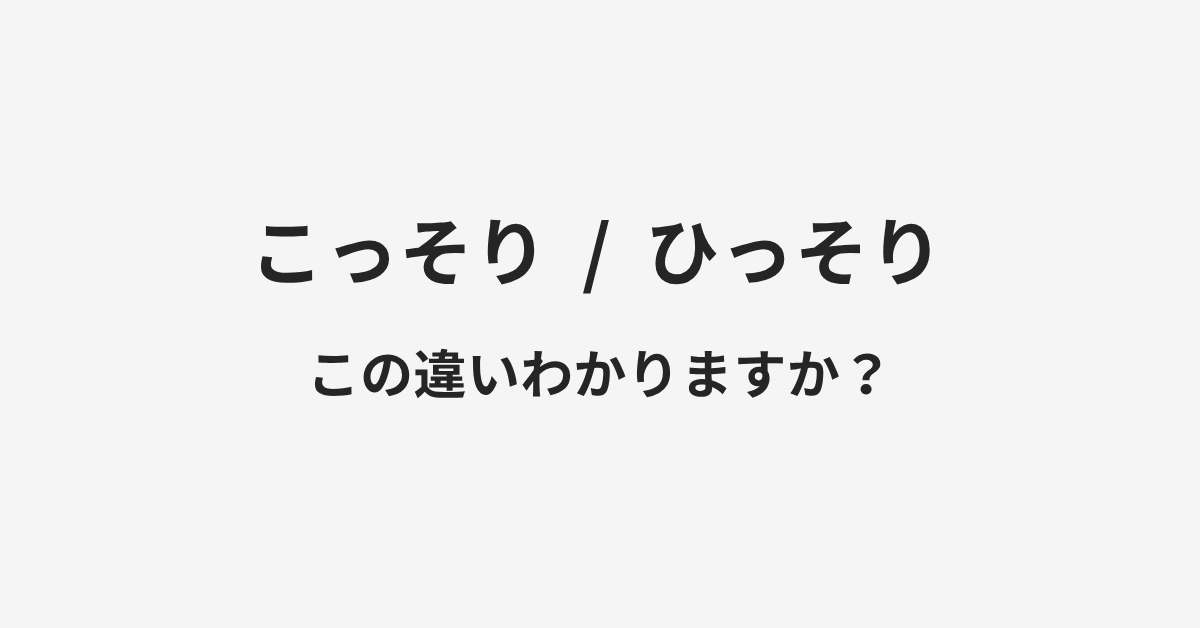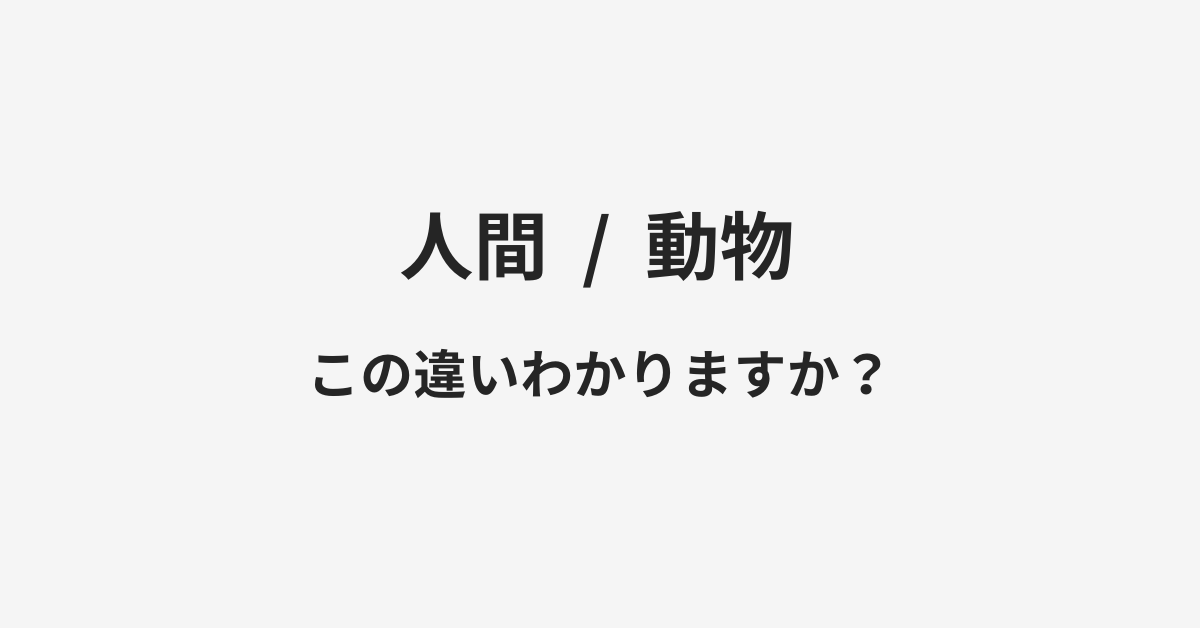【頻度】と【確率】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
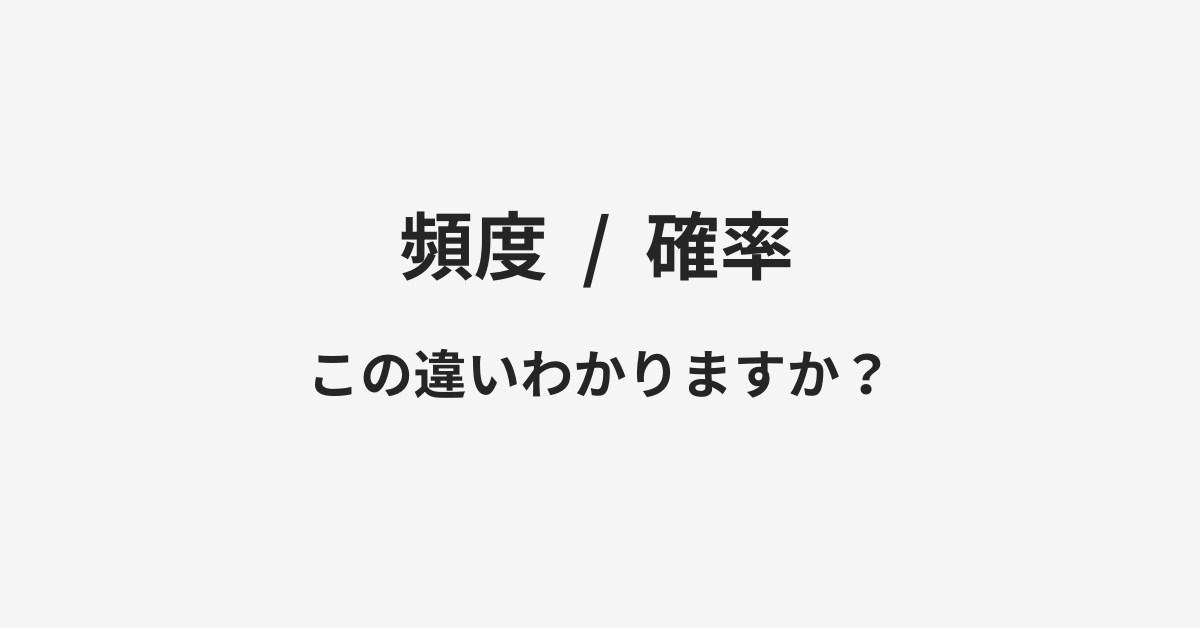
頻度と確率の分かりやすい違い
頻度は、ある出来事が起こる回数や頻繁さを表します。週に3回の頻度、頻度が高いのように、実際に起きた回数や間隔を示す言葉で、過去の実績を表現します。
確率は、ある出来事が起こる可能性を数値で表します。50%の確率、確率が低いのように、将来の可能性を0から1(または0%から100%)で示します。
頻度は実際の回数、確率は起こる可能性という違いがあります。
頻度とは?
頻度とは、ある事象が一定期間内に起こる回数や、どのくらい頻繁に起こるかを表す概念です。毎日、週に2回、月1回など、実際の発生回数や間隔を具体的に示します。過去のデータや観察に基づく実績値です。
頻度は時間の単位と組み合わせて使われることが多く、使用頻度、更新頻度、発生頻度などの形で日常的に使われます。高頻度、低頻度という表現もあり、物事の頻繁さを相対的に表現できます。
ビジネスでは顧客の購買頻度、医療では症状の発生頻度など、様々な分野で重要な指標となります。頻度分析は、パターンを見つけたり、効率を改善したりする際の基礎データとして活用されます。
頻度の例文
- ( 1 ) メールチェックの頻度は1日3回です。
- ( 2 ) 最近、頭痛の頻度が増えています。
- ( 3 ) 更新頻度を上げてください。
- ( 4 ) 使用頻度の高い機能を優先します。
- ( 5 ) 地震の発生頻度が心配です。
- ( 6 ) 会議の頻度を減らしたいです。
頻度の会話例
確率とは?
確率とは、ある事象が起こる可能性を0から1(または0%から100%)の数値で表したものです。数学的・統計的な概念で、不確実な未来の出来事について、その起こりやすさを定量的に示します。コイン投げで表が出る確率は50%、サイコロで1が出る確率は約16.7%など、理論的に計算できるものから、天気予報の降水確率のように統計データに基づくものまで様々です。
確率は予測や意思決定の重要な指標となります。
日常生活では、宝くじの当選確率、病気の発症確率、成功確率など、リスクや可能性を評価する際に使われます。確率を理解することで、より合理的な判断ができるようになります。
確率の例文
- ( 1 ) 雨の確率は80%です。
- ( 2 ) 成功する確率は五分五分です。
- ( 3 ) 宝くじが当たる確率は極めて低いです。
- ( 4 ) 事故が起こる確率を計算しました。
- ( 5 ) 合格の確率を上げるため勉強します。
- ( 6 ) この確率では賭けられません。
確率の会話例
頻度と確率の違いまとめ
頻度は実際に起こった回数や頻繁さを表し、過去の観察や実績に基づく具体的な数値です。時間単位と組み合わせて使われます。
確率は将来起こる可能性を0から1の数値で表し、理論的または統計的な予測です。不確実性を定量化する概念です。簡単に言えば、頻度はどのくらい起きたか、確率はどのくらい起きそうかという違いで、過去と未来の視点が異なります。
頻度と確率の読み方
- 頻度(ひらがな):ひんど
- 頻度(ローマ字):hinndo
- 確率(ひらがな):かくりつ
- 確率(ローマ字):kakuritsu