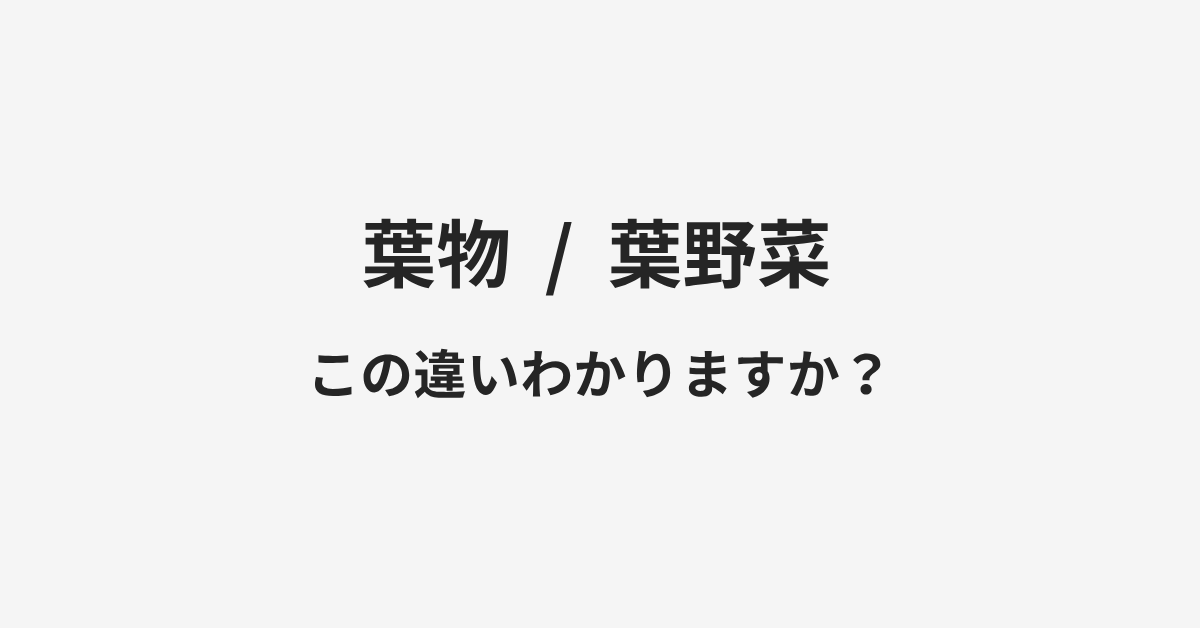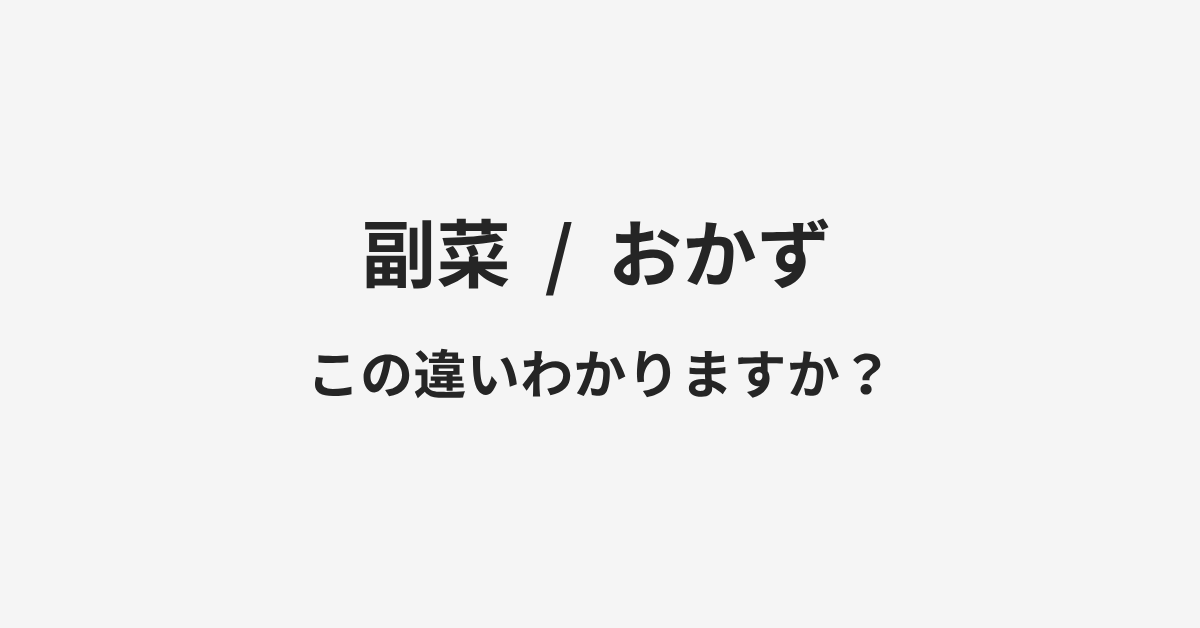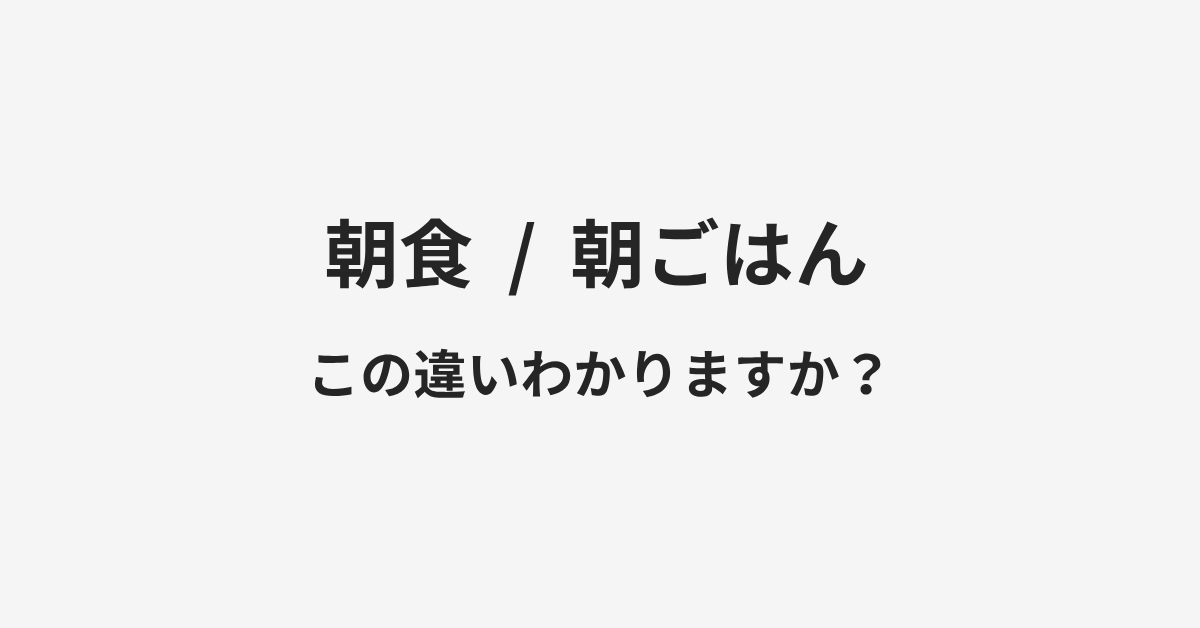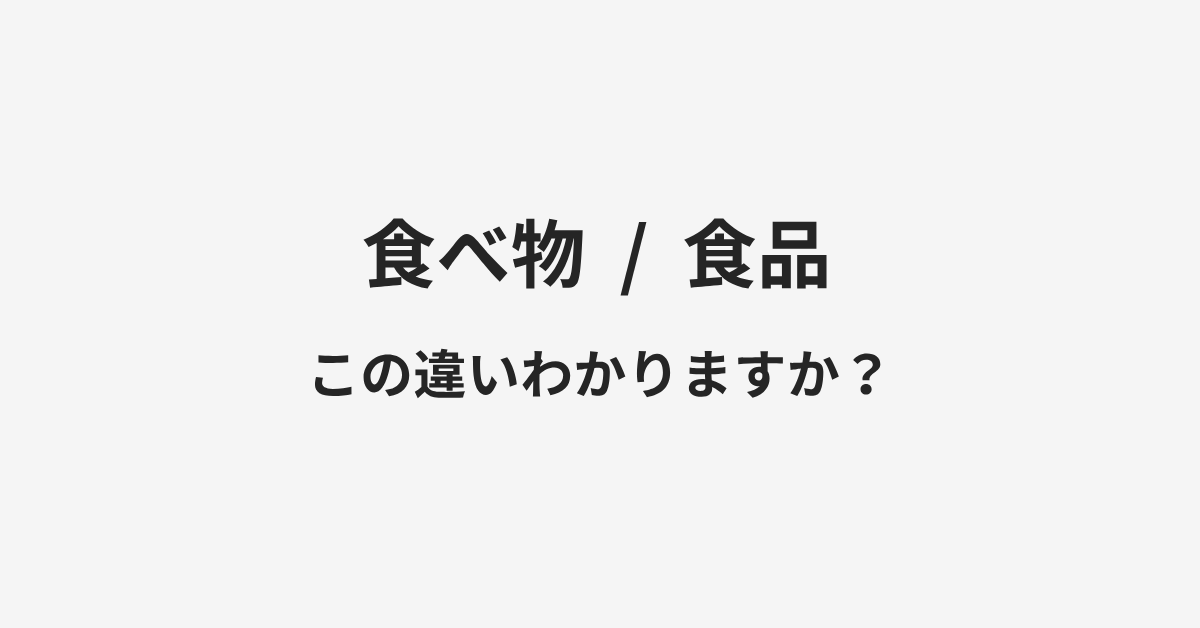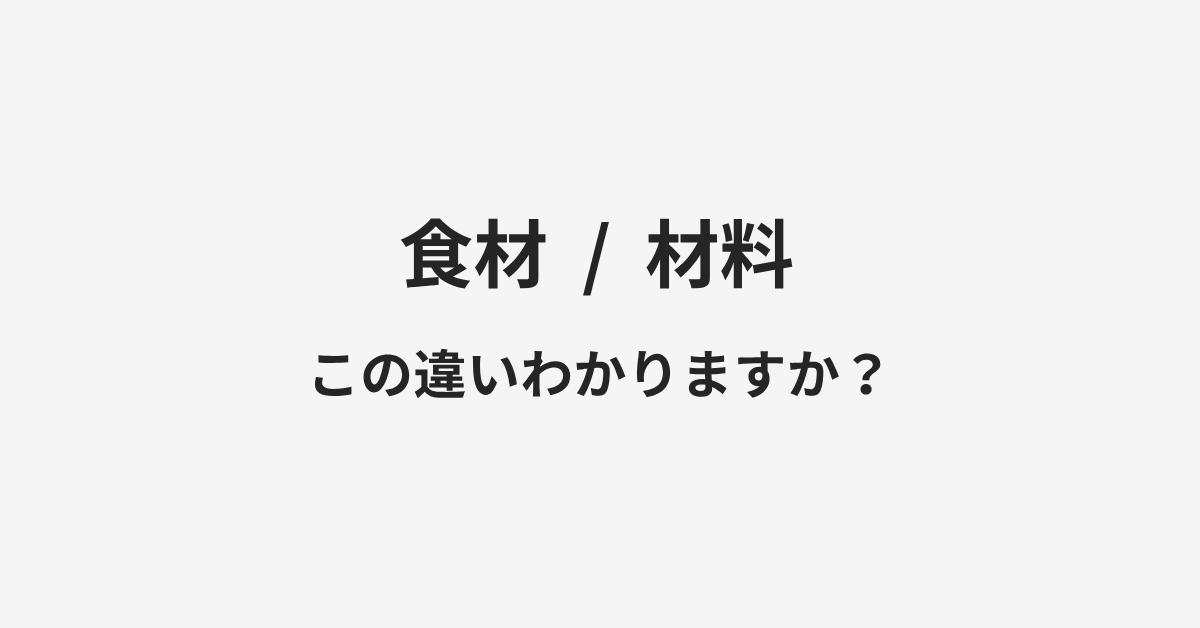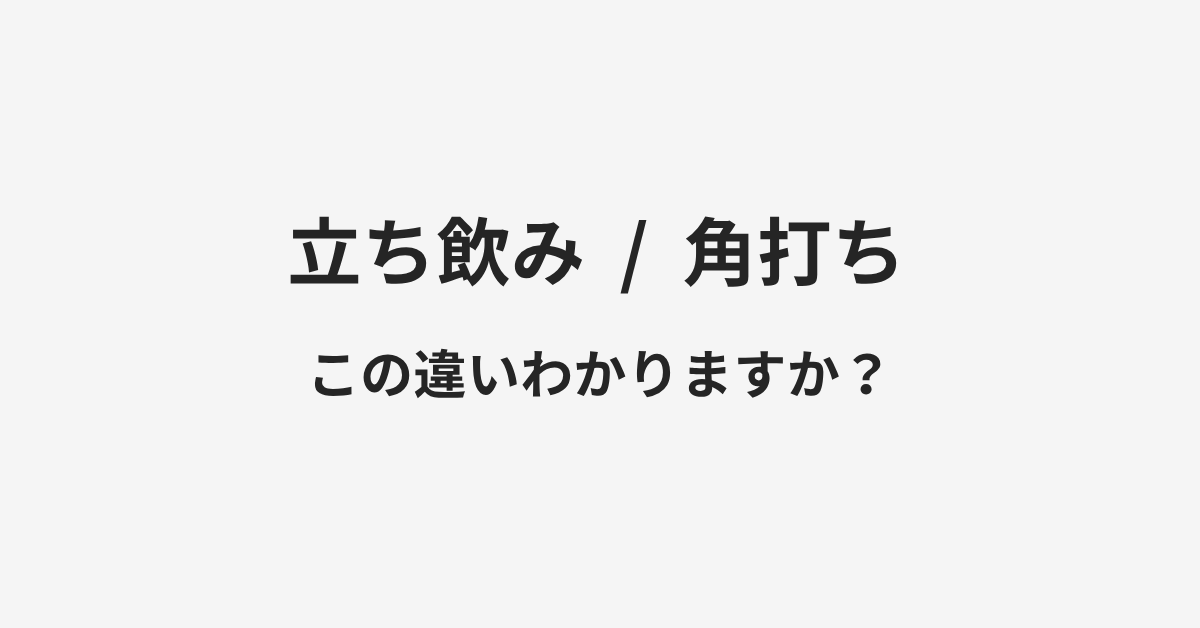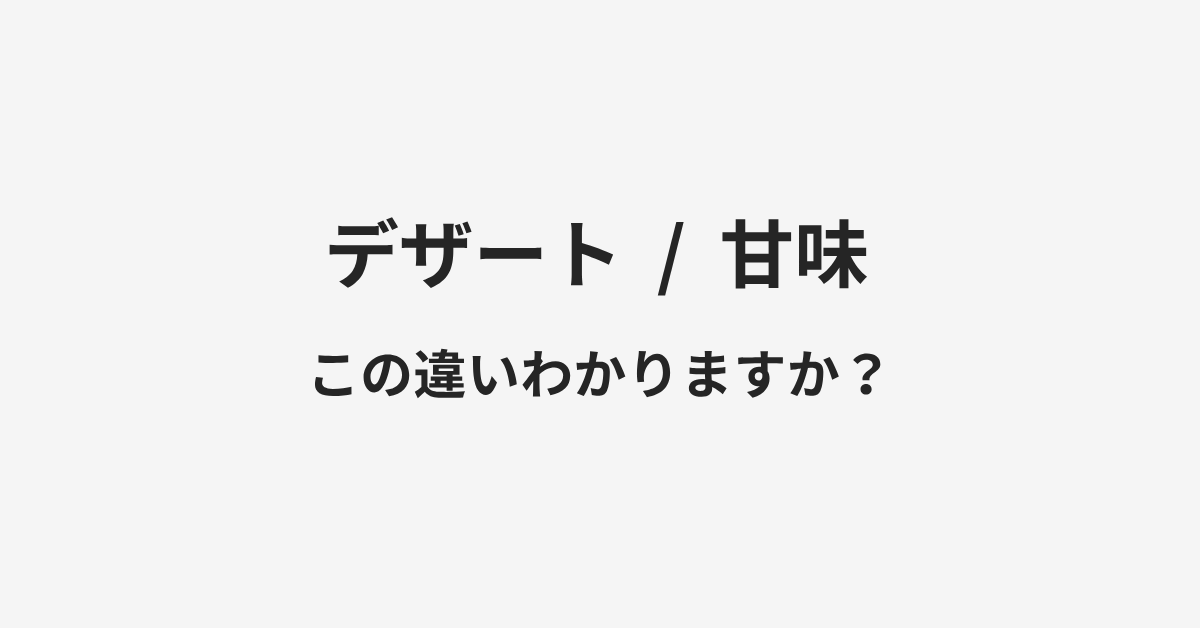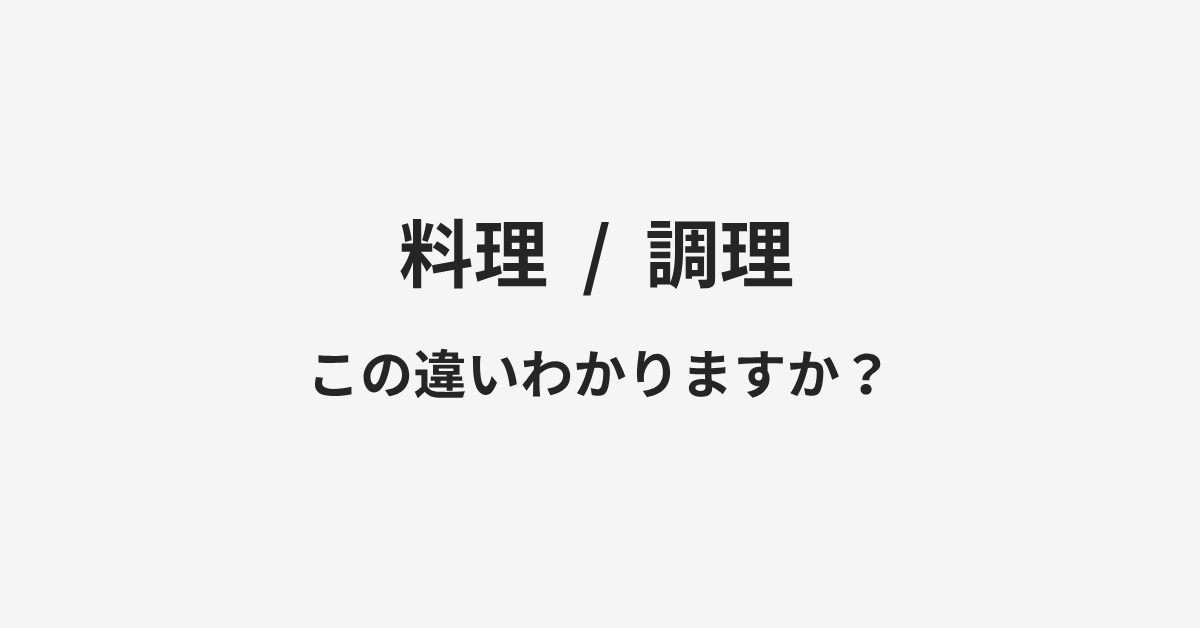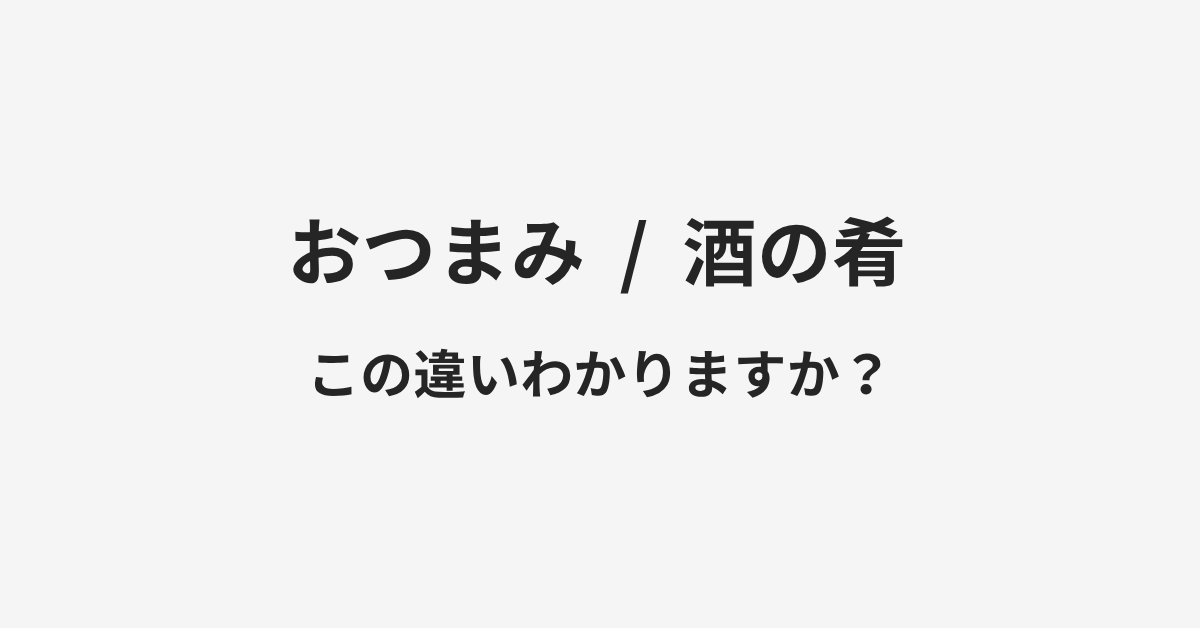【野菜】と【菜類】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
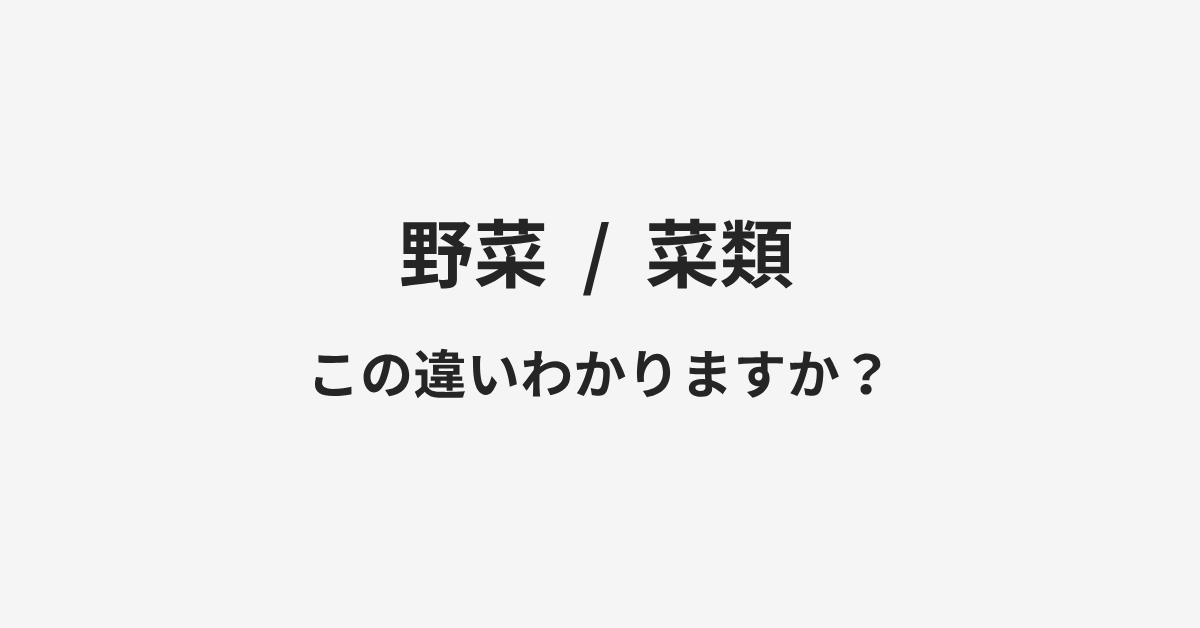
野菜と菜類の分かりやすい違い
野菜は、食べるために栽培される植物全般を指す、誰もが使う一般的な言葉です。菜類は、主にホウレンソウや白菜などの葉物野菜を指す、専門的な分類の言葉です。
野菜は食用植物全般・日常語、菜類は葉物中心・専門語という違いがあります。
野菜とは?
野菜とは、食用として栽培される植物の総称で、葉、茎、根、花、実など様々な部位を食べる植物全般を指す日常的な言葉です。トマト、キュウリ、ニンジン、タマネギ、レタスなど、種類は多岐にわたり、日本の食卓に欠かせない食材群です。野菜を食べる、野菜不足など、最も一般的に使われます。
野菜は、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含み、健康維持に不可欠な食材です。厚生労働省は1日350g以上の野菜摂取を推奨しており、野菜をもっと食べようという啓発活動も行われています。
生食、炒め物、煮物、漬物など、調理法も多様です。緑黄色野菜、淡色野菜、有機野菜、地場野菜など、様々な分類や呼び方があり、それぞれ特徴があります。最近では、機能性野菜やベビーリーフなど、新しいタイプの野菜も注目されています。
野菜の例文
- ( 1 ) 新鮮な野菜を直売所で購入しました。
- ( 2 ) 野菜中心の食生活に変えてから、体調が良くなりました。
- ( 3 ) 子どもの野菜嫌いを克服させたいです。
- ( 4 ) 有機野菜の宅配サービスを利用しています。
- ( 5 ) 野菜ソムリエの資格を取得しました。
- ( 6 ) 季節の野菜を使った料理が好きです。
野菜の会話例
菜類とは?
菜類とは、主に葉を食用とする野菜の分類群を指す専門用語で、アブラナ科の植物を中心に、ホウレンソウ、小松菜、白菜、キャベツなどが含まれます。植物学的・農学的な分類として使われ、葉菜類(ようさいるい)とも呼ばれます。一般会話ではあまり使用されません。
菜類の特徴は、葉の部分を主に食用とすることで、ビタミンやミネラル、特に葉酸や鉄分が豊富です。菜っ葉という俗称もあり、青菜類として親しまれています。農業統計や栄養学の文献では、菜類の生産量、菜類の栄養価などの表現で使用されます。
中国語の蔬菜(そさい)から派生した言葉とも言われ、東アジアの食文化において重要な位置を占めています。ただし、現代日本では野菜に統合されて使われることがほとんどで、専門分野以外では使用頻度が低い用語です。
菜類の例文
- ( 1 ) 菜類の栽培技術について学んでいます。
- ( 2 ) 冬場の菜類は、甘みが増して美味しいです。
- ( 3 ) 菜類に含まれる栄養素の研究をしています。
- ( 4 ) アブラナ科の菜類は、種類が豊富です。
- ( 5 ) 菜類の病害虫対策が課題です。
- ( 6 ) 伝統的な菜類の品種を守る活動をしています。
菜類の会話例
野菜と菜類の違いまとめ
野菜は食用植物全般を指す日常語、菜類は葉物野菜中心の専門的分類語という違いがあります。スーパーでは野菜売り場、農学書では菜類の栽培というように、一般用と専門用で使い分けられます。
野菜は誰もが理解できる言葉、菜類は限定的な使用にとどまります。
日常生活では野菜で十分通じ、菜類は専門知識として知っておく程度で良いでしょう。
野菜と菜類の読み方
- 野菜(ひらがな):やさい
- 野菜(ローマ字):yasai
- 菜類(ひらがな):さいるい
- 菜類(ローマ字):sairui