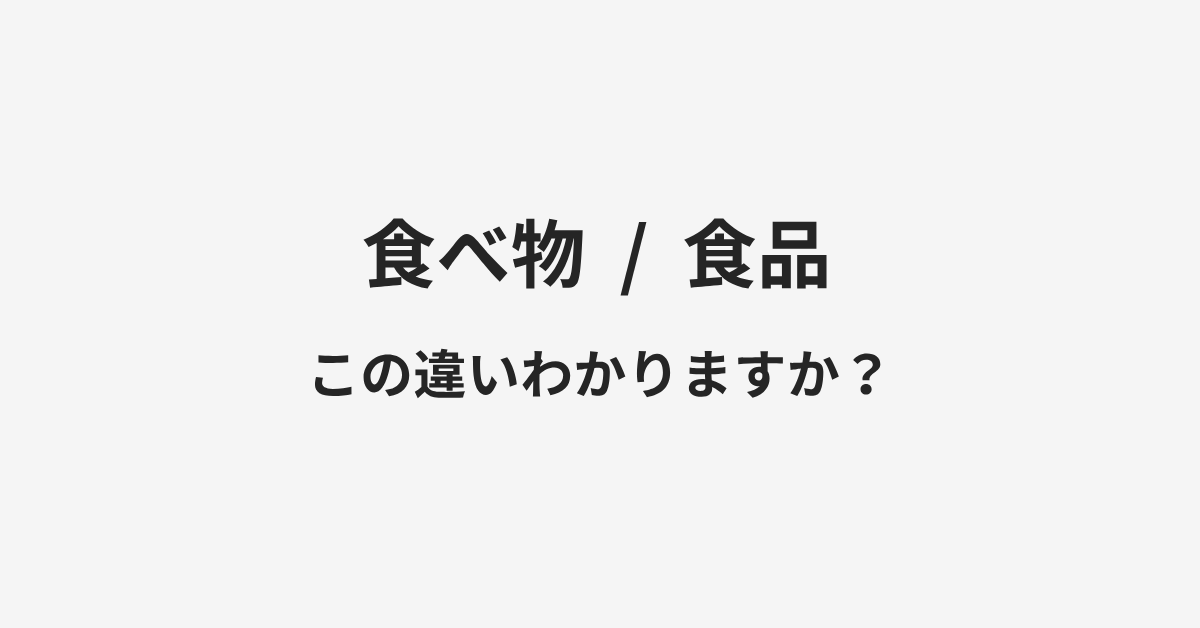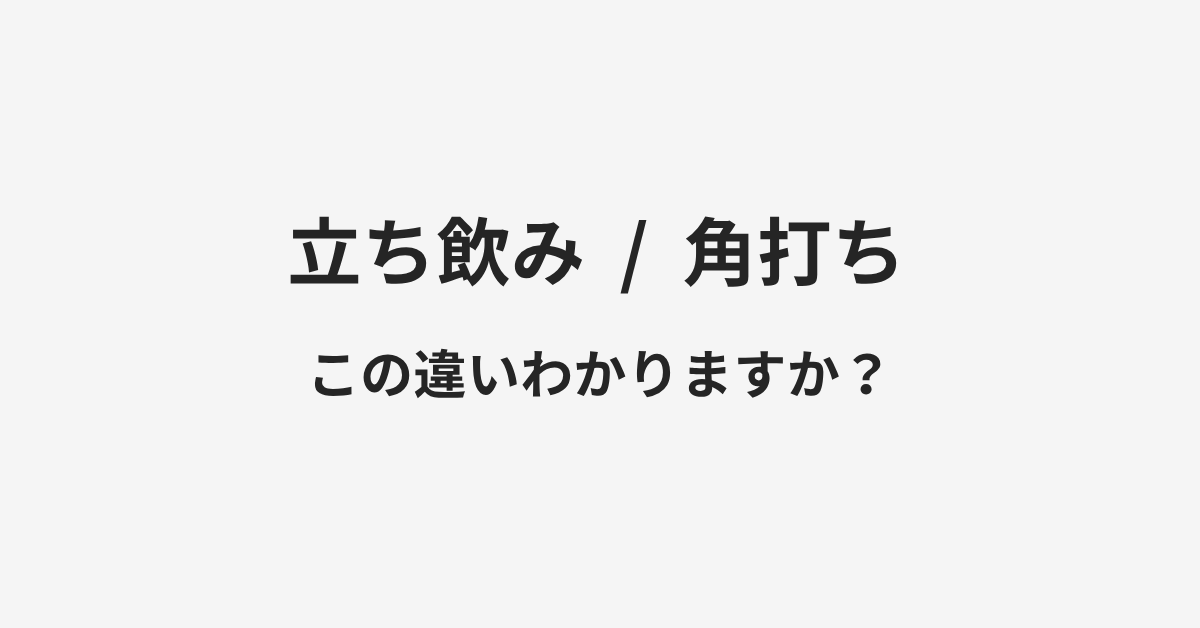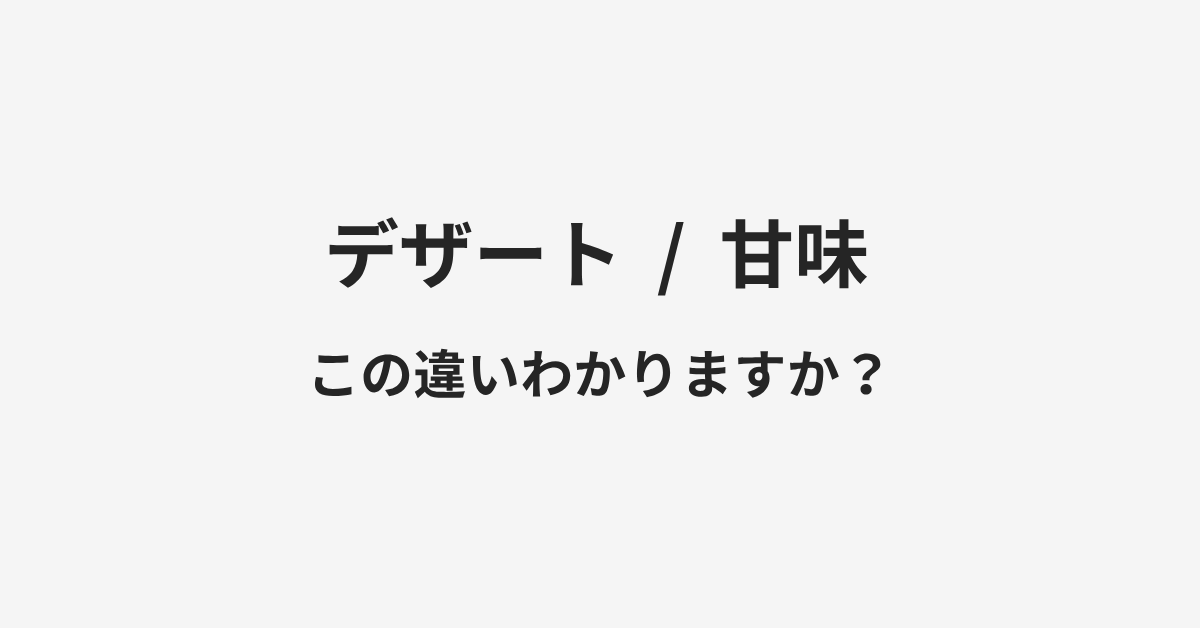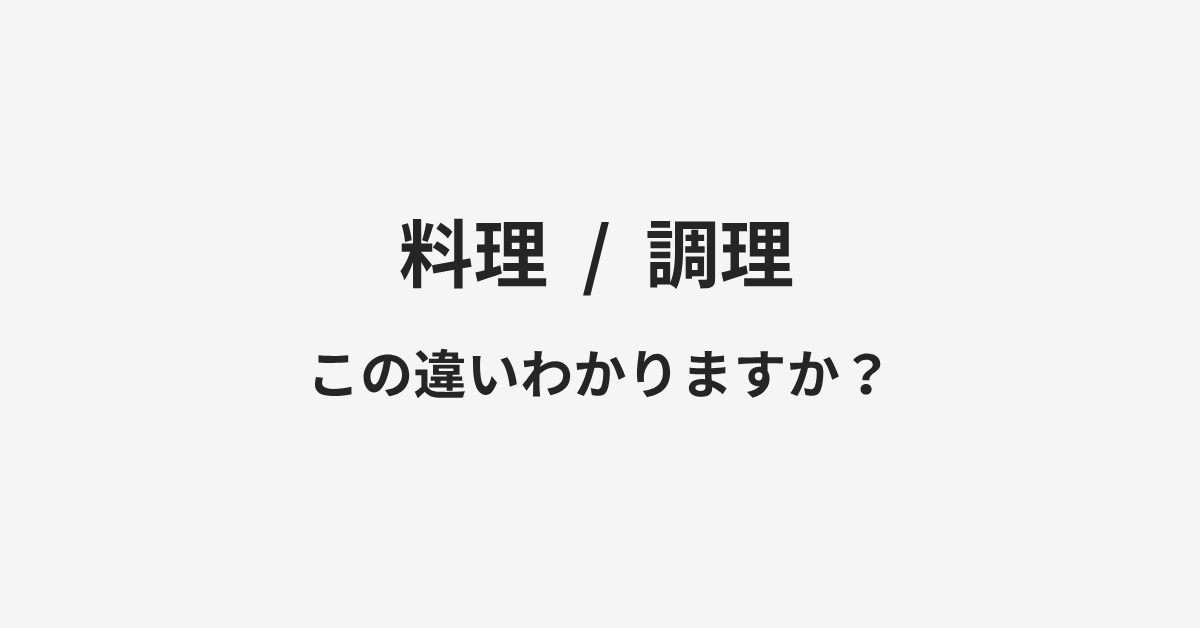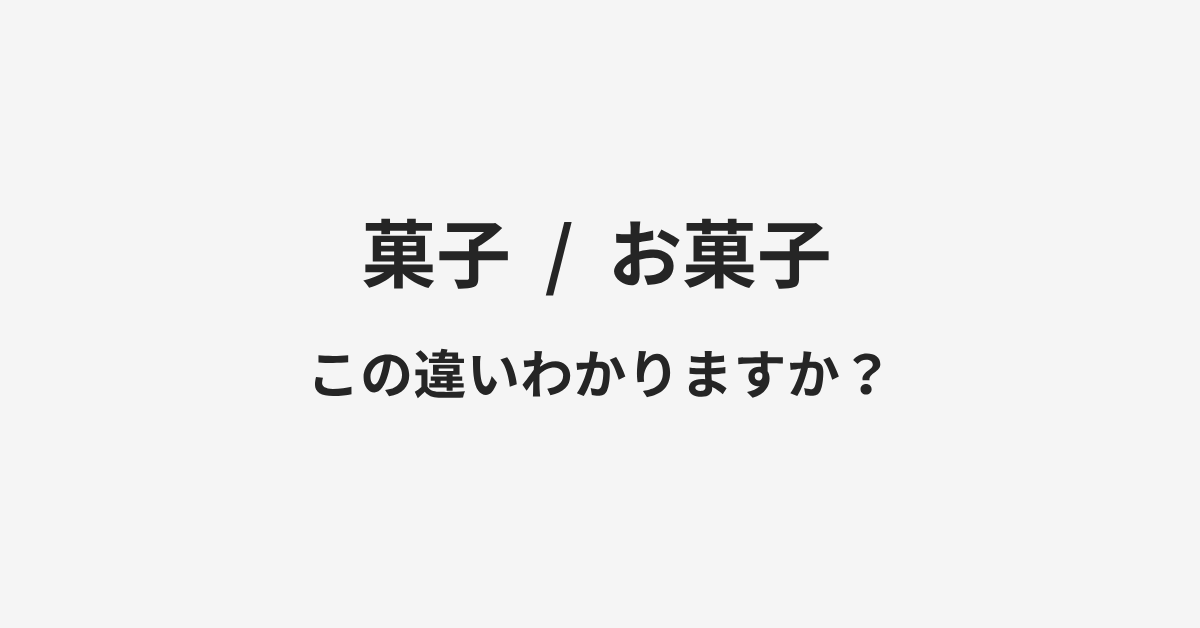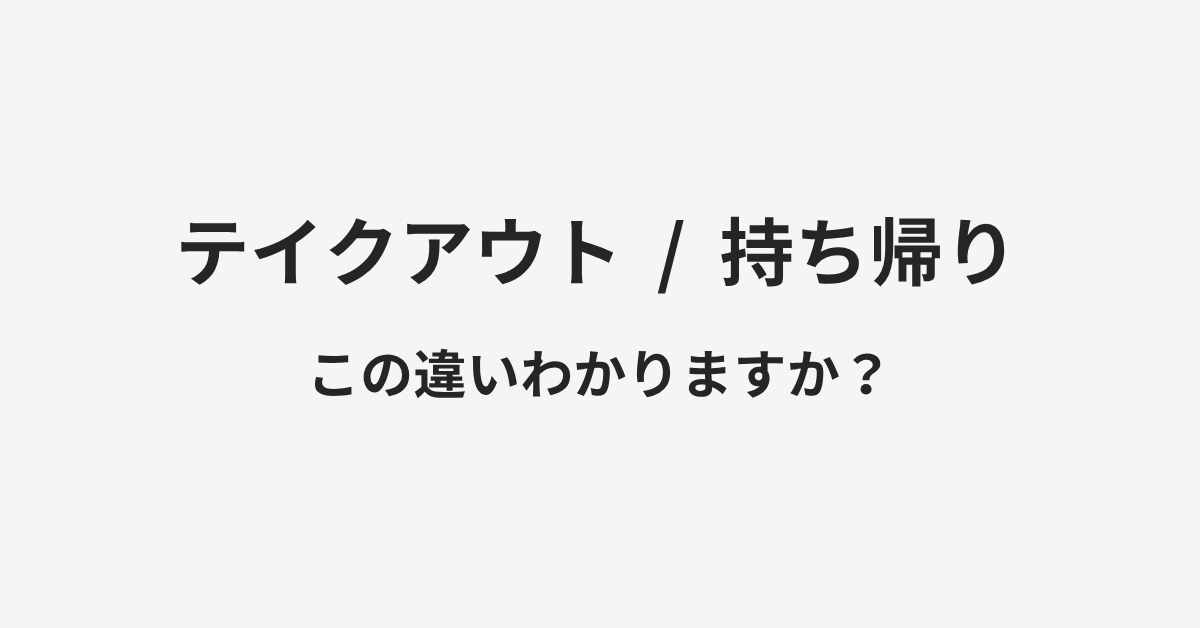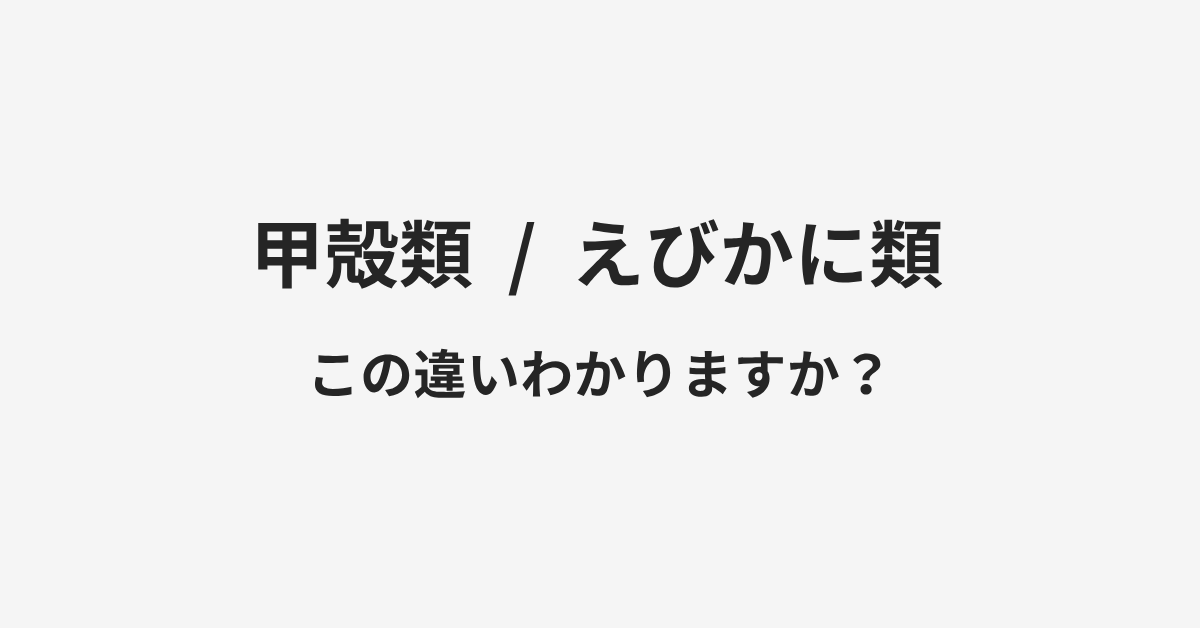【食料】と【食糧】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
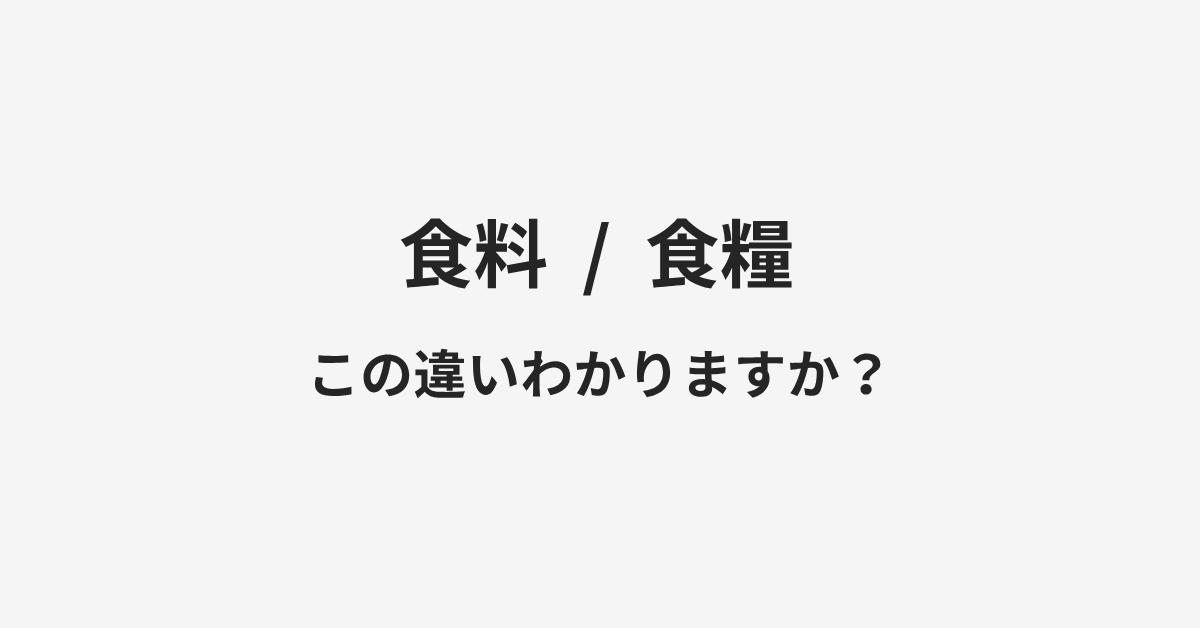
食料と食糧の分かりやすい違い
食料は、人が食べるもの全般を指す一般的な言葉で、野菜も肉も含みます。
食糧は、主に米や小麦など主食となる穀物を指す、政策的・公的な場面で使われる言葉です。
食料は食べ物全般、食糧は主食用の穀物中心という違いがあります。
食料とは?
食料とは、人間が食べるために用意される食べ物全般を指す包括的な言葉です。肉、魚、野菜、果物、乳製品、加工品など、あらゆる食べ物が含まれます。食料品店、食料自給率、食料問題など、日常生活から国際問題まで幅広い文脈で使用される一般的な用語です。
現代では、食料の安定供給、食料安全保障、食料廃棄問題など、グローバルな課題と関連して使われることが多くなっています。また、備蓄食料、非常食料など、災害対策の文脈でも重要な概念です。家庭レベルでは食料の買い出し、食料費など、日常的な場面で使われます。
食料という言葉は、量的な側面や供給の観点から語られることが多く、食料不足、食料援助など、社会的・経済的な文脈で使用される傾向があります。栄養学的には、バランスの取れた食料摂取が健康維持に重要とされています。
食料の例文
- ( 1 ) 週末に食料の買い出しに行きます。
- ( 2 ) 食料品の値上がりが家計を圧迫しています。
- ( 3 ) 災害に備えて、非常用食料を準備しました。
- ( 4 ) 食料自給率の向上が課題です。
- ( 5 ) 新鮮な食料を求めて、朝市に通っています。
- ( 6 ) 食料ロスを減らす工夫をしています。
食料の会話例
食糧とは?
食糧とは、主に米、小麦、トウモロコシなどの主食となる穀物を中心とした、国民の生存に不可欠な基本的食物を指す公的な用語です。食糧庁(現在は廃止)、食糧管理制度など、国の政策や行政に関わる文脈で使用されることが特徴的です。歴史的には、戦時中や戦後の配給制度において食糧という言葉が頻繁に使われ、国家による管理・統制の対象としての意味合いが強くありました。
現在でも食糧安全保障、食糧自給率など、国家戦略レベルの議論で使用されます。食糧は、単なる食べ物を超えて、国の独立性や安全保障に関わる戦略物資としての側面があります。
食糧危機、食糧増産など、より深刻で公的な文脈で使われることが多く、個人の日常生活よりも、国家や地域レベルの課題を論じる際に適した言葉です。
食糧の例文
- ( 1 ) 日本の食糧自給率は40%程度です。
- ( 2 ) 戦後の食糧難を経験した世代の話は貴重です。
- ( 3 ) 食糧安全保障の観点から、農業振興が重要です。
- ( 4 ) 主要食糧である米の生産量が減少しています。
- ( 5 ) 食糧管理制度の歴史を学びました。
- ( 6 ) 世界的な食糧危機が懸念されています。
食糧の会話例
食料と食糧の違いまとめ
食料は食べ物全般を指す一般的な言葉、食糧は主食穀物中心の公的な言葉という違いがあります。スーパーでの買い物は食料品、国の農業政策では食糧自給率というように使い分けられます。
日常会話では食料、行政文書では食糧が使われる傾向があります。現代では食料の使用頻度が高く、食糧は限定的な場面での使用となっていますが、両者の違いを理解することで、より適切な言葉選びが可能になります。
食料と食糧の読み方
- 食料(ひらがな):しょくりょう
- 食料(ローマ字):shokuryou
- 食糧(ひらがな):しょくりょう
- 食糧(ローマ字):shokuryo