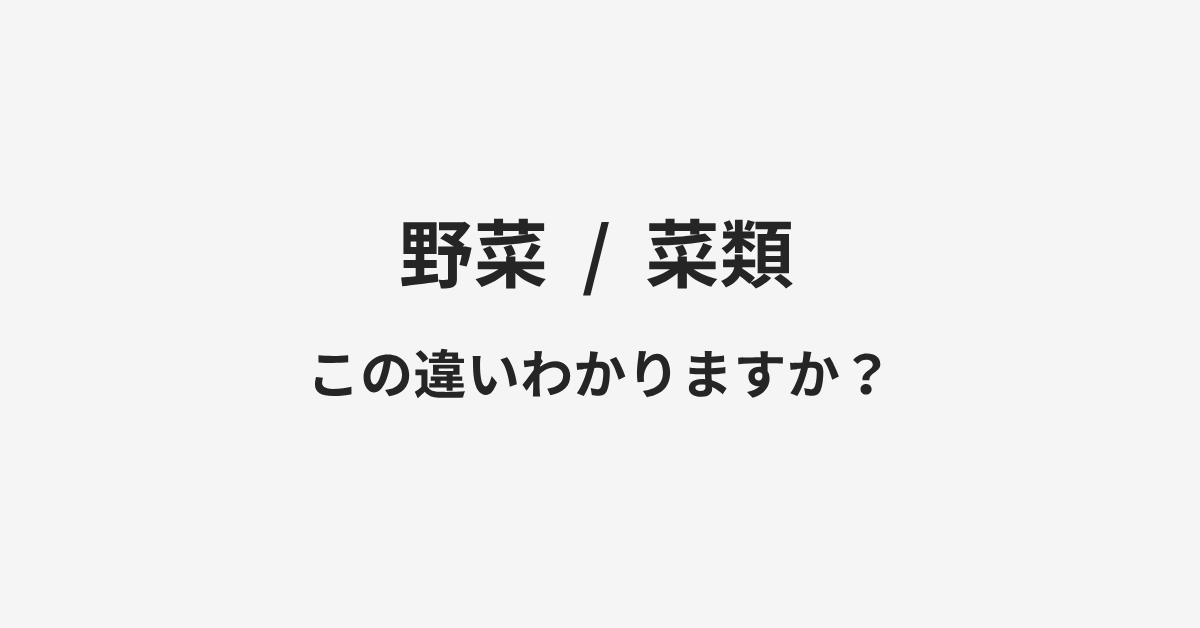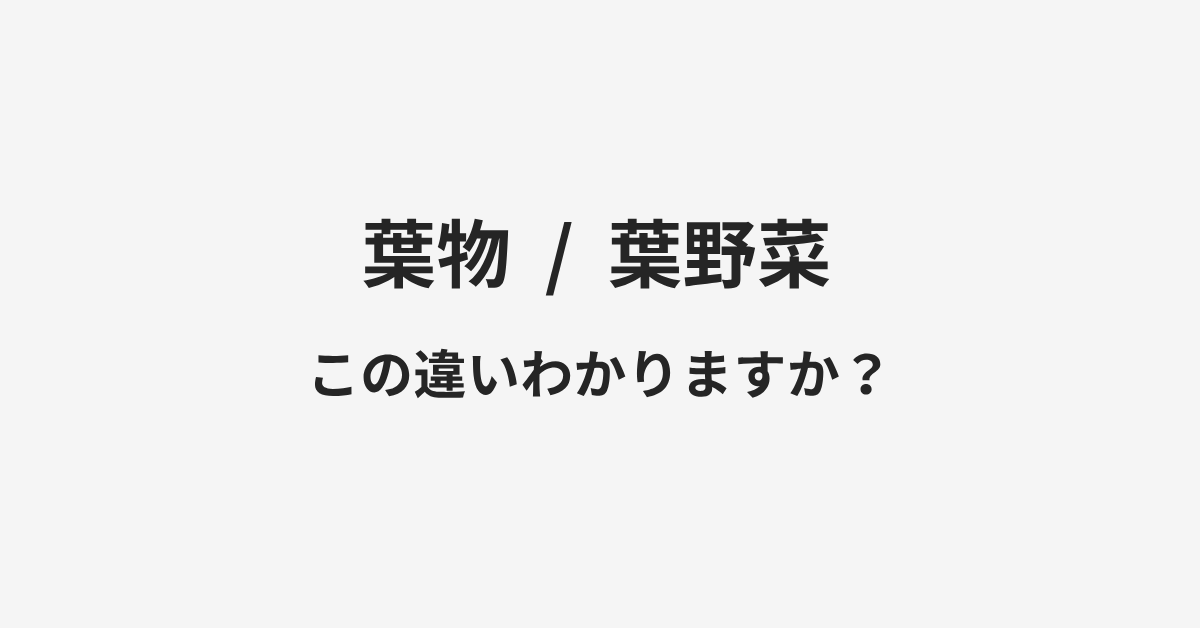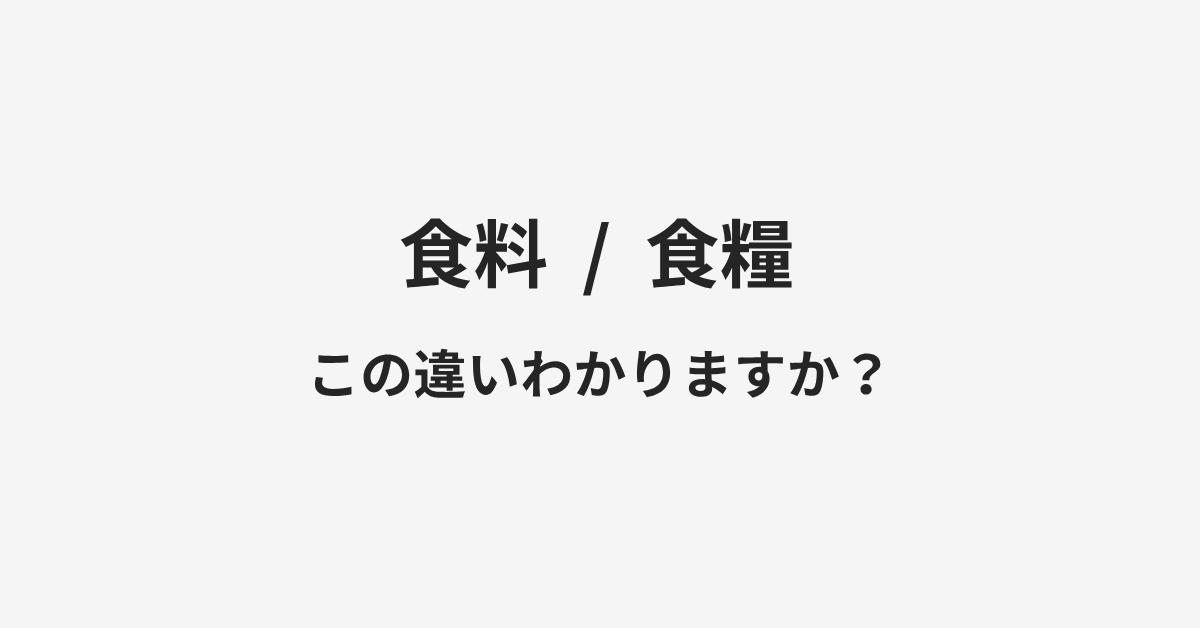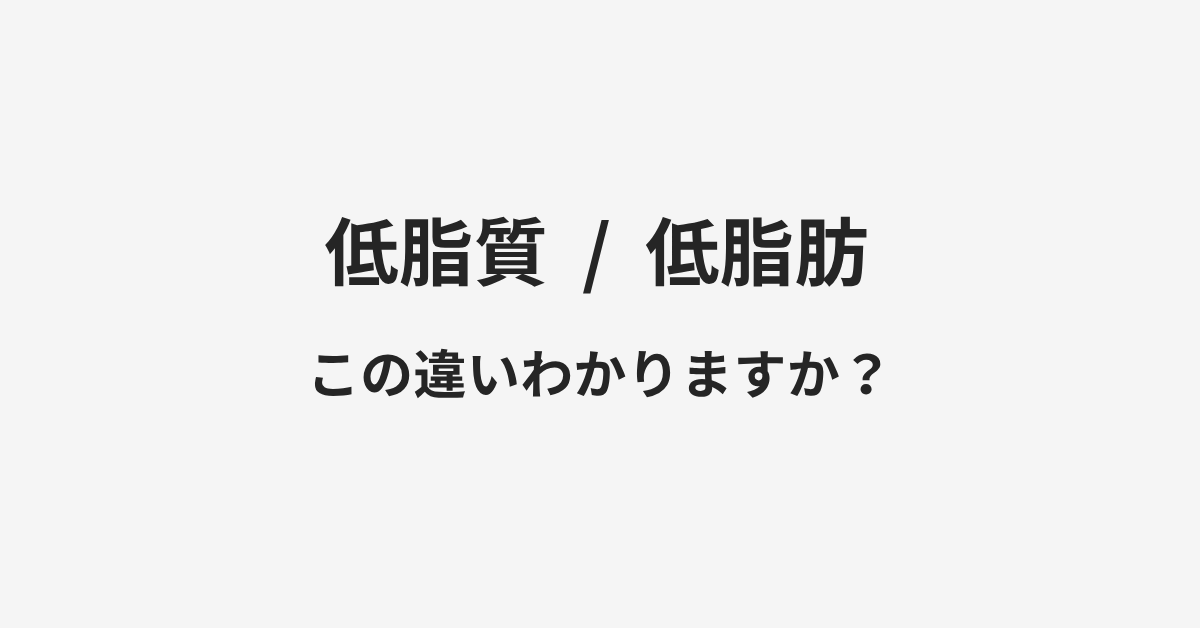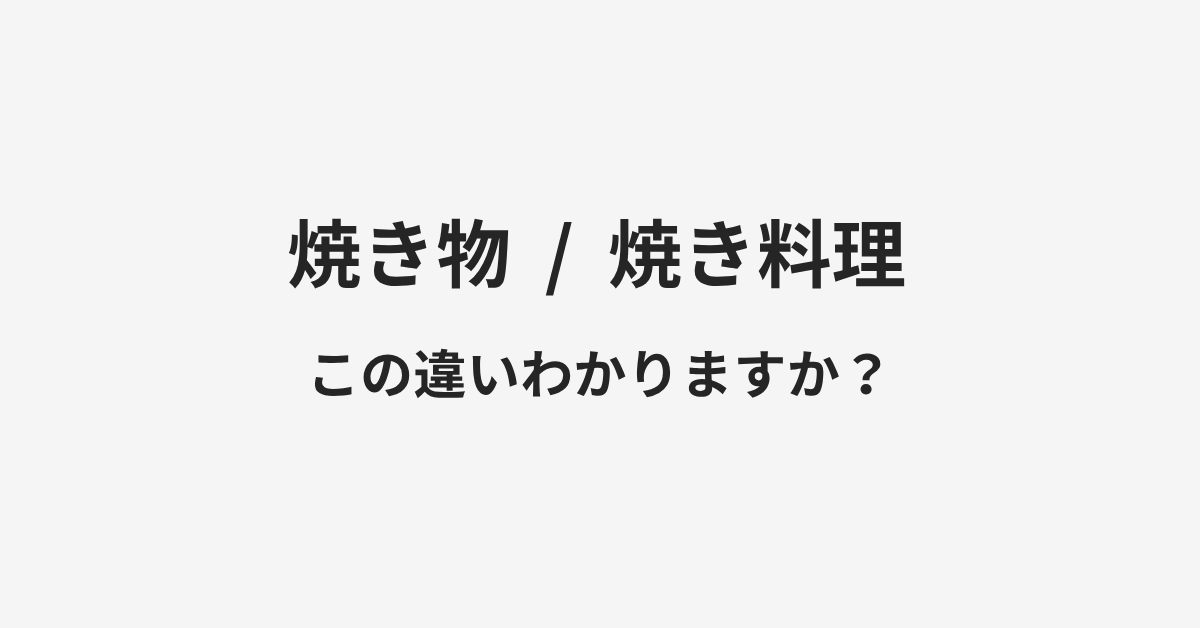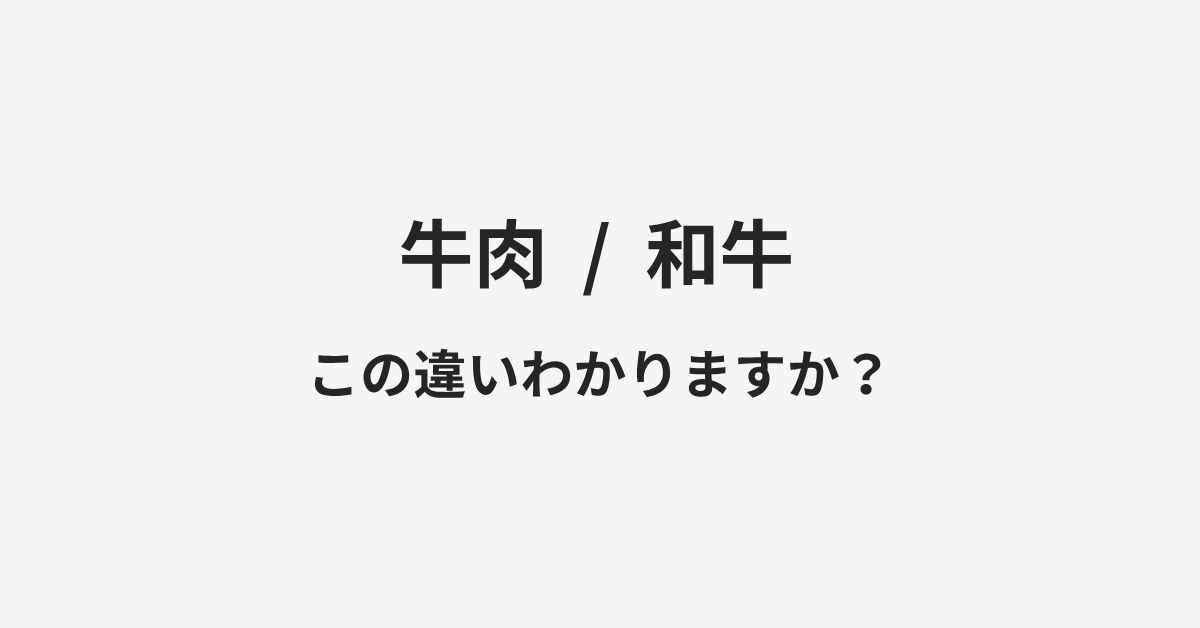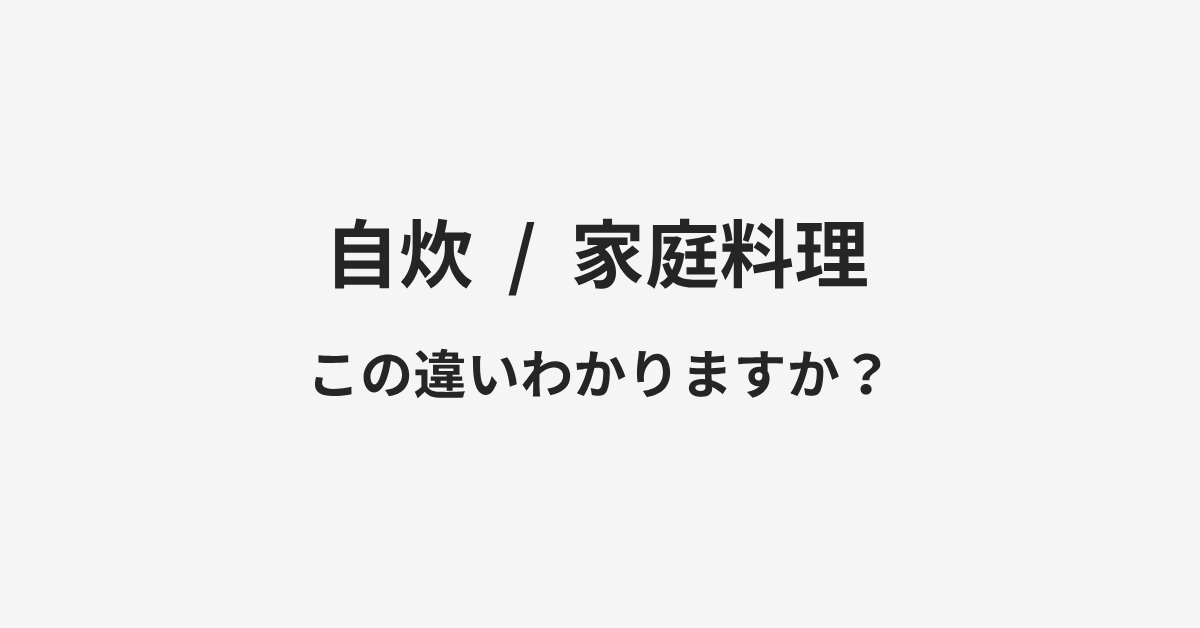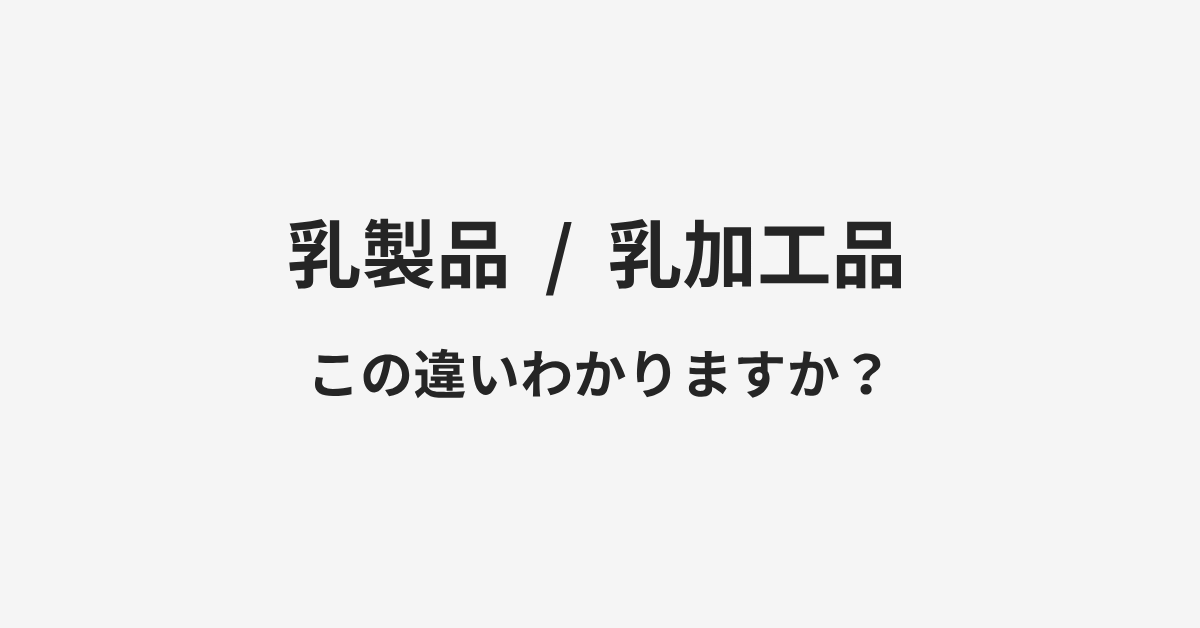【根菜】と【根もの】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
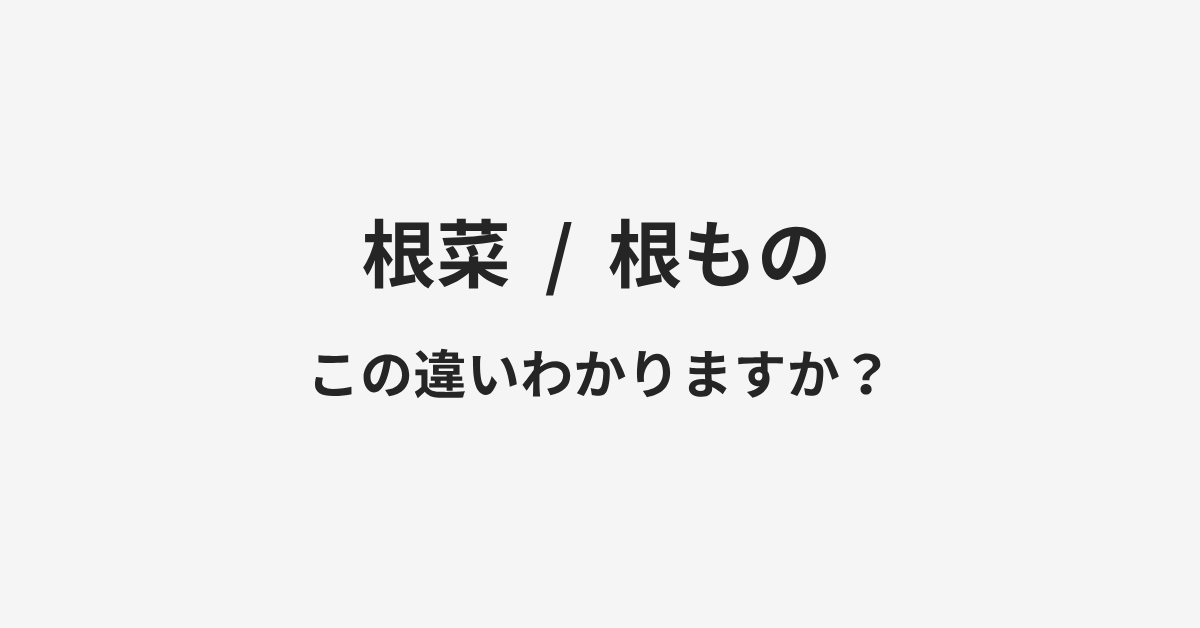
根菜と根ものの分かりやすい違い
根菜は、大根やニンジンなど、根や地下の部分を食べる野菜の正式な名前です。
根ものは、根菜と同じ意味ですが、より親しみやすい俗称で、地域によって使われます。
根菜は正式名称・標準語、根ものは俗称・方言的という違いがあります。
根菜とは?
根菜とは、主に根や地下茎、球根など、土の中で育つ部分を食用とする野菜の総称です。大根、ニンジン、ゴボウ、レンコン、サトイモ、ジャガイモ、サツマイモなどが代表的で、日本料理に欠かせない食材群です。根菜類とも呼ばれ、最も一般的に使用される正式名称です。
根菜の特徴は、でんぷん質や食物繊維が豊富で、保存性が高いことです。体を温める効果があるとされ、特に冬場の煮物や汁物に重用されます。根菜の煮物、根菜サラダ、根菜チップスなど、様々な調理法で楽しまれ、腸内環境改善にも効果的とされています。
栄養学的には、根菜は糖質を多く含むものの、食物繊維も豊富で血糖値の急上昇を抑える効果があります。また、土の中で育つため、ミネラル分も豊富で、健康的な食生活に欠かせない野菜群として位置づけられています。
根菜の例文
- ( 1 ) 根菜たっぷりの豚汁を作りました。
- ( 2 ) 根菜は体を温める効果があるそうです。
- ( 3 ) 根菜の皮にも栄養があるので、よく洗って使います。
- ( 4 ) 秋冬は根菜が美味しい季節です。
- ( 5 ) 根菜を使った精進料理を習っています。
- ( 6 ) 根菜類の保存方法を工夫しています。
根菜の会話例
根ものとは?
根ものとは、根菜と同じく地下部分を食べる野菜を指す俗称・通称です。主に関西地方や市場関係者、年配の方々の間で使われることが多く、根もの野菜、今日は根ものが安いなどの表現で用いられます。親しみやすさと温かみのある表現として愛用されています。
根ものという呼び方は、八百屋さんや市場での会話、家庭での日常会話で聞かれることがあり、地域性や世代による言葉の違いを感じさせます。根ものは日持ちがする、根ものを入れると煮物が美味しくなるなど、生活に密着した使い方がされています。
ただし、根ものは標準的な用語ではないため、レシピ本や栄養指導などの公的な場面では使用されません。若い世代にはあまり馴染みがない言葉でもあり、地域や世代によって通じない場合もあります。
根ものの例文
- ( 1 ) 今日は根ものが特売やで。
- ( 2 ) 根もの入れたら、煮物に深みが出るんや。
- ( 3 ) うちのおばあちゃんは、根もの料理が得意です。
- ( 4 ) 市場で新鮮な根ものを仕入れてきました。
- ( 5 ) 根ものは日持ちするから、買い置きに便利やね。
- ( 6 ) 冬は根ものの煮っころがしが美味しいです。
根ものの会話例
根菜と根ものの違いまとめ
根菜は正式で標準的な名称、根ものは親しみやすいが地域的な俗称という違いがあります。料理本では根菜、八百屋さんでは根ものというように、場面により使い分けられることがあります。
ただし、一般的には根菜を使用すれば、どこでも確実に通じます。
現代では根菜が圧倒的に一般的で、根ものは限定的な使用にとどまっています。
根菜と根ものの読み方
- 根菜(ひらがな):こんさい
- 根菜(ローマ字):konsai
- 根もの(ひらがな):ねもの
- 根もの(ローマ字):nemono