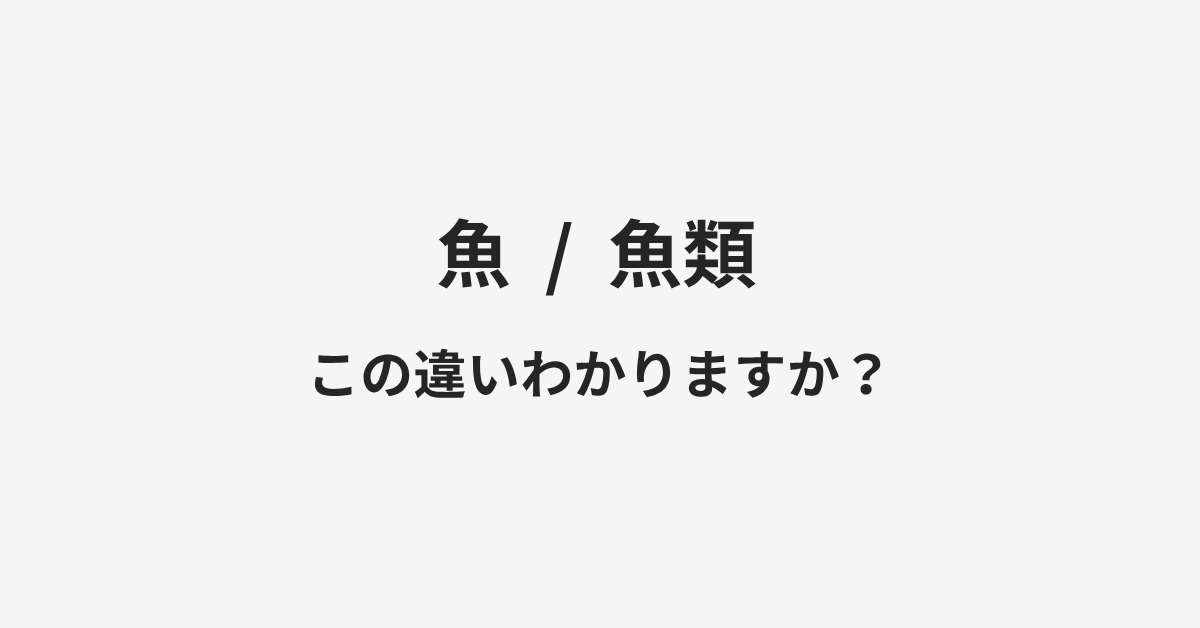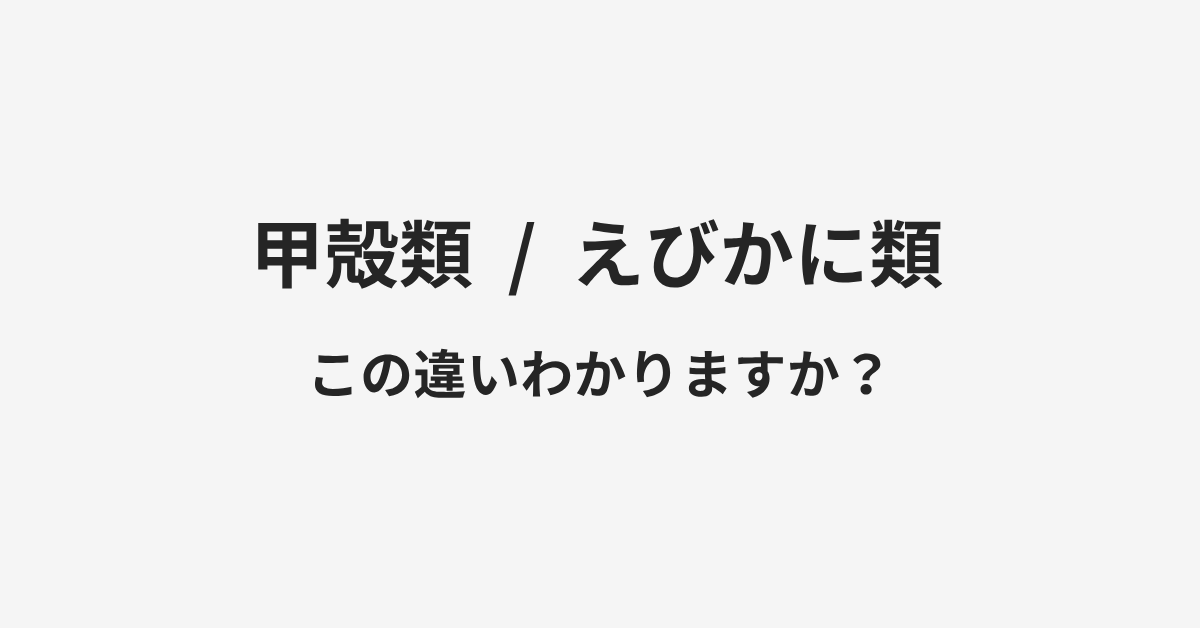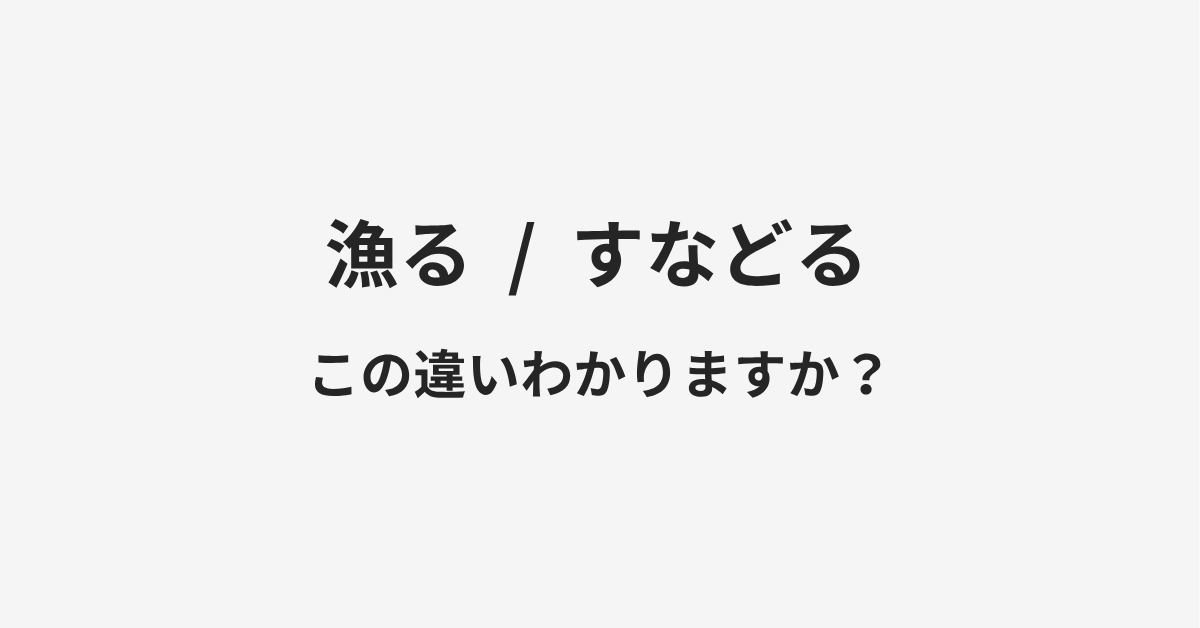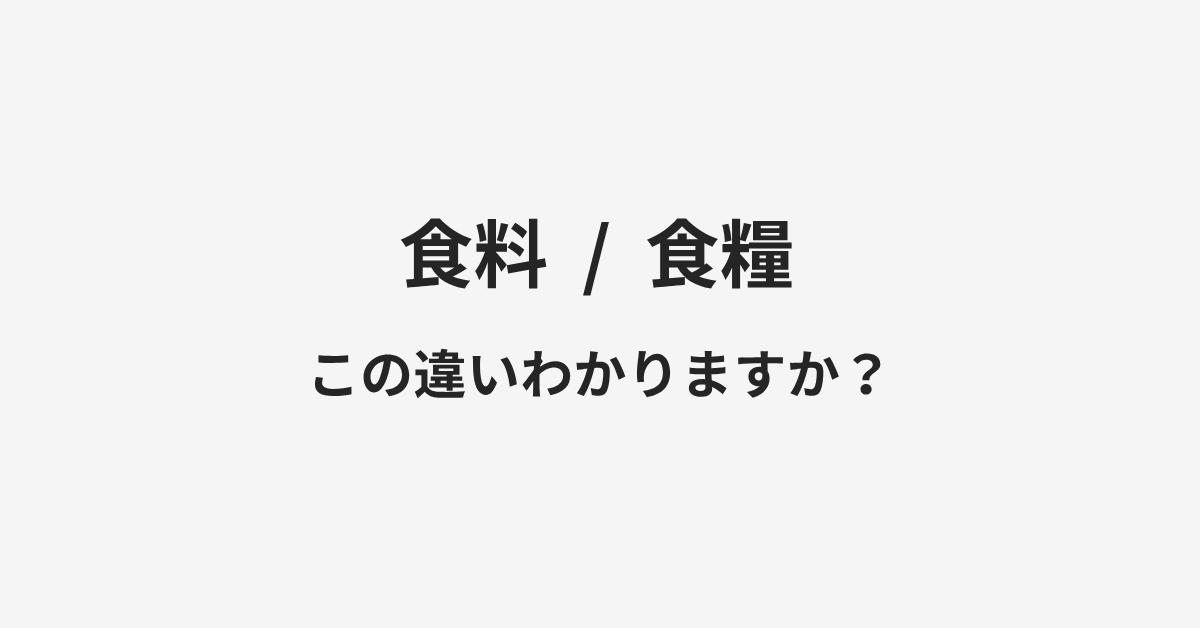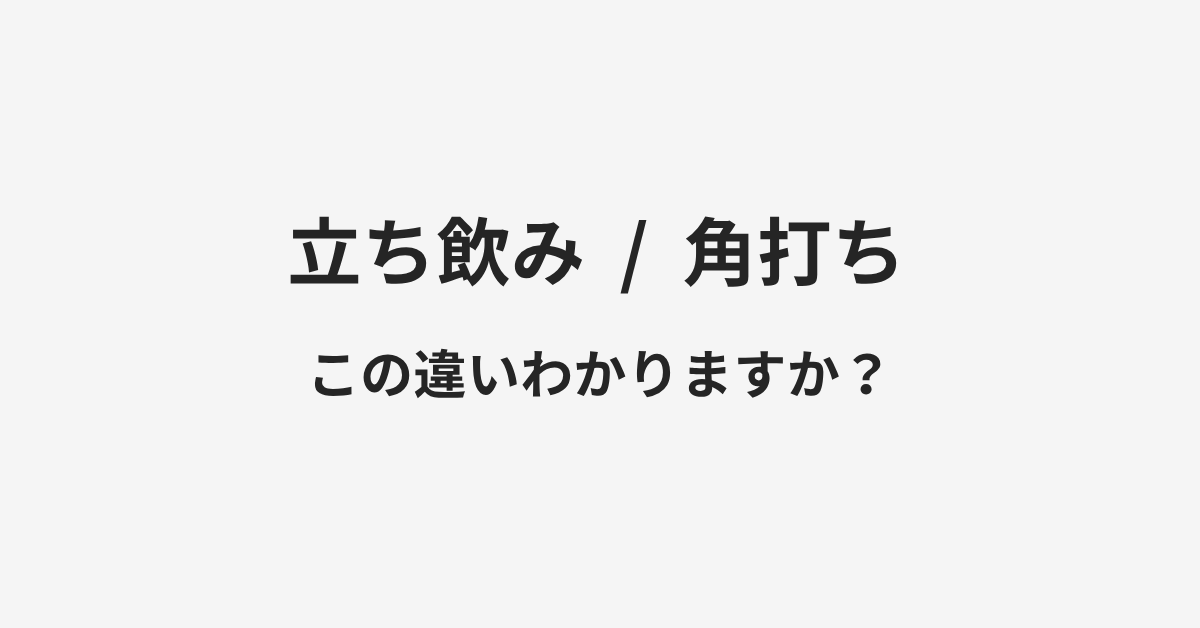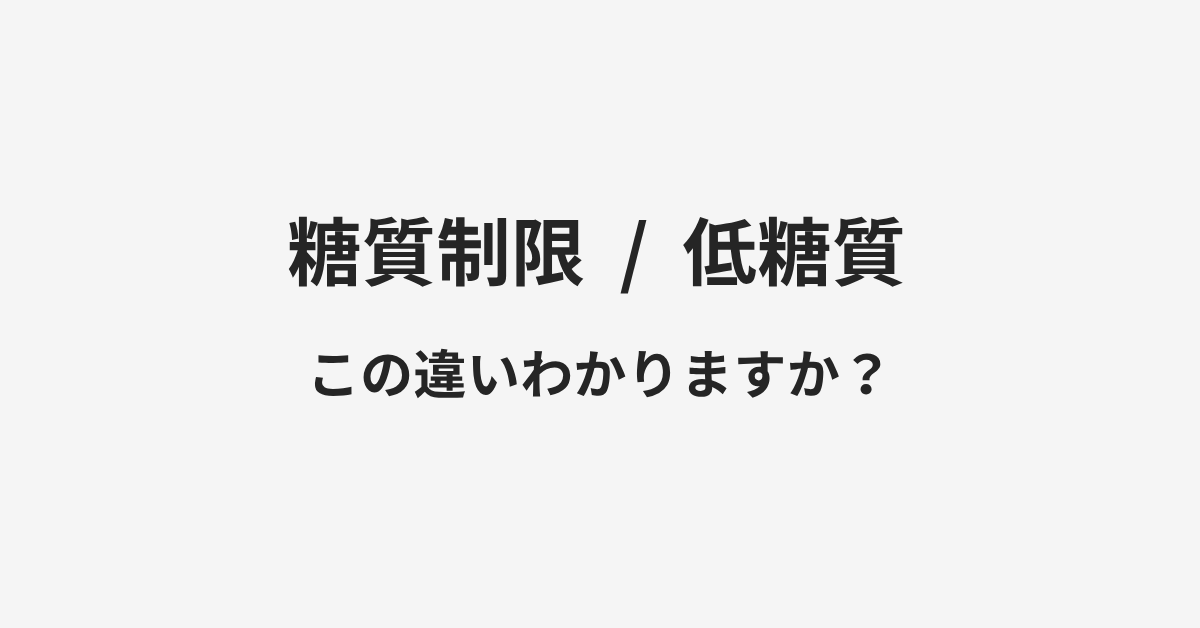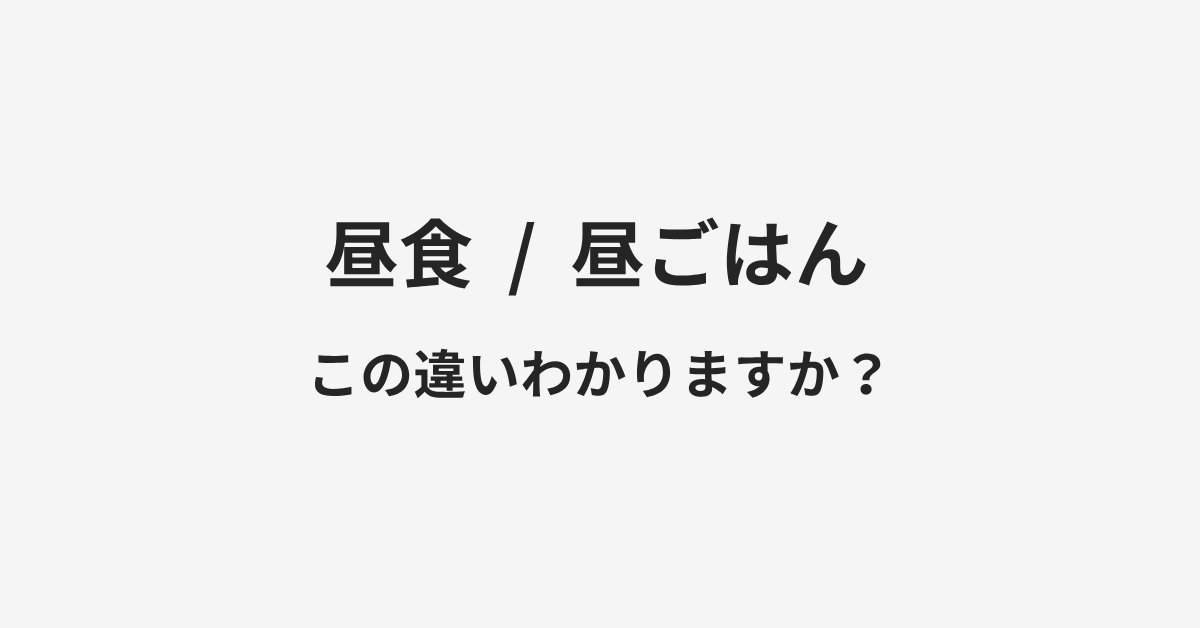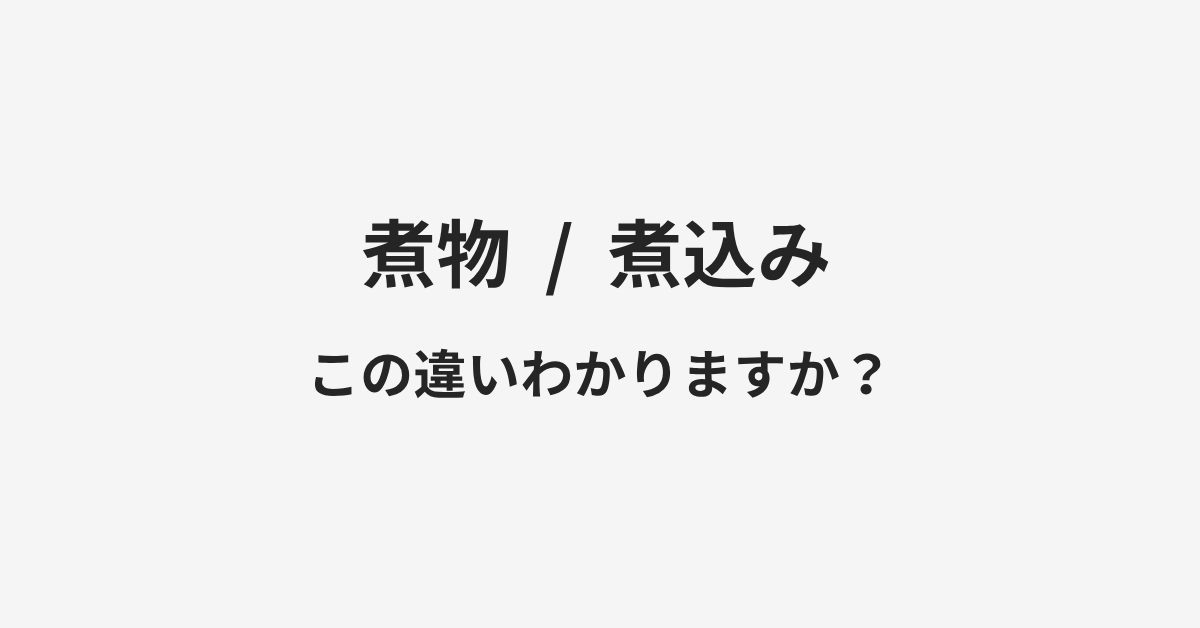【貝類】と【貝】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
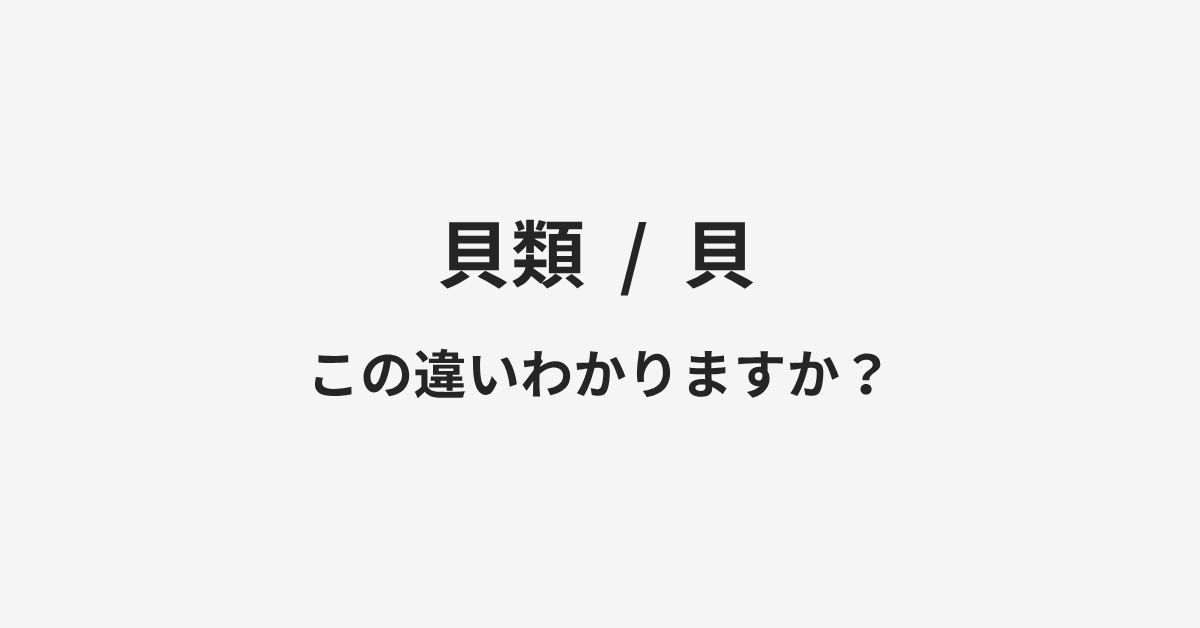
貝類と貝の分かりやすい違い
貝類は、アサリやカキなど貝の仲間全体を指す、生物学的な分類の言葉です。
貝は、個々の貝や食材としての貝を指す、日常的に使われる一般的な言葉です。
貝類は分類群・学術語、貝は個体・日常語という違いがあります。
貝類とは?
貝類とは、軟体動物門に属する、貝殻を持つ動物の総称で、二枚貝類(アサリ、シジミ、カキ、ホタテ)、巻貝類(サザエ、アワビ、バイ貝)などを含む生物学的分類群です。貝類の養殖、貝類アレルギー、貝類の栄養など、学術的・産業的な文脈で使用される専門用語です。
貝類は、良質なタンパク質、タウリン、亜鉛、鉄分、ビタミンB12などを豊富に含む栄養価の高い食材群です。また、水質浄化作用があることから、環境指標生物としても重要視されています。貝類毒のように、食品安全の観点からも注意が必要な分類群です。
水産統計や食品表示では貝類という表記が正式に使用され、貝類加工品、貝類の漁獲量など、産業や行政の文書でも標準的に用いられます。ただし、日常会話では堅い印象を与えることがあります。
貝類の例文
- ( 1 ) 貝類の養殖技術について学んでいます。
- ( 2 ) 貝類アレルギーの方は注意が必要です。
- ( 3 ) 日本近海の貝類は種類が豊富です。
- ( 4 ) 貝類の水質浄化能力は環境保護に役立ちます。
- ( 5 ) 貝類加工品の輸出が増加しています。
- ( 6 ) 貝類に含まれるタウリンは肝機能に良いそうです。
貝類の会話例
貝とは?
貝とは、貝殻を持つ軟体動物の個体や、食材としての貝を指す日常的な言葉です。貝を拾う、貝を食べる、貝の味噌汁など、具体的な個体や料理を表現する際に最も一般的に使用されます。アサリ、シジミ、ハマグリなど、親しみやすい食材としてのイメージが強い言葉です。
日本では、潮干狩りで貝を採る文化があり、季節の風物詩として親しまれています。貝は、酒蒸し、味噌汁、パスタ、炊き込みご飯など、多彩な料理に使われ、独特の旨味と食感が楽しめます。貝柱、貝ひもなど、部位による呼び名もあります。
また、貝殻は装飾品や工芸品の材料としても利用され、貝細工、貝塚など、文化的な側面も持ちます。子どもから大人まで親しみやすい、日本の食文化に深く根付いた言葉です。
貝の例文
- ( 1 ) 潮干狩りで貝をたくさん採りました。
- ( 2 ) 新鮮な貝で酒蒸しを作ります。
- ( 3 ) 貝の砂抜きは、塩水で行います。
- ( 4 ) この貝、身がぷりぷりで美味しそう!
- ( 5 ) 貝殻を集めるのが趣味です。
- ( 6 ) 貝の旨味がよく出たお吸い物です。
貝の会話例
貝類と貝の違いまとめ
貝類は分類学的な総称、貝は個体や食材を指す日常語という違いがあります。研究論文では貝類の生態、スーパーでは新鮮な貝というように、学術と日常で使い分けられます。
すべての貝は貝類に属しますが、貝類という表現は個々の貝を指すには適しません。
一般的な会話では貝、専門的な文脈では貝類を使うことで、適切な表現ができます。
貝類と貝の読み方
- 貝類(ひらがな):かいるい
- 貝類(ローマ字):kairui
- 貝(ひらがな):かい
- 貝(ローマ字):kai