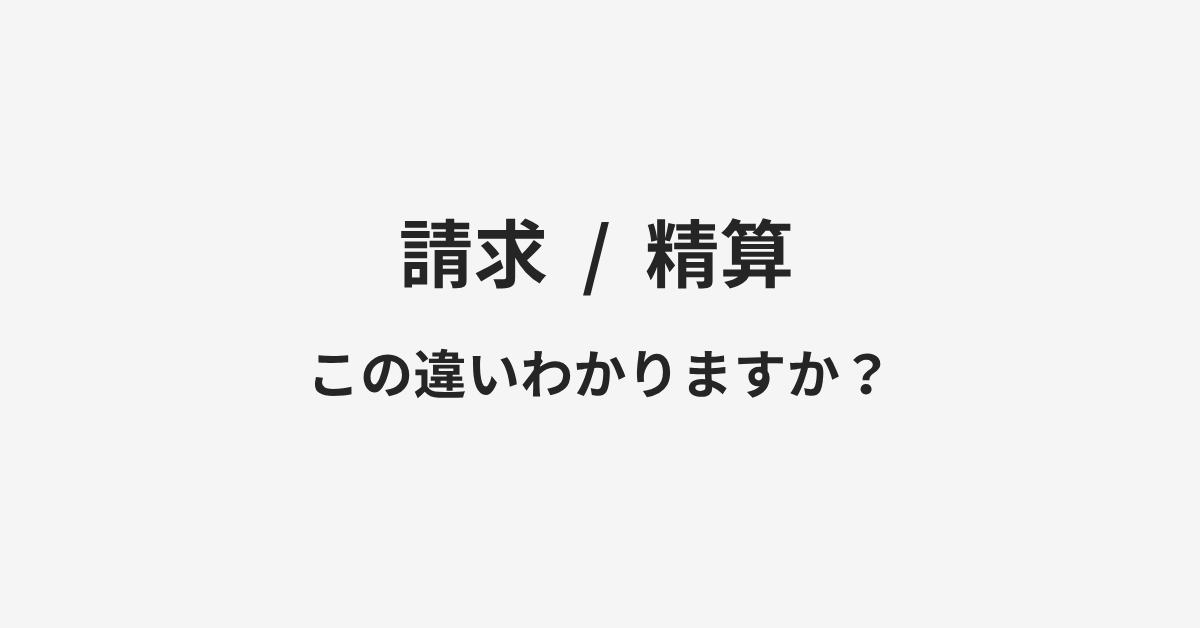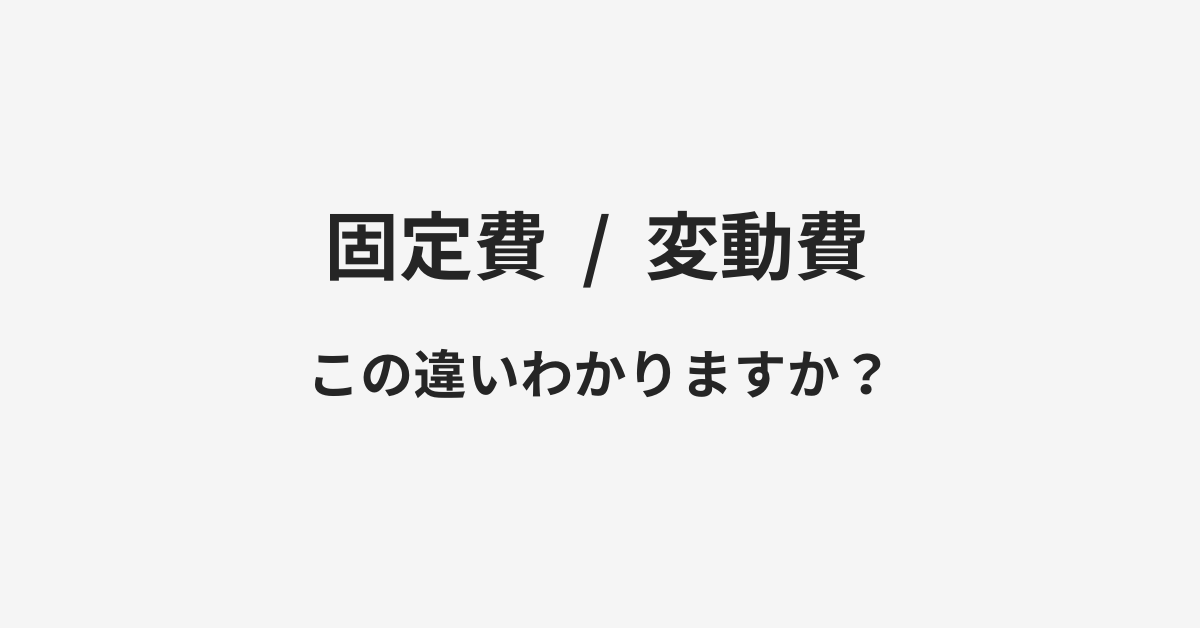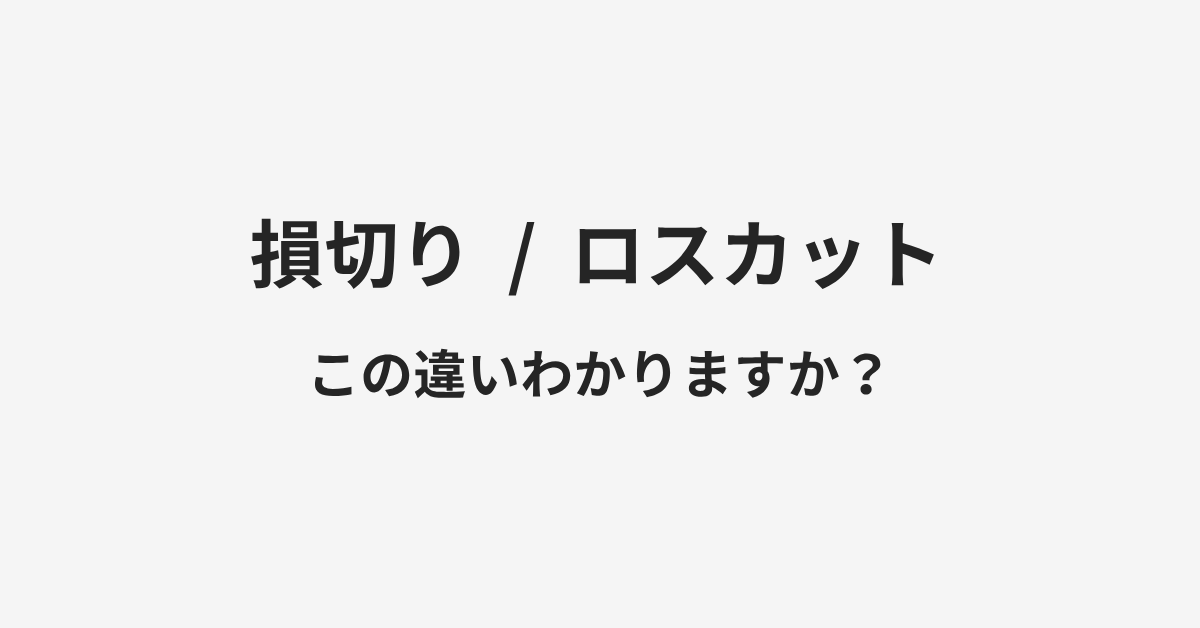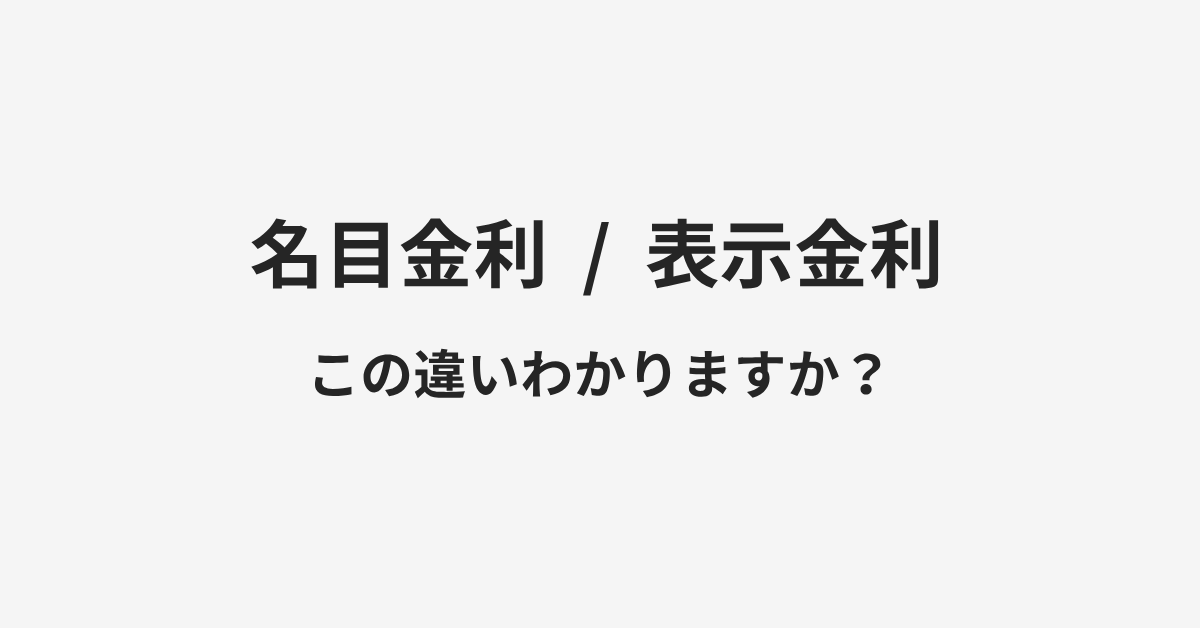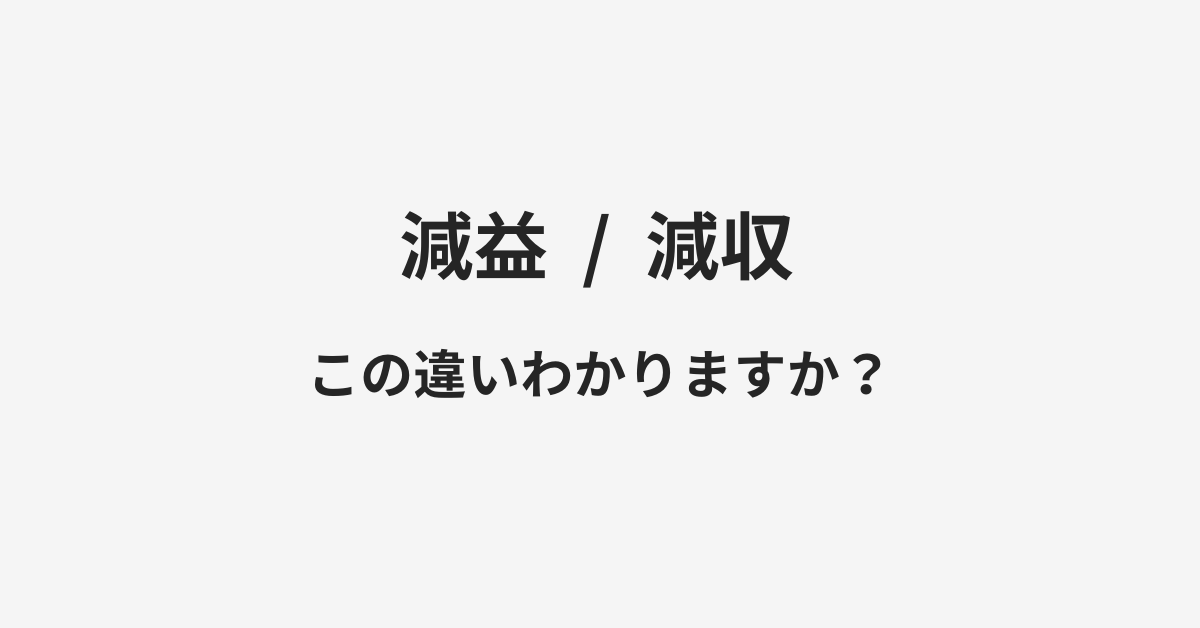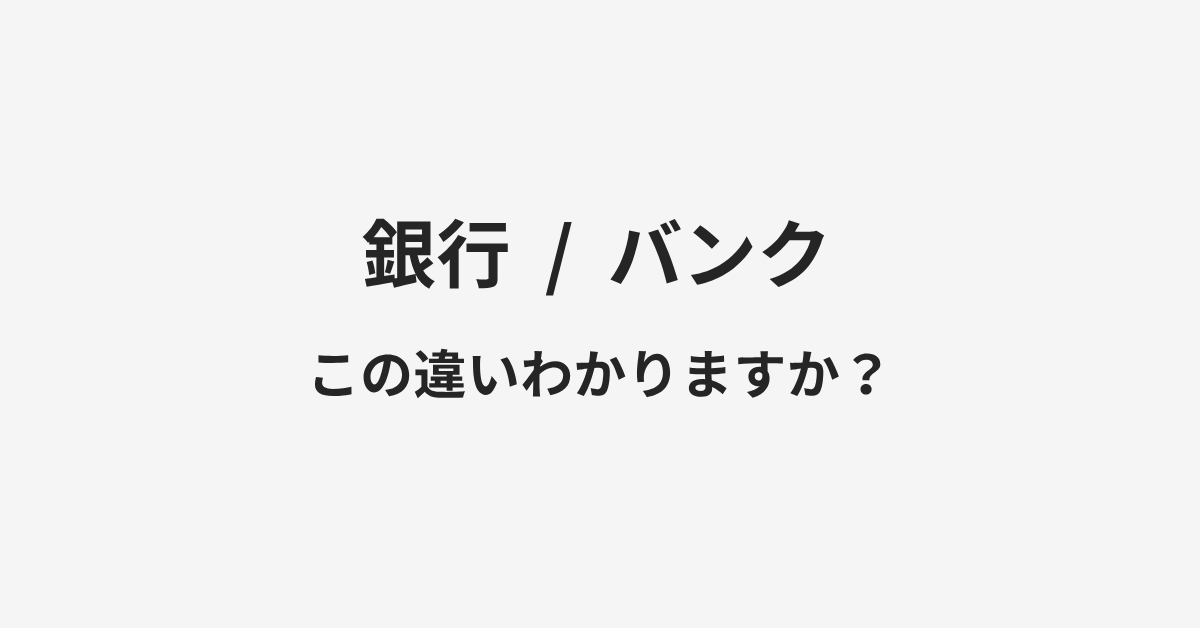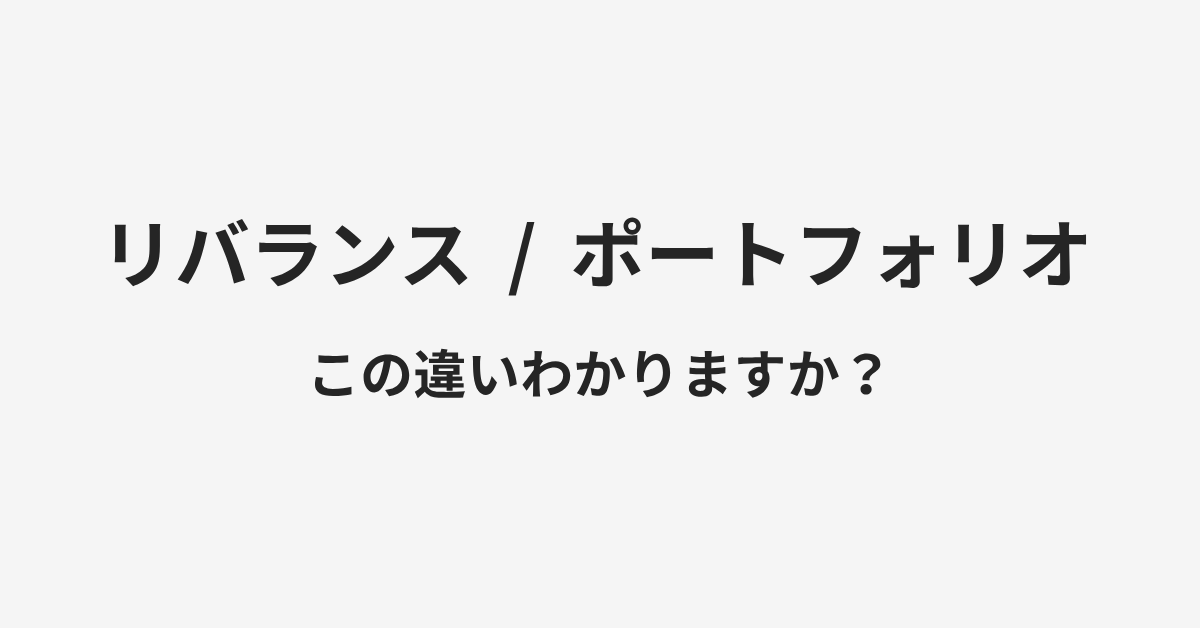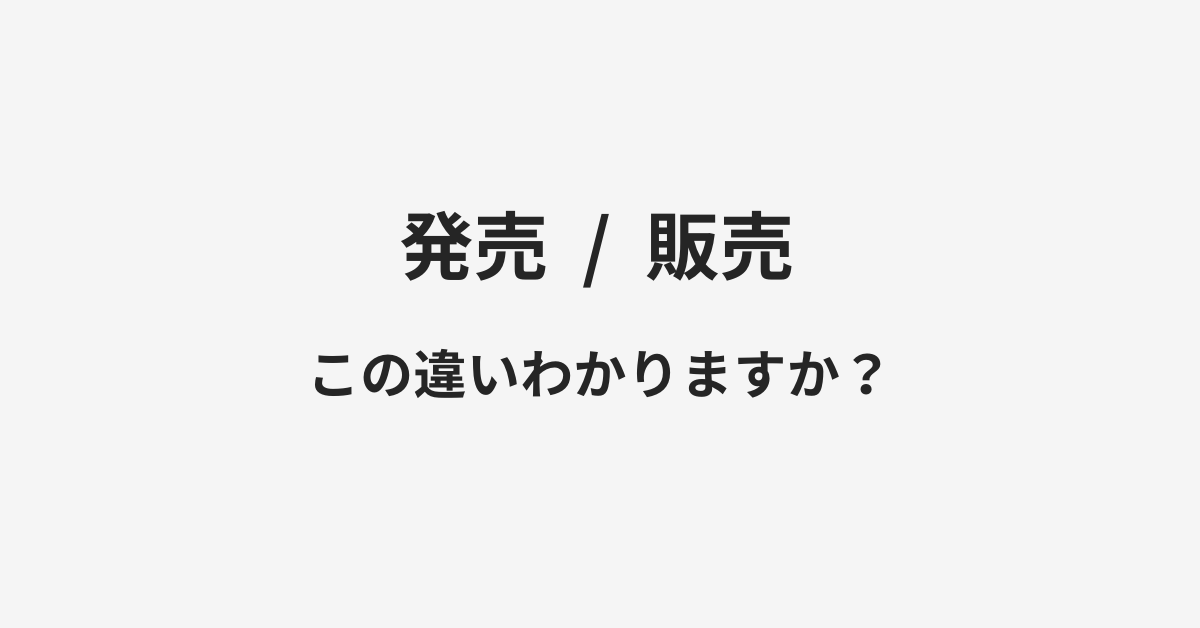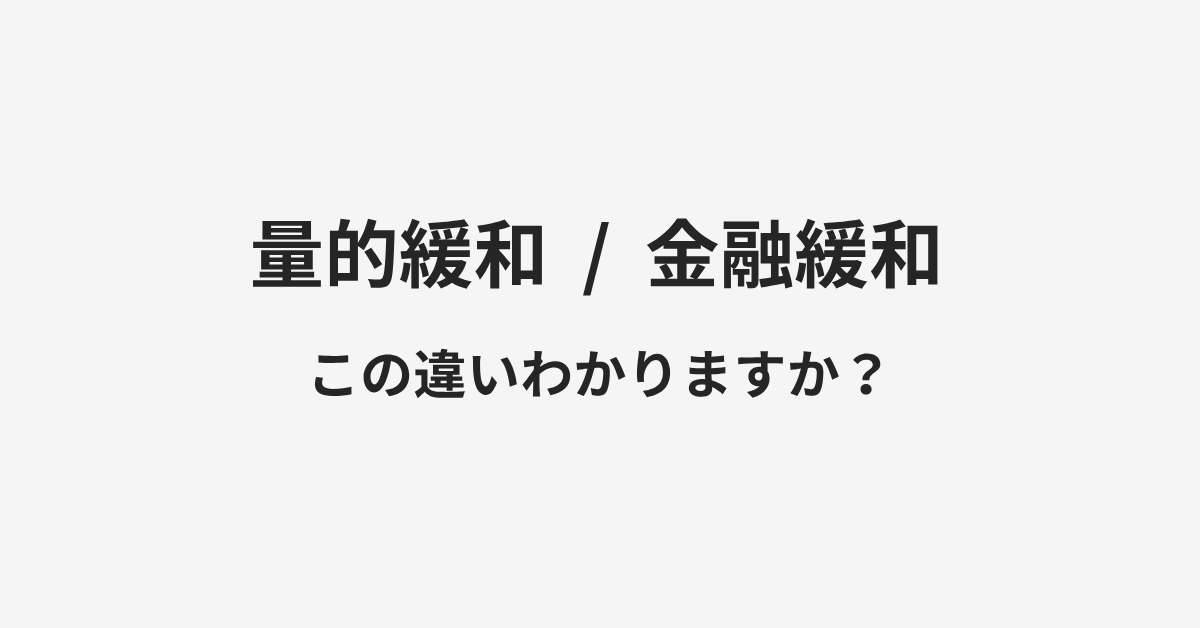【未払金】と【未払費用】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
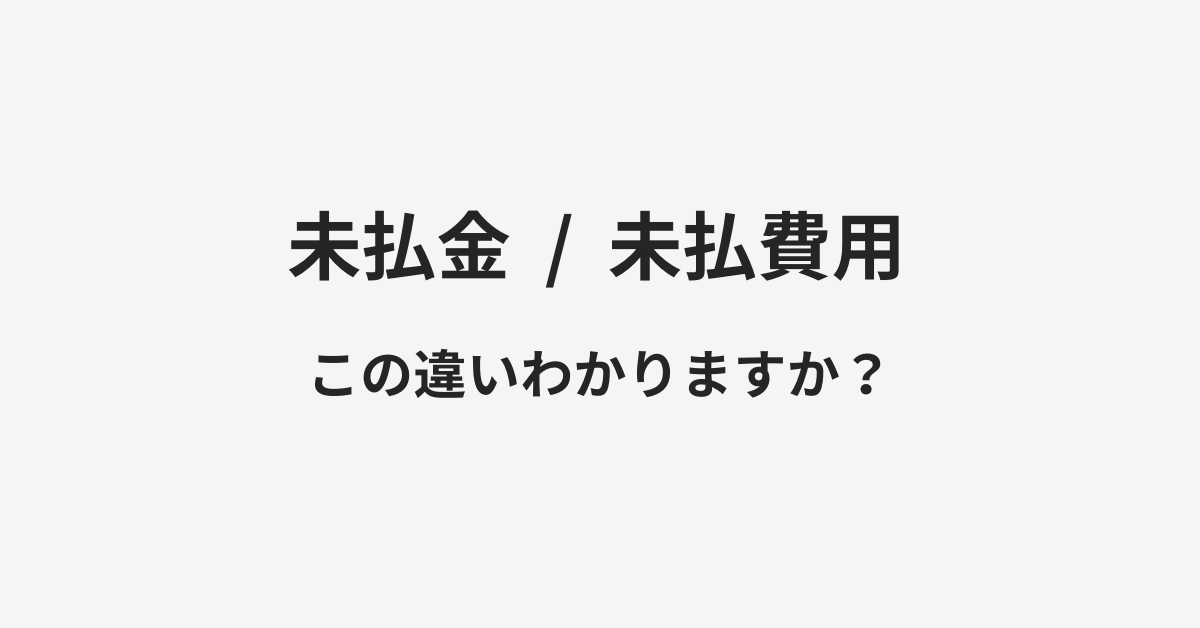
未払金と未払費用の分かりやすい違い
未払金と未払費用は、どちらも支払いがまだ済んでいない債務ですが、発生の仕組みが異なります。
未払金は買い物などで金額が確定した支払い、未払費用は給料や利息など時間とともに発生する支払いです。
請求書が来ているものは未払金、月末締めで計算するものは未払費用と覚えましょう。
未払金とは?
未払金とは、物品の購入やサービスの提供を受けた際に発生する債務で、すでに金額が確定しているが、まだ支払っていないものを指します。例えば、事務用品を購入して請求書を受け取ったが、支払期日が来月の場合、その金額は未払金として計上されます。取引先との契約に基づいて発生し、通常は請求書や納品書などの証憑(しょうひょう:取引を証明する書類)があります。
会計処理では、商品やサービスを受け取った時点で費用/未払金という仕訳を行います。未払金は貸借対照表の流動負債に計上され、通常は1年以内に支払われます。企業の資金繰りを考える上で重要な項目で、支払いサイト(支払いまでの期間)の管理が財務戦略上重要になります。
未払金の管理を適切に行うことで、キャッシュフローの最適化が可能です。ただし、支払いを遅延させると信用を失い、今後の取引に影響する可能性があるため、計画的な支払い管理が必要です。
未払金の例文
- ( 1 ) オフィス家具を50万円で購入し、翌月払いとしたため未払金に計上しました。
- ( 2 ) コンサルティング費用の請求書が届いたので、未払金として処理しています。
- ( 3 ) 月次決算で未払金の残高を確認し、支払い漏れがないかチェックしています。
- ( 4 ) システム開発費300万円を未払金に計上し、3ヶ月の分割払いで契約しました。
- ( 5 ) 未払金の年齢調べ(滞留期間分析)を実施し、長期未払いがないか確認しています。
- ( 6 ) 税務調査で未払金の計上基準について質問され、社内規程を説明しました。
未払金の会話例
未払費用とは?
未払費用とは、継続的な契約に基づいて時間の経過とともに発生する費用のうち、決算日時点でまだ支払っていない部分を指します。代表的なものに、従業員の給与(締め日から月末までの分)、借入金の利息、家賃、保険料などがあります。これらは日々発生していますが、支払いは後日まとめて行われるため、決算時に未払い分を計算して計上します。
未払費用は発生主義という会計原則に基づいて計上されます。つまり、現金の支払いがなくても、費用が発生した期間に計上する必要があります。例えば、3月決算の会社で、3月分の給与を4月に支払う場合、3月31日時点で3月分の給与を未払費用として計上します。
決算時には、各種契約書や計算根拠を基に未払費用を正確に見積もる必要があります。これにより、その期の正しい利益を計算でき、財務諸表の信頼性が確保されます。税務調査でも重要なチェック項目となるため、適切な計上が求められます。
未払費用の例文
- ( 1 ) 3月分の給与は4月25日支払いのため、3月31日に未払費用として計上します。
- ( 2 ) 借入金の利息は日割り計算で未払費用に計上する必要があります。
- ( 3 ) 社会保険料の会社負担分も、月末時点で未払費用として認識しています。
- ( 4 ) 決算時に未払費用の計算書を作成し、監査法人のチェックを受けています。
- ( 5 ) 賞与引当金と異なり、確定した賞与の未払い分は未払費用に計上します。
- ( 6 ) 水道光熱費の検針日と決算日のずれによる未払費用も忘れずに計上しています。
未払費用の会話例
未払金と未払費用の違いまとめ
未払金と未払費用は、どちらも将来支払う債務ですが、性質が異なります。未払金は取引完了後の確定債務、未払費用は時間経過により発生する見積債務です。
経理実務では、請求書があるものは未払金、期間計算が必要なものは未払費用として区別します。
両者を正しく区分して計上することで、正確な財務諸表の作成と適切な資金繰り管理が可能になります。
未払金と未払費用の読み方
- 未払金(ひらがな):みはらいきん
- 未払金(ローマ字):miharaikinn
- 未払費用(ひらがな):みはらいひよう
- 未払費用(ローマ字):miharaihiyo