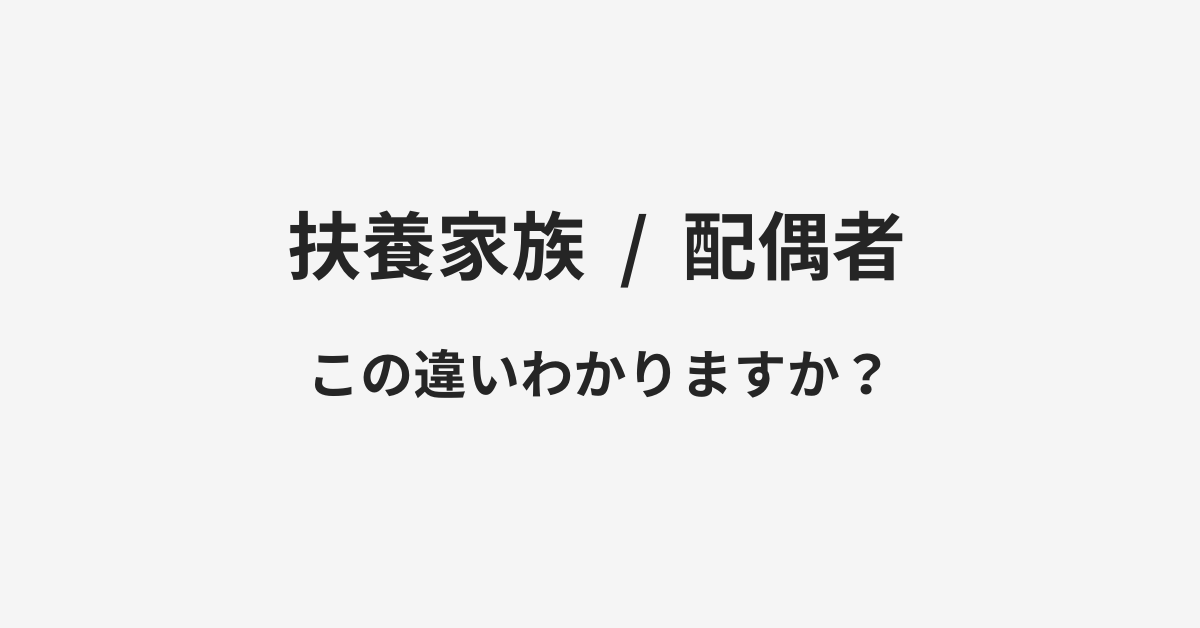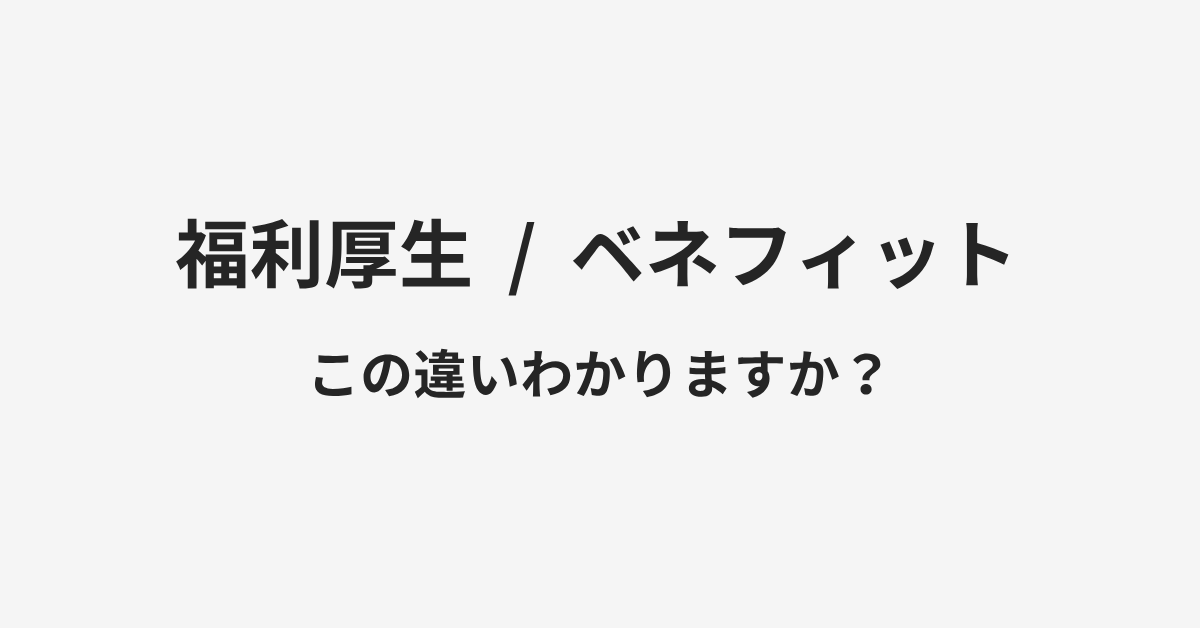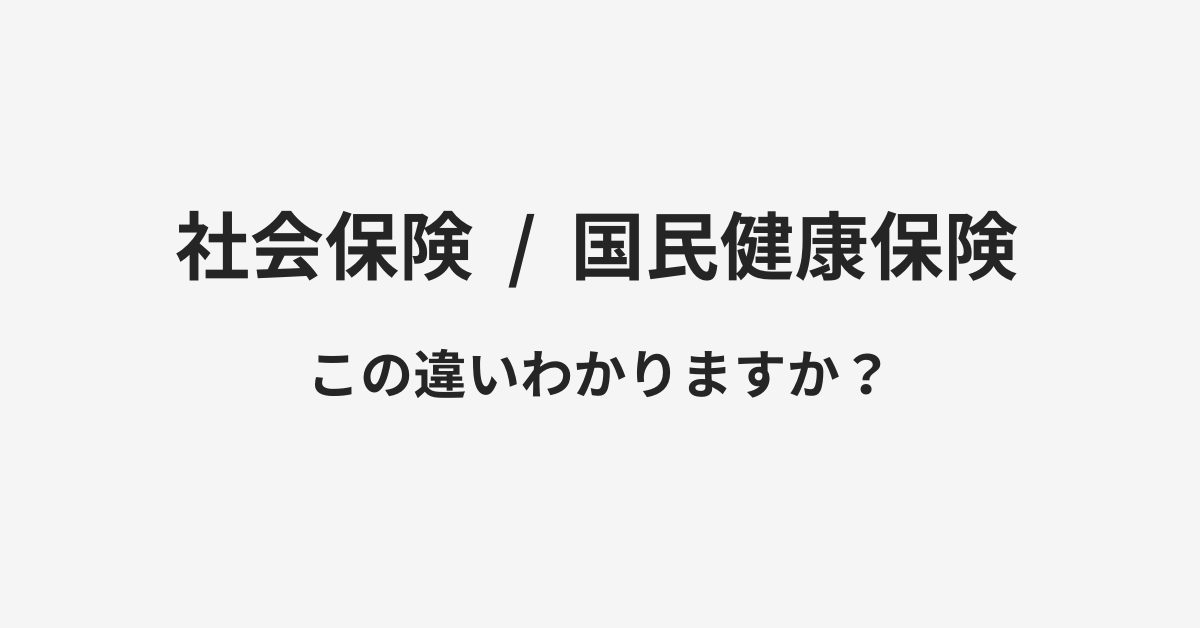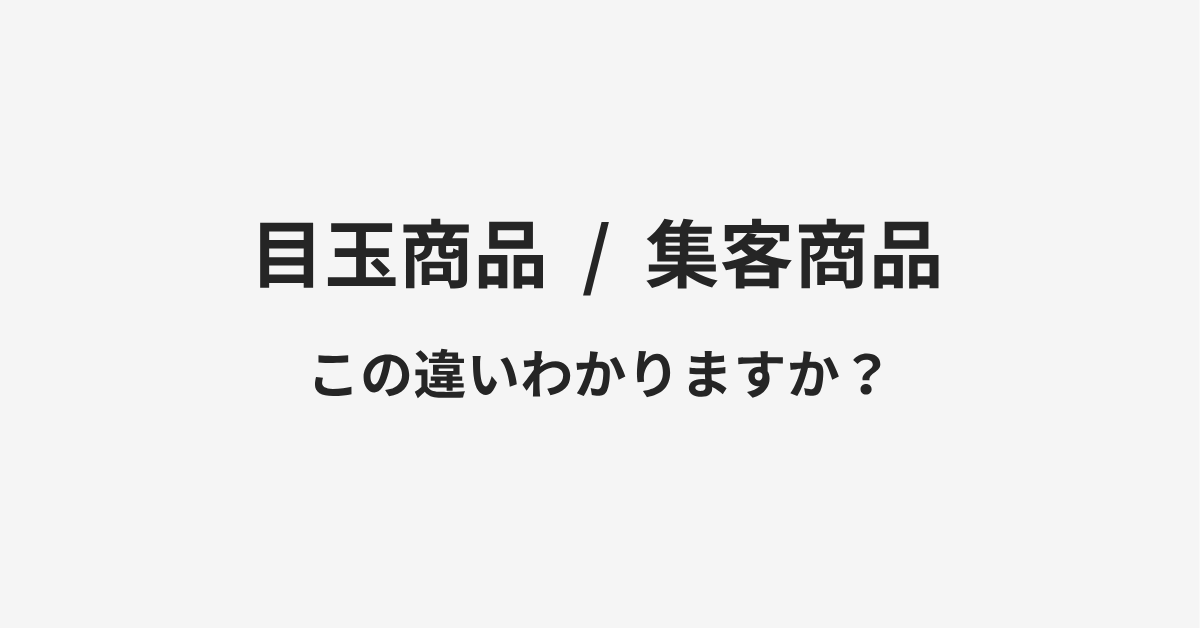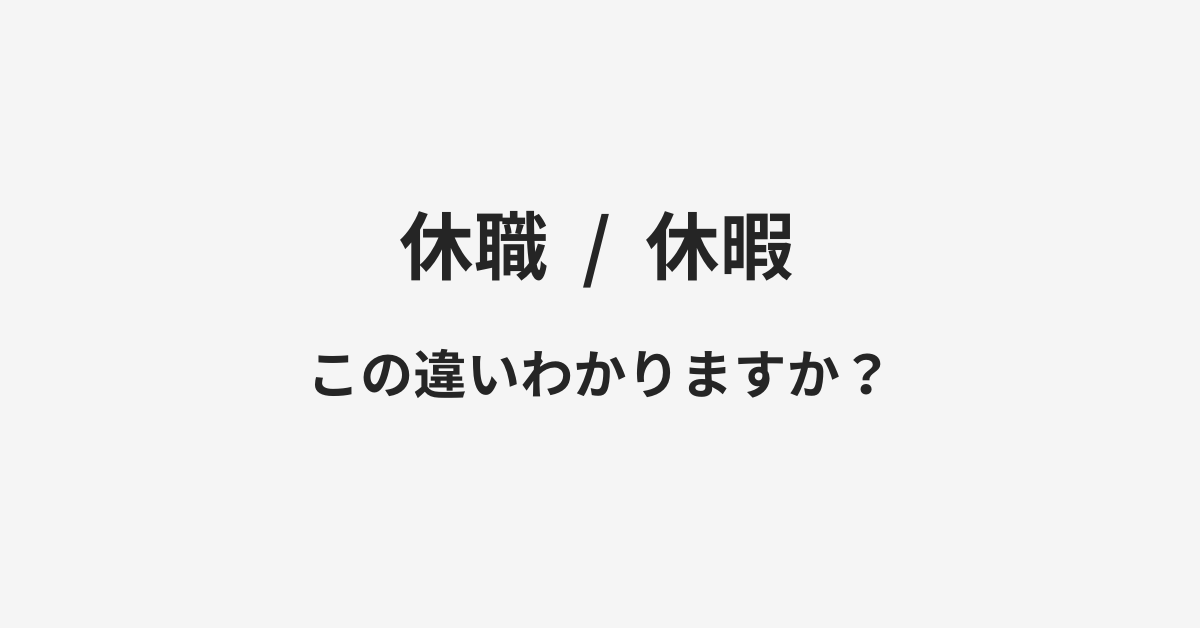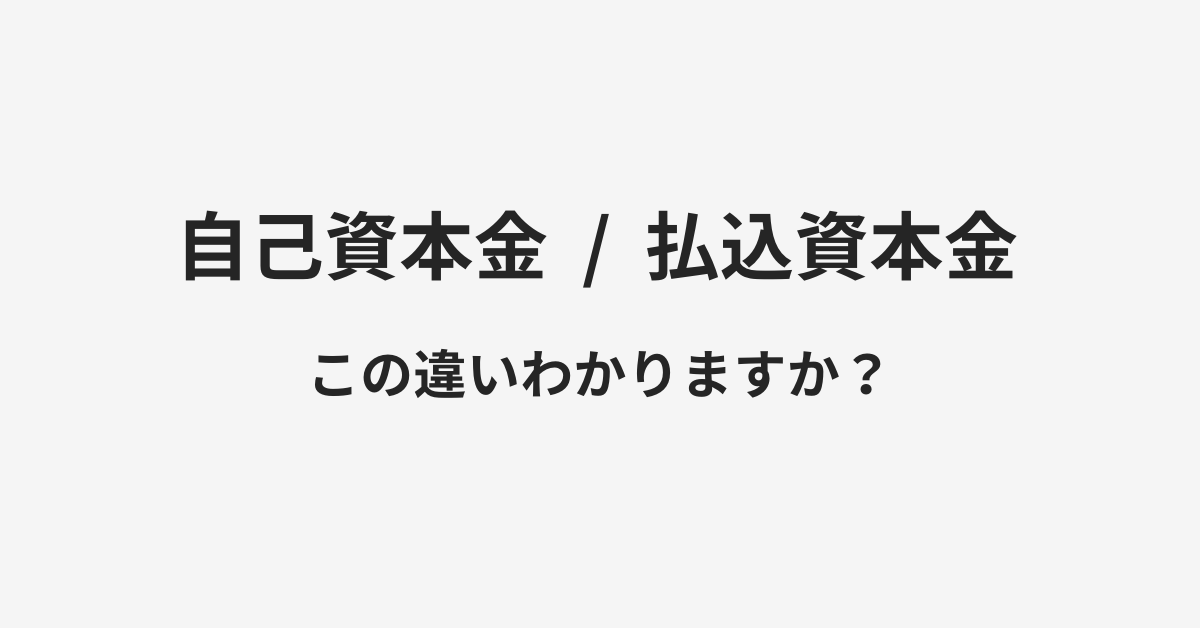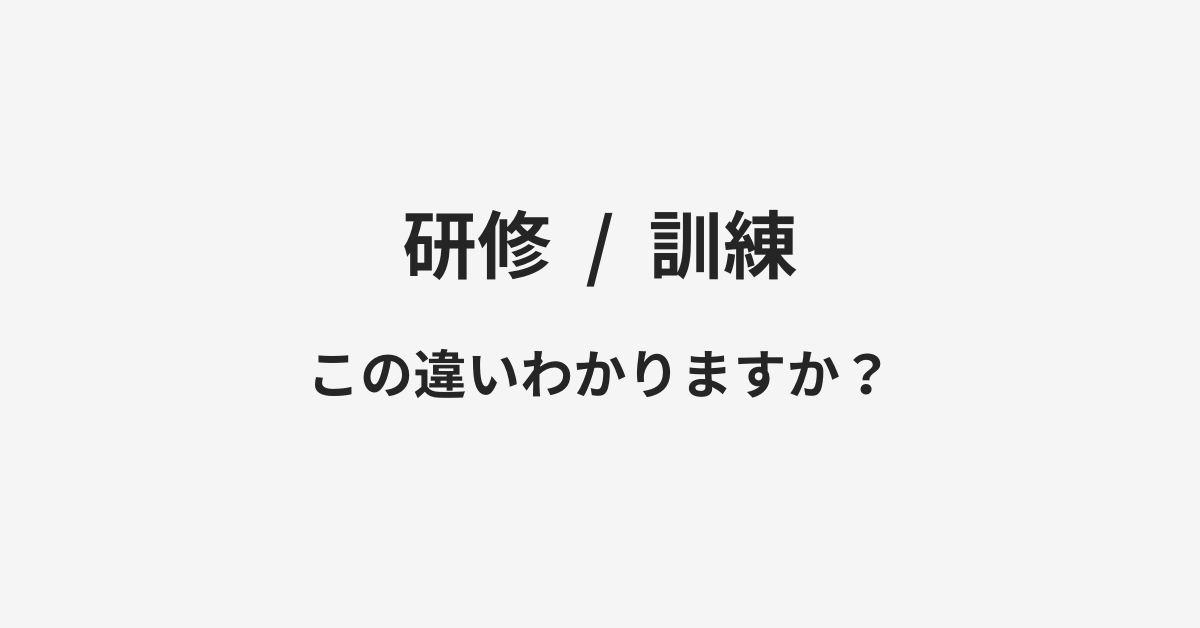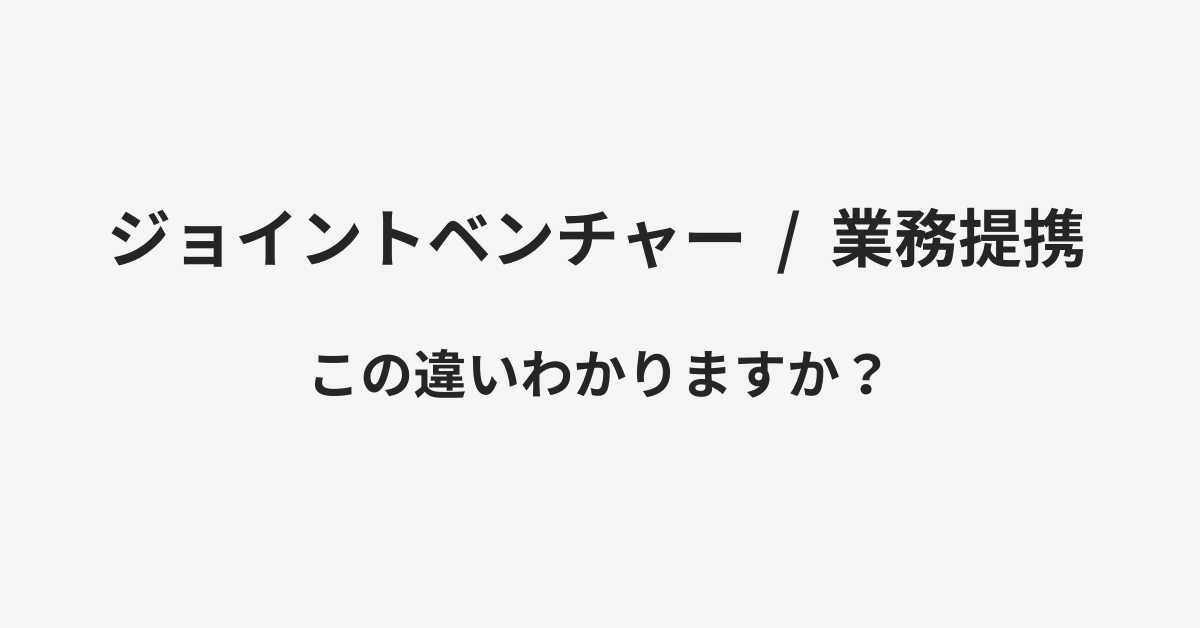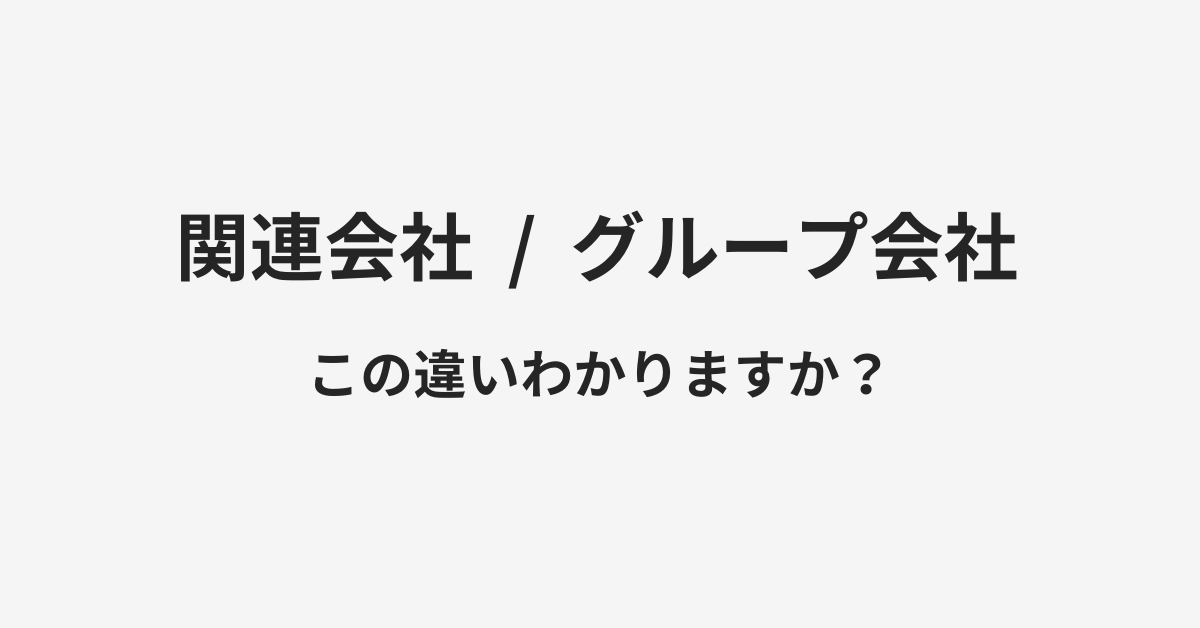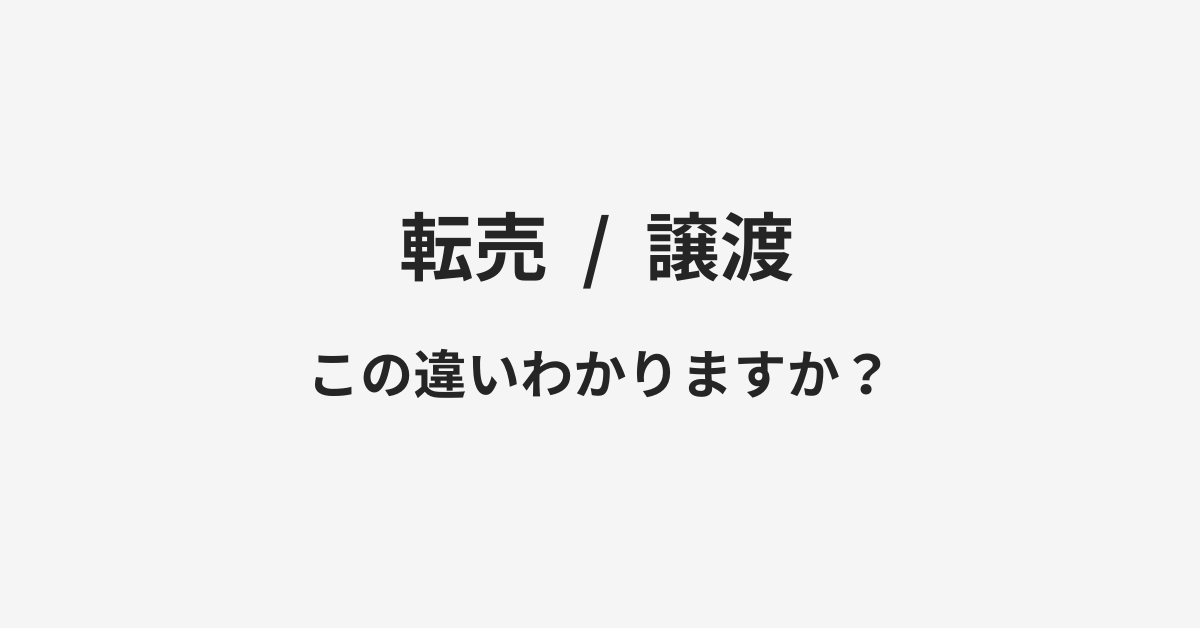【生計維持】と【生計同一】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
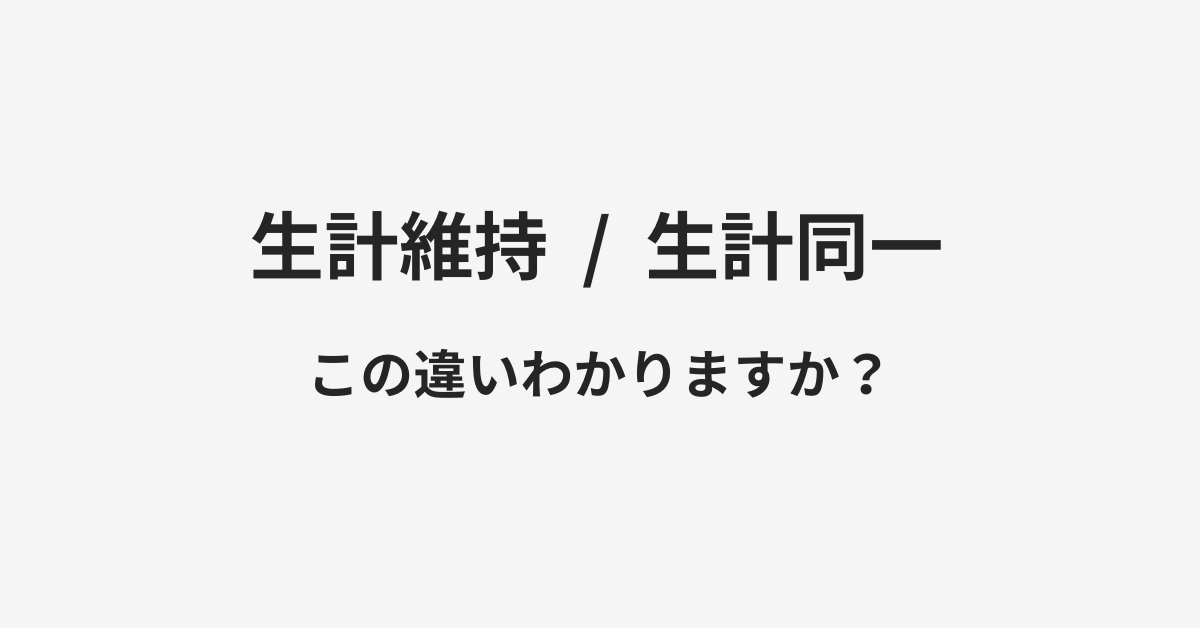
生計維持と生計同一の分かりやすい違い
生計維持と生計同一は、どちらも家族の経済関係を表す言葉ですが、その意味と適用場面が異なります。生計維持は、ある人が他の人の生活費を主に負担している関係を指します。
一方、生計同一は、同じ財布で生活している、つまり家計を共にしている関係を意味します。企業の人事・労務管理では、健康保険の扶養認定や各種手当の支給判定において、この2つの概念を正確に理解し、適切に運用することが求められます。
生計維持とは?
生計維持とは、ある人が他の人の生活に必要な経済的支援を継続的に行い、その人の生計を成り立たせている関係を指します。健康保険や厚生年金の被扶養者認定、税法上の扶養控除の判定などで重要な要件となります。主たる生計維持者が家族の生活費の大部分を負担している状態を表します。生計維持関係の認定では、収入の有無や金額が重要な判断基準となります。
例えば、健康保険の被扶養者認定では、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることが条件となります。別居していても仕送りで生活を支えていれば生計維持関係が認められます。
企業の人事部門では、従業員の家族手当支給や社会保険の扶養認定において、生計維持関係の確認が必要です。給与明細、送金証明、通帳コピーなどの書類により、実態を確認することが重要です。適切な判定により、従業員の福利厚生の適正な運用が可能となります。
生計維持の例文
- ( 1 ) 妻がパート収入を得ていますが、私が主な生計維持者として家族を支えています。
- ( 2 ) 大学生の子供の学費と生活費を負担しており、生計維持関係にあります。
- ( 3 ) 別居している両親に毎月仕送りをしており、生計維持の実態があります。
- ( 4 ) 健康保険の被扶養者認定のため、生計維持関係を証明する書類を提出しました。
- ( 5 ) 育児休業中の妻も、私が生計維持することで被扶養者として認定されました。
- ( 6 ) 生計維持者である私が万一の時のため、生命保険を増額しました。
生計維持の会話例
生計同一とは?
生計同一とは、日常生活において家計を共にしている関係を指します。必ずしも同居している必要はなく、生活費を共通の財布から支出している実態があれば生計同一と認められます。遺族年金の受給要件、生活保護の世帯認定、各種給付金の支給判定などで用いられる概念です。生計同一の判定では、住民票上の世帯が同じかどうかだけでなく、実際の生活実態が重視されます。
例えば、単身赴任で別居していても、生活費を同一の家計から支出していれば生計同一と認められます。逆に、同居していても家計が完全に分離していれば生計同一とは認められません。
企業実務では、慶弔規程の適用範囲や、社宅入居資格の判定などで生計同一の概念が使われます。また、従業員が死亡した場合の遺族年金請求においても、生計同一関係の証明が必要となります。光熱費の領収書、家計簿、預金通帳などにより実態を確認することが重要です。
生計同一の例文
- ( 1 ) 単身赴任中ですが、家族とは生計同一の関係を維持しています。
- ( 2 ) 同居している義母とは生計同一であるため、世帯として各種申請を行います。
- ( 3 ) 別居の大学生の子供も、仕送りで生活しているので生計同一と認定されました。
- ( 4 ) 生計同一の証明のため、光熱費の支払い記録を保管しています。
- ( 5 ) 遺族年金の申請において、生計同一関係の証明書類を準備しています。
- ( 6 ) 二世帯住宅ですが、家計は一つなので生計同一世帯として扱われます。
生計同一の会話例
生計維持と生計同一の違いまとめ
生計維持と生計同一の最大の違いは、経済的依存関係の有無です。生計維持は支える側と支えられる側という上下関係があり、生計同一は対等な家計共同体を形成している関係です。実務上の使い分けとして、健康保険の扶養認定では主に生計維持関係が問われ、遺族年金の受給では生計同一関係が重視されます。
単身赴任の場合、生計維持関係は認められやすいですが、生計同一の認定には追加の証明が必要になることがあります。
企業の人事労務管理では、両概念を正確に理解し、各種制度の適用において適切に判断することが、コンプライアンスの観点からも重要です。
生計維持と生計同一の読み方
- 生計維持(ひらがな):せいけいいじ
- 生計維持(ローマ字):seikeiiji
- 生計同一(ひらがな):せいけいどういつ
- 生計同一(ローマ字):seikeidouitsu