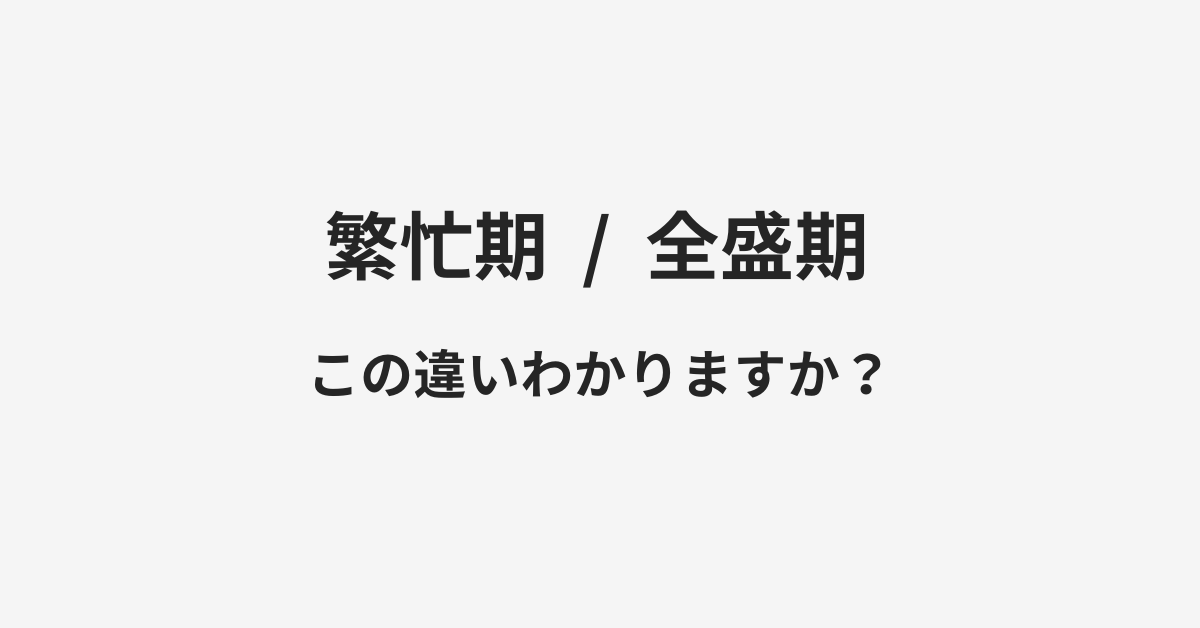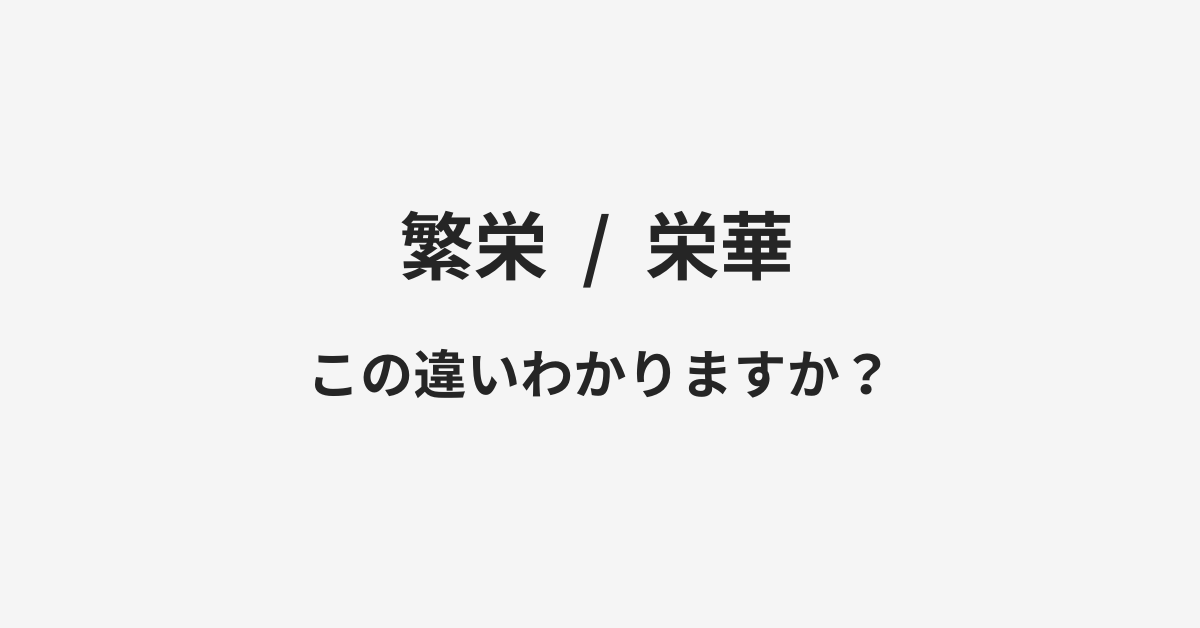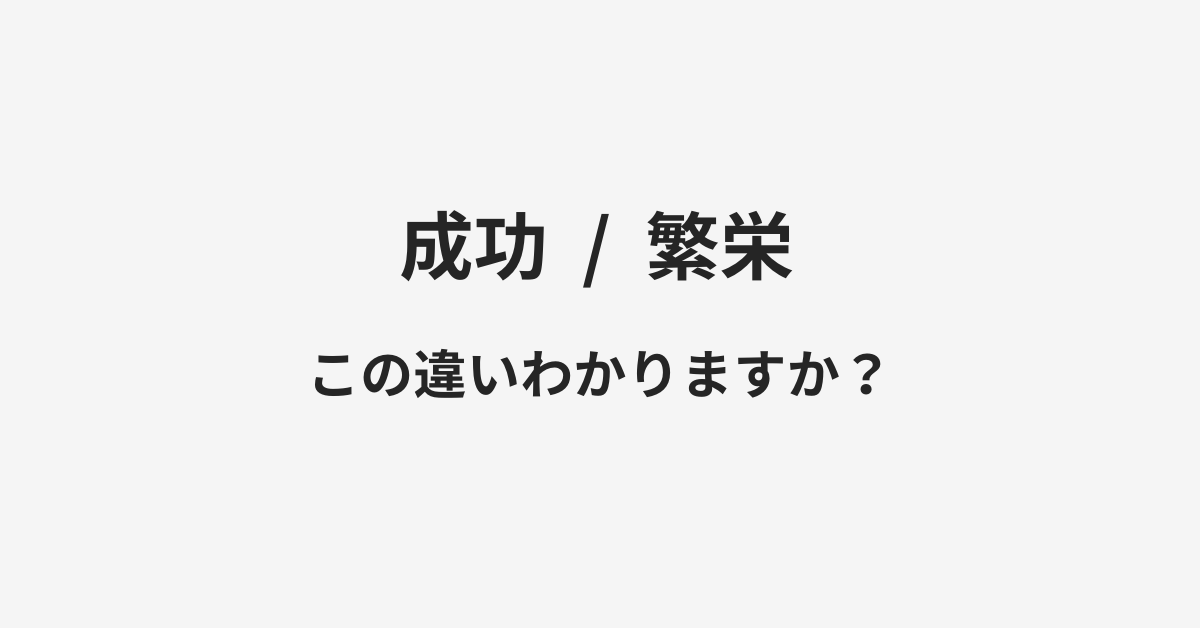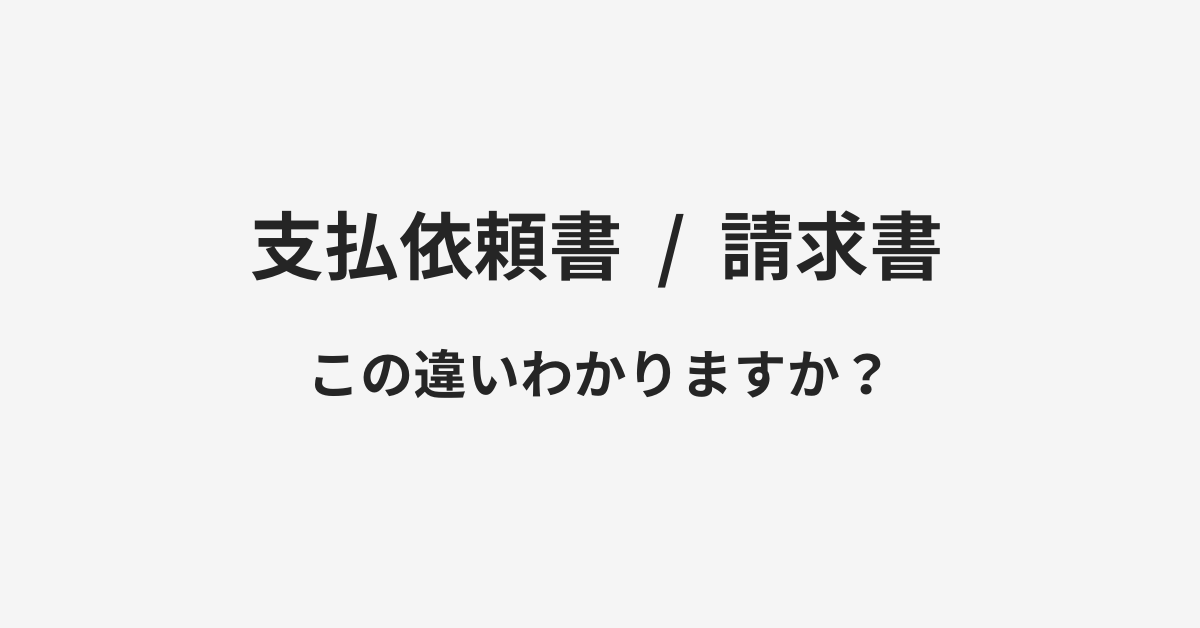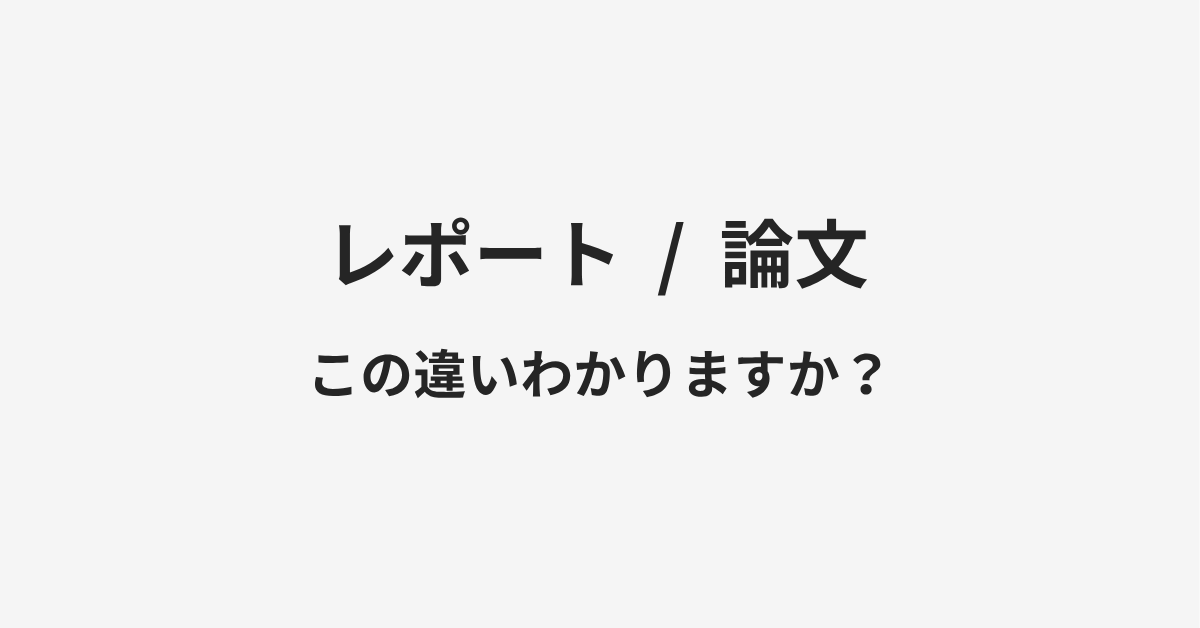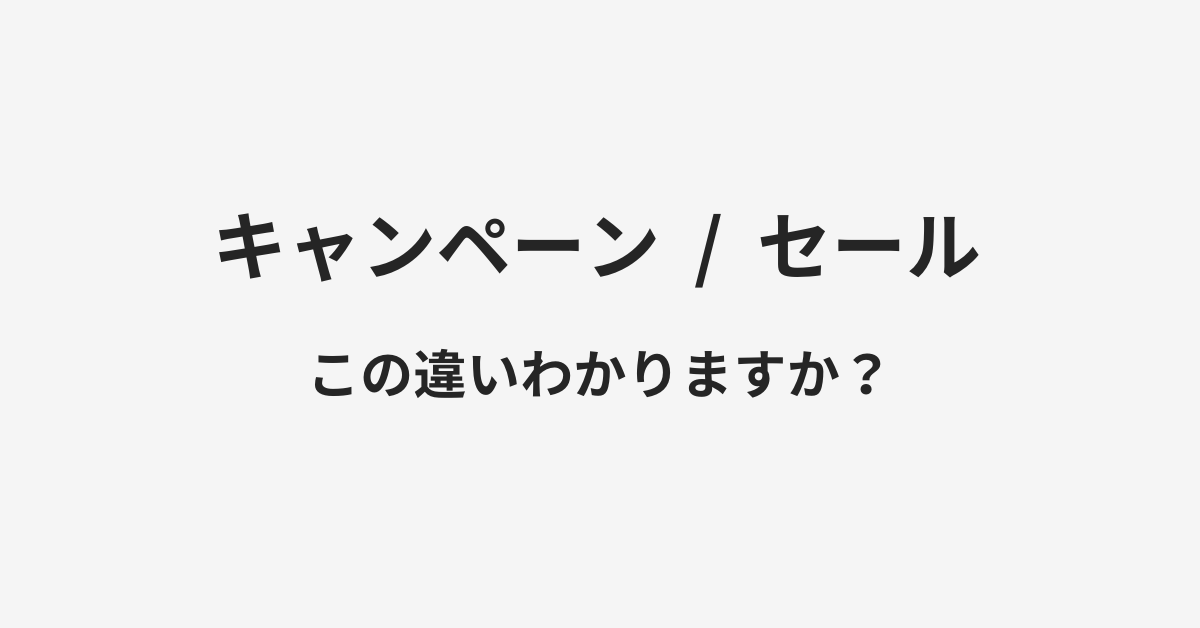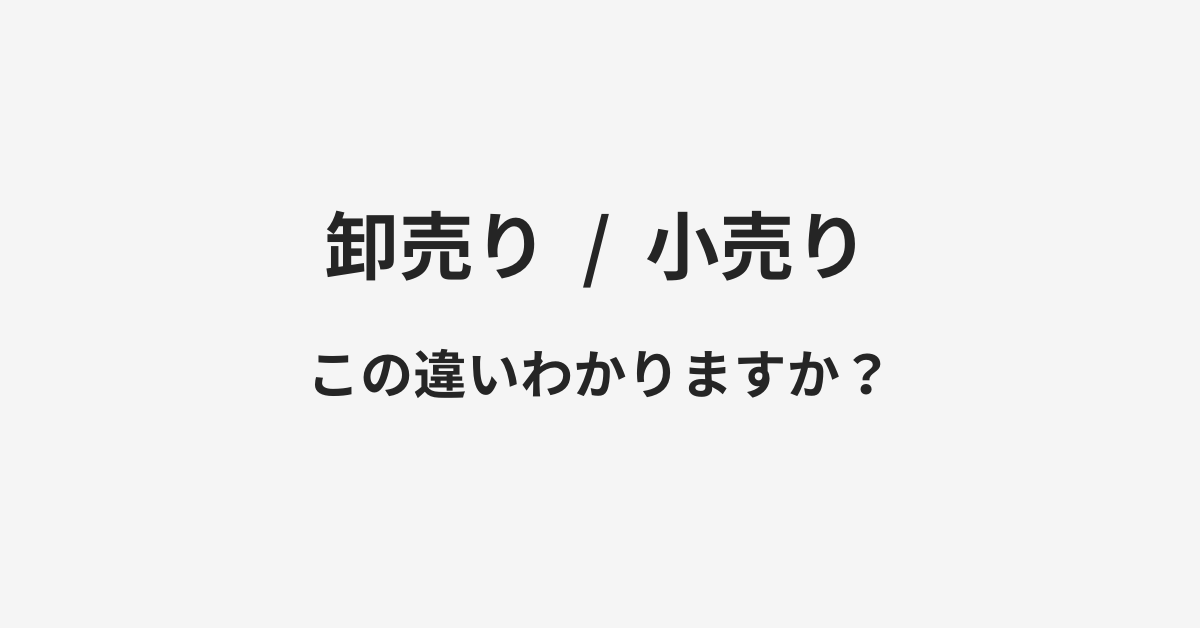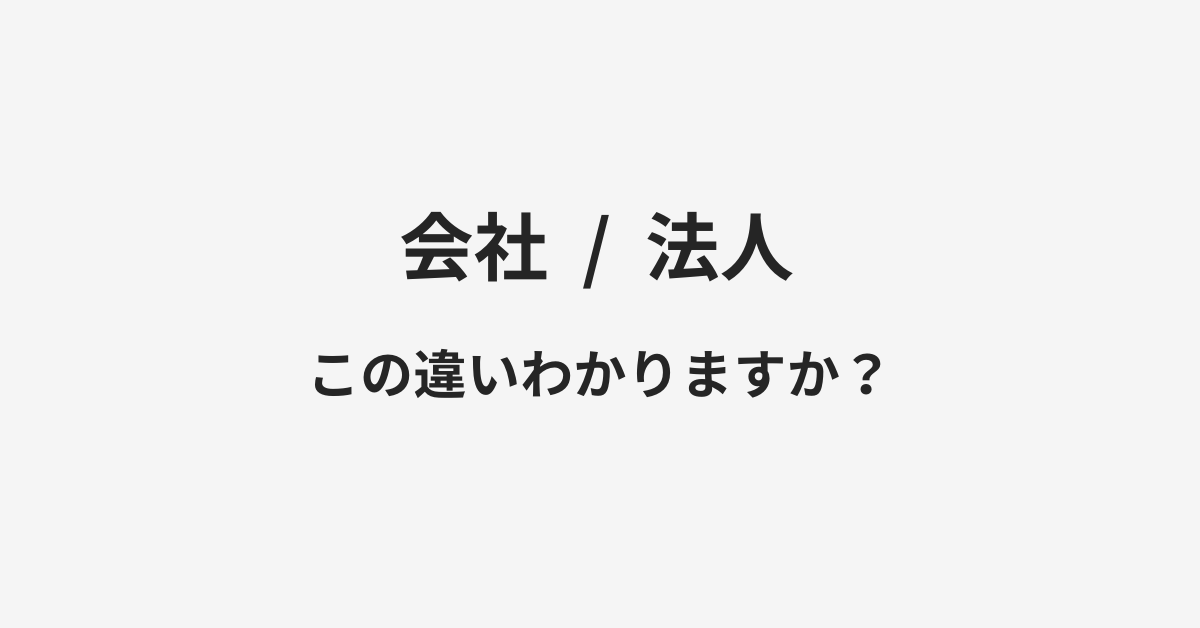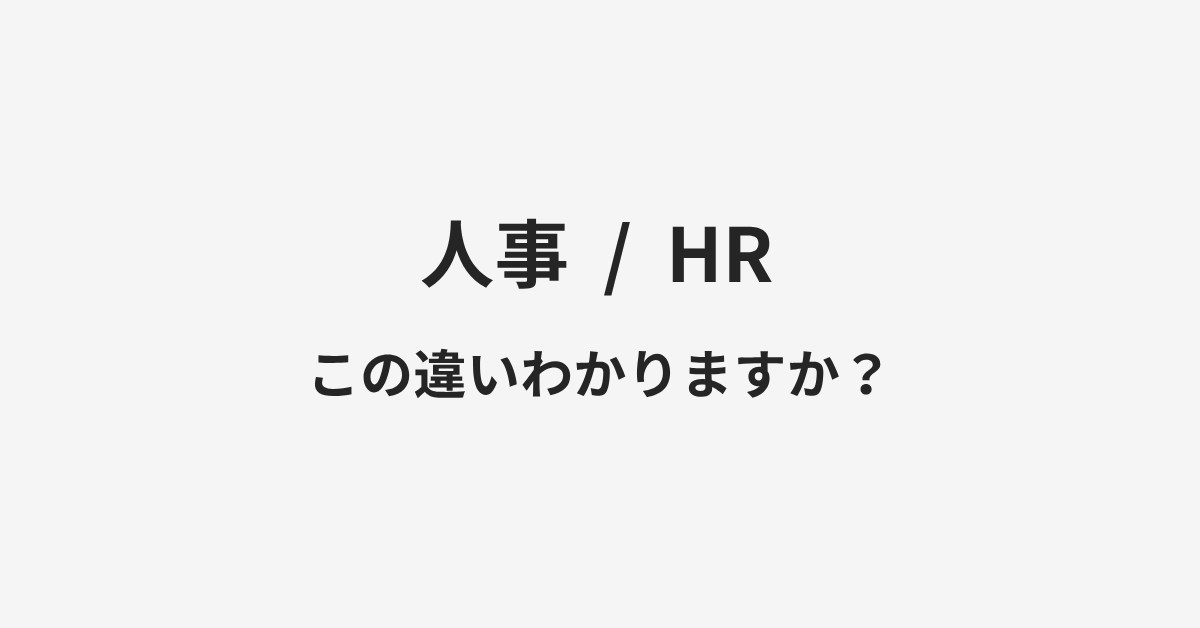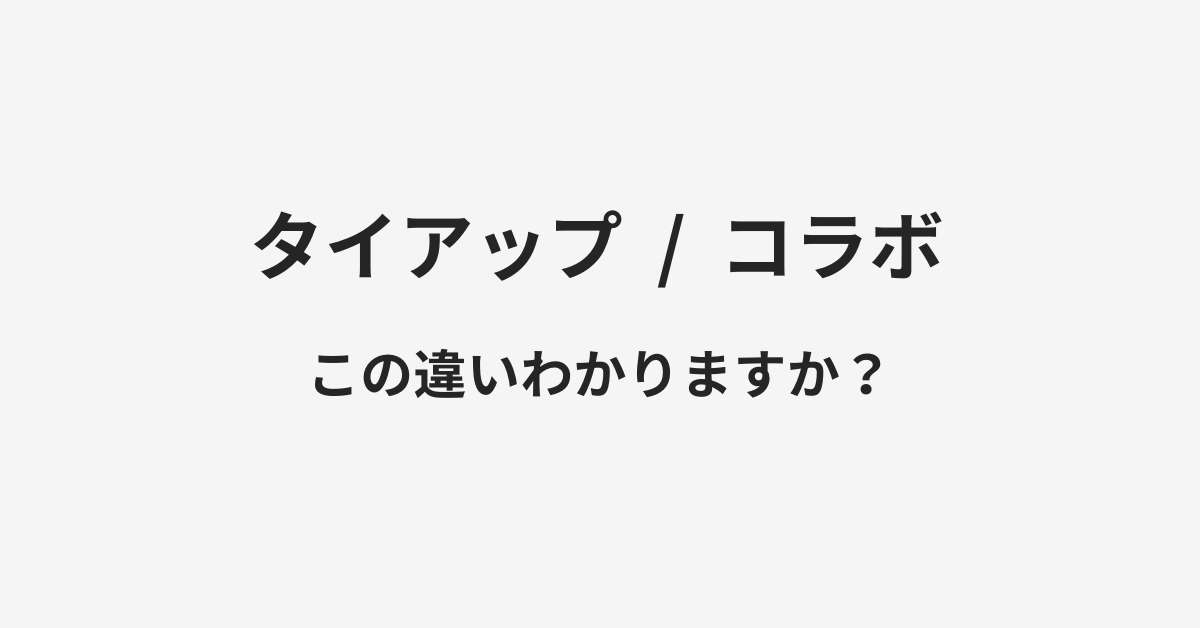【繁盛期】と【繁忙期】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
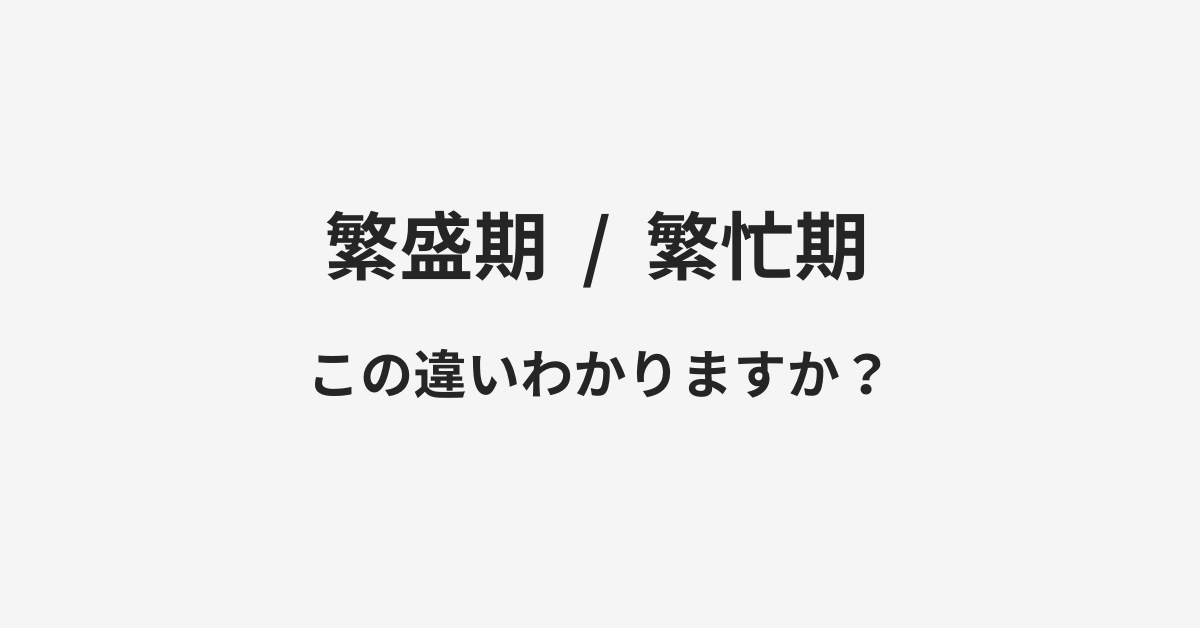
繁盛期と繁忙期の分かりやすい違い
繁盛期と繁忙期は、どちらも忙しい時期を表しますが、その性質が異なります。繁盛期は売上や利益が上がる良い忙しさを表し、主に小売業や飲食業で使われます。
繁忙期は単に業務量が多い時期を指し、業種を問わず使用され、収益性とは直接関係しません。
繁盛期とは?
繁盛期とは、商売が繁盛し、売上や客数が大幅に増加する好調な時期を指します。小売業、飲食業、観光業などで多く使われ、クリスマス商戦、ゴールデンウィーク、お盆などの季節要因や、地域のイベントに連動することが多いです。
売上増加に伴い忙しくなりますが、収益性が高く、年間利益の大部分を稼ぐ重要な期間です。繁盛期に向けた仕入れ強化、人員増強、販促活動の集中など、戦略的な準備が欠かせません。
顧客満足度を維持しながら、最大限の売上を確保することが求められます。商売繁盛という言葉があるように、ポジティブなニュアンスを持ち、ビジネスの成功を表す表現として使われます。
繁盛期の例文
- ( 1 ) 年末年始は当店の最大の繁盛期です。
- ( 2 ) 繁盛期に備えて、アルバイトを増員しました。
- ( 3 ) 今年の繁盛期は、前年比120%の売上を達成しました。
- ( 4 ) 繁盛期の売上データを分析し、来年の戦略を立てます。
- ( 5 ) 観光地なので、夏休みが繁盛期のピークです。
- ( 6 ) 繁盛期でも、サービスの質を落とさないよう注意しています。
繁盛期の会話例
繁忙期とは?
繁忙期とは、業務量が通常より多く、非常に忙しい時期を指す一般的な表現です。年度末の決算期、税務申告時期、プロジェクトの納期前、イベント準備期間など、業種や部門によって様々です。必ずしも売上増加を伴うとは限りません。
製造業の生産ピーク、会計事務所の確定申告時期、人事部の採用シーズンなど、定期的に訪れる繁忙期もあれば、突発的な案件による臨時の繁忙期もあります。残業増加、ストレス上昇などの課題があり、適切な業務管理が重要です。
繁忙期対策として、事前の準備、業務の効率化、臨時スタッフの活用、従業員の健康管理などが求められます。計画的な対応により、品質を保ちながら乗り切ることが大切です。
繁忙期の例文
- ( 1 ) 決算期は経理部門の繁忙期です。
- ( 2 ) 繁忙期の残業時間管理を徹底してください。
- ( 3 ) システム移行により、繁忙期でも定時退社が可能になりました。
- ( 4 ) 繁忙期に備えて、業務の優先順位を明確にしました。
- ( 5 ) 毎年3月は人事異動で繁忙期となります。
- ( 6 ) 繁忙期を乗り切るため、チーム全体で協力体制を構築しました。
繁忙期の会話例
繁盛期と繁忙期の違いまとめ
繁盛期と繁忙期は、忙しさの質が異なる概念です。繁盛期は収益向上を伴う前向きな忙しさで、ビジネスチャンスの時期です。
一方、繁忙期は業務集中による忙しさで、効率的な業務遂行が課題となります。
それぞれの特性を理解し、適切な対策を講じることで、ビジネスの成功につながります。
繁盛期と繁忙期の読み方
- 繁盛期(ひらがな):はんじょうき
- 繁盛期(ローマ字):hannjouki
- 繁忙期(ひらがな):はんぼうき
- 繁忙期(ローマ字):hannbouki