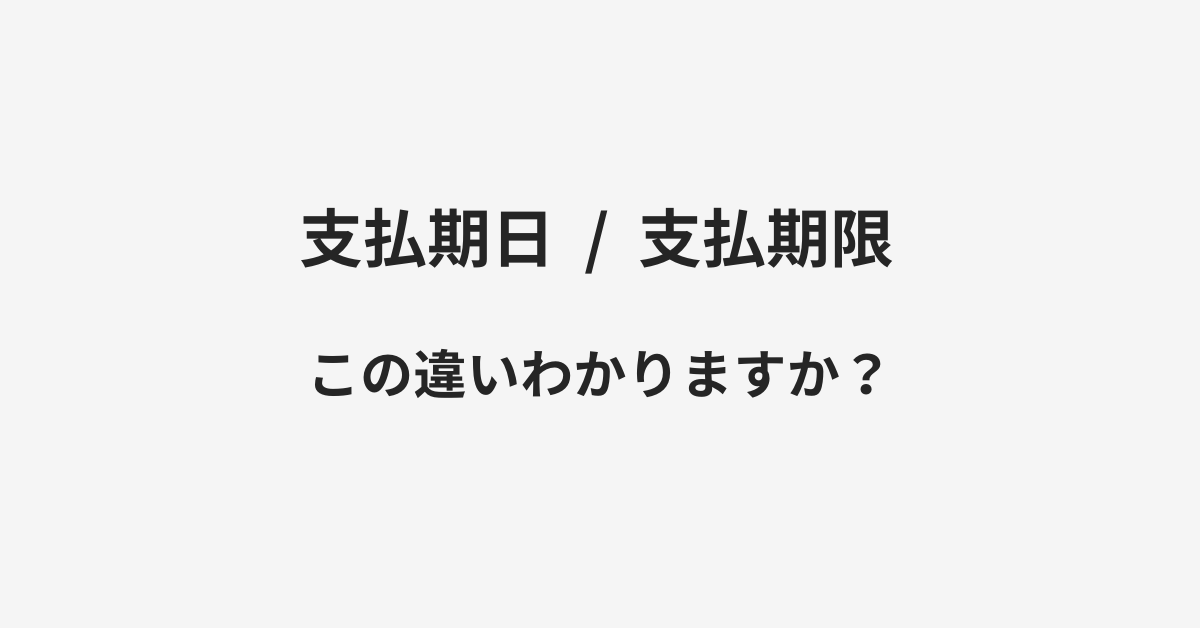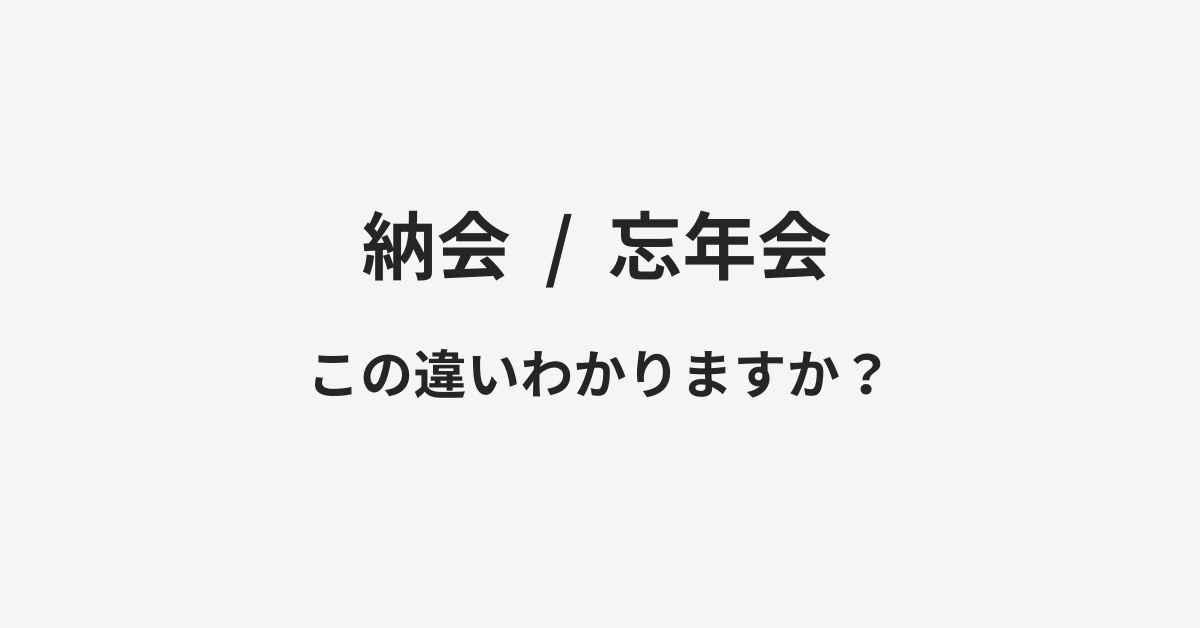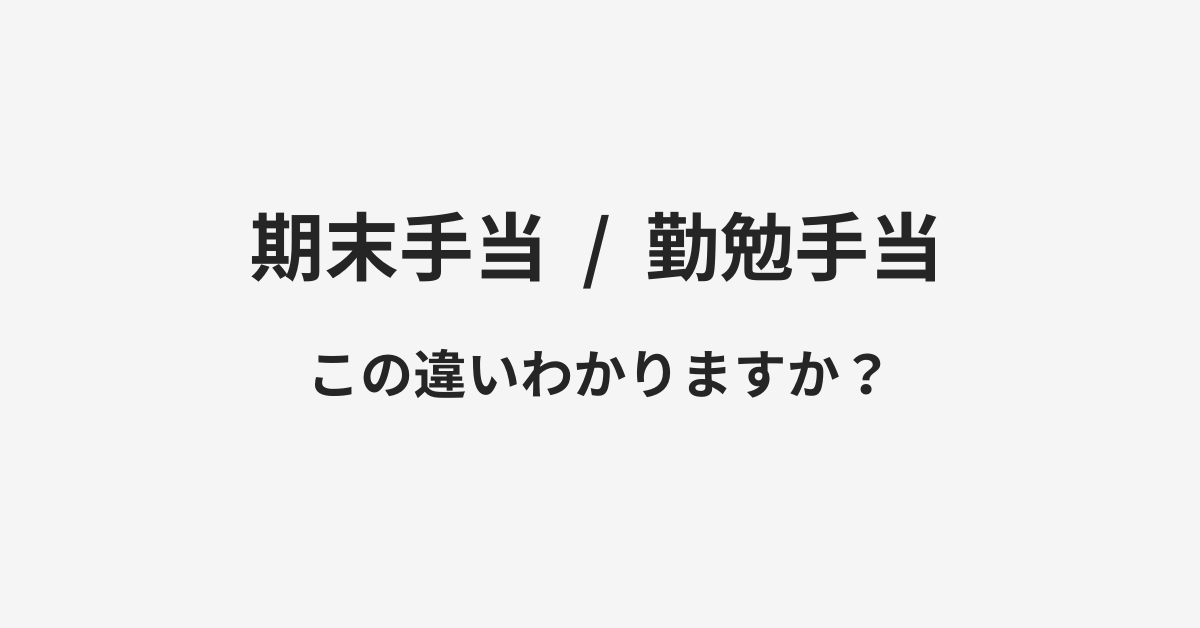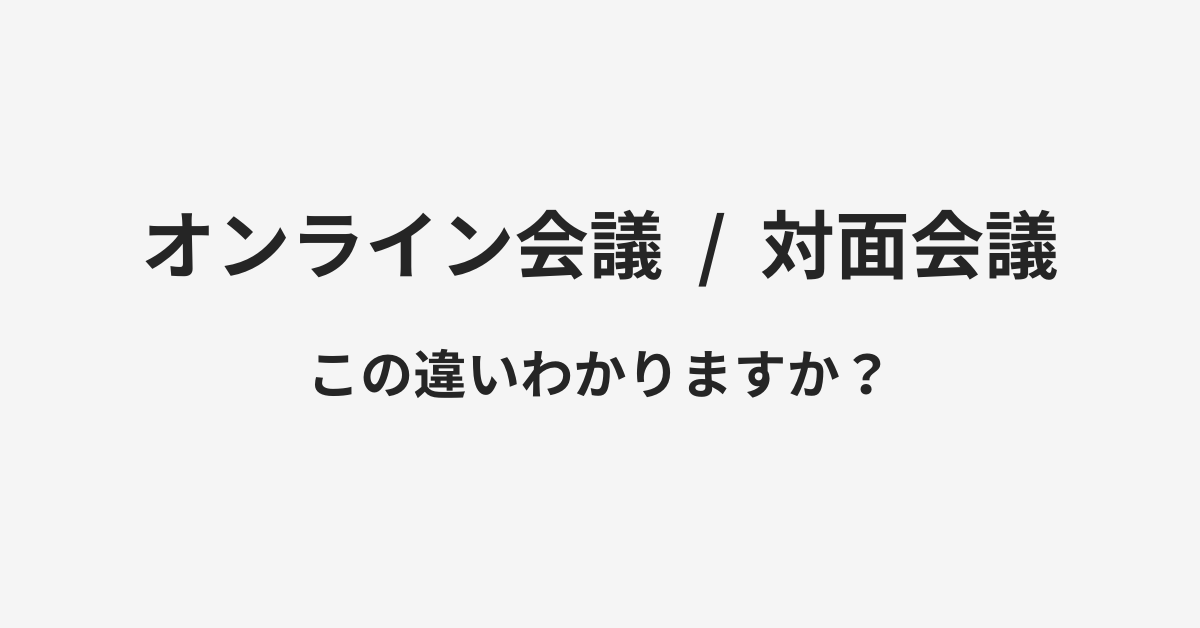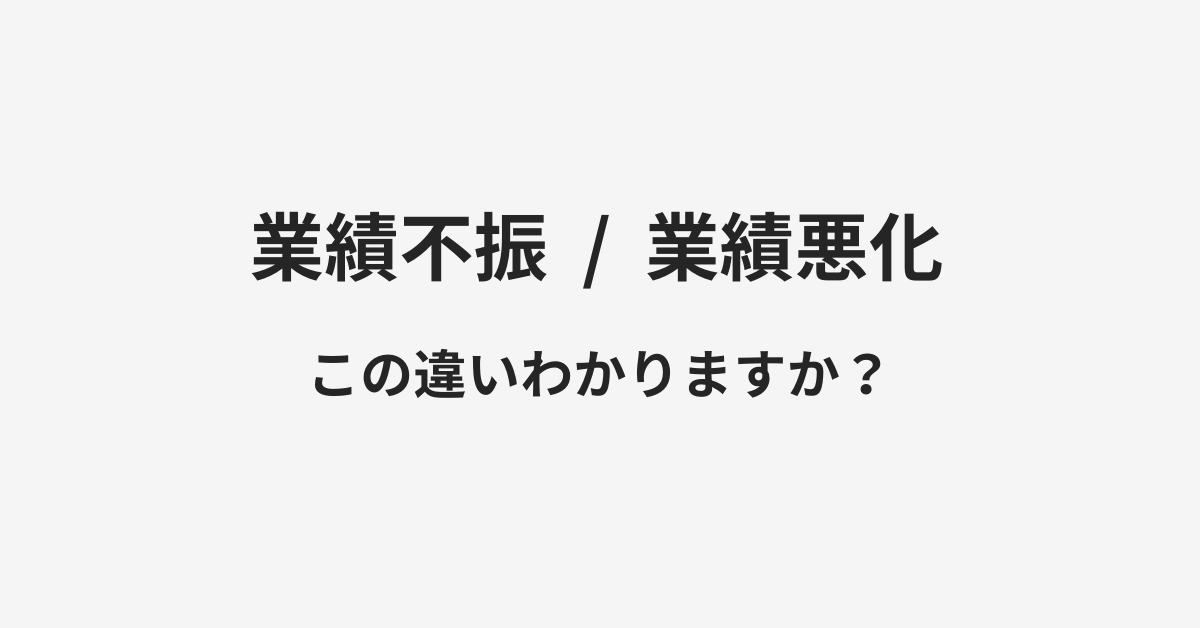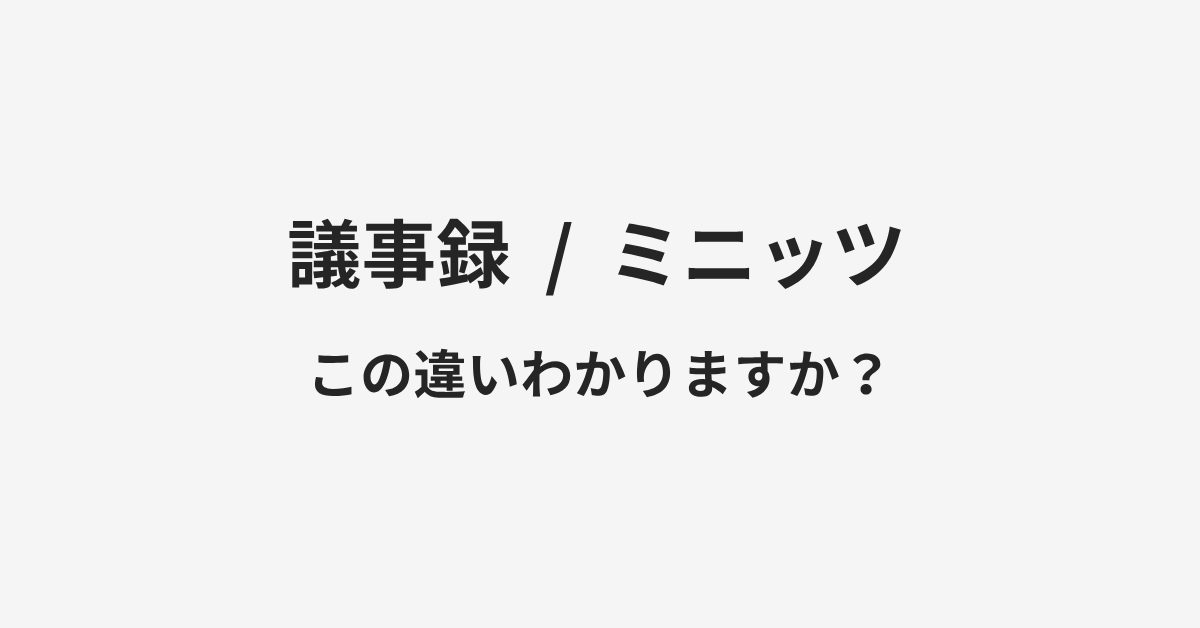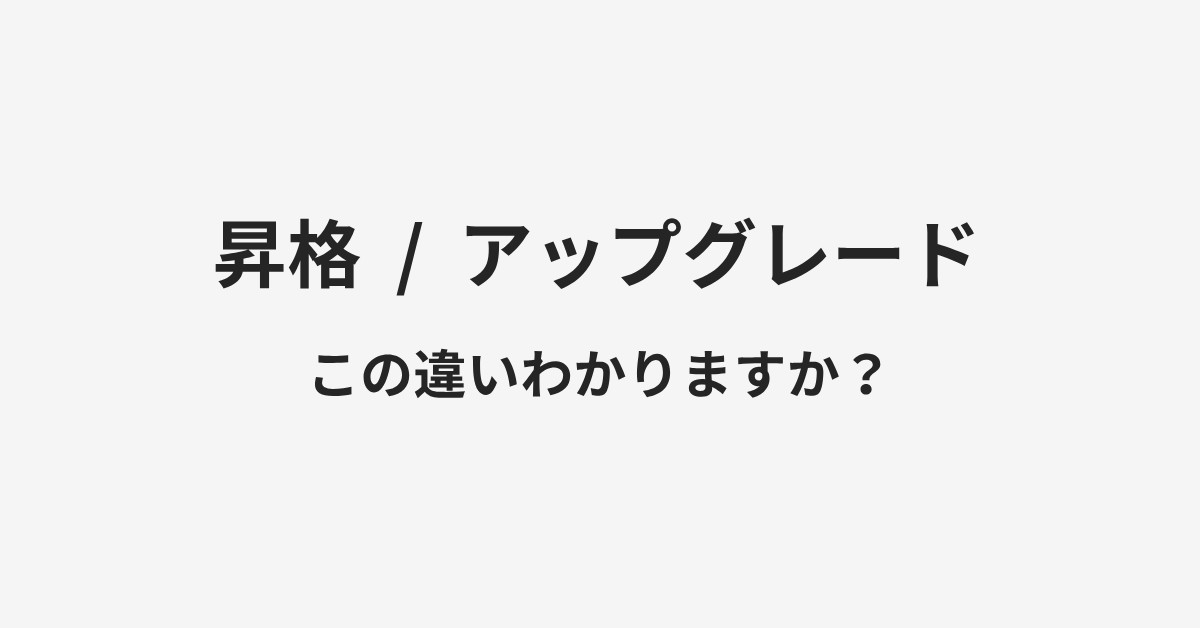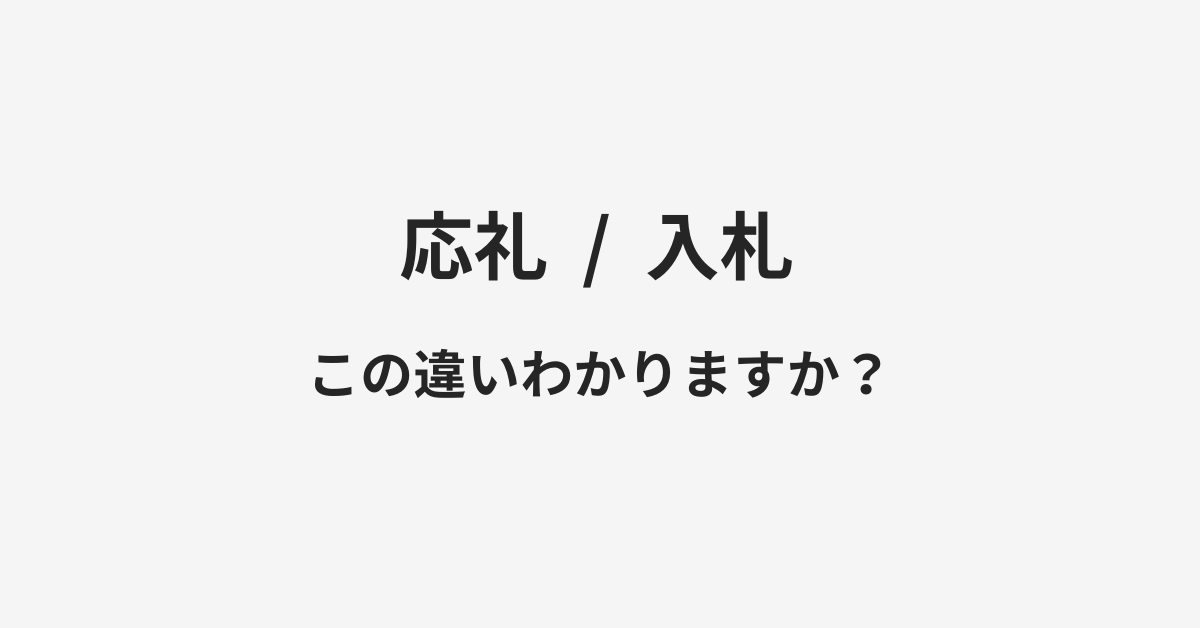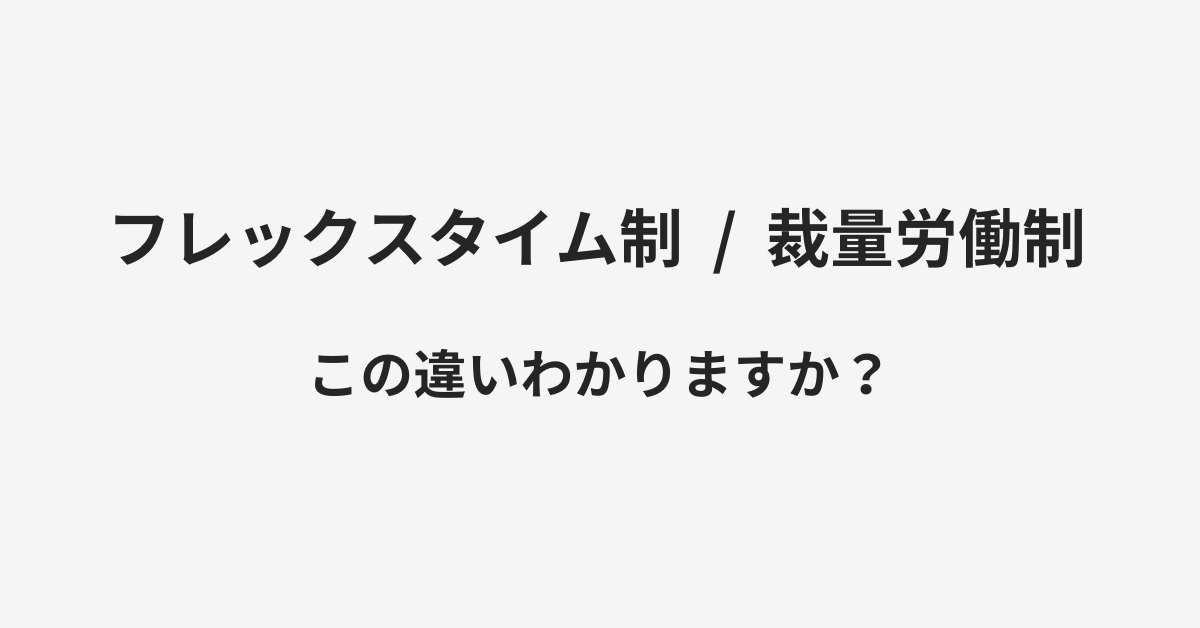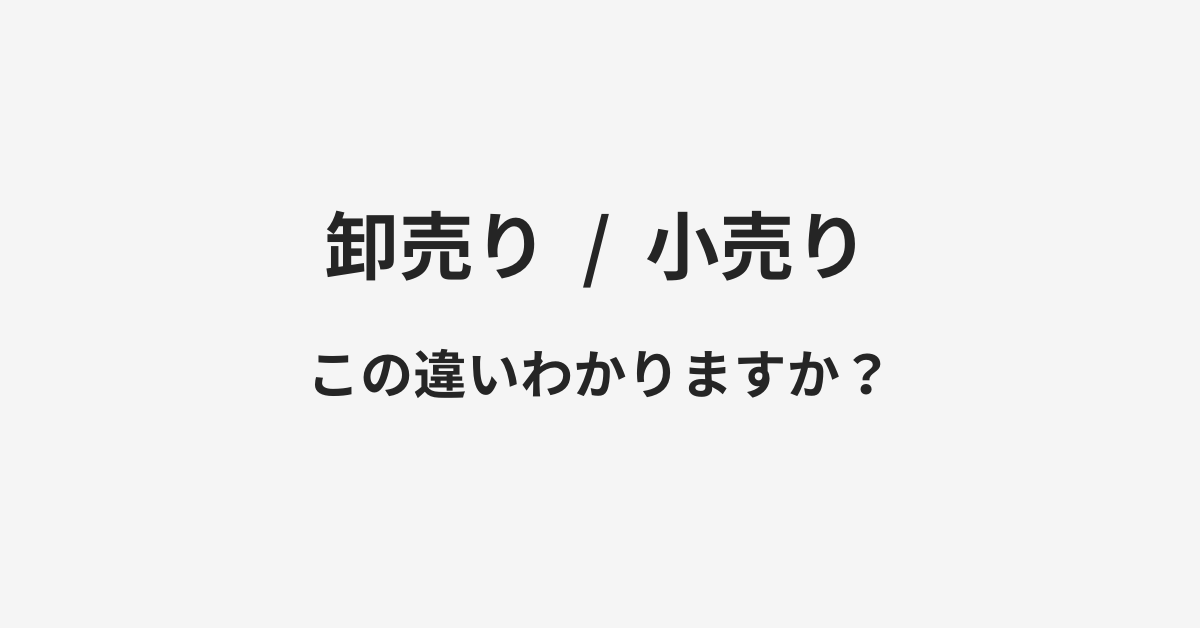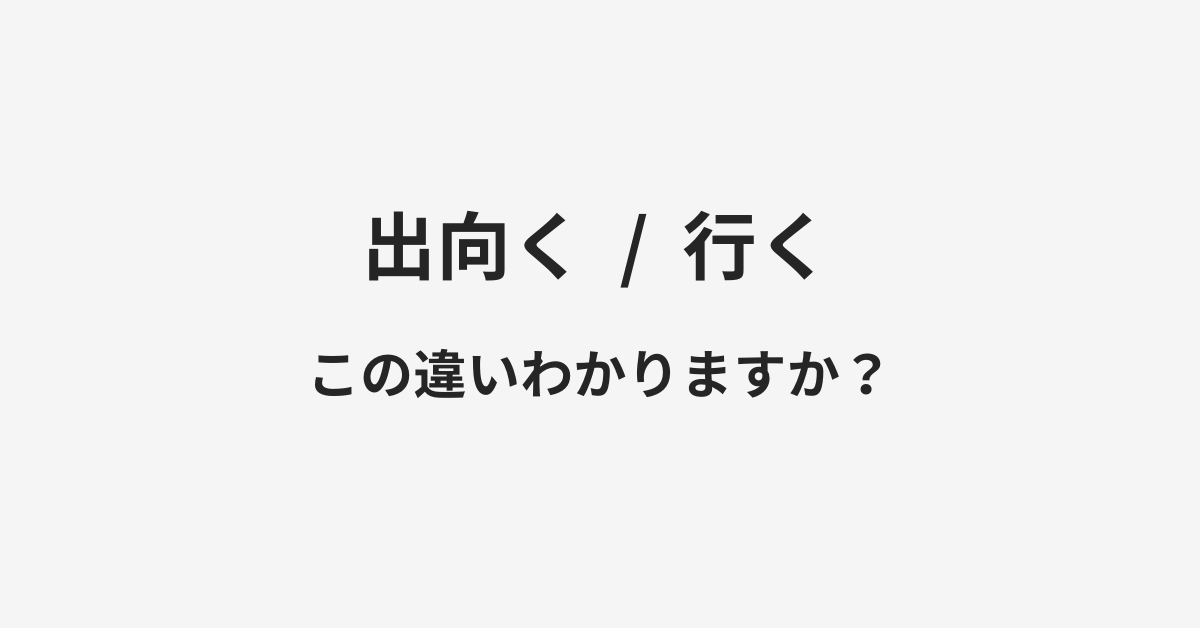【御用納め】と【仕事納め】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
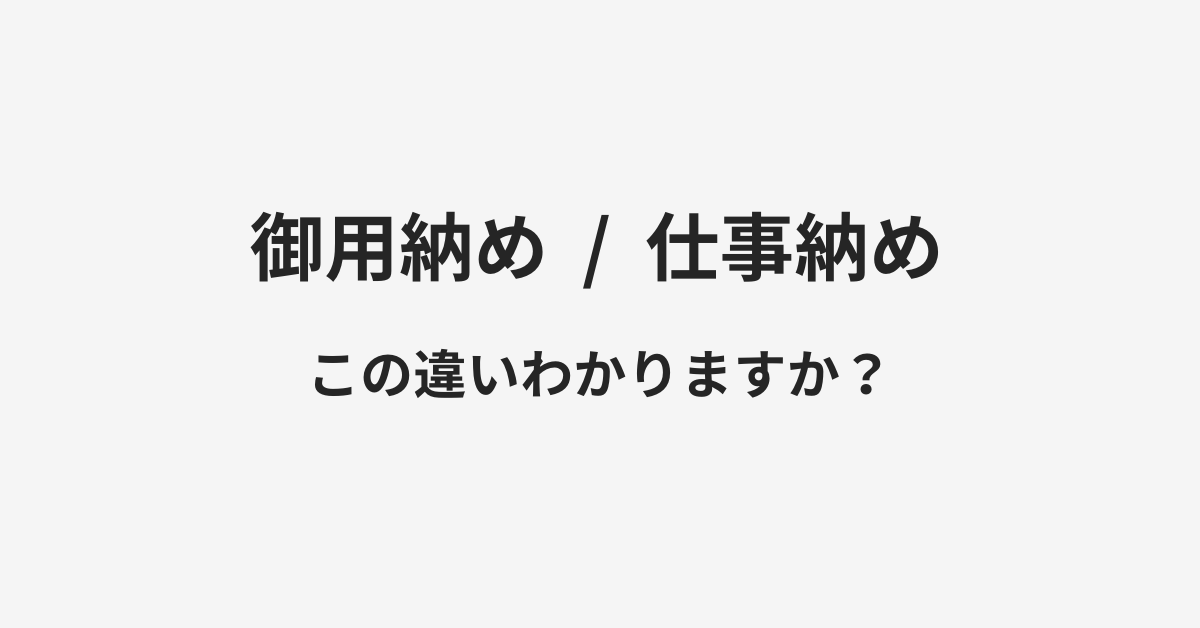
御用納めと仕事納めの分かりやすい違い
御用納めと仕事納めは、どちらも年末の最終業務を表しますが、その対象と使用範囲に違いがあります。御用納めは官公庁の12月28日の最終業務日を指す公式用語で、仕事納めは民間企業や個人が使う一般的な表現です。
前者は制度的、後者は慣習的という性質の違いがあります。
年末の挨拶や予定調整において、この違いを理解することは、相手に応じた適切な表現の使用に重要です。
御用納めとは?
御用納めとは、官公庁における年内最後の業務日を指す言葉で、原則として12月28日と定められています。御用は公務を意味し、江戸時代から使われている伝統的な表現です。国の機関、地方自治体、裁判所などの公的機関で使用され、この日をもって年内の通常業務を終了し、12月29日から1月3日まで年末年始休暇に入ります。
御用納めの日は、各省庁や自治体で式典が行われることもあり、大臣や首長が職員に向けて一年の労をねぎらう挨拶をすることが慣例となっています。ただし、警察、消防、病院など、24時間体制が必要な部署では交代制で業務を継続します。
また、12月28日が土日の場合は、直前の平日が御用納めとなります。民間企業でも、官公庁との取引が多い企業では御用納めという表現を使うことがありますが、正確には官公庁特有の用語です。年末の挨拶状では御用納めを迎えられという表現で、官公庁向けに使用されます。
御用納めの例文
- ( 1 ) 本日12月28日をもちまして、御用納めとなります。
- ( 2 ) 御用納め後も、緊急対応窓口は開設しております。
- ( 3 ) 御用納めまでに申請書類の提出をお願いいたします。
- ( 4 ) 市役所は御用納めのため、12月29日から1月3日まで閉庁します。
- ( 5 ) 御用納めの式典で、市長から職員への感謝の言葉がありました。
- ( 6 ) 御用納め前に、来年度予算の最終調整を行います。
御用納めの会話例
仕事納めとは?
仕事納めとは、民間企業や個人事業主が年内最後の営業日や業務を終えることを指す一般的な表現です。官公庁の御用納めとは異なり、企業により日程は様々で、12月28日前後から30日頃までと幅があります。業種によっては大晦日まで営業する場合もあり、サービス業や小売業では年末年始も休まない企業も多くあります。
仕事納めの日には、大掃除、忘年会、挨拶回り、年末年始の準備などが行われます。多くの企業では、社長や上司から従業員への感謝の言葉、来年への抱負などが語られます。取引先への年末挨拶、お歳暮の手配、年賀状の準備なども、仕事納めまでに済ませる重要な業務です。
最近では、働き方改革の影響で、仕事納めを早める企業も増えています。また、リモートワークの普及により、物理的な納めの概念が薄れ、業務の区切りとしての意味合いが強くなっています。
仕事納めの例文
- ( 1 ) 本日で仕事納めとし、新年は1月4日から営業いたします。
- ( 2 ) 仕事納めの大掃除で、オフィスがきれいになりました。
- ( 3 ) 取引先への挨拶回りを済ませ、無事に仕事納めを迎えました。
- ( 4 ) 仕事納めの日に、忘年会を兼ねた納会を開催します。
- ( 5 ) 今年の仕事納めは12月27日の予定です。
- ( 6 ) 仕事納めまでに、すべての案件を片付けたいと思います。
仕事納めの会話例
御用納めと仕事納めの違いまとめ
御用納めと仕事納めの主な違いは、使用対象と日程の確定性です。御用納めは官公庁限定で12月28日固定、仕事納めは民間企業・個人で日程は自由という明確な違いがあります。言葉の格式も異なり、御用納めは公式で格式高い表現、仕事納めは一般的で親しみやすい表現です。
ビジネス文書では、相手が官公庁なら御用納め、民間企業なら仕事納めを使うのが適切です。年末の挨拶では、この使い分けを意識することで、相手に対する理解と配慮を示すことができます。
ただし、最近では民間でも御用納めを使うケースもあり、厳密な使い分けは緩やかになっています。
御用納めと仕事納めの読み方
- 御用納め(ひらがな):ごようおさめ
- 御用納め(ローマ字):goyouosame
- 仕事納め(ひらがな):しごとおさめ
- 仕事納め(ローマ字):shigotoosame