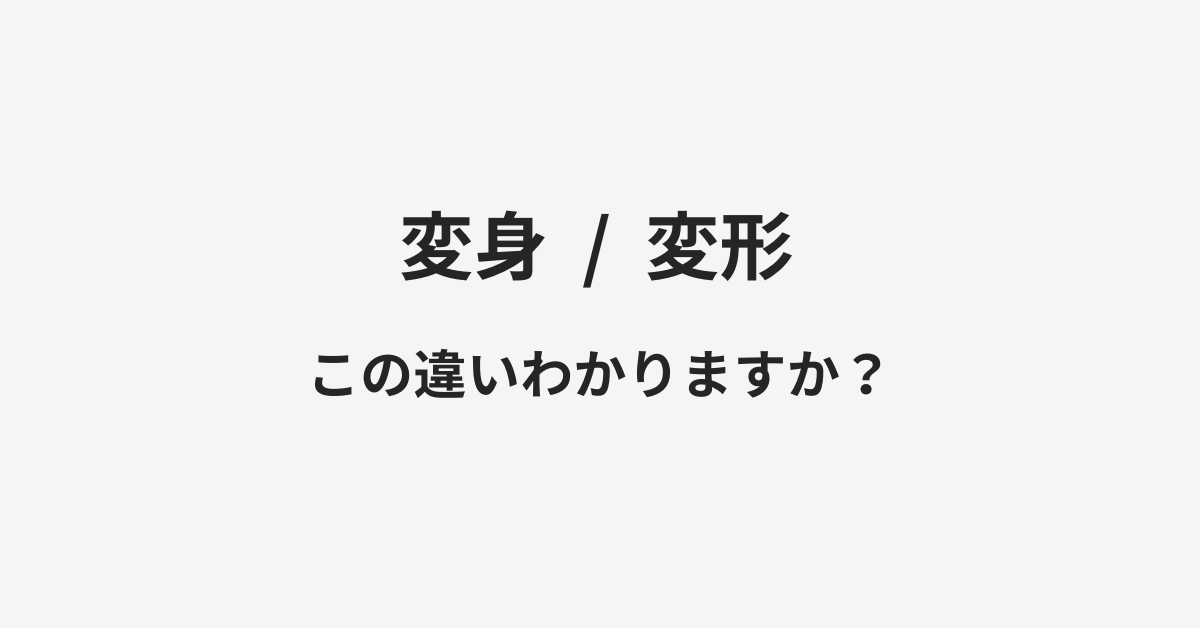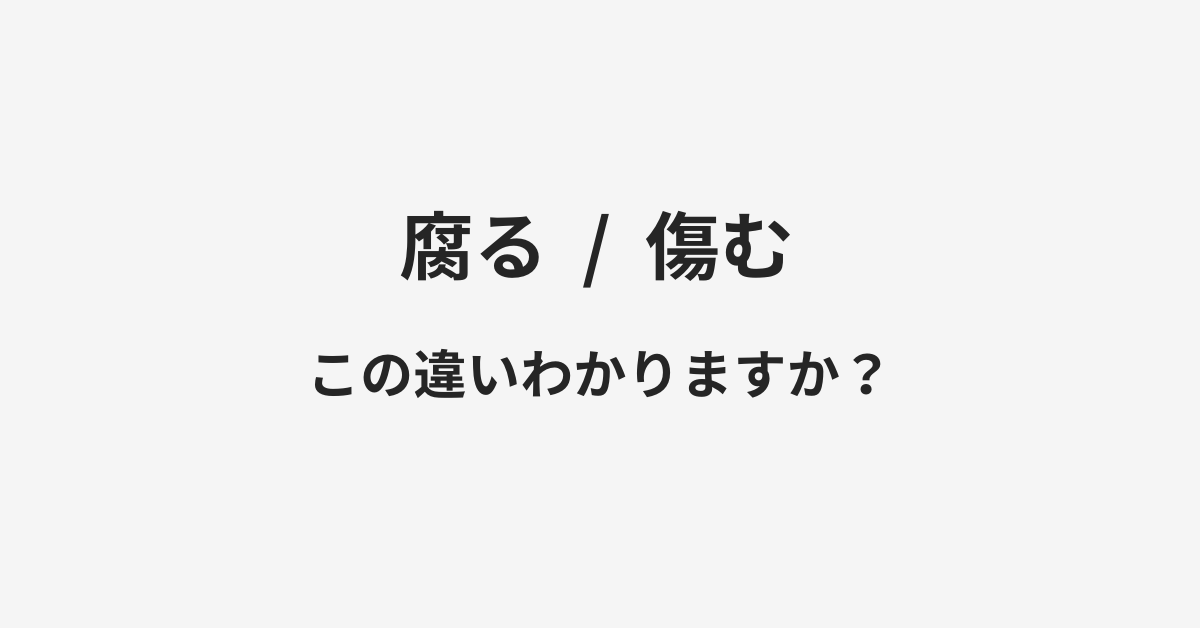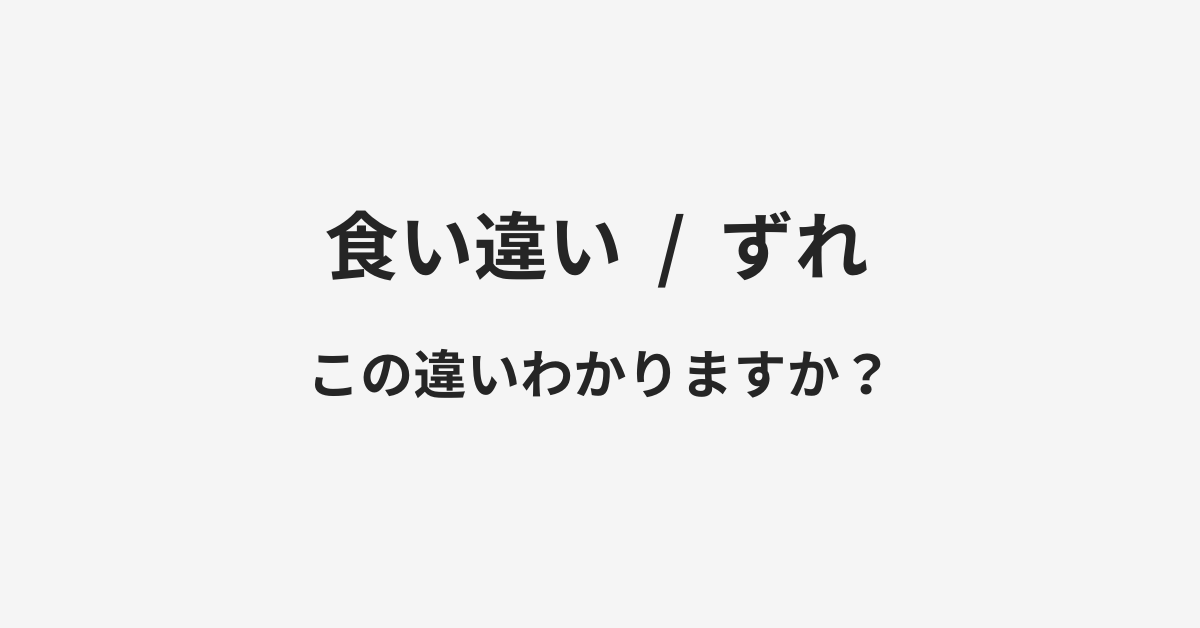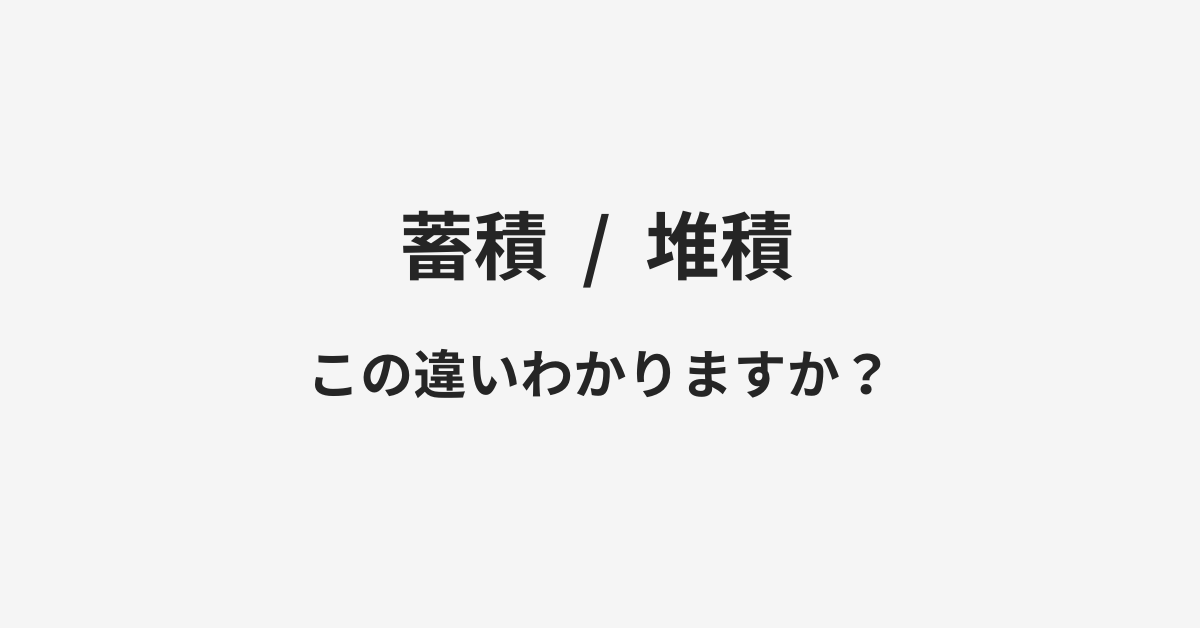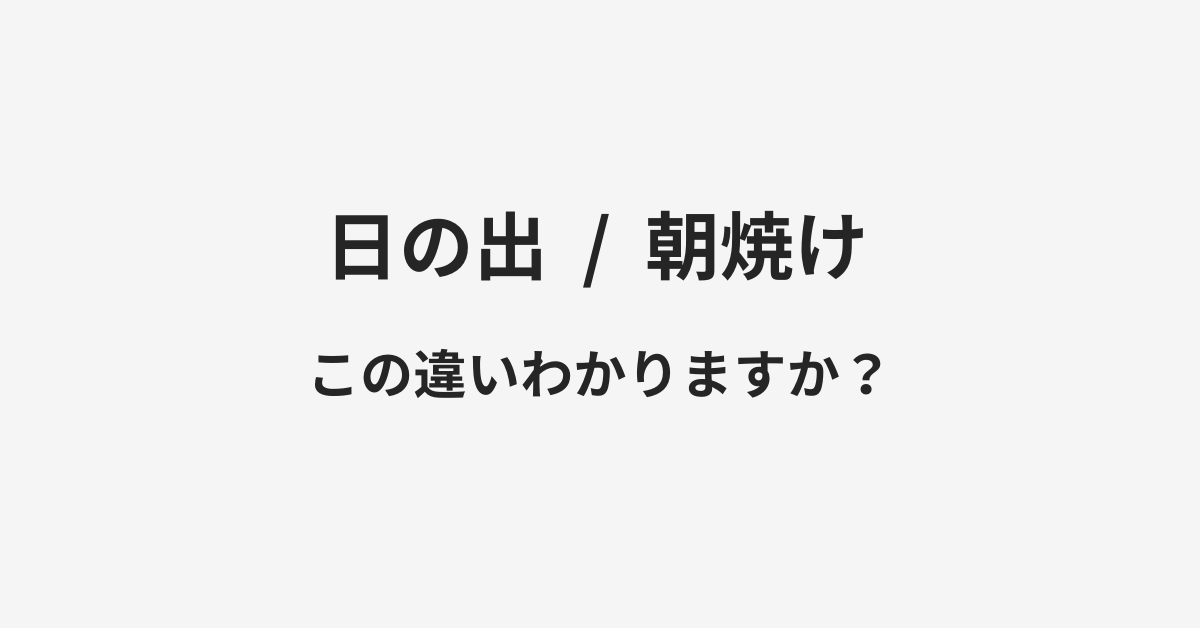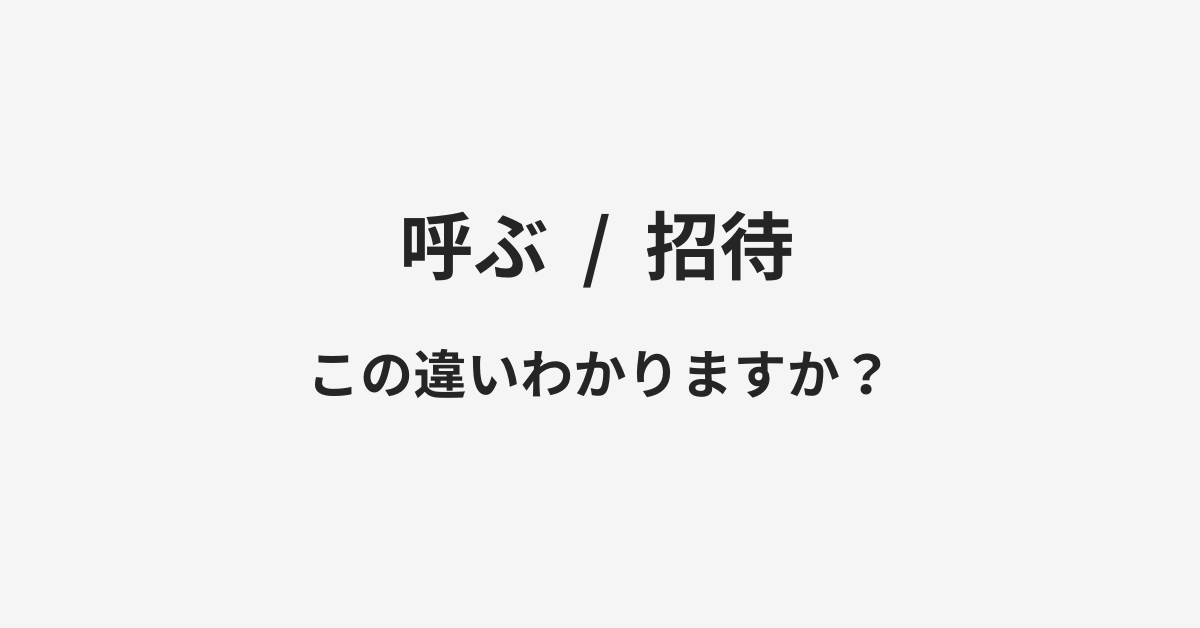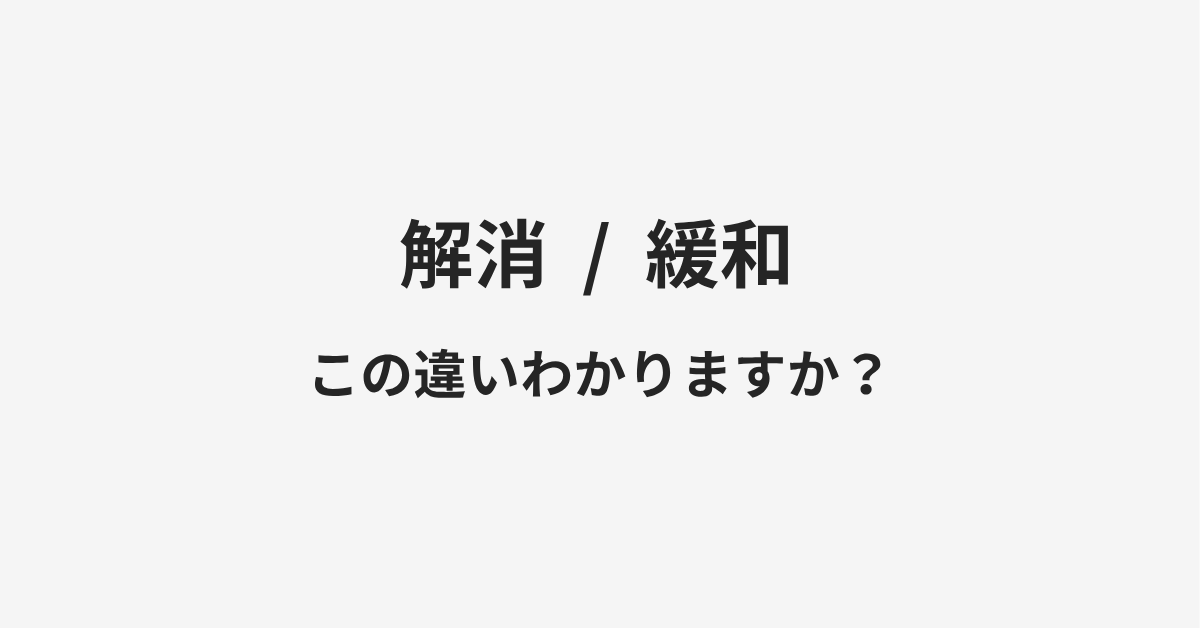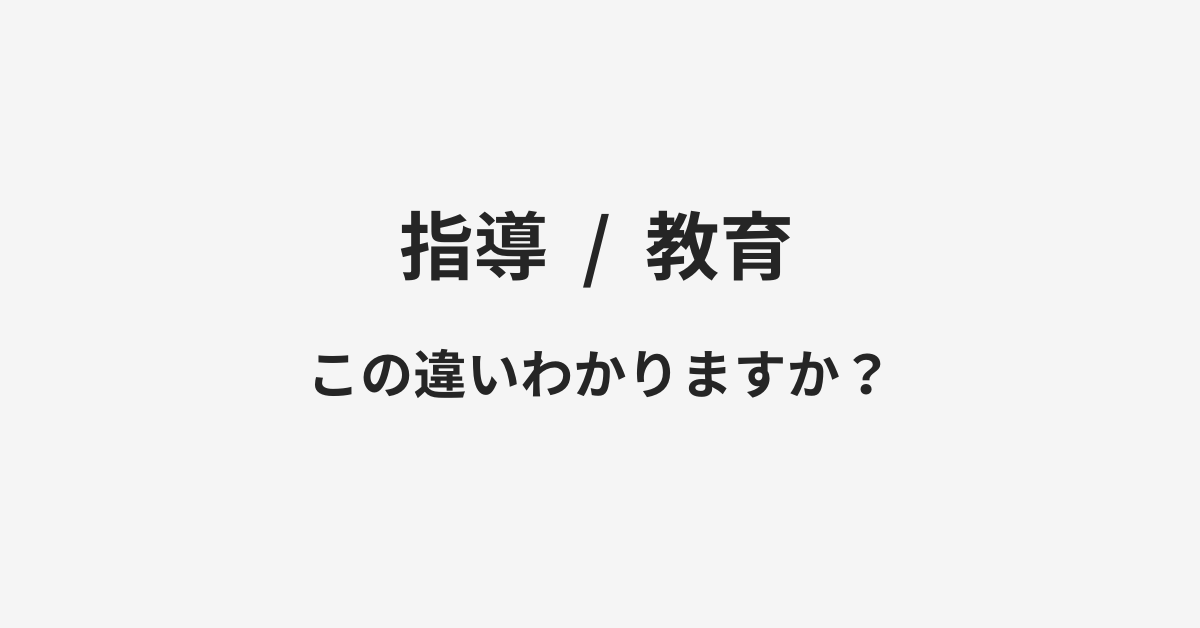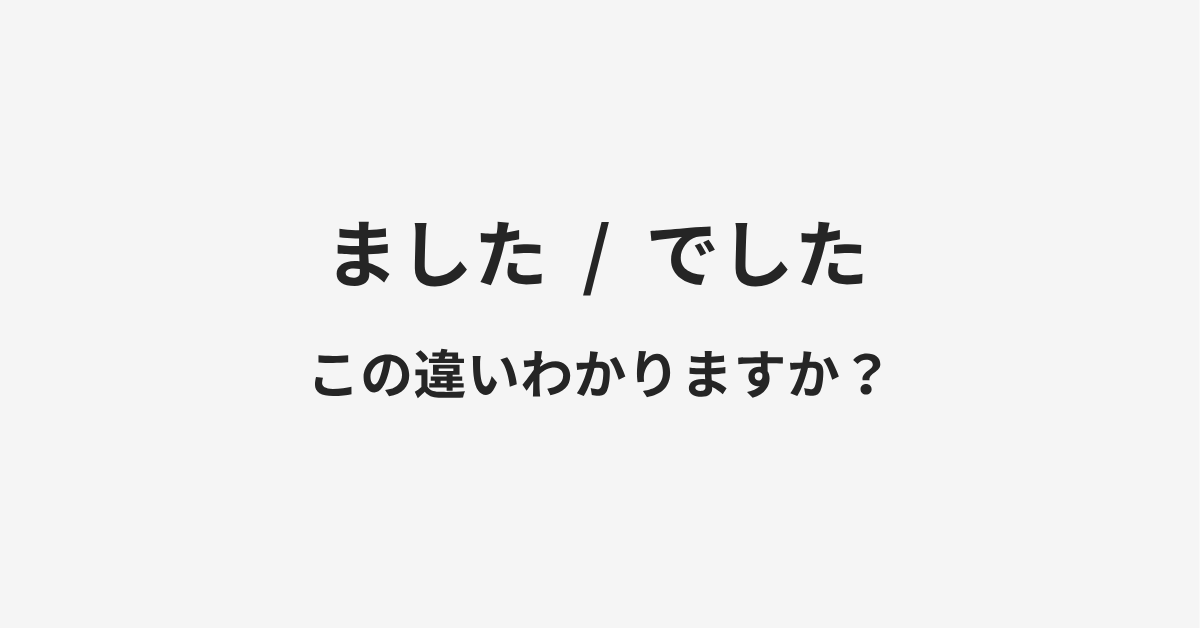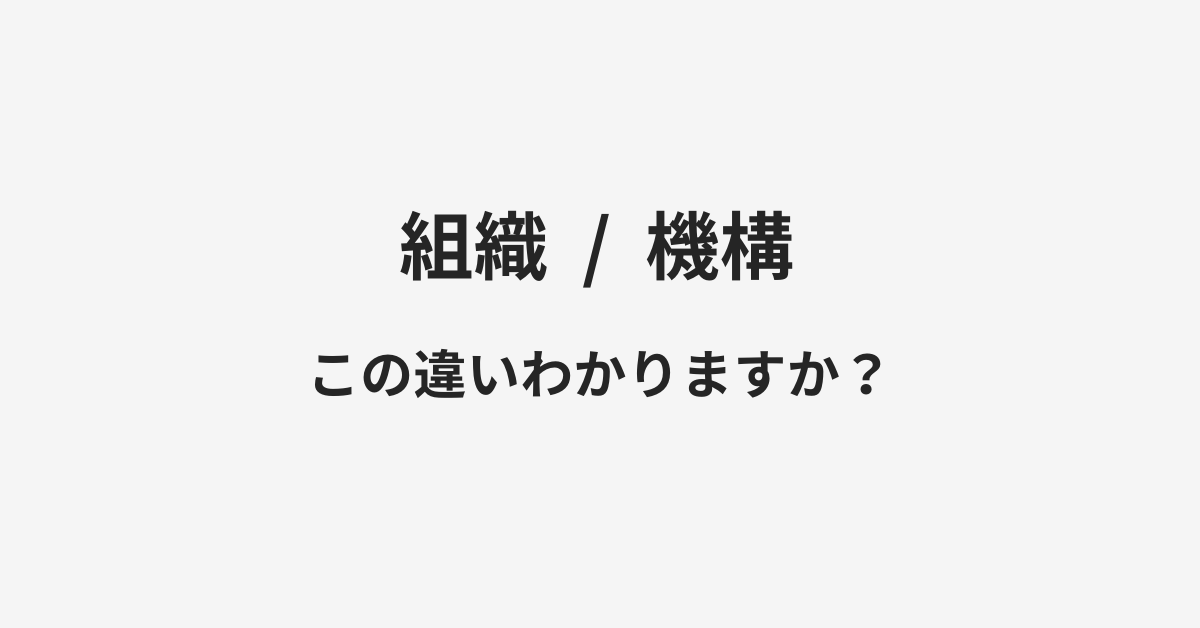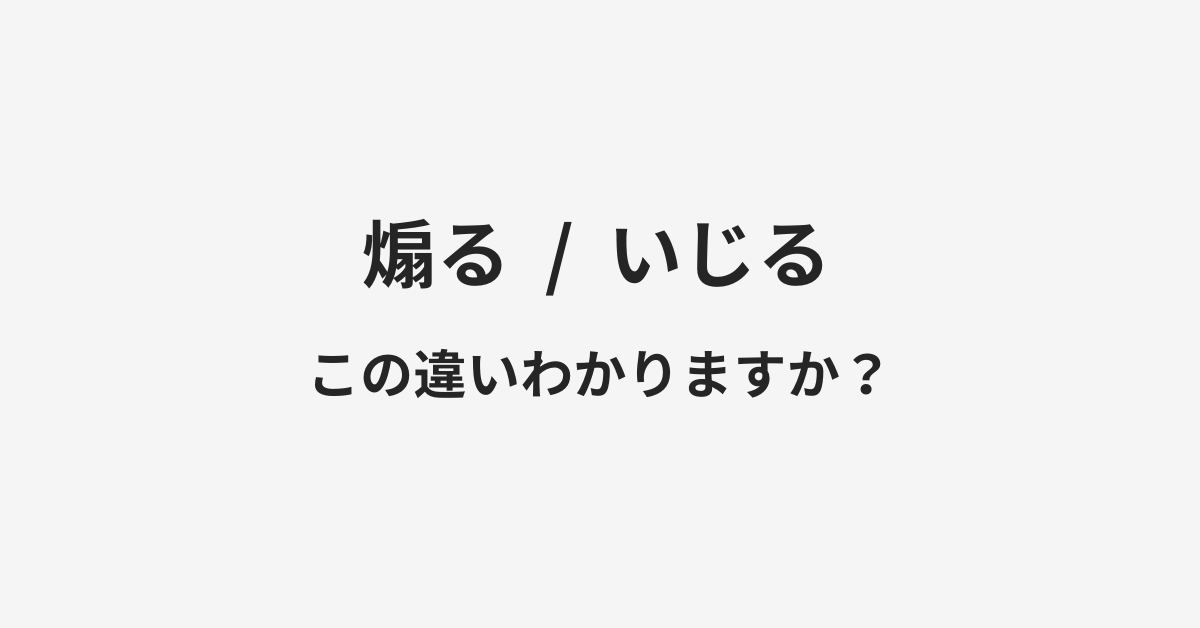【溶ける】と【解ける】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
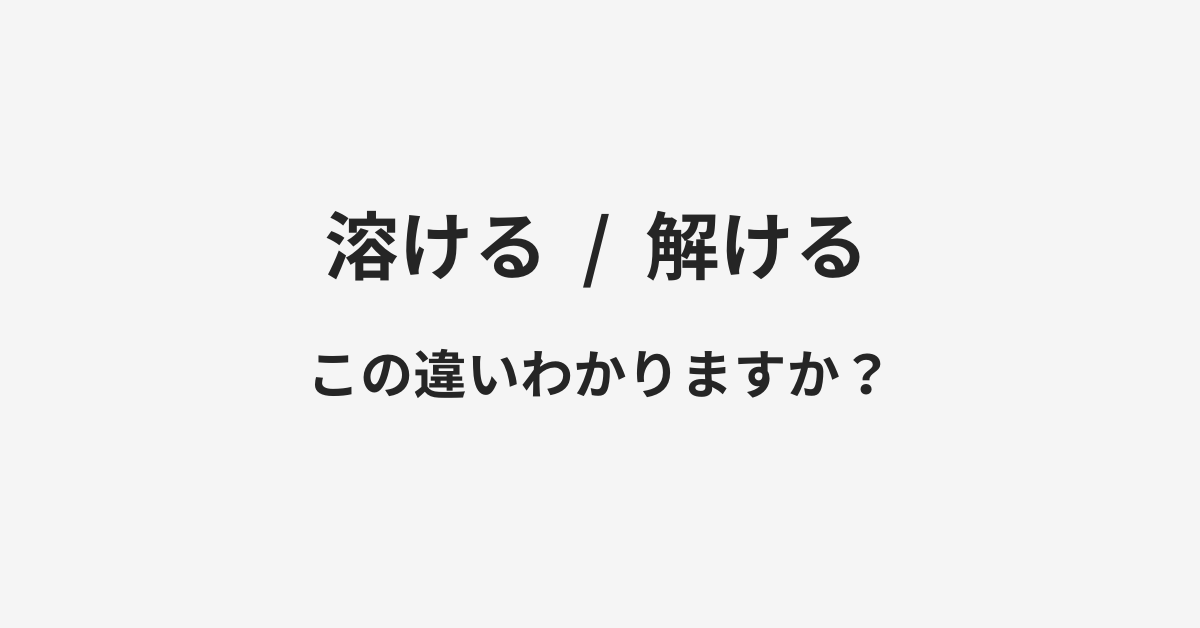
溶けると解けるの分かりやすい違い
溶けると解けるは、同じ「とける」と読みますが、意味が異なります。
溶けるは氷や砂糖が液体になること、解けるは結び目がほどけることです。
氷が「溶けて」水になり、靴紐が「解けて」ほどけるという使い分けをします。
溶けるとは?
溶けるとは、固体が熱や水分によって液体に変化することです。氷が水になる、砂糖が水に混ざる、チョコレートが温度で液状になるなど、物質の状態が固体から液体へ変わる物理的な変化を指します。化学の授業でも学ぶ基本的な現象です。
「氷が溶ける」「砂糖が溶ける」「雪が溶ける」など、固体が液体になる様子を表現します。日常生活でよく見られる自然現象です。
料理での調味料の使用、暑い日のアイスクリーム、春の雪解けなど、身の回りで起こる物質の状態変化を表す時に使われます。
溶けるの例文
- ( 1 ) 暖かくなって雪が溶け始めた。
- ( 2 ) コーヒーに砂糖が溶けるまで混ぜる。
- ( 3 ) アイスクリームが溶ける前に食べよう。
- ( 4 ) 熱でプラスチックが溶けてしまった。
- ( 5 ) バターがフライパンで溶けた。
- ( 6 ) 口の中でチョコレートが溶ける。
溶けるの会話例
「アイス大丈夫?」
「もう溶けちゃってる」
「砂糖入れた?」
「まだ溶けてないから待って」
「チョコどうした?」
「ポケットで溶けちゃった」
解けるとは?
解けるとは、結ばれていたものがほどける、固まっていたものがばらばらになる、または問題や疑問が解決することを表します。物理的なほどけから、抽象的な解決まで幅広い意味を持ちます。緊張が解ける、誤解が解けるなど、心理的な状態変化にも使われます。
「紐が解ける」「緊張が解ける」「問題が解ける」など、結束や固定が緩む様子や、解決する様子を表現します。幅広い場面で使われる表現です。
靴紐のほどけ、緊張の緩和、数学問題の解決など、物理的・精神的・知的な様々な「ほどける」状態を表す時に使われます。
解けるの例文
- ( 1 ) 靴紐が解けているよ。
- ( 2 ) やっと緊張が解けてきた。
- ( 3 ) 誤解が解けて仲直りできた。
- ( 4 ) この問題が解けたらすごい。
- ( 5 ) 魔法が解けて元に戻った。
- ( 6 ) 凍った関係が少しずつ解けてきた。
解けるの会話例
「靴紐大丈夫?」
「また解けちゃった」
「緊張してる?」
「だいぶ解けてきたよ」
「仲直りした?」
「誤解が解けて良かった」
溶けると解けるの違いまとめ
溶けるは固体の液体化、解けるは結束の解除や問題の解決を表します。
溶けるは物質の物理変化、解けるは状態や関係の変化という違いがあります。
理科では溶ける現象を学び、日常では解ける瞬間を経験します。
溶けると解けるの読み方
- 溶ける(ひらがな):とける
- 溶ける(ローマ字):tokeru
- 解ける(ひらがな):とける
- 解ける(ローマ字):tokeru