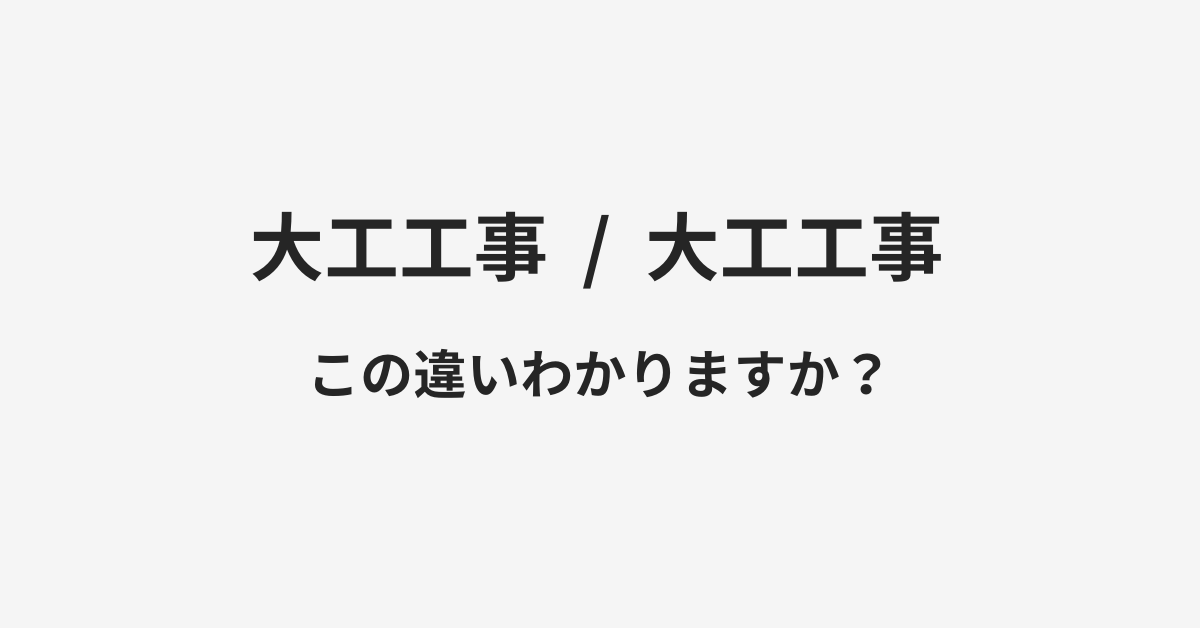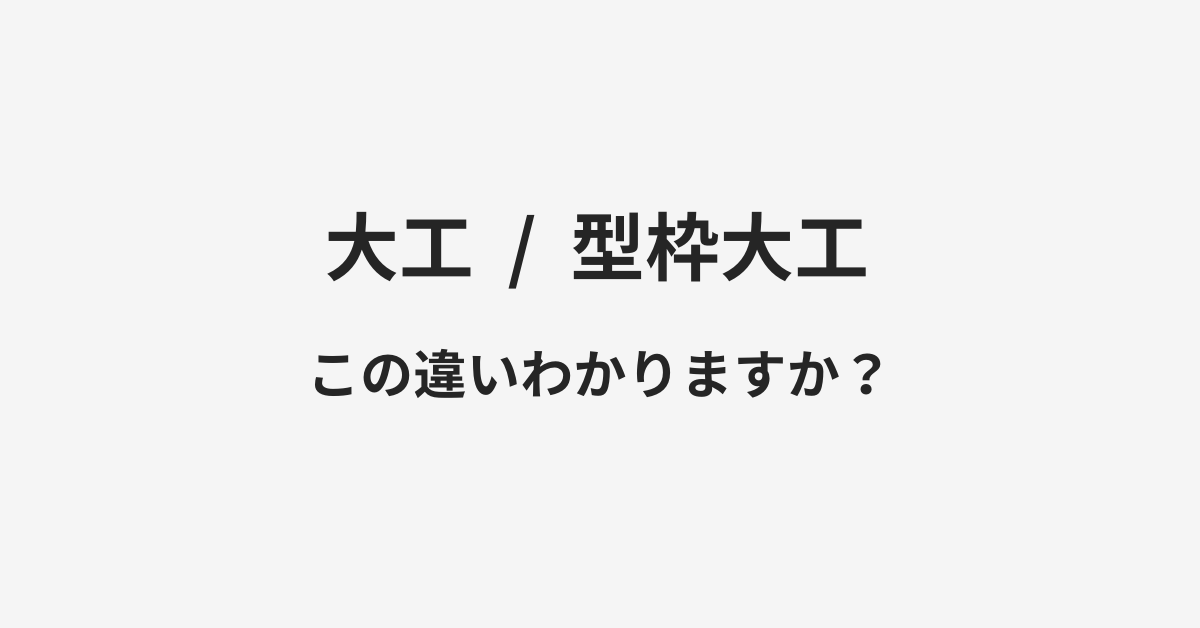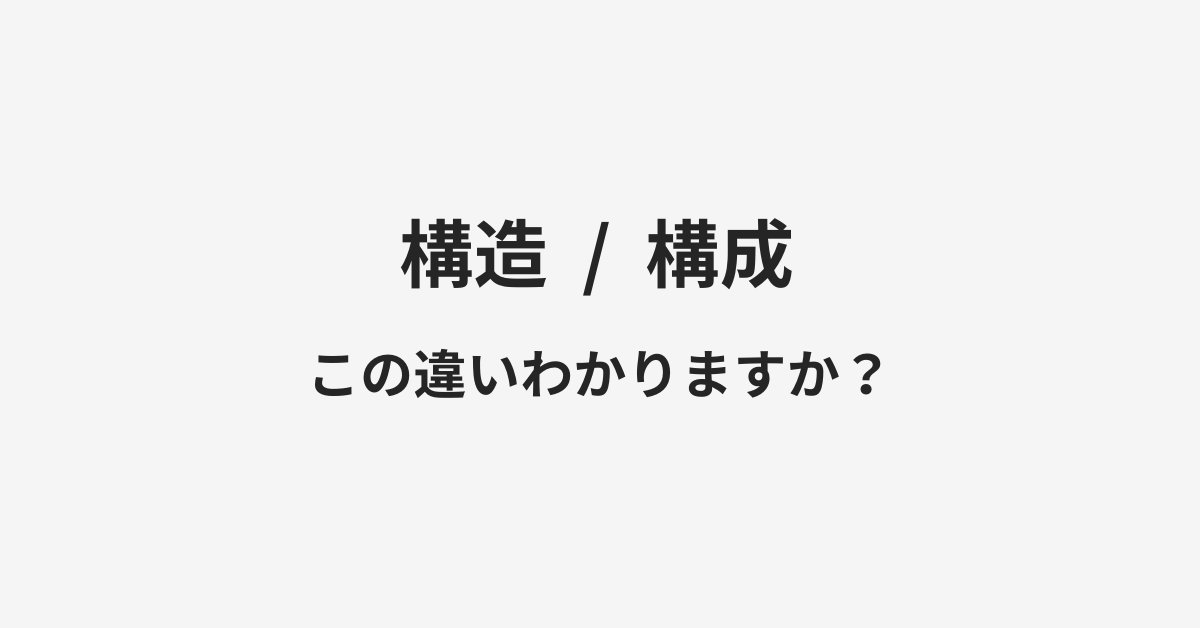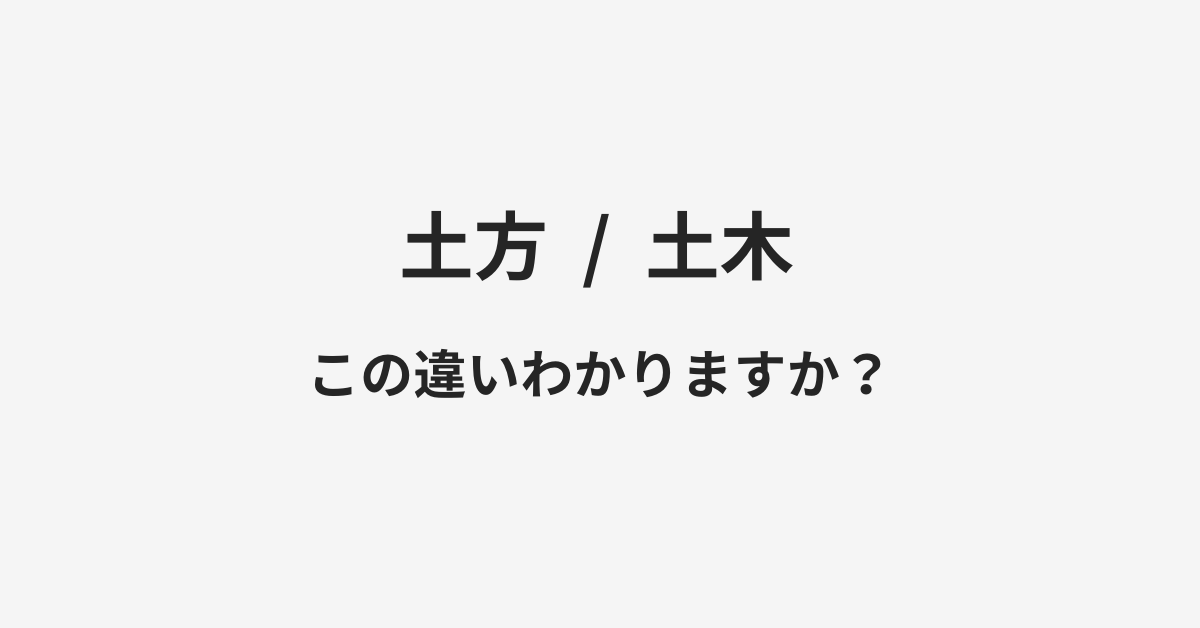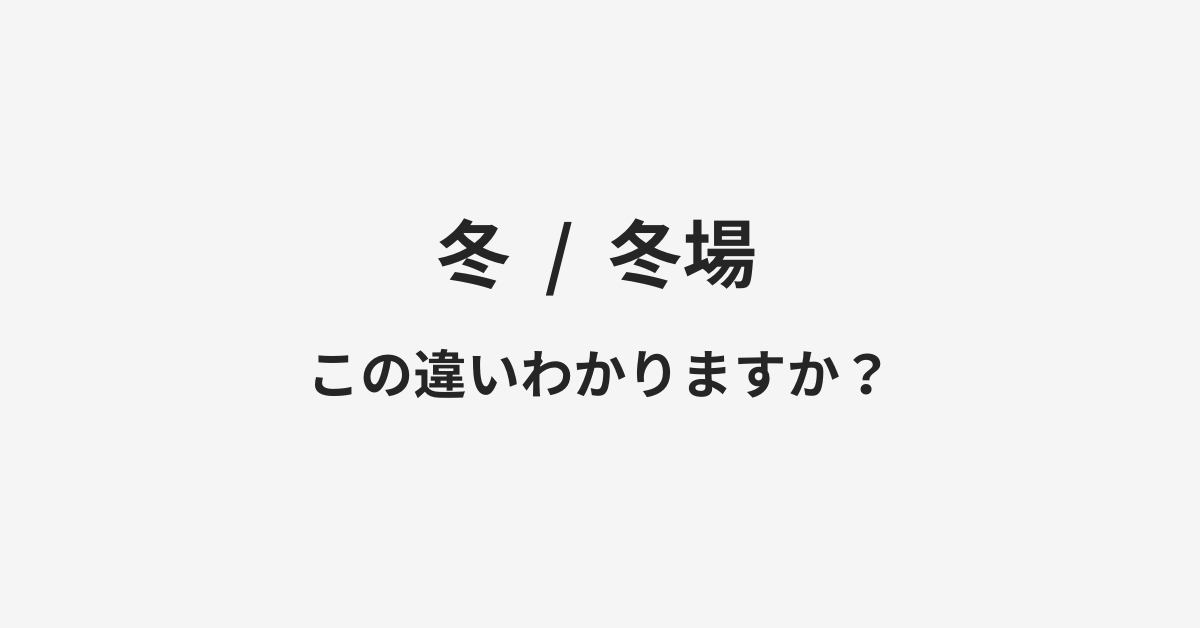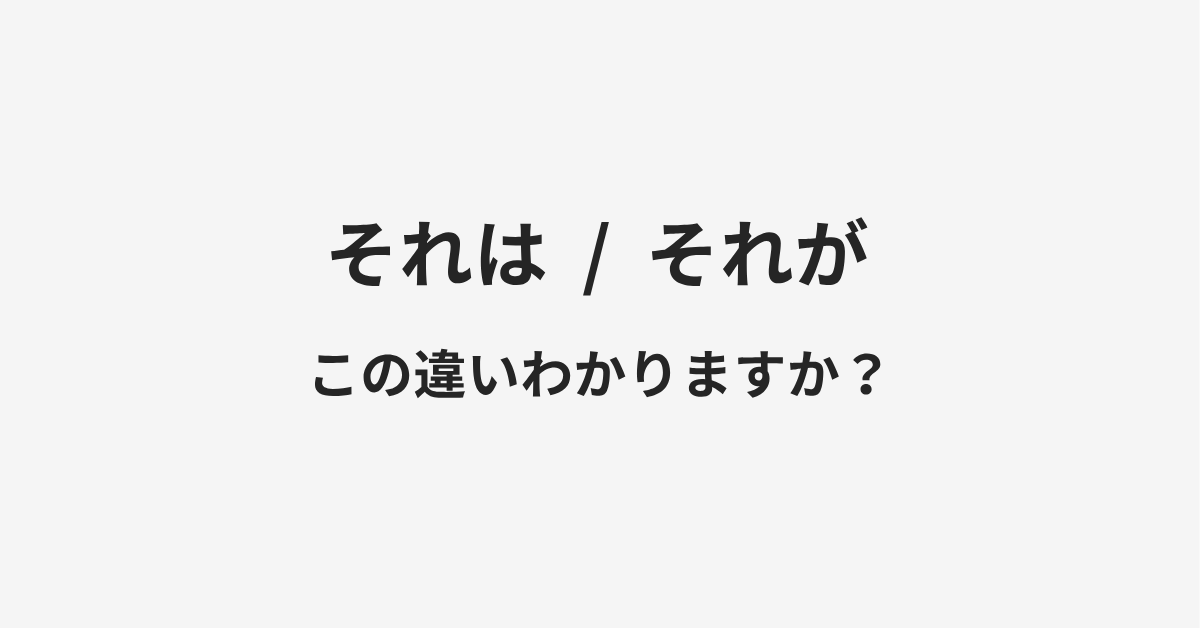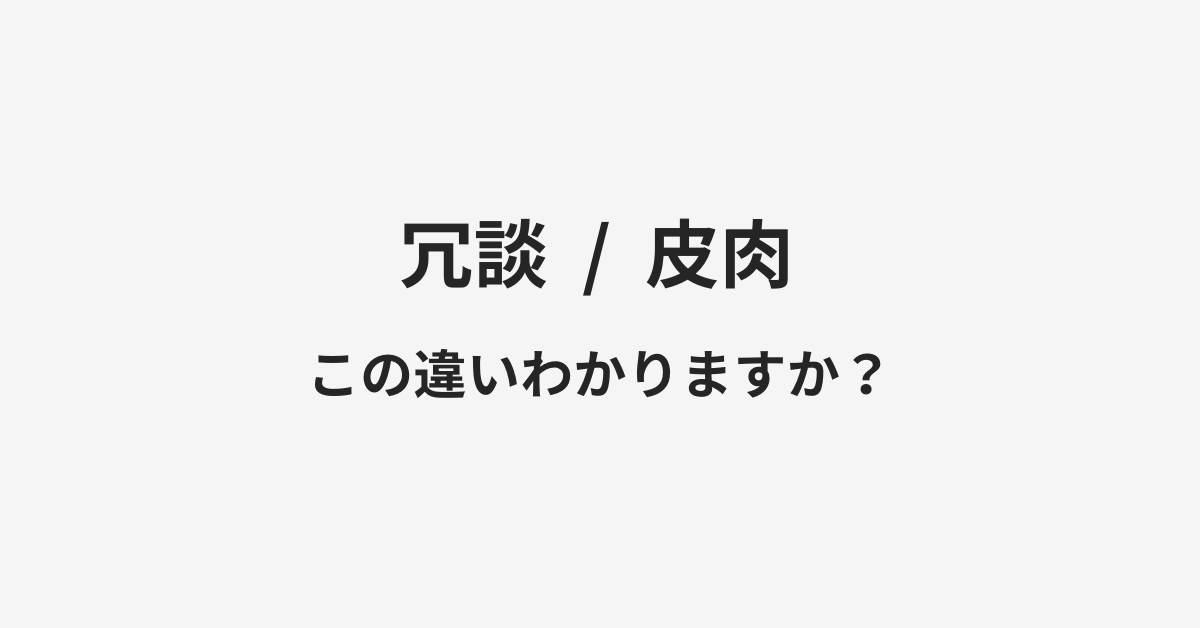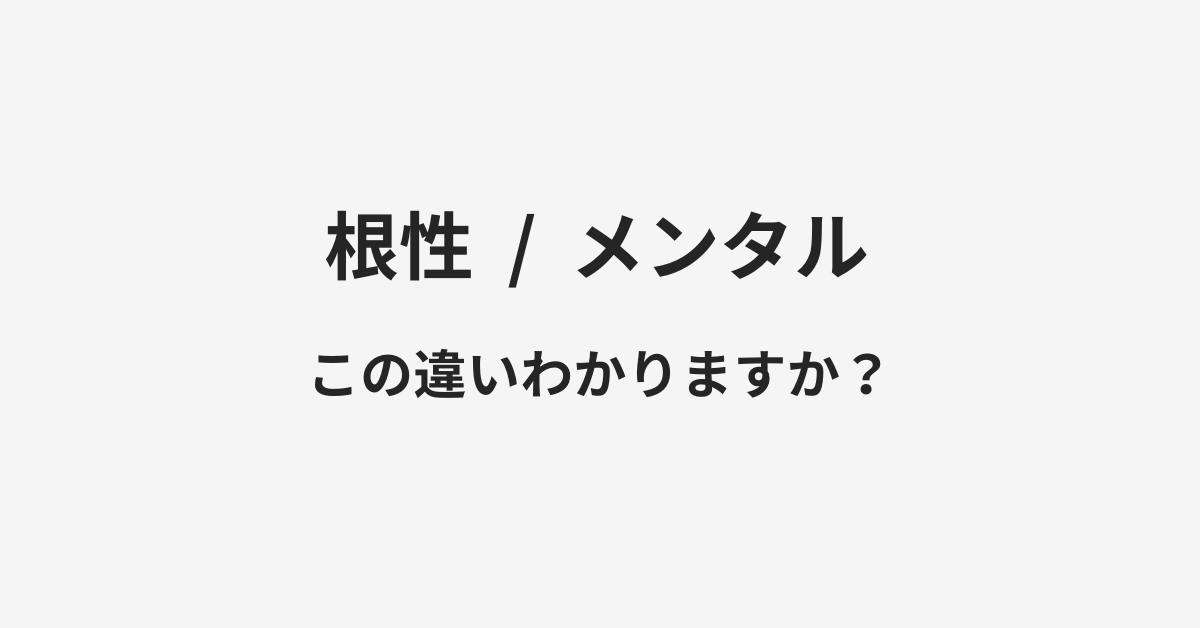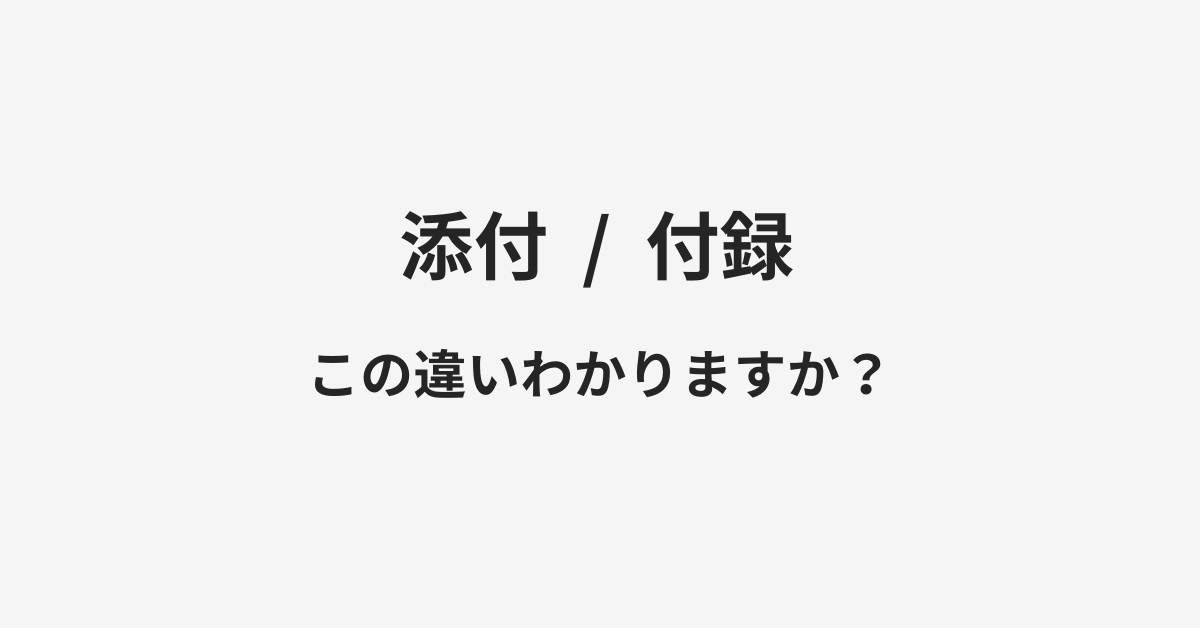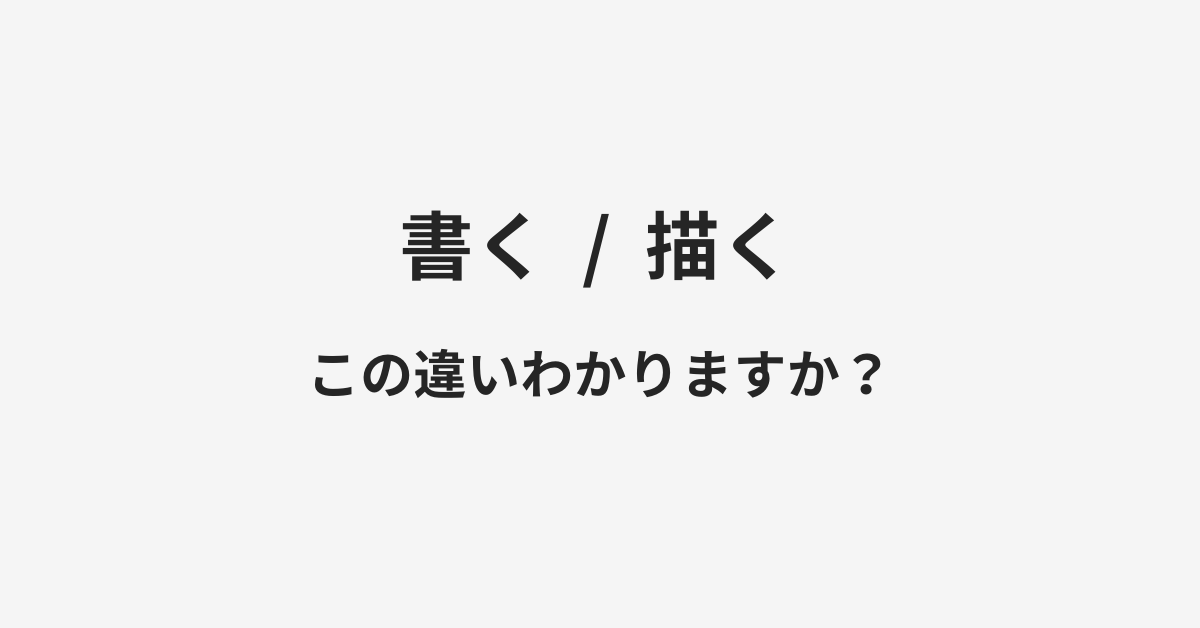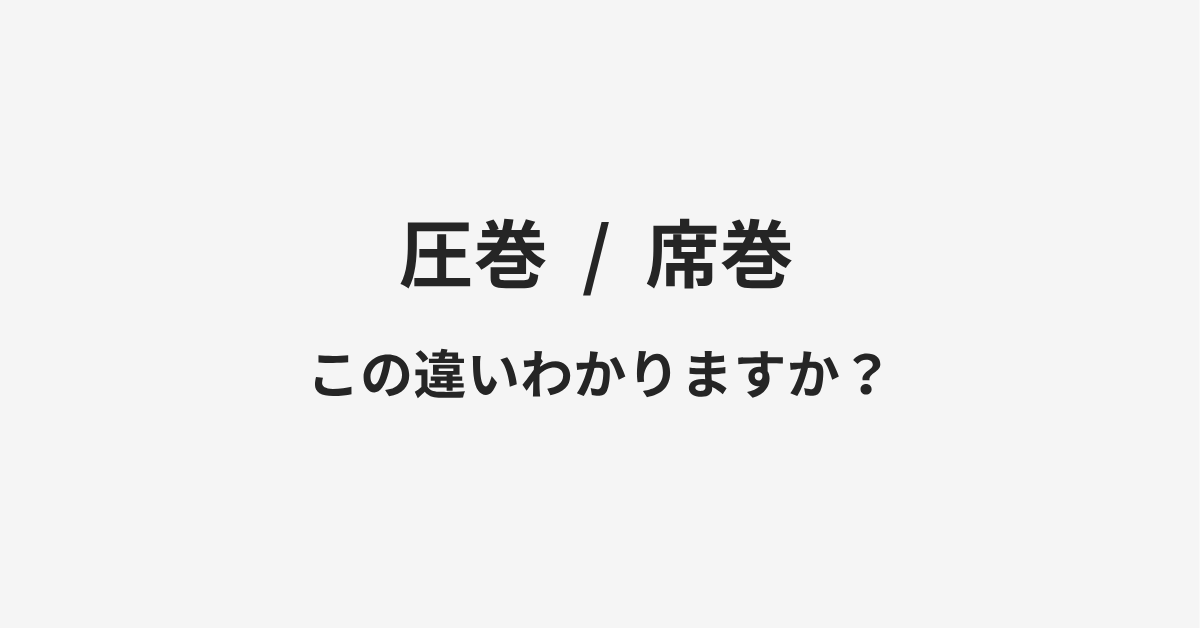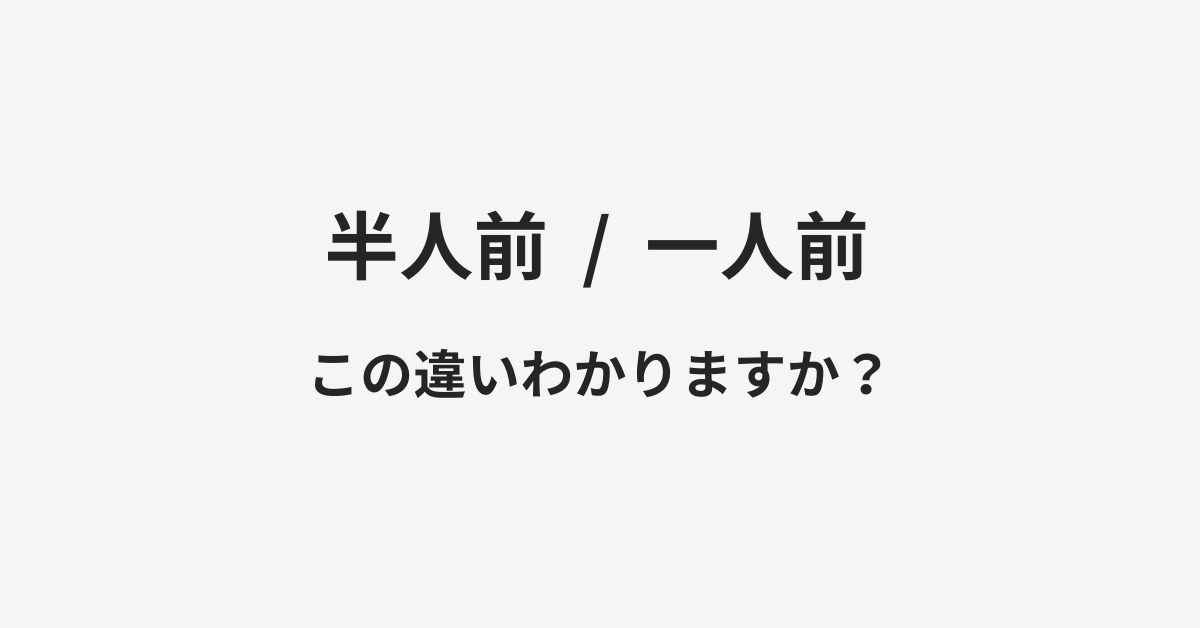【建物】と【構築物】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
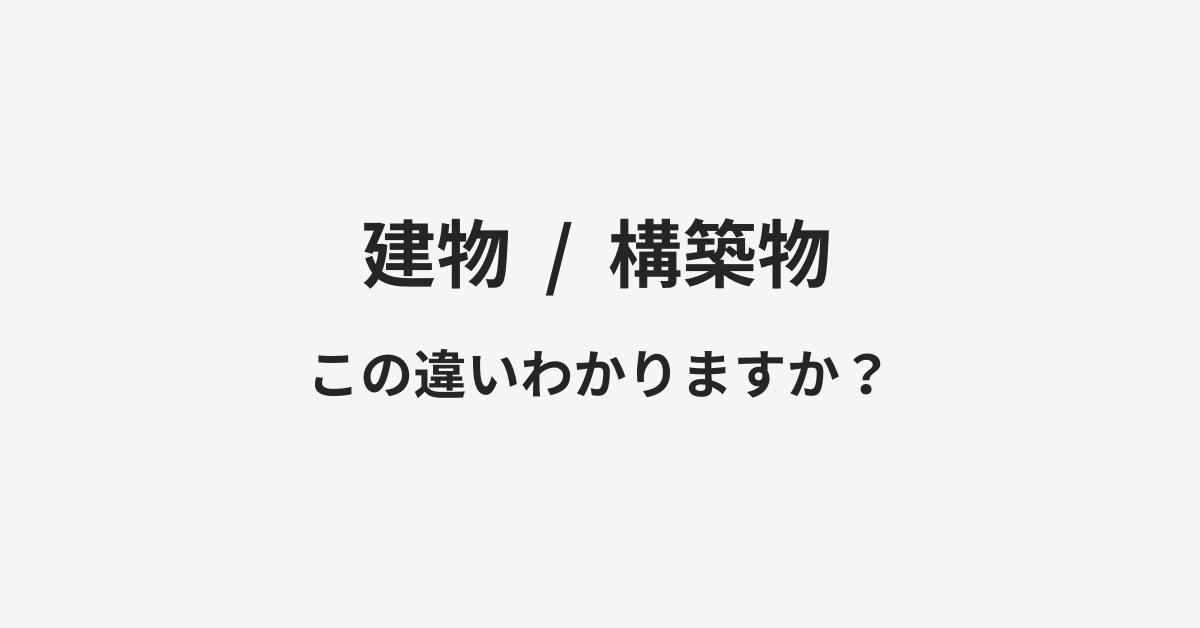
建物と構築物の分かりやすい違い
建物と構築物は、どちらも人工的に作られたものですが、その範囲と用途が異なります。
建物は「家」「ビル」など、屋根と壁があり人が中に入って使う施設です。構築物は「橋」「ダム」など、土地に固定された構造物全般を指します。
日常では、住んだり働いたりする場所は「建物」、インフラ設備は「構築物」として区別されます。
建物とは?
建物とは、屋根と壁(または柱)を持ち、人が居住、勤務、活動するための空間を提供する構造物です。住宅、オフィスビル、学校、病院、店舗など、人が中に入って利用することを前提に作られています。建築基準法では、土地に定着し、屋根と柱または壁を有するものと定義されています。
日常生活では、「あの建物は何?」「古い建物を改装する」のように、主に人が使う施設を指すときに使います。マンション、アパート、一戸建て、商業施設など、私たちの生活に身近な構造物のほとんどが建物に分類されます。
建物の特徴は、内部空間があり、その空間を人が何らかの目的で利用できることです。また、不動産としての価値を持ち、売買や賃貸の対象にもなります。耐震性や断熱性など、人が快適に過ごすための機能も重要な要素です。
建物の例文
- ( 1 ) 駅前に新しい建物が完成し、多くのテナントが入居しました。
- ( 2 ) 古い建物をリノベーションして、おしゃれなカフェにしました。
- ( 3 ) 地震に強い建物を建てるため、最新の耐震技術を採用しています。
- ( 4 ) この建物は築50年ですが、しっかりメンテナンスされています。
- ( 5 ) 高層建物からの眺めは素晴らしく、街全体を見渡せます。
- ( 6 ) 歴史的な建物を保存しながら、現代的な用途に活用しています。
建物の会話例
構築物とは?
構築物とは、土地に固定されて作られた人工的な構造物全般を指す広い概念です。建物も構築物の一種ですが、構築物には橋、トンネル、ダム、鉄塔、煙突、擁壁、道路、線路など、建物以外の様々な構造物も含まれます。土木工学や建設業界でよく使われる専門用語です。
法律や行政の文書では、「建物及びその他の構築物」という表現がよく使われ、建物とそれ以外の構築物を区別しています。例えば、固定資産税の対象となる「家屋」は建物を指し、「構築物」は建物以外の工作物を指します。
構築物の特徴は、必ずしも人が中に入って使うものではないことです。インフラストラクチャーの多くが構築物に該当し、社会生活を支える重要な役割を果たしています。耐久性や機能性が重視され、長期間にわたって使用されることが前提となっています。
構築物の例文
- ( 1 ) 新しい橋の構築物が完成し、交通の便が大幅に改善されました。
- ( 2 ) 老朽化した構築物の点検と補修工事が始まりました。
- ( 3 ) この地域には、様々な構築物が計画的に配置されています。
- ( 4 ) トンネルなどの地下構築物は、特殊な技術が必要です。
- ( 5 ) 構築物の設計には、安全性と経済性の両立が求められます。
- ( 6 ) 河川の構築物は、治水と利水の両方の機能を持っています。
構築物の会話例
建物と構築物の違いまとめ
建物と構築物の最大の違いは、対象範囲の広さです。建物は人が利用する屋内空間を持つ施設、構築物はそれを含む人工構造物全般です。
日常会話では、家やビルは「建物」、橋やダムは「構築物」と呼ぶのが一般的です。建物は構築物の一部という関係にあります。
この区別を知っていると、不動産や建設関係の話題で、より正確な表現ができるようになります。
建物と構築物の読み方
- 建物(ひらがな):たてもの
- 建物(ローマ字):tatemono
- 構築物(ひらがな):こうちくぶつ
- 構築物(ローマ字):kouchikubutsu