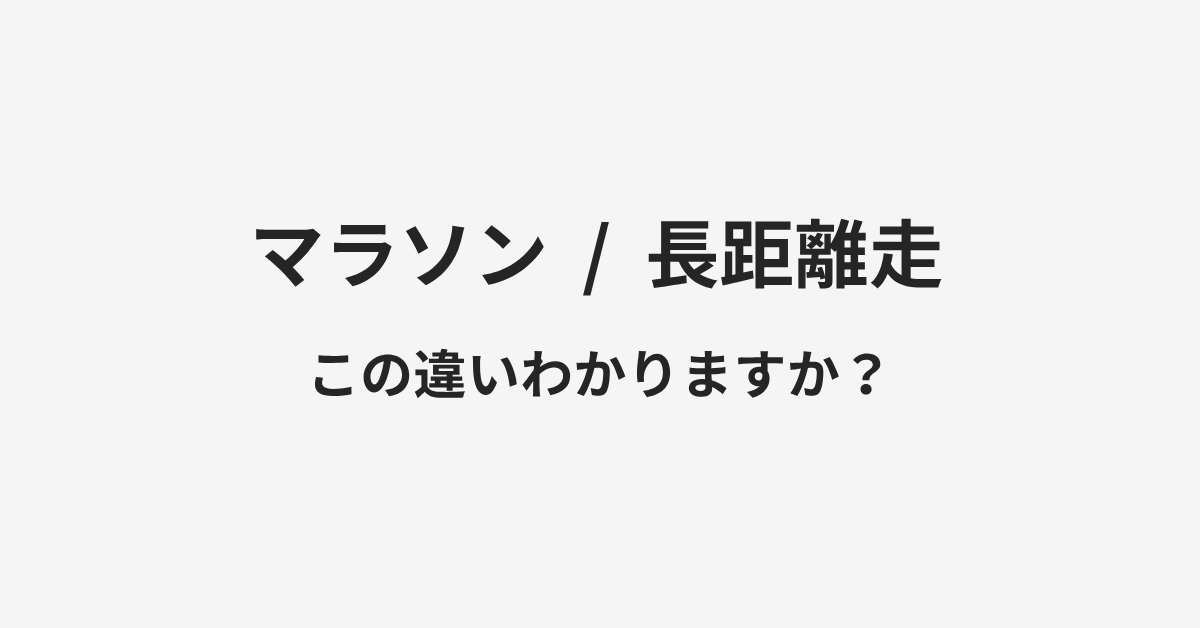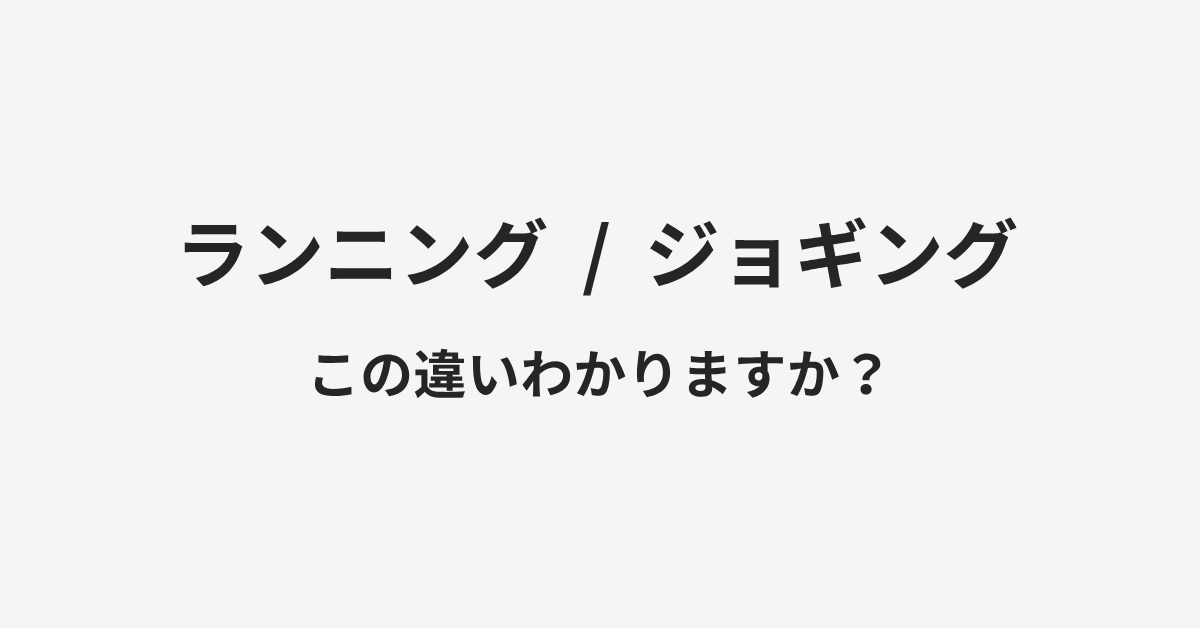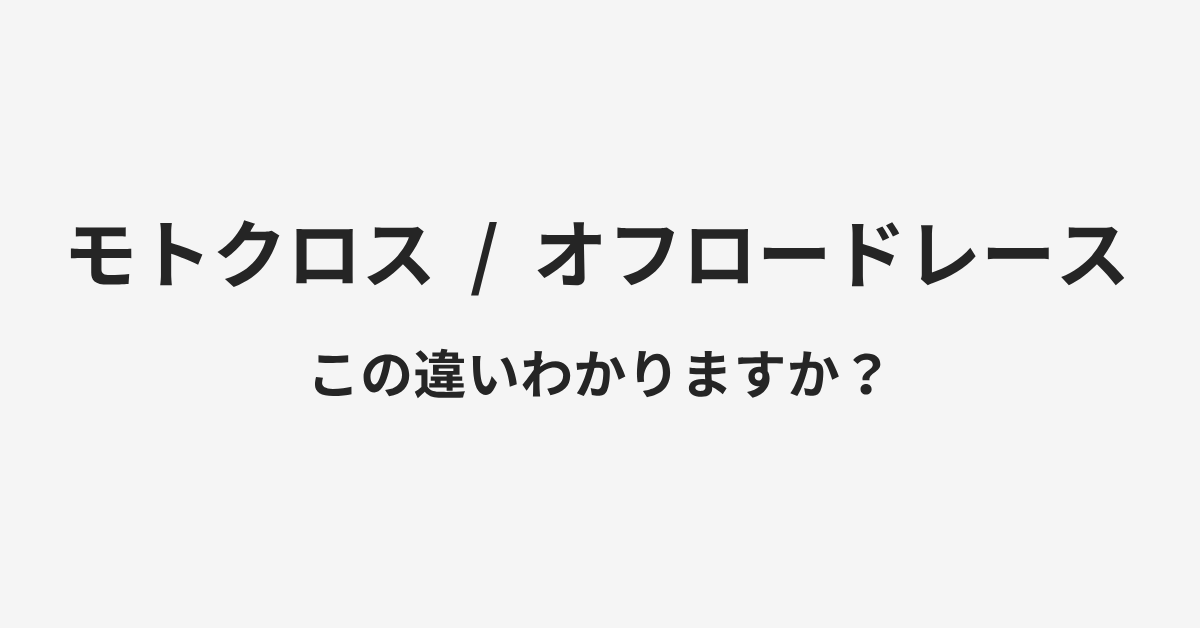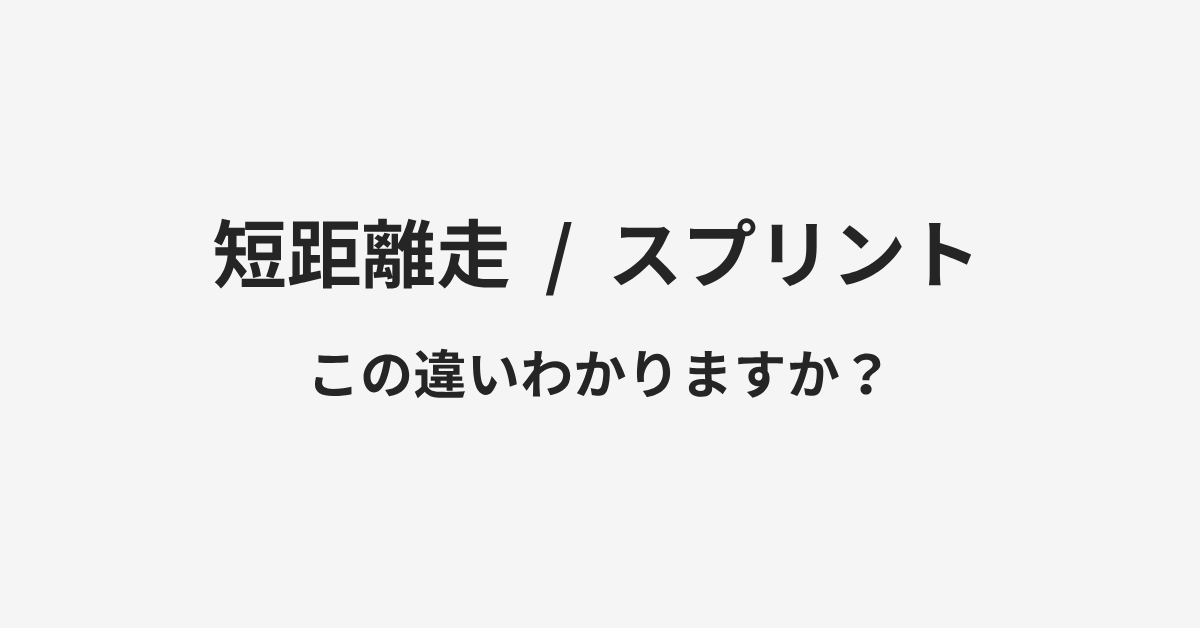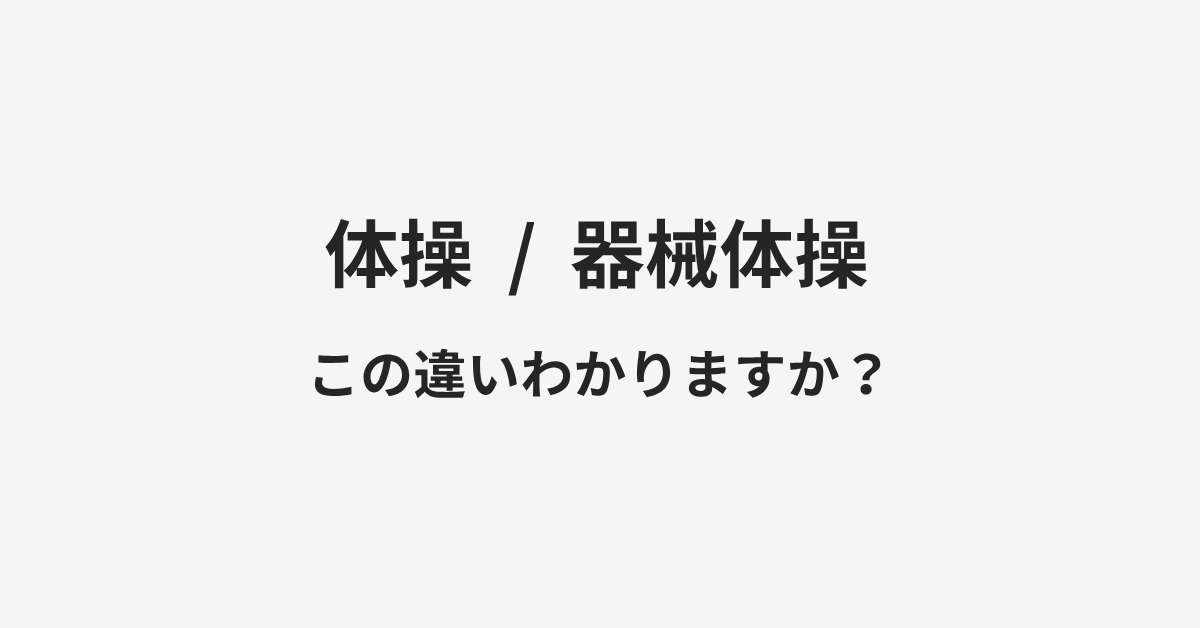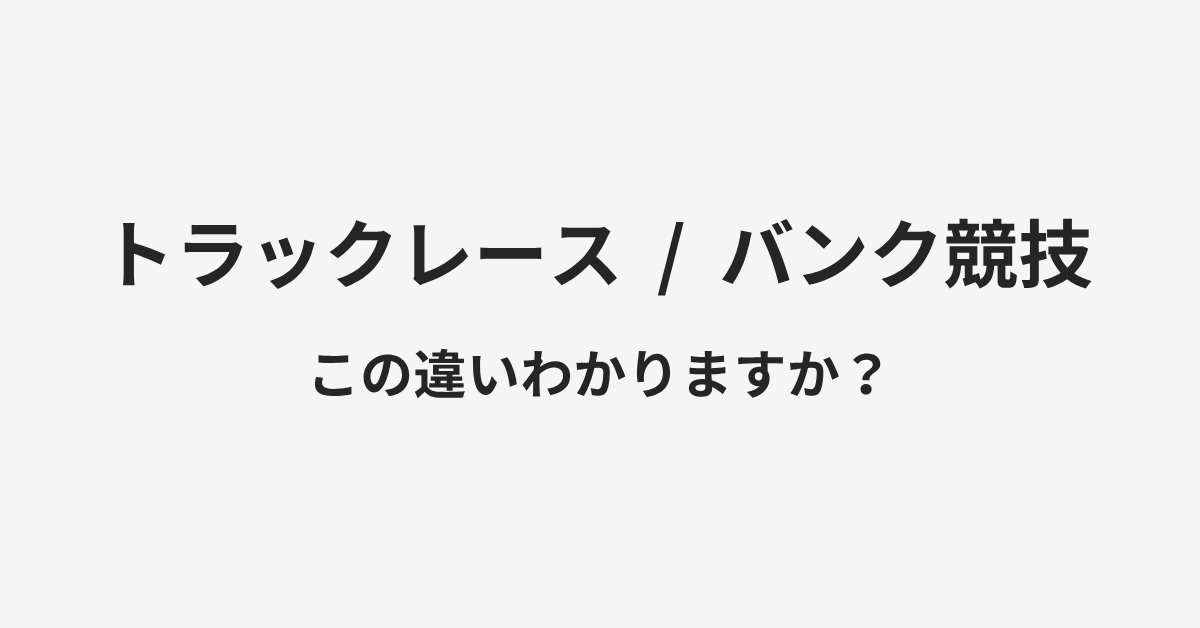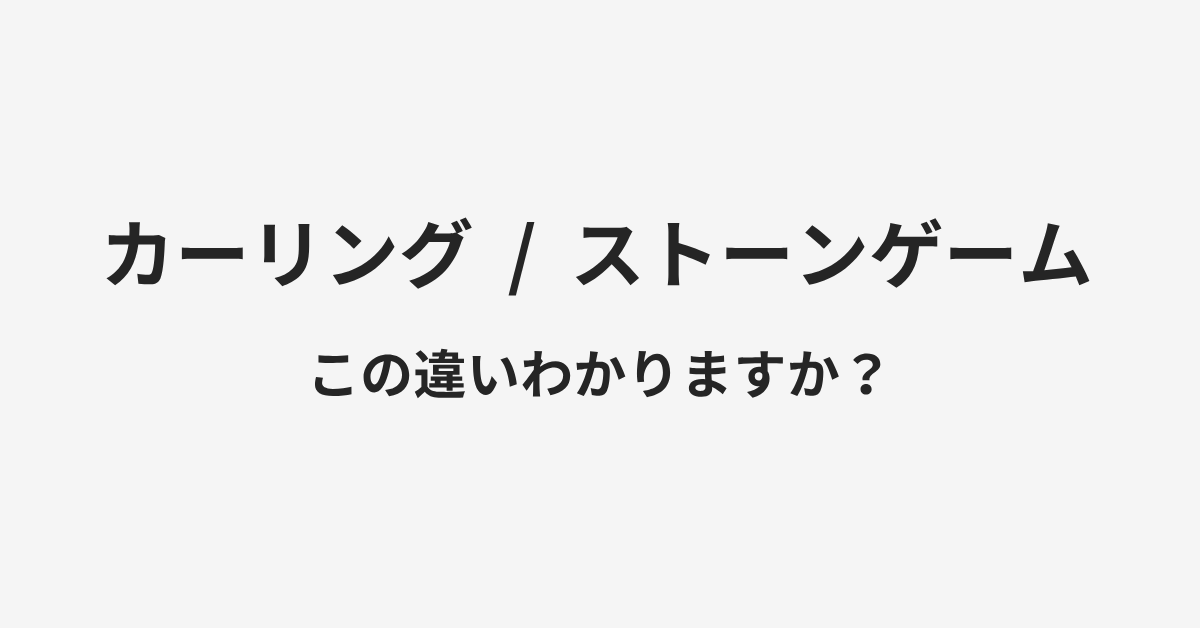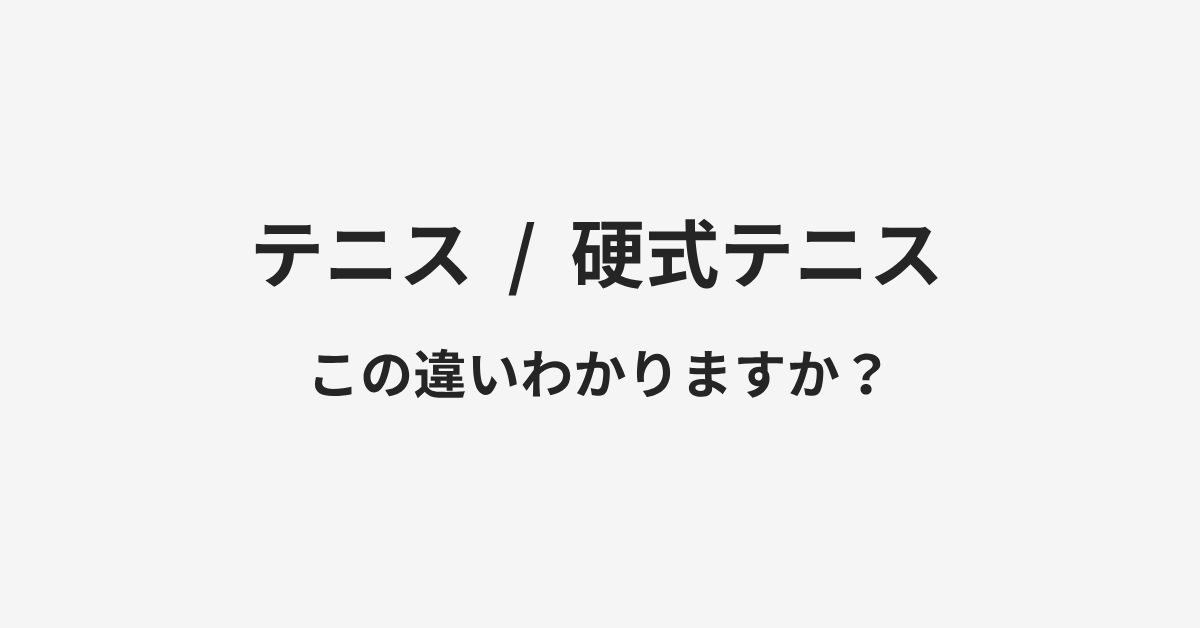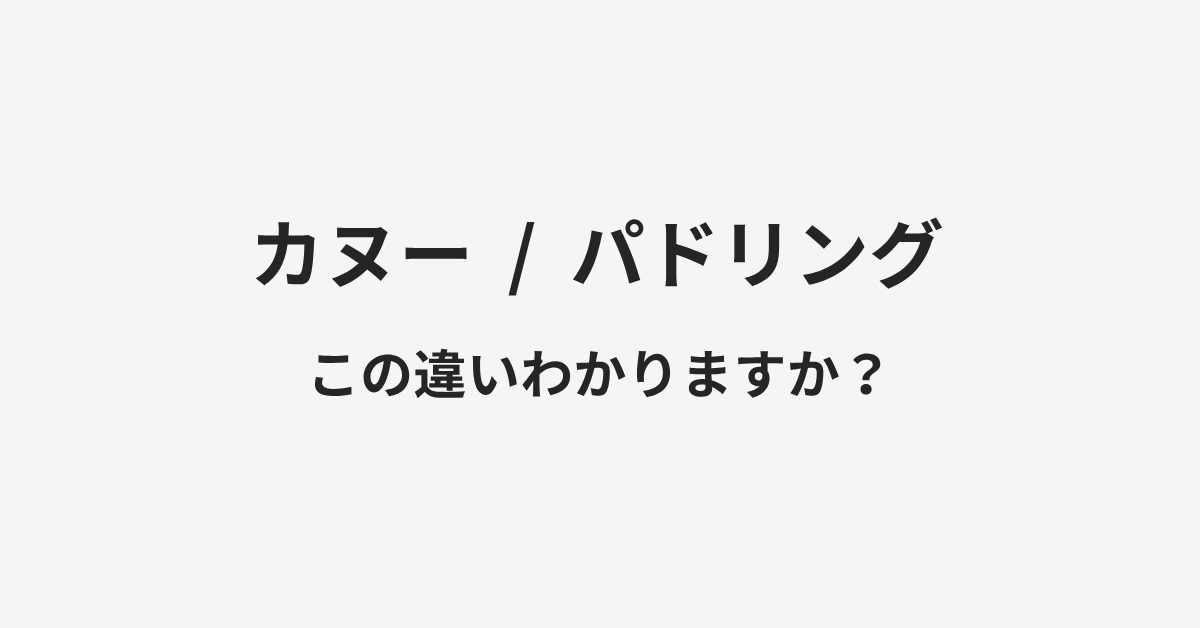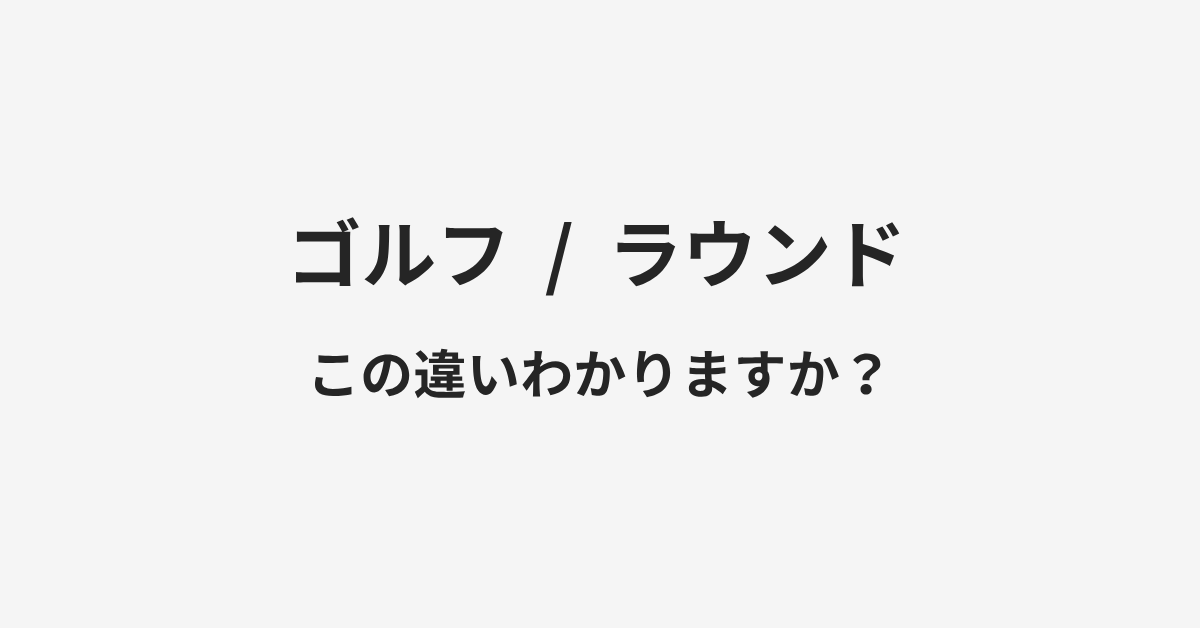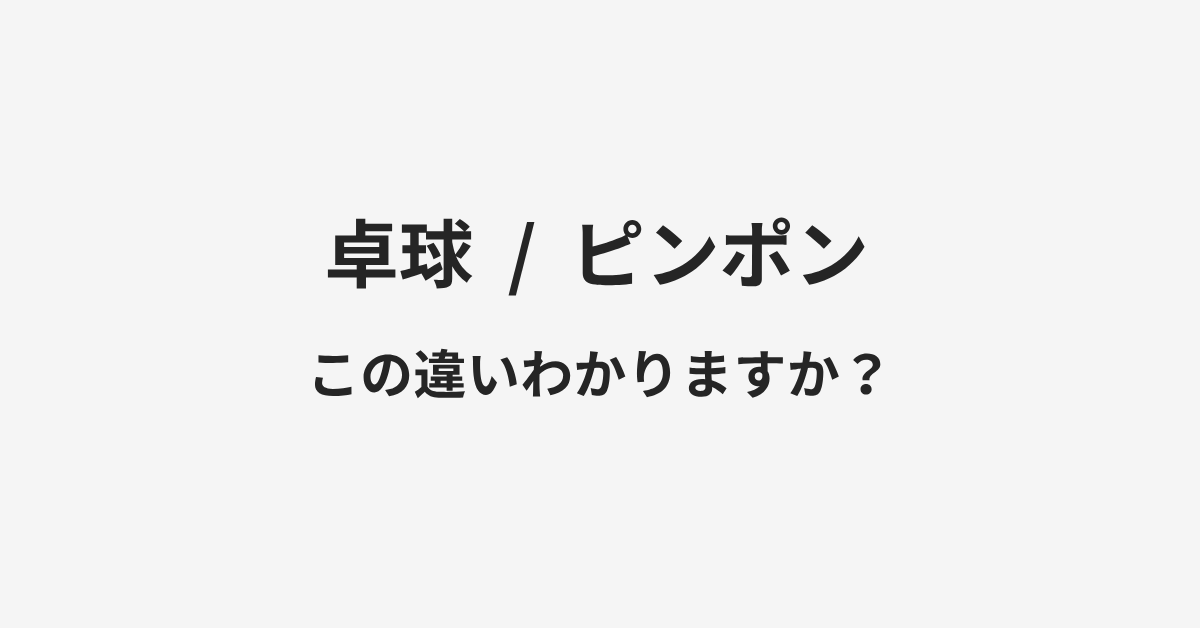【ハードル走】と【障害走】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
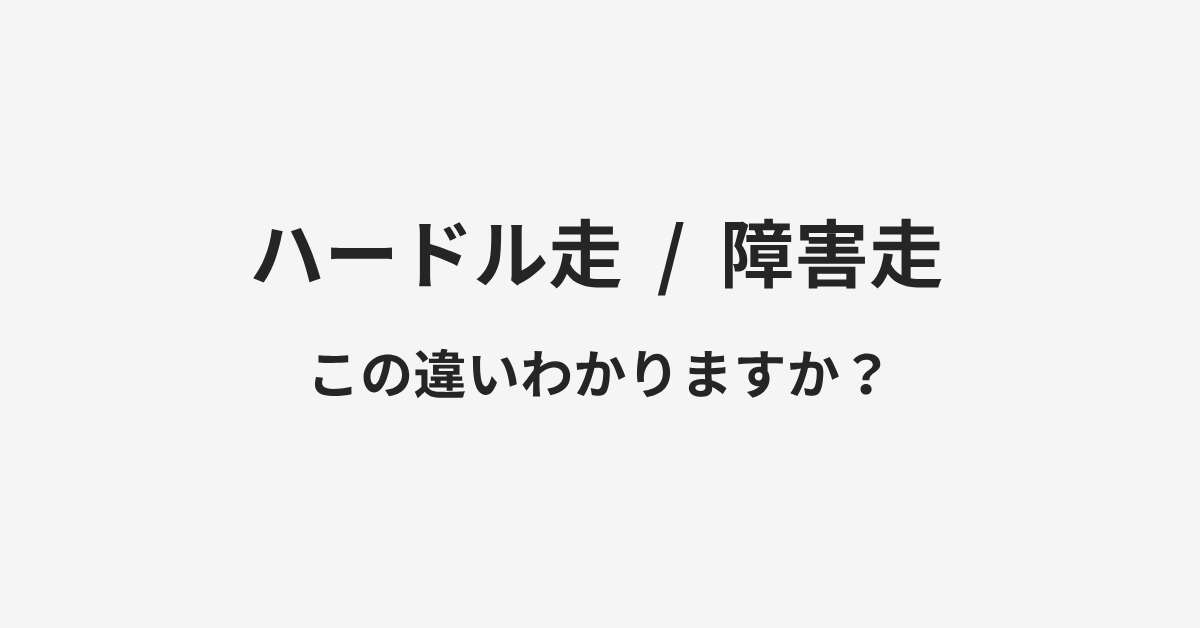
ハードル走と障害走の分かりやすい違い
ハードル走と障害走は、どちらも障害物を越えながら走る陸上競技ですが、種目の内容が全く異なります。ハードル走は、等間隔に置かれた倒れるハードルを越えながらスピードを競う短・中距離種目です。
障害走は、主に3000m障害を指し、固定された障害物と水濠みずごうを越えながら走る長距離種目です。
スポーツビジネスでは、それぞれの競技特性を理解し、適切な施設整備やトレーニングプログラムの開発が求められます。
ハードル走とは?
ハードル走は、一定間隔で配置されたハードル高さ76.2cm〜106.7cmを跳び越えながら走る陸上競技です。主な種目は男子110mハードル、女子100mハードル、男女400mハードルで、スピードを維持しながら効率的にハードルをクリアする技術が求められます。ハードルは倒れる構造で、接触しても前進できます。
日本のハードル走は、近年著しい発展を遂げています。特に男子110mハードルでは、日本記録が13秒台前半まで向上し、世界大会でも決勝進出者が出るようになりました。この背景には、ハードリング技術の科学的分析と、専門的なトレーニング方法の確立があります。
ビジネス面では、ハードル走は観客に分かりやすく、スピード感あふれる種目として人気があります。ハードル専用の練習器具ミニハードル、調整式ハードルなどの市場も拡大しており、トレーニング施設では必須の設備となっています。企業の陸上部でも、ハードル走は花形種目の一つです。
ハードル走の例文
- ( 1 ) 日本選手権のハードル走で好記録が続出しました。
- ( 2 ) ハードル走の技術革新が、日本のレベルアップにつながっています。
- ( 3 ) ハードル走専門のコーチを募集しています。
- ( 4 ) 高度なハードル走技術の指導には、専門知識が不可欠です。
- ( 5 ) ハードル走用の最新トレーニング器具を導入します。
- ( 6 ) 可変式ハードルなど、ハードル走の練習効率を上げる投資は重要です。
ハードル走の会話例
障害走とは?
障害走は、主に3000m障害3000mSC:スティープルチェースを指す陸上競技です。トラック7周半3000mの間に、固定された障害物28個と水濠7個を越えながら走ります。障害物の高さは91.4cm男子・76.2cm女子で、倒れない構造のため、飛び越えるか上に乗って越える必要があります。
日本の障害走は、持久力と跳躍力を兼ね備えた特殊な種目として位置づけられています。マラソンや駅伝が盛んな日本では、長距離選手が障害走に転向するケースも多く、独特の強化体系が構築されています。水濠の技術習得が特に重要で、専門的な指導が必要です。
施設面では、障害走には水濠を含む特殊な設備が必要なため、実施できる競技場が限られます。このため、障害走専門の選手は少なく、希少性の高い種目となっています。しかし、その独特の過酷さと技術性から、観客には人気があり、大会の注目種目となることが多いです。
障害走の例文
- ( 1 ) 3000m障害走の日本代表選手が決定しました。
- ( 2 ) 過酷な障害走で世界と戦える選手の育成は、大きな成果です。
- ( 3 ) 障害走の水濠設備を改修する必要があります。
- ( 4 ) 安全で適正な障害走の実施には、水濠の管理が欠かせません。
- ( 5 ) 障害走の普及プログラムを立ち上げたいのですが。
- ( 6 ) 特殊な障害走の魅力を伝える工夫が必要ですね。
障害走の会話例
ハードル走と障害走の違いまとめ
ハードル走と障害走は、障害物を越える点は共通ですが、全く異なる競技特性を持ちます。ハードル走はスピード系種目で技術の精密さが勝負、障害走は持久系種目で総合的な強さが求められます。
施設整備やトレーニング方法も大きく異なるため、それぞれの特性を理解した上での取り組みが必要です。
スポーツビジネスにおいては、両種目の違いを明確に理解し、適切な強化策や普及活動を展開することが重要となります。
ハードル走と障害走の読み方
- ハードル走(ひらがな):はーどるそう
- ハードル走(ローマ字):ha-dorusou
- 障害走(ひらがな):しょうがいそう
- 障害走(ローマ字):shougaisou