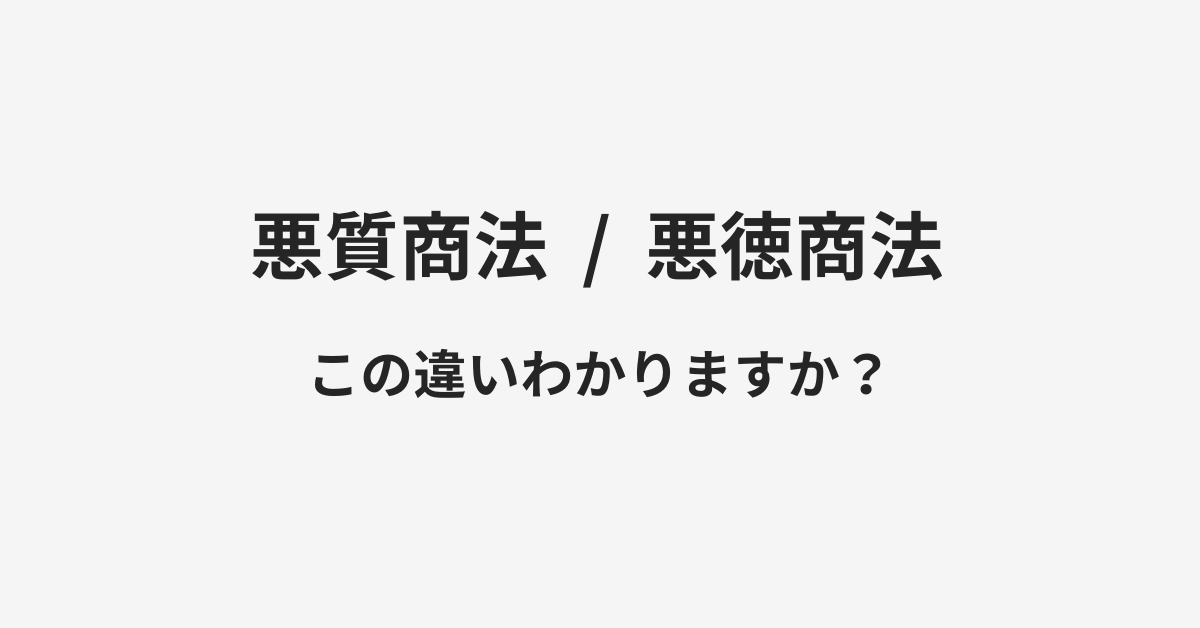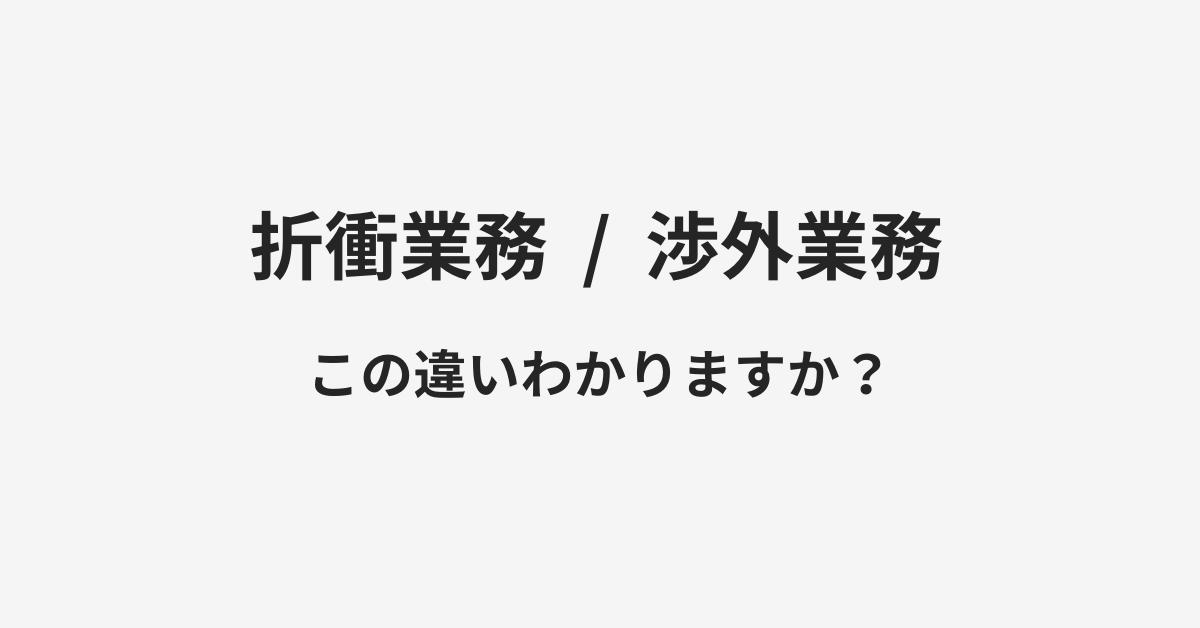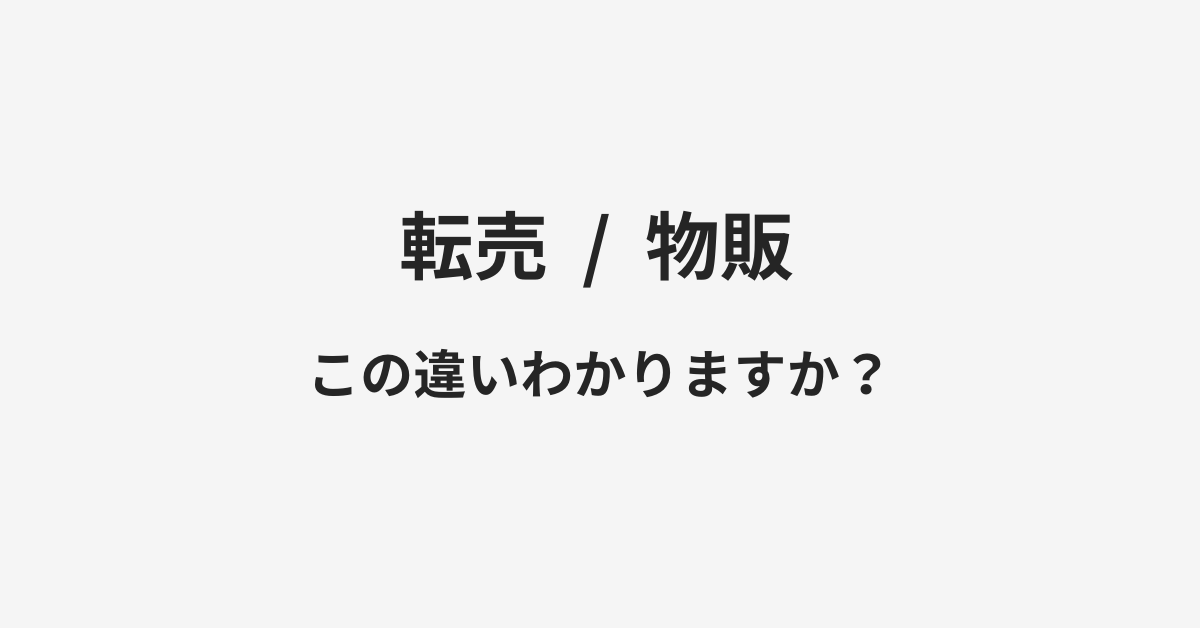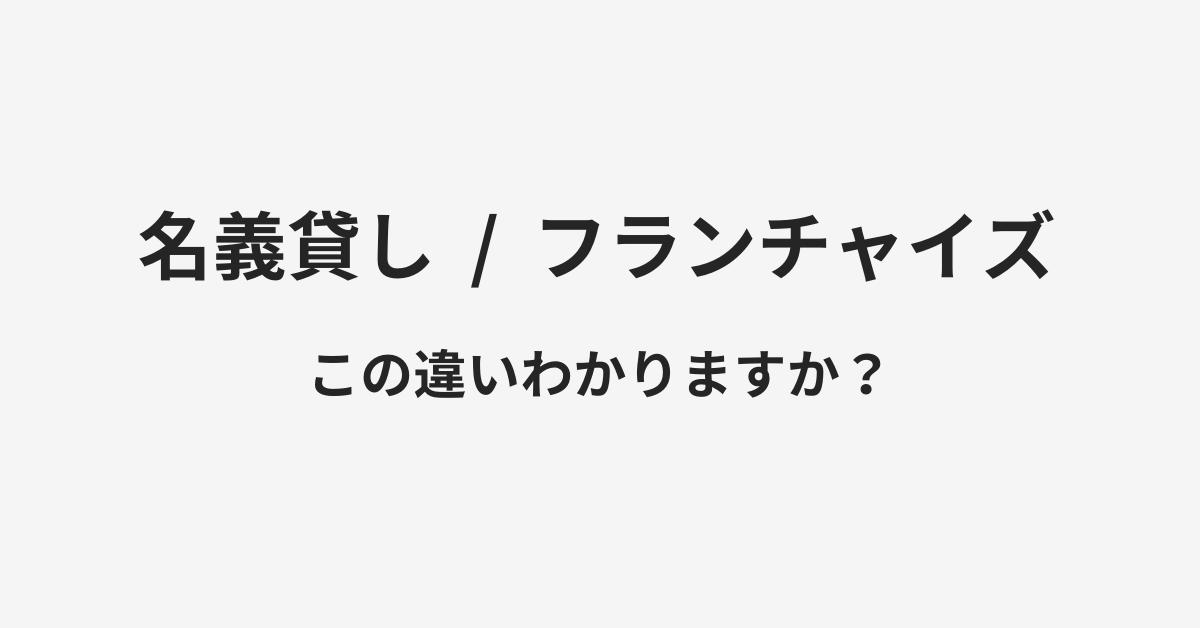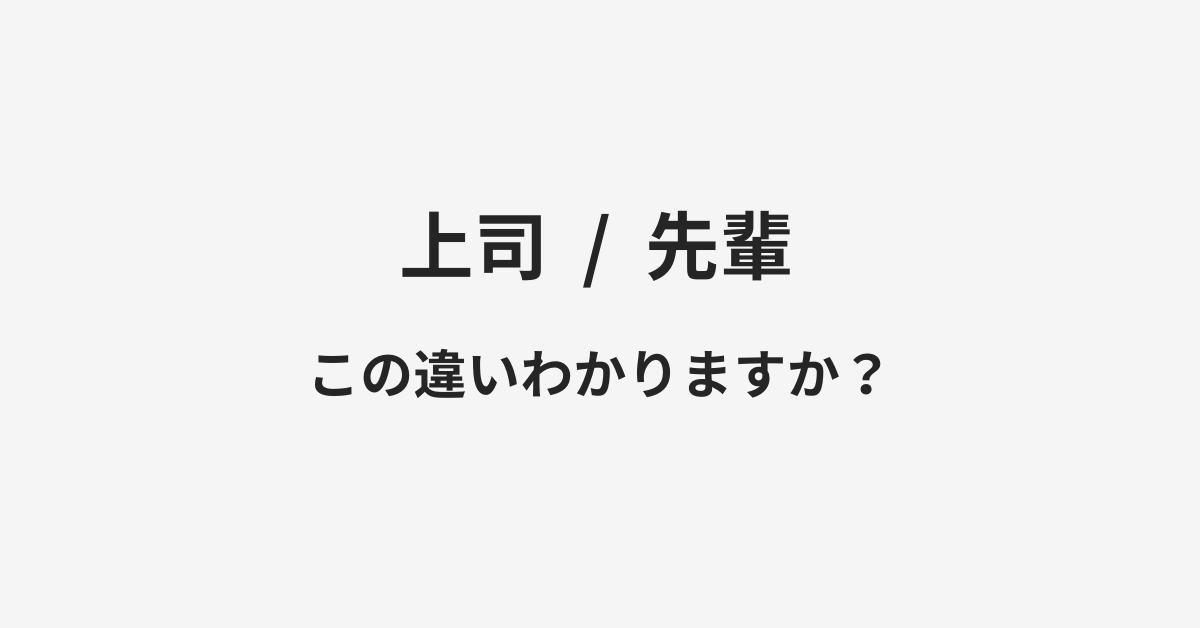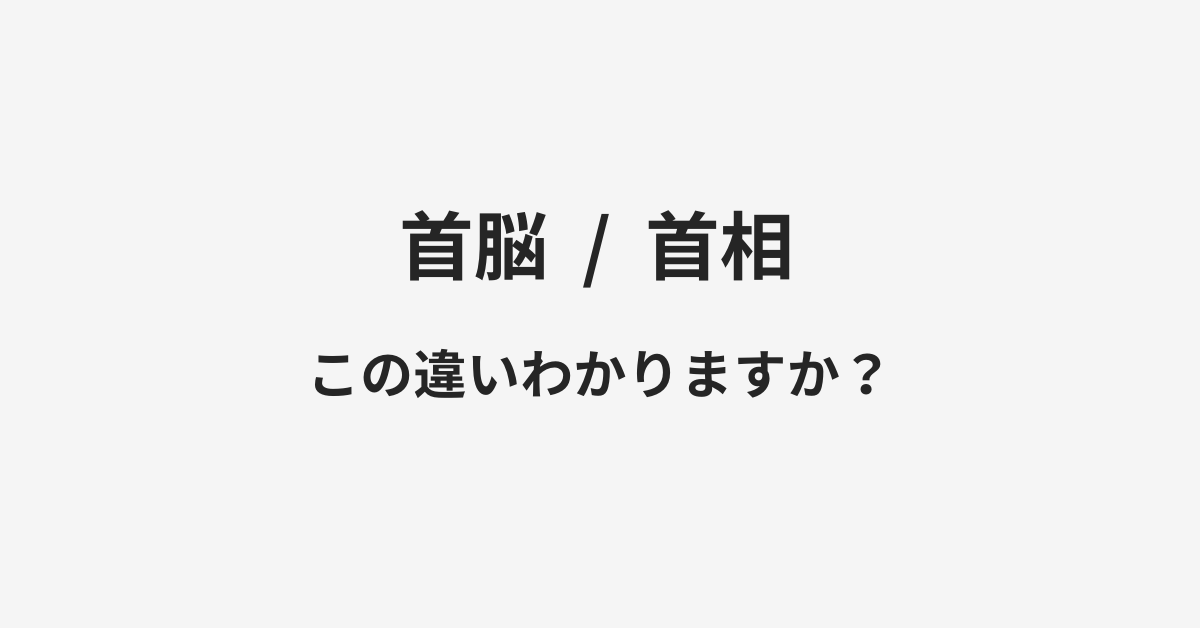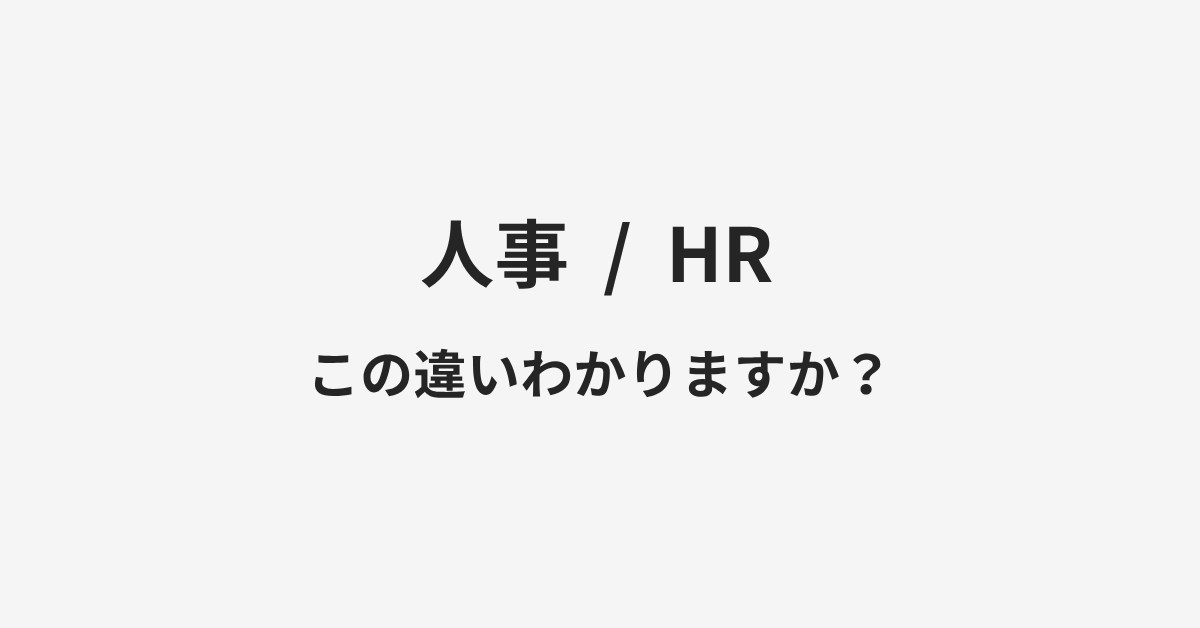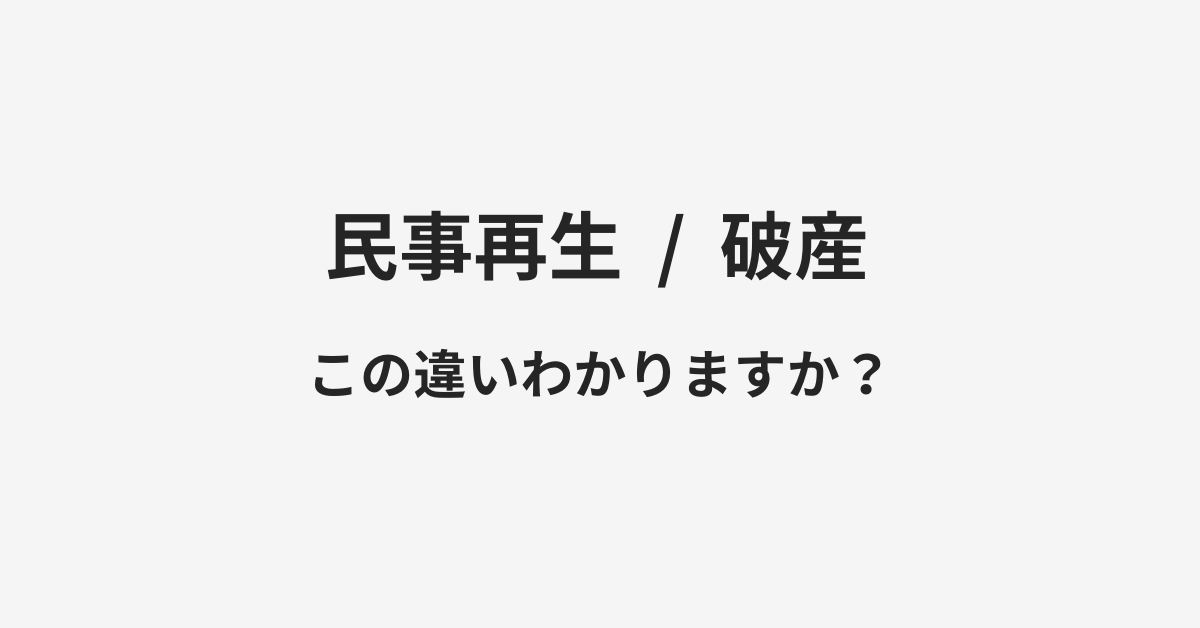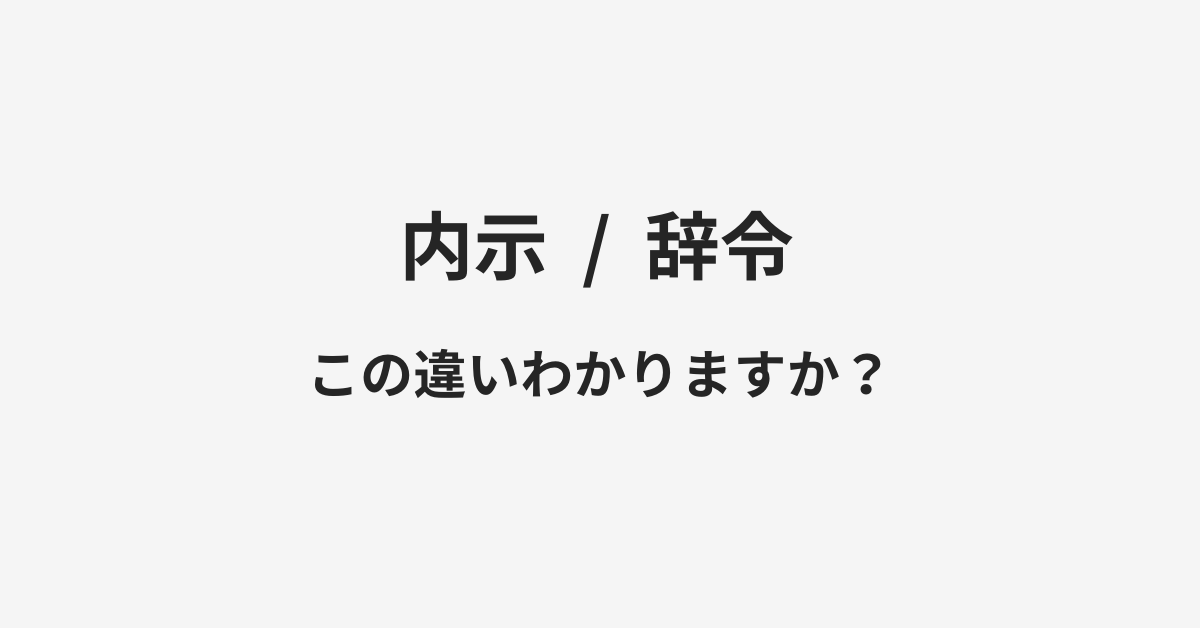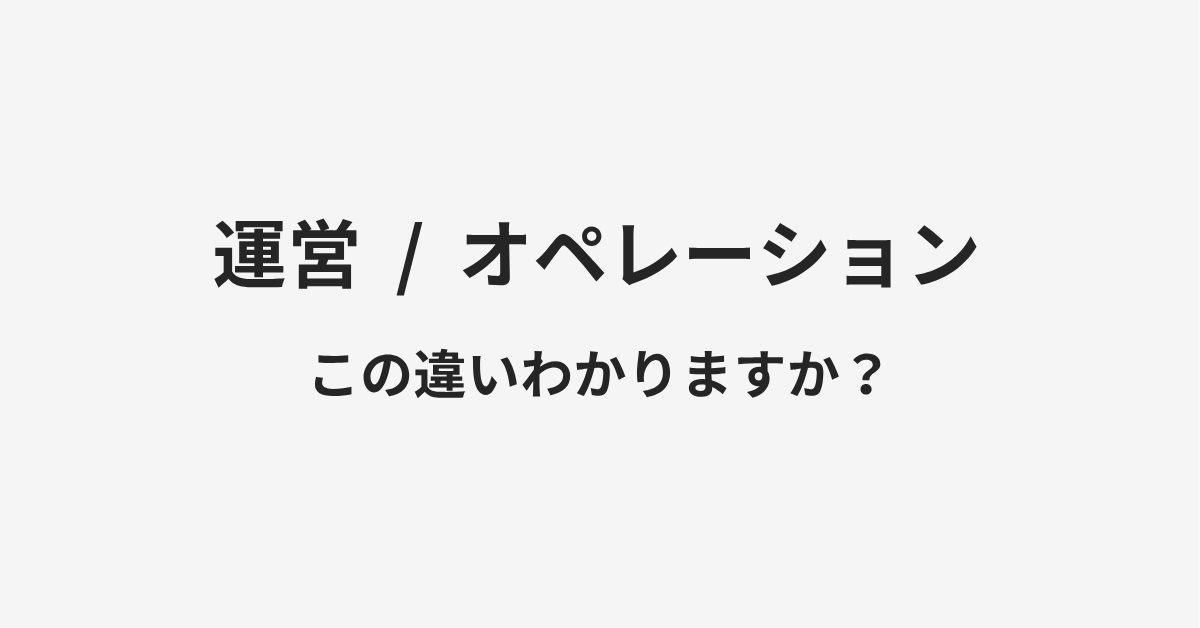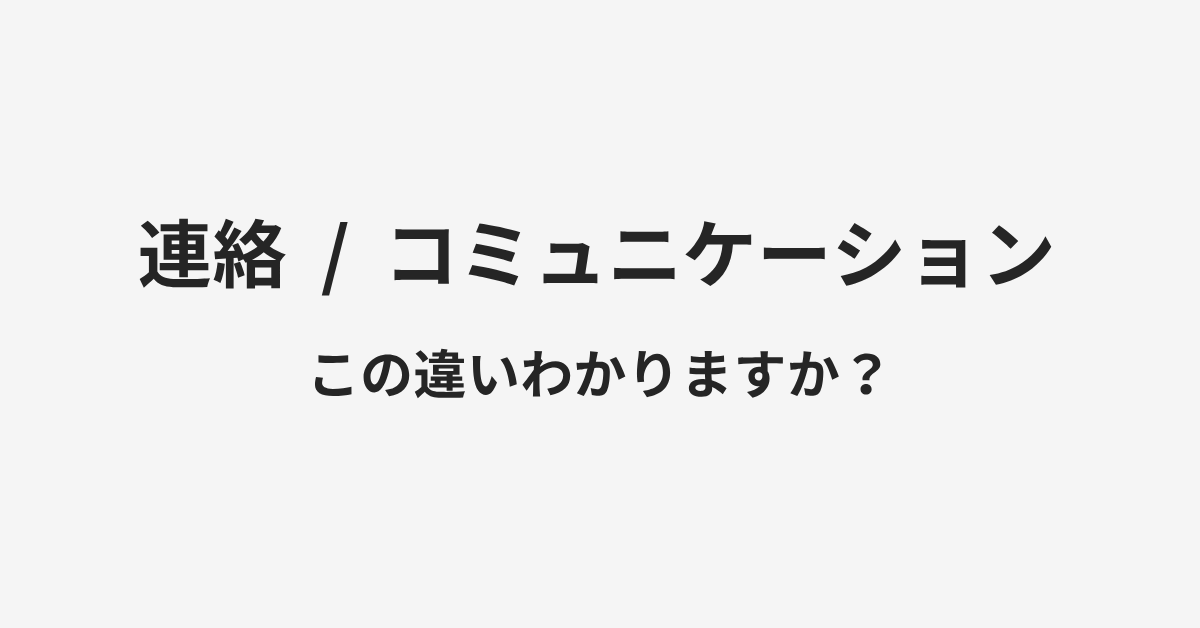【利益相反取引】と【競業避止義務】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説

利益相反取引と競業避止義務の分かりやすい違い
利益相反取引と競業避止義務は、どちらも会社の利益を守る制度ですが、対象が異なります。
利益相反取引は会社と役員間の取引を規制し、不正を防ぎます。
競業避止義務は従業員の競合他社での活動を制限し、機密情報や顧客の流出を防ぎます。
利益相反取引とは?
利益相反取引とは、取締役や執行役員などの会社役員が、自己または第三者の利益のために会社の利益と相反する取引を行うことです。会社法により規制され、取締役会の承認が必要となります。直接取引(役員が会社と直接契約)と間接取引(役員が第三者を介して会社と取引)の2種類があります。
典型例として、取締役が経営する別会社と自社との取引、会社資産の役員への売却、役員への金銭貸付などがあります。これらの取引は、役員が自己の利益を優先し、会社に損害を与える可能性があるため、厳格に管理されます。
「利益相反取引の承認を得る」「利益相反取引に該当する」のように、会社と役員の利益が対立する取引を表現する際に使用される言葉です。
利益相反取引の例文
- ( 1 ) 取締役が個人で所有する不動産を会社に賃貸する場合、利益相反取引として承認が必要だ。
- ( 2 ) 利益相反取引の承認を得ずに契約した場合、取締役は損害賠償責任を負う。
- ( 3 ) 子会社との取引も、親会社取締役にとっては利益相反取引となる可能性がある。
- ( 4 ) 利益相反取引について、取締役会議事録に詳細を記録することが重要だ。
- ( 5 ) 監査役は利益相反取引が適正に行われているか、厳格にチェックする責任がある。
- ( 6 ) 利益相反取引の開示は、コーポレートガバナンスの重要な要素となっている。
利益相反取引の会話例
競業避止義務とは?
競業避止義務とは、従業員や役員が在職中または退職後に、勤務先と競合する事業を行ったり、競合他社で働いたりすることを制限する義務です。会社の営業秘密、顧客情報、ノウハウなどの流出を防ぎ、競争上の優位性を保護することが目的です。
在職中は当然に負う義務ですが、退職後については雇用契約書や誓約書で明確に定める必要があります。ただし、職業選択の自由との兼ね合いから、退職後の競業避止は期間、地域、職種などを合理的に限定する必要があり、過度な制限は無効となる可能性があります。
「競業避止義務違反で訴える」「競業避止義務契約を締結する」のように、競合活動の制限を表現する際に使用される言葉です。
競業避止義務の例文
- ( 1 ) 退職する営業部長に、2年間の競業避止義務を課す契約を結んでもらった。
- ( 2 ) 競業避止義務違反が発覚し、元従業員に対して差止請求を行うことになった。
- ( 3 ) 重要な技術情報を扱う従業員には、より厳格な競業避止義務を設定している。
- ( 4 ) 競業避止義務の対価として、退職後も一定期間手当を支給する制度を導入した。
- ( 5 ) 転職先が競合他社かどうか、競業避止義務の観点から慎重に検討する必要がある。
- ( 6 ) 競業避止義務契約は、合理的な範囲内でないと裁判で無効とされるリスクがある。
競業避止義務の会話例
利益相反取引と競業避止義務の違いまとめ
利益相反取引と競業避止義務は、どちらも会社の利益保護を目的としますが、規制の対象と内容が異なります。
利益相反取引は役員の取引行為を事前承認制により管理し、会社財産の不正流出を防ぎます。競業避止義務は従業員の競合活動を制限し、情報やノウハウの流出を防ぎます。
両制度を適切に運用することで、会社の健全な経営が維持されます。
利益相反取引と競業避止義務の読み方
- 利益相反取引(ひらがな):りえきそうはんとりひき
- 利益相反取引(ローマ字):riekisouhanntorihiki
- 競業避止義務(ひらがな):きょうぎょうひしぎむ
- 競業避止義務(ローマ字):kyougyouhishigimu