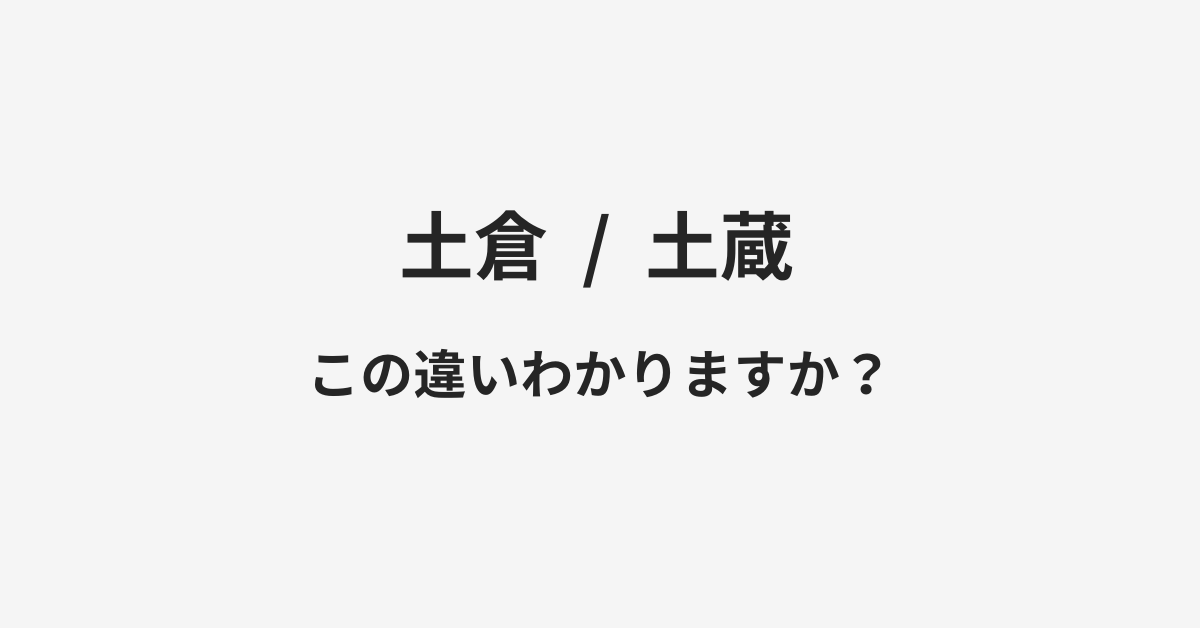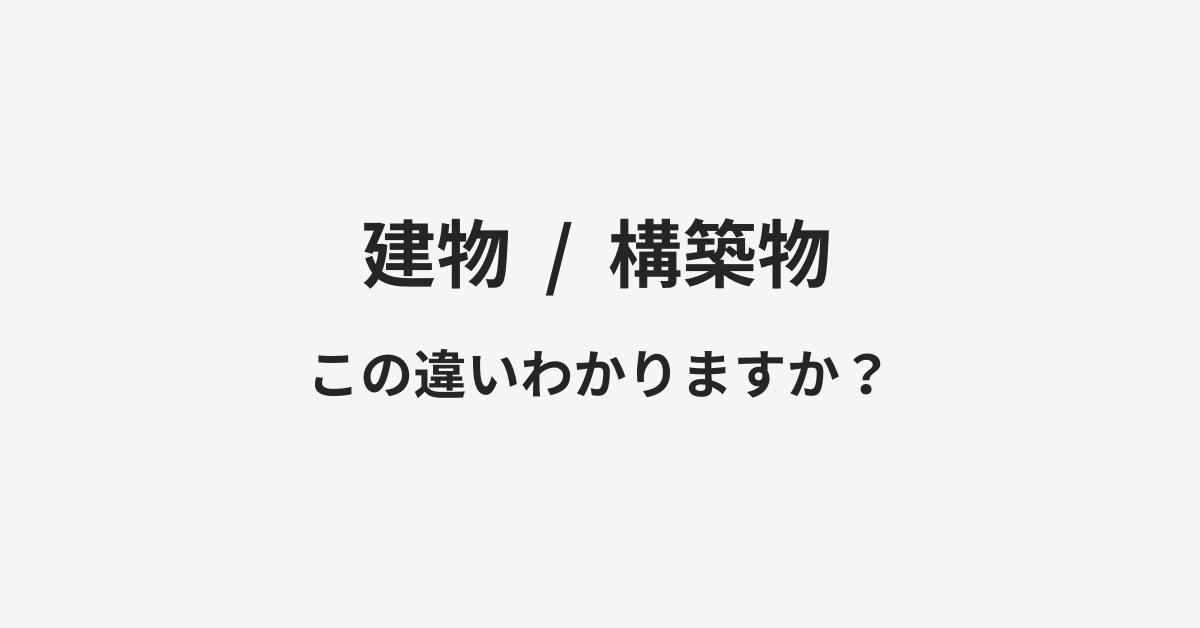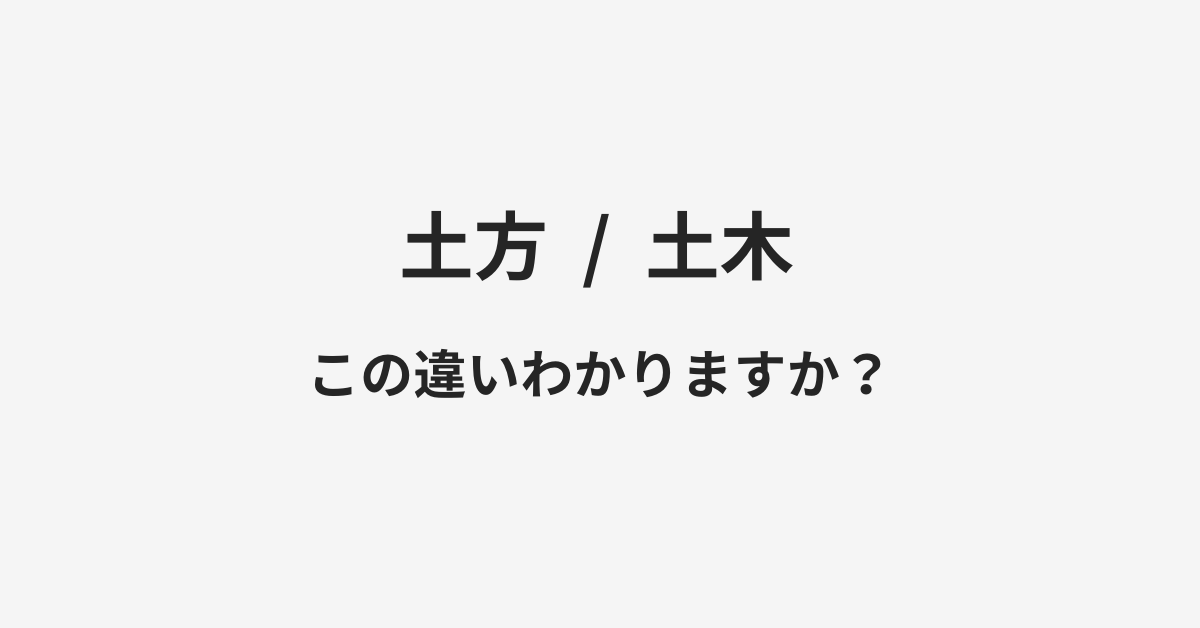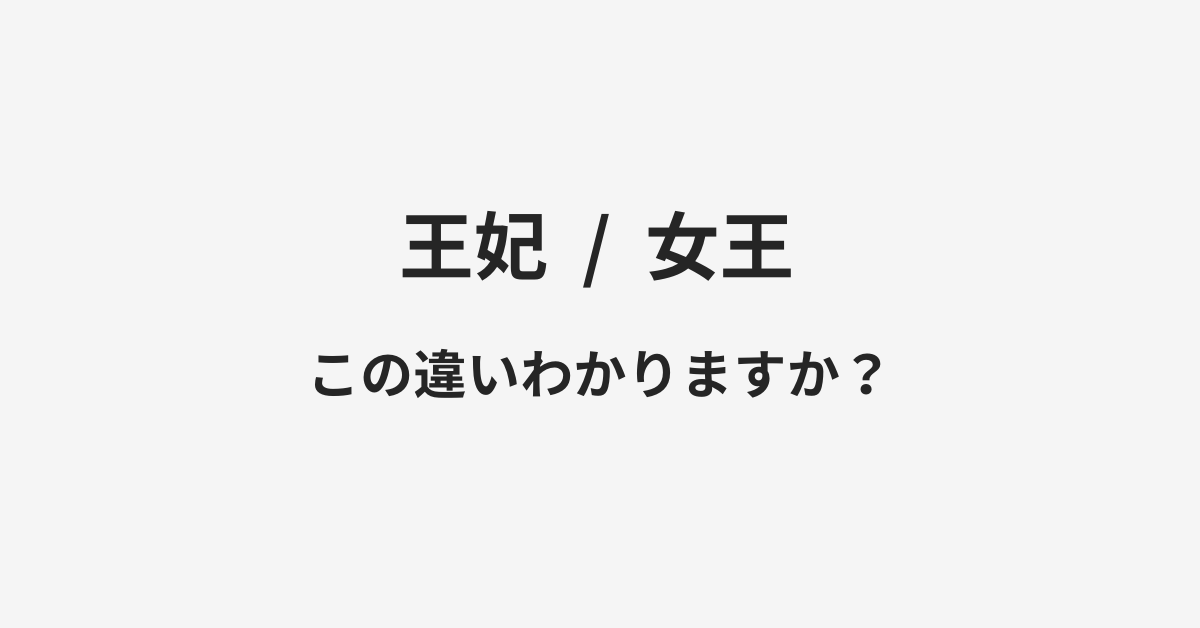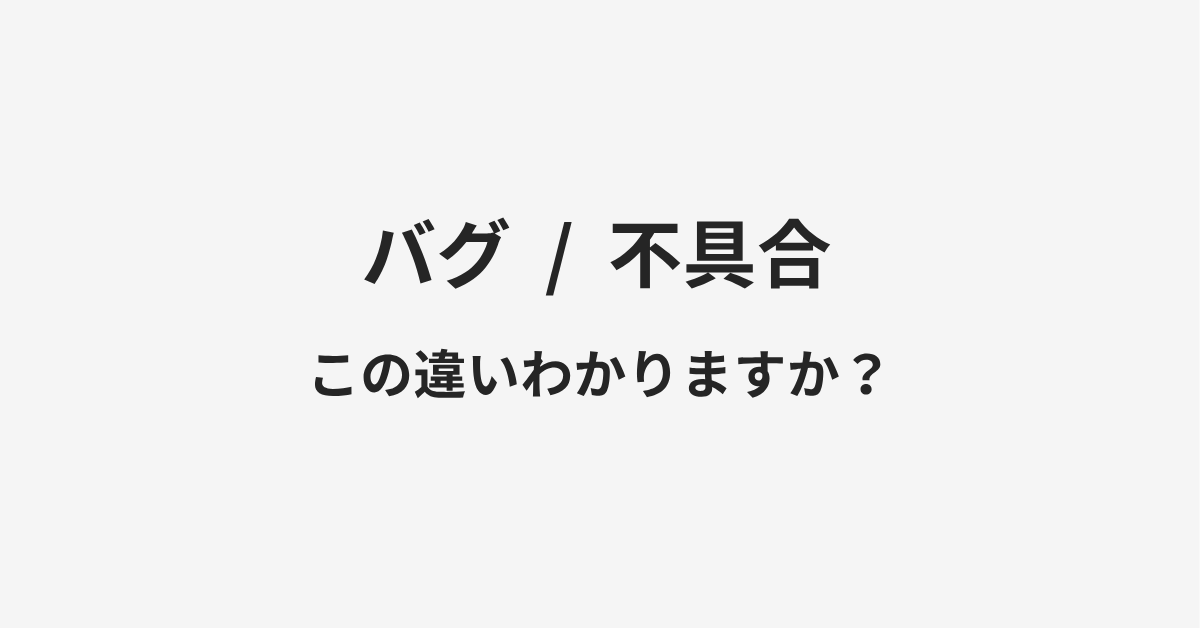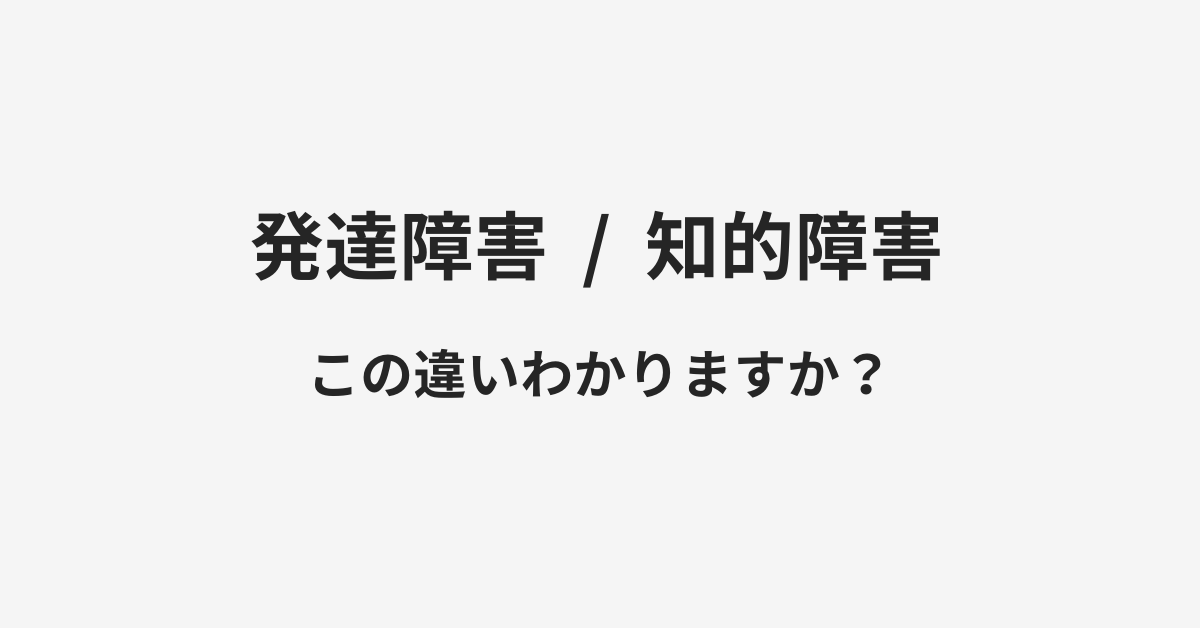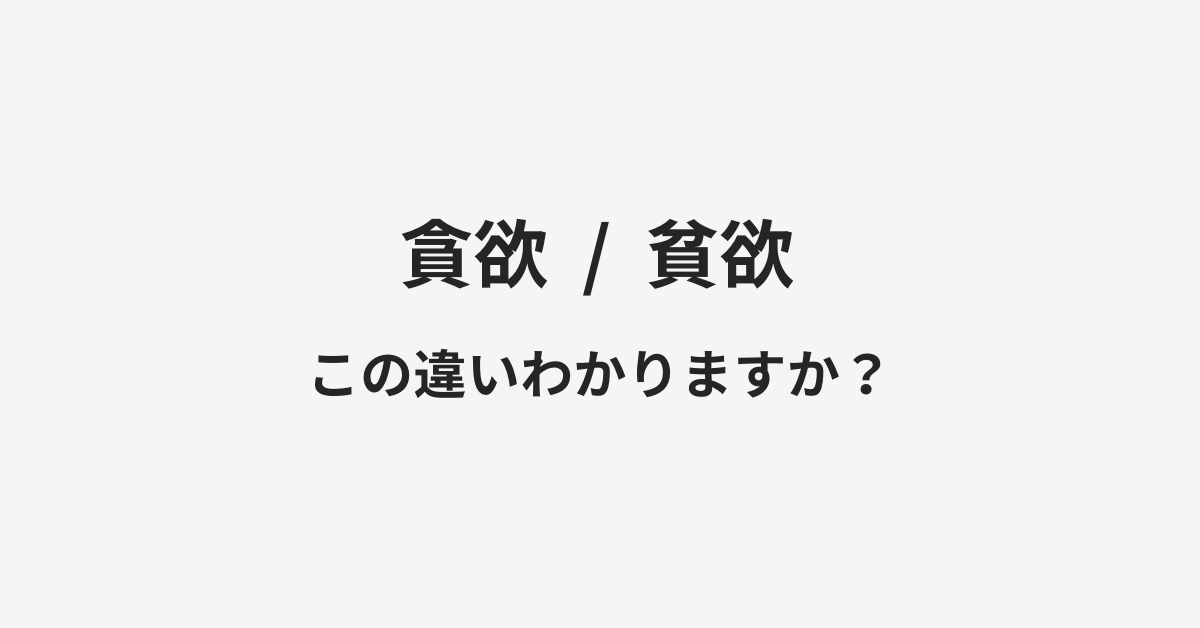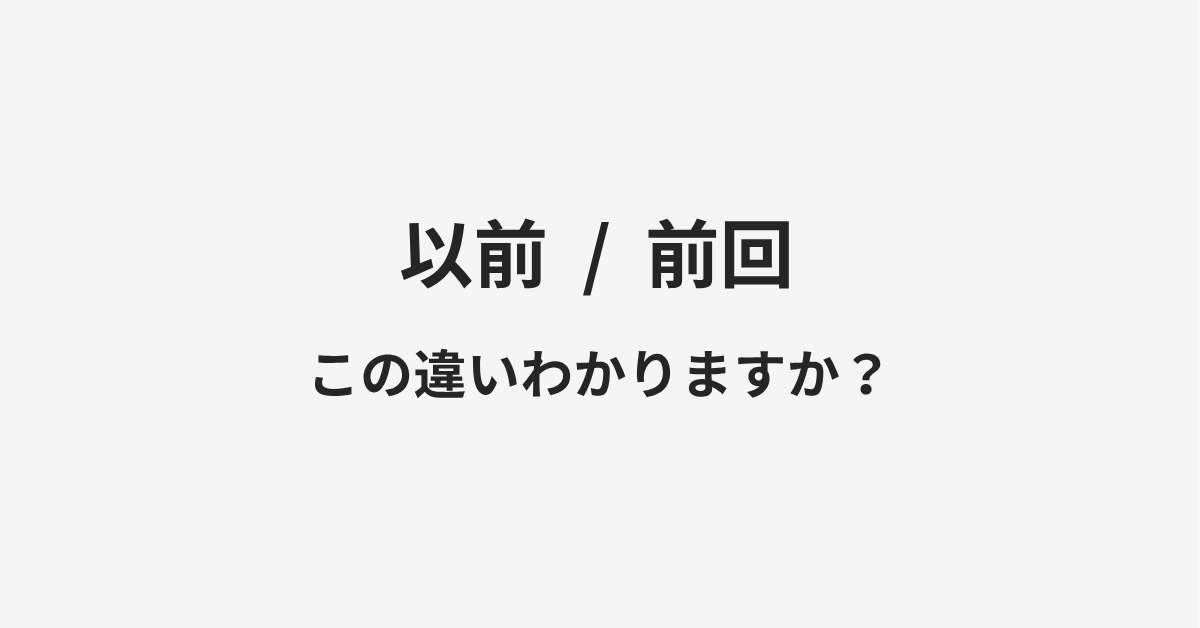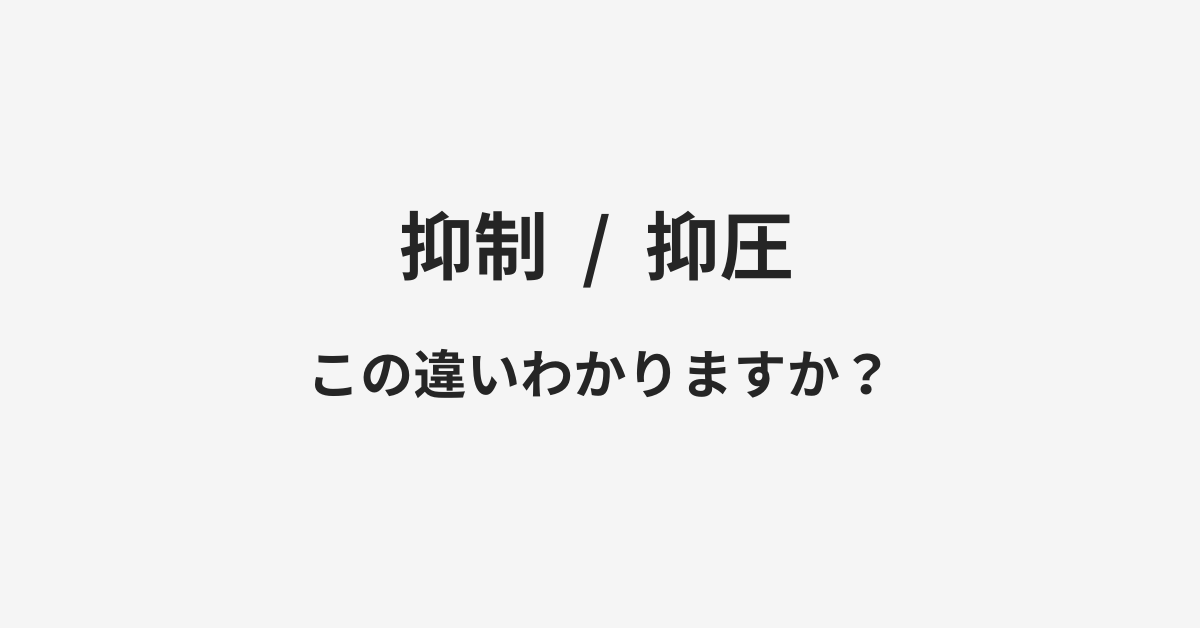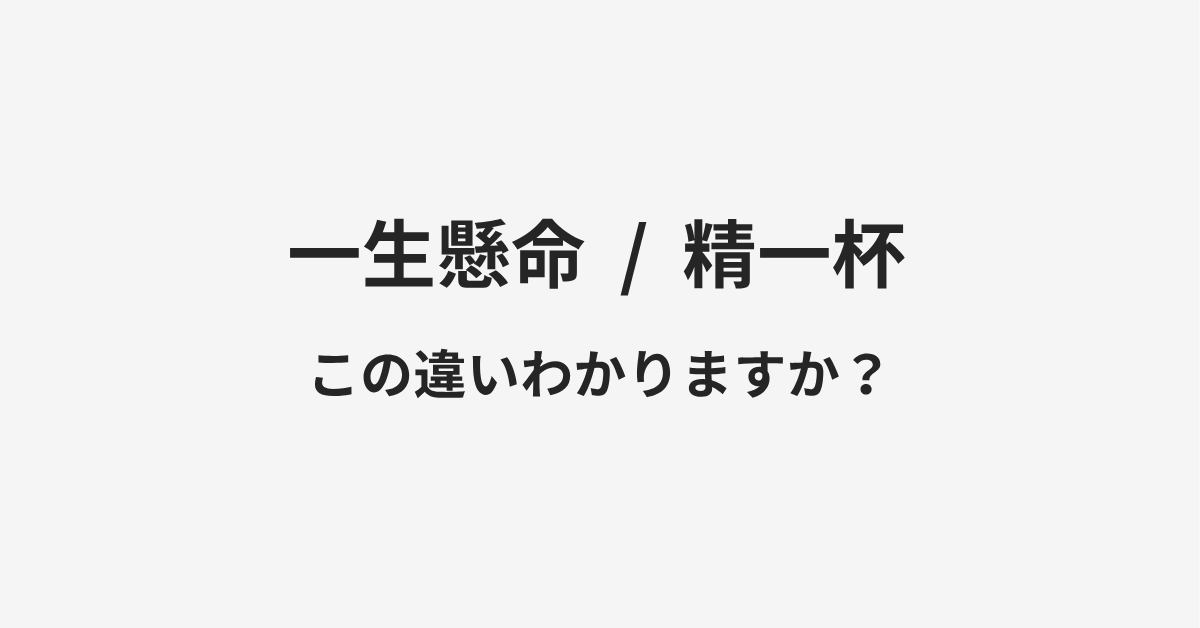【物置】と【土蔵】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
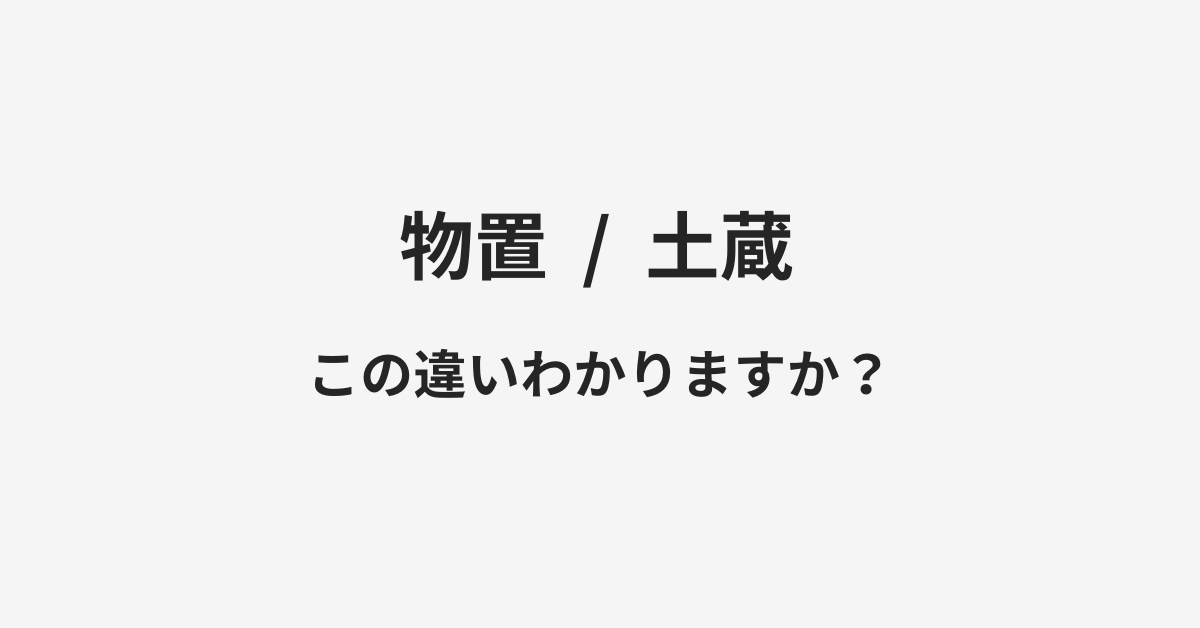
物置と土蔵の分かりやすい違い
物置と土蔵はどちらも物を保管する建物ですが、大きな違いがあります。
物置は、庭に置く小さな倉庫で、ガーデニング用品や季節物などを入れる簡単な建物です。土蔵は、土壁で作られた伝統的な蔵で、火事から大切な物を守るための頑丈な建物です。
普段使いは「物置」、歴史的建築は「土蔵」という違いがあります。
物置とは?
物置とは、住宅の庭や敷地内に設置される、日用品や道具類を収納するための簡易な建物や小屋のことです。
「物置小屋」とも呼ばれ、プレハブ製、木製、スチール製など様々な素材で作られます。ガーデニング用品、自転車、季節家電、アウトドア用品など、家の中に置ききれない物を保管します。組み立て式の製品も多く、比較的安価で設置も簡単です。
現代の住宅事情において、収納スペース不足を解決する実用的な選択肢として広く利用されています。
物置の例文
- ( 1 ) 庭に物置を設置して収納スペースが増えた。
- ( 2 ) 物置の中を整理して、使いやすくした。
- ( 3 ) 台風に備えて物置をしっかり固定した。
- ( 4 ) 物置にしまっていた扇風機を出してきた。
- ( 5 ) 組み立て式の物置は設置が簡単だった。
- ( 6 ) 物置があると季節物の収納に便利だ。
物置の会話例
物置買おうと思ってるんだけど、どのサイズがいい?
家族の人数と収納したい物の量で決めるといいよ。
物置って結構便利?
すごく便利!家の中がすっきりして物置様様だよ。
物置の設置は大変だった?
意外と簡単だったよ。説明書通りにやれば大丈夫。
土蔵とは?
土蔵とは、土壁を厚く塗り重ねて作られた日本の伝統的な耐火建築物で、貴重品や財産を火災から守るための蔵です。
「蔵造り」とも呼ばれ、壁の厚さは30cm以上にもなり、優れた耐火性と調湿性を持ちます。江戸時代から明治時代にかけて、商家や豪農の家に多く建てられ、現在では歴史的建造物として保存されているものも多いです。内部は温度・湿度が安定しており、美術品や文書の保管に適しています。
川越の蔵造りの街並みなど、観光資源としても価値が認められています。
土蔵の例文
- ( 1 ) 古い土蔵をリノベーションしてカフェにした。
- ( 2 ) 土蔵の中は夏でも涼しく感じる。
- ( 3 ) この土蔵は江戸時代から残っている。
- ( 4 ) 土蔵造りの街並みは観光名所になっている。
- ( 5 ) 祖父の家の土蔵に古い道具が残っていた。
- ( 6 ) 土蔵の厚い壁は防火性能が優れている。
土蔵の会話例
実家に古い土蔵があるんだ。
土蔵があるなんてすごい!歴史を感じるね。
でも土蔵の維持管理が大変みたい。
確かに土蔵は手入れが必要だよね。
でも土蔵の雰囲気は独特で素敵だよ。
文化財として土蔵を大切に保存したいね。
物置と土蔵の違いまとめ
物置は現代的な簡易収納建物で、日用品の保管に使われ、設置も簡単です。
一方、土蔵は伝統的な耐火建築で、貴重品を守るための堅牢な構造を持ちます。
現代の収納には「物置」、歴史的建造物には「土蔵」という時代的な違いもあります。
物置と土蔵の読み方
- 物置(ひらがな):ものおき
- 物置(ローマ字):monooki
- 土蔵(ひらがな):どぞう
- 土蔵(ローマ字):dozou