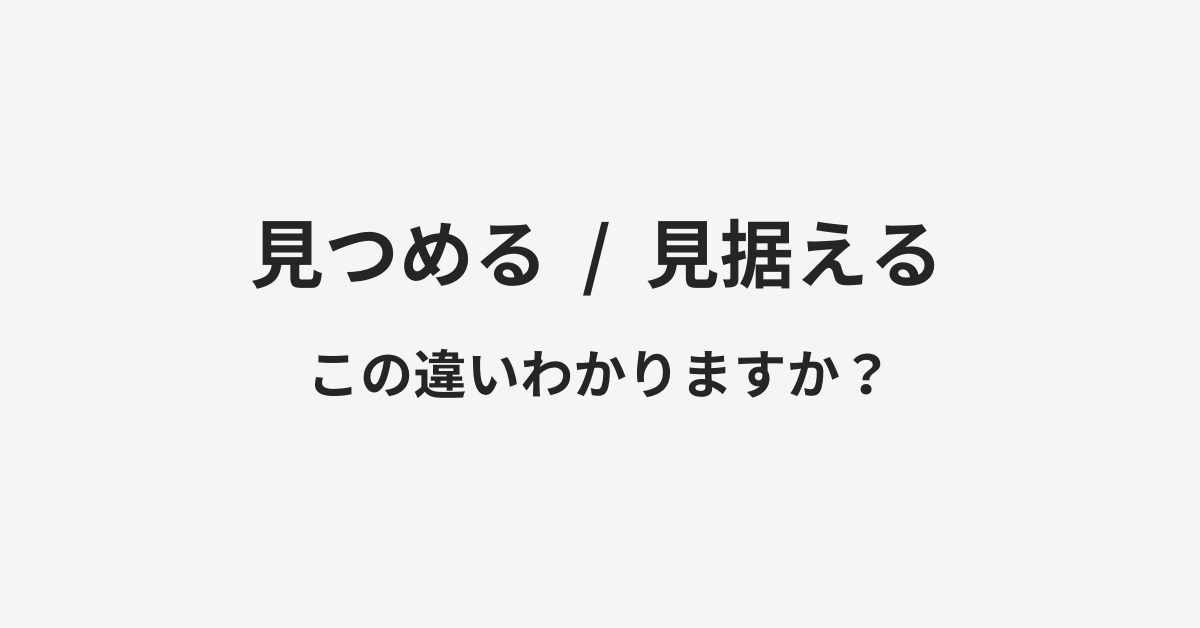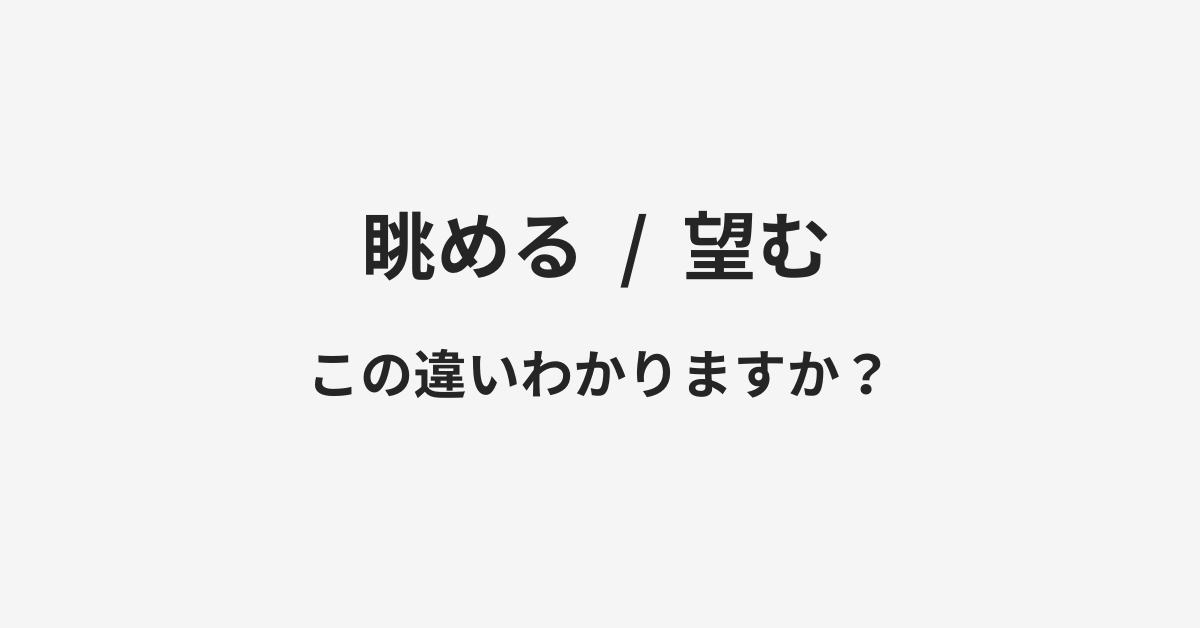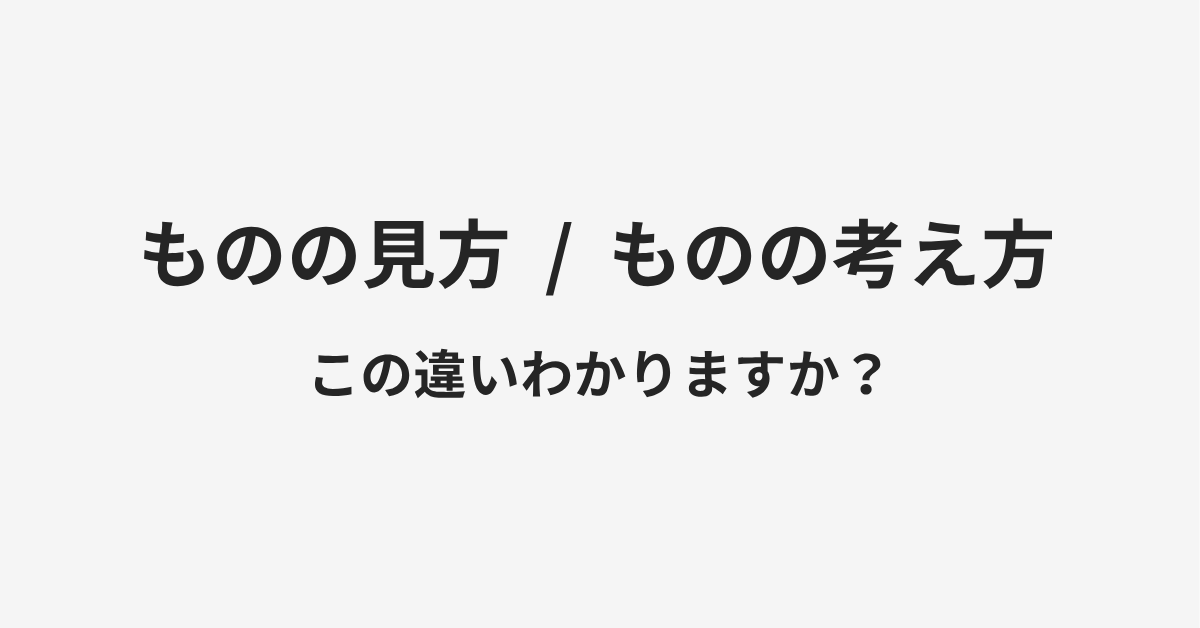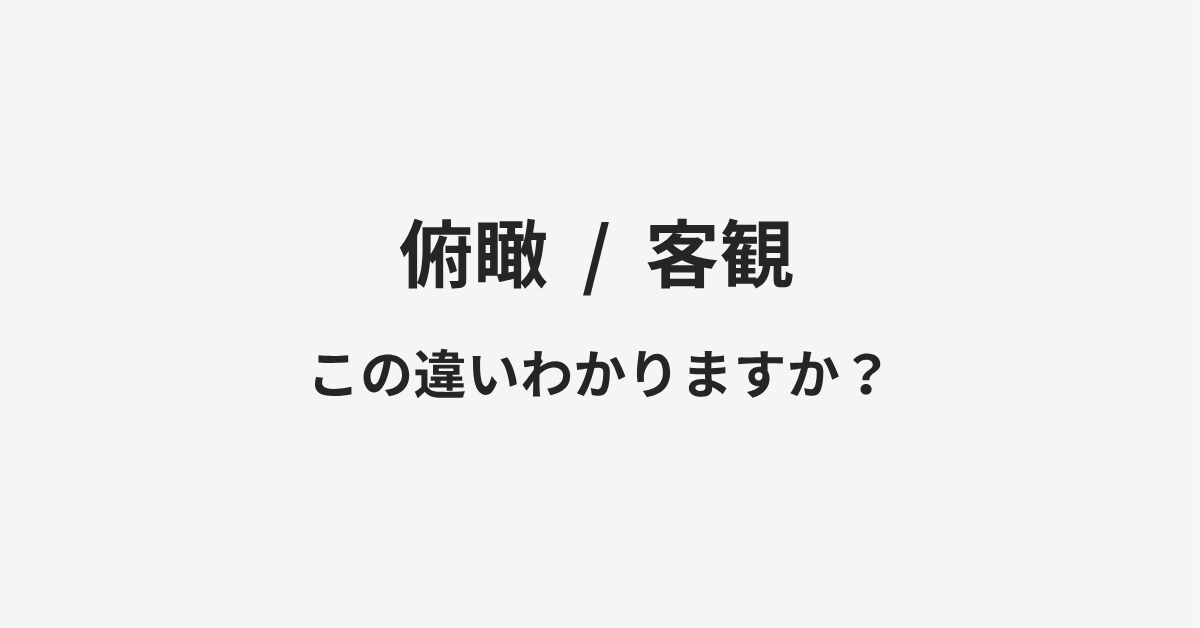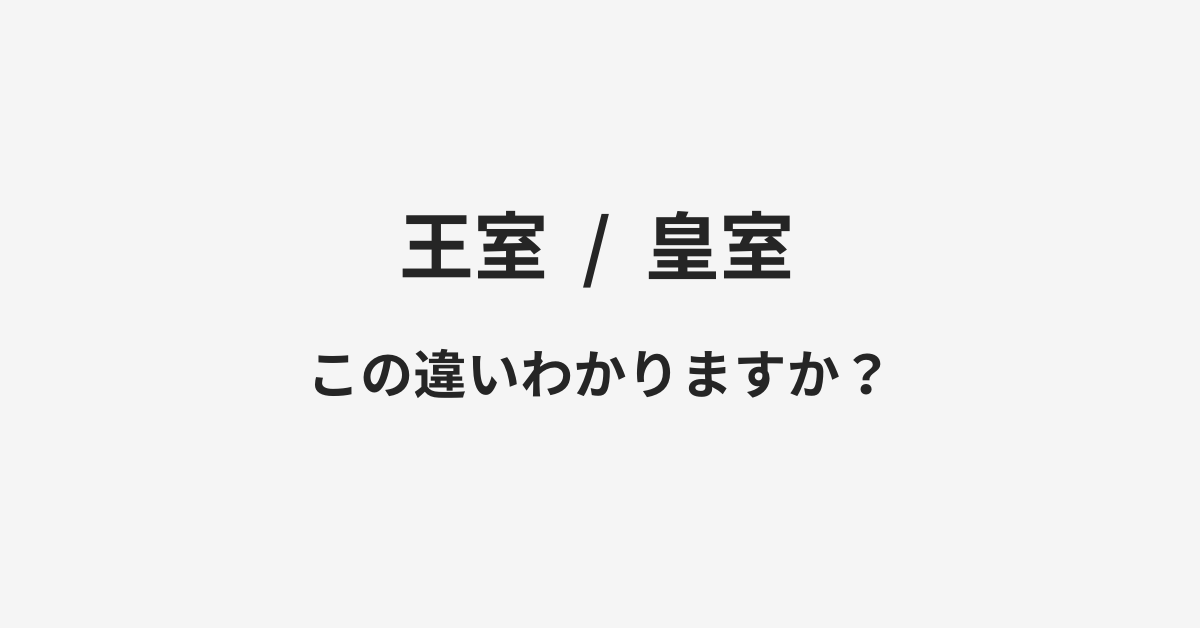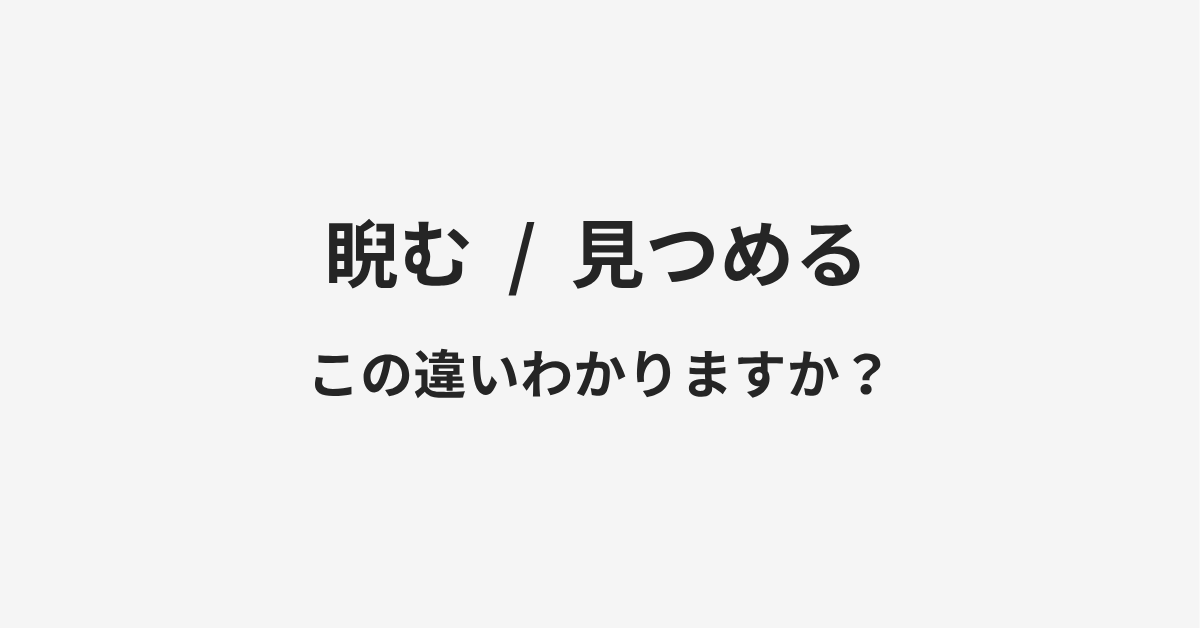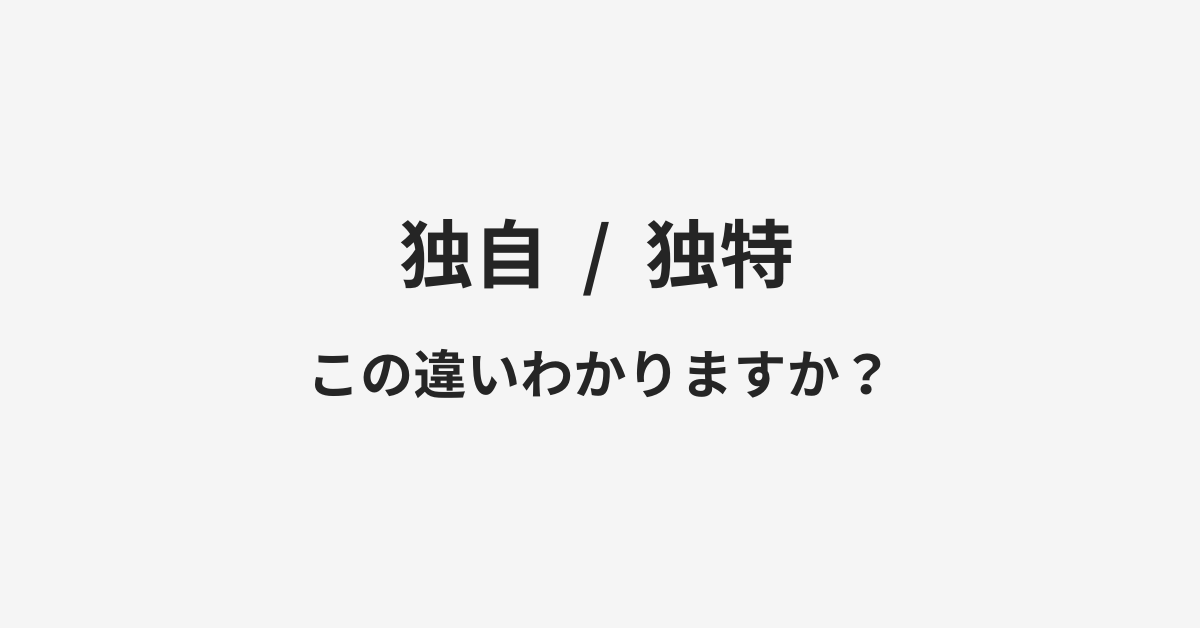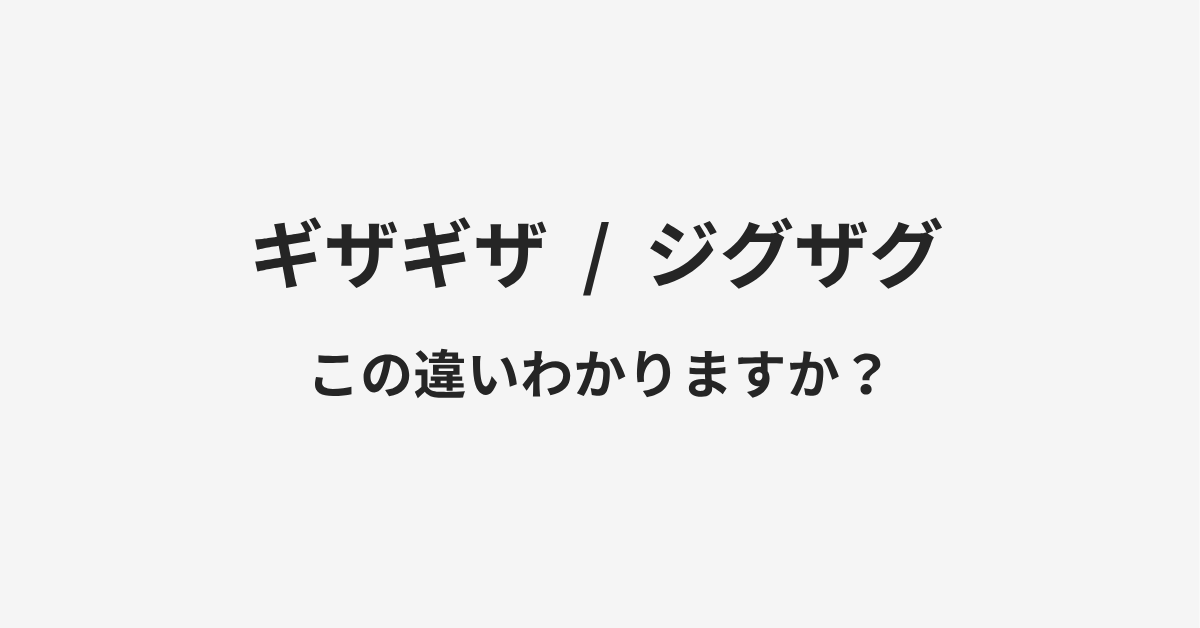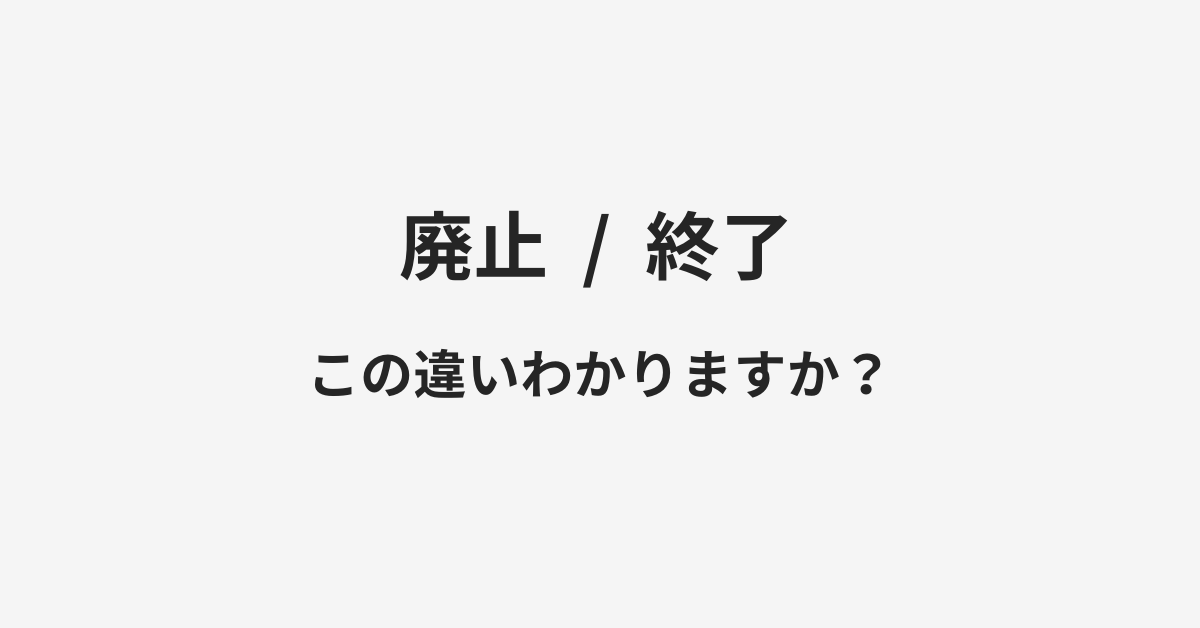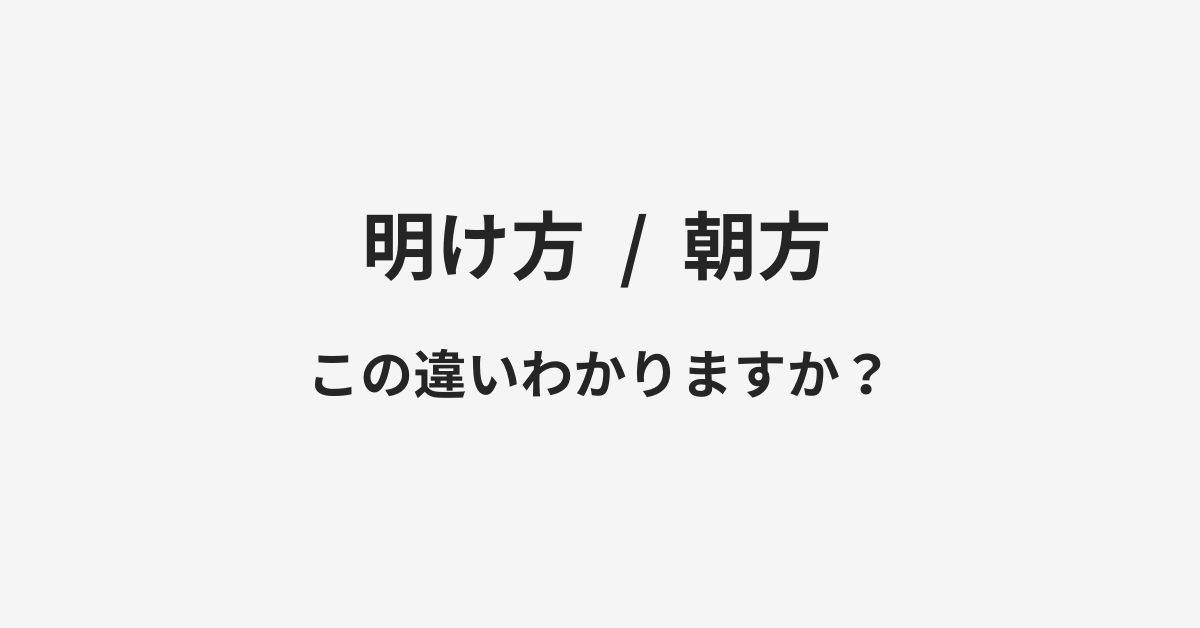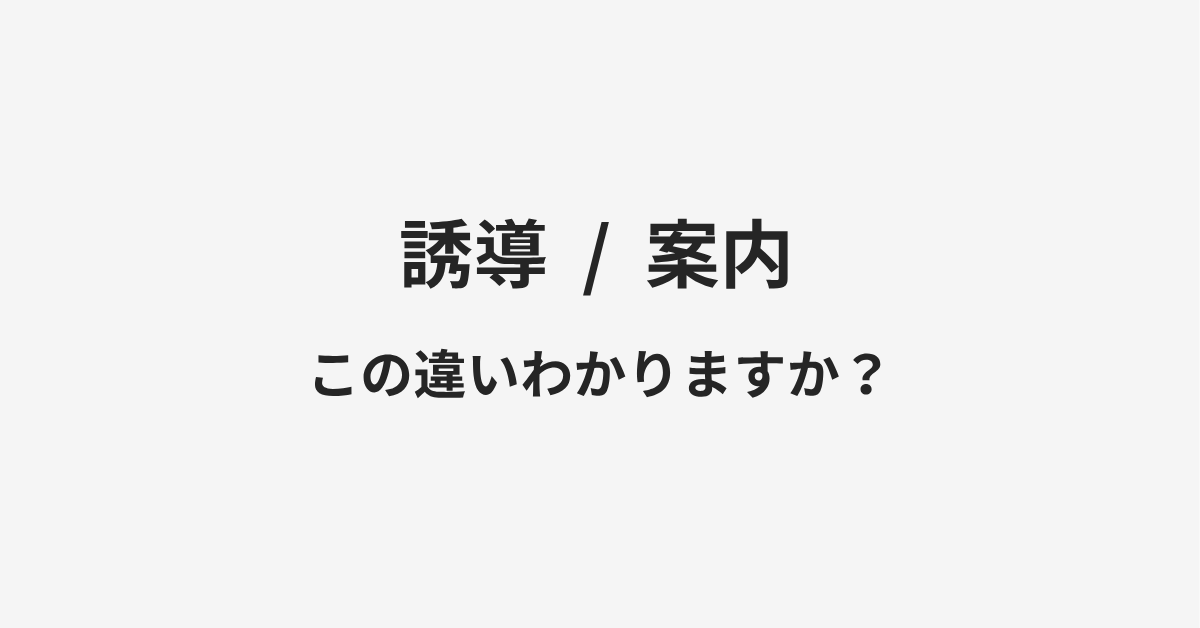【見通し】と【見晴らし】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
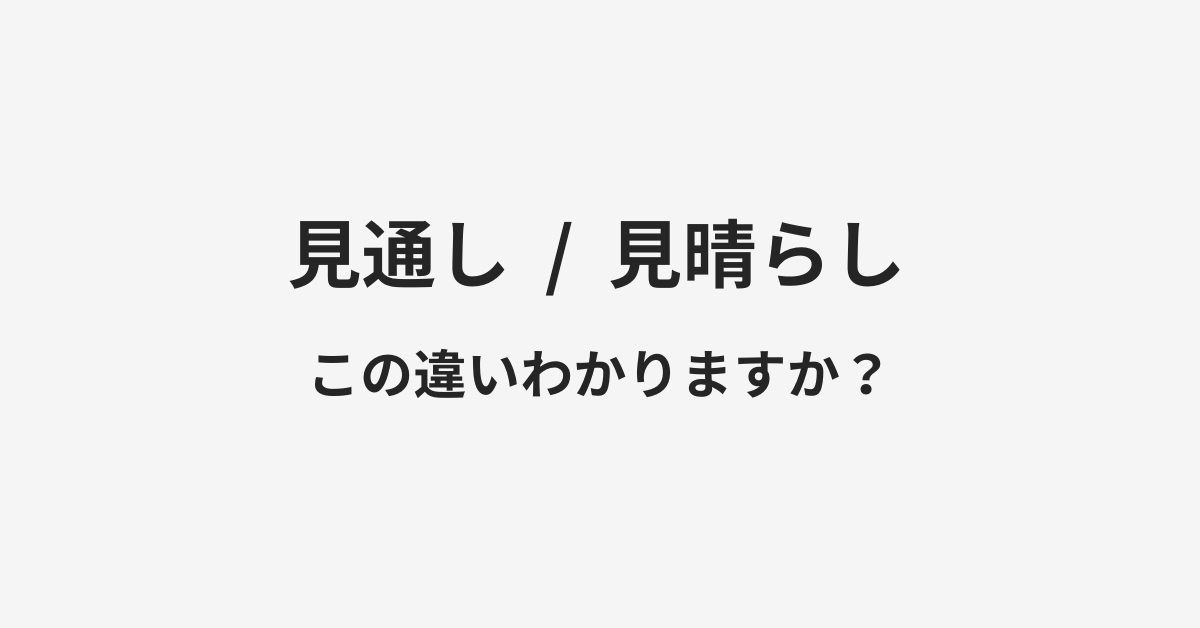
見通しと見晴らしの分かりやすい違い
見通しと見晴らしは、どちらも視界に関する言葉ですが、使う場面と意味が異なります。
見通しは「道路の見通しが良い」「計画の見通しが立つ」のように、物理的な視界や将来の予測を表します。見晴らしは「山頂の見晴らしが素晴らしい」のように、高い場所からの眺めを表します。
日常では、安全や計画には「見通し」、景色や眺望には「見晴らし」を使い分けます。
見通しとは?
見通しとは、視界を遮るものがなく遠くまで見える状態、または将来の予測や展望を表す言葉です。「カーブの見通しが悪い」のような物理的な視界と、「事業の見通しが明るい」のような抽象的な予測の両方で使われます。安全確認や計画立案で重要な概念です。
日常生活では、交通安全の文脈でよく使われます。「見通しの良い交差点」「見通しの悪い曲がり角」など、事故防止のために重要な表現です。また、ビジネスや生活設計では「売上の見通し」「老後の見通し」のように、将来予測の意味で頻繁に使用されます。
見通しは「立つ・立たない」「良い・悪い」「明るい・暗い」などの表現と組み合わせて使われます。物理的な見通しは安全に、抽象的な見通しは計画性に関わる重要な概念で、日本語の中でも使用頻度の高い言葉の一つです。
見通しの例文
- ( 1 ) この交差点は見通しが悪いので、一時停止して安全確認しましょう。
- ( 2 ) 来年の経済の見通しは、専門家によると比較的明るいそうです。
- ( 3 ) 霧で見通しが利かないので、車の運転は控えた方がいいですね。
- ( 4 ) プロジェクトの完成時期の見通しが立ちました。
- ( 5 ) 見通しの良い直線道路でも、スピードの出し過ぎには注意が必要です。
- ( 6 ) 退職後の生活の見通しを立てるため、ファイナンシャルプランナーに相談しました。
見通しの会話例
見晴らしとは?
見晴らしとは、主に高い場所から周囲を広く見渡せる眺望の良さを表す言葉です。「展望台からの見晴らしが素晴らしい」「見晴らしの良いレストラン」のように、景色の美しさや開放感を強調する際に使われます。観光や不動産の分野でよく使用される表現です。
日常会話では、景色を楽しむ場面で使われることが多く、「見晴らしの良い部屋」「見晴らしの良い席」など、眺望を重視する状況で用いられます。登山やハイキング、旅行の際にも「山頂からの見晴らしは最高だった」のように、感動を伝える表現として使われます。
見晴らしは基本的に「良い・悪い」で評価され、特に「見晴らしが良い」という肯定的な文脈で使われることがほとんどです。高所からの眺めだけでなく、視界が開けている状態全般を指すこともあり、開放感や爽快感を表現する際に適した言葉です。
見晴らしの例文
- ( 1 ) 展望台からの見晴らしは絶景で、富士山まで見えました。
- ( 2 ) 新居は5階なので、見晴らしが良くて気持ちいいです。
- ( 3 ) 山頂まで登ると、360度の見晴らしが楽しめます。
- ( 4 ) 見晴らしの良いカフェで、のんびりとお茶を楽しみました。
- ( 5 ) ホテルの最上階にある見晴らしの良いレストランで食事をしました。
- ( 6 ) 桜の季節は、見晴らしの良い公園が人気スポットになります。
見晴らしの会話例
見通しと見晴らしの違いまとめ
見通しと見晴らしの最大の違いは、用途と視点です。見通しは安全確認や将来予測に使い、見晴らしは景色の良さを表現します。
日常生活では、道路や計画には「見通し」、眺望や景色には「見晴らし」を使うと自然な表現になります。
どちらも「よく見える」ことを表しますが、目的が異なることを理解して使い分けましょう。
見通しと見晴らしの読み方
- 見通し(ひらがな):みとおし
- 見通し(ローマ字):mitooshi
- 見晴らし(ひらがな):みはらし
- 見晴らし(ローマ字):miharashi