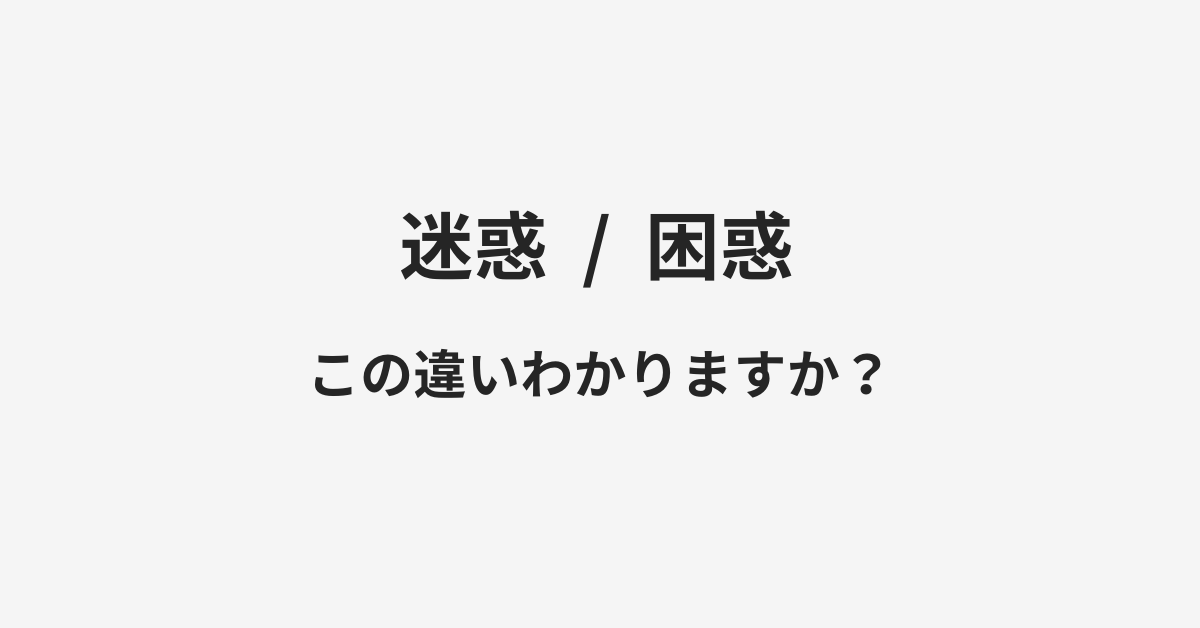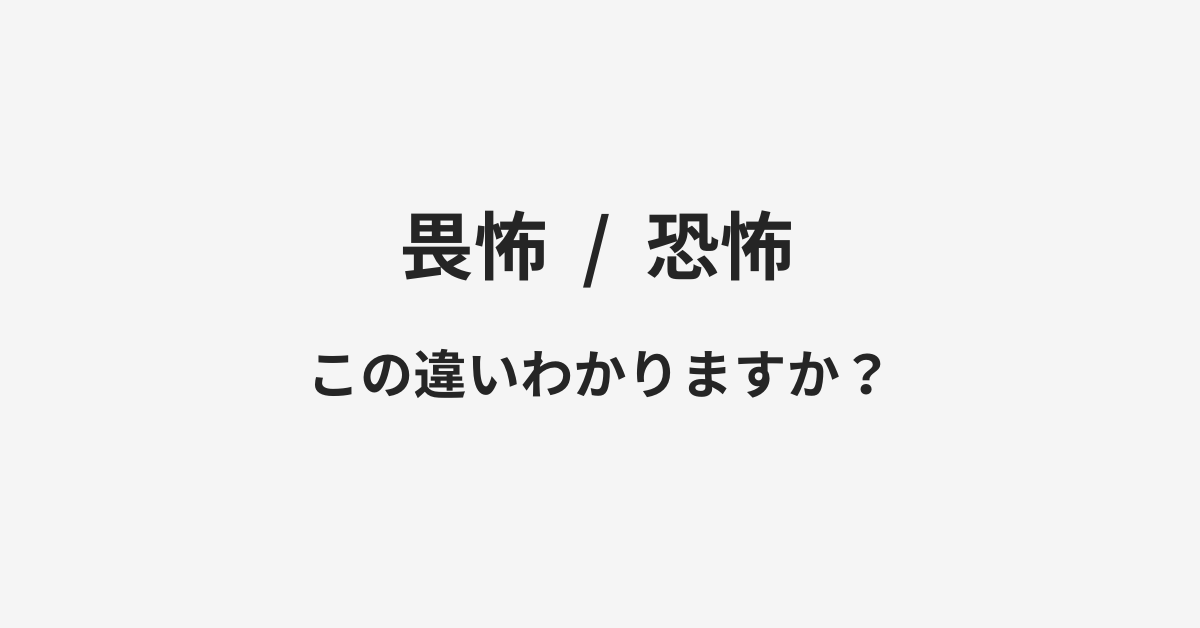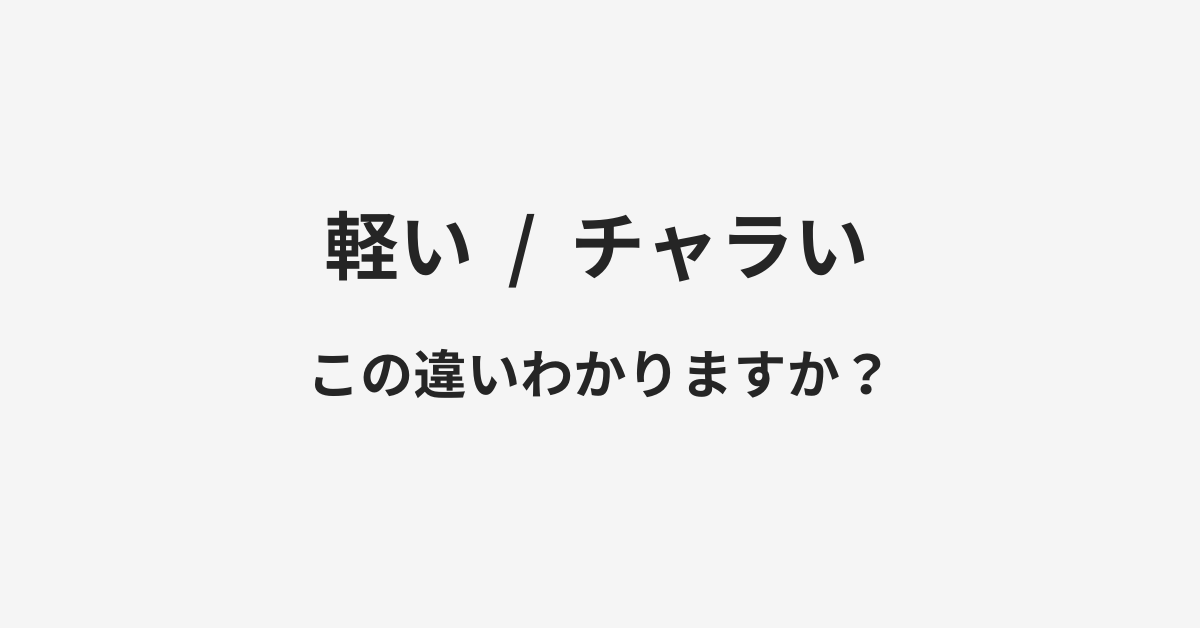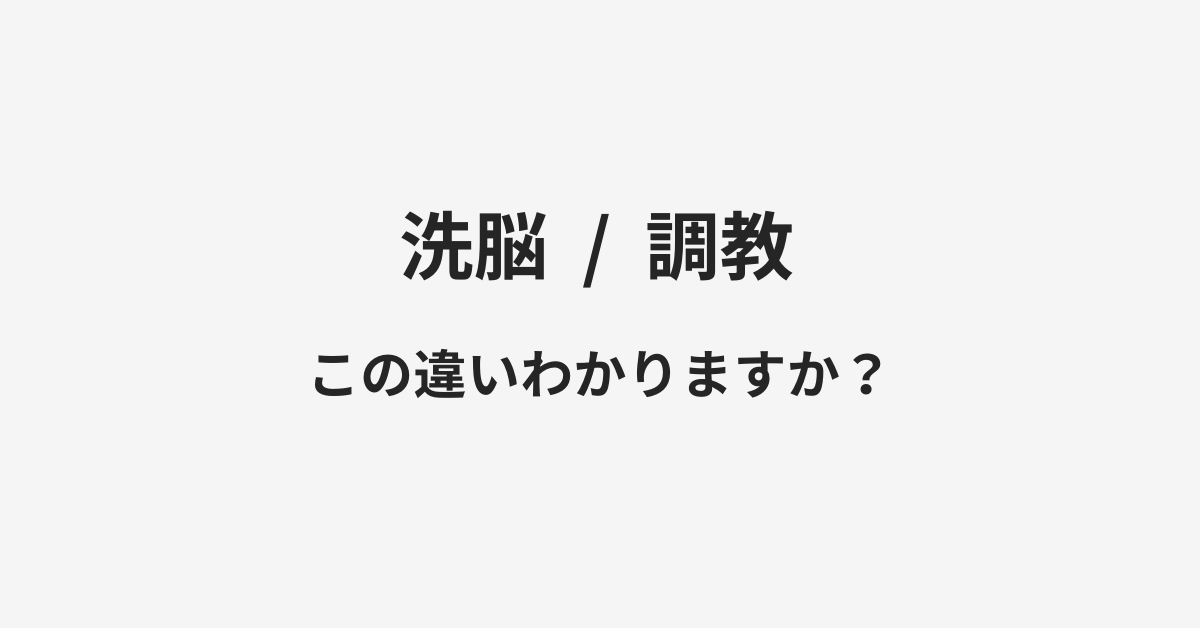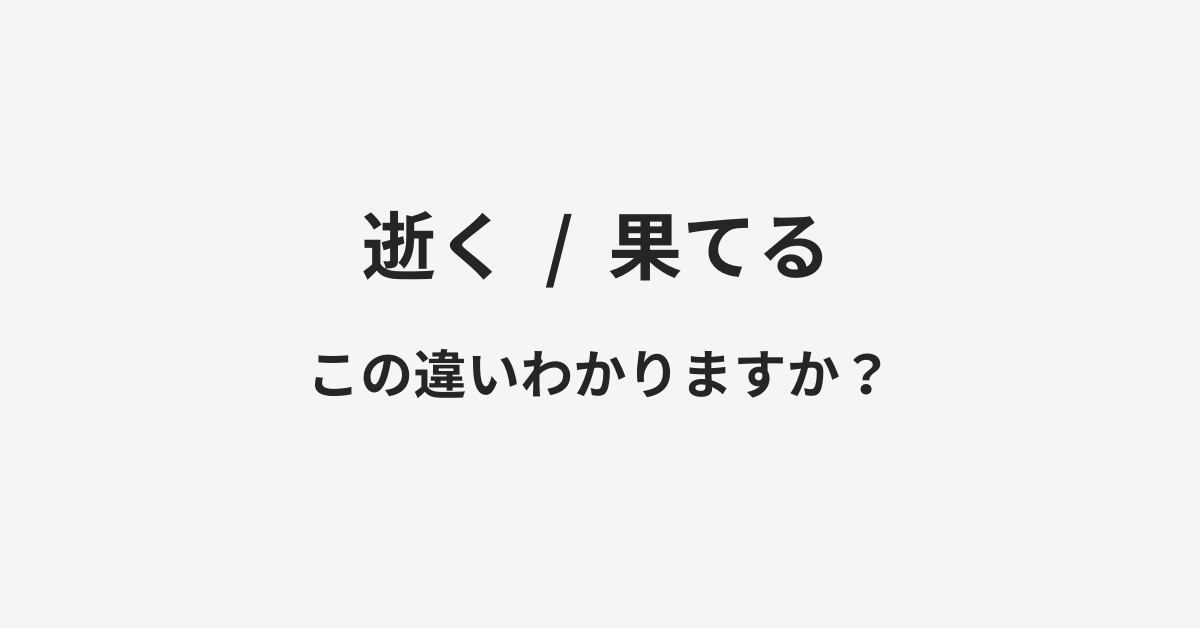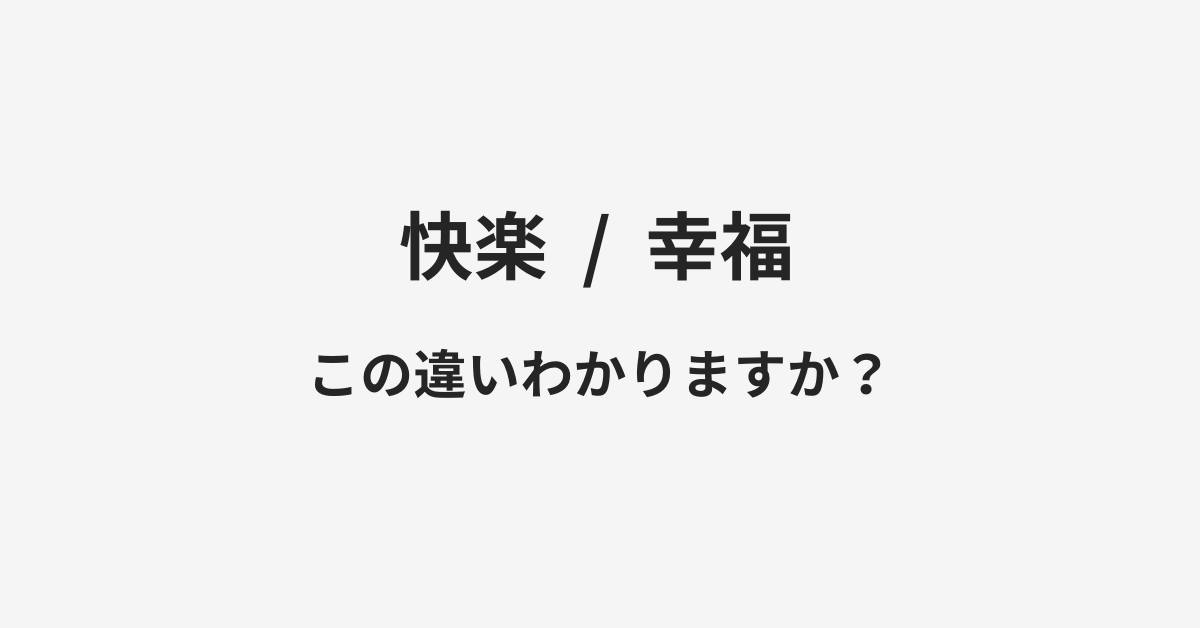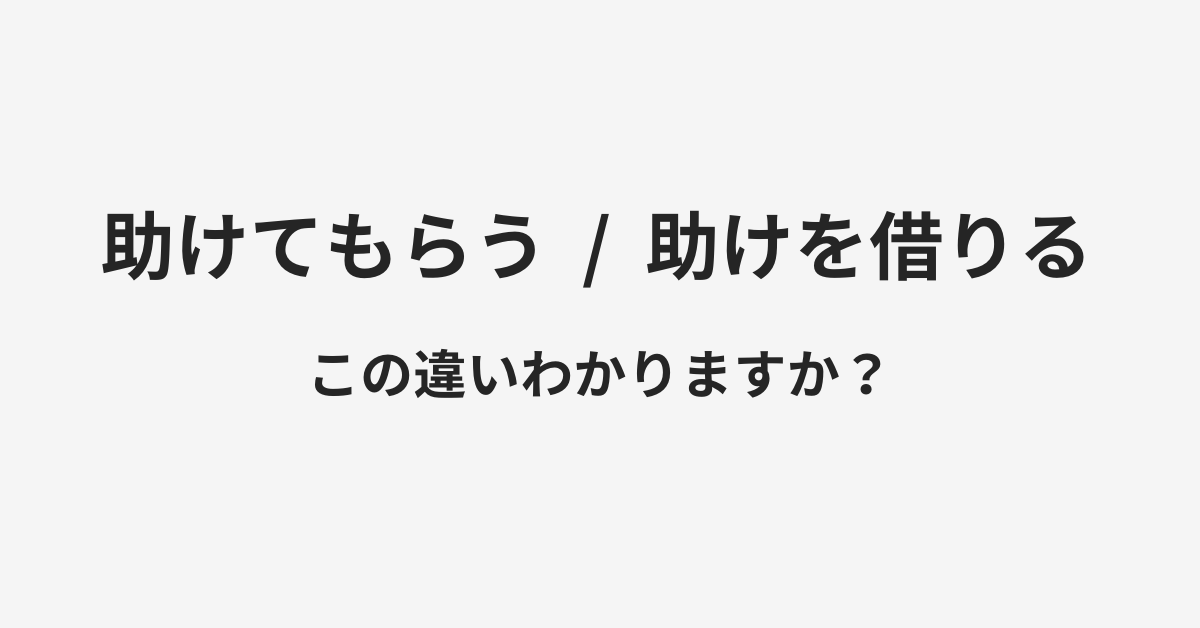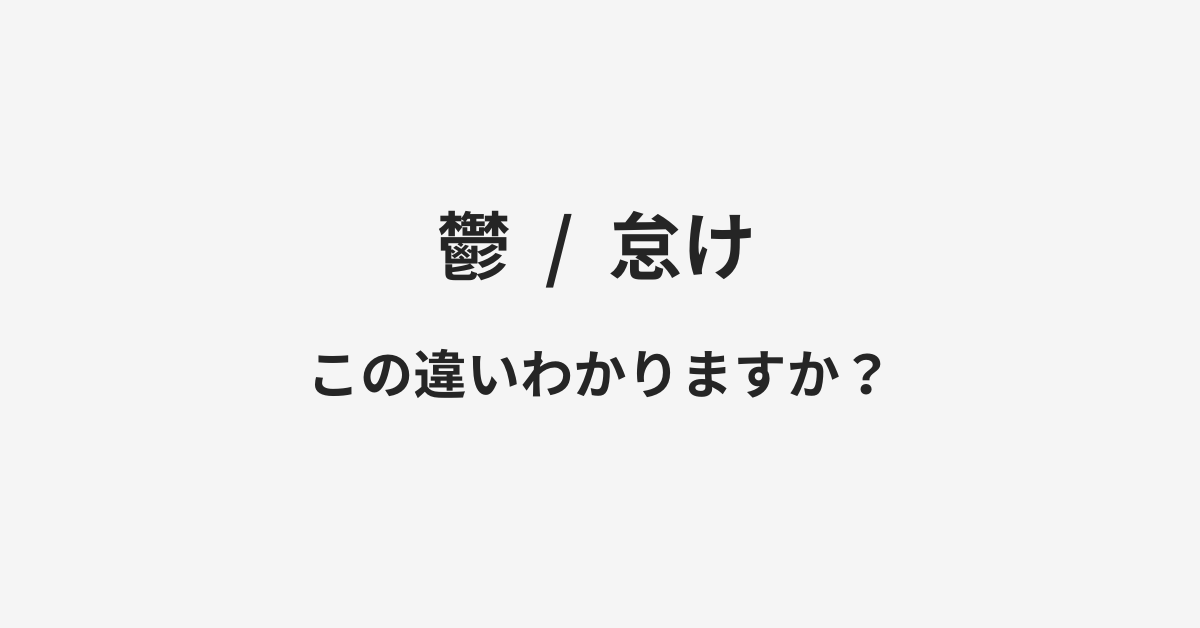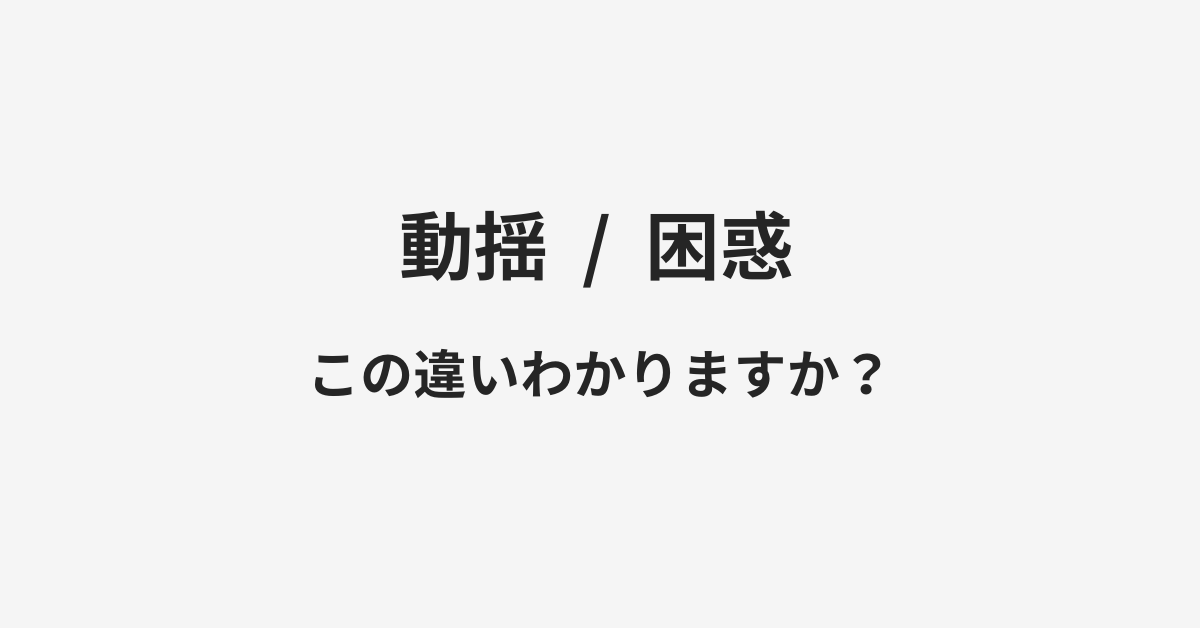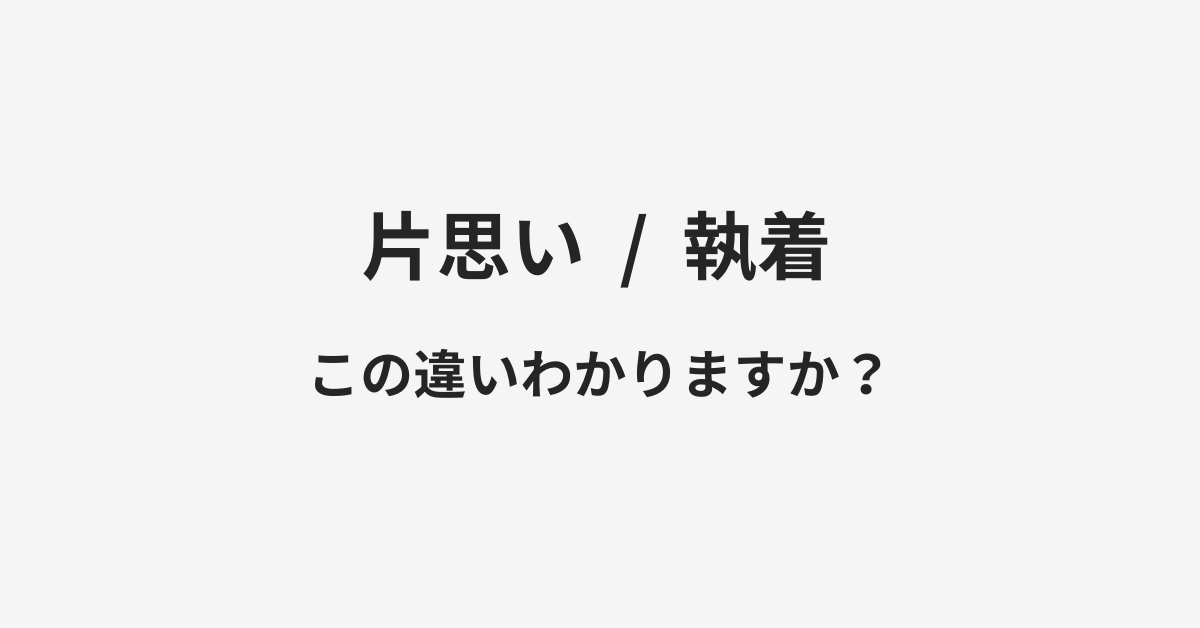【不測の事態】と【パニック】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
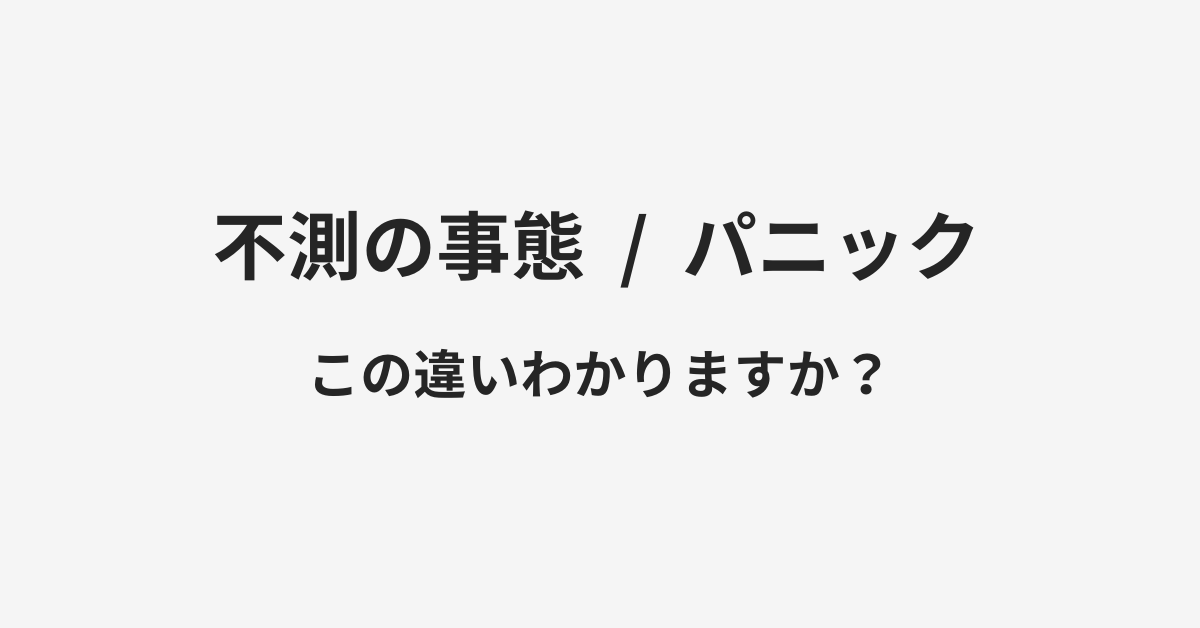
不測の事態とパニックの分かりやすい違い
不測の事態とパニックは、密接に関連しながらも異なる概念です。不測の事態は予想外の出来事や状況そのものを指し、外的な現象です。
一方、パニックはそうした状況に対する極度の恐怖や混乱という心理的反応です。メンタルヘルスでは、不測の事態への準備と対処スキルを身につけることで、パニックを防ぎ、心の安定を保つことができます。
不測の事態とは?
不測の事態とは、予想や計画していなかった突発的な出来事や状況を指します。自然災害、事故、急な体調不良、予期せぬ人間関係の変化など、日常生活で起こりうる想定外の出来事全般を表します。それ自体は中立的な出来事であり、必ずしも否定的とは限りません。心理学的には、不測の事態への対処能力(コーピング能力)は、個人のレジリエンスと密接に関連しています。
過去の経験、準備の程度、サポートシステムの有無などが、不測の事態への適応力を左右します。認知的評価理論では、同じ出来事でも個人の評価によってストレスの程度が変わるとされています。メンタルヘルスの観点から、不測の事態への備えは重要です。
完全に予測することは不可能ですが、心理的な柔軟性を養い、基本的な対処スキルを身につけることで、不測の事態が生じても冷静に対応できるようになります。これには、問題解決能力、感情調整スキル、社会的支援の活用などが含まれます。
不測の事態の例文
- ( 1 ) 急な異動という不測の事態に直面しましたが、新しい環境への適応を前向きに捉えています。
- ( 2 ) 病気の診断という不測の事態でしたが、家族のサポートで乗り越えることができました。
- ( 3 ) 不測の事態に備えて、日頃からストレス対処法を練習するようになりました。
- ( 4 ) 地震という不測の事態を経験し、心の準備の大切さを実感しました。
- ( 5 ) 不測の事態が起きても動じない心を育てるため、マインドフルネスを実践しています。
- ( 6 ) カウンセリングで不測の事態への対処法を学び、不安が軽減されました。
不測の事態の会話例
パニックとは?
パニックとは、突然の強い恐怖や不安により、理性的な判断ができなくなり、極度の混乱状態に陥ることを指します。心拍数の急上昇、呼吸困難、発汗、震えなどの身体症状を伴い、このまま死んでしまうのではないかという強い恐怖を感じることが特徴です。心理学的には、パニックは急性の不安反応であり、扁桃体の過剰な活性化により引き起こされます。
パニック発作は、実際の危険がない状況でも起こることがあり、一度経験するとまた起こるのではないかという予期不安から、パニック障害に発展することがあります。メンタルヘルスケアにおいて、パニックへの対処は重要なスキルです。
深呼吸法、グラウンディング技法、認知的再評価などの技法が有効です。パニック発作を経験した場合は、専門家の支援を受けることが推奨されます。適切な治療により、パニックは管理可能な状態になります。
パニックの例文
- ( 1 ) 電車の中でパニック発作を起こし、それ以来乗るのが怖くなってしまいました。
- ( 2 ) 初めてパニックを経験した時は、本当に死ぬかと思うほど恐ろしかったです。
- ( 3 ) パニック障害と診断されましたが、適切な治療で症状をコントロールできるようになりました。
- ( 4 ) パニックになりそうな時は、教わった呼吸法で落ち着くようにしています。
- ( 5 ) パニック発作の予兆を感じ取れるようになり、早めの対処ができるようになりました。
- ( 6 ) グループセラピーで他の人のパニック体験を聞き、一人じゃないと安心しました。
パニックの会話例
不測の事態とパニックの違いまとめ
不測の事態とパニックの違いは、外的現象と内的反応の違いです。不測の事態は起こった出来事、パニックはそれに対する極度の心理的反応です。
メンタルヘルスでは、不測の事態に備える心理的準備と、パニックを管理するスキルの両方が重要です。前者は予防、後者は対処に焦点を当てます。
健康的な心の状態を保つには、不測の事態を受け入れる柔軟性と、パニックに陥らない感情調整能力を育てることが大切です。
不測の事態とパニックの読み方
- 不測の事態(ひらがな):ふそくのじたい
- 不測の事態(ローマ字):fusokunojitai
- パニック(ひらがな):ぱにっく
- パニック(ローマ字):panikku