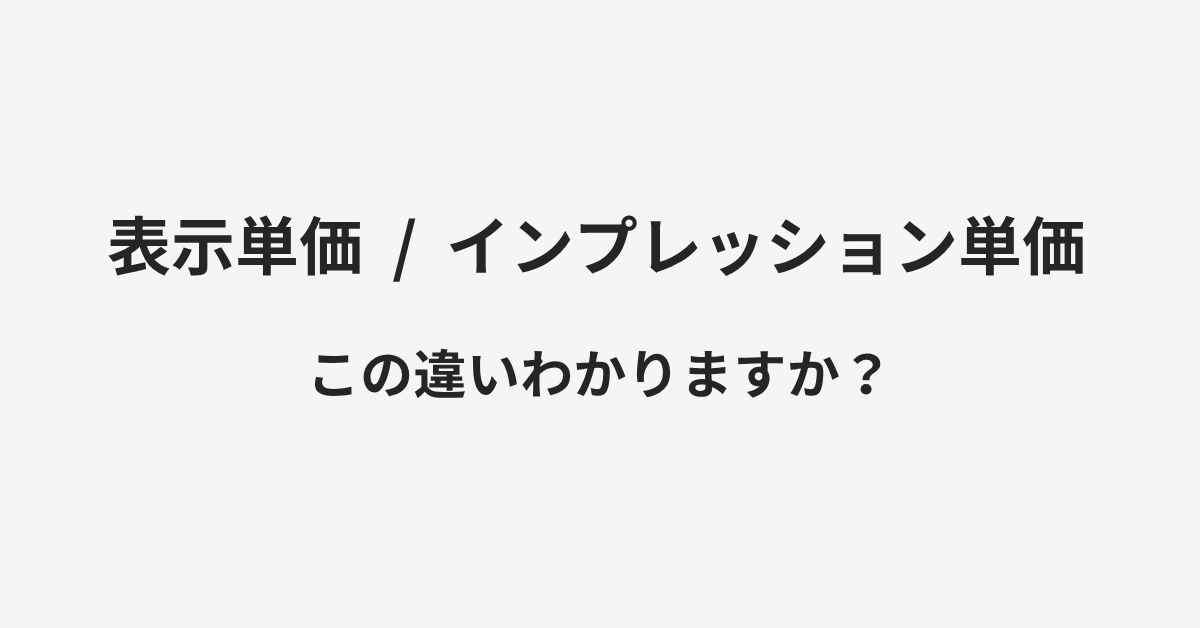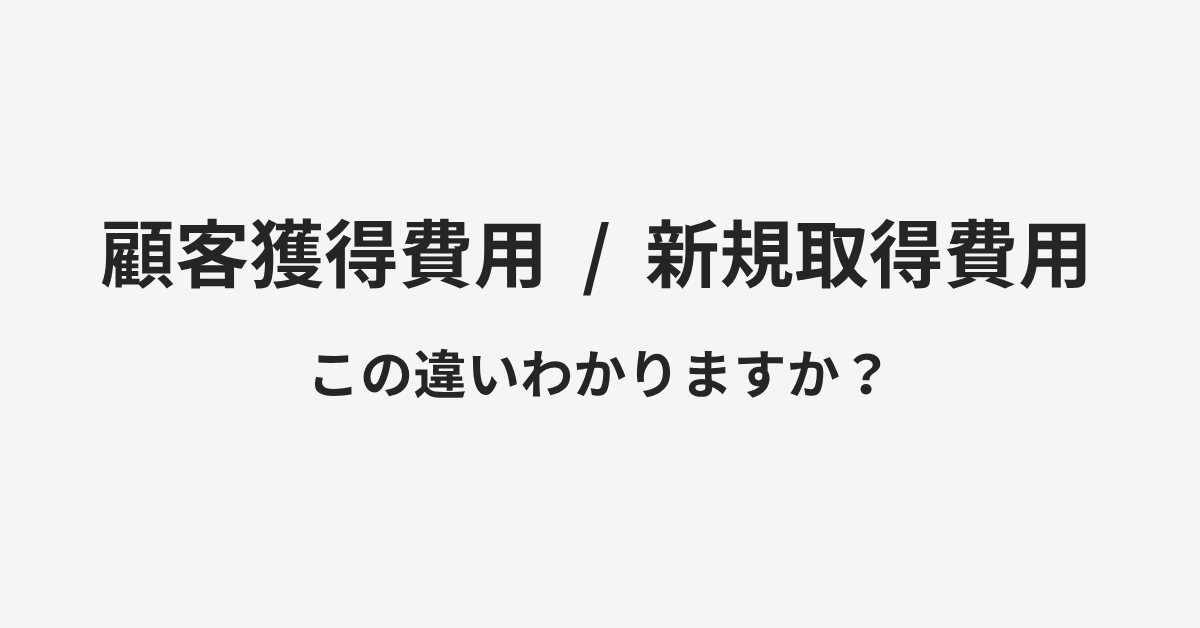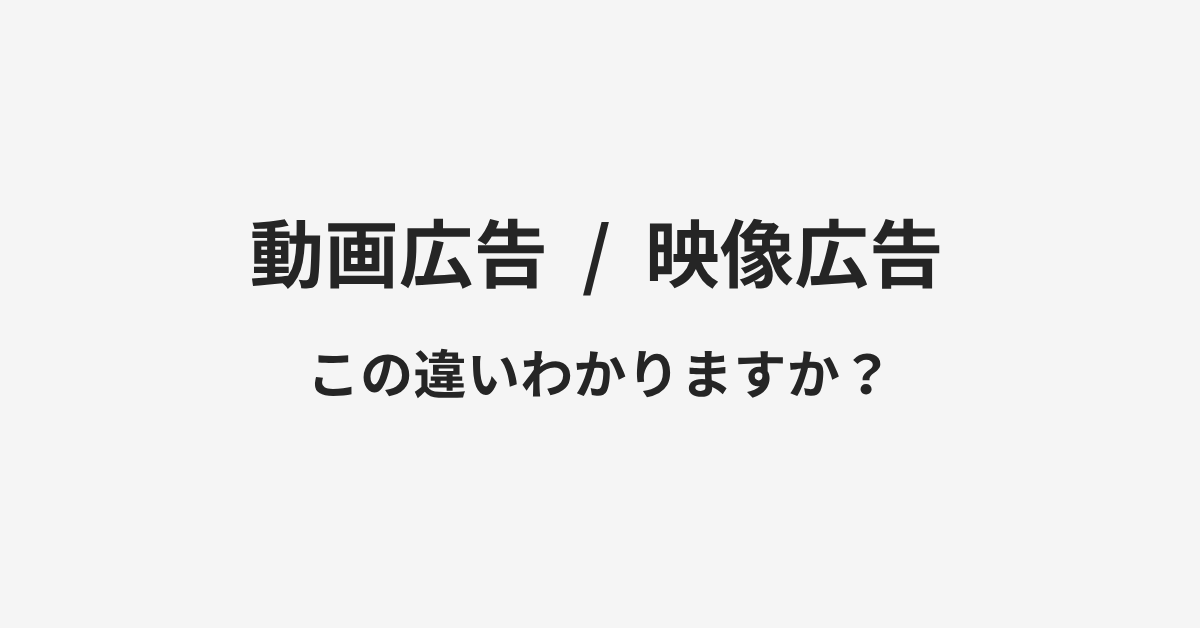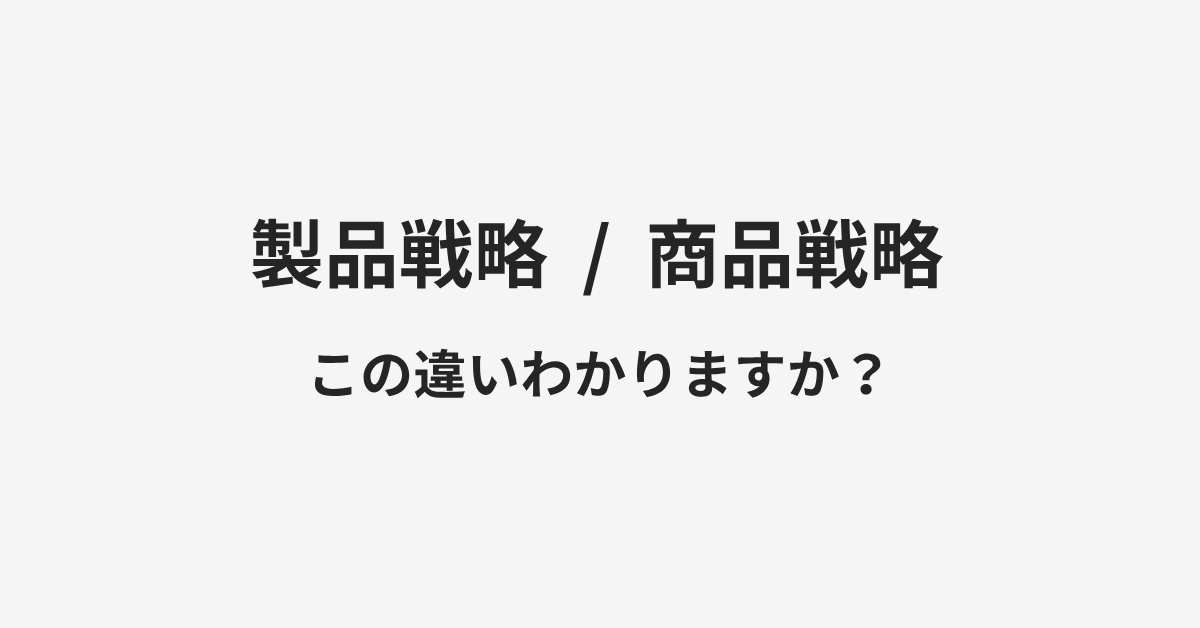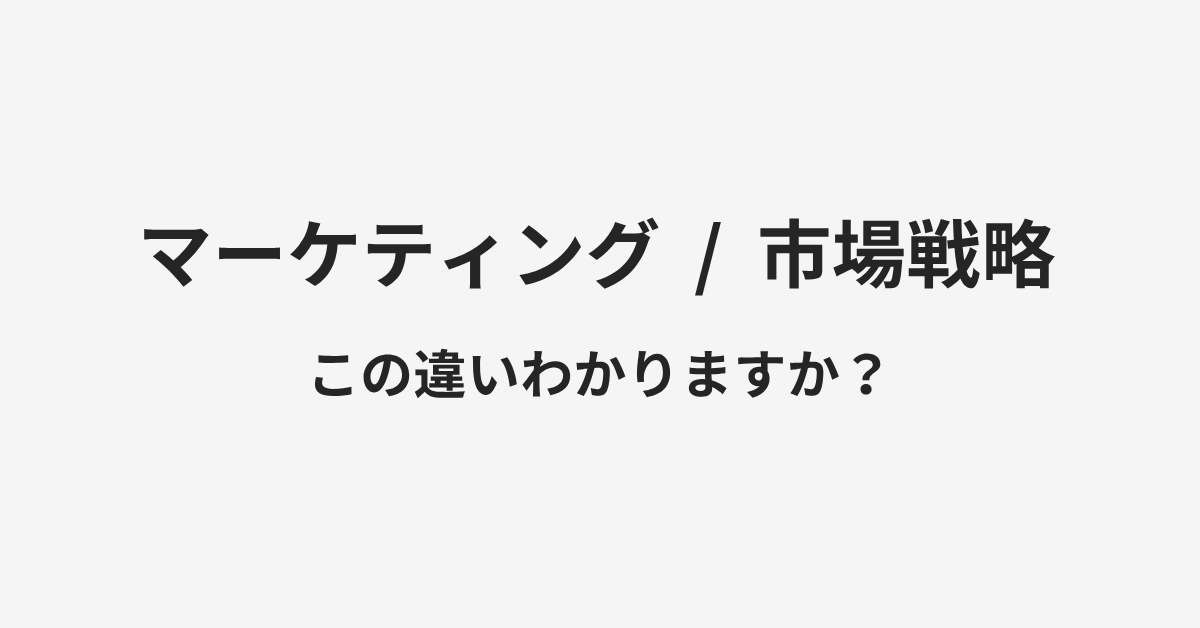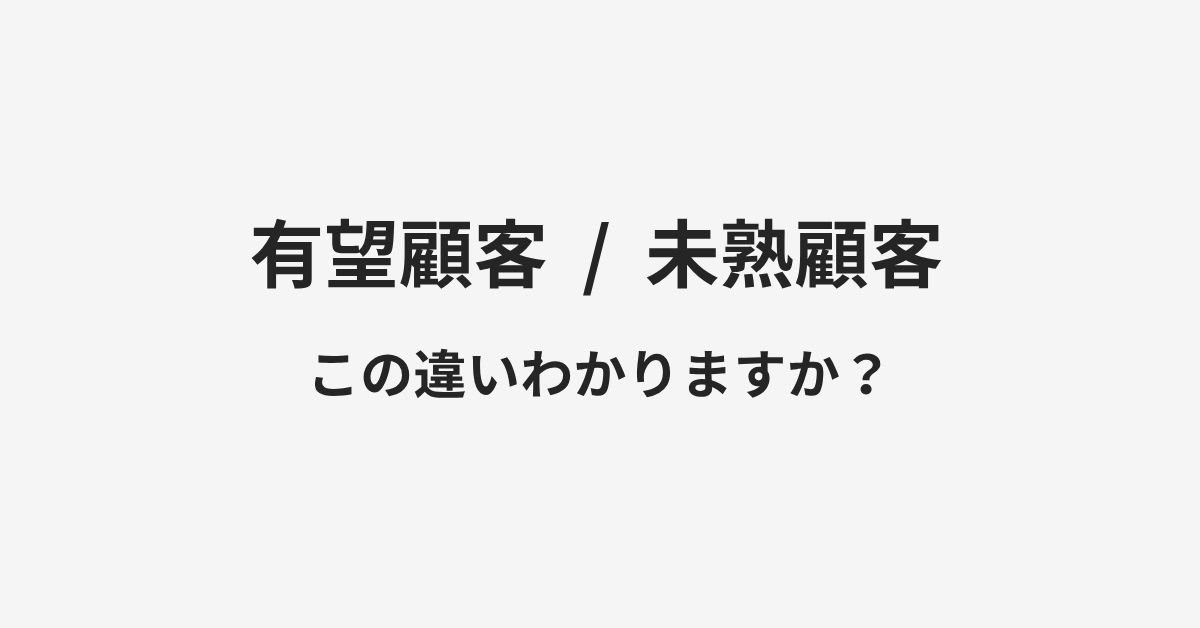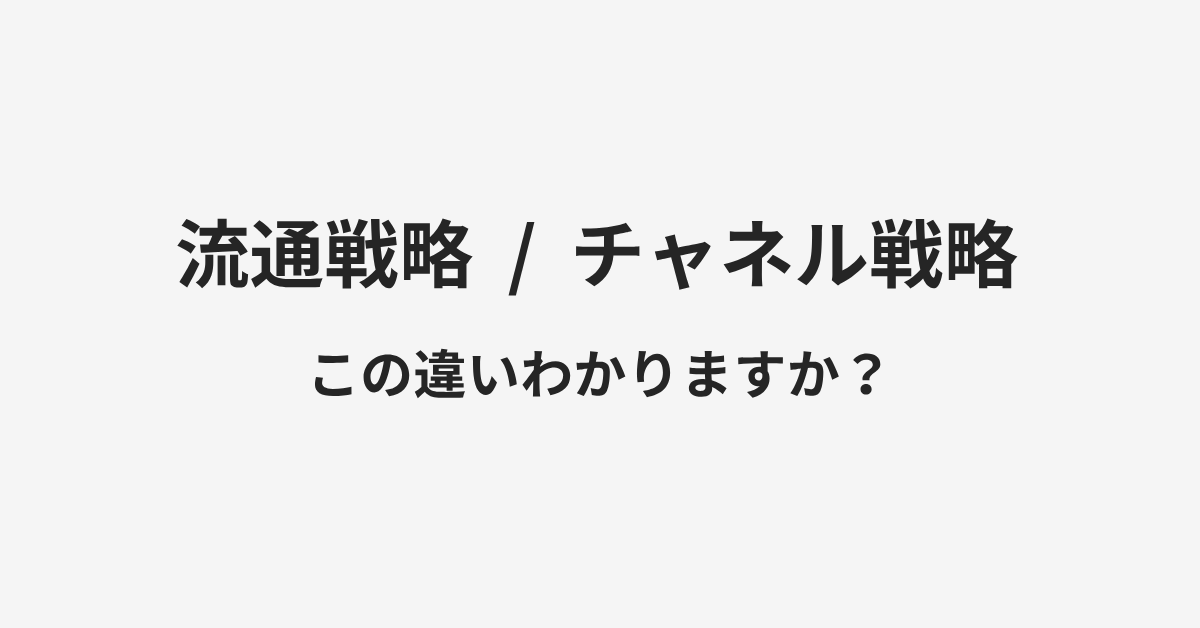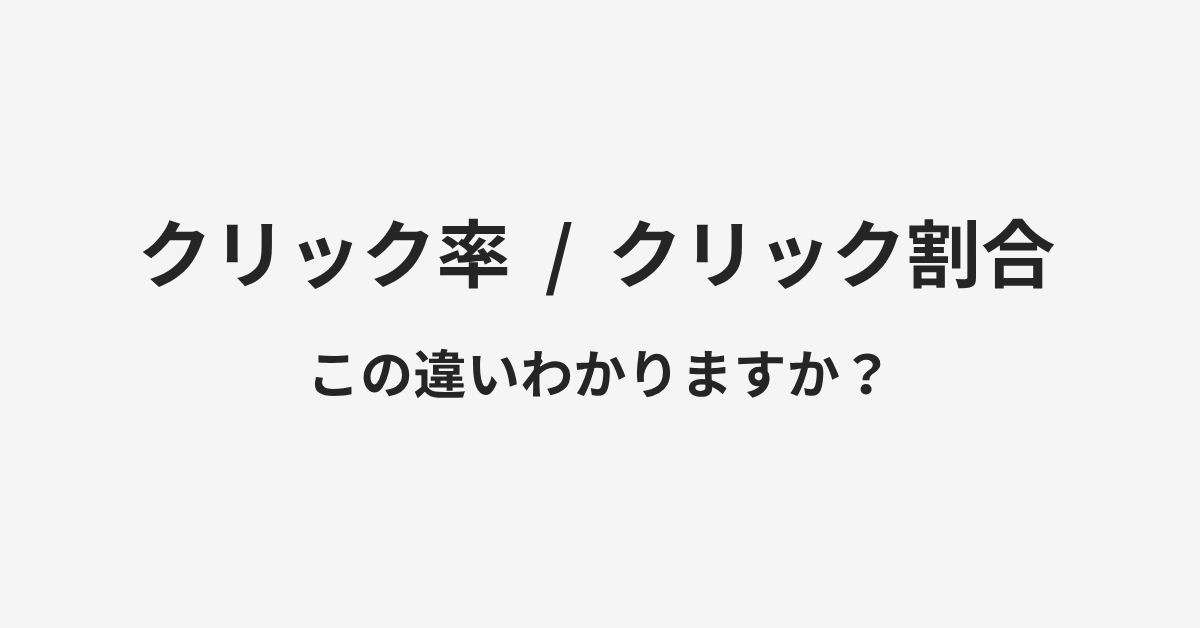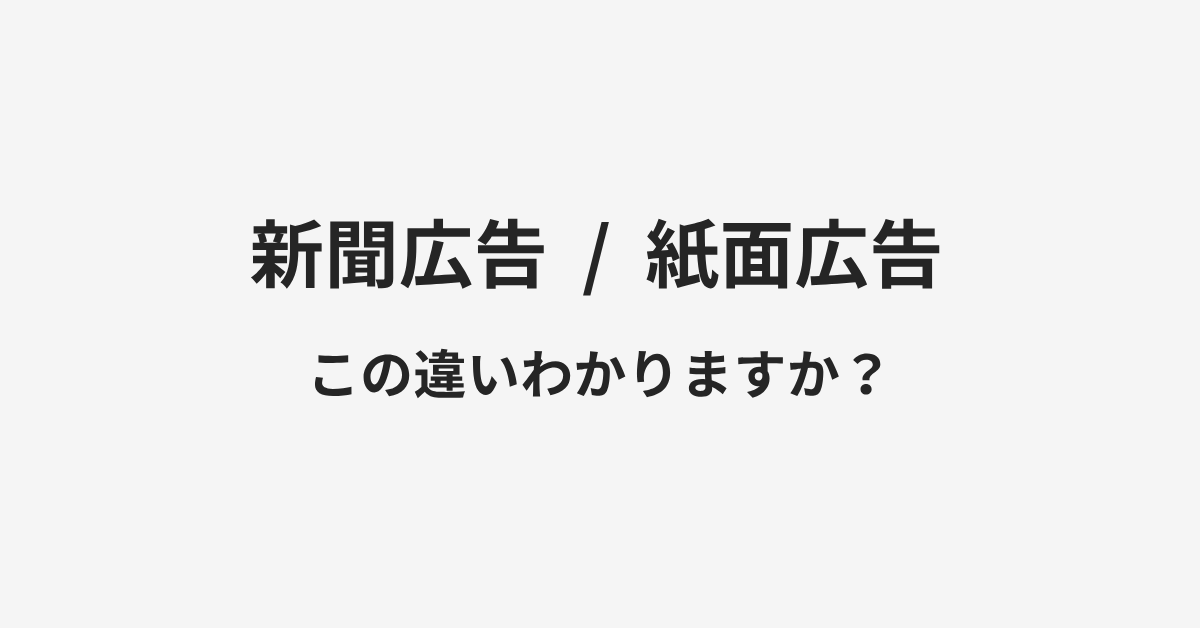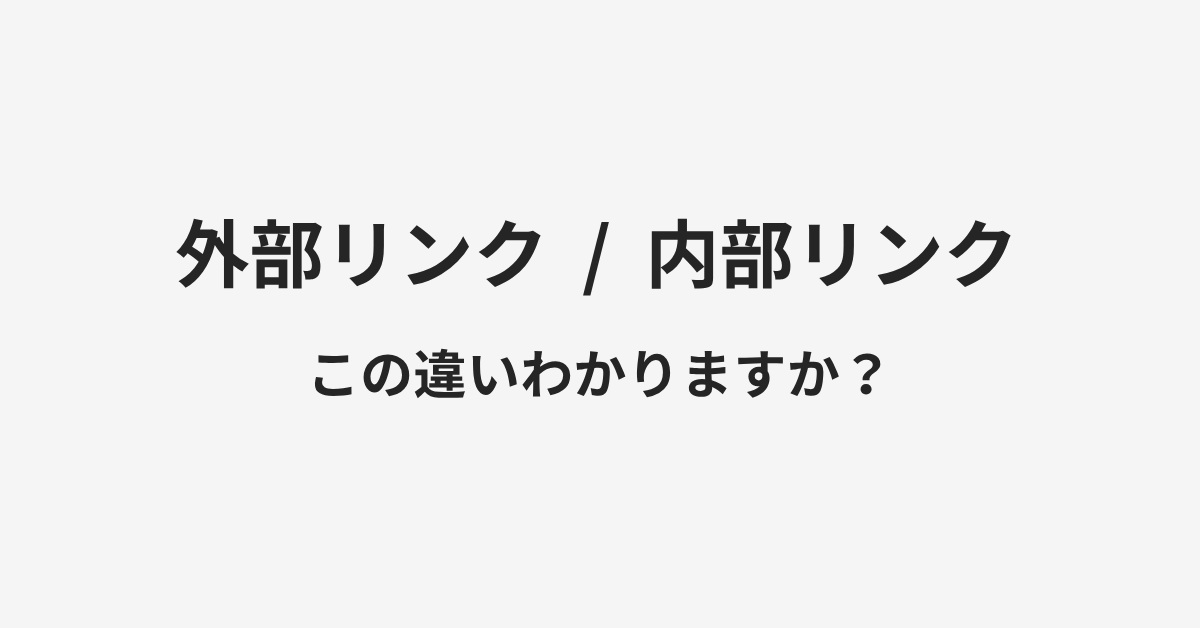【獲得単価】と【取得単価】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
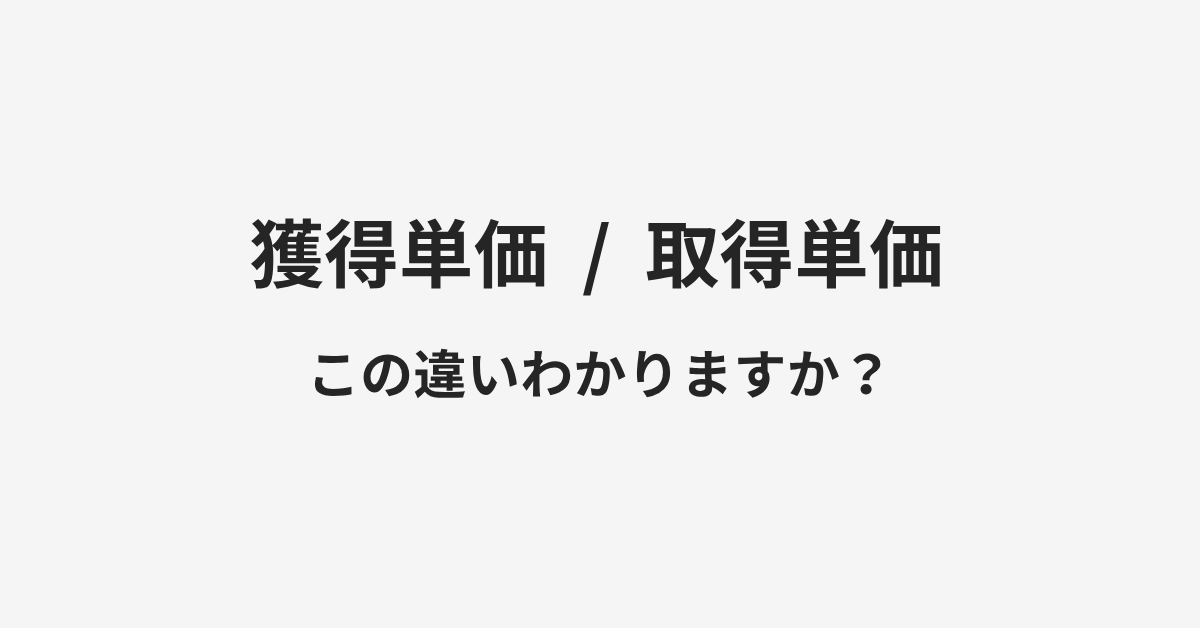
獲得単価と取得単価の分かりやすい違い
獲得単価は、新しい顧客や成果を1件獲得するのにかかった費用のことです。広告費や営業コストを獲得数で割って計算し、CPA(Cost Per Acquisition)とも呼ばれます。
取得単価は、獲得単価と同じ意味で使われる言葉です。何かを手に入れるための1件あたりの費用を表します。
マーケティング業界では獲得単価が一般的で、取得単価は日常的な説明で使われることがありますが、意味は同じです。
獲得単価とは?
獲得単価(Cost Per Acquisition:CPA)とは、新規顧客獲得、会員登録、商品購入などの成果を1件獲得するために要した総コストを示す重要な効率性指標です。計算式は総マーケティングコスト÷獲得成果数で、広告費、人件費、システム費用などを含めた包括的なコスト管理に使用されます。
LTV(顧客生涯価値)との比較により、投資対効果を評価します。業界や商材により大きく異なり、EC業界では数千円、B2B SaaSでは数万円、金融業界では数万~十数万円が一般的です。獲得単価の最適化には、ターゲティング精度向上、コンバージョン率改善、クリエイティブ最適化、媒体選定の見直しが重要です。
許容獲得単価(目標CPA)の設定は、商品単価、粗利率、リピート率を考慮して決定され、持続可能なビジネスモデル構築の基準となります。
獲得単価の例文
- ( 1 ) 新規顧客の獲得単価を5,000円から3,500円に削減し、利益率が大幅に改善しました
- ( 2 ) 獲得単価とLTVの比率が1:3を超えており、健全な投資効率を維持しています
- ( 3 ) チャネル別の獲得単価分析により、最も効率的な集客経路を特定しました
- ( 4 ) リターゲティング広告の獲得単価が新規広告の半分以下で、予算配分を最適化しています
- ( 5 ) AIによる入札最適化で獲得単価を25%削減し、同予算で獲得数を増加させました
- ( 6 ) 季節変動を考慮した獲得単価の予測モデルにより、効率的な予算計画を実現しています
獲得単価の会話例
取得単価とは?
取得単価とは、資産、顧客、データなどを取得する際の1単位あたりのコストを示す用語で、マーケティング文脈では獲得単価(CPA)と同義で使用されることが多いです。会計用語としては固定資産の取得原価を指すこともありますが、デジタルマーケティングでは顧客獲得コストの意味で用いられます。
取得という表現は、より広範な対象(データ、権利、資産等)に使われる傾向があり、獲得は主に顧客や成果に対して使用されます。実務では顧客獲得単価リード獲得単価など、対象を明確にした表現が推奨されます。
マーケティング業界標準としては獲得単価(CPA)が定着しており、国際的なコミュニケーションや専門的な議論では、CPA/CPAcquisitionという用語の使用が適切です。
取得単価の例文
- ( 1 ) データ取得単価の削減により、分析基盤の構築コストを30%圧縮できました
- ( 2 ) 顧客情報の取得単価を適切に管理し、CRMシステムのROIを最大化しています
- ( 3 ) アプリユーザーの取得単価が業界平均を下回り、競争優位性を確立しています
- ( 4 ) 見込み客リストの取得単価とその後の成約率を分析し、最適な投資判断を行っています
- ( 5 ) 会員取得単価の推移をモニタリングし、マーケティング施策の効果を定量的に評価しています
- ( 6 ) 市場調査データの取得単価を考慮し、自社調査と外部データ購入のバランスを最適化しています
取得単価の会話例
獲得単価と取得単価の違いまとめ
獲得単価と取得単価は、本質的に同一の概念を表す異なる表現です。マーケティング業界では獲得単価(CPA)が標準用語として確立されており、KPI管理や業界比較で広く使用されています。
実務においては、用語の統一性を保つため獲得単価を使用することで、社内外のコミュニケーションが円滑になります。重要なのは、この指標を正しく算出し、事業の収益性改善に活用することです。
効果的なマーケティング戦略では、獲得単価の継続的な改善とLTVの向上を両輪として、持続可能な成長を実現することが成功の鍵となります。
獲得単価と取得単価の読み方
- 獲得単価(ひらがな):かくとくたんか
- 獲得単価(ローマ字):kakutokutannka
- 取得単価(ひらがな):しゅとくたんか
- 取得単価(ローマ字):shutokutannka