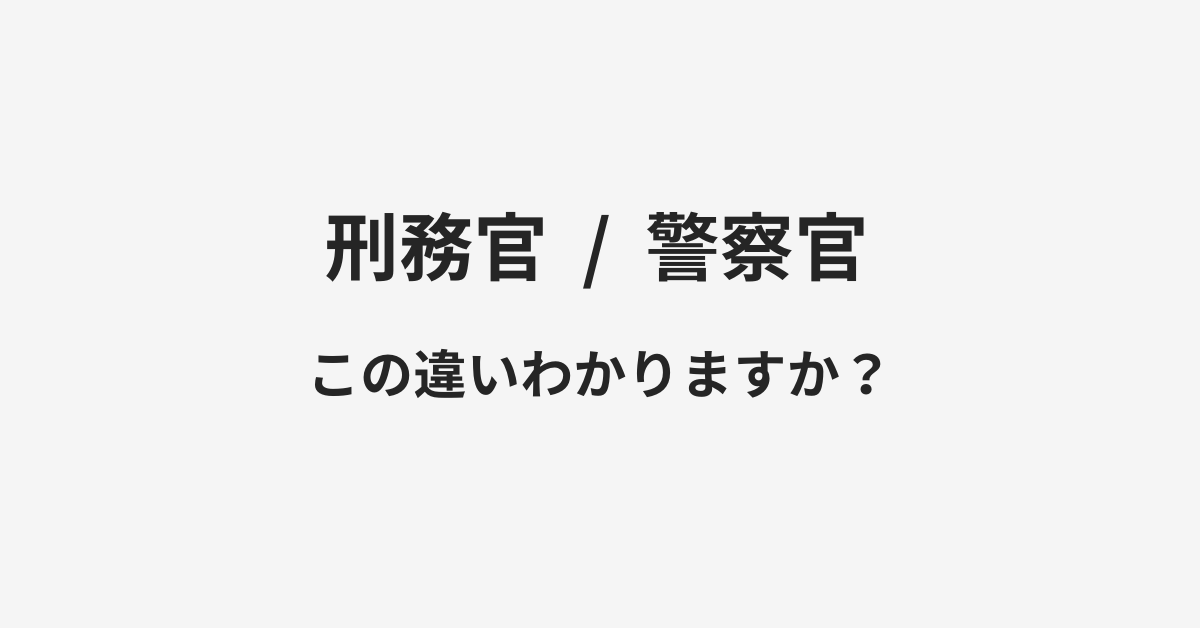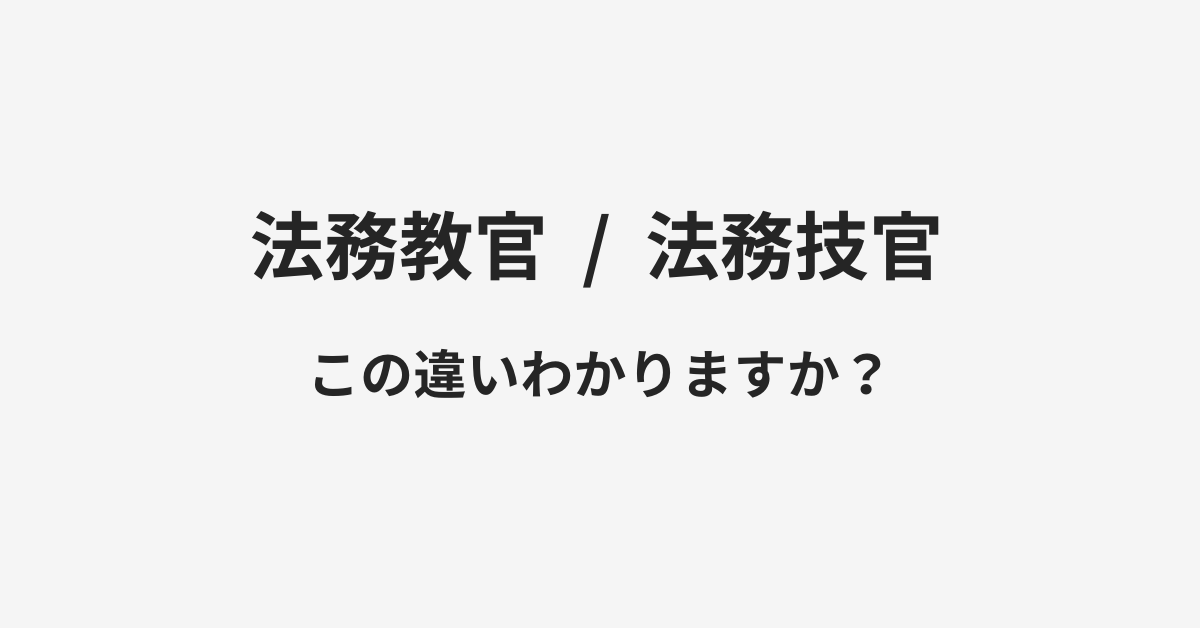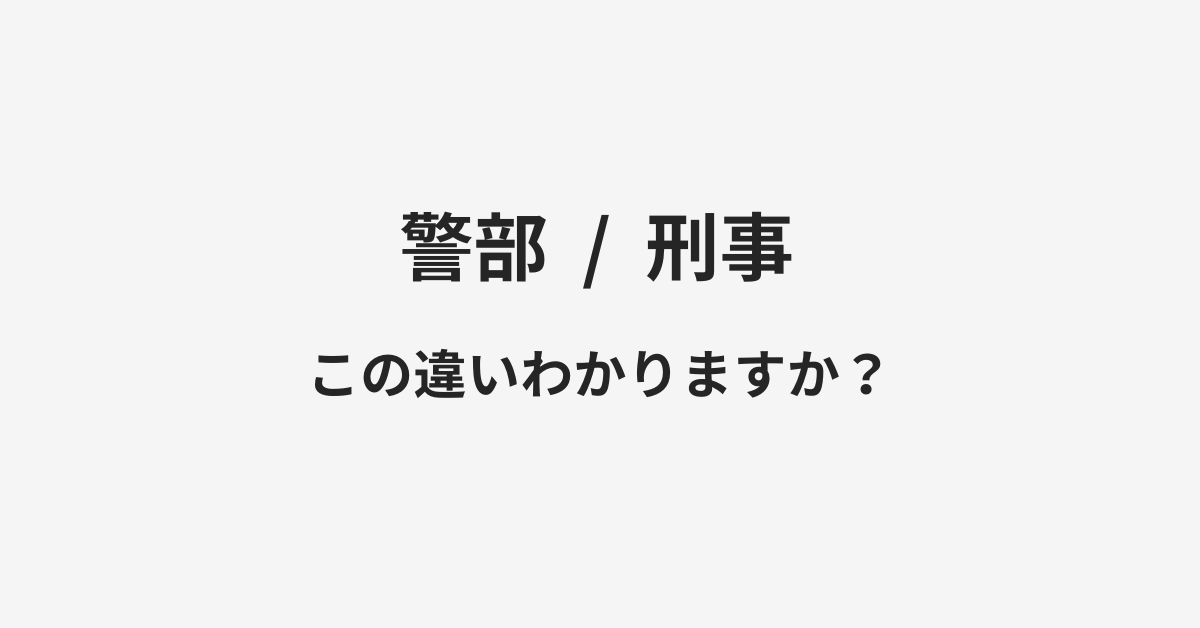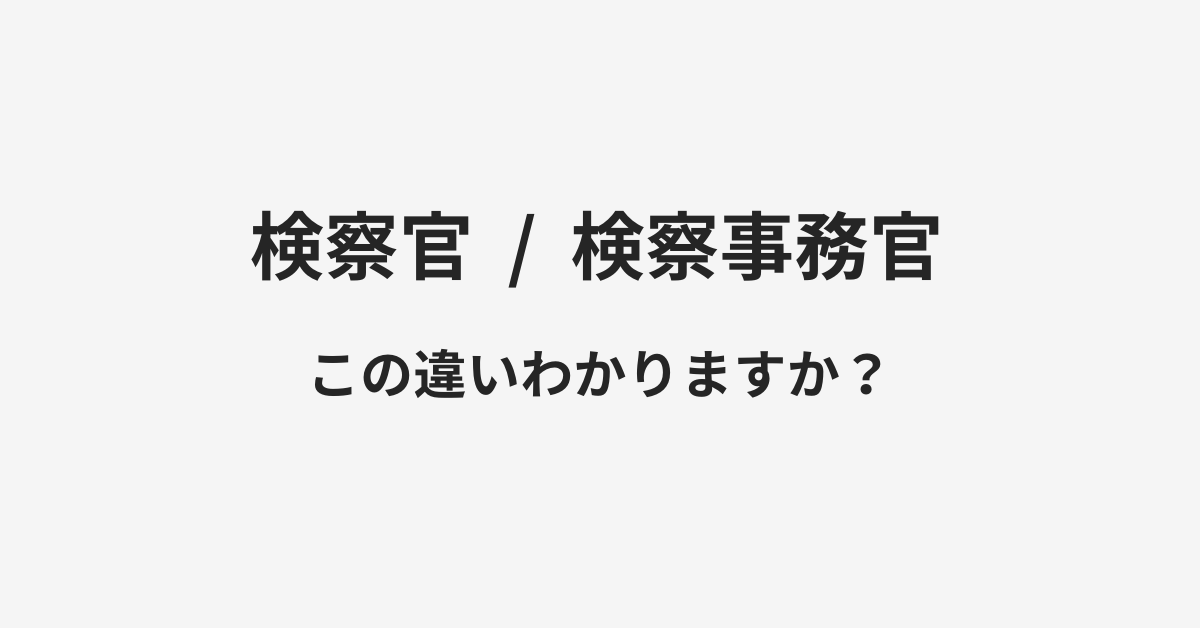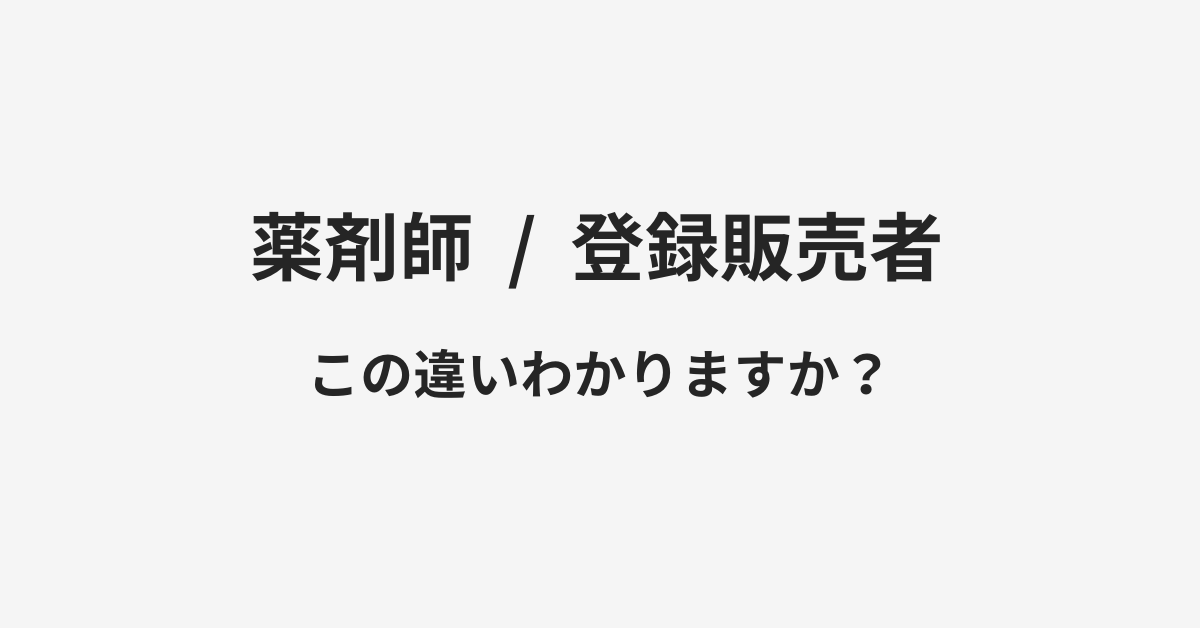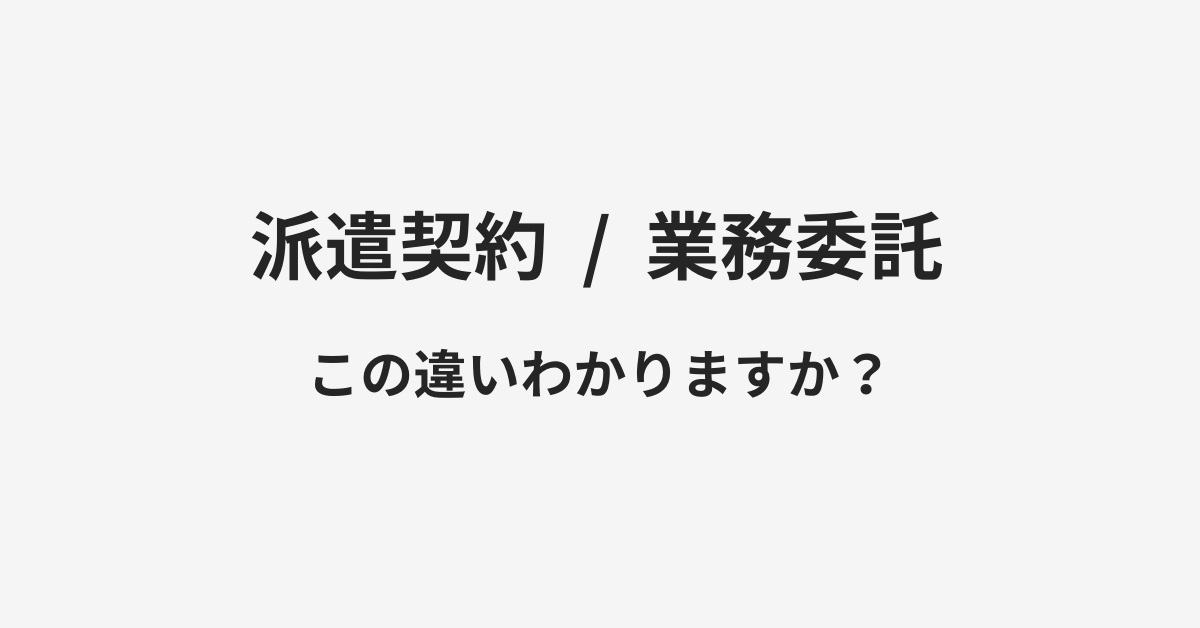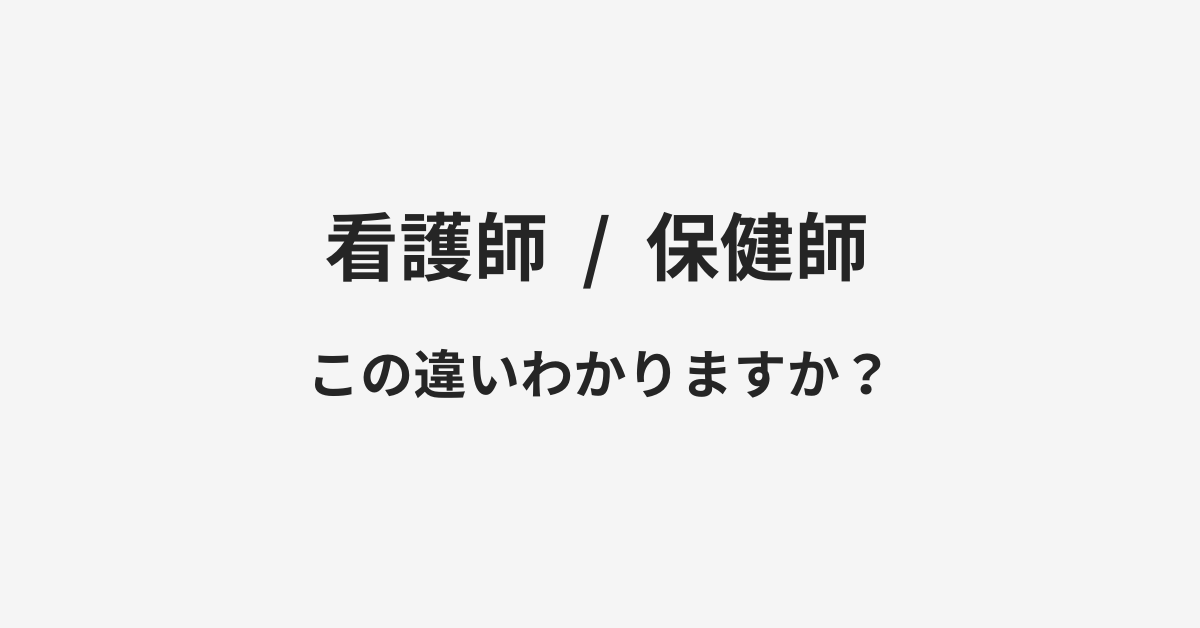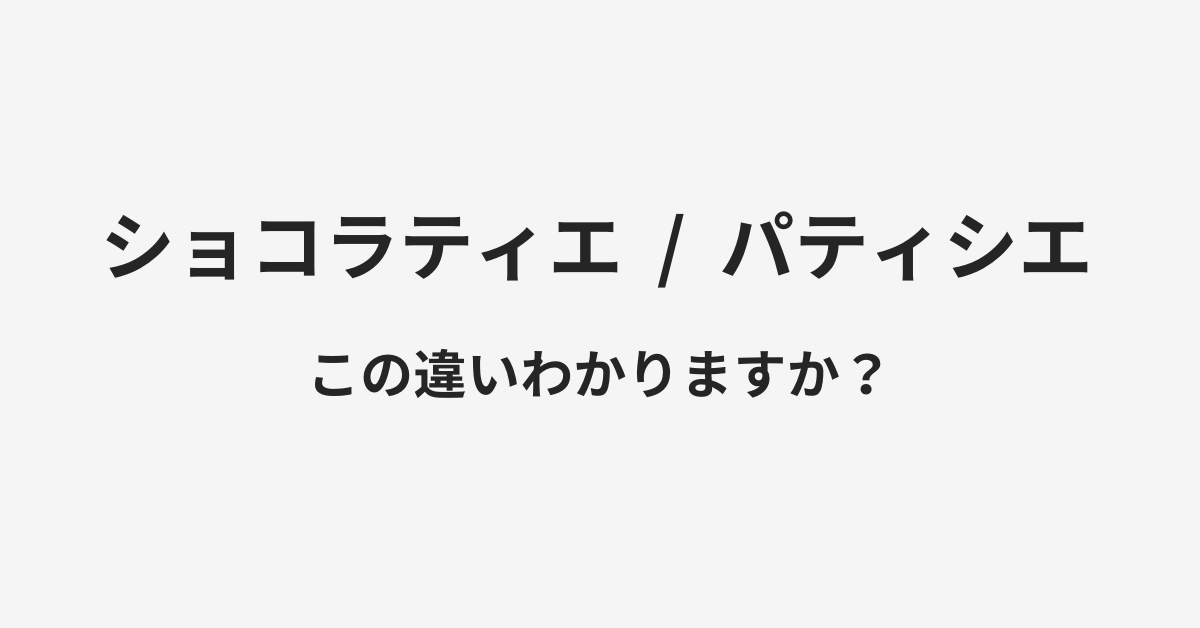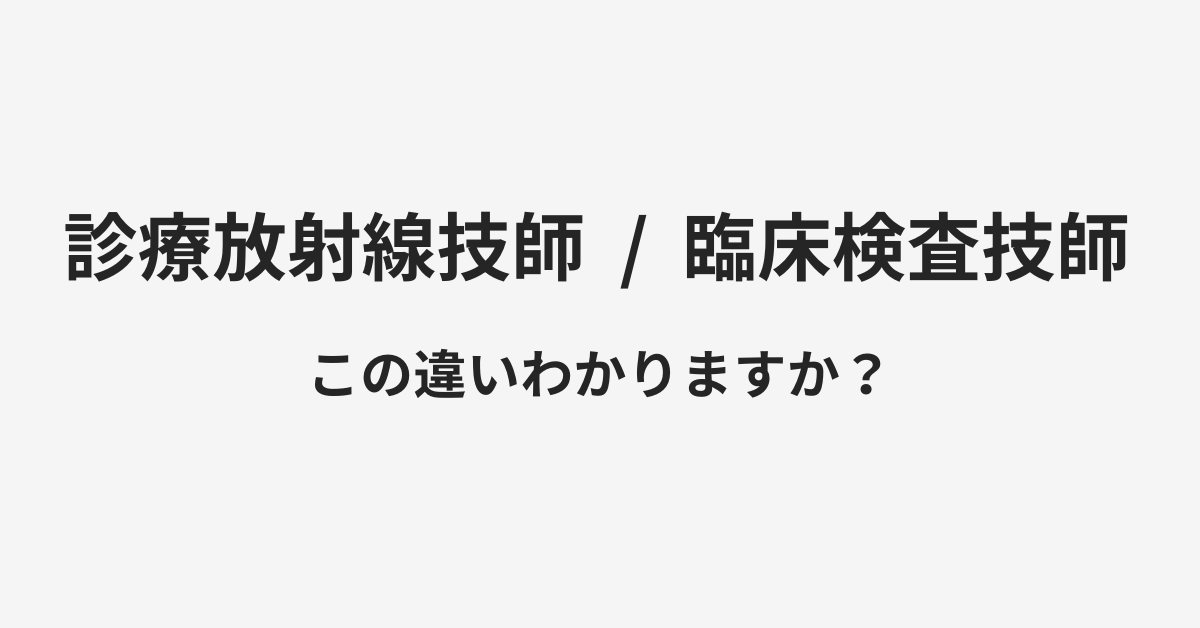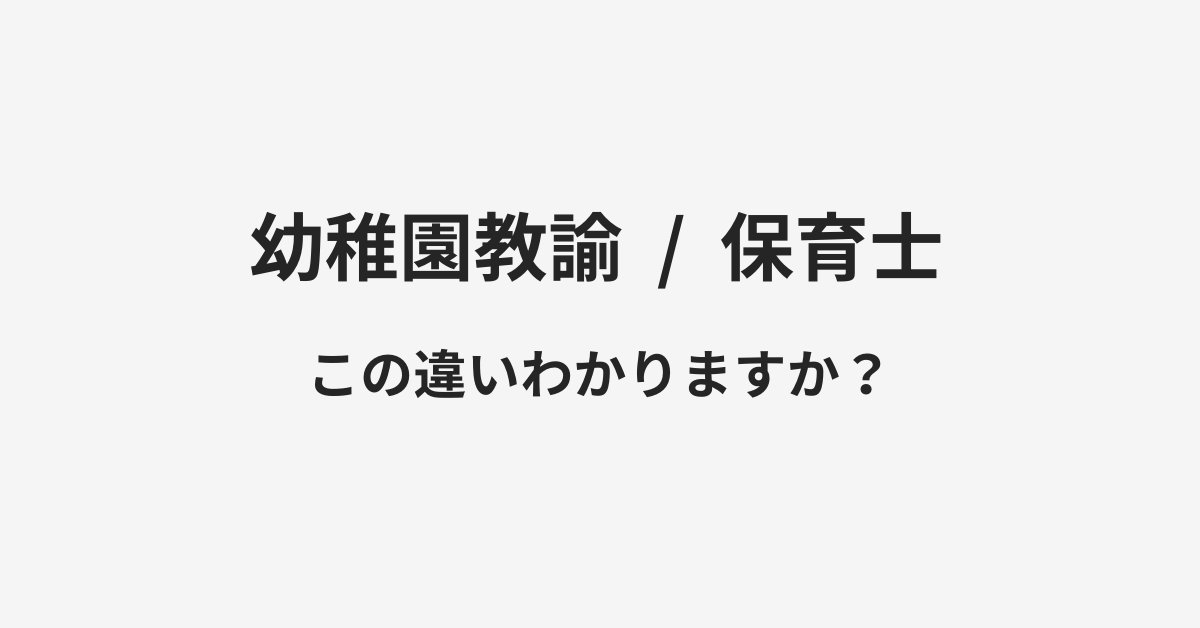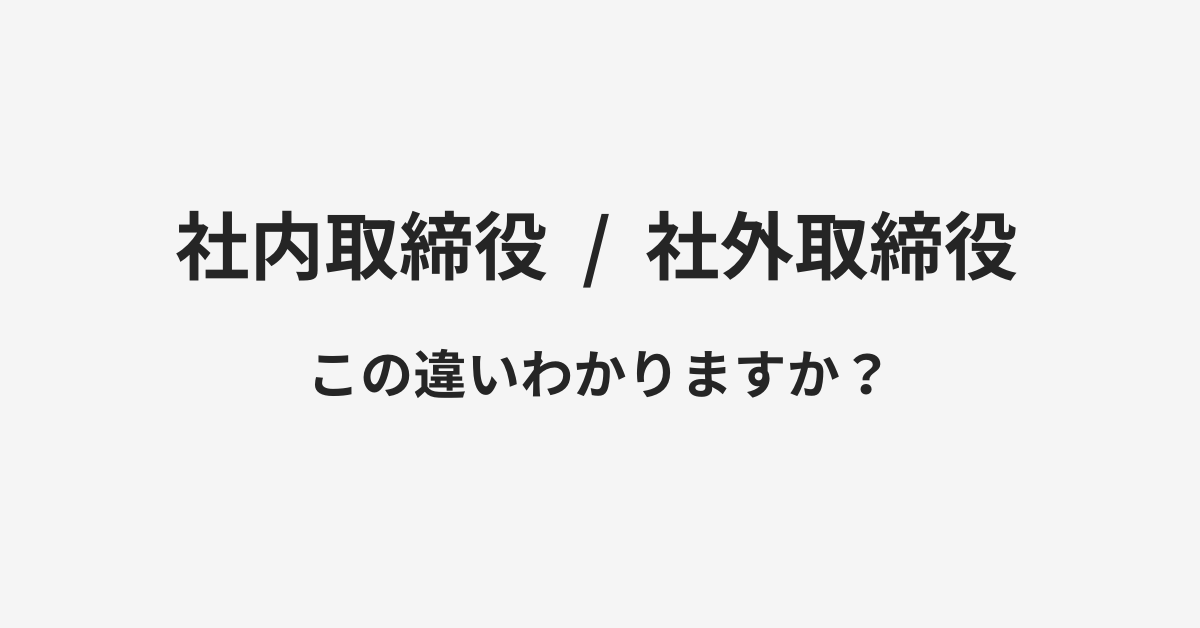【刑務官】と【看守】の違いとは?例文付きで使い方や意味をわかりやすく解説
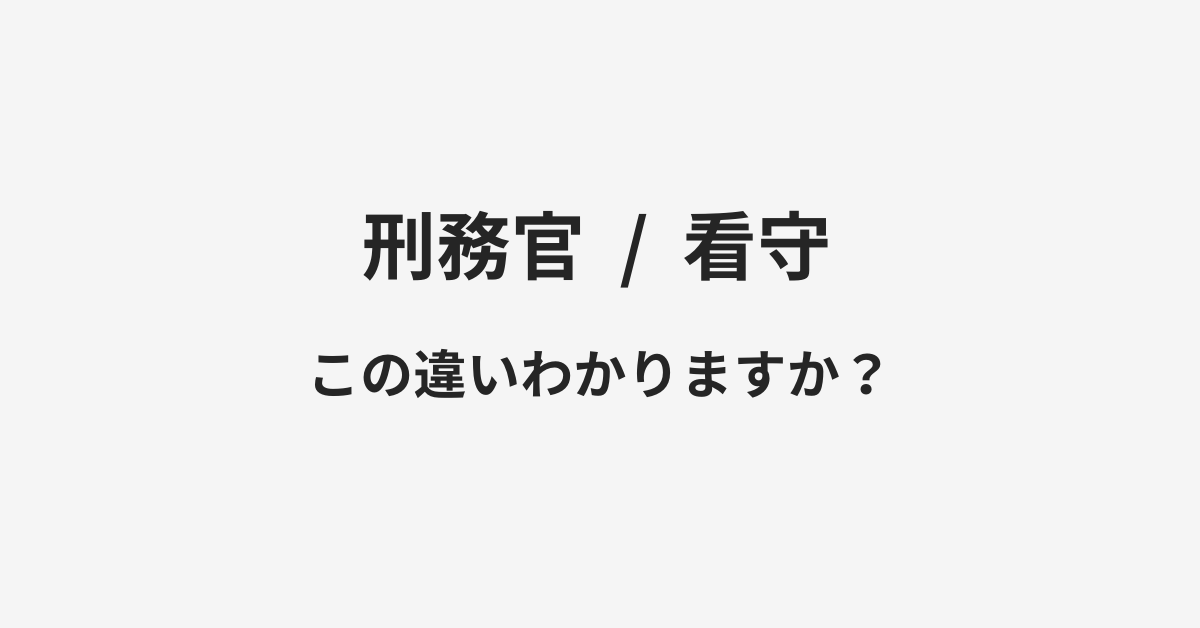
刑務官と看守の分かりやすい違い
刑務官と看守は、基本的に同じ刑務所で働く職員を指しますが、呼び方の新旧に違いがあります。
刑務官は現在使われている正式な職名で、受刑者の更生を支援する国家公務員です。
一方、看守は昔使われていた呼び方で、今ではほとんど使われませんが、刑務所の職員を指す古い言葉です。
刑務官とは?
刑務官とは、法務省矯正局に所属する国家公務員で、刑務所、少年刑務所、拘置所などの刑事施設で勤務する職員の正式名称です。受刑者の改善更生と社会復帰を支援することが主な任務で、保安業務、作業指導、教育指導、生活指導などを行います。単なる監視ではなく、更生支援の専門家です。
刑務官になるには、刑務官採用試験(高卒程度)に合格する必要があります。採用後は法務省矯正研修所で初任科研修を受け、法律、心理学、護身術などを学びます。武道有段者は優遇されることもあります。体力と精神力、そして人間性が求められます。
国家公務員として安定した身分と給与が保障され、年収は400-700万円程度です。危険手当などの特殊勤務手当も支給されます。24時間交代制勤務で、受刑者の人権に配慮しながら、社会の安全を守る重要な職業です。
刑務官の例文
- ( 1 ) 刑務官として、受刑者の更生プログラムの実施に携わっています。
- ( 2 ) 女性刑務官として、女子刑務所で受刑者の生活指導を担当しています。
- ( 3 ) 刑務官として、職業訓練指導員の資格も取得し、受刑者の社会復帰を支援しています。
- ( 4 ) ベテラン刑務官として、新人職員の教育指導も行っています。
- ( 5 ) 刑務官として、受刑者の人権に配慮しながら、規律の維持に努めています。
- ( 6 ) 少年刑務所の刑務官として、若年受刑者の教育的処遇に力を入れています。
刑務官の会話例
看守とは?
看守とは、刑務官の旧称で、かつて刑務所や拘置所で受刑者の監視や管理を行う職員を指した言葉です。明治時代から昭和中期まで使用されていましたが、1947年の刑務所法改正以降、正式には刑務官という名称に変更されました。現在では公式には使用されません。
歴史的に見ると、看守は主に受刑者の監視と規律維持が中心的な役割でした。現代の刑務官が更生支援を重視するのに対し、当時は管理・統制的な側面が強かったとされています。しかし、基本的な職務内容は現在の刑務官と同様です。
現在でも一般会話や文学作品、時代劇などでは看守という言葉が使われることがありますが、実際の職業名としては使用されません。法務省や刑事施設で働く職員を指す場合は、必ず刑務官という正式名称を使用します。
看守の例文
- ( 1 ) 昔は看守と呼ばれていたが、今は刑務官として誇りを持って職務に当たっています。
- ( 2 ) 祖父が看守だった時代の話を聞き、現在の刑務官の仕事との違いを実感しています。
- ( 3 ) 時代劇で看守が出てくるが、現代の刑務官とは職務内容がかなり違います。
- ( 4 ) 看守という言葉は古いので、正式には刑務官と呼ぶようにしています。
- ( 5 ) 文学作品に出てくる看守のイメージと、現代の刑務官の実際は大きく異なります。
- ( 6 ) 看守から刑務官へと名称が変わった背景には、職務の近代化があったと学びました。
看守の会話例
刑務官と看守の違いまとめ
刑務官と看守は、本質的に同じ職業を指しますが、時代による呼称の違いがあります。
刑務官は現在の正式名称、看守は過去に使われていた旧称です。
現代では、受刑者の更生支援という役割が重視され、刑務官という名称がその職務内容をより適切に表しています。刑事施設で働くことを目指す場合は、刑務官採用試験を受験することになります。
刑務官と看守の読み方
- 刑務官(ひらがな):けいむかん
- 刑務官(ローマ字):keimukann
- 看守(ひらがな):かんしゅ
- 看守(ローマ字):kanshu